研究テーマ・トピックス
長野泰彦

チベット概念図(クリックすると拡大して見られます) |
チベットに対して日本人が抱く感じ、ないしイメージは多種多様である。ある人は山また山の向こう側にある荒涼たる荒原を想い、ある人はラマ教や鳥葬を軸とした、おどろおどろしい習俗の残る秘境を考える。チベットのある断面だけを見ればこれらのイメージはどちらも正しい。しかし、全体的にみれば誤りである。
確かにチベットは標高がたかい。チベット高原の中でも高度のさほどないラサでさえ、約3700メートルで、富士山頂とほぼ同じである。しかし、荒涼たる原野は、チャンタン高原を除けば、少ないし、森林もあれば、良質の草地もあり、大麦の二期作を可能にする肥沃な農地も少なくない。また、チベットは独特の論理学体系を築き上げてきた高精神文化地域であり、アジア人の思惟を語る時、インド、中国と並ぶ不可欠の柱となっているのである。一見変わった習俗があることは事実だが、それらが高度の精神文化と豊かなフォークロアに支えられていることを忘れてはならない。

四川省チベット族居住地域の山々 |
|

少年とロバ |
|
これには、チベットが現在独立国でなく、また、直接の経済関係を持っていないために、チベットの実態や歴史に目が向かない、といったきわめて実際的な理由も考えられるが、最大の理由は、チベットないしチベット文化についての情報が決定的に少ないことにあると思う。
例えば、学校の教科書でチベットという固有名詞が出てくるのは大変稀である。高校社会科の世界史の教科書で、チベットを取り上げているのは二種のみで、それも中国の唐の時代に、唐朝の混乱に乗じて極めて短期間「吐蕃(とばん=チベットを漢人は昔こう呼んだ)」が長安を占領したという記述があるに過ぎない。
しかし、チベットと日本の出会いは意外に古い。『続日本紀』巻19、孝謙天皇丙寅(天平勝宝6年)の条に、遣唐副使大伴宿弥古麻呂が帰国報告を行った記事の中に、「大唐天宝十二載(西紀753年)正月に、多くの唐の高官や周辺諸国の朝使が帝に朝賀に訪れました。天子には蓬来宮含元殿において拝謁賜りました。この日、朝使の序列は、私を西畔の第2、吐蕃の次に置き、東畔第1に新羅使を、第2に大食(サラセン)となっていました。そこで私は、“新羅は昔から日本に朝賀に来ているのに、それがここで我が国より上席にいるのはおかしいではないか”と抗議しました。将軍呉懐実は私が容易に引き下がらないことを見て取って、日本と新羅の席次を入れ替えました」とある。

吐蕃期のチベットの図(クリックすると拡大して見られます) |
この無血入城に絡んでひとつ面白い話がある。唐の代宗は北東に逃れ、チベットはそのかわりに、チベットの先代の王に降嫁した金城公主の兄にあたる広武王承宏をたてたが、唐の軍が帰還するのを恐れて、15日目にさっと引き上げてしまった。唐の軍が戻ってきて慌てたのは広武王承宏である。逃げようとしたが、捕らえられ、華州で亡くなった。この逃亡劇の際、承宏は金銀財宝の類を金城公主の父、雍王の屋敷に隠したらしい。最近中国による発掘が行われ、西安市南郊のある村から唐代の穴蔵が見つかった。これがちょうど雍王屋敷跡で、しかもその発掘品の中に日本の和銅開珎の銀銭が5枚あったとのことである。日本最初の貨幣が遠く長安にまで運ばれていたのは、朝貢のためだろうか?チベットと広武王承宏との関係を考えると、チベットのどこかにも和同開珎がまだ埋まっているかもしれない。
中央集権国家のイデオロギーとしての仏教

ラマ僧の問答風景 |
「ラ」というのは、自分の生命の根源を言い、それをすべて捧げるべき師をラマと言う。このラマを大変大切にするためにラマ教という呼び名ができたのである。しかし、この理屈でゆけば、どんな宗教も全部ラマ教である。そろそろこういった変な呼称はやめて、チベット大乗仏教と言い直す時期にきていると思うのだが。
仏教はインドに興った。その外来の宗教を、チベットを初めて統一したソンツェン・ガンポ王はある意図を持って人為的に移入したのである。実際はもっと早い時期から仏教が入り込んでいたであろうが、国家統一の手段として仏教というイデオロギーが強力に利用されたのは注目に値する。ちょうど同じ頃に日本でも聖徳太子によって仏教が保護されたのとよく似ている。在来の豪族たちを束ね、朝廷を頂点とする中央集権国家の成立のためには高度のイデオロギーを必要としたのであるから。この王のもくろみは、聖徳太子の場合と同様に必ずしも成功したとは言えない。事実、反仏教勢力の抵抗はつよく、王の死後、巻き返しにでた。結局仏教が国の宗教としての地位を確立するのは8世紀後半に入ってからである。

チベット主要都市・主要寺院の図(クリックすると拡大して見られます) |

タンカ |
14世紀になると、今の青海省にひとりの宗教的天才が現れた。ツォンカ・ロブサン・タクパという。彼の思想的な柱は「中観」であるが、従来チベットに行われていた中観諸派の思想をことごとく退け、独自の密教解釈をもっていわゆるタントラ仏教を否定した。また、厳格な戒律主義と独身主義をとったため、民衆の信頼を勝ち得たと言われる。彼の始めた派はゲル(ク)派とも、黄帽派とも、改革派とも呼ばれる。

かつてのダライラマの居城・ポタラ宮 |
ダライラマに限らず、「活仏」というのは転生する生き仏である。ある活仏が死ぬと、必ずその生まれ変わりが現れると信じられている。この考え方は当初カルマ派によって体系的に採用されたが、後にゲル派もこれにならった。生まれ変わりがどこに、どの様な容貌で、どういう状況にあるかを専門家(多くはシャマン)に頼んで占ってもらうこともあるし、かなり時間がたってから、信望のある僧が実は転生者だったという同定の仕方をすることもある。また、ゲル派の場合は一部の活仏のポストが政権内部で力のある貴族たちの持っている一種の“株”として扱われてきた面もある。現在の14世ダライはインドにいるのだが、この転生者をどうやって選ぶのか、大変興味がある。
フォークロアにおける平行性
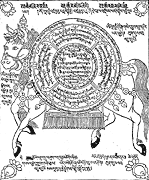
護符 |
チベット人は、宗教を「ハチュ(神の宗教)」と「ミチュ(人の宗教)」に分ける。啓示を伴うものがハチュ、習俗・民間信仰がミチュである。ハチュは、仏教と仏教伝来以前からチベットにあったポン教を言うことが多い。これに対し、ミチュは踊りを含む習俗全般を指す。お守りも勿論ミチュに含まれる。
ミチュたるお守りも一応仏教またはポン教のオーソライズを見かけ上受けているが、お守りの中身はまさに民間信仰そのものである。近頃仏教における曼荼羅(まんだら)が注目されているが、そのデザインはもともと護符=図=ではないかとする説さえある。
能の『翁』の中で、「とーとーたらり」という意味の分からない台詞を唱える場面がある。今世紀初頭チベットに入った多田等観師はかつて、これをチベット語だと論じたことがある。チベットに行われる宗教舞踊の中に同定できる音節が聞かれることは事実だが、どう考えてもこれは自然言語としてのチベット語とは思われない。おそらく、インドにおける一種の宗教的偈文(マントラ)が芸能の中にたまたまチベットと日本で生き残ったと考えるべきかと思う。
むしろここで注目すべきは、能とチベット演劇ないし宗教舞踊の構造や登場人物の平行性であろう。例えば、白い老人「翁」と黒い老人「三番叟」の面は誰でも御存知と思うが、これらはチベットの「白い悪魔」と「狩人」(黒)に対応し、その演劇における機能も同じである。だからといって、能とチベット宗教舞踊が互いに歴史関係があったと考えるのは危険だが、他の能にも平行する現象があるとすれば、面白い類似と言っていいだろう。
「日本語とチベット語の間には何らかの関係があるのか?」日本人はルーツ探しに異常なまでの熱意を示す国民であるから、私がチベット語を専攻していると言うと、必ずこの質問が飛ぶ。何らかの関係という意味は、歴史的・系統的にみて両者に関係があるか、ということである。これは、今のところ、言語学の「比較方法」ということばの歴史を再構する方法による限り、証明できない。興味深い類似や平行性が認められるのは事実だが、体系的とは言い難く、また、比較すべきレベルがずれていると思われる。日本語の系統については昔から、アルタイ語、南方諸語、レプチャ語などとの関係が取りざたされ、近年、チベット、ビルマ諸語、タミル語とのそれも問題になっている。だが、いずれも決定的な証拠を提出するに至っていない。
どこかのテレビ番組で、チベット人に数字の1から10まで勘定させ、「日本語とよく似ていますね、なにか関係があるんじゃないでしょうか」とのコメントがついていた。チー、ニー、スム、シ、ガ・・・は、日本語のそれによく似ている。しかし、それは数の算え方を日本語とチベット語が漢語の古い層から借用したから似ているのであって、系統関係があるから似ているのではない。
チベットの魅力

筆者(中央)とチベットの友人 |
ヒューマンであることは、あるいは「中世」に留まることは、本質を見きわめようとする人々にとって良いことである。だが、それが社会・政治・歴史にまで徹底してくると、問題は大きい。彼らの社会・政治・歴史は、近現代においてもなお、中世のままであり、そこから抜けるべしと主張した者は排除され、外国人をも寄せつけなかった。これがチベット人自身の選択だったと言えばそれまでだが、本当にそうだったか否か、よく分からない。このようなチベットを効果的に統制することは、中国にとって訳もないことであった。その効果にチベット人が気づいたとき、動乱が勃発した。1959年のことである。
かつて、チベット学の泰斗R・A・スタン教授はこの事態を「身のまわりに突然起こった変化に徐々に対応して生きていくということを知らなかったため、滅亡に瀕した一文明の悲劇」と形容したことがある。この形容はおそらく正しい。しかし、幸いにもチベット人たちは急速に社会的対応への成熟度を高めてきており、いったんは滅亡の危機に瀕した文明をしたたかに蘇生させているように思われる。「対応」に伴って、若干の「中世」を切り捨ててではあるが・・・。
チベット学の現在

マンダラ |
また、研究の傾向そのものも変化しつつある。精緻な文献学一辺倒から、やや荒削りではあっても、チベット文化の持つ独自性とともに普遍性に眼を向けた研究が現れている。これは特に宗教学関係に見られる傾向で、同じ儀礼を観察するにしても、それがインド仏教の何に対応するのかを問う態度ではなく、チベット独自の体系は何であるのか、それが人類文化にとっていかに普遍的であるのかに注目する態度に変わってきた、ということである。
この傾向は、チベットの山岳信仰、シャマニズム的事象、狩猟採集民の文化との比較、などにおいて顕著に見られる。仏教であろうと、ポン教であろうと、民間信仰であろうと、それらを貫いて脈々と息づいているものは何か?という視点が強く押し出されている分野である。

ポン教高僧 テンジン・ナムタク師 |
また、古いポン教徒はシャンシュン語という未だその系統も文法も明らかにされていない言語を用いていた。この言語は敦煌文献に6点シャンシュン語とされるものが残っている他は他に手がかりがないが、チベット文語の成立にも重大な影響を及ぼしたと考えられ、チベット・ビルマ系諸言語の歴史を論ずる際、不可欠の要素となるはずである。
このようにポン教とその文化は、チベットの基層文化と社会を理解する上で欠くべからざる研究対象であるが、世界的に見ても、組織的なポン教研究が行われたことはかつて一度もなかった。ポン教研究は、仏教研究に比べて、非常に立ち遅れている。託宣を現地調査によって研究したものや幾つかの文献研究がないではないが、組織的なフィールドワークを軸に据えた研究はない。特に日本では、チベット学の中心的牽引力はあくまでも仏教研究であり、研究基盤そのものが存在しない。わずかに寺本婉雅の『十万白龍』の訳注があるのみである。
ここ8年間上記のような状態を少しでも改善するため、ポン教文化研究の研究基盤を整備することと、シャンシュン語の基礎的研究に注力してきた。1999年にはその中締めとして国際シンポジウムを開催し、現段階でのポン教研究の世界的水準を示すことができ、また、研究のネットワークづくりに成功した。研究基盤の整備に関しては、ポン教大藏経(カンギュルとテンギュル)及び藏外文献の収集を行い、研究者の利用に供する態勢を整えた。これらの成果は国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports)として刊行されている。
 Bon Studies 1: Senri Ethnolgical Reports No.12
Bon Studies 1: Senri Ethnolgical Reports No.12Mandalas of the Bon Religion, Edited by Tenzin Namdak, Yasuhiko Nagano and Musashi Tachikawa
 Bon Studies 2: Senri Ethnolgical Reports No.15
Bon Studies 2: Senri Ethnolgical Reports No.15New Horizons in Bon Studies, Edited by Samten G. Karmay and Yasuhiko Nagano
 Bon Studies 3: Senri Ethnolgical Reports No.19
Bon Studies 3: Senri Ethnolgical Reports No.19New Research on Zhangzhung and Related Himalayan Languages, Edited by Yasuhiko Nagano and Randy J. LaPolla
 Bon Studies 4: Senri Ethnolgical Reports No.24
Bon Studies 4: Senri Ethnolgical Reports No.24A Catalogue of the New Collection of Bonpo Katen Texts, Edited by Samten G. Karmay and Yasuhiko Nagano
 Bon Studies 5: Senri Ethnolgical Reports No.25 (with CD-ROM)
Bon Studies 5: Senri Ethnolgical Reports No.25 (with CD-ROM)A Catalogue of the New Collection of Bonpo Katen Texts - indices, Edited by Samten G. Karmay and Yasuhiko Nagano
 Bon Studies 6: Senri Ethnolgical Reports No.32
Bon Studies 6: Senri Ethnolgical Reports No.32The Call of the Blue Cukoo, Edited by Samuten G. Karmay, Yasuhiko Nagano
 Bon Studies 7 : Senri Ethnolgical Reports No.38
Bon Studies 7 : Senri Ethnolgical Reports No.38A Survey of Bonpo Monasteries and Temples in Tibet and the Himalaya, Edited by Samten G. Karmay, Yasuhiko Nagano
 Bon Studies 8: Senri Ethnolgical Reports No.40
Bon Studies 8: Senri Ethnolgical Reports No.40A Catalogue of the Bon Kanjur, Edited by Dan Martin (General editor), Per Kvarne (Project coordinator), Yasuhiko Nagano (Series editor)
 Bon Studies 9: Senri Ethnolgical Reports No.57
Bon Studies 9: Senri Ethnolgical Reports No.57Feast of the Morning Light, The Eighteenth Century Wood-engravings of Shenrab's Life-stories and the Bon Canon from Gyalrong, Edited by Samten G. Karmay
さらにチベットを知りたい人のために
チベット文化全体に関する概説書として次の本を推奨する。
 『チベット文化史』D.スネルグローヴ(春秋社)
『チベット文化史』D.スネルグローヴ(春秋社)
 『チベットの文化』R.A.スタン(岩波書店)
『チベットの文化』R.A.スタン(岩波書店)
 『チベット』山口瑞鳳(東京大学出版会)
『チベット』山口瑞鳳(東京大学出版会)
 『チベットの言語と文化』長野泰彦・立川武蔵編(冬樹社)
『チベットの言語と文化』長野泰彦・立川武蔵編(冬樹社)
『チベット文化史』はチベットの社会・歴史・文化についての、最もバランスのとれた優れた概説である。早い時期からポン教文化のもつ重要性を主張していた著者の見識が随所に窺われる。また、日本語訳もこなれている。『チベットの文化』は中国文明・インド文明との対照においてチベット文明を観察する態度に裏づけられており、また、膨大な文献を渉猟した泰斗にして初めて可能となった洞察に満ちている。特にフォークロアに関する解釈はすばらしい。『チベット』もバランスよく概説がなされているが、チベット古代史の部分が詳しく、かつ、優れている。『チベットの言語と文化』は論説を集めたもので、書き下ろしでない分、読みにくいかもしれない。仏教と言語の部分に力点がおかれている。
書籍ではないが、
 『季刊仏教』1994年1月号
『季刊仏教』1994年1月号
「チベット」が特集されていて、特にポン教の「ゾクチェン」に関する解説は読み応えがある。
チベット文化全体に関する概説書として次の本を推奨する。
 『チベット文化史』D.スネルグローヴ(春秋社)
『チベット文化史』D.スネルグローヴ(春秋社) 『チベットの文化』R.A.スタン(岩波書店)
『チベットの文化』R.A.スタン(岩波書店) 『チベット』山口瑞鳳(東京大学出版会)
『チベット』山口瑞鳳(東京大学出版会) 『チベットの言語と文化』長野泰彦・立川武蔵編(冬樹社)
『チベットの言語と文化』長野泰彦・立川武蔵編(冬樹社)『チベット文化史』はチベットの社会・歴史・文化についての、最もバランスのとれた優れた概説である。早い時期からポン教文化のもつ重要性を主張していた著者の見識が随所に窺われる。また、日本語訳もこなれている。『チベットの文化』は中国文明・インド文明との対照においてチベット文明を観察する態度に裏づけられており、また、膨大な文献を渉猟した泰斗にして初めて可能となった洞察に満ちている。特にフォークロアに関する解釈はすばらしい。『チベット』もバランスよく概説がなされているが、チベット古代史の部分が詳しく、かつ、優れている。『チベットの言語と文化』は論説を集めたもので、書き下ろしでない分、読みにくいかもしれない。仏教と言語の部分に力点がおかれている。
書籍ではないが、
 『季刊仏教』1994年1月号
『季刊仏教』1994年1月号「チベット」が特集されていて、特にポン教の「ゾクチェン」に関する解説は読み応えがある。
 長野泰彦
長野泰彦