研究の意義・目的
近年、伝統産業の衰退や大量生産・大量廃棄の進行、材料・素材の変化などにより、明治時代から高度経済成長期にかけての生活資料が急速に失われつつある。それに伴い、モノを生産してきた技術や道具の使い方なども、徐々に忘れさられてきている。博物館は本来、そのような生活資料を収集し、それに関する技術や知識を記録保存する使命を担っているが、例えば渋沢敬三のアチック・ミュージアムが工業製品を民具と見なさず、収集の対象から除外したことを典型として、民俗学や歴史学の博物館が近代化・工業化以降の生活資料を積極的に収集したとは言い難い状況にある。
また、近現代の生活資料はガラスや金属、樹脂など長期的な保存に向かないものが多く、全国の博物館でその扱いに苦慮している。だからといって、それらを記録・保存していかなければ、近現代の生活活動に関する博物館展示の手法が制限されてしまう。とくに歴博では第6室の現代展示がオープンし、さらに第4室の民俗展示の新構築を進めていることもあり、モノの状態や民俗学、近現代史学の研究蓄積に合わせた、生活資料の収集方針や整理・保存の方法をあらためて検討する必要に迫られている。
ただし、近現代の生活資料の収集・整理、保存は、まだ全国的にノウハウが蓄積されていない。それは主に素材の面から修復、保存が困難なためであるが、近現代の研究・展示を進展させていくためには、その可能性と限界をどこかで示す必要がある。そこで本研究は、近現代資料の状態調査を通じて、それらの収集から保存に至るまでの1つの提案を示していきたい。
その際、本研究ではモノ資料を、産業史との関わりに重点をおくことに特徴をもつ。近代化・工場化、大量生産の進展といった産業の歴史は、新商品の開発や素材・材料、部品の転換など、いわばモノの歴史でもある。大量生産・大量流通された近現代のモノ資料には、時代を遡るほど産地や製造年の不明なものが多いが、産業史と関連させることで、それを使用した地域や時代的背景を合わせて調査することができる。また、商品開発や素材・材料・部品の歴史が整理されれば、地域の生活史をモノの面からより具体的に復元し、かつそれらの情報をモノ資料の収集方針や保存計画にも有効活用できると思われる。
研究計画の概要・研究方法
近現代の生活資料を扱っていく上では、製造年が明らかにされていないものが多いこと、商品名や部品名、部位名称などが業者や地方によって異なること、形状が複雑であること、材料・素材が変化すること、などが難点となっている。これらの課題に対して,本研究では商品カタログや取扱説明書を収集して、主だった生活資料の製造年、商品名、部品名、部位名称のデータベースを作成し、かつそれを活かした方法で整理・保存のための分類方法を検討する。また,素材の化学分析をおこなうとともに、社史や企業への聞き取り調査などによって、素材と材料の変化について明らかにし、収集方針と保存のための基礎データとする。おそらく、本研究におけるデータベースや基礎データの作成は、全国的にも初の試みかと思われる。
具体的には、種類や材質が多様な館蔵の「金沢地方近代生活資料」(H-686)や「石川県白山麓山村生活用具」(F-12)、「飛騨路の民具」(大塚集古資料館旧蔵コレクション,F-169)、「婚礼衣裳・婚礼用具及び生活用具」(F-148)などを対象として,生活資料の分類・整理の方法を検討しつつ、素材分析を行う。
次に,分類・整理した生活資料を商品開発の歴史や素材の変化などと照らし合わせ、産業史・技術史の中に位置づけるため、商品カタログや取扱説明書、社史などを収集し、それらを用いてデータベースを作成する。商品カタログや取扱説明書、社史で明らかにできなかった主要な生活資料については、該当する業界団体や個別の企業への訪問によって情報をいただく。
以上の研究成果は、歴博の他、国立民族学博物館や石川県立歴史博物館、元興寺文化財研究所での研究会で報告し、情報を共有化する。
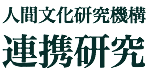
 総括班ホーム
総括班ホーム