研究内容
研究の進捗状況
状態調査の方法は,おおよそ安定してきている。そのため、現在はさらに研究を進めて、モノ資料に残されている文字データの活用方法を検討している。具体的には、ラベルや焼き印、記名などを記録収集し,それを金沢市商工業者のデータベースと重ね合わせることで、来歴を明らかにしようと試みている。他に商品・部品データベースの作成や金属分析は継続して,データを収集している。
研究計画の意義・目的に即した研究の実施
近現代の生活資料を整理・保存するための手法やデータベースの構築を検討していくという当初の計画は,今のところ順調に進められている。ただし、当初の計画で想定していなかったこととして、状態調査の実施中に家電の液漏れが発見された時は、有害物質の性質や法規制に関する調査をおこない、博物館資料としての保存方法や安全管理に関する検討をおこなった。
連携の効果(連携による新たな視座の開拓、高度化)
「『人間文化資源』の総合的研究」は紙資料、モノ資料、映像資料といった研究資料を幅広く対象にしているが,その中で本研究は近現代のモノ資料と紙資料を中心に扱っている。それらには,製品の多様化や部品の複雑化、新素材の開発、コレクションの枠組み(誰がどこで何を目的として収集したかが部分的にわかること)といった問題が横たわっているが、方法の確立していない資料を収集・保存し、地域の生活や歴史とどのように関わらせて研究していくかといった点で他班と共通の問題意識をもっていると考えている。
研究体制
機関間の連携体制
国立民族学博物館の館蔵資料,とくに日本国内の生活関連資料と収集・保存の方法を比較検討することで、連携を図っている。また、資料の整理・保存に実績のある元興寺文化財研究所と連携することで、これまでのノウハウを共有化しつつ、新たな方法を模索している。
機構外研究者の有機的参画
おもな研究対象資料が「金沢地方近代生活資料」であることから、石川県立歴史博物館の本康宏史氏と金沢市史の編纂に関わっていた神奈川大学の松村敏氏に参加していただき、地域史の視点から資料の特徴を明らかにしようと試みている。また、この資料収集に関わった北陸大学の小林忠雄氏より,都市民俗学の視点からこの資料に着目した経緯とその後の整理方法について教えていただいた。
基盤となる機関の研究との合理的相補関係
状態調査の方法やデータベースの作成は、館内での資料保存に向けた提案をするとともに、将来的には他館で広く参考にしてもらうことを目指して進めている。
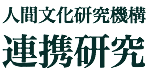
 総括班ホーム
総括班ホーム