研究成果の公表(研究成果物を含む)
青木隆浩「『金沢地方近代生活資料』を収蔵した経緯と意義」総合誌歴博166,2011年。
調査分析
館蔵資料「金沢地方近代生活資料」の文字情報調査
館蔵資料「金沢地方近代生活資料」の蛍光X線分析
その他の成果
特集展示「山の流行服」(2015年3月10日~9月6日(日)
概要説明
国立歴史民俗博物館所蔵の「石川県白山麓山村生活用具」は,もともと石川県加賀市に在住していた自称・民具収集家の故・伊藤常次郎氏が収集していた個人コレクションを加賀市の「白山麓の山村生活用具及び民家」と「白山麓の積雪期用具」,小松市の「白山麓西谷の人生儀礼用具及び民家」と分割収蔵したものである。そこで,本研究会では,昨年度から伊藤氏のコレクションの全体像を把握するため,それらの関係について調査をしている。昨年度の段階では,歴博所蔵資料の内訳と資料カードの内容について調査したうえで,加賀市と小松市の資料と比較考察した。
今年度は,さらに調査を進めるため,まず分割収蔵と加賀市,小松市の資料の文化財指定に関わった文化庁元職員の天野武氏より,当時の様子をうかがい,さらなる資料調査をおこなったうえで,その成果を2015年3月10日(火)~9月6日(日)の特集展示「山の流行服」で公開した。また,3館の中で最も点数の多い加賀市の資料を再度調査し,資料の収集先である山中温泉東谷地区での現地調査をおこなう。
それらに加え,研究会の初年度から続けている館蔵資料「金沢地方近代生活資料」の文字情報調査と蛍光X線分析をおこない,モノ資料から直接得られる情報を収集して分析に用いた。
5年間の成果
本研究班は,もともと国立歴史民俗博物館の館蔵資料「金沢地方近代生活資料」を対象として,来歴のよくわからない資料群を整理し,モノ自体から得られる情報をもとに調査・研究することを目的として組織した。これは,全国の博物館・資料館の多くが,未整理のモノ資料,とくに民俗資料の扱いに苦慮していることをふまえ,1つのモデルケースとして活用・保存のあり方を検討することを意識している。
そこで,本研究会では,追跡できる限りの来歴調査を聞き取りによっておこなったうえで,モノ資料自体に記載されている文字情報や素材の科学的な分析からデータを得て,調査研究をおこなった。文字情報からは,しばしば屋号や製造所,使用地,使用者などを知ることができるので,商工業者の名簿などと比較すれば,一部ではあるがさらなる情報を得ることができる。一方,素材の蛍光X線分析からは,時代ごとに素材の変化を追うことができる。
また,それらのデータを分析するのに有用な商品カタログやチラシ類を収集し,目録を作成した。それらはあまり市場に出回っていないが,5年間で728件もの資料を収集することができた。年代の異なる商品カタログやチラシ類を幅広く収集すれば,工業製品にほぼ限られるが,モノ資料の製作年代や製作地,使用方法,部位名称などについて情報を得ることができる。まとまった数の商品カタログやチラシ類を収蔵している博物館は少ないので,今後はこれらを国立歴史民俗博物館の館蔵資料として登録し,全国の研究者に活用していただきたいと考えている。さらに,2016年度秋には,この商品カタログやチラシ類の一部を用いて,「身体をめぐる商品史」という企画展示を開催する計画である。
次に,研究を進める過程で,「金沢地方近代生活資料」に白山麓の資料が含まれていることに注目して,同じ館蔵資料の「石川県白山麓山村生活用具」との比較考察をはじめた。そして,この「石川県白山麓山村生活用具」が,もともと加賀市の「白山麓の山村生活用具及び民家」と「白山麓の積雪期用具」,小松市の「白山麓西谷の人生儀礼用具及び民家」と同じ個人コレクションであったことを知り,それらの全体像を把握すべく聞き取り調査や資料調査を開始した。結果的に,昭和30年代以前における白山麓の生活用具は,全国的にも古いタイプのものであったことが判明し,その成果を平成27年3月10日(火)~9月6日(日)の特集展示「山の流行服」で公開することができた。
さらに,これらの個人コレクションを国立民族学博物館所蔵の「大村しげコレクション」と比較考察したことで,」2013年12月1日(日)には,金沢市の石川県政しいのき迎賓館で「博物館における地方資料の収集と活用」という公開研究会を開催し,国立博物館による地方資料の活用や保存の現状について報告することができた。
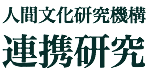
 総括班ホーム
総括班ホーム