研究会・シンポジウム・学会などのお知らせ
-
2009年3月8日(日)
《機関研究成果公開》公開シンポジウム「人類学の挑戦―これまでとこれから」 -
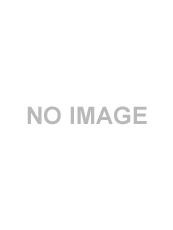
- 日時:2009年3月8日(日) 13:00~17:30
- 場所:国立民族学博物館 第5セミナー室
趣旨
国立民族学博物館と日本文化人類学会は、平成20年度連携事業「実践人類学ワークショップ」の一環として、国際協力の実践人類学シンポジウムを開催します。 国立民族学博物館の機関研究領域「文化人類学の社会的活用」(2004~2008年度)では、日本における実践人類学の展開を目指して、日本文化人類学会や国際協力機構等と協力しながら複数のプロジェクトを実施し、調査研究活動を行ってきました。このシンポジウムでは、これまでの研究活動を振り返り、検討することを通して、今後どのような調査研究を実施すべきかについて考えます。
プログラム
【総合司会:田村克己(民博)】
13:00~13:40 基調講演
「文化人類学の何が国際協力に役立つのか-基礎研究と応用をめぐって」
松園万亀雄(民博) 基調講演の内容を読む
基調講演の内容を読む13:40~13:55 「みんぱくにおける実践人類学の展開:機関研究「文化人類学の社会的活用」の総括」
岸上伸啓(民博) 総括の内容を読む
総括の内容を読む14:00~17:30 シンポジウム 【座長:岸上伸啓(民博)】 報告1「開発援助プロジェクトとの付き合い方」  報告1の内容を読む
報告1の内容を読む
報告者:鈴木紀(民博)
報告1のコメンテーター:関根久雄(筑波大)報告2「文化人類学と国際医療協力のつながり・へだたり」  報告2の内容を読む
報告2の内容を読む
報告者:白川千尋(民博)
報告2のコメンテーター:杉田映理(東洋大)報告3「大量虐殺を記憶する装置:グアテマラにおけるあるNGOの活動」  報告3の内容を読む
報告3の内容を読む
報告者:關雄二(民博)
報告3のコメンテーター:栗本英世(大阪大)報告4「災害の人類学的研究から防災学へ」  報告4の内容を読む
報告4の内容を読む
報告者:林勲男(民博)
報告4のコメンテーター:田中聡(富士常葉大)<休憩10分> 総合討論 【座長:鈴木紀(民博)】
総合コメント1 佐藤 寛(アジ研)
総合コメント2 沖浦文彦(JICA)
総合討論(真崎克彦、石田慎一郎、信田敏宏、滝村卓司、花谷厚が参加)基調講演
文化人類学の何が国際協力に役立つのか―基礎研究と応用をめぐって
松園万亀雄(国立民族学博物館)かつて私は「援助機関と人類学の世界、ともに相手の近年の動きを『向こう岸の出来事』とみなすのをやめて、目と目を合わせる時期にきているのではないだろうか」と書いた(1999年)。その心は、ひとつには日本の人類学者が開発援助活動に参画する度合いがきわめて低い、つまり「お呼びでない」のは、日本の国際協力事業の哲学に問題があるのだろうということ。二つめには、援助機関で仕事をしたことのある数少ない人類学者の体験が個人的な体験として閉じこめられるか小さなイングループの中だけで語り合われ、一般の人類学者のあいだでほとんど共有されていないこともまた大きな問題であること。この二つのことを言いたかったのである。
民博では、2004年から開始した機関研究「文化人類学の社会的活用」のなかで、開発や国際協力に関連する実践人類のありかたについて、さまざまに議論してきた。欧米の社会科学者で開発援助にも携わってきた人びとを招いてワークショップを度重ねて開催し、一般にも公開されたシンポジウム、フォーラム、ワークショップも数多い。この間、実践人類学関連の民博共同研究も活発におこなわれてきた。
この5、6年で状況はいくらか改善されてきたようにみえる。民博の研究集会にはJICAや関連機関、国連諸機関、NGOの関係者に熱心に参加していただいたし、またJICAと大学、研究機関との間では制度的な人材交流がいっそう活発になってきた。しかし、ようやく緒についたというところであろう。まだまだ問題は多い。
この数十年で人類学のフィールドワークをとりまく状況は一変した。どんな僻遠の地にも開発の波が押しよせている。人類学者の民族誌の書きかたにも変更が求められている。開発による変化の章を書かねばならない。しかも、次の変化の大波のまえに書きあげて出版せねばならない。人類学者にはカルチュア・アズ・ア・ホールを旨としたかつてのような民族誌が書けるのだろうか。学生に対しては、どんなフィールドワーク論を語ればよいのか。
開発という名の変化に対する自分の位置どりを、人類学者はそれぞれに選択しなければならなくなった。
みんぱくにおける実践人類学の展開―機関研究「文化人類学の社会的活用」
岸上伸啓(国立民族学博物館)1 はじめに
平成16年度から民博の機関研究のひとつとして「文化人類学の社会的活用」がスタートした。そのプロジェクトとして「日本における応用人類学の展開のための基礎的研究」と「防災対応プロセスに関する人類学的研究」が採択され、平成20年度まで5ヵ年間(延長1年を含む)実施された。欧米では、文化人類学者が政府の開発援助機関や営利企業において人類学的な知識を活用しながら活躍している。一方、日本の文化人類学は、欧米とくらべると応用研究や実践的な側面の展開がたち遅れている。この研究プロジェクトは、そのギャップを埋めるための基礎的な研究であり、その目的は日本における応用人類学の形成とその展開を促進させるための基礎的な研究を行うことであった。この5年間に民博を中心に展開された研究を紹介し、総括するのが、この報告の目的である。また、議論のための問題提起を行う。
2 実践人類学とは何か
実践人類学とは、人類学的な方法や知見を利用して現代社会が直面しているさまざまな問題を理解・解明し、その解決を試みようとする人類学的な研究である。鈴木紀が指摘するように、それは基礎研究や理論研究の延長線上にその成果の社会的活用を試みるものであり、応用だけに特化したものではない。
3 プロジェクトの展開
この実践人類学を日本において推進するための基礎的研究プロジェクト「日本における応用人類学の展開のための基礎的研究」を国際ワークショプ、シンポジウム、共同研究会、科研調査、他機関との連携ワークショップなどと組み合わせて実施するとともに、その成果を公開シンポジウムや書籍の出版によって公開した。
3.1 国際ワークショップ・シンポジウムの実施
2004年度:「デンマーク、スウェーデン、日本の開発援助:開発における社会科学の役割」、「ジェノサイド後の社会の再編成‐中米グァテマラのケース」、「開発とジェンダー(1)」
2005年度:「「歴史と記憶」-ラテンアメリカの先住民族と暴力の歴史化」、「開発とジェンダー(2)」、「カナダ国際開発庁と世界銀行における人類学者・社会学者の役割:社会評価と参加型開発、社会の安全配慮」、「ジェノサイド後の社会の再編成―平和のためのコミュニティ・ミュージアム」
2006年度:「人間を中心にしたマラリア対策―ミャンマーJICAプロジェクトからの提言」、「ノルウェーの開発協力―ベルゲン大学、クリスチャン・マイケルセン研究所、NGO」
2007年度:「オランダの社会研究所とNGOおよび世界銀行の国際協力」3.2 みんぱく共同研究会の実施
「開発援助の人類学的評価法」、「開発と先住民族」、「フェアトレードの思想と実践」など3.3 科研調査の実施
「先住民による海洋資源の流通と管理」(基盤A)、「世界の開発援助機関と援助活動に関する文化人類学的研究」(基盤B)、「開発援助プロジェクトの評価方法に関する文化人類学的研究」(基盤B)など3.4 国際協力機構との連携ワークショップの実施
JICA大阪とみんぱくの連携ワークショップとして開始し、2008年度から阪大GLOCOLが参加し、「研究者と実務者による国際協力勉強会(JICA大阪・民博・阪大GLOCOLセミナー)」となる。2008年度末までには9回の勉強会を実施。3.5 日本文化人類学会との連携ワークショップの実施
「国際協力のための実践人類学ワークショップ」ワークショプを研究大会の分科会などとして1年に2度、実施。3.6 公開シンポジウム
人間文化研究機構第7回公開講演会・シンポジウム「国際開発協力へのまなざし‐実践とフィールドワーク」(2007年)や一般公開シンポジウム「実践としての文化人類学―国際開発協力と防災への応用」(2006年)など3.7 『みんぱく実践人類学シリーズ』の刊行
松園ほか編著『人類学と国際保健医療協力』(2008年、明石書店)など平成20年度末までに第6巻までを刊行。平成21年度末までに第9巻までを刊行予定。4 これまでの成果
4.1 各国の援助機関や開発NGOにおける文化人類学の状況の把握
4.2 国際協力機構や日本文化人類学会との連携の展開
4.3 開発事業評価や医療保健協力、防災・復興、資源管理などの分野への貢献5 問題提起
*どのようにして実践人類学を展開させていくか。
*人類学者は、何をどのように研究し、実践していくべきか。開発援助プロジェクトとの付き合い方
鈴木紀(国立民族学博物館)本報告では2004年度から2007年度にわたって実施した共同研究会「開発援助の人類学的評価法」を振り返り、文化人類学者がどのように開発援助プロジェクトを研究し、その成果をフィードバックできるかを考察する。
共同研究会の目的は第1に日本のODA政策やNGOによる開発援助活動を推進するために必要な人類学の役割を検討すること、第2にその検討結果を開発援助活動に導入するための方法や制度を考案、提言することにあった。
第1の目的については、以下の点が確認された。1)人類学が開発援助活動に貢献するための基本は、開発途上国の住民(援助の受益者)が援助活動をどのように理解し、どのように行動するかを分析することにある。2)分析に際しては全体論的視点を意識し、当該社会にプロジェクト開始以前から存在する多様な因果関係を把握すること、およびプロジェクト以後の中長期的な影響を視野にいれることが望ましい。3)受益者の行動を理解する際に特に重要なのは、受益者側リーダーシップの構築プロセスと、リーダーと支援者との関係である。4)研究者が専門とする地域のプロジェクトを研究対象としつつも、特定の開発セクターに関する通文化的比較を試みることも必要である。
第2の目的については、以下の点が確認された。1)開発援助実施機関は、プロジェクト評価の充実によるプロジェクトの質的向上を重視しているため、「評価」を話題にすることが、研究者と実務者の対話を促進する。2)そのためには既存のプロジェクト評価手法(PCM手法など)に精通し、それを批判的に理解するだけでなく、人類学者の研究成果を導入することでどのように改善できるかを示すことが必要である。3)人類学者は、自らの概念や用語を実務者の概念や用語と対応させて表現する工夫が必要である。4)研究成果を実践に活用するためには、いわゆる「プロジェクト民族誌」を書くことだけでなく、調査行為そのものが実践性をもつこと、あるいは実践性を期待されていることを意識する必要がある。
共同研究会後に明らかになってきた課題として、次の点があげられる。1)共同研究会であつかったプロジェクト評価は、ほとんどがプロジェクトを事後的に考察するものであった。今後は、プロジェクトの計画段階や実施段階に対する、人類学者の関わり方を検討する必要がある。2)個別プロジェクトの評価にとどまらず、援助手法や政策課題に関しても研究を進める必要がある。例えば、日本の生活改善運動を現代の開発途上国の農村開発のために再モデル化すること、官民協調の文脈で開発援助プロジェクトによるフェアトレード推進の方法を検討すること、およびキャパシティ・デベロップメント(能力発展)の文脈で、プロジェクトの成果が持続拡大する条件を精査すること、などが喫緊の課題である。
文化人類学と国際医療協力のつながり・へだたり
白川千尋(国立民族学博物館)2006年10月に長崎市で開催された第21回日本国際保健医療学会・第47回日本熱帯医学会合同大会では、国立民族学博物館の機関研究『文化人類学の社会的活用』の一環として、「文化人類学は医療協力の役に立つのか?-医療従事者と人類学者の対話に向けて」と題したシンポジウムが行われた。4名の発表者がいずれも文化人類学者であったのに対して、フロアーのオーディエンスの多くは医学系の研究者や学生、医療従事者などであり、シンポジウムの主題となった問いなどをめぐって、異分野間の「対話」が活発に行われた。シンポジウムの各発表の内容については、シンポジウムをもとにして編まれた論集『みんぱく実践人類学シリーズ1-人類学と国際保健医療協力』(松園・門司・白川編、明石書店、2008年2月刊行)から知ることができる。
この論集に所収された諸論文では、医療協力プロジェクトの対象となる地域社会の人々が、下痢症、ハイリスク妊娠・出産、避妊といった健康や病気、身体などに関係するものごとに関して、生物医学的(bio-medical)なものとは異なる独自の知識や認識、行動様式などをもっていることが、詳細に明らかにされている。今日の日本の医療協力プロジェクトがもっぱら生物医学的な視点に基づいて行われていることを念頭に置くならば、こうしたいわゆる民俗知識などの理解に携わる文化人類学的な営為は、国際医療協力とは縁の薄い(へだたりのある)ものとみることができるかもしれない。
しかしながら、論集の各論文のなかでも明示的ないし暗示的に述べられているように、とりわけ「住民参加」や「住民ニーズ」などを強く意識した医療協力プロジェクトを行おうとする場合には、先の民俗知識などに関する知見を十分にもっていることが、プロジェクトを効果的なものにしてゆくうえで重要と言える。そして、この点からすれば、地域社会の人々の側の知識や認識、行動様式などを理解しようとしてきた文化人類学と、国際医療協力の間には接点(つながり)があることも理解できる。
とするならば、文化人類学、あるいは文化人類学者が、国際医療協力に関わる機会は少なからずありそうだが、実際の状況(とくに今日の日本において)は果たしてどうであろうか。本発表では、この問いを手がかりにしながら、文化人類学と国際医療協力の関係のあり方(つながりとへだたり)について考えてみたい。なお、その際には、具体的な対象として、医療協力プロジェクトのなかで用いられることの多いKAP(knowledge, attitude, practice)サーベイに目を向ける。
大量虐殺を記憶する装置:グアテマラにおけるあるNGOの活動
関雄二(国立民族学博物館)本報告の契機は、2004年11月27日に国立民族学博物館において開催された機関研究ワークショップ「ジェノサイド後の社会の再編成―中米グアテマラのケース―」および、2006年3月11日に、やはり国立民族学博物館で開催された機関研究ワークショップ「ジェノサイド後の社会の再編成―平和のためのコミュニティ・ミュージアム―」に遡る。ワークショップに招へいしたのは、グアテマラにおいて虐殺された遺体を発掘し、裁判で証言するなど、大量虐殺の記憶をとどめようと奔走するグアテマラの人類学者フェルナンド・モスコソであった。以来、報告者は短期間ではあるが、モスコソが率いるNGO組織「平和のための歴史化」の活動を調査してきた。今回の概要報告は、現地でのインタビュー、活動関係の書類の分析に基づくものである。
モスコソが虐殺案件の刑事裁判に関わると同時に、実現しようと試みているのは、内戦後の復興に必要な記憶の回復であり、崩壊したコミュニティの再生である。そのため彼が率いるNGOは、虐殺に関わる証言収集もさることながら、コミュニティ・ミュージアムやモニュメントの建設、そして壁画の制作を推進している。本報告では、まず、こうした活動の発端となったアルタ・ベラパス(Alta Verapaz)県パンソス(Panz?s)村で起きた大量虐殺事件に焦点をあて、土地問題と関連した歴史的背景、さらにはモスコソがかつて所属したグアテマラ法人類学協会による証言や遺体発掘データの一部を紹介する。その上で、「平和のための歴史化」が、博物館やモニュメントを建設し、壁画を制作するにあたって、パンソス村や周辺の住民らとともに、数年にわたって実施してきた共同作業に注目する。
報告者は、この共同作業の過程こそが、崩壊した村における新たなリーダーの誕生と結びつき、また一方的な展示の強制に終わらなかった点で評価できると考えている。一方で、現在の博物館は、開館当時に比べ、活動は停滞している事実にも触れる。この原因として、虐殺とは直接関わり合いをもたない若者を対象としたリーダーシップの養成が、逆に虐殺の記憶を保持する生存者や遺族の意識や行動と乖離する結果をもたらした点を指摘する。
最後に、本報告の研究的位置づけを示しておきたい。現在、開発の分野で主張される「人間の安全保障」は、縦軸として、国家による上からの安全保障と、個人・家族・地域社会という下からの安全保障とをつなぐことをめざし、一方で横軸として、欠乏・貧困に対する安全保障、そして国内統治を深め、人々の知識を高める安全保障を掲げている。いわば、人間の安全保障の中核概念は、「恐怖からの自由」と「欠乏からの自由」の双方を同時に複眼的に考慮することでもある。
後者の「欠乏からの自由」について言うならば、アマルティア・センの問題意識に代表されるように、その概念基盤に脆弱性、エンタイトルメント、ケイパビリティといった貧困の経済社会的分析を置いている点で、これまで多くの文化人類学者や社会学者が議論や実践に加わってきた点を指摘できよう。
一方で、破綻国家のもとでの紛争犠牲者である難民及び国内避難民の保護や自立支援など、人間の基本的人権と自由を脅かす国家の破綻、政治暴力からの保護といった側面に関する我が国の文化人類学的研究は、そのテーマの大きさ、国家など対象とする組織や集団の特徴故に、どのように取り組むべきか迷いがあり、いまだ研究は緒についたばかりだと言わざるを得ない。「人間の安全保障」が机上の空論に終わらず、二つの自由が相互補完的であり、かつ国家レベルの問題の現象面は、常にフィールドという現場で生じていることを認めるのなら、やはり「恐怖からの自由」の分野についても文化人類学的研究を推進していく必要があることはいうまでもない。
災害の人類学的研究から防災学へ
林勲男(国立民族学博物館)1 背景
近年の災害を見るとその頻度や規模は拡大しており、今後も、地震・津波・火山噴火などの地盤災害や、気候変動に伴う海面上昇や降雨量・降雨時期の変化などが、人間の生活環境や生活手段に与える影響の拡大が懸念されている。それは農漁業など自然環境に直接的に依存した生活を送る人びとだけでなく、都市に暮らす人びとにとっても同様である。
一方、そうした環境変化に対応すべき人間の生活も、近代化やグローバル化のなかで都市と地方の双方において大きく変化してきている。都市においては人口の過密化や交通・情報インフラの発達が災害の複雑化を招き、住民の流動性は地域的な人のつながりを弱めており、地方においては過疎化や高齢化が進むことで、やはり地域社会の災害対応力を減衰させている。災害に対する地域社会が孕むこうした脆弱性は、人口の過密化や過疎化以外にも、歴史的・文化的・政治的なさまざまな要因の絡み合いとして形成されたものであるにもかかわらず、実態の正確な把握が不十分のまま、防災や災害復興の国際協力が行われているのが現状であり、文化人類学をはじめとするフィールドサイエンスの知見や研究手法を用いた、現状の正確かつ詳細な把握とそれに基づく対策が緊急の課題としてあげられる。2 機関研究
機関研究「災害対応プロセスに関する人類学的研究」では、アジア・太平洋地域における自然災害への社会対応について研究してきた。調査対象は、(a)災害後の復旧・復興プロセスと、(b)将来の災害リスクの軽減化を図るプロセスの二つである。両プロセスは、災害の経験からいかに生活を再建しようとしているのか、災害に対してどのように向き合って人びとは暮らしているのかを把握する重要な局面であり、政治・経済構造、社会組織、住民の価値観などを含めた総体的な民族誌的アプローチが求められる。
ここで重要なのは、両プロセスとも発災から人道支援を含めた緊急対応、復旧、復興そして次の災害対策としての防災という災害サイクルを構成する局面であるという点である。被災地の被害状況やそれへの緊急対応についての情報量に比べ、災害サイクルの他の局面についてはマスメディアを通じて入手できる情報も少なく、とくに外部(地域外、国外など)からの把握が難しく、また一般の関心もけっして高いと言えないのが現状である。
本研究プロジェクトでは、2004年12月に発生したインド洋地震津波災害をはじめ、アジア・太平洋地域で発生した災害の被災地、および近い将来の災害発生が懸念されている地域を調査対象として研究を実施してきた。支援組織間の調整の不備、支援する側とそれを受ける側の間に生じた問題、災害サイクルや住民の生活再建を長期的な視点から捉えずに提供された支援が引き起こす問題、地域防災活動の持続性の難しさなどが浮き彫りとなった。災害サイクルという長期的かつ総体的な視点から現地社会を捉えながら、支援の実務者のみならず防災学分野の研究者や地元行政と共に、人類学者や地域研究者による広い意味での防災プロジェクトへの積極的な関与が一層求められている。3 これから
現在、地球規模で取り組むべき課題の一つに温暖化対策がある。温室効果ガスの排出量削減や化石燃料からクリーン・エネルギーへの転換の促進が図られ、一般にも資源のリサイクルや冷暖房温度の調整など、「省エネ」が市民レベルでも実践されている。こうした温暖化「緩和策」を推し進める一方で、温暖化の影響として高まる災害リスクへの「適応策」を講じることも急務であるが、その取り組みの動きは「緩和策」に比べると鈍いと言わざるをえない。
日本では、首都直下地震、東海・東南海・南海地震などの巨大地震に加え、温暖化の影響による海面水位と海水温度の上昇、大気中の水蒸気量の増加により、大型で勢力の強い台風や豪雨による、河川氾濫・内水氾濫・高潮といった大規模な水災害や土砂災害の発生が予測されており、リスク評価、防災施設整備、土地利用、人材育成等を含めた適応策の検討がすでに開始されている。 国内では、将来起こりうる災害について生活環境の中で具体的に理解し、災害発生時の迅速な退避・対応が可能となるように、ハザードマップの作成とそれに基づいた防災・避難訓練、災害情報システムの整備、要援護者支援対策など、行政と市民が連携し、地域社会の特性に沿った災害対応力の強化が図られている。しかしながら、ハザードの理解やハード面での被害抑止策に関する研究は大きな進展を見せているのに対して、ハザードに対抗する、あるいは被害を受ける社会については、社会科学の研究蓄積が防災に十分に反映されているとは言えない。たとえば、国内外の防災を含めた開発分野で用いられている固定的で静態的な地域社会(「コミュニティ」が好んで用いられる)の概念では、もはや捉えきれない状況に人びとは暮らしている。これは日本をはじめとする先進諸国に限ったことではなく、開発途上国においても変化のスピードに緩急の差はあるものの、同じ傾向を示している。
地域社会における災害に対する社会的脆弱性の的確な把握と、他分野の研究者や実務者と連携しながらの災害対応力あるいは適応力の強化支援が国際的に必要であり、人類学や地域研究からの参加も求められている。公開シンポジウム「人類学の挑戦―これまでとこれから」実行委員会
- 松園万亀雄(国立民族学博物館)
- 田村克己(国立民族学博物館)
- 石田慎一郎(大阪大学)
- 沖浦文彦(国際協力機構)
- 岸上伸啓(国立民族学博物館)
- 栗本英世(大阪大学)
- 佐藤寛(アジア経済研究所)
- 白川千尋 (国立民族学博物館)
- 杉田映理(東洋大学)
- 鈴木紀(国立民族学博物館)
- 関雄二(国立民族学博物館)
- 関根久雄(筑波大学)
- 滝村卓司(国際協力機構)
- 田中聡(富士常葉大学)
- 信田敏宏(国立民族学博物館)
- 花谷厚(国際協力機構JICA研究所)
- 林勲男(国立民族学博物館)
- 真崎克彦(清泉女子大学)
