研究の意義・目的
歴博が創設以来、遂行してきた正倉院文書のレプリカ製作事業を基礎に、レプリカ写真をデジタル化したうえで表裏の接続状況を容易に観察できるシステムを整備する。そのうえで木簡・漆紙文書などとの比較により古代における帳簿・文書論の深化を目指し、さらには中世や近世文書との機能論的比較を行う。
約一万点に及ぶ正倉院文書は日本古代史研究の基本資料であり、文献史学だけなく多様な学問分野にわたる歴史情報資源の貴重な宝庫といえる。豊富な内容を有する正倉院文書の情報は、保存の問題からこれまで十分には公開されてこなかった。そのため原本保管機関である正倉院事務所の協力を得て、デジタル情報として利用できる基盤を整備することは大きな意義を有する。古代日本の歴史情報資源の開発は、新たな古代史像を描くことを可能とし、まさに国立歴史民俗博物館が目指す「博物館型研究統合」(博物館という形態をもつ大学共同利用機関としての特長を最大限に活かして、資料の収集・共同研究・展示を有機的に連鎖した研究)にふさわしい研究事業であるといえる。
研究方法
歴博が創設以来、遂行してきたレプリカ複製事業を基礎にして、それをデジタル化したうえで表裏の接続状況を容易に観察できるシステムを整備する。そのうえで帳簿の復元・分析、中世・近世文書との比較検討を行う。
研究計画
- 第一年目 レプリカ撮影およびデジタル的接続(三年目まで継続)
- 第二年目 自在閲覧方式の改良(表示位置反転・微細連動表示・画面切り替えなど)
- 第三年目 写経所帳簿群の分析、下総・美濃戸籍等の現地調査、中間総括シンポジウム
- 第四年目 中世・近世文書との比較検討、韓国文字史料との比較
- 第五年目 復元複製の作成、従来の釈文訂正、総括国際シンポジウム
- おおよその重点的年次進行を示すものであり、内容は重複していく
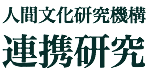
 総括班ホーム
総括班ホーム