研究内容
研究の進捗状況
当初の予定であった正倉院文書自在閲覧システムの基本ソフト開発および素材としてのレプリカ写真のデジタル化は、公文部分であるおよそ120巻において完成した。また、断簡情報を活用した仮想的接続により正倉院文書を復元・活用する高度化利用を可能とするため、複数の書籍やDBなどに分散している情報を断簡ごとに整理したDBは公文部分においてはほぼ完成した。また、共同研究員による各分野の発表は一巡し、総括的なシンポジウムを開催する段階に達した。さらに下総戸籍の遺称地を現地調査し、地理情報などを高度化する方法、異体字などの時代的変遷などについて議論した。韓国中央博とも展示や講演会を通じて連携した。
研究計画の意義・目的に即した研究の実施
基盤機関が開館以来、継続的に製作してきた正倉院文書レプリカを基礎として、歴史情報資源を高度化し、有効活用の方策を探るという点で、三年間においては、ほぼその基礎作業を行うことができたと考える。
連携の効果(連携による新たな視座の開拓、高度化)
これまで正倉院文書の調査研究をおこなってきた正倉院事務所・東京大学史料編纂所・大阪市立大学などの研究機関がかかえる問題点や調査研究内容の総括をおこなってもらい、学界におけるニーズと各機関のミッションとの間で、どのように連携して活動していくかを議論した。そのうえで写真情報を中心とするデータベースの公開が必要であるとの共通認識を得た。
研究体制
機関間の連携体制
機構内部には正倉院文書を専門に扱う研究者はいないので、歴史情報学というやや広い立場からの共同研究への参加を求め、他の時代の文書論との協業としては、国文研チームの連携として構想している。
機構外研究者の有機的参画
これまで正倉院文書の調査研究を中心的におこなってきた正倉院事務所・東京大学史料編纂所・大阪市立大学などの研究機関の研究者を共同研究員に委嘱した。
基盤となる機関の研究との合理的相補関係
歴博が創設以来、遂行してきた正倉院文書レプリカを基礎にしており、また出土文字研究も活発に推進しており、それらを前提にデジタル化したシステムを整備し、古代文書論を深化するという意味では合理的相補性があると考える。
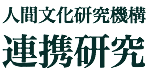
 総括班ホーム
総括班ホーム