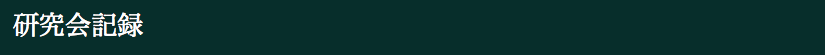第1回研究会
【日程】2010年8月23日
【場所】国立歴史民俗博物館第2会議室
【報告】
鈴木 卓治氏プレゼンテーション「歴博のデジタル資料について」
【討論】
議題1「歴博正倉院文書DBのシステムの方向性を考える」
最終的な方向性として、他DB(東大史料編纂所大日本古文書DB、SOMODA)との相互連携という方向性が提示された。具体的表示形式については、表裏同時表示が有用であるという意見や正倉院文書研究ツールの情報が盛り込まれていると良いなどの意見が出された。また、正倉院文書展示における解説版としてもDBが活用できるとの提案がなされた。さらに、帳簿論の見地からもDBの方向性の議論が行われ、整理が難しい続々修などについてはまず作業用・研究用ツールとしてのDBを作成すべきとの提案がなされた。
議題2「研究後の展示の方向性を考える」
展示においてはまず正倉院文書の表裏の仕組みを立体的に示す必要があるとの提案がなされた。写経所関係の展示の方法については、写経の国家的・政治的な側面、写経生、物品などに着目した展示が提案されたほか、ストーリーのある展示にする必要性があるとの意見が出された。また、DBと展示の連関のさせ方を明確にする必要があるとの意見が出された。
議題3「DBの運用の問題点を考える」
DBのネット公開における諸問題について説明がなされた。また、DB運用におけるセキュリティー・運用規定・著作権・宮内庁書陵部の見解などについて議論がなされたが、各位の見解は一致しなかった。
第2回研究会
【日程】2010年12月15日
【場所】国立歴史民俗博物館第2会議室
【報告・主な討論内容】
仁藤敦史氏「研究の現状と方向性」
歴博DBはデジタル化カラー写真、東大史料編纂所は文字列・接続情報の調査という目的の違いがあり、相互利用ができるとよいとの意見が出された。また、レプリカは精密性、DBは検索・一覧性という特性があり、相俟った使い方をすればよいとの提案がなされた。
後藤真氏「SOMODAと歴博データベースの連携の可能性について」
報告内容について、システムプログラムを確立する必要があることが説明された。DBで研究素材を提供するのか結果を提供するのか、という問題提起がなされ、復原結果の提示にも一定の意義があるとの意見が出された。また、SOMODA「個別写経事業DB」の内容は、①人、②間写経No.、③事業名、④経典、⑤部数、⑥巻、⑦日付、⑧断簡ID、⑨宣者、⑩根拠史料、⑪初見・終見である、との説明がなされた。
安達文夫氏「正倉院文書と画像閲覧―表裏の比較、仮想的再構成」
まず、一次面・二次面の表示方法について、上下(研究者は見慣れている。全体像表示に有効)・左右(文字の比較や部分閲覧に有効)・単一表示すべてができるのが最善である、との意見が出された。また、表示機能について、複数巻を並べる・紙端や継目の画像を見るといった機能の要望があった。左右は反転する必要はなく、上下は反転がフレキシブルにできるようにしたいということでまとまった。但し、技術上の問題がクリアできても操作が煩雑になる可能性が指摘された。
溝口優樹氏・稲葉蓉子氏「正倉院文書関係文献目録の作成作業について」
再録文献の扱い方について、別の項目を設けるなどの意見が出された。また、論文の内容に関するキーワードを出す、NDL-OPAC・Webcat・CiNiiへのリンクがはられていると良いとの意見が出された。
第3回研究会
【日程】2011年3月1日
【場所】国立歴史民俗博物館第2会議室
【報告・主な討論内容】
今津勝紀氏「日本古代史研究とシミュレーション-地震・集落・人口-」
シミュレーションについては、材料となるデータを吟味する必要性が指摘された。正倉院文書に関わるものとして、戸籍を素材にして人口シミュレーションを行う場合は地図情報との統合も必要であるとの意見が出された。また、郡域や郷域の推定への活用の可能性が指摘された。
倉本一宏氏「古代史料とデジタル化-『御堂関白記』をめぐって」
DB公開における情報の出し方について討論が行われた。
稲葉蓉子氏「作業経過報告」
【意見交換】
- 歴博購入「山辺諸公手実」(二通)の実見と意見交換
第1回見学会
下総国府と大島郷を歩く
【日程】2011年5月6日
下総国府・下総国葛飾郡大島郷比定地などを見学した。主な見学場所は、アイリンクタウン市川、伝真間の継橋、伝真間の井、弘法寺古墳、和洋女子大学文化資料館、旧六所神社、明戸古墳、矢切りの渡し、柴又八幡神社古墳、胡録天神社、立石様、推定古代東海道駅路であった。
第4回研究会
【日程】2011年6月27日
【場所】国立歴史民俗博物館第2会議室
【報告・主な討論内容】
飯田剛彦氏「国立歴史民俗博物館蔵・山辺諸公手実をめぐって」
二通の手実の料紙や書き込みの状態などについて意見が出された。また、外部に出た手実が外れた理由について、二重巻になっていた可能性が指摘された。さらなる検討として、天理大学図書館所蔵の物との比較や非破壊的検討、レプリカやカラー写真と合わせた検討という方向性が示された。
安達文夫氏「正倉院文書と画像閲覧システム-22年度の到達点と今後の課題-」
画像データの補正・表裏画像のズレなどの問題点が指摘され、解決策として写真の中に印を入れて自動補正を行うという提案がなされた。また、適宜ピンポイントで微調整する機能を加えることを優先するとの方向が示された。歪みを含んだ画像閲覧システムがどこまで研究に耐えられるかという点については、細かい比較は現物あるいはレプリカにあたらなくてはならないとの意見が出された。
仁藤敦史氏「第一期連携研究の実績評価について/中間総括シンポ構成案」
稲葉蓉子氏・溝口優樹氏「正倉院文書目録・関係文献目録の作成作業の進捗状況」
第5回研究会
【日程】2011年9月21日
【場所】国立歴史民俗博物館第2会議室
【報告・主な討論内容】
高田智和氏「字体変遷モデルと国語研本『金剛頂経』の漢字字体」
国立国語学研究所「漢字字体規範DB」が紹介され、漢字字体の収集による字体変遷モデル構築の有効性が指摘された。それに基づいた研究として、国語研本『金剛頂経』の検討が行われた。討論においては、DBは地域・時代による漢字字体の変遷モデル構築が目的であるとの説明がなされた。DBにおける古文書の文字や書写した文字の位置づけについて質問があり、それに対し「正字」の用語の概念が統一されていないこと、墨書の文字は比較的安定的であるが活版化が字体変化の画期となる場合があると説明がなされた。
山口英男氏「正倉院文書調査110年-史料編纂所の正倉院文書研究-」
東京大学史料編纂所が行ってきた正倉院文書調査の歴史について報告がなされた。討論において、調査過程で蓄積された調書及び正倉院事務所に残る調書の保存・活用について検討する必要性が指摘された。また、明治37・38年における正倉院文書の還納について質問があり、借り受けた正倉院文書を全て宝庫に還納し、改めて全ての文書を借り受けたのだろうとの説明がなされた。
【説明】
- 正倉院文書の高度情報化研究」の現況と来年度計画について
- 正倉院文書画像閲覧システムの現況について(仁藤敦史氏)
- 企画展示「古代東アジアの文字文化(仮)」の展示計画について(小倉慈司氏)
- 正倉院文書DBの入力状況について(溝口優樹氏)
第6回研究会
【日程】2012年6月11日
【場所】国立歴史民俗博物館第2会議室
【報告・主な討論内容】
富田正弘氏「古代文書(公家様文書を中心に)の様式の中世への展開」
報告では、古代文書論から中世文書論への連続性の重要性が指摘され、古代の公式様文書を「文書形式の名拠」により類型化するという試みが行われた。討論では、御教書の定義の再検討の必要性、古代における書札様文書の位置づけ、正倉院文書写経関係文書などの文書群の分類論などの論点が提示された。正倉院文書の文書体系論については、帳簿論という切り口が指摘されたほか、大平聡氏の指摘した帳簿の四様式が紹介された。
脇正宏氏「正倉院文書における再構成支援システムに関する研究報告」
正倉院文書DB「切り分け機能」に関する研究経過と問題点が報告された。それらについて歴史研究者側からの意見として、画像固定点やカットライン等、ユーザーの任意調整が可能となるような機能の設置が提案された。
鈴木卓治氏「正倉院文書と画像閲覧システム-23年度の到達点と今後の課題-」
画像の「たわみ」に関する問題点が報告された。それらについて歴史研究者側からの意見として、DB操作におけるユーザーの任意調整機能が提案された。また、異なる巻の画像情報を同一画面に並べて表示する機能の設置が要望された。
第7回研究会
【日程】2012年7月6日〜7月7日
【場所】宮内庁正倉院事務所、東大寺ミュージアム・東大寺図書館・宮内庁正倉院事務所・奈良国立博物館
【報告・主な討論内容】(2012年7月6日)
佐々田悠氏「正倉院事務所における古文書調査のあゆみ」
討論ではまず、新羅国官文書について、紹介された経緯の確認、昭和8年修理時の写真の閲覧が行われた。また、「三次元蛍光分光光度計」の詳細について質問があり、有機系の色料の判定に使用する旨が説明された。東大寺献物帳の写真について質問があり、良質なものとして正倉院事務所編『正倉院宝物』(毎日新聞社、1993〜1997)が紹介された。また、正倉院事務所の事業の今後の方向性について、薬袋類など古文書以外の墨書資料の調査などを行うが、丹裹文書は今後再調査の予定はない旨が説明された。
【閲覧・見学】(2012年7月7日)
- 大方広仏華厳経自巻第12至巻第20の閲覧
- 東大寺ミュージアム見学(開館記念特別展「奈良時代の東大寺」)
- 宮内庁正倉院事務所敷地内見学(飯田剛彦氏のご案内による。「宮内庁正倉院事務所敷地内の東大寺旧跡」)
- 奈良国立博物館見学(「名品展 珠玉の仏教美術」、特別陳列「古事記の歩んできた道」)
第8回研究会
【日程】2012年10月20日
【場所】国立歴史民俗博物館第2会議室
【報告・主な討論内容】
山下有美氏「写経所文書研究の展開と課題」
報告は、1984年〜2012年に発表された写経所文書の研究文献を整理し、研究の展開と今後の課題を示したものであった。討論では、東京大学のゼミ、山口英男氏の科研、正倉院事務所における正倉院文書整理などの現況について説明がなされた。また、正倉院文書の展示方法について経典と帳簿をセットで展示する必要性が指摘された。さらに、写経所文書の分類論の文書名の付け方への反映、写経所文書の新たな分類基準の必要性といった課題が提示された。
高橋一樹氏「中世の「書状」フォーマットと機能-古代文書との対話をもとめて」
報告は、正倉院文書に残された書札・書状が官司内における公的文書の性格を持っていたという指摘を踏まえ、私文書としての書札様文書の性格を根本的に捉え直すものであった。討論では、下文系文書(公式様文書)も書札様文書も公験と捉える主張に対し反論が行われ、主に国司庁宣の副状をどう捉えるかという点について議論が行われた。また、古代史研究の立場からは口頭伝達の重要性、真名文書と仮名文書との使い分けといった視点が提示された。
【意見交換】
正倉院文書表裏同時表示システムについて(安達文夫氏)
全画面表示ができるとよい、DB使用説明書をわかりやすくしてほしい、との要望があった。また、操作性、情報表示、解像度などについて問題点が指摘されたほか、研究用・一般用で操作ボタンの数などを区別してはどうかという意見が出された。
第9回研究会
人間文化研究機構連携研究 正倉院文書の高度情報化研究シンポジウム
【日程】2013年1月26日
【場所】東大寺総合文化センター金鐘会館会議室A
【シンポジウム報告・質疑】
栄原永遠男氏「大阪市立大学栄原ゼミにおける写経所文書研究」
山口英男氏「史料編纂所と正倉院文書調査」
佐々田悠氏「正倉院事務所における古文書調査のあゆみ」
仁藤敦史氏「正倉院文書研究と歴博複製事業の役割」
山下有美氏「写経所文書研究の課題」
端継ぎなどの紙の情報の研究を正倉院文書研究史の中に位置づける必要があるとの意見が出された。
飯田剛彦氏「三つの山辺諸公手実をめぐって」
A手実(天平二十年五月二十日付山辺諸公手実〔正倉院文書拾遺26〕)の伝来に関する由緒書について質問があり、歴博が購入した際には由緒書等は存在しなかった旨が説明された。また、千部法華経書写事業の天平二十年付手実が流出していることとの関連性について質問があった。
小倉慈司氏「『正倉院文書拾遺』後の正倉院流出文書」
レジュメ別表「『正倉院文書拾遺』後に所蔵者が変更となった正倉院流出文書」について、訂正箇所の指摘があった。
高田智和氏「ヲコト点の座標表現」
後藤真氏「正倉院文書の情報化の意義と課題-SOMODAその改善データベース作成経過に即して」
安達文夫氏・鈴木卓治氏「超高精細画像自在閲覧方式を適用した正倉院文書研究支援用閲覧システム」
稲葉蓉子氏「正倉院文書データベースの作成と課題」
DBにおける『正倉院古文書影印集成』の文書名の入力方針について意見が出された。
【紙上報告】
今津勝紀氏「古代家族の復原シミュレーションに関する覚書」
倉本一宏氏「摂関期古記録データベースをめぐって」
高橋一樹氏「古代と中世の文書論をつなぐ「書状」研究の必要性」
富田正弘氏「古代文書様式の中世への展開①-早川庄八『宣旨試論』の検討-」
第10回研究会
【日程】2013年6月3日
【場所】国立歴史民俗博物館第二会議室
【報告・主な討論内容】
安達文夫氏・鈴木卓治氏「正倉院文書研究支援閲覧システムと今後の課題」
画像表示について、上下表示・左右表示・単一表示を選択できることが報告された。微調整ができるとよいとの意見に対しては、「非連動」ボタンで可能である旨が説明された。主な課題として、接続関係確認用画面のデザイン、資料情報の表示方法といった点が挙がった。また、今後必要なものとして、軸・付箋部分の詳細部分画像、料紙・断簡の位置を示すための位置情報の入力といった点が指摘された。
津田光弘氏プレゼンテーション「画像の仮想的な再配置シミュレータについて」
電子付箋・画像の仮想切り出しを含む支援システムの正倉院文書DBへの応用についてプレゼンテーションが行われた。具体的には、接続確認、電子付箋の情報に基づいた検索といった形での応用が可能である。切り取りのピースが多くなると処理が難しくなるという問題については、現時点では「隣り合うものを決める」ことがシステムの目的であることが述べられた。また、表裏を同時に見ることや透過光画像の活用などについて意見が出され、長期的に取り組むという方向性が示された。
遠藤慶太氏「資財としての書物―正倉院文書の漢籍から」
報告は、正倉院文書に見える漢籍を素材とし、奈良時代における漢籍の存在形態を考察し、また「書物に印を捺す」行為は資材管理と捉えられることを論じた。討論では、写経所について天平年間までは光明子の家の施設としての性格が強く、経典に限らず必要な書物の書写を行っていたのではないかという意見が出された。また、蔵書印・管理のための印という区分の可否、「更可請章疏等目録」の性格、技術の伝習における僧侶の役割について議論が行われた。
第11回研究会「前近代日本における官僚制的文書主義」
「正倉院文書の高度情報化研究」班と「9-19世紀文書資料の多元的複眼的比較研究」との合同研究会
【日時】2013年9月7日
【場所】国文学研究資料館 オリエンテーション室
【報告・主な討論内容】
- 山口英男氏報告「古代官司の書類と業務-正倉院文書の解析から-」
- 高橋一樹氏報告「意思決定の記録と伝達にみる日本中世の官僚制的組織と文書」
- 大友一雄氏報告「幕府役職と大名・旗本」
山口英男氏報告
報告では、写経所の業務の流れに即した写経所関係文書の分類が提示され、それぞれの文書・帳簿の業務との関係が説明された。また、業務解析のための「書類学」の必要性、利用形態によって書類を分類する基準として情報定着、情報伝達というとらえ方が提示された。
討論においては、まず報告内容の普遍性について質問がなされ、官僚制と正倉院文書を関連させて論ずるのは難しいこと、但し正倉院文書は文書行政が練り上げられていく時期の文書であるという観点が重要で、律令制以前の業務のあり方の変化を探る手がかりになるのではないかとの回答があった。また、写経所関係文書の呼称について、完成した文書としての呼称だけでなく歴史的変遷を踏まえた呼称という切り口も必要ではないかという指摘がなされた。
高橋一樹氏報告
報告では、中世文書の特徴として本郷和人氏が指摘された手続きを「はぶく」ことに注目した上で、中世における政府的組織の意思決定と文書との関係について以下の論点が提示された。1、直状(裁決権者からの直接命令)に比して奉書(侍臣による伝達)は裁決権者の意思が制約もしくは補強される。2、同一の事案について裁決文書とは別に執行文書が発行されることで実務担当者が明示され、裁決を実現させる権限との合意調達が可視化される。3、古代行政文書に系譜をもつ公文書とは別に評議(合議)の内容を記した文書が発行されるようになる。また、朝廷に対し遅れていた武士の文書行政は一定レベルに達するが、それがそのまま近世の文書行政にはつながらない部分が大きいことも指摘された。
討論においては、報告者が注目した「はぶく」の背景には手続きを担う人々の性格や編成の変化があったのではないか、中世の事務組織はどうだったのかとの質問なされ、鎌倉幕府成立時の文書行政能力は朝廷から輸入されたものであったが、次第にその子孫でない役人も現れてくるとの回答があった。また、応仁の乱による中央人材の流出とともに、地方の文書が15世紀半ばを境に劣化することの背景を考えることの必要性も指摘された。
大友一雄氏報告
報告では、「幕藩官僚制」という論点から役職の組織構造と役人編成が論じられた。江戸幕府の役職序列において大番組・勘定所(旗本職)は組織内での主従関係はないのに対し、寺社奉行においては大名-家来という関係が基本となっている。一方で実際には各役職の業務には家来が関わっており、真田家文書を取り上げて老中職における家来の機能が検討された。
討論においては、家の中での業務の具体相を辿れる文書はあるのかとの質問がなされ、業務の具体相を示す文書が真田家に大量に残されているとの回答があり、蓄積された文書には事務文書が多く、独自の事務文書の作成に官僚制の特徴があるのではないかとの意見が述べられた。また、江戸詰の役人と報告内容との関係、業務への家来の参画のあり方、組織内の事務文書という点で正倉院文書と関係させて考えることの可能性などの論点が提示された。
討論全体のまとめとして仁藤敦史氏より以下の論点が指摘された。
- 似たような文書がいくつかあるという状況が古代にも中世にもあるが、必ずしも案文ではなく役割が違う場合があるということは重要な提言である。
- 文書において、人の権威と匿名性のある行政との関係をどう考えるか。
- 「上司-部下」、「主-従」どちらの関係に力点を置いているかによって文書の内容が変わっているのではないか。
- 家柄・能力主義など、どのように役人が選ばれているのかという面を検討する必要があるのではないか。
第2回現地調査「大島郷(柴又周辺)を歩く」
【日時】2013年10月24日
下総国葛飾郡大島郷比定地などを谷口榮氏のご案内により調査した。主な調査場所は、①国府道、②古録天神社、③古録天遺跡(発掘現場)、④柴又八幡神社古墳、⑤柴又帝釈天、⑥江戸川土手(矢切の渡しを臨む)などであった。
第12回研究会
【日時】2013年11月20日
【場所】国立歴史民俗博物館第二会議室
【報告・主な討論内容】
安達文夫氏・鈴木卓治氏プレゼンテーション
正倉院文書表裏自在閲覧システムについて、今年1月時点以降加わった左右表示の機能についてプレゼンテーションが行われた。また、仁藤敦史氏より今後の計画について説明があった。
討論においては、裏にうつった文字は上下表示で確認できることが確認された。また、透過光写真と題簽軸の写真が付属情報として加わるとの説明があった。
谷口榮氏報告
報告は大嶋郷の様相に考古学的知見から迫り、東京低地の歴史を弥生時代後期から平安時代まで見通すものであった。また、大嶋郷域の交通における重要性を指摘した。
討論においては、まず大嶋郷の様相に関する各質問に対し、微高地上には集落が点在しているが中でも柴又は遺構・遺物が充実している、古代の川の流れがどのようであったかどうかは判断が難しいが、嶋俣里での岩盤を避け国府のふもとをえぐるS字の流れは変わらないだろうとの回答があった。また報告者より、5世紀の空白期を強調したのは一般に安康天皇の時期に穴穂部を設定したとされていることと相反するためであること、一方6〜7世紀には渡来系の文物が確認されており、それと部民、穴穂部との関係を考えていく必要があることが述べられた。交通路に関しては、立石から帝釈天へ抜ける「帝釈道」は本来東海道と渡河地点(矢切の渡し)を結ぶ道であったとの説明があった。また、大嶋郷と駅との関係については、戸籍に駅戸が見えないことから郷内には存在しなかったのではないか、また、平安時代の交通路について後期駅路の設定と渡の機能・運営を合わせて考える必要があるとの指摘がなされた。
田中禎一氏報告
報告は、大嶋郷戸籍の統計学的分析を通して編戸の秩序を明らかにするものであり、戸主は40歳以上という原則があり、養老の戸籍は「養老」思想が貫徹したものであったと指摘した。
討論においては、戸主の年齢について、若年戸主には配偶者を付さなくてよいとの原則があると見られ妻がおらず母・庶母がいる場合が多く、高齢者を優先的に戸主にした結果余った「予備的な戸」であったのではないかという見通しが述べられた一方、編戸の方針に郡差が見られることも指摘された。また、「養老」思想について報告者より、行政的なものではなく社会実態として養老年間に浸透したと考えているとの説明があった。そのほか、妻と妾の差、同居、寄口などをどう捉えるかといった戸籍を分析する上での諸問題について議論がなされた。
第13回研究会
【日時】2014年1月10日
【場所】奈良国立博物館・宮内庁正倉院事務所
【報告・主な討論内容】
- 奈良国立博物館所蔵「万昆嶋足解」・『紫の水』の熟覧調査
- 佐々田悠報告「経巻製作の作法と正倉院文書―継打界と端継をめぐって―」
佐々田氏の報告は、コロタイプの観察から得られる情報として継打界の作業と端継の処理・再利用を取り上げたもので、端継が経巻の巻首・巻末両方に付けられた可能性を指摘した上で、手実の多くが端継の反故を用いていたのではないかという試案が提示された。
討論においては、報告内容の一般性について、紹介された端継を用いた帳簿は特定の案主による工夫なのではないかとの指摘があったが、ほとんどの経の第一紙が一行分短いことは端継と一緒に切り落としていると説明するのが自然ではないか、また、端継を誰が切って誰が再利用するのかという問題があるとの回答があった。また、奥の端継を写経生が切り落とすという報告者の解釈は手順を考えれば最も合理的であるとの指摘があった一方、紙継目ではずしていたのではないかとの指摘もあった。また、界線の試し書きとみられる薄墨が巻末の端継に多く見られるとの指摘があり、界線の引き方について議論がなされた。そのほか、余った経紙の流れ、糊付けや打紙の方法などについて議論がなされた。さらに報告者より、手実などのコロタイプが出来つつあるのでその活用の試みとして本報告を行ったこと、画像としての情報量が多くなれば研究の可能性が広がるとの見通しが述べられた。
第14回研究会
【日時】2014年7月31日
【場所】国立歴史民俗博物館第2会議室
【報告・主な討論内容】
佐藤雄基氏報告「中世文書様式成立史再考 試案」
報告は、中世古文書学の前提とされてきた「公式様文書から武家文書へ」という捉え方に疑問を呈し、古代における非公式様文書について検討し中世文書(特に下文・奉書)へのつながりを見通すものであった。討論では、「公式様文書」の定義が一定でない、中世文書論の側から見た古代が必ずしも古代史研究者の認識と一致していない、等の点について課題が提示された。
野尻忠氏「写経遺品からみる宝亀初年の一切経書写と正倉院文書」
報告は、薬師寺に伝来した『大般若波羅蜜多経』(魚養経)の巻末紙背に残った校正記の多くが正倉院文書の手実から分かる先一部一切経における『大般若経』の書写・校正担当者と一致することから、魚養経の多くは先一部一切経で書写されたものが薬師寺に納められ伝来したものであることを明らかにした。討論では、書写した経巻の一部を編入した背景について議論がなされたほか、魚養経そのもの(紙の材質・品質や大きさ、現在の状態など)についての質疑があった。
展示用パワーポイントについての意見交換
写経事業の流れを描いたイラストについて、紙や文書に関する描写を中心に改善すべき点が指摘された。また、パワーポイントを印刷したものも準備してはどうかという提案がなされた。
正倉院文書画像閲覧システムについての意見交換
複数の巻を同時に比較できる画面表示、透過光画像や軸の画像の表示方法の説明がなされた。透過光画像・軸の画像の場所を示す枠を表示せずに探すことができると良いとの要望があり、現状では枠を一度表示させなければならないが、必要ならば断簡情報に付加することも可能であるとの回答があった。

第15回研究会(国際シンポジウム)
【日時】2014年11月2日
【場所】国立歴史民俗博物館大会議室
【シンポジウム報告・質疑】
- 金在弘氏「新羅統一期梵鐘銘文の様式と変化相:上院寺梵鐘の銘文を中心に」
- 権仁瀚氏「月城垓字149号木簡を通じて見た新羅の写経所について」v
- 三上喜孝氏「帳簿文書をめぐる古代日本と古代朝鮮」
質疑では、史料中の文字の解釈や技術を通じた文字の交流について、報告者同士での意見交換が行われた。また、参加者より、149号木簡の読み方や遺跡の性格付け、新羅における写経所の存在に関する質問がなされ、日本の史料や他の仏教関連史料も見た上で捉えていく必要があるとの回答があった。

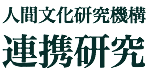
 総括班ホーム
総括班ホーム