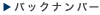月刊みんぱく 2006年11月号
2006年11月号
第30巻第11号通巻第350号
2006年11月1日発行
2006年11月1日発行
二〇〇六年夏のふたつの映画祭
大森一樹
この夏、ふたつの映画祭に招かれた。ひとつはアメリカのシカゴで開かれたG-FEST。GはゴジラのGで、全米周辺から怪獣ファンが年に一度集まり交流するイベントで、今年で一三回目。講演会やグッズ販売、さまざまなコンテストに映画の上映と盛りだくさん。
アメリカでのゴジラ人気についてはむかしから聞かされていたが、目にするのは初めてで、そのパワーには圧倒された。参加者は三日間で三〇〇〇人近くと聞いた。会場となったホテルに出店されたマーケットでは、フィギュアやプラモデル、ポスターなど日本でも手に入らないような日本製のものがところ狭しと並んでいる。
日本ではマニアとかオタクといわれる特別な人たちの集まりを想像されるが、ここではファミリーが主流で、よきパパが妻と子どもたちと思い思いの怪獣Tシャツを着ている。コンテストも、怪獣の絵や扮装、鳴き声など子ども向けのものが多い。
二本のゴジラ映画を監督したわたしは、参加者の多くから予想もしなかった賞賛と敬意をもって迎えられた。サイン会では何百人という長蛇の列ができ、会場近くの年代を感じさせる大劇場で「ゴジラVSキングギドラ」が上映された後は、スタンディングオベーションまで受けた。
正直なところ、日本では「ゴジラの監督」と言われると、三〇本近くいろいろな映画を撮っているのに、そのうちの二本じゃないかと、あまり快く思わなかった。しかし、このときは「ゴジラの監督」であることを心から幸福に思った。と同時に半世紀以上も前に、日本のクリエーターたちが生み出した映画のキャラクターが、本場アメリカで時代を超えてなおも支持されていることに、日本文化の誇りを感じずにはいられなかった。
もうひとつは、九州大分の湯布院映画祭。今年で三一回目になるというが、全国の至る所で町おこし的な映画祭が生まれては消えていくなかで、ここまで続いているのは唯一といっていい。今回はわたしの新作「悲しき天使」が地元大分オールロケということもあり、ようやく実現した。
こちらの参加者はかっての映画青年たちが主流で、当然年齢層も高い。上映の後のシンポジウムでも辛辣(しんらつ)なことばが飛び交うが、自分が映画監督になってからほぼ同じ歳月を通過してきた同世代感覚があって心地よい。彼らの三一年の変わらない映画愛が、この映画祭を支えてきたのだという感慨があった。
映画という文化は、いつの時代でも若さと新しさが求められるものだ。しかしそれだけに目を奪われていると、必ず足元をすくわれる。先駆者たちの歴史と伝統、同世代の観客たちの熱い眼差しを置き忘れて明日は決してないと改めて思い直した夏だった。
おおもり かずき/1952年大阪市生まれ。映画監督。「恋する女たち」(東宝)で文化庁優秀映画賞、第11回日本アカデミー賞、優秀脚本賞・優秀監督賞受賞。「わが心の銀河鉄道~宮沢賢治物語」(東映)で第20回日本アカデミー賞、優秀監督賞受賞。1988年文部省芸術選奨新人賞受賞。大阪芸術大学映像学科同大学院教授。著書に『あなたの人生案内』(平凡社)など。
アメリカでのゴジラ人気についてはむかしから聞かされていたが、目にするのは初めてで、そのパワーには圧倒された。参加者は三日間で三〇〇〇人近くと聞いた。会場となったホテルに出店されたマーケットでは、フィギュアやプラモデル、ポスターなど日本でも手に入らないような日本製のものがところ狭しと並んでいる。
日本ではマニアとかオタクといわれる特別な人たちの集まりを想像されるが、ここではファミリーが主流で、よきパパが妻と子どもたちと思い思いの怪獣Tシャツを着ている。コンテストも、怪獣の絵や扮装、鳴き声など子ども向けのものが多い。
二本のゴジラ映画を監督したわたしは、参加者の多くから予想もしなかった賞賛と敬意をもって迎えられた。サイン会では何百人という長蛇の列ができ、会場近くの年代を感じさせる大劇場で「ゴジラVSキングギドラ」が上映された後は、スタンディングオベーションまで受けた。
正直なところ、日本では「ゴジラの監督」と言われると、三〇本近くいろいろな映画を撮っているのに、そのうちの二本じゃないかと、あまり快く思わなかった。しかし、このときは「ゴジラの監督」であることを心から幸福に思った。と同時に半世紀以上も前に、日本のクリエーターたちが生み出した映画のキャラクターが、本場アメリカで時代を超えてなおも支持されていることに、日本文化の誇りを感じずにはいられなかった。
もうひとつは、九州大分の湯布院映画祭。今年で三一回目になるというが、全国の至る所で町おこし的な映画祭が生まれては消えていくなかで、ここまで続いているのは唯一といっていい。今回はわたしの新作「悲しき天使」が地元大分オールロケということもあり、ようやく実現した。
こちらの参加者はかっての映画青年たちが主流で、当然年齢層も高い。上映の後のシンポジウムでも辛辣(しんらつ)なことばが飛び交うが、自分が映画監督になってからほぼ同じ歳月を通過してきた同世代感覚があって心地よい。彼らの三一年の変わらない映画愛が、この映画祭を支えてきたのだという感慨があった。
映画という文化は、いつの時代でも若さと新しさが求められるものだ。しかしそれだけに目を奪われていると、必ず足元をすくわれる。先駆者たちの歴史と伝統、同世代の観客たちの熱い眼差しを置き忘れて明日は決してないと改めて思い直した夏だった。
おおもり かずき/1952年大阪市生まれ。映画監督。「恋する女たち」(東宝)で文化庁優秀映画賞、第11回日本アカデミー賞、優秀脚本賞・優秀監督賞受賞。「わが心の銀河鉄道~宮沢賢治物語」(東映)で第20回日本アカデミー賞、優秀監督賞受賞。1988年文部省芸術選奨新人賞受賞。大阪芸術大学映像学科同大学院教授。著書に『あなたの人生案内』(平凡社)など。
「目合」(まぐわい)。見つめ合って愛情を知らせることと、男女の交りを意味する。精神の交信を経て、はじめて肉体の交接が果たされることを匂わす、こんな気の利いた言葉が、日本語にはあるのである。
男女が求め合う気持ちは、文化を産み出す原動力になってきた。が同時に、野生の性は、社会の秩序を乱すタブーとされ、文化と時代の規制を受けてきた。
出会いと契りの神秘は、いったい、どこへ行ってしまうのであろう。
頭のなかの尾てい骨
規制を受ける性
動物は、成熟するとオスの方が美しく見栄えよくなるようだ。孔雀を見るたびにそう思う。そういえば、ひところ「ピーコック革命」という流行現象があった。一九六〇年代後半のことだった。ひょっとすると、男のコたちはあのころから先祖がえりし始めたのかも。
貧相なオスはメスを惹きつけることができない。それはヒトも同じだ。だから、黄金色にかがやくたてがみをもつオスのライオンに「百獣の王」という立派な称号を与えたのだ。でも、たてがみのないメスのライオンを「百獣の女王」とはよばなかったし、今もいわない。フェミニストたちも、動物に対するセクハラ行為にまでは気がまわらずにいる。
ヒトの求愛と性行為は、双方が合意すれば、誰とでも、いかようにでもおこなえると思われそうだが、じつは違う。それぞれが属している社会が保持している文化の規制を受けている。だから、近親婚の忌避や宗教上の禁欲などが遵守されてきたのだし、一方的な要求が痴漢行為・強姦・ストーカーなどとよばれる性犯罪となる。そして、この規制を無視したペアは、駆け落ちだ不義密通だと糾弾されたり、姦通(かんつう)だ不倫だと後ろ指をさされたりする。また、買売春や同性愛を許容する社会もあれば、拒絶する社会もある。一夫多妻制の社会もあれば、一人の女性を兄弟で共有するような一妻多夫制を是とする社会もある。
発情か、愛情か
人間も、もとはといえば野生の存在だったから、ほかの動物と同様に発情期があった。女性の月経は年に一度だった、繁殖にもっとも適した季節に排卵していたからだという文章を、何かの本で読んだことがある。何を根拠にそういえるのかと思いつつも、もっともらしいことをいうと感心した。そして思い出した。そういえば、日本語には「木の芽立ち」ということばがあったと…。
これは、春に木々が芽吹き始める時期をあらわすことばである。しかし、その時期になると、陽気のせいでか、サカリがついたようにおかしな行動をおこす輩(やから)があらわれがちだった。そのことを婉曲に表現するためにも使われていたのである。「今は木の芽立ちやさかいなあ」とぼやいては、娘や姪の身を案じたのである。
季節を問わず、四六時中出会い系サイトの交信が盛んな昨今、このことばは死語になりつつあるようだ。でも『広辞苑』には載っている。比喩的用法には触れていないが、現代日本語のもっとも権威ある辞書に載っている。それは、高度に発達した現代文明を謳歌しているわたしたちの体内に、神経系の中枢部に、野生の痕跡が残存していることの証しである。尻尾は消滅しても、まだ尾てい骨が残っているのと同じことだ。つまり『広辞苑』を読むことは、医学書の胎児月齢標本の図解を見ることに通じているのだ。
人間-類人猿というべきか-も、ほかの動物と同じように自然界の法則にしたがって生存していたのだという主張はわかりやすい。なるほどと思う。類人猿とはくらべようもないほど進化をとげていた北京原人も、ネアンデルタール人も、モグラやネズミと同じように、たしかに洞窟をすみかにしていた。クロマニヨン人もそうだった。
「そんな時代に、夜ごとセックスを楽しむ余裕があったと思うのかね」と問われれば、これも「まあ、たしかになあ」と、納得させられそうな話だ。
動物は、成熟するとオスの方が美しく見栄えよくなるようだ。孔雀を見るたびにそう思う。そういえば、ひところ「ピーコック革命」という流行現象があった。一九六〇年代後半のことだった。ひょっとすると、男のコたちはあのころから先祖がえりし始めたのかも。
貧相なオスはメスを惹きつけることができない。それはヒトも同じだ。だから、黄金色にかがやくたてがみをもつオスのライオンに「百獣の王」という立派な称号を与えたのだ。でも、たてがみのないメスのライオンを「百獣の女王」とはよばなかったし、今もいわない。フェミニストたちも、動物に対するセクハラ行為にまでは気がまわらずにいる。
ヒトの求愛と性行為は、双方が合意すれば、誰とでも、いかようにでもおこなえると思われそうだが、じつは違う。それぞれが属している社会が保持している文化の規制を受けている。だから、近親婚の忌避や宗教上の禁欲などが遵守されてきたのだし、一方的な要求が痴漢行為・強姦・ストーカーなどとよばれる性犯罪となる。そして、この規制を無視したペアは、駆け落ちだ不義密通だと糾弾されたり、姦通(かんつう)だ不倫だと後ろ指をさされたりする。また、買売春や同性愛を許容する社会もあれば、拒絶する社会もある。一夫多妻制の社会もあれば、一人の女性を兄弟で共有するような一妻多夫制を是とする社会もある。
発情か、愛情か
人間も、もとはといえば野生の存在だったから、ほかの動物と同様に発情期があった。女性の月経は年に一度だった、繁殖にもっとも適した季節に排卵していたからだという文章を、何かの本で読んだことがある。何を根拠にそういえるのかと思いつつも、もっともらしいことをいうと感心した。そして思い出した。そういえば、日本語には「木の芽立ち」ということばがあったと…。
これは、春に木々が芽吹き始める時期をあらわすことばである。しかし、その時期になると、陽気のせいでか、サカリがついたようにおかしな行動をおこす輩(やから)があらわれがちだった。そのことを婉曲に表現するためにも使われていたのである。「今は木の芽立ちやさかいなあ」とぼやいては、娘や姪の身を案じたのである。
季節を問わず、四六時中出会い系サイトの交信が盛んな昨今、このことばは死語になりつつあるようだ。でも『広辞苑』には載っている。比喩的用法には触れていないが、現代日本語のもっとも権威ある辞書に載っている。それは、高度に発達した現代文明を謳歌しているわたしたちの体内に、神経系の中枢部に、野生の痕跡が残存していることの証しである。尻尾は消滅しても、まだ尾てい骨が残っているのと同じことだ。つまり『広辞苑』を読むことは、医学書の胎児月齢標本の図解を見ることに通じているのだ。
人間-類人猿というべきか-も、ほかの動物と同じように自然界の法則にしたがって生存していたのだという主張はわかりやすい。なるほどと思う。類人猿とはくらべようもないほど進化をとげていた北京原人も、ネアンデルタール人も、モグラやネズミと同じように、たしかに洞窟をすみかにしていた。クロマニヨン人もそうだった。
「そんな時代に、夜ごとセックスを楽しむ余裕があったと思うのかね」と問われれば、これも「まあ、たしかになあ」と、納得させられそうな話だ。
耳から心に染み込んで・・・
佐伯 順子
音の官能
国産み神話のカップル、イザナミとイザナギは、「あなにやしえをとこを」「あなにやしえをとめを」と互いをよび合った後に交わり、イザナミは国を産んだという。太古の「まぐわひ」は神々の尊い営みとして語り伝えられている。
古代の求愛は、容姿を見ての判断よりも、まずは相手をよぶ声、あるいは歌によっておこなわれた。目よりも、耳の世界である。対象との距離がある視覚よりも、身体の内部に入り込む聴覚のほうが、より全身的であり、官能的である(M.デュフレンヌ『眼と耳』)といわれるゆえんであろう。『万葉集』に残される歌垣の風習も、歌をうたい合っての求愛であり、古代の遊女たちもまた、姿形ではなく、まずは優れた歌声で客を誘ったのである。
耳に訴える求愛は、近代文学にも随所に残されている。二葉亭四迷『平凡』(明治四〇年)の主人公・古谷は、三味線の音に合わせたお糸さんという女性の声にほれ込み、「お糸さんの声」が「私の耳から心に染込んで…全存在をゆるがされる」と手放しの賛辞を送り、彼女を「巫女」「シャマン」とまであがめるようになる。夏目漱石『こころ』(大正三年)の先生も、下宿のお嬢さんのへたくそ(!)な琴の音に心をかき乱されるのであった。
お糸さんや『こころ』のお静さんは、必ずしも求愛のために音曲をたしなんだわけではないけれども、音楽が結果として求愛機能を果たすのは、古代の求愛風俗の名残といえよう。
求愛のむくい
だが、女性からの求愛は、文学のなかではしばしば悲劇に終わる。『平凡』のお糸さんは、自分に気があると見てとった古谷に芝居見物をねだり、その夜に男の部屋を訪れて関係を結ぶ。まるで女性からしかけた夜這いのようである。だが、彼女が玄人あがりを想像させる身もちの悪い女性であると察した古谷は、自分から手切れ金を出して身を引いてしまう。一方、『こころ』のお静さんは、先生と結婚したものの、夫に自殺され、一人とり残される。一見清純派のヒロインであっても、男性から見て、異性を挑発するかのような行動は”処罰“される。男性中心の社会は、求愛の主導権も男性にあるべきと主張する。
イザナミ、イザナギの神話でも、女性が先に相手をよんだことがよくないとされ、男性を先にしてやり直したところ、無事に国が生まれた。求愛はまず男性から、という規範は、すでに『古事記』の時代から存在していた。
「おい、木村さん信さん、寄っておいでよ」
女性から男性へのよびかけで始まる、樋口一葉『にごりえ』(明治二八年)のヒロイン・お力が、非業の死を遂げるのも、その意味で象徴的であろう。お力もまた、「わが恋は細谷川の丸木橋…」と、座敷で切ない歌声を響かせる女であった。
今も中国の一部地方に残る歌垣の風習は、開放的でおおらかな印象がするけれども、文学のなかの女性の求愛の歌声と、その果てにある契りとは、はかなく哀しい。
国産み神話のカップル、イザナミとイザナギは、「あなにやしえをとこを」「あなにやしえをとめを」と互いをよび合った後に交わり、イザナミは国を産んだという。太古の「まぐわひ」は神々の尊い営みとして語り伝えられている。
古代の求愛は、容姿を見ての判断よりも、まずは相手をよぶ声、あるいは歌によっておこなわれた。目よりも、耳の世界である。対象との距離がある視覚よりも、身体の内部に入り込む聴覚のほうが、より全身的であり、官能的である(M.デュフレンヌ『眼と耳』)といわれるゆえんであろう。『万葉集』に残される歌垣の風習も、歌をうたい合っての求愛であり、古代の遊女たちもまた、姿形ではなく、まずは優れた歌声で客を誘ったのである。
耳に訴える求愛は、近代文学にも随所に残されている。二葉亭四迷『平凡』(明治四〇年)の主人公・古谷は、三味線の音に合わせたお糸さんという女性の声にほれ込み、「お糸さんの声」が「私の耳から心に染込んで…全存在をゆるがされる」と手放しの賛辞を送り、彼女を「巫女」「シャマン」とまであがめるようになる。夏目漱石『こころ』(大正三年)の先生も、下宿のお嬢さんのへたくそ(!)な琴の音に心をかき乱されるのであった。
お糸さんや『こころ』のお静さんは、必ずしも求愛のために音曲をたしなんだわけではないけれども、音楽が結果として求愛機能を果たすのは、古代の求愛風俗の名残といえよう。
求愛のむくい
だが、女性からの求愛は、文学のなかではしばしば悲劇に終わる。『平凡』のお糸さんは、自分に気があると見てとった古谷に芝居見物をねだり、その夜に男の部屋を訪れて関係を結ぶ。まるで女性からしかけた夜這いのようである。だが、彼女が玄人あがりを想像させる身もちの悪い女性であると察した古谷は、自分から手切れ金を出して身を引いてしまう。一方、『こころ』のお静さんは、先生と結婚したものの、夫に自殺され、一人とり残される。一見清純派のヒロインであっても、男性から見て、異性を挑発するかのような行動は”処罰“される。男性中心の社会は、求愛の主導権も男性にあるべきと主張する。
イザナミ、イザナギの神話でも、女性が先に相手をよんだことがよくないとされ、男性を先にしてやり直したところ、無事に国が生まれた。求愛はまず男性から、という規範は、すでに『古事記』の時代から存在していた。
「おい、木村さん信さん、寄っておいでよ」
女性から男性へのよびかけで始まる、樋口一葉『にごりえ』(明治二八年)のヒロイン・お力が、非業の死を遂げるのも、その意味で象徴的であろう。お力もまた、「わが恋は細谷川の丸木橋…」と、座敷で切ない歌声を響かせる女であった。
今も中国の一部地方に残る歌垣の風習は、開放的でおおらかな印象がするけれども、文学のなかの女性の求愛の歌声と、その果てにある契りとは、はかなく哀しい。
めぢから―目は口よりもモノをいう―
水口 千里
出陣儀礼
朝の女性専用車両は、テレビタレントの出番待ちの楽屋かと思うときがある。彼女たちが長い時間、真剣に取り組んでいるのはアイメイクである。アイラインやアイシャドウで縁取りやグラデーションを施し、ビューラーで癖づけした睫毛(まつげ)を、マスカラでこれでもかというほど長く濃く増殖させていく。完成した目は、もはや原型をとどめていない。そう、彼女たちは「目力」を手に入れたのだ。
「恋を呼ぶ目力」「目力養成ゼミナール」「即効目力UP技」「単色グラデーション技でセクシー目力UP」「モテ目確実!アイメイクコスメ」・・・若い女性向けの雑誌『non-no』六月五日号に、こんなキャッチコピーが散りばめられた特集が組まれていた。紹介されたのは、「目力」のある瞳を創るためのさまざまな化粧用具の使い方、造作の欠点の補正の仕方、好みのイメージを演出する技などの化粧テクニックである。
交信の行方
古くから化粧は、多くの役割を果たしてきた。身分や階級の証し、呪術宗教的な変身の手段、たしなみなどである。美しく装うための化粧もそのひとつであった。化粧によって追求される美とは、極限すれば、異性として認識される女性らしさである。もともと平坦な顔の日本人が、女性らしい色香を表現しやすいパーツは唇であった。「紅をさす」ということばに、本来もっている意味以上の何かを感じるのは文化的背景があるからである。しかし、西欧化の波は化粧方法にも影響を与え、一九七六年「揺れるまなざし」をテーマにした化粧品会社のキャンペーンを契機に、アイメイクは一気に一般女性のあいだに拡まった。その後もアイメイクが特化され続けているのは、化粧品会社やマスコミの戦略によるだけでなく、目が顔の印象をもっとも決定づけるパーツだからなのだろう。合コンに行くとき、メイクでもっとも気合を入れるのが目であるという統計結果もそれを裏づけている。
合コンで相手の男性から携帯電話の番号やメールアドレスを尋ねられる。それは求愛の一種である。女性は、合コンに限らず日常生活においても、より多くの、そしてより好ましい男性から求愛されることを望んでいる。一見、男性からの働きかけを待つ受身の行動に見えるが、それは違う。男性が求愛したくなるような美しい女性になるための労力を費やし、ときには演出もする。そしてひとたび意中の相手を定めれば、万感の思いを込めて見つめる。向けられた視線を受け止めることは、交信である。一方が目をそらせば交信は成り立たない。「目力」があるとは、目を離せなくなるほど魅惑的なまなざしをもつことなのだ。「目合」(まぐわい)に、交接、性交だけでなく目を見合わせて愛情を知らせるという意味があるのも、偶然ではない。
合コンで出会った男性から、後日連絡が入る。求愛の成就の第一歩だ。それに応える価値があるかどうかを見極めるのは、メイク・マジックの及ばない本当の意味の「目力」であろう。
朝の女性専用車両は、テレビタレントの出番待ちの楽屋かと思うときがある。彼女たちが長い時間、真剣に取り組んでいるのはアイメイクである。アイラインやアイシャドウで縁取りやグラデーションを施し、ビューラーで癖づけした睫毛(まつげ)を、マスカラでこれでもかというほど長く濃く増殖させていく。完成した目は、もはや原型をとどめていない。そう、彼女たちは「目力」を手に入れたのだ。
「恋を呼ぶ目力」「目力養成ゼミナール」「即効目力UP技」「単色グラデーション技でセクシー目力UP」「モテ目確実!アイメイクコスメ」・・・若い女性向けの雑誌『non-no』六月五日号に、こんなキャッチコピーが散りばめられた特集が組まれていた。紹介されたのは、「目力」のある瞳を創るためのさまざまな化粧用具の使い方、造作の欠点の補正の仕方、好みのイメージを演出する技などの化粧テクニックである。
交信の行方
古くから化粧は、多くの役割を果たしてきた。身分や階級の証し、呪術宗教的な変身の手段、たしなみなどである。美しく装うための化粧もそのひとつであった。化粧によって追求される美とは、極限すれば、異性として認識される女性らしさである。もともと平坦な顔の日本人が、女性らしい色香を表現しやすいパーツは唇であった。「紅をさす」ということばに、本来もっている意味以上の何かを感じるのは文化的背景があるからである。しかし、西欧化の波は化粧方法にも影響を与え、一九七六年「揺れるまなざし」をテーマにした化粧品会社のキャンペーンを契機に、アイメイクは一気に一般女性のあいだに拡まった。その後もアイメイクが特化され続けているのは、化粧品会社やマスコミの戦略によるだけでなく、目が顔の印象をもっとも決定づけるパーツだからなのだろう。合コンに行くとき、メイクでもっとも気合を入れるのが目であるという統計結果もそれを裏づけている。
合コンで相手の男性から携帯電話の番号やメールアドレスを尋ねられる。それは求愛の一種である。女性は、合コンに限らず日常生活においても、より多くの、そしてより好ましい男性から求愛されることを望んでいる。一見、男性からの働きかけを待つ受身の行動に見えるが、それは違う。男性が求愛したくなるような美しい女性になるための労力を費やし、ときには演出もする。そしてひとたび意中の相手を定めれば、万感の思いを込めて見つめる。向けられた視線を受け止めることは、交信である。一方が目をそらせば交信は成り立たない。「目力」があるとは、目を離せなくなるほど魅惑的なまなざしをもつことなのだ。「目合」(まぐわい)に、交接、性交だけでなく目を見合わせて愛情を知らせるという意味があるのも、偶然ではない。
合コンで出会った男性から、後日連絡が入る。求愛の成就の第一歩だ。それに応える価値があるかどうかを見極めるのは、メイク・マジックの及ばない本当の意味の「目力」であろう。
おやめなさい、そんな歌
齊藤 純
今から三五年ほど前、京都市の小学生だったわたしは、学校で友人たちとこんな歌を歌っていた(「キラキラ星」または「ABCの歌」の節で)。
「ABCDしくじって、カニにチンポを挟まれた。痛いじゃないか放さんか。放すものか、むけチンポ」
級友に教わった替歌で、別に「ABCD豚のケツ」と連呼するタイプもあった。試みにインターネットの検索を使い、「カニ」だのなんだので調べると、ほぼ同じ歌詞の報告が見つかる。相応に流布していた歌らしい。なぜこんな歌を喜んだのか。子どもの気持ちは説明しにくいが、今思うと「性」という、大人が公言を憚(はばか)る事柄を、実態は知らないが口にする。いけない事であるのは察せられ、そのスリルが楽しくてゲラゲラ笑っていたように思う。
民俗学を学んで驚いたのは、同じような歌を、民俗行事で子どもたちが歌っていたことだ。たとえば東京都大田区羽田では、稲荷の初午祭で、子どもたちが賽銭や薪を集めて回るとき、次のように囃した。
「ちんちょ、ちんちょ、ごじゅうにおわげ、高い屋根から落っこって、赤いちんちんすりむいた。膏薬銭おくれ…」
伝わるうちに原意が不明になった部分があるが、同様な台詞は他地区でも報告され、いずれも囃し始めに「ちんちょやまんちょ」と性に関することばを意味もわからず囃していたという(『大田区史(資料編)民俗』)。
山の神の祭りにも性的な囃ことばがあった。愛知県や岐阜県では一二月または二月の七日にヤマノコという山神祭がおこなわれる。この日、子どもたちが供物を集め、山神の祠(ほこら)の前で会食し、小屋に泊まった。その際、岐阜県武儀郡では「やまのこうさんぜんぼう、山の神様の剃刀は、よう切れる剃刀で、大根切りて、菜切りて、馬のちんぽ断ち割って、三里の山へほりあげて、ささゑんやらわい」と歌った。また美濃加茂市でも「山の神の剃刀は、よう切れる剃刀で、大根切りて馬の金玉剃り切って、おかかの臍(へそ)の下へ祭りこんで、ヤハイヤハイ」と囃した(林魁一「美濃国に於ける山の『こ』」)。
こちらにもやはり意味不明のところがある。しばしば歌詞にあらわれることばなのだが、山の神の「剃刀」もわかりにくい。が、山の神は女性という伝承を勘案すると、世界各地の神話伝説に登場する「歯の生えた女陰」のことで、野生的な女性原理の象徴ではないだろうか。いずれにしろ性の表現は十分読みとれる。
子どもだけではない。かつて日本のいくつかの旧家には「粟穂・稗穂」「大穂ぶらぶら」あるいは「裸回り」などとよばれる風習があった。正月や節分に夫婦が裸で囲炉裏のまわりを回り、局部を互いに示しながら「粟穂も稗穂もこの通り」「割れた、割れた、実入って割れた」などと唱えるのである(飯島吉晴『一つ目小僧と瓢箪』)。
これら性に関することばや所作は、出産力にあやかろうとした豊穣儀礼の一要素と解釈されている。たしかに稲荷や山神には豊穣神の側面がある。またその深層には、性によって男・女、上・下、文化・自然といった基本的な区分を撹乱し、日常の秩序を破壊して始原状態を招来しようとする、世界再生の観念も指摘されている。
ひょっとすると例の猥歌には、こうした儀礼ことばの断片が含まれていたのかもしれない。もちろん小学生の悪ふざけは、時と場所を定めておこなう家・村公認の行事ではなく、豊穣の祈願もありはしない。が、それでも、知り合いのあいだを伝わってきた、型をもつリズミカルな性表現に、秩序を撹乱する効果があるというのは、なんとなく理解していたのである。
「ABCDしくじって、カニにチンポを挟まれた。痛いじゃないか放さんか。放すものか、むけチンポ」
級友に教わった替歌で、別に「ABCD豚のケツ」と連呼するタイプもあった。試みにインターネットの検索を使い、「カニ」だのなんだので調べると、ほぼ同じ歌詞の報告が見つかる。相応に流布していた歌らしい。なぜこんな歌を喜んだのか。子どもの気持ちは説明しにくいが、今思うと「性」という、大人が公言を憚(はばか)る事柄を、実態は知らないが口にする。いけない事であるのは察せられ、そのスリルが楽しくてゲラゲラ笑っていたように思う。
民俗学を学んで驚いたのは、同じような歌を、民俗行事で子どもたちが歌っていたことだ。たとえば東京都大田区羽田では、稲荷の初午祭で、子どもたちが賽銭や薪を集めて回るとき、次のように囃した。
「ちんちょ、ちんちょ、ごじゅうにおわげ、高い屋根から落っこって、赤いちんちんすりむいた。膏薬銭おくれ…」
伝わるうちに原意が不明になった部分があるが、同様な台詞は他地区でも報告され、いずれも囃し始めに「ちんちょやまんちょ」と性に関することばを意味もわからず囃していたという(『大田区史(資料編)民俗』)。
山の神の祭りにも性的な囃ことばがあった。愛知県や岐阜県では一二月または二月の七日にヤマノコという山神祭がおこなわれる。この日、子どもたちが供物を集め、山神の祠(ほこら)の前で会食し、小屋に泊まった。その際、岐阜県武儀郡では「やまのこうさんぜんぼう、山の神様の剃刀は、よう切れる剃刀で、大根切りて、菜切りて、馬のちんぽ断ち割って、三里の山へほりあげて、ささゑんやらわい」と歌った。また美濃加茂市でも「山の神の剃刀は、よう切れる剃刀で、大根切りて馬の金玉剃り切って、おかかの臍(へそ)の下へ祭りこんで、ヤハイヤハイ」と囃した(林魁一「美濃国に於ける山の『こ』」)。
こちらにもやはり意味不明のところがある。しばしば歌詞にあらわれることばなのだが、山の神の「剃刀」もわかりにくい。が、山の神は女性という伝承を勘案すると、世界各地の神話伝説に登場する「歯の生えた女陰」のことで、野生的な女性原理の象徴ではないだろうか。いずれにしろ性の表現は十分読みとれる。
子どもだけではない。かつて日本のいくつかの旧家には「粟穂・稗穂」「大穂ぶらぶら」あるいは「裸回り」などとよばれる風習があった。正月や節分に夫婦が裸で囲炉裏のまわりを回り、局部を互いに示しながら「粟穂も稗穂もこの通り」「割れた、割れた、実入って割れた」などと唱えるのである(飯島吉晴『一つ目小僧と瓢箪』)。
これら性に関することばや所作は、出産力にあやかろうとした豊穣儀礼の一要素と解釈されている。たしかに稲荷や山神には豊穣神の側面がある。またその深層には、性によって男・女、上・下、文化・自然といった基本的な区分を撹乱し、日常の秩序を破壊して始原状態を招来しようとする、世界再生の観念も指摘されている。
ひょっとすると例の猥歌には、こうした儀礼ことばの断片が含まれていたのかもしれない。もちろん小学生の悪ふざけは、時と場所を定めておこなう家・村公認の行事ではなく、豊穣の祈願もありはしない。が、それでも、知り合いのあいだを伝わってきた、型をもつリズミカルな性表現に、秩序を撹乱する効果があるというのは、なんとなく理解していたのである。
森の民のクマとの絆
シベリアや北米の森林地帯ではクマに対する崇拝、信仰が共通に見られる。これらの地域ではクマが捕れると村を挙げての盛大なお祭りをする。逆にお祭りをするためにわざわざ冬眠中のクマを捕ってくることも多い。北海道のアイヌやサハリン、アムールのニヴフは仔グマを家で飼育して、ある程度大きくなったところで、祭りを開いてクマを殺し、霊魂を送ってその肉を食べる。アイヌではイオマンテ(熊送り儀礼)とよばれる。
ロシアで長年シベリアの森の狩人たちの世界観を研究してきたセルゲイ・ベレズニツキー博士によれば、彼らのなかには、雌グマが捕れるとすぐにその場で捕れたクマとセックスする人びとがいるという。それはこの神聖な動物との絆をより強めるためであるといわれる。また、森の狩人たちはクマのセックスが人ときわめてよく似ていることを知っている。そして逆にクマがすることは神聖な行為であることから、人びともそのまねをしようとする。つまりクマのセックスの体位は人間にとっても神聖な形なのである。
そういえば、北方の森の民のあいだにはいわゆる獣婚譚(じゅうこんたん)とよばれる民話のジャンルが広まっている。その多くは雄グマが人間の女性をさらう、または人間の女性の方がクマの雄を選んで結婚することによって、子どもが生まれるという話である。その結末は、子どもが超自然的な力をもっていて一族を繁栄させるというものから、夫のクマもその子どもも人間の猟師によって殺されてしまう悲劇的なものまであるが、おそらくそのクマは人間と全く同じように夫婦生活を送っていたはずである。
そういえば、北方の森の民のあいだにはいわゆる獣婚譚(じゅうこんたん)とよばれる民話のジャンルが広まっている。その多くは雄グマが人間の女性をさらう、または人間の女性の方がクマの雄を選んで結婚することによって、子どもが生まれるという話である。その結末は、子どもが超自然的な力をもっていて一族を繁栄させるというものから、夫のクマもその子どもも人間の猟師によって殺されてしまう悲劇的なものまであるが、おそらくそのクマは人間と全く同じように夫婦生活を送っていたはずである。
グシイ流正統派
西ケニアのグシイ人には、正統とされる夫婦の性交の仕方がある。一般的な性交体位は対面側位と男性上位の二種である。なかでも対面側位は、これこそ正統的でもっとも普遍的な体位として語られる。結婚したてのころ、男は側位と上位の両方を用いるが、子どもが生まれて結婚生活が落ち着いてくると側位一本槍になるようだ。
「(女が)脚を上げる」というのはセックスを意味するグシイ流の表現だ。この場合の脚は単数、つまり片脚であり、男が女の両脚のあいだに下半身を入れる側位を示している。この側位はまた、「夫の腕」(右腕のこと)ともよばれる。「夫の腕」とは、男が右腕で女の首を抱きかかえた姿勢で性交することを意味する。左腕は「妻の腕」ともよばれ、弱い、優しい、恥ずかしがる腕とされる。なお、グシイ語の腕(オコボコ)は腕の付け根から指先までの全体を指す。
以上、まとめていえば、男が体の右側を寝床につけて、右腕をすべり込ませて女を抱き、左手で愛撫するというのが、グシイ夫婦の正統的なセックス体位である。この性交体位は、男女が埋葬されるときの姿勢と同じである。こうした男女に対応する右、左の区分は、屋内屋外の空間利用や家屋の左右にとりつけたドアの使い方にも密接に関係している。アフリカでは、側位の性交体位が意外に多いようだ。
しかし、こうした正統的な体位も、近年、若夫婦のあいだでは多様な体位のうちのひとつになりつつある。
「(女が)脚を上げる」というのはセックスを意味するグシイ流の表現だ。この場合の脚は単数、つまり片脚であり、男が女の両脚のあいだに下半身を入れる側位を示している。この側位はまた、「夫の腕」(右腕のこと)ともよばれる。「夫の腕」とは、男が右腕で女の首を抱きかかえた姿勢で性交することを意味する。左腕は「妻の腕」ともよばれ、弱い、優しい、恥ずかしがる腕とされる。なお、グシイ語の腕(オコボコ)は腕の付け根から指先までの全体を指す。
以上、まとめていえば、男が体の右側を寝床につけて、右腕をすべり込ませて女を抱き、左手で愛撫するというのが、グシイ夫婦の正統的なセックス体位である。この性交体位は、男女が埋葬されるときの姿勢と同じである。こうした男女に対応する右、左の区分は、屋内屋外の空間利用や家屋の左右にとりつけたドアの使い方にも密接に関係している。アフリカでは、側位の性交体位が意外に多いようだ。
しかし、こうした正統的な体位も、近年、若夫婦のあいだでは多様な体位のうちのひとつになりつつある。
展示室の柔軟性
―金沢21世紀美術館の試み―
―金沢21世紀美術館の試み―
鷲田 めるろ
展覧会開催ごとに、使用する展示室を
自由に組み合わせ、限りない可能性を引き出す
金沢21世紀美術館。
その名にふさわしく、二一世紀の新しい試みに
挑むすがたを紹介したい。
自由に組み合わせ、限りない可能性を引き出す
金沢21世紀美術館。
その名にふさわしく、二一世紀の新しい試みに
挑むすがたを紹介したい。
可動壁を無くす
金沢21世紀美術館の建物を設計する際、柔軟な空間構成の実現は重要な課題であった。それは、観客の動きの自由度を高めることと、展覧会ごとの展示室の組み合わせの柔軟性とにわけられる。
従来の美術館が、ひとつの正面入り口と、ひとつの順路に沿って展示室を巡る空間構成とをもつのに対し、金沢21世紀美術館は、五ヵ所の入り口をもち、都市を歩き回るようにさまざまな経路をとることができる(図1)。この建物は、自ら選び、探すという観客の能動的な行為を引き出す空間構成をもつといえる。これが観客の動きの自由度を高めるのであり、この点については、これまでにも設計にかかわった学芸員としての立場からさまざまな機会に触れてきた。ここでは、展示室の組み合わせの柔軟性について、開館後約二年間に建物を使った結果の一部を報告したい。
展示室の設計では、可動壁を用いないことを当初から目指していた。可動壁とは、天井から吊り下がる壁を移動させることで、展覧会ごとに空間を仕切るシステムである。金沢21世紀美術館で可動壁を避けた理由のひとつは、自然光が十分に入る天井の高い空間を作るためであった。すなわち、外の空間との繋がりを展示室のなかにいても感じられるような、開放感をもたせるためである。そのためには天井の構造が大仰かつ複雑になり、天井高にも限界のある可動壁を避ける必要があった。また、それぞれの空間に独立性と完結性を追求したことも理由のひとつである。映像作品など音を伴う作品、部屋全体の空間を使った作品の増加がその背景にあるが、一方、「展示室」以外での展示が一般化するなかで、あえて作る展示室ではシンプルなホワイトキューブの完成度を高めたいという意図もあった。
可動壁を使わずに、空間の多様性を確保するためには、あらかじめさまざまな大きさやプロポーションをもった空間を用意する必要がある。なおかつ、それらがさまざまな組み合わせを可能とする配置になっていなければならない。そこで、各展示室が廊下を挟んで互いに離れて配置されることになった。設計段階では、「企画展示室」「常設展示室」という名称で区別していたが、最終的にその区別も無くし、「展示室1~14」という通し番号をつけた。
展覧会ごとの組み合わせ
二〇〇四年一〇月に開館してから、本稿執筆時の二〇〇六年八月において、約二年近く経った。その間にこの一四の展示室を会場として金沢21世紀美術館が主催したおもな企画展は八本だが、毎回、使用する展示室は少しずつ異なっている。開館記念展「21世紀の出会い、共鳴、ここ・から」(以下「開館展」)と「Alternative Paradise:もうひとつの楽園」展では、すべての展示室を使用した(「もうひとつの楽園」展では、展示室1は使用しなかった)。「世界の美術館:未来への架け橋」展と「妹島和世+西沢立衛/SANAA」展(以下「SANAA展」)では、前者が展示室7-12および14を使用し、後者が展示室2-6および13を使用した。「マシュー・バーニー:拘束のドローイング」展(以下「バーニー」展)は、展示室1、5-12、14を使用し、続く「ゲルハルト・リヒター:鏡の絵画」展(以下「リヒター展」)では展示室7-12、14を用いたが、この二本の展覧会と同時に、コレクションからのテーマ展「アナザー・ストーリー」展がおこなわれた。バーニー展とリヒター展で使用する展示室が異なっていたため、「アナザー・ストーリー」展は、バーニー展からリヒター展への展示替えに際して、展示室1、5、6が付け加わることになった。「人間は自由なんだから:ゲント現代美術館コレクションより」展では、リヒター展と同じ展示室7-12、14が用いられた。このように、毎回さまざまな組み合わせ方がとられた。
設計者自身による使用例
そのなかで本稿では、SANAA展を例に、展示室の組み合わせの一例を具体的に紹介したい。SANAA展を例にするのは、この展覧会が設計者自身の個展であったため、どの展示室をどのような組み合わせで使うのかに関する、設計者の考え方も反映されたからである。
SANAA展とともにおこなわれた「世界の美術館」展は、スイスのバーゼル・アート・センターで企画された美術館建築の国際巡回展である。二五の美術館建築を模型やパネルなどで紹介するものだが、国内巡回にあたって、日本人建築家による四件の美術館建築を紹介する「日本から未来へ: Museums by Japanese Architects」という展示が追加された。SANAA展と「世界の美術館」展は、初めてふたつの展覧会を同時期に開催する機会であった。
まず、美術館側からSANAAに対し、有料ゾーンを横切るように無料の通路を作ることを提案した。これは、コンペ時のプロポーザル案が、円形の建物の中央を横切って通り抜けられる計画になっており(図2)、また、基本設計段階でのさまざまな検討案のなかでも、通り抜けられる通路がある案が挙がっていたためである。通り抜けられるようにすることで、建物のなかを歩き回る来館者の流動性を高めたいと考えた。
一方で、天井高が高く自然光の入る展示室6と11を使いたいという提案がSANAA側からあった。これらの部屋は、それぞれ天井高が一二メートルと九メートルあり、それまでの美術館建築にはめずらしいサイズの部屋である。だが、このふたつの展示室は、離れた場所にあった。展示室を廻っていくときのリズムを考え、大きな展示室と小さな展示室が比較的交互にあることを考慮したためである。これらの展示室を組み合わせることは、全部で五、六室程度の規模の展覧会では難しかったため、展示室6を選び、中央の通路を無料ゾーンとして開放することになった。また、中央の通路の部分にある円形の展示室14は、「世界の美術館」展の日本追加展示「日本から未来へ」に使用することになった。ここで展示された四館のなかには、金沢21世紀美術館も含まれており、空間的な配置においても、「世界の美術館」展とSANAA展をつなぐこととなった。この展示部分は、無料で入場できるようにした。さらに、アニッシュ・カプーアの常設作品《世界の起源》の隣にある展示室1は、コレクションよりカプーアの作品を展示し、この二部屋も入場無料とした。このようにして、SANAA展開催時は、有料ゾーンが三つのエリアに分かれることとなった(図3)。
設計への貢献目指し
このようなエリアわけで開催した結果、各エリアでのまとまりはよかったが、一ヵ所しかないチケットの発券場所からSANAA展の入り口がわかりにくいということが反省点として残った。その後の展覧会では、チケットの発券場所に近い三ヵ所が展覧会の入り口として定着しつつある。また、無料ゾーンの開館時間は九時から二二時、有料ゾーンの開場時間は一〇時から一八時と異なっているが、有料ゾーン内で無料に開放した中央の通路は、有料ゾーンの開場時間しか開放されないため、館内サインやパンフレットなど印刷物との整合性をとるのが難しいという課題も残った。柔軟な空間構成の実現には、空間のみならず、発券システム、サイン、印刷物などインターフェースとの連携も重要であることを感じた。さらに、SANAA展の会場であった展示室6にレアンドロ・エルリッヒの常設作品《スイミング・プール》への入り口があるが、この作品のみ見たいという来館者も多い。この展示室を入場料金の高い企画展示に使いにくいことも考慮に入れる必要がある。
こうした制約を考え合わせながら、いかに建物の可能性を引き出し、柔軟に空間を使うことができるかを今後も試みてゆきたい。それと同時に、課題となる点を検証してゆくことで今後の美術館建築の設計に役立てられればと思う。
金沢21世紀美術館の建物を設計する際、柔軟な空間構成の実現は重要な課題であった。それは、観客の動きの自由度を高めることと、展覧会ごとの展示室の組み合わせの柔軟性とにわけられる。
従来の美術館が、ひとつの正面入り口と、ひとつの順路に沿って展示室を巡る空間構成とをもつのに対し、金沢21世紀美術館は、五ヵ所の入り口をもち、都市を歩き回るようにさまざまな経路をとることができる(図1)。この建物は、自ら選び、探すという観客の能動的な行為を引き出す空間構成をもつといえる。これが観客の動きの自由度を高めるのであり、この点については、これまでにも設計にかかわった学芸員としての立場からさまざまな機会に触れてきた。ここでは、展示室の組み合わせの柔軟性について、開館後約二年間に建物を使った結果の一部を報告したい。
展示室の設計では、可動壁を用いないことを当初から目指していた。可動壁とは、天井から吊り下がる壁を移動させることで、展覧会ごとに空間を仕切るシステムである。金沢21世紀美術館で可動壁を避けた理由のひとつは、自然光が十分に入る天井の高い空間を作るためであった。すなわち、外の空間との繋がりを展示室のなかにいても感じられるような、開放感をもたせるためである。そのためには天井の構造が大仰かつ複雑になり、天井高にも限界のある可動壁を避ける必要があった。また、それぞれの空間に独立性と完結性を追求したことも理由のひとつである。映像作品など音を伴う作品、部屋全体の空間を使った作品の増加がその背景にあるが、一方、「展示室」以外での展示が一般化するなかで、あえて作る展示室ではシンプルなホワイトキューブの完成度を高めたいという意図もあった。
可動壁を使わずに、空間の多様性を確保するためには、あらかじめさまざまな大きさやプロポーションをもった空間を用意する必要がある。なおかつ、それらがさまざまな組み合わせを可能とする配置になっていなければならない。そこで、各展示室が廊下を挟んで互いに離れて配置されることになった。設計段階では、「企画展示室」「常設展示室」という名称で区別していたが、最終的にその区別も無くし、「展示室1~14」という通し番号をつけた。
展覧会ごとの組み合わせ
二〇〇四年一〇月に開館してから、本稿執筆時の二〇〇六年八月において、約二年近く経った。その間にこの一四の展示室を会場として金沢21世紀美術館が主催したおもな企画展は八本だが、毎回、使用する展示室は少しずつ異なっている。開館記念展「21世紀の出会い、共鳴、ここ・から」(以下「開館展」)と「Alternative Paradise:もうひとつの楽園」展では、すべての展示室を使用した(「もうひとつの楽園」展では、展示室1は使用しなかった)。「世界の美術館:未来への架け橋」展と「妹島和世+西沢立衛/SANAA」展(以下「SANAA展」)では、前者が展示室7-12および14を使用し、後者が展示室2-6および13を使用した。「マシュー・バーニー:拘束のドローイング」展(以下「バーニー」展)は、展示室1、5-12、14を使用し、続く「ゲルハルト・リヒター:鏡の絵画」展(以下「リヒター展」)では展示室7-12、14を用いたが、この二本の展覧会と同時に、コレクションからのテーマ展「アナザー・ストーリー」展がおこなわれた。バーニー展とリヒター展で使用する展示室が異なっていたため、「アナザー・ストーリー」展は、バーニー展からリヒター展への展示替えに際して、展示室1、5、6が付け加わることになった。「人間は自由なんだから:ゲント現代美術館コレクションより」展では、リヒター展と同じ展示室7-12、14が用いられた。このように、毎回さまざまな組み合わせ方がとられた。
設計者自身による使用例
そのなかで本稿では、SANAA展を例に、展示室の組み合わせの一例を具体的に紹介したい。SANAA展を例にするのは、この展覧会が設計者自身の個展であったため、どの展示室をどのような組み合わせで使うのかに関する、設計者の考え方も反映されたからである。
SANAA展とともにおこなわれた「世界の美術館」展は、スイスのバーゼル・アート・センターで企画された美術館建築の国際巡回展である。二五の美術館建築を模型やパネルなどで紹介するものだが、国内巡回にあたって、日本人建築家による四件の美術館建築を紹介する「日本から未来へ: Museums by Japanese Architects」という展示が追加された。SANAA展と「世界の美術館」展は、初めてふたつの展覧会を同時期に開催する機会であった。
まず、美術館側からSANAAに対し、有料ゾーンを横切るように無料の通路を作ることを提案した。これは、コンペ時のプロポーザル案が、円形の建物の中央を横切って通り抜けられる計画になっており(図2)、また、基本設計段階でのさまざまな検討案のなかでも、通り抜けられる通路がある案が挙がっていたためである。通り抜けられるようにすることで、建物のなかを歩き回る来館者の流動性を高めたいと考えた。
一方で、天井高が高く自然光の入る展示室6と11を使いたいという提案がSANAA側からあった。これらの部屋は、それぞれ天井高が一二メートルと九メートルあり、それまでの美術館建築にはめずらしいサイズの部屋である。だが、このふたつの展示室は、離れた場所にあった。展示室を廻っていくときのリズムを考え、大きな展示室と小さな展示室が比較的交互にあることを考慮したためである。これらの展示室を組み合わせることは、全部で五、六室程度の規模の展覧会では難しかったため、展示室6を選び、中央の通路を無料ゾーンとして開放することになった。また、中央の通路の部分にある円形の展示室14は、「世界の美術館」展の日本追加展示「日本から未来へ」に使用することになった。ここで展示された四館のなかには、金沢21世紀美術館も含まれており、空間的な配置においても、「世界の美術館」展とSANAA展をつなぐこととなった。この展示部分は、無料で入場できるようにした。さらに、アニッシュ・カプーアの常設作品《世界の起源》の隣にある展示室1は、コレクションよりカプーアの作品を展示し、この二部屋も入場無料とした。このようにして、SANAA展開催時は、有料ゾーンが三つのエリアに分かれることとなった(図3)。
設計への貢献目指し
このようなエリアわけで開催した結果、各エリアでのまとまりはよかったが、一ヵ所しかないチケットの発券場所からSANAA展の入り口がわかりにくいということが反省点として残った。その後の展覧会では、チケットの発券場所に近い三ヵ所が展覧会の入り口として定着しつつある。また、無料ゾーンの開館時間は九時から二二時、有料ゾーンの開場時間は一〇時から一八時と異なっているが、有料ゾーン内で無料に開放した中央の通路は、有料ゾーンの開場時間しか開放されないため、館内サインやパンフレットなど印刷物との整合性をとるのが難しいという課題も残った。柔軟な空間構成の実現には、空間のみならず、発券システム、サイン、印刷物などインターフェースとの連携も重要であることを感じた。さらに、SANAA展の会場であった展示室6にレアンドロ・エルリッヒの常設作品《スイミング・プール》への入り口があるが、この作品のみ見たいという来館者も多い。この展示室を入場料金の高い企画展示に使いにくいことも考慮に入れる必要がある。
こうした制約を考え合わせながら、いかに建物の可能性を引き出し、柔軟に空間を使うことができるかを今後も試みてゆきたい。それと同時に、課題となる点を検証してゆくことで今後の美術館建築の設計に役立てられればと思う。
夜這い棒
よばい棒(標本番号K5872〈上〉K413〈下〉) カロリン諸島のチューク諸島
よばい棒(標本番号K5872〈上〉K413〈下〉) カロリン諸島のチューク諸島
須藤 健一
トラック(現チューク)の若者は生業活動を年配者に任せ、戦い、航海、性などの知識の習得に専念し、「男らしく」振舞うことが期待されてきた。性知識として、恋心を相手に伝える伝統的な手法は、「夜這い棒」と「ほれ薬」である。男性は精魂込めて自分のデザインを棒に刻み、夜這い棒を作った。
男性はこの棒をもち歩き、意中の女性に出会うと棒の刻みを見せびらかし、また触れてもらう。その効果は夜にあらわれる。男性は夜這い棒を肩にお目当ての女性宅へ出かける。彼女が家のどこに寝ているかは予想がつく。家屋はヤシの葉葺きの屋根と壁で、男性は壁越しに夜這い棒の先を差し入れ、彼女の髪の毛にまきつける。彼女はその棒に手をやり、彫刻で相手が誰かを知る。お気に入りだと、棒を二回引く。「どうぞ家のなかに入りなさい」という合図。もしくは一回引いて一回押すと「私が外へ出てゆく」という意味である。関心のないやつには二回とも押し返す。間違って母親を起こして、「盗人」と騒がれて面目をつぶす、間抜けな男性もいた。
家屋は木造やコンクリート製へと変わり、夜這い棒の効力はうせた。それでも、若者は手紙や電話ではなく、窓から注射器で水を寝ている彼女の顔面直撃という手荒なやり方など、夜這い棒のかわりにしている。一方、芳香性の植物や樹液を何種類も調合した秘伝の「ほれ薬」(トラックの香水)は、今でも健在である。
最近、携帯電話がはやりだした。トラックの若者が、携帯電話の威力を愛の伝達の伝統と組み合わせて、どんな新しい「性文化」を作り出すか楽しみである。
男性はこの棒をもち歩き、意中の女性に出会うと棒の刻みを見せびらかし、また触れてもらう。その効果は夜にあらわれる。男性は夜這い棒を肩にお目当ての女性宅へ出かける。彼女が家のどこに寝ているかは予想がつく。家屋はヤシの葉葺きの屋根と壁で、男性は壁越しに夜這い棒の先を差し入れ、彼女の髪の毛にまきつける。彼女はその棒に手をやり、彫刻で相手が誰かを知る。お気に入りだと、棒を二回引く。「どうぞ家のなかに入りなさい」という合図。もしくは一回引いて一回押すと「私が外へ出てゆく」という意味である。関心のないやつには二回とも押し返す。間違って母親を起こして、「盗人」と騒がれて面目をつぶす、間抜けな男性もいた。
家屋は木造やコンクリート製へと変わり、夜這い棒の効力はうせた。それでも、若者は手紙や電話ではなく、窓から注射器で水を寝ている彼女の顔面直撃という手荒なやり方など、夜這い棒のかわりにしている。一方、芳香性の植物や樹液を何種類も調合した秘伝の「ほれ薬」(トラックの香水)は、今でも健在である。
最近、携帯電話がはやりだした。トラックの若者が、携帯電話の威力を愛の伝達の伝統と組み合わせて、どんな新しい「性文化」を作り出すか楽しみである。
友の会とミュージアム・ショップからのご案内
震災によるファッション事情
上羽 陽子
俯(うつぶ)せ寝できない女性用上衣
俯せで寝転がるのはわたしの癖だ。寝る、本を読む、キーボードを打つ。最近、ギックリ腰をしてからは、この俯せの姿勢が腰に悪いとわかっているけれどやめられない。
フィールド先でも昼寝のときについつい俯せになって寝ていることがある。すると、「こら!なんて姿勢で寝てるの!!」と調査先の母親から叱られる。わたしが調査しているインドのラバーリーの女性にとって、俯せで寝るということは決して人前でしてはいけないことのひとつなのである。
その理由は、女性用上衣の形態にある。カンチャリとよばれる上衣は、ブラウスの胸部分にギャザーをとり、その部分に胸を入れる形をしているが、背中部分がすっぽりとあいている。背中のあいているブラウスとブラジャーが一体化したような形をしているのだ。彼女たちは大判ショールを纏(まと)っているため、普段はそのショールによって背中が隠れている。つまり、俯せで寝転がると、はだけたショールから背中があらわになるため、このような姿勢は良くないのだ。
ここ西インド、グジャラート州カッチ県の灼熱の気候を考えれば、この衣裳はとても理にかなっている。時折、わたしも自分で作ったこのカンチャリを身に着けることがあるが、炎暑の陽射しのなかで、風が背中をスーッとなでてくれたときには、とても気持ちが良く機能的だ。当然、形態上の理由から、女性一人ひとりが自分の身体の寸法に合わせて製作をする。
男性の目を意識して
ところが、最近フィールドを訪れると、この背中のあいた上衣の下にタンクトップを着る若い女性を頻繁に見かけるようになった。彼女たちに理由を尋ねると、さきほどまで「今日も暑いね」と会話していたにもかかわらず、「寒いから」と、みな口をそろえて答える。
そしてついに、調査先の家の嫁もカンチャリの下にタンクトップを着るようになった。理由を聞いても他の女性と同じように「寒いから」と答える。しかし、あるとき、彼女の実家を訪れる機会があった。彼女の母親に、娘がタンクトップを着る理由について尋ねるとゆっくりと答えてくれた。「あなたも知っているように、娘の嫁ぎ先の村では震災復興が盛んにおこなわれているでしょ。新しい家が次々と建ち、その家を建てるために村には外部から多くの男性がやって来る。どうやらその男の人たちの視線が気になっているらしい」と言う。
グジャラート州では、カッチ県を震源地とした大きな地震が二〇〇一年一月末に起きた。死者二万人という大災害であった。
確かに、家事の最中にハラリとショールが落ち、背中があらわになった彼女を見かけると、女性のわたしでもドキッとすることがある。まして外部の男性ならば言うまでもない。以前から若い女性のなかには背中があいているこの衣裳に抵抗を感じ、下にタンクトップを着ることもあった。ただし、非常に稀であり、そのような女性を見かけることは少なかった。
ところが震災後、外部の男性の視線がきっかけとなり、ラバーリー女性のタンクトップ着用が一気に増加した。そして、同時に、以前では自分の身体の寸法にぴったりと合わせて製作されていた上衣が、その下にタンクトップを着用することによって、全体的にゆったりとした縫製のデザインへと変化してきている。
そして今では、「どうせ下にタンクトップを着るから」と言って、大まかな寸法を親戚や友人に伝えて、製作の依頼をする若い女性が増えている。彼女たちに上衣の作り方を知っているかと尋ねると、「なんとなくは知っているけれど、実際には作れない」と、恥ずかしそうに答えるのである。
衣裳に流行はつきものである。このラバーリーのタンクトップ着用がただの一時の流行に終わるか、それとも定番化し、いつか俯せで寝転がるラバーリー女性を見る日が来るのか、興味津々である。
俯せで寝転がるのはわたしの癖だ。寝る、本を読む、キーボードを打つ。最近、ギックリ腰をしてからは、この俯せの姿勢が腰に悪いとわかっているけれどやめられない。
フィールド先でも昼寝のときについつい俯せになって寝ていることがある。すると、「こら!なんて姿勢で寝てるの!!」と調査先の母親から叱られる。わたしが調査しているインドのラバーリーの女性にとって、俯せで寝るということは決して人前でしてはいけないことのひとつなのである。
その理由は、女性用上衣の形態にある。カンチャリとよばれる上衣は、ブラウスの胸部分にギャザーをとり、その部分に胸を入れる形をしているが、背中部分がすっぽりとあいている。背中のあいているブラウスとブラジャーが一体化したような形をしているのだ。彼女たちは大判ショールを纏(まと)っているため、普段はそのショールによって背中が隠れている。つまり、俯せで寝転がると、はだけたショールから背中があらわになるため、このような姿勢は良くないのだ。
ここ西インド、グジャラート州カッチ県の灼熱の気候を考えれば、この衣裳はとても理にかなっている。時折、わたしも自分で作ったこのカンチャリを身に着けることがあるが、炎暑の陽射しのなかで、風が背中をスーッとなでてくれたときには、とても気持ちが良く機能的だ。当然、形態上の理由から、女性一人ひとりが自分の身体の寸法に合わせて製作をする。
男性の目を意識して
ところが、最近フィールドを訪れると、この背中のあいた上衣の下にタンクトップを着る若い女性を頻繁に見かけるようになった。彼女たちに理由を尋ねると、さきほどまで「今日も暑いね」と会話していたにもかかわらず、「寒いから」と、みな口をそろえて答える。
そしてついに、調査先の家の嫁もカンチャリの下にタンクトップを着るようになった。理由を聞いても他の女性と同じように「寒いから」と答える。しかし、あるとき、彼女の実家を訪れる機会があった。彼女の母親に、娘がタンクトップを着る理由について尋ねるとゆっくりと答えてくれた。「あなたも知っているように、娘の嫁ぎ先の村では震災復興が盛んにおこなわれているでしょ。新しい家が次々と建ち、その家を建てるために村には外部から多くの男性がやって来る。どうやらその男の人たちの視線が気になっているらしい」と言う。
グジャラート州では、カッチ県を震源地とした大きな地震が二〇〇一年一月末に起きた。死者二万人という大災害であった。
確かに、家事の最中にハラリとショールが落ち、背中があらわになった彼女を見かけると、女性のわたしでもドキッとすることがある。まして外部の男性ならば言うまでもない。以前から若い女性のなかには背中があいているこの衣裳に抵抗を感じ、下にタンクトップを着ることもあった。ただし、非常に稀であり、そのような女性を見かけることは少なかった。
ところが震災後、外部の男性の視線がきっかけとなり、ラバーリー女性のタンクトップ着用が一気に増加した。そして、同時に、以前では自分の身体の寸法にぴったりと合わせて製作されていた上衣が、その下にタンクトップを着用することによって、全体的にゆったりとした縫製のデザインへと変化してきている。
そして今では、「どうせ下にタンクトップを着るから」と言って、大まかな寸法を親戚や友人に伝えて、製作の依頼をする若い女性が増えている。彼女たちに上衣の作り方を知っているかと尋ねると、「なんとなくは知っているけれど、実際には作れない」と、恥ずかしそうに答えるのである。
衣裳に流行はつきものである。このラバーリーのタンクトップ着用がただの一時の流行に終わるか、それとも定番化し、いつか俯せで寝転がるラバーリー女性を見る日が来るのか、興味津々である。
18世紀啓蒙主義スペインとアメリカ先住民
―マラスピーナ探検隊の貢献
―マラスピーナ探検隊の貢献
黒田 悦子
探検隊と先住民の関係
最近、中米・カリブ海の先住民の歴史と現在の状況について解説を書くことになり、あちこちに知識と理解の不足を感じた。そのひとつが一八世紀ブルボン朝スペインの植民地政策に関わる個所であった。
一般的には、この王朝の重商主義政策は植民地を圧迫し先住民の反乱を誘発した、ということになっているが、スペイン史の脈絡から見ると、この期の啓蒙主義が先住民に益したこともあるのではないか、とわたしは考えた。そこで一八世紀のスペイン史を読んでいると、この期の探検隊と先住民の関係について興味深い史実に出合った。歴史家は既にご存知かもしれないが、先住民への関心にしぼって要点をお伝えしたい。
一八世紀のスペインは、中南米の植民地をおもな対象として六〇余りの科学探検隊を派遣している。時期は一七三五~一八〇七年で、カルロス三世とカルロス四世の治世下に集中している。このなかで、規模が大きく人類学的にも興味深いのは一七八九~一七九四年のアレハンドロ・マラスピーナの探検隊である。
マラスピーナはイタリアのパルマ公爵領で貴族の息子として生まれ、当時スペイン領のシチリアで育ち、ローマで物理学を学び啓蒙思想に接した。一七七四年、二〇歳でスペインに渡り、海軍に入隊し、アジアや南米への航海経験を積んだ。一七八九年、アトレビーダ号とデスクビエルタ号二艘の船団の隊長としてカディス港から出発し、南米のモンテビデオに向かい(地図)、南米から中米、アラスカ、南下してバンクーバー島、カリフォルニア、メキシコのアカプルコ、そこから太平洋に出て、グアム、フィリピン、マカオ、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、南米と巡り、スペインに戻った。
植民地の独立を願う
啓蒙主義者マラスピーナと将校の、先住民への興味は植民地体制に組み込まれていない人びとにあった。南米では、パタゴニア人とウィリチェ(マプーチェの一部)についての記録と絵が印象的である。カシーケ(首長)は威厳に満ち、子どもの姿には愛らしさと力強さが並存している。北米北西海岸のトリンギットとヌートカについての絵では、表情に満ちた首長や妻と子どもたち、カヌーに乗った大勢の人びと、平和交渉を身振りで求める男たち、火葬用の積みまきと墓などが注目を集める。これらの絵と記録のほとんどは、別の探検隊による収集品と一緒にマドリードのアメリカ博物館と海軍博物館に所蔵されている。実物を見てみたいものである。
マラスピーナは一七九四年、スペインに戻り、カルロス四世とマリア・ルイサに労をねぎらわれ、海軍でも昇進した。しかし、彼は植民地の独立や関税と貿易制限の軽減を答申し、逮捕され七年の刑に服し、シチリアで死亡した。探検の成果は生存中には出版されず、先住民とスペインの関係の改善に貢献することもできなかった。
最近、中米・カリブ海の先住民の歴史と現在の状況について解説を書くことになり、あちこちに知識と理解の不足を感じた。そのひとつが一八世紀ブルボン朝スペインの植民地政策に関わる個所であった。
一般的には、この王朝の重商主義政策は植民地を圧迫し先住民の反乱を誘発した、ということになっているが、スペイン史の脈絡から見ると、この期の啓蒙主義が先住民に益したこともあるのではないか、とわたしは考えた。そこで一八世紀のスペイン史を読んでいると、この期の探検隊と先住民の関係について興味深い史実に出合った。歴史家は既にご存知かもしれないが、先住民への関心にしぼって要点をお伝えしたい。
一八世紀のスペインは、中南米の植民地をおもな対象として六〇余りの科学探検隊を派遣している。時期は一七三五~一八〇七年で、カルロス三世とカルロス四世の治世下に集中している。このなかで、規模が大きく人類学的にも興味深いのは一七八九~一七九四年のアレハンドロ・マラスピーナの探検隊である。
マラスピーナはイタリアのパルマ公爵領で貴族の息子として生まれ、当時スペイン領のシチリアで育ち、ローマで物理学を学び啓蒙思想に接した。一七七四年、二〇歳でスペインに渡り、海軍に入隊し、アジアや南米への航海経験を積んだ。一七八九年、アトレビーダ号とデスクビエルタ号二艘の船団の隊長としてカディス港から出発し、南米のモンテビデオに向かい(地図)、南米から中米、アラスカ、南下してバンクーバー島、カリフォルニア、メキシコのアカプルコ、そこから太平洋に出て、グアム、フィリピン、マカオ、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、南米と巡り、スペインに戻った。
植民地の独立を願う
啓蒙主義者マラスピーナと将校の、先住民への興味は植民地体制に組み込まれていない人びとにあった。南米では、パタゴニア人とウィリチェ(マプーチェの一部)についての記録と絵が印象的である。カシーケ(首長)は威厳に満ち、子どもの姿には愛らしさと力強さが並存している。北米北西海岸のトリンギットとヌートカについての絵では、表情に満ちた首長や妻と子どもたち、カヌーに乗った大勢の人びと、平和交渉を身振りで求める男たち、火葬用の積みまきと墓などが注目を集める。これらの絵と記録のほとんどは、別の探検隊による収集品と一緒にマドリードのアメリカ博物館と海軍博物館に所蔵されている。実物を見てみたいものである。
マラスピーナは一七九四年、スペインに戻り、カルロス四世とマリア・ルイサに労をねぎらわれ、海軍でも昇進した。しかし、彼は植民地の独立や関税と貿易制限の軽減を答申し、逮捕され七年の刑に服し、シチリアで死亡した。探検の成果は生存中には出版されず、先住民とスペインの関係の改善に貢献することもできなかった。
地方と世界の橋渡し役をになって
―イラン人大量入国のその後―
―イラン人大量入国のその後―
イラン人の行方
もう一五年以上も前のことになる。当時の新聞は関東各地で日曜になると公園などに集まるイラン人のニュースであふれていた。突如あらわれた、それもほとんどなじみのなかったイラン人の到来に人びとはとまどい、驚きの目をもってうけとめた。外国人へのさまざまなうわさや偏見が行きかったのもそのころだった。景気はすでに停滞期に入りはじめていたが、肉体労働でも確実に現金がかせげるといううわさで、短期の日本滞在にはビザが不要であったパキスタンやイランから人びとが大挙しておしよせていた。
今考えると、当時が最近日本で話題になっている本格的な多民族化のはじまりであった。その後、外国人の話題は、ブラジルなど南米からの日系人、急増する中国人や韓国人に集中し、公園に集まるイラン人の話は聞かなくなった。実際、一九九二年の相互ビザ協定の見直しの結果、日本へのイラン人の入国やビザの延長は困難になったため、かつての七万人は一万人台に激減したといわれている。その後、イラン人が違法電話カード販売などでニュースにときおりながれることはあったが、日本に残ったイラン人の話はあまり聞くことはない。彼らは今、どこにいるのだろうか。
友人に助けられて
メヘラバンさんもじつはそのような十数年前来日したイラン人の一人だった。京都府南部の国道沿いに車の解体工場の集まる一角がある。周囲には田園風景も広がり、むかしながらの村落も残る。メへラバンさんはイラン人の友人レザーさんとともに、ここで倉庫の一部をかり、車の解体と解体部品の輸出業にたずさわって七年になる。扱うのは廃車された外車が中心で、イランを除く中近東の国々がおもな輸出相手である。普段は車の解体とともに、ケータイ片手に車で商談やオークションにかけまわっている。もちろん用いるのは流暢な大阪弁の商いことば。同業者のパキスタン人たちとも日本語でやりとりをすることが多い。経営規模の拡大などという構想はない。儲かっているわけではないが、やれるだけ続けていくという。ニッチ(すき間)産業ではあっても零細企業であることには変わりない。
イランで自動車工だった当時二三歳のメヘラバンさんが来日したのは一五年前、観光ビザだった。ビザが切れても建築現場をわたりあるき、重労働もやってきた。しかし、若かった当時、苦しかったという思いはあまりない。イラン人の友人が大勢まわりにいて助けてくれたし、日本語も知らないうちに身に付いた。日本語学校に通ったことはないが、日常でも商売でもことばで苦労することはほとんどなくなった。
メヘラバンさんは友人のレザーさんと同様に、今では日本人の女性と結婚して家族をもっている。戒律を比較的ゆるやかに解釈することも可能なシーア派であり、近代化の進んでいるイラン出身の彼らにとって日本での生活は、宗教的にも日常の生活でもそれほど窮屈とは感じていない。決して多くはないが日常の礼拝や禁酒、禁食慣行にもそれほどこだわらない人もいるほどだ。メヘラバンさんは逆に日本人がアメリカの政治的見方をとおして抱くイランの暗く、怖いイメージにとまどうくらいだ。庶民の生活レベルでは礼儀作法や人情では日本人と通じるところはかなりあると思っている。とはいえ、状況次第では家族とイランに戻ることもありうる。そのため三歳の息子にはペルシャ語で話し、ことばだけは身に付けさせてやりたいと思う。
かつて滞在期限切れ期間の摘発や病気ケガへの不安、安定しない生活など、ひとなみの苦労は彼にもあったはずだ。しかし、いつもイラン人や日本人の知人のおかげでなんとかなった、切り抜けてきたという彼に、悲壮感はない。日本語を話し、永住ビザをもつ外国人に対しても日本人、日本社会がときおり見せるよそ者扱いには閉口するが、十数年のあいだに除々ではあるが、これらもかなり改善されてきたという。また関西はイラン人の大量流入時代の偏見がないだけ暮らしやすいと思っている。週日は晩遅くまで工場や外まわりの仕事をしながら、土曜の夜は友人たちとちょっと羽をのばし、日曜は家族と買い物やドライブでくつろぐのが楽しみだという。
地域を世界と結ぶ
地球時代のビジネスなどというと、アタッシュケースを手に、商品には手も触れずに世界の都市をとびまわる姿を連想しがちだ。合理性を重んじるビジネスの世界では、家族やねちっこい人間関係が前面にあらわれるのはきわめて稀である。しかしメヘラバンさんたちの仕事は、確かに世界を相手に展開してはいるものの、日常の舞台はあくまでローカル、家庭的で、対面主義である。都心からはなれた地で、少し前までポンコツ車として部品をとる以外ごみ扱いされてきた廃車の町を世界に直結させたのは、彼らに負うところが多い。かといって、彼らにことさら特別な気負いがあるわけでも、周囲に国際性やエスニック性を誇示するわけでもない。
一時のピークから十数年も経て、家庭を築いて定着したイラン人は、現在、日本各地に分散するが、中国やブラジル出身者やコリアンのように堅固なコミュニティも集住地ももってはいない。とはいえ、外見はもとより、仲間内で使うことばからいっても彼らの存在自体、特に地方においては周囲からは大きく際立っているのは事実だ。しかし地域の産業の一端を担い、あるいは住民として、その存在自体がすでに町の風景の一部となっているイラン人は決して少なくはないはずだ。社会の多民族化にはいくつものパターンがある。そのひとつがメヘラバンさんのような人びとによって担われているのは確かである。
もう一五年以上も前のことになる。当時の新聞は関東各地で日曜になると公園などに集まるイラン人のニュースであふれていた。突如あらわれた、それもほとんどなじみのなかったイラン人の到来に人びとはとまどい、驚きの目をもってうけとめた。外国人へのさまざまなうわさや偏見が行きかったのもそのころだった。景気はすでに停滞期に入りはじめていたが、肉体労働でも確実に現金がかせげるといううわさで、短期の日本滞在にはビザが不要であったパキスタンやイランから人びとが大挙しておしよせていた。
今考えると、当時が最近日本で話題になっている本格的な多民族化のはじまりであった。その後、外国人の話題は、ブラジルなど南米からの日系人、急増する中国人や韓国人に集中し、公園に集まるイラン人の話は聞かなくなった。実際、一九九二年の相互ビザ協定の見直しの結果、日本へのイラン人の入国やビザの延長は困難になったため、かつての七万人は一万人台に激減したといわれている。その後、イラン人が違法電話カード販売などでニュースにときおりながれることはあったが、日本に残ったイラン人の話はあまり聞くことはない。彼らは今、どこにいるのだろうか。
友人に助けられて
メヘラバンさんもじつはそのような十数年前来日したイラン人の一人だった。京都府南部の国道沿いに車の解体工場の集まる一角がある。周囲には田園風景も広がり、むかしながらの村落も残る。メへラバンさんはイラン人の友人レザーさんとともに、ここで倉庫の一部をかり、車の解体と解体部品の輸出業にたずさわって七年になる。扱うのは廃車された外車が中心で、イランを除く中近東の国々がおもな輸出相手である。普段は車の解体とともに、ケータイ片手に車で商談やオークションにかけまわっている。もちろん用いるのは流暢な大阪弁の商いことば。同業者のパキスタン人たちとも日本語でやりとりをすることが多い。経営規模の拡大などという構想はない。儲かっているわけではないが、やれるだけ続けていくという。ニッチ(すき間)産業ではあっても零細企業であることには変わりない。
イランで自動車工だった当時二三歳のメヘラバンさんが来日したのは一五年前、観光ビザだった。ビザが切れても建築現場をわたりあるき、重労働もやってきた。しかし、若かった当時、苦しかったという思いはあまりない。イラン人の友人が大勢まわりにいて助けてくれたし、日本語も知らないうちに身に付いた。日本語学校に通ったことはないが、日常でも商売でもことばで苦労することはほとんどなくなった。
メヘラバンさんは友人のレザーさんと同様に、今では日本人の女性と結婚して家族をもっている。戒律を比較的ゆるやかに解釈することも可能なシーア派であり、近代化の進んでいるイラン出身の彼らにとって日本での生活は、宗教的にも日常の生活でもそれほど窮屈とは感じていない。決して多くはないが日常の礼拝や禁酒、禁食慣行にもそれほどこだわらない人もいるほどだ。メヘラバンさんは逆に日本人がアメリカの政治的見方をとおして抱くイランの暗く、怖いイメージにとまどうくらいだ。庶民の生活レベルでは礼儀作法や人情では日本人と通じるところはかなりあると思っている。とはいえ、状況次第では家族とイランに戻ることもありうる。そのため三歳の息子にはペルシャ語で話し、ことばだけは身に付けさせてやりたいと思う。
かつて滞在期限切れ期間の摘発や病気ケガへの不安、安定しない生活など、ひとなみの苦労は彼にもあったはずだ。しかし、いつもイラン人や日本人の知人のおかげでなんとかなった、切り抜けてきたという彼に、悲壮感はない。日本語を話し、永住ビザをもつ外国人に対しても日本人、日本社会がときおり見せるよそ者扱いには閉口するが、十数年のあいだに除々ではあるが、これらもかなり改善されてきたという。また関西はイラン人の大量流入時代の偏見がないだけ暮らしやすいと思っている。週日は晩遅くまで工場や外まわりの仕事をしながら、土曜の夜は友人たちとちょっと羽をのばし、日曜は家族と買い物やドライブでくつろぐのが楽しみだという。
地域を世界と結ぶ
地球時代のビジネスなどというと、アタッシュケースを手に、商品には手も触れずに世界の都市をとびまわる姿を連想しがちだ。合理性を重んじるビジネスの世界では、家族やねちっこい人間関係が前面にあらわれるのはきわめて稀である。しかしメヘラバンさんたちの仕事は、確かに世界を相手に展開してはいるものの、日常の舞台はあくまでローカル、家庭的で、対面主義である。都心からはなれた地で、少し前までポンコツ車として部品をとる以外ごみ扱いされてきた廃車の町を世界に直結させたのは、彼らに負うところが多い。かといって、彼らにことさら特別な気負いがあるわけでも、周囲に国際性やエスニック性を誇示するわけでもない。
一時のピークから十数年も経て、家庭を築いて定着したイラン人は、現在、日本各地に分散するが、中国やブラジル出身者やコリアンのように堅固なコミュニティも集住地ももってはいない。とはいえ、外見はもとより、仲間内で使うことばからいっても彼らの存在自体、特に地方においては周囲からは大きく際立っているのは事実だ。しかし地域の産業の一端を担い、あるいは住民として、その存在自体がすでに町の風景の一部となっているイラン人は決して少なくはないはずだ。社会の多民族化にはいくつものパターンがある。そのひとつがメヘラバンさんのような人びとによって担われているのは確かである。
クワクワカワクの丸木舟
特別展「ラッコとガラス玉ー北太平洋の先住民交易」を二〇〇一年に開催することになり、準備を開始した。わたしの担当は北太平洋の東側にあたるアラスカからカナダの太平洋側にかけての先住民族の交易であった。
この展覧会の目玉のひとつとして、クワクワカワクの交易用の丸木舟を展示しようということになった。しかし国内にはなく、現地で収集するか、外国から借用するかのいずれかだ。わたしたちには、かの有名な人類学者フランツ・ボアズの調査に協力した先住民ロバート・ハントの孫にあたるグローリア・クランマー=ウエブスターさんという力強い味方がいた。
そこで、わたしたちは彼女に意見を求めたところ、丸木舟を製作できる技術をもつ人がおり、技術の伝承のためにもぜひ、丸木舟を作りたいとの回答であった。作り手は、彼女の兄ダグラス・クランマーさんであるという。わたしたちはグローリアさんを窓口として、彼女の住むバンクーバー島のアラート・ベイを中心に先住民交易に関係する工芸品、儀礼道具、装飾品、そして全長約一〇メートルの丸木舟を収集することにした。
ひとは変わっても、思いは同じ
民博の現地収集の基本のひとつは、むかしから伝わるお宝を収集するのではなく、現地で製作してもらい、それを買いとるやり方である。この方法は、あらたに製作したものを買いとるわけだから、現地からのものをもち去るのではなく、現地に迷惑をかけることもない。むしろ現地には現金が落ちるし、製作技術の伝承にも一役買うことができ、現地のほうも大喜びだ。しかもときとして製作過程を詳細に知ることができる。
しかし、バンクーバー島で大型の丸木舟をあらたに製作してもらうことには一抹の不安があった。今から三〇年ほど前、民博の先輩たちはアメリカ展示を開設するべく、カナダの北西海岸先住民にトーテムポールの製作を依頼した。依頼したはよいが、一年近く経っても現地から音沙汰なしであった。心配した館員がカナダに飛んだところ、トーテムポールは完成していなかったという。現地のペースで、あまり時間にとらわれることなく製作をしていたようだ。ご存知のように、日本は単年度で会計がしめられる。三月末までに購入し、支払いを終了すべきであった。担当者は、胃の痛む思いをしたという。
収集は忍耐
それから二〇年以上が過ぎた二〇〇〇年の夏、わたしはアラート・ベイを訪れた。そのときまでには、丸木舟が完成しているはずで、明後日には、カナダ日通のトラックが村まで来ることになっていた。グローリアさんのところを訪ねると、開口一番、申し訳なさそうに「丸木舟はまだ、完成していない」という。目の前が真っ暗になったが、当面は、丸木舟以外の木箱、楽器、仮面、ビーズ製のネックレス、銀製の腕輪などを地元で収集することにした。カナダ日通の方には電話で連絡し、大型のトラックではなく、中型のトラックでよいと知らせたが、手遅れだった。翌日には、愛想のよい中国系カナダ人ドライバーがやって来て、まる一日かけて梱包(こんぽう)し、翌日、アラート・ベイを去った。
わたしは丸木舟を製作している工房を訪ね、完成の時期を確認するとともに、日本からもってきた小切手で代金を全額支払った。後ろ髪を引かれながら、アラート・ベイを後にした。
それから二ヵ月経っても、現地からは音信不通である。すでに一一月にわたしは現地に丸木舟を受けとりに行くことになっていた。心配になって、当時、バンクーバー島のキャンベル・リバーでフィールドワークをおこなっていた立川陽仁君に頼んで、現地に行って様子を見てもらうことにした。わたしの出発の二週間ほど前のことである。
現地からメールが届いた。まだ、丸木舟は完成していないが、わたしが到着するころには完成するだろうというものだった。わたしは不安をいだきつつ、ふたたびアラート・ベイに向かった。
二度あることは三度ある
到着すると、またもやグローリアさんが「船首にひびが入ったために、その処置で、完成が遅れている」とすまなさそうにいう。二人で工房を訪ねてみると、ほぼ完成していたが、船体にウミヘビの図柄の下絵を描いているところであった。また、トラックをキャンセルするはめになってしまった。特別展示の開幕までは、時間があるものの、会計年度が終わるまで四ヵ月をきっている。とりあえず、ほかの標本の収集をおこない、また、後ろ髪を引かれながら現地を去り、別件の調査に向かった。
その後、バンクーバーにあるカナダ日通から日本に何度かメールが入り、丸木舟を現地にとりに行こうとしたが、完成しておらず、何度もキャンセルされたとのことであった。先輩たちの思い出話が頭を横切ったが、ひたすら待つよりほかになかった。年が明ける直前に、グローリアさんから完成したとの朗報が入った。
一安心したとたんに、今度はカナダ日通からメールが入り、バンクーバーまでトラックとフェリーで運んで来たものの、丸木舟には水がたまり、すぐには日本に船便で発送できないとの知らせであった。あとでわかったことだが、先住民の人たちは、輸送中に丸木舟にひびが入らないように、その内側に水をはり、トラック輸送をさせたそうだ。バンクーバーで少し船体を乾かせてから、それは輸送船で太平洋を横断して、年明けに大阪に到着した。
ふりかえれば、製作依頼から民博に届くまで一年以上かかったことになる。無事、特別展示も終わり、今、その舟は収蔵庫に眠っている。近年、これだけ大きい丸木舟の製作は、稀である。その理由は、丸木舟を作ることができるほどのシダーの巨木が、この一五〇年あまりの森林伐採でバンクーバー島にはないこと、さらにその製作技術をもつ先住民の数が限られていることである。忍耐に忍耐を重ねて手に入れた丸木舟は、わたしにとっては、思い出に残る逸品である。
この展覧会の目玉のひとつとして、クワクワカワクの交易用の丸木舟を展示しようということになった。しかし国内にはなく、現地で収集するか、外国から借用するかのいずれかだ。わたしたちには、かの有名な人類学者フランツ・ボアズの調査に協力した先住民ロバート・ハントの孫にあたるグローリア・クランマー=ウエブスターさんという力強い味方がいた。
そこで、わたしたちは彼女に意見を求めたところ、丸木舟を製作できる技術をもつ人がおり、技術の伝承のためにもぜひ、丸木舟を作りたいとの回答であった。作り手は、彼女の兄ダグラス・クランマーさんであるという。わたしたちはグローリアさんを窓口として、彼女の住むバンクーバー島のアラート・ベイを中心に先住民交易に関係する工芸品、儀礼道具、装飾品、そして全長約一〇メートルの丸木舟を収集することにした。
ひとは変わっても、思いは同じ
民博の現地収集の基本のひとつは、むかしから伝わるお宝を収集するのではなく、現地で製作してもらい、それを買いとるやり方である。この方法は、あらたに製作したものを買いとるわけだから、現地からのものをもち去るのではなく、現地に迷惑をかけることもない。むしろ現地には現金が落ちるし、製作技術の伝承にも一役買うことができ、現地のほうも大喜びだ。しかもときとして製作過程を詳細に知ることができる。
しかし、バンクーバー島で大型の丸木舟をあらたに製作してもらうことには一抹の不安があった。今から三〇年ほど前、民博の先輩たちはアメリカ展示を開設するべく、カナダの北西海岸先住民にトーテムポールの製作を依頼した。依頼したはよいが、一年近く経っても現地から音沙汰なしであった。心配した館員がカナダに飛んだところ、トーテムポールは完成していなかったという。現地のペースで、あまり時間にとらわれることなく製作をしていたようだ。ご存知のように、日本は単年度で会計がしめられる。三月末までに購入し、支払いを終了すべきであった。担当者は、胃の痛む思いをしたという。
収集は忍耐
それから二〇年以上が過ぎた二〇〇〇年の夏、わたしはアラート・ベイを訪れた。そのときまでには、丸木舟が完成しているはずで、明後日には、カナダ日通のトラックが村まで来ることになっていた。グローリアさんのところを訪ねると、開口一番、申し訳なさそうに「丸木舟はまだ、完成していない」という。目の前が真っ暗になったが、当面は、丸木舟以外の木箱、楽器、仮面、ビーズ製のネックレス、銀製の腕輪などを地元で収集することにした。カナダ日通の方には電話で連絡し、大型のトラックではなく、中型のトラックでよいと知らせたが、手遅れだった。翌日には、愛想のよい中国系カナダ人ドライバーがやって来て、まる一日かけて梱包(こんぽう)し、翌日、アラート・ベイを去った。
わたしは丸木舟を製作している工房を訪ね、完成の時期を確認するとともに、日本からもってきた小切手で代金を全額支払った。後ろ髪を引かれながら、アラート・ベイを後にした。
それから二ヵ月経っても、現地からは音信不通である。すでに一一月にわたしは現地に丸木舟を受けとりに行くことになっていた。心配になって、当時、バンクーバー島のキャンベル・リバーでフィールドワークをおこなっていた立川陽仁君に頼んで、現地に行って様子を見てもらうことにした。わたしの出発の二週間ほど前のことである。
現地からメールが届いた。まだ、丸木舟は完成していないが、わたしが到着するころには完成するだろうというものだった。わたしは不安をいだきつつ、ふたたびアラート・ベイに向かった。
二度あることは三度ある
到着すると、またもやグローリアさんが「船首にひびが入ったために、その処置で、完成が遅れている」とすまなさそうにいう。二人で工房を訪ねてみると、ほぼ完成していたが、船体にウミヘビの図柄の下絵を描いているところであった。また、トラックをキャンセルするはめになってしまった。特別展示の開幕までは、時間があるものの、会計年度が終わるまで四ヵ月をきっている。とりあえず、ほかの標本の収集をおこない、また、後ろ髪を引かれながら現地を去り、別件の調査に向かった。
その後、バンクーバーにあるカナダ日通から日本に何度かメールが入り、丸木舟を現地にとりに行こうとしたが、完成しておらず、何度もキャンセルされたとのことであった。先輩たちの思い出話が頭を横切ったが、ひたすら待つよりほかになかった。年が明ける直前に、グローリアさんから完成したとの朗報が入った。
一安心したとたんに、今度はカナダ日通からメールが入り、バンクーバーまでトラックとフェリーで運んで来たものの、丸木舟には水がたまり、すぐには日本に船便で発送できないとの知らせであった。あとでわかったことだが、先住民の人たちは、輸送中に丸木舟にひびが入らないように、その内側に水をはり、トラック輸送をさせたそうだ。バンクーバーで少し船体を乾かせてから、それは輸送船で太平洋を横断して、年明けに大阪に到着した。
ふりかえれば、製作依頼から民博に届くまで一年以上かかったことになる。無事、特別展示も終わり、今、その舟は収蔵庫に眠っている。近年、これだけ大きい丸木舟の製作は、稀である。その理由は、丸木舟を作ることができるほどのシダーの巨木が、この一五〇年あまりの森林伐採でバンクーバー島にはないこと、さらにその製作技術をもつ先住民の数が限られていることである。忍耐に忍耐を重ねて手に入れた丸木舟は、わたしにとっては、思い出に残る逸品である。
海を渡るオウム
笹岡 正俊
罠を見回りにきたわたしたちの気配を感じたのであろう。罠に足をとられて身動きがとれなくなったオオバタンは、翼をばたつかせながら「ギャーッ、ギャーッ」とけたたましく鳴いた。獲物を確認したアコさん(仮名)は、山刀で入れた切り込みのわずかなくぼみに足をかけ、罠が仕掛けてあるドリアンの大木をよじ登って行った。
二〇〇四年一月。インドネシア東部セラム島の中央山岳地帯に位置するM村でわたしはアコさんがおこなうオオバタンの猟に同行させてもらっていた。
オウムで副収入
オオバタンは、セラム島とその周辺域にしか生息しない白色のオウムである。かつてペットとして国際的に高い人気を集め、八〇年代にはこの島から七万五〇〇〇羽以上が海外に輸出されたといわれる。その後、乱獲による絶滅への懸念から「ワシントン条約」の付属書Ⅰの記載種となり、国際取引が禁止された。また、国内法でもその捕獲や商取引が厳しく禁じられることになった。しかし、住民は今もオオバタンの猟を続けている。
M村は島のなかでももっとも奥地に位置する。麓(ふもと)の村へは丸一日から二日かけて山道を徒歩で行くしかない。したがって、もち運びが容易で高い値がつくオオバタンは僻地山村から市場に出せる数少ない林産物のひとつとなっている。
とはいえM村住民にとってもっとも重要な収入源は、オウムではなく丁子(ちょうじ)(クローブ)だ。彼らは九月から一一月にかけて、南海岸に出稼ぎに出て、沿岸住民の農園で農業労働者として丁子(ちょうじ)の摘みとりをおこなう。収穫した丁子を山地民は農園保有者と折半した後、自分のもち分を集荷人に売っている。そうやってえた現金は、その後数ヵ月、場合によっては一年以上にわたり、彼らが塩や灯油など生活必需品を購入するために充てられる。丁子の出来は年によって大きく変動する。したがって、アコさんによると、丁子収入が芳(かんば)しくないときはオオバタンを捕獲して沿岸部の仲買人に売り、当座を凌(しの)ぐ現金をえるのだという。つまり、オオバタンは、丁子収入の補完的・代替的収入源のひとつなのだ。
貧者が獲り、富者が買(飼)う
アコさんたちが捕獲したオオバタンはいったいどこに運ばれてゆくのだろうか。一部は国内の野鳥マーケットに、そして一部はおそらく国外に密輸されている。日本は現在、シンガポールなどから年間一〇〇羽以上のオオバタンを輸入しており、その多くはブリーダーの繁殖個体だとされている。しかし、TRAFFIC(野性生物取引のモニタリングをおこなっている国際NGO)の調査によると、セラム島で捕獲された野生のオオバタンがメダン(スマトラ島)を経由してシンガポールなどに密輸されているという。したがって、日本に輸入されるオオバタンのなかに、そうした野生個体が含まれている可能性もないとはいえない。
そのようなことを考えながら、日本におけるオオバタン価格をインターネットで調べていて驚いた。某ペットショップで一羽七〇万円の売値がついていたからだ。山地民の売値は一羽七~一〇万ルピア(八〇〇~一二〇〇円)だから、その差はじつに五八三~八七五倍である!
わたしが見た山地民のオオバタン猟は、おおむね生活必需品の購入などで現金が必要になったときにおこなわれる「小規模かつ必要充足的な猟」であるといってよかった。しかし、日本でこんなにも高く売れることを知ったら、彼らのなかには次のように言い出す人がいるかもしれない。
「マサ、たくさん獲るから日本に運んで売ってくれ。一緒にひと儲けしよう!」
二〇〇四年一月。インドネシア東部セラム島の中央山岳地帯に位置するM村でわたしはアコさんがおこなうオオバタンの猟に同行させてもらっていた。
オウムで副収入
オオバタンは、セラム島とその周辺域にしか生息しない白色のオウムである。かつてペットとして国際的に高い人気を集め、八〇年代にはこの島から七万五〇〇〇羽以上が海外に輸出されたといわれる。その後、乱獲による絶滅への懸念から「ワシントン条約」の付属書Ⅰの記載種となり、国際取引が禁止された。また、国内法でもその捕獲や商取引が厳しく禁じられることになった。しかし、住民は今もオオバタンの猟を続けている。
M村は島のなかでももっとも奥地に位置する。麓(ふもと)の村へは丸一日から二日かけて山道を徒歩で行くしかない。したがって、もち運びが容易で高い値がつくオオバタンは僻地山村から市場に出せる数少ない林産物のひとつとなっている。
とはいえM村住民にとってもっとも重要な収入源は、オウムではなく丁子(ちょうじ)(クローブ)だ。彼らは九月から一一月にかけて、南海岸に出稼ぎに出て、沿岸住民の農園で農業労働者として丁子(ちょうじ)の摘みとりをおこなう。収穫した丁子を山地民は農園保有者と折半した後、自分のもち分を集荷人に売っている。そうやってえた現金は、その後数ヵ月、場合によっては一年以上にわたり、彼らが塩や灯油など生活必需品を購入するために充てられる。丁子の出来は年によって大きく変動する。したがって、アコさんによると、丁子収入が芳(かんば)しくないときはオオバタンを捕獲して沿岸部の仲買人に売り、当座を凌(しの)ぐ現金をえるのだという。つまり、オオバタンは、丁子収入の補完的・代替的収入源のひとつなのだ。
貧者が獲り、富者が買(飼)う
アコさんたちが捕獲したオオバタンはいったいどこに運ばれてゆくのだろうか。一部は国内の野鳥マーケットに、そして一部はおそらく国外に密輸されている。日本は現在、シンガポールなどから年間一〇〇羽以上のオオバタンを輸入しており、その多くはブリーダーの繁殖個体だとされている。しかし、TRAFFIC(野性生物取引のモニタリングをおこなっている国際NGO)の調査によると、セラム島で捕獲された野生のオオバタンがメダン(スマトラ島)を経由してシンガポールなどに密輸されているという。したがって、日本に輸入されるオオバタンのなかに、そうした野生個体が含まれている可能性もないとはいえない。
そのようなことを考えながら、日本におけるオオバタン価格をインターネットで調べていて驚いた。某ペットショップで一羽七〇万円の売値がついていたからだ。山地民の売値は一羽七~一〇万ルピア(八〇〇~一二〇〇円)だから、その差はじつに五八三~八七五倍である!
わたしが見た山地民のオオバタン猟は、おおむね生活必需品の購入などで現金が必要になったときにおこなわれる「小規模かつ必要充足的な猟」であるといってよかった。しかし、日本でこんなにも高く売れることを知ったら、彼らのなかには次のように言い出す人がいるかもしれない。
「マサ、たくさん獲るから日本に運んで売ってくれ。一緒にひと儲けしよう!」
オオバタン (学名:Cacatua moluccensis)
体長46~52センチメートルの大型白色オウム。インドネシア東部セラム島とその周辺の島々にのみ生息する。堅果類、果実、昆虫などを食べる。ビヌアン(Octmeles sumatrana)などの大木の洞に営巣し、1年に1度1~2個の卵を生むといわれているが、繁殖生態はまだよくわかっていない。国際野鳥保護団体バードライフ・インターナショナルの『絶滅の恐れのあるアジアの鳥』によると、推定生息数は6万2400羽から19万5200羽。個体数は減少傾向にあるとされ、その原因として住民の捕獲が批判されてきた。しかし、近年の研究では、当初考えられていたよりも差し迫った絶滅の危機に瀕していないこと、低地で展開する木材伐採が住民の捕獲よりもより深刻な脅威となり得ること、などが指摘されている。
体長46~52センチメートルの大型白色オウム。インドネシア東部セラム島とその周辺の島々にのみ生息する。堅果類、果実、昆虫などを食べる。ビヌアン(Octmeles sumatrana)などの大木の洞に営巣し、1年に1度1~2個の卵を生むといわれているが、繁殖生態はまだよくわかっていない。国際野鳥保護団体バードライフ・インターナショナルの『絶滅の恐れのあるアジアの鳥』によると、推定生息数は6万2400羽から19万5200羽。個体数は減少傾向にあるとされ、その原因として住民の捕獲が批判されてきた。しかし、近年の研究では、当初考えられていたよりも差し迫った絶滅の危機に瀕していないこと、低地で展開する木材伐採が住民の捕獲よりもより深刻な脅威となり得ること、などが指摘されている。
ベトナム人流遺跡活用法
西村 昌也
李朝王妃の祖先墓は何処?
二〇〇一年の夏、北部ベトナムの平野部に位置するバックニン省で建設中の国道脇から磚室墓(せんしつぼ)が発見された。磚室墓とは、墓室をレンガで築いた墳墓のことである。磚室墓は中国系の古墓であるがため、緊急発掘されないことも多い。しかし、ここの場合は違った。ズオンロイ村のはずれに位置しており、李朝(一一~一三世紀初頭)王室の故郷として有名なディンバン村にも隣接していた。ズオンロイ村は、李朝初代王のお后の故郷という伝承があり、地元の古老を中心に、墓が王妃、あるいはその祖先の墓ではないかという話が広まった。緊急調査をおこなったハノイの考古学者が、調査初動時に李朝期という憶測の年代をそのまま口にしてしまい、マスコミの注目するところとなり、保存を希望する地元の意見が公にされた。調査が進み、磚室墓自体は李朝のものではなく、中国支配下の四~六世紀位のものだと判明したが、先に流れた年代観は修正できないまま一人歩き。結局、地元の保存案を受け入れなければ、国道建設は進められないまでに膠着(こうちゃく)し、最終的には墓を移設し、李朝王室のお后の祖先墓として上屋を建てて保存された。
じつはこの話には裏があって、磚室墓移設・保存にかこつけて国道建設側から、大きな資金獲得をもくろむ人びとがこの保存運動を利用していたようだ。
地面の下とのつながり
ベトナムで考古学調査をおこなって一〇年以上になるが、ときどき感じることは、ベトナム人(キン族)は、自分たちの生活空間が地面の下と直結しているととらえているのではないかということだ。
北部のナムディン省バッコック村で、村の歴史を探ろうとしていたときのことである。発掘開始に当たって、地霊や祖先に対してお供えをして、伺いを立ててからでないと、発掘はできないと土地所有者にしばしば言われてきた。もちろん田んぼや畑にしているところでは、ほとんどそのようなことはないのだが、代々家を建ててきたような屋敷地の場合、たとえそこに今屋敷がなくても、先祖に伺いを立てないといけないのだ。隣村のフーコックという村の場合、三〇〇年くらいしか人が住んだ歴史がなく、ベトナムの村のなかでは新しい方なのだけれど、古老のなかには、土地に代々の地霊が蓄積しているかのように話す人もいた。もちろん新しく開墾して住んでいる場合は、それほど気にしなくていいことのようだ。
歴史認識の再生産
次は、もっと積極的かつ肯定的な話である。ハノイ市郊外の観光地バッチャンは窯業で有名だが、南隣りにキムランという村がある。キムランは二五年ほど前から、バッチャンから窯業技術を移転し、農業から窯業へ転身を図っている。僕たちは、ここで考古学の調査と集落史の聞きとり調査をしている。もともと、古老たちが歴史研究グループを作って村の歴史を調べており、その活動を通じた啓蒙で、村人の過去への関心が高まってきていた。最初の発掘のとき、終了時に現地説明会を開いたが、「すまないね、外国人にこの村の歴史なんかを調べてもらって」と言いながら、おじいさんおばあさんが、菓子や果物を差し入れにもって来てくれた。なかには僕のポケットに小遣い銭をねじ込む人もいた。二度目の調査時には、寺の奉仕会のおばあさんグループが、わたしたちも発掘に参加するよと言って、炎天下の発掘にボランティアで参加してくれた。そして、去年の年始に発掘調査報告会を村役場の前でおこなったが、人口五〇〇〇人前後の村で聴衆が一〇〇〇人近くも集まった。みんなキムランの過去に関心が大ありなのだ。
発掘では、陳朝期(一三~一四世紀)を中心に高級施釉(せゆう)陶器を生産していたことが明らかとなり、出土したきれいな施釉陶器たちは、過去に自分たちの村も高級な陶磁器を作っていたんだという意識をもたらしたようだ。一方、北隣りのバッチャンの方は文献などから陶磁器生産が古くに遡ることは確実ながらも、考古学調査が進展しておらず、キムランのような物証がない。キムランの人の意識にはバッチャンよりこちらの方が、生産開始が古かったのではないかとか、こちらの方が陶磁器生産の本場だったのではないかという希望的憶測も生まれはじめた。
歴史研究グループの班長を努めるホン氏はさっそく出土した陶磁器類の複製をはじめた。特に美しい青磁の釉薬(うわぐすり)復元を目指して、試行錯誤を重ねているところだ。そして、役場や住民は、それまでさほど興味を示さなかった出土陶磁器片に興味をもち、それらをぜひ村で展示したいということになった。キムランの人は臨時展示室建設のために、お金を寄付し、市の文化局に出土品の移譲をお願いするまでに話が進み、出土陶磁器の一部は、キムランの管理となった。これから村の過去の栄光として、価値づけられるのだろう。
このように、地中からあらわれた遺跡や古物が、住民の郷土への意識に影響することはよくあるようだ。もちろん、人びとの歴史認識は学問的手続きをへず、過去の姿を現在に映して、見栄えの良いところだけから作られている。しかし、これもひとつの歴史である。もともと人間は歴史認識の再生産を積極的におこなってきたのだから。面白いのは、彼らの場合、地中の物証を自分たちの現在のために積極的に活用しているところだ。考古学者や文化財保護関係者顔負けである。
二〇〇一年の夏、北部ベトナムの平野部に位置するバックニン省で建設中の国道脇から磚室墓(せんしつぼ)が発見された。磚室墓とは、墓室をレンガで築いた墳墓のことである。磚室墓は中国系の古墓であるがため、緊急発掘されないことも多い。しかし、ここの場合は違った。ズオンロイ村のはずれに位置しており、李朝(一一~一三世紀初頭)王室の故郷として有名なディンバン村にも隣接していた。ズオンロイ村は、李朝初代王のお后の故郷という伝承があり、地元の古老を中心に、墓が王妃、あるいはその祖先の墓ではないかという話が広まった。緊急調査をおこなったハノイの考古学者が、調査初動時に李朝期という憶測の年代をそのまま口にしてしまい、マスコミの注目するところとなり、保存を希望する地元の意見が公にされた。調査が進み、磚室墓自体は李朝のものではなく、中国支配下の四~六世紀位のものだと判明したが、先に流れた年代観は修正できないまま一人歩き。結局、地元の保存案を受け入れなければ、国道建設は進められないまでに膠着(こうちゃく)し、最終的には墓を移設し、李朝王室のお后の祖先墓として上屋を建てて保存された。
じつはこの話には裏があって、磚室墓移設・保存にかこつけて国道建設側から、大きな資金獲得をもくろむ人びとがこの保存運動を利用していたようだ。
地面の下とのつながり
ベトナムで考古学調査をおこなって一〇年以上になるが、ときどき感じることは、ベトナム人(キン族)は、自分たちの生活空間が地面の下と直結しているととらえているのではないかということだ。
北部のナムディン省バッコック村で、村の歴史を探ろうとしていたときのことである。発掘開始に当たって、地霊や祖先に対してお供えをして、伺いを立ててからでないと、発掘はできないと土地所有者にしばしば言われてきた。もちろん田んぼや畑にしているところでは、ほとんどそのようなことはないのだが、代々家を建ててきたような屋敷地の場合、たとえそこに今屋敷がなくても、先祖に伺いを立てないといけないのだ。隣村のフーコックという村の場合、三〇〇年くらいしか人が住んだ歴史がなく、ベトナムの村のなかでは新しい方なのだけれど、古老のなかには、土地に代々の地霊が蓄積しているかのように話す人もいた。もちろん新しく開墾して住んでいる場合は、それほど気にしなくていいことのようだ。
歴史認識の再生産
次は、もっと積極的かつ肯定的な話である。ハノイ市郊外の観光地バッチャンは窯業で有名だが、南隣りにキムランという村がある。キムランは二五年ほど前から、バッチャンから窯業技術を移転し、農業から窯業へ転身を図っている。僕たちは、ここで考古学の調査と集落史の聞きとり調査をしている。もともと、古老たちが歴史研究グループを作って村の歴史を調べており、その活動を通じた啓蒙で、村人の過去への関心が高まってきていた。最初の発掘のとき、終了時に現地説明会を開いたが、「すまないね、外国人にこの村の歴史なんかを調べてもらって」と言いながら、おじいさんおばあさんが、菓子や果物を差し入れにもって来てくれた。なかには僕のポケットに小遣い銭をねじ込む人もいた。二度目の調査時には、寺の奉仕会のおばあさんグループが、わたしたちも発掘に参加するよと言って、炎天下の発掘にボランティアで参加してくれた。そして、去年の年始に発掘調査報告会を村役場の前でおこなったが、人口五〇〇〇人前後の村で聴衆が一〇〇〇人近くも集まった。みんなキムランの過去に関心が大ありなのだ。
発掘では、陳朝期(一三~一四世紀)を中心に高級施釉(せゆう)陶器を生産していたことが明らかとなり、出土したきれいな施釉陶器たちは、過去に自分たちの村も高級な陶磁器を作っていたんだという意識をもたらしたようだ。一方、北隣りのバッチャンの方は文献などから陶磁器生産が古くに遡ることは確実ながらも、考古学調査が進展しておらず、キムランのような物証がない。キムランの人の意識にはバッチャンよりこちらの方が、生産開始が古かったのではないかとか、こちらの方が陶磁器生産の本場だったのではないかという希望的憶測も生まれはじめた。
歴史研究グループの班長を努めるホン氏はさっそく出土した陶磁器類の複製をはじめた。特に美しい青磁の釉薬(うわぐすり)復元を目指して、試行錯誤を重ねているところだ。そして、役場や住民は、それまでさほど興味を示さなかった出土陶磁器片に興味をもち、それらをぜひ村で展示したいということになった。キムランの人は臨時展示室建設のために、お金を寄付し、市の文化局に出土品の移譲をお願いするまでに話が進み、出土陶磁器の一部は、キムランの管理となった。これから村の過去の栄光として、価値づけられるのだろう。
このように、地中からあらわれた遺跡や古物が、住民の郷土への意識に影響することはよくあるようだ。もちろん、人びとの歴史認識は学問的手続きをへず、過去の姿を現在に映して、見栄えの良いところだけから作られている。しかし、これもひとつの歴史である。もともと人間は歴史認識の再生産を積極的におこなってきたのだから。面白いのは、彼らの場合、地中の物証を自分たちの現在のために積極的に活用しているところだ。考古学者や文化財保護関係者顔負けである。
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。