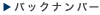月刊みんぱく 2007年4月号
2007年4月号
第31巻第4号通巻第355号
2007年4月1日発行
2007年4月1日発行
アフリカで「間」を考える
小原 秀雄
わたしの行きつけの店ならぬ「ロッジ」が、ケニヤのヴォイ・サファリロッジである。二〇年近く毎年、半月から一ヵ月、滞在している。大きな岩などを利用し、水場などを設定して人間界との「間」の働きでサバンナの野生動物界が見渡せるからだ。東部から南部まで方々のアフリカの野生動物界を訪れたが、小高い丘にあるこのロッジは、大はアフリカゾウから小はコビトマングースまで、肉眼でさまざまな種の行動や生態が一望できる。
人間界と基本的にすみわけて、「間」を作っている野生動物とちがい、ヒヒとハイラックスの二種の動物だけは、このロッジで人間と独特の間柄である。それを見ながら、わたしは最近「間」についていろいろと考えている。
ハイラックスはもともとロッジの建った岩山に住んでいた。建物ができても、それを岩とみなしてか、すき間などに入り込み、適応した。小型なのが幸いし、生活空間を別にしたのである。ヒヒは夜間、岩山の木々を眠り場にするなどしていたが、行動能力が高く、今は人間との「間」を巧みに調整している。観光客の側も餌を与え、馴化(じゅんか)しかけている。部屋に入り込んで食べ物を奪うなど、人間との「間」に安定した調整ができていないままである。動物が食物獲得に適応するのは一般に驚くほど速やかであるが、人間の側の問題も多くトラブルは絶えない。安定するまで時間がかかる。人間の側に広い空間があり、時間をかければ動物は習得する。それが日本のように人間界が野生動物界と接しているところは、クマの事例のように新しい「間」を設ける必要を示している。野生動物が安心できる空間が充分ある地が、今まだアフリカの一部にはある。
「間」については五〇年余り前に、スイスの動物学者ヘディガーが「臨界空間」の概念を提起した。詳細は省くが、動物が逃走や反撃行動をするのに、「間」をとる距離で、各種動物や個体の生得的調整能力であろうか。
一方、飼育される愛玩動物や飼育動物は、人間中心の「間」に適応していく。野生動物の方は、殺されたりしながらも、ときとともに人間との「間」のとり方ができるかが心配である。現代の動物行動学にはヘディガーの遺産は生かされるのだろうか。
唐突かも知れないが、新しい知が現代の自然科学や社会・人文科学の総合再構成に必要なことを考えさせられている。生きている動物や人間のあり方、それらを知るうえでも現代の学問や認識の間に溝やすき間があるように思えてならない。
おばら ひでお/1927年東京生まれ。女子栄養大学名誉教授、(財)日本自然環境保護協会元理事長・現在顧問、野生生物保全論研究会(JWCS)会長、共生社会システム学会会長ほか。主著に『レッド・データ・アニマルズ(共編全9巻)』(講談社)『現代ホモ・サピエンスの変貌』(朝日新聞社)『人類は絶滅を選択するのか』(明石書店)など多数。
人間界と基本的にすみわけて、「間」を作っている野生動物とちがい、ヒヒとハイラックスの二種の動物だけは、このロッジで人間と独特の間柄である。それを見ながら、わたしは最近「間」についていろいろと考えている。
ハイラックスはもともとロッジの建った岩山に住んでいた。建物ができても、それを岩とみなしてか、すき間などに入り込み、適応した。小型なのが幸いし、生活空間を別にしたのである。ヒヒは夜間、岩山の木々を眠り場にするなどしていたが、行動能力が高く、今は人間との「間」を巧みに調整している。観光客の側も餌を与え、馴化(じゅんか)しかけている。部屋に入り込んで食べ物を奪うなど、人間との「間」に安定した調整ができていないままである。動物が食物獲得に適応するのは一般に驚くほど速やかであるが、人間の側の問題も多くトラブルは絶えない。安定するまで時間がかかる。人間の側に広い空間があり、時間をかければ動物は習得する。それが日本のように人間界が野生動物界と接しているところは、クマの事例のように新しい「間」を設ける必要を示している。野生動物が安心できる空間が充分ある地が、今まだアフリカの一部にはある。
「間」については五〇年余り前に、スイスの動物学者ヘディガーが「臨界空間」の概念を提起した。詳細は省くが、動物が逃走や反撃行動をするのに、「間」をとる距離で、各種動物や個体の生得的調整能力であろうか。
一方、飼育される愛玩動物や飼育動物は、人間中心の「間」に適応していく。野生動物の方は、殺されたりしながらも、ときとともに人間との「間」のとり方ができるかが心配である。現代の動物行動学にはヘディガーの遺産は生かされるのだろうか。
唐突かも知れないが、新しい知が現代の自然科学や社会・人文科学の総合再構成に必要なことを考えさせられている。生きている動物や人間のあり方、それらを知るうえでも現代の学問や認識の間に溝やすき間があるように思えてならない。
おばら ひでお/1927年東京生まれ。女子栄養大学名誉教授、(財)日本自然環境保護協会元理事長・現在顧問、野生生物保全論研究会(JWCS)会長、共生社会システム学会会長ほか。主著に『レッド・データ・アニマルズ(共編全9巻)』(講談社)『現代ホモ・サピエンスの変貌』(朝日新聞社)『人類は絶滅を選択するのか』(明石書店)など多数。
環境破壊が深刻化する今、森林も減少の危機にさらされている。人は森に多くの恩恵を求め、そのかかわり方もさまざまである。特集では、人と森がどのような関係を作ってきたのか、これからどう共存していくべきかを考える
森と人
恐怖も与える空間
「森林浴」ということばがあるように、森には人の心と体をリフレッシュさせる働きがある。特に都会で仕事や人間関係に疲れ果てている人には効果が大きい。森の緑は目に優しく、鳥の声や川のせせらぎを聞いていると、自然と心が落ち着く。森のなかに開けた日だまりのなかに座っていると、ついうとうととしたくなる。
しかし、森にしばらくいると、何か落ち着かなくなるようなことはないだろうか。都会のなかの小さな公園の森などではありえないが、どこまで歩いても車の音はおろか、人の話し声も、ときには鳥の声すら聞こえなくなるような場所に入ったとき、何か背筋が寒くなるような感じを覚えたことはないだろうか。この先に進んでいいものかどうか、あるいは同じ道を引き返して、きちんと元の場所に戻れるのかどうか心配になったような経験はないだろうか。
それは未知の場所に対する不安からくるものであるが、その不安感、あるいは恐怖感はそれだけで生ずるわけではない。森に生まれ、その森を子どものころから歩いてすみずみまで知り尽くしているはずの猟師ですら、森に対して畏怖あるいは恐怖を覚えることがあるという。森は人びとに資源や安らぎを与えるだけでなく、恐ろしいものも含めてさまざまな想像力も喚起するのである。
わたしが近年しばしば訪れている極東ロシアの先住民族であるウデヘやナーナイの猟師たちも、森ではたびたび恐ろしい経験をしている。それはトラやクマと直面するという現実的な恐怖だけではなく、精神的あるいは霊的な恐怖である。例えば、猟に出て森で野営すると夜に不審な物音を耳にする。あるいは、急に寒気や髪の毛が逆立つような感覚に襲われたり、悪夢にうなされたりする。そのようなときには必ず何らかの悪霊が彼らに接触しているという。他方、森には悪意をもった霊だけでなく、適切に対応すれば人びとを助けてくれる霊もいる。ビキン川のウデヘたちは猟運を支配するラオバトゥを信じて、狩りの前には必ずウォッカを捧げ、丸木船を作るために木を切り倒すと、木の霊に対する謝罪と感謝の気持ちをもって、切り株の上に小枝を立てる。
森との共存共栄
森をよく知る人ほどそのなかに霊的なものを感じる。しかし、猟師たちはそのような霊たちとの緊張関係を楽しんでいる風でもある。彼らは森の楽しさと恐ろしさのバランスの上に立って、その資源を使わせてもらっているのである。
材木を切り出すために木をすべてなぎ倒して森を破壊したり、あるいは逆に森を有効に使わずに放置したりするのは、人が森との関係を見失ったからである。あるいは森の霊たちの存在を見失ったからである。いま、日本では人間が森に対抗する力を失いつつある。クマやシカ、サルなどが人里にあらわれて被害をもたらすのは、森が人間世界に迫っていることを意味する。しかし、森との関係を見失った人間たちの世界に森が入り込めば、双方とも無用の傷を負うことになりかねない。それを防ぐためには、科学技術で森を支配しようとするのではなく、伝統と経験に培われた猟師や林業関係者の知識を活かして、人と森が共存共栄できる状態に戻る必要がある。
「森林浴」ということばがあるように、森には人の心と体をリフレッシュさせる働きがある。特に都会で仕事や人間関係に疲れ果てている人には効果が大きい。森の緑は目に優しく、鳥の声や川のせせらぎを聞いていると、自然と心が落ち着く。森のなかに開けた日だまりのなかに座っていると、ついうとうととしたくなる。
しかし、森にしばらくいると、何か落ち着かなくなるようなことはないだろうか。都会のなかの小さな公園の森などではありえないが、どこまで歩いても車の音はおろか、人の話し声も、ときには鳥の声すら聞こえなくなるような場所に入ったとき、何か背筋が寒くなるような感じを覚えたことはないだろうか。この先に進んでいいものかどうか、あるいは同じ道を引き返して、きちんと元の場所に戻れるのかどうか心配になったような経験はないだろうか。
それは未知の場所に対する不安からくるものであるが、その不安感、あるいは恐怖感はそれだけで生ずるわけではない。森に生まれ、その森を子どものころから歩いてすみずみまで知り尽くしているはずの猟師ですら、森に対して畏怖あるいは恐怖を覚えることがあるという。森は人びとに資源や安らぎを与えるだけでなく、恐ろしいものも含めてさまざまな想像力も喚起するのである。
わたしが近年しばしば訪れている極東ロシアの先住民族であるウデヘやナーナイの猟師たちも、森ではたびたび恐ろしい経験をしている。それはトラやクマと直面するという現実的な恐怖だけではなく、精神的あるいは霊的な恐怖である。例えば、猟に出て森で野営すると夜に不審な物音を耳にする。あるいは、急に寒気や髪の毛が逆立つような感覚に襲われたり、悪夢にうなされたりする。そのようなときには必ず何らかの悪霊が彼らに接触しているという。他方、森には悪意をもった霊だけでなく、適切に対応すれば人びとを助けてくれる霊もいる。ビキン川のウデヘたちは猟運を支配するラオバトゥを信じて、狩りの前には必ずウォッカを捧げ、丸木船を作るために木を切り倒すと、木の霊に対する謝罪と感謝の気持ちをもって、切り株の上に小枝を立てる。
森との共存共栄
森をよく知る人ほどそのなかに霊的なものを感じる。しかし、猟師たちはそのような霊たちとの緊張関係を楽しんでいる風でもある。彼らは森の楽しさと恐ろしさのバランスの上に立って、その資源を使わせてもらっているのである。
材木を切り出すために木をすべてなぎ倒して森を破壊したり、あるいは逆に森を有効に使わずに放置したりするのは、人が森との関係を見失ったからである。あるいは森の霊たちの存在を見失ったからである。いま、日本では人間が森に対抗する力を失いつつある。クマやシカ、サルなどが人里にあらわれて被害をもたらすのは、森が人間世界に迫っていることを意味する。しかし、森との関係を見失った人間たちの世界に森が入り込めば、双方とも無用の傷を負うことになりかねない。それを防ぐためには、科学技術で森を支配しようとするのではなく、伝統と経験に培われた猟師や林業関係者の知識を活かして、人と森が共存共栄できる状態に戻る必要がある。
日本の森世界
山田 勇(やまだ いさむ) 京都大学名誉教授
心の安らぎの源
「日本の森は、こじんまりしているが、存在感がある」という想いがこのところ徐々にふくらんできている。
若いころの金閣寺の裏山を皮切りに世界の森を見るかたわら、日本の森も北山から北アルプスにはじまり、南は西表のマングローブ、屋久島の屋久杉、宮崎の綾の森、魚梁瀬(やなせ)の千本杉、大山のブナ、京都の北山スギ、白山のブナ、赤沢のヒノキ、東北のブナや秋田杉やヒバ、そして、北限の歌才のブナや、北海道の針葉樹林帯ほか、名もない森も多く見てきた。そこには、たとえば北米太平洋岸の巨大林や、アマゾンの熱帯林のように無限に広がる大きさはないが、どこかしっかりとととのった美しさを感じさせるものがある。日本の森には、何か人の心を落ち着かせる雰囲気が、ある限られた空間のなかにただよっていると想う。
それは、ヨーロッパの古都の歴史地区に入ったときの気持ちにも通ずる。クラコフ、ハイデンベルク、チェスケークルムコフ、パレルモ、ピサなど、ヨーロッパには無数といっていいほどの美しい小さな都市が点在する。そのひとつひとつに足を踏み入れ、石畳の道を歩みつつ、まわりの古い民家や城を見上げるときの気持ちは、ちょうど、日本の森を歩いてブナや杉、ヒノキをながめるときに感じる心の安らぎと同じである。
そこに共通するものは歴史の重さである。人は、長い歴史の前には謙虚にならざるをえない。都市には人間の歴史がきざまれ、森にはより長い生命複合体の歴史がある。一本一本の木の寿命は短いようだが、それでも、人間の数倍から数十倍の年月を生きている。そして、単に一個体だけではなく、森というひとつの共同体のなかに無数の生命がやどっているのである。それは古い歴史都市のなかで生きてきた人びとの生活と同じである。どちらも、内に長いさまざまな生命体の生活史が隠されているのである。
人類の未来を示唆
日本を含め、今世界は大きな曲がり角にさしかかっている。これからの世界をどう考えていけばいいのか、これは今を生きる我々に課された大きな問題である。森の重要性が叫ばれた一九八〇年代から、今はどちらをむいても戦争や内戦、難民などの話題が優占している。こういうときにこそ、森のなかへ入り、じっくりと未来を考えなければならない。森のあらたな役割は豊かな生命のいとなみによって、これからの人類の生きるべき方向を示唆してくれることではないだろうか。そのために手近に格好の場を日本の森は提供してくれている。
「日本の森は、こじんまりしているが、存在感がある」という想いがこのところ徐々にふくらんできている。
若いころの金閣寺の裏山を皮切りに世界の森を見るかたわら、日本の森も北山から北アルプスにはじまり、南は西表のマングローブ、屋久島の屋久杉、宮崎の綾の森、魚梁瀬(やなせ)の千本杉、大山のブナ、京都の北山スギ、白山のブナ、赤沢のヒノキ、東北のブナや秋田杉やヒバ、そして、北限の歌才のブナや、北海道の針葉樹林帯ほか、名もない森も多く見てきた。そこには、たとえば北米太平洋岸の巨大林や、アマゾンの熱帯林のように無限に広がる大きさはないが、どこかしっかりとととのった美しさを感じさせるものがある。日本の森には、何か人の心を落ち着かせる雰囲気が、ある限られた空間のなかにただよっていると想う。
それは、ヨーロッパの古都の歴史地区に入ったときの気持ちにも通ずる。クラコフ、ハイデンベルク、チェスケークルムコフ、パレルモ、ピサなど、ヨーロッパには無数といっていいほどの美しい小さな都市が点在する。そのひとつひとつに足を踏み入れ、石畳の道を歩みつつ、まわりの古い民家や城を見上げるときの気持ちは、ちょうど、日本の森を歩いてブナや杉、ヒノキをながめるときに感じる心の安らぎと同じである。
そこに共通するものは歴史の重さである。人は、長い歴史の前には謙虚にならざるをえない。都市には人間の歴史がきざまれ、森にはより長い生命複合体の歴史がある。一本一本の木の寿命は短いようだが、それでも、人間の数倍から数十倍の年月を生きている。そして、単に一個体だけではなく、森というひとつの共同体のなかに無数の生命がやどっているのである。それは古い歴史都市のなかで生きてきた人びとの生活と同じである。どちらも、内に長いさまざまな生命体の生活史が隠されているのである。
人類の未来を示唆
日本を含め、今世界は大きな曲がり角にさしかかっている。これからの世界をどう考えていけばいいのか、これは今を生きる我々に課された大きな問題である。森の重要性が叫ばれた一九八〇年代から、今はどちらをむいても戦争や内戦、難民などの話題が優占している。こういうときにこそ、森のなかへ入り、じっくりと未来を考えなければならない。森のあらたな役割は豊かな生命のいとなみによって、これからの人類の生きるべき方向を示唆してくれることではないだろうか。そのために手近に格好の場を日本の森は提供してくれている。
森と文明
安田 喜憲(やすだ よしのり) 国際日本文化研究センター教授
森と文明との関係
文明には森を破壊しつくした文明と森を守る文明がある。その森と文明の関係の相違は、人間が何を食べるかによって生まれた。とりわけタンパク質として何を摂取するかによって森と文明の関係は大きく異なるものとなった。端的に言えば肉を食べるか魚を食べるかによって、森と文明の関係は根本的に相違する道をえらんだのである。肉を食べミルクを飲んでバターやチーズを食べる畑作牧畜民の人びとは、森を徹底的に破壊する文明を創造した。畑作牧畜民が森を嫌いだったわけではない。森を破壊したのはタンパク源となったヒツジやヤギたちである。ヒツジやヤギは人間が寝ている夜のあいだにも草木を食べ尽くす。こうして、肥沃な三日月地帯は現在では一木一草もない荒野に変わってしまった。
これに対し、魚を食べる稲作漁撈民は森と水の循環系を守った。魚は川に水が流れていなければ生きられない。川に水を確保するためには、森を守らなければならない。こうして稲作漁撈民はタンパク質を魚に求めたことによって、森と水の循環系を守ることになったのである。
持続性の高い循環型
これまで我々は、森を破壊し尽くした畑作牧畜民の文明のみを文明と定義してきた。メソポタミア、エジプト、インダス、黄河の四大文明はまさにパンを食べ、ミルクを飲み、肉を食べる畑作牧畜民が作り出した文明である。そしてその畑作牧畜民の文明が繁栄した後は、森のない荒野に変わり果てた。それは何も古代だけではない、ヨーロッパは畑作牧畜民の大開墾によって七〇パーセント近い森が一七世紀の段階で破壊されていたし、一六ニ〇年にアメリカにヒツジを連れた畑作牧畜民が移住してから、たった三〇〇年でアメリカの森の八〇パーセントが破壊されたのである。
これに対し、稲作漁撈民はこれまで文明をもたなかったとみなされてきた。ところが、近年の長江文明の発見によって、稲作漁撈民も立派な文明をもっていたことがあきらかとなった。その長江文明はミルクの香りのしない文明であった。森と水の循環系を持続的に維持した文明である。六〇〇〇年前の中国湖南省城頭山遺跡は、今でも豊かな水の大地が維持されている。それは不毛の荒野に変わってしまったメソポタミアの大地とは大きく相違している。稲作漁撈民はきわめて持続性の高い地球にやさしい循環型の文明を発展させてきたのである。
文明には森を破壊しつくした文明と森を守る文明がある。その森と文明の関係の相違は、人間が何を食べるかによって生まれた。とりわけタンパク質として何を摂取するかによって森と文明の関係は大きく異なるものとなった。端的に言えば肉を食べるか魚を食べるかによって、森と文明の関係は根本的に相違する道をえらんだのである。肉を食べミルクを飲んでバターやチーズを食べる畑作牧畜民の人びとは、森を徹底的に破壊する文明を創造した。畑作牧畜民が森を嫌いだったわけではない。森を破壊したのはタンパク源となったヒツジやヤギたちである。ヒツジやヤギは人間が寝ている夜のあいだにも草木を食べ尽くす。こうして、肥沃な三日月地帯は現在では一木一草もない荒野に変わってしまった。
これに対し、魚を食べる稲作漁撈民は森と水の循環系を守った。魚は川に水が流れていなければ生きられない。川に水を確保するためには、森を守らなければならない。こうして稲作漁撈民はタンパク質を魚に求めたことによって、森と水の循環系を守ることになったのである。
持続性の高い循環型
これまで我々は、森を破壊し尽くした畑作牧畜民の文明のみを文明と定義してきた。メソポタミア、エジプト、インダス、黄河の四大文明はまさにパンを食べ、ミルクを飲み、肉を食べる畑作牧畜民が作り出した文明である。そしてその畑作牧畜民の文明が繁栄した後は、森のない荒野に変わり果てた。それは何も古代だけではない、ヨーロッパは畑作牧畜民の大開墾によって七〇パーセント近い森が一七世紀の段階で破壊されていたし、一六ニ〇年にアメリカにヒツジを連れた畑作牧畜民が移住してから、たった三〇〇年でアメリカの森の八〇パーセントが破壊されたのである。
これに対し、稲作漁撈民はこれまで文明をもたなかったとみなされてきた。ところが、近年の長江文明の発見によって、稲作漁撈民も立派な文明をもっていたことがあきらかとなった。その長江文明はミルクの香りのしない文明であった。森と水の循環系を持続的に維持した文明である。六〇〇〇年前の中国湖南省城頭山遺跡は、今でも豊かな水の大地が維持されている。それは不毛の荒野に変わってしまったメソポタミアの大地とは大きく相違している。稲作漁撈民はきわめて持続性の高い地球にやさしい循環型の文明を発展させてきたのである。
フィンランドの森
木の文化
飛行機からながめたフィンランドの田舎の遠景は一面の緑である。やがて、その濃淡や水面のかがやきから、さまざまな植生の森や耕地、湖や河川が見わけられるようになり、やっと道路や湖岸にそって点在する家屋がすがたをあらわしてくる。
国土の六八パーセントが森林といわれる。日本も森林面積がほとんど同値であるのは興味深いが、世界的にも突出した値のようである。しかし、森林と山がほとんど同義で、宅地や耕地に使えない山が森として残ったような日本にくらべ、フィンランドの森林は平坦な大地に果てしなく広がる。日本にわずか足りぬ面積に人口が五二〇万人程度のフィンランドでは、南部をのぞき、人びとが広大な森林の端にしがみついて生きているという印象をもっても不思議ではない。事実、フィンランドの人びとの生活にとって森林はなくてはならないものであった。
しばしばフィンランドの文化は木の文化とよばれる。伝統的な家屋である丸太で組んだログハウスをはじめ、家具から食器までが木製であったのは驚くには値しないが、日本なら竹や藁(わら)で作るような、靴や繊細な籠(かご)、曲げ物が白樺の樹皮(樺皮)細工として発達したのは興味深い。針葉樹である赤松やトウヒがフィンランドの寒帯樹林を支配してきたのに対し、白樺林は家屋や耕地の周囲に二次林として勝手に育つ雑草のような存在であった。樺皮の採集はもちろん、長い冬のあいだ暖を提供し、料理のための燃料となったのは大量の白樺であった。白樺の樹液は甘い飲料となり、若枝を束ねて作るバスタでほてった肌をたたくのはサウナには欠かせない習慣である。ちなみに、近年歯を守る甘味料としてガムなどに用いられているキシリトールも白樺を原料としている。
森林は意外なことに穀物の栽培にも用いられた。一九世紀末まで東フィンランドに残っていた針葉樹林の焼畑である。針葉樹林のふんだんにあった近世、数十年の周期でおこなわれた焼畑は大量の収穫をのぞめる手段として全国に広がった。やがて生産性の低下と森林の荒廃をもたらし、禁止されることになったが、白樺林はそれとともに拡大したともいわれている。
万人の権利
現在、焼畑はいうにおよばず、樺皮にも燃料としても一般のフィンランド人には大して用いられなくなった森林だが、人びとのつながりは決して弱まってはいない。夏から秋口にかけて森林でのベリー摘みやキノコの採集は、レクリエーションをかねた大きな楽しみだし、ベリーはジャムやジュース、キノコは乾燥物や塩漬け食品として結構家計もおぎなっている。フィンランドには国有林であれ私有林であれ、通行やべリーなどの採集の権利は認める万人の権利というのが慣習法としてあった。これは今、成文法としても存在する。彼らのこころの拠り所としての森林の重要性が法律でも認められているということになろう。
飛行機からながめたフィンランドの田舎の遠景は一面の緑である。やがて、その濃淡や水面のかがやきから、さまざまな植生の森や耕地、湖や河川が見わけられるようになり、やっと道路や湖岸にそって点在する家屋がすがたをあらわしてくる。
国土の六八パーセントが森林といわれる。日本も森林面積がほとんど同値であるのは興味深いが、世界的にも突出した値のようである。しかし、森林と山がほとんど同義で、宅地や耕地に使えない山が森として残ったような日本にくらべ、フィンランドの森林は平坦な大地に果てしなく広がる。日本にわずか足りぬ面積に人口が五二〇万人程度のフィンランドでは、南部をのぞき、人びとが広大な森林の端にしがみついて生きているという印象をもっても不思議ではない。事実、フィンランドの人びとの生活にとって森林はなくてはならないものであった。
しばしばフィンランドの文化は木の文化とよばれる。伝統的な家屋である丸太で組んだログハウスをはじめ、家具から食器までが木製であったのは驚くには値しないが、日本なら竹や藁(わら)で作るような、靴や繊細な籠(かご)、曲げ物が白樺の樹皮(樺皮)細工として発達したのは興味深い。針葉樹である赤松やトウヒがフィンランドの寒帯樹林を支配してきたのに対し、白樺林は家屋や耕地の周囲に二次林として勝手に育つ雑草のような存在であった。樺皮の採集はもちろん、長い冬のあいだ暖を提供し、料理のための燃料となったのは大量の白樺であった。白樺の樹液は甘い飲料となり、若枝を束ねて作るバスタでほてった肌をたたくのはサウナには欠かせない習慣である。ちなみに、近年歯を守る甘味料としてガムなどに用いられているキシリトールも白樺を原料としている。
森林は意外なことに穀物の栽培にも用いられた。一九世紀末まで東フィンランドに残っていた針葉樹林の焼畑である。針葉樹林のふんだんにあった近世、数十年の周期でおこなわれた焼畑は大量の収穫をのぞめる手段として全国に広がった。やがて生産性の低下と森林の荒廃をもたらし、禁止されることになったが、白樺林はそれとともに拡大したともいわれている。
万人の権利
現在、焼畑はいうにおよばず、樺皮にも燃料としても一般のフィンランド人には大して用いられなくなった森林だが、人びとのつながりは決して弱まってはいない。夏から秋口にかけて森林でのベリー摘みやキノコの採集は、レクリエーションをかねた大きな楽しみだし、ベリーはジャムやジュース、キノコは乾燥物や塩漬け食品として結構家計もおぎなっている。フィンランドには国有林であれ私有林であれ、通行やべリーなどの採集の権利は認める万人の権利というのが慣習法としてあった。これは今、成文法としても存在する。彼らのこころの拠り所としての森林の重要性が法律でも認められているということになろう。
コンゴの森の民
市川 光雄(いちかわ みつお) 京都大学アジア・アフリカ地域研究科教授
生活を脅かす森林破壊
毎年、数百万ヘクタールの熱帯雨林を商業的伐採によって失っている中央アフリカでは、節度ある森林の利用と管理のために「森林法」の改訂が進んでいる。一九九四年にはカメルーンで「狩猟法」を含む「森林法」が改訂され、また二〇〇ニ年にはコンゴ民主共和国がFAO(国連食糧農業機関)等の援助により新しい「森林法」を制定した。改訂された森林法で謳(うた)われているのは、自然保護と持続的な伐採のための森林管理の義務化と伐採権収入の地方への配分、そして森林に対する慣習的な利用権の保全などであるが、この森で長年生活してきた住民にとってとりわけ重要なのが最後の問題である。
森は彼らの食物、とくにタンパク源となる野生獣肉を供給してきた。また、病気や怪我の治療にはもっぱら森の植物の樹皮や根、葉などが薬として用いられてきた。毎日の燃料や建材のほか、ほとんどの物質文化の素材は森でえたものである。さらに、学校教育や近代医療へのアクセス、税金や罰金、そして結婚や葬式などの社会的義務に伴う支払いにあてる現金も、獣肉や蜂蜜その他の森の産物の販売収入に依存している。コンゴ民主共和国でのおおよその試算によると、このようにして利用される非木材森林資源の市場価値は年間およそ数十億ドルに達するが、一方、伐採による収入はせいぜい毎年一億五〇〇〇万ドルほどで、しかもそのほとんどはごく一部の人間の手に集中し、森の民がその恩恵をこうむることはほとんどない。逆に、国から伐採権をえた事業者が森林への入域料を要求する例さえあり、伐採事業は森の民をさらに周縁化しているように見える。加えて最近では、砂金やコルタン(携帯電話等に使われる半導体)の採掘のために森の外から人口流入が続き、森林破壊に拍車がかけられている。
権利を求め団結するピグミー
このような状況のなかで最近、「ピグミー」とよばれてきた森の民が、コンゴの森の「先住民」として名乗りを上げ、自分たちの権利を求めて立ち上がった。これまでは各地の森のなかで、狩猟と採集に依存しながら小さな居住単位にわかれて暮らしていた人びとが、共通のアイデンティティと権利の確立のために団結し、より大きな社会集団として行動を起こしたのである。第II期国際先住民年の追い風をうけたこの運動が成功するかは、国際社会の支援と現地政府の理解にかかっている。
毎年、数百万ヘクタールの熱帯雨林を商業的伐採によって失っている中央アフリカでは、節度ある森林の利用と管理のために「森林法」の改訂が進んでいる。一九九四年にはカメルーンで「狩猟法」を含む「森林法」が改訂され、また二〇〇ニ年にはコンゴ民主共和国がFAO(国連食糧農業機関)等の援助により新しい「森林法」を制定した。改訂された森林法で謳(うた)われているのは、自然保護と持続的な伐採のための森林管理の義務化と伐採権収入の地方への配分、そして森林に対する慣習的な利用権の保全などであるが、この森で長年生活してきた住民にとってとりわけ重要なのが最後の問題である。
森は彼らの食物、とくにタンパク源となる野生獣肉を供給してきた。また、病気や怪我の治療にはもっぱら森の植物の樹皮や根、葉などが薬として用いられてきた。毎日の燃料や建材のほか、ほとんどの物質文化の素材は森でえたものである。さらに、学校教育や近代医療へのアクセス、税金や罰金、そして結婚や葬式などの社会的義務に伴う支払いにあてる現金も、獣肉や蜂蜜その他の森の産物の販売収入に依存している。コンゴ民主共和国でのおおよその試算によると、このようにして利用される非木材森林資源の市場価値は年間およそ数十億ドルに達するが、一方、伐採による収入はせいぜい毎年一億五〇〇〇万ドルほどで、しかもそのほとんどはごく一部の人間の手に集中し、森の民がその恩恵をこうむることはほとんどない。逆に、国から伐採権をえた事業者が森林への入域料を要求する例さえあり、伐採事業は森の民をさらに周縁化しているように見える。加えて最近では、砂金やコルタン(携帯電話等に使われる半導体)の採掘のために森の外から人口流入が続き、森林破壊に拍車がかけられている。
権利を求め団結するピグミー
このような状況のなかで最近、「ピグミー」とよばれてきた森の民が、コンゴの森の「先住民」として名乗りを上げ、自分たちの権利を求めて立ち上がった。これまでは各地の森のなかで、狩猟と採集に依存しながら小さな居住単位にわかれて暮らしていた人びとが、共通のアイデンティティと権利の確立のために団結し、より大きな社会集団として行動を起こしたのである。第II期国際先住民年の追い風をうけたこの運動が成功するかは、国際社会の支援と現地政府の理解にかかっている。
主張する美術作品
常設展示場オセアニア展示のオーストラリア・アボリジニのコーナーに、「先住権試合」という画題の油絵が展示されている。ノーザンテリトリ美術博物館が一九八四年以来毎年開催し、今ではオーストラリアで権威のある芸術賞のひとつ、「アボリジニとトレス海峡諸島民芸術賞」にニ〇〇〇年入選した、アボリジニ作家ゴードン・ホッケイ氏の作品である。オーストラリア白人政府の圧政、植民地主義、複数国家による土地収奪などに対するアボリジニの抵抗をあらわすさまざまなシンボルが散りばめられた絵画で、カンガルーがアボリジニを、ブタが白人政府と多国籍企業をあらわす、というかなり強烈な図柄だ。この絵画を購入したのは、先住民の現状や運動を説明するのに適切と考えたからだ。逆に言えば、先住民の主張がストレートに描かれた絵画はわかりやすい、ということがある。
アボリジニ資料については、すでに一九八〇年代初めから、美術工芸運動と文化表象運動の高まりを示す資料として、美的価値で選ぶのではなく全体を集めるという方針で絵画や彫刻が収集されてきた。民博の従来の収集方針、すなわち標本資料は、ほぼ現在の時点で普通の人びとが生産・生活・製作・宗教儀礼に用いる用具類を対象とし、偽物か本物かが重大な問題となるもの、美術、骨董的価値のあるものは、原則対象としない、宝物に主眼を置かない、という方針からは逸脱しない、と考えられたからである。
しかし近年の民博では、特別展に合わせた大型コレクションとともに、美術作品の収集が多くなっている。その理由のひとつは、生活様式のグローバル化が進み、生活用具には見かけ上の地球的差異が少なくなり、そうしたモノから文化を語ることが難しい、と考えられるようになったからだ。また、先住民をはじめマイノリティがアイデンティティを主張する表現メディアとして芸術・芸能活動を活発化してきた歴史的な流れもある。
アボリジニに関しても、一九八〇年代前半以降、先住民芸術市場が確立していく。そのきっかけのひとつが先述した芸術賞などの創設であり、これが西欧美術市場にアボリジニ社会を巻き込み、結果、作品の値段が上がっていく、という現象も起きた。この価格高騰に美術館や博物館の収集が一役買ってきたこともまた、紛れもない事実である。
これらアイデンティティ表象のための資料は、現地の人びとが自ら使う従来型の用具と異なり、内部外部に向けたメッセージ発信がおもな機能であり、情報メディアの性格をもつ。元をたどれば芸能や芸術は、神や人間同士のコミュニケーションのメディア、象徴や表象のためのメディアであり、情報メディアだった。したがってこれら資料は本来能弁である。現代の人びとの文化を表現するために、こうした資料収集が増えていくのは当然の流れであろう。
しかし、能弁な情報メディアに比べ、過去に集積された大量の用具類などは寡黙である。その地域固有の生態・歴史環境に見合った人びとの観念、知、身体技法や技術、さらには、政治・経済的な関係性の網など、モノが背負った背景情報について、さまざまな切り口からの突っ込みを重ねていかないと、モノは語り出さない。これらを語らしめる努力は十分になされてきたのだろうか。
さらに言うなら、製作、使用、廃棄、収集、博物館への収蔵、という、個々のモノのライフサイクルに伴うストーリーも数多くあるはずだ。例えば民博には、一九五〇年代から一九七〇年代に東南アジアでおこなわれた数々の民族学調査団の活動に伴って収集された資料が所蔵されている。ところが、こうした調査団が収集したモノ、記録した写真資料、映像資料が、さまざまな経緯から複数の博物館に分散している、という状況がある。したがって、他の博物館所蔵資料との総合的な付き合わせ、写真や映像など他の情報メディアとの付き合わせがないと、モノの背景の全体像が見えてこないことがあるのだ。
そこで、写真や映像などの情報メディアも含め、他の博物館に分散している資料や情報との突き合わせも含めて、民博所蔵の各種資料に、あらためて光を当てていきたい、というのがこのコーナーの趣旨である。このコーナーには、「モノ・グラフ」と名付けてみた。モノに関する、専門論文としてのモノグラフ、記述としてのグラフィ、落書きが原義であるグラフィティ、となることを狙ったものだ。モノと情報をめぐるさまざまな切り口の物語が展開することを期待していただきたい。
アボリジニ資料については、すでに一九八〇年代初めから、美術工芸運動と文化表象運動の高まりを示す資料として、美的価値で選ぶのではなく全体を集めるという方針で絵画や彫刻が収集されてきた。民博の従来の収集方針、すなわち標本資料は、ほぼ現在の時点で普通の人びとが生産・生活・製作・宗教儀礼に用いる用具類を対象とし、偽物か本物かが重大な問題となるもの、美術、骨董的価値のあるものは、原則対象としない、宝物に主眼を置かない、という方針からは逸脱しない、と考えられたからである。
しかし近年の民博では、特別展に合わせた大型コレクションとともに、美術作品の収集が多くなっている。その理由のひとつは、生活様式のグローバル化が進み、生活用具には見かけ上の地球的差異が少なくなり、そうしたモノから文化を語ることが難しい、と考えられるようになったからだ。また、先住民をはじめマイノリティがアイデンティティを主張する表現メディアとして芸術・芸能活動を活発化してきた歴史的な流れもある。
アボリジニに関しても、一九八〇年代前半以降、先住民芸術市場が確立していく。そのきっかけのひとつが先述した芸術賞などの創設であり、これが西欧美術市場にアボリジニ社会を巻き込み、結果、作品の値段が上がっていく、という現象も起きた。この価格高騰に美術館や博物館の収集が一役買ってきたこともまた、紛れもない事実である。
これらアイデンティティ表象のための資料は、現地の人びとが自ら使う従来型の用具と異なり、内部外部に向けたメッセージ発信がおもな機能であり、情報メディアの性格をもつ。元をたどれば芸能や芸術は、神や人間同士のコミュニケーションのメディア、象徴や表象のためのメディアであり、情報メディアだった。したがってこれら資料は本来能弁である。現代の人びとの文化を表現するために、こうした資料収集が増えていくのは当然の流れであろう。
しかし、能弁な情報メディアに比べ、過去に集積された大量の用具類などは寡黙である。その地域固有の生態・歴史環境に見合った人びとの観念、知、身体技法や技術、さらには、政治・経済的な関係性の網など、モノが背負った背景情報について、さまざまな切り口からの突っ込みを重ねていかないと、モノは語り出さない。これらを語らしめる努力は十分になされてきたのだろうか。
さらに言うなら、製作、使用、廃棄、収集、博物館への収蔵、という、個々のモノのライフサイクルに伴うストーリーも数多くあるはずだ。例えば民博には、一九五〇年代から一九七〇年代に東南アジアでおこなわれた数々の民族学調査団の活動に伴って収集された資料が所蔵されている。ところが、こうした調査団が収集したモノ、記録した写真資料、映像資料が、さまざまな経緯から複数の博物館に分散している、という状況がある。したがって、他の博物館所蔵資料との総合的な付き合わせ、写真や映像など他の情報メディアとの付き合わせがないと、モノの背景の全体像が見えてこないことがあるのだ。
そこで、写真や映像などの情報メディアも含め、他の博物館に分散している資料や情報との突き合わせも含めて、民博所蔵の各種資料に、あらためて光を当てていきたい、というのがこのコーナーの趣旨である。このコーナーには、「モノ・グラフ」と名付けてみた。モノに関する、専門論文としてのモノグラフ、記述としてのグラフィ、落書きが原義であるグラフィティ、となることを狙ったものだ。モノと情報をめぐるさまざまな切り口の物語が展開することを期待していただきたい。
―開館三〇周年にあたって―
日本における文化人類学・民族学の拠点研究機関として国立民族学博物館(「みんぱく」)が設置され、その三年後、世界の諸民族の文化を展示する博物館が開館してから、三〇周年を迎えます。この間、「みんぱく」をとりまく環境は激変しました。グローバル化の進行にともない、人間の体感する時空は縮み、研究の対象としての文化と社会も、予想外のスピードで変化しています。世界は狭くなると同時に、個々の社会では多文化状況が進み、個人の生活体験の中には異文化の要素がさまざまな形で浸透しつつあります。それは世界が、社会の中に、個人の中に、モザイク状に乱反射している状況だといえます。
こうした変化に合わせて、「みんぱく」も生まれ変わりを要請されています。私たちは斬新な研究課題を開拓し、それにふさわしい手法を追究しているところです。博物館展示においても、文化を固定的、静的なものとして表象することは、もはやできなくなっています。研究者だけでなく、表象されている側の人々も積極的に展示に参加することが、一般的になってきました。「みんぱく」もそうした方針で展示に取り組んでいます。また、これまでは展示を見る側であった市民の積極的な参加も歓迎しています。
「みんぱく」は人間を知るために、三〇年間歩んできました。その旅は、今後も果てしなく続きます。文化は絶え間なく交流し変貌し、人は越境していきます。そうしたなかで、よりよい共生をもとめて未来社会を構想するためには、人間文化の探求の裾野をひろげ、広範な分野にまたがる知の融合を図る必要があります。
人間を探求する九十九(つづら)折りの旅路です。小さな、小さな謎解きを積み上げて、ようやく足元に小さな明かりがともります。人間の叡智をもとめる旅に終わりはありません。異なるものへの寛容と共感をもとめて、広く社会とともに歩むことこそ、今後の「みんぱく」の使命であると考えます。
「みんぱく」ルネサンスに、みなさまのご注目とご支援をお願いいたします。
こうした変化に合わせて、「みんぱく」も生まれ変わりを要請されています。私たちは斬新な研究課題を開拓し、それにふさわしい手法を追究しているところです。博物館展示においても、文化を固定的、静的なものとして表象することは、もはやできなくなっています。研究者だけでなく、表象されている側の人々も積極的に展示に参加することが、一般的になってきました。「みんぱく」もそうした方針で展示に取り組んでいます。また、これまでは展示を見る側であった市民の積極的な参加も歓迎しています。
「みんぱく」は人間を知るために、三〇年間歩んできました。その旅は、今後も果てしなく続きます。文化は絶え間なく交流し変貌し、人は越境していきます。そうしたなかで、よりよい共生をもとめて未来社会を構想するためには、人間文化の探求の裾野をひろげ、広範な分野にまたがる知の融合を図る必要があります。
人間を探求する九十九(つづら)折りの旅路です。小さな、小さな謎解きを積み上げて、ようやく足元に小さな明かりがともります。人間の叡智をもとめる旅に終わりはありません。異なるものへの寛容と共感をもとめて、広く社会とともに歩むことこそ、今後の「みんぱく」の使命であると考えます。
「みんぱく」ルネサンスに、みなさまのご注目とご支援をお願いいたします。
ニヴフの狩猟用革帯
狩猟用ベルト(男性用)(標本番号K2417、重さ/320g)
狩猟用ベルト(男性用)(標本番号K2417、重さ/320g)
革製の帯にさまざまなかたちをした道具が下がっている。これは樺太の先住民であるニヴフが用いていた、いわば七つ道具である。猟に行くときなどに衣服の上から腰につける。
写真(表紙)のベルト先端にはトナカイ角製の帯鉤(たいこう)がつく。右端の筒状のものはトナカイの角で作った針入れ、次は蝶鮫(ちょうざめ)の革製の火打ち石入れ、そしてトナカイの革製の火口(ほくち)入れ、最後が蝶鮫の皮で鞘(さや)を作った小刀である。小刀は柄が木製で柄先を削ぎ握りやすくしている。また柄全体に紐状(ひもじょう)の刻み目を入れて滑るのを防ぐ工夫がなされている。刀身は鉄製で片刃。ニヴフや樺太アイヌの小刀は刀身に比して柄が長いという特色がある。昨年アムール川河口の村で、ニヴフの老媼(ろうおう)がこの種の小刀を実際に使用したのを見た。この手の小刀は現用なのである。蝶鮫の皮を接ぎ合わせて鞘を作る。この技法の鞘もニヴフや樺太アイヌで見るタイプである。
トナカイ角製品にはニヴフ独特の細緻な文様が彫刻され、あるいは透かし彫りがなされるなど、角の加工技術の高さと彼らのすぐれた芸術意識を知ることができる。
この資料は鳥居龍蔵が大正一〇(一九二一)年に北樺太(現在のロシア連邦サハリン州の北部)のティミ川中流域で採集したもので、東京大学理学部人類学教室からの寄託品である。
樺太アイヌも同様の革帯を用いたが、ニヴフのものに比べると幅が広い。これをチシタイキ・クフとよぶが、北海道アイヌには伝わらなかった。樺太アイヌとニヴフとのあいだには技術交流や品物の交換があったらしく、相似た作品をよく見ることがある。どちらの民族のものか、注意が必要なところであろう。
写真(表紙)のベルト先端にはトナカイ角製の帯鉤(たいこう)がつく。右端の筒状のものはトナカイの角で作った針入れ、次は蝶鮫(ちょうざめ)の革製の火打ち石入れ、そしてトナカイの革製の火口(ほくち)入れ、最後が蝶鮫の皮で鞘(さや)を作った小刀である。小刀は柄が木製で柄先を削ぎ握りやすくしている。また柄全体に紐状(ひもじょう)の刻み目を入れて滑るのを防ぐ工夫がなされている。刀身は鉄製で片刃。ニヴフや樺太アイヌの小刀は刀身に比して柄が長いという特色がある。昨年アムール川河口の村で、ニヴフの老媼(ろうおう)がこの種の小刀を実際に使用したのを見た。この手の小刀は現用なのである。蝶鮫の皮を接ぎ合わせて鞘を作る。この技法の鞘もニヴフや樺太アイヌで見るタイプである。
トナカイ角製品にはニヴフ独特の細緻な文様が彫刻され、あるいは透かし彫りがなされるなど、角の加工技術の高さと彼らのすぐれた芸術意識を知ることができる。
この資料は鳥居龍蔵が大正一〇(一九二一)年に北樺太(現在のロシア連邦サハリン州の北部)のティミ川中流域で採集したもので、東京大学理学部人類学教室からの寄託品である。
樺太アイヌも同様の革帯を用いたが、ニヴフのものに比べると幅が広い。これをチシタイキ・クフとよぶが、北海道アイヌには伝わらなかった。樺太アイヌとニヴフとのあいだには技術交流や品物の交換があったらしく、相似た作品をよく見ることがある。どちらの民族のものか、注意が必要なところであろう。
ある僧侶とのかかわり―北タイの村での15年
馬場 雄司(ばば ゆうじ) 京都文教大学教授
仏教者としてキャリアアップ
タイ北部ナーン県のある村に通い始めて一五年あまりになる。一九九〇年、チェンマイ大学留学中、わたしはそこで一人の少年僧に出会った。それ以来、この僧侶とのつきあいが続いている。
この村の調査を始めたとき、村のことばや生活についてあれこれと教えてもらい、調査に同行してもらうことも多かった。彼が二〇歳を迎え正式な僧侶となり、中等学校前期(日本の中学にあたる)の義務教育化の動きによって、隣村の寺院に開かれた少年僧のために中等教育をおこなう学校で仏教について教えるようになった。一方、それと並行して、自らも通信教育によって中等学校卒業(日本の高卒にあたる)の資格をとり、ついで、僧侶が多く学ぶマハーチュラロンコン仏教大学に入学する。
少年僧のころの彼は、成人して正式な僧侶になったあと、しばらくしてから還俗(げんぞく)し、普通の村人として暮らしていくと語っていた。しかし、彼は仏教者としてのキャリアをアップさせる方向へと進んだ。教育の普及にともない、後進の僧侶の指導という立場に立ち、わたしの調査にも参加するなかで、次第に地域が抱える問題などに興味を抱いていくようになったことが、彼をそうした方向へすすませた要因であった。
わたしは、この村の出来事や文化について調べていた。そして彼は、それを好奇心で協力していた。ひとつの地域にかかわるわたしと彼の立場は異なる。わたしの調査はけっして地域の人びとの役に立つことを意図しておこなわれたものではない。しかし、彼の目には、自らが属する社会・文化において見過ごしていたものが見えたのであろう。この経験は、わたしに「調査をすること」と「協力をすること」の関係を考えさせることとなった。
役に立とうとして焦って失敗することがある。役に立とうと焦らずに役に立つこと、外部者との自然な接触が地域の人びとに自らを思い起こさせるようなかかわり方(自然治癒力を覚醒させるような)を、開発の実務家のような「役に立つこと」を目的とする人びとと考えていくことにわたしは関心をもつようになった。
互いに触発されながら
その後彼は大学を卒業し、三〇歳を過ぎたころ、隣村にある僧侶のための中等学校で校長を務めることになり、現在にいたっている。隣国ラオス北部の古都ルアンパバーンにならって、町の人びとの生活も含めて世界遺産化をねらうナーン市であるが、その委員会にも彼は顔を出すなど、地元の重要な人物となっている。
一九九〇年代の経済成長は、村の生活を大きく変化させた。フィールドを訪れた当初は、電話局が郡にひとつあるだけだったが、IT化や携帯電話の普及した現在、フィールドについての疑問を、日本から携帯電話やメールで簡単に現地にたずねることもできるようになった。
件(くだん)の僧侶からは、急速に変化する社会で、伝統的な文化が次第に失われつつあることを憂(うれ)う発言がしきりに聞かれるようになった。しかしながら、彼はけっして新しいものを拒んではいない。それどころか、とりわけコンピューターには明るく、また、村人の電化製品の修理もしばしばうけおっている。彼の今日の姿に何がしかのきっかけを与えたわたしは、伝統的文化の保護に目をむけ、新しいものを否定しない彼の今後に、どこか期待をしている。これからも、わたしが何か指示をしたり、何かしてあげたりするというのではなく、あくまでお互いに触発されるものがあることを期待してかかわっていきたいと思っている。
タイ北部ナーン県のある村に通い始めて一五年あまりになる。一九九〇年、チェンマイ大学留学中、わたしはそこで一人の少年僧に出会った。それ以来、この僧侶とのつきあいが続いている。
この村の調査を始めたとき、村のことばや生活についてあれこれと教えてもらい、調査に同行してもらうことも多かった。彼が二〇歳を迎え正式な僧侶となり、中等学校前期(日本の中学にあたる)の義務教育化の動きによって、隣村の寺院に開かれた少年僧のために中等教育をおこなう学校で仏教について教えるようになった。一方、それと並行して、自らも通信教育によって中等学校卒業(日本の高卒にあたる)の資格をとり、ついで、僧侶が多く学ぶマハーチュラロンコン仏教大学に入学する。
少年僧のころの彼は、成人して正式な僧侶になったあと、しばらくしてから還俗(げんぞく)し、普通の村人として暮らしていくと語っていた。しかし、彼は仏教者としてのキャリアをアップさせる方向へと進んだ。教育の普及にともない、後進の僧侶の指導という立場に立ち、わたしの調査にも参加するなかで、次第に地域が抱える問題などに興味を抱いていくようになったことが、彼をそうした方向へすすませた要因であった。
わたしは、この村の出来事や文化について調べていた。そして彼は、それを好奇心で協力していた。ひとつの地域にかかわるわたしと彼の立場は異なる。わたしの調査はけっして地域の人びとの役に立つことを意図しておこなわれたものではない。しかし、彼の目には、自らが属する社会・文化において見過ごしていたものが見えたのであろう。この経験は、わたしに「調査をすること」と「協力をすること」の関係を考えさせることとなった。
役に立とうとして焦って失敗することがある。役に立とうと焦らずに役に立つこと、外部者との自然な接触が地域の人びとに自らを思い起こさせるようなかかわり方(自然治癒力を覚醒させるような)を、開発の実務家のような「役に立つこと」を目的とする人びとと考えていくことにわたしは関心をもつようになった。
互いに触発されながら
その後彼は大学を卒業し、三〇歳を過ぎたころ、隣村にある僧侶のための中等学校で校長を務めることになり、現在にいたっている。隣国ラオス北部の古都ルアンパバーンにならって、町の人びとの生活も含めて世界遺産化をねらうナーン市であるが、その委員会にも彼は顔を出すなど、地元の重要な人物となっている。
一九九〇年代の経済成長は、村の生活を大きく変化させた。フィールドを訪れた当初は、電話局が郡にひとつあるだけだったが、IT化や携帯電話の普及した現在、フィールドについての疑問を、日本から携帯電話やメールで簡単に現地にたずねることもできるようになった。
件(くだん)の僧侶からは、急速に変化する社会で、伝統的な文化が次第に失われつつあることを憂(うれ)う発言がしきりに聞かれるようになった。しかしながら、彼はけっして新しいものを拒んではいない。それどころか、とりわけコンピューターには明るく、また、村人の電化製品の修理もしばしばうけおっている。彼の今日の姿に何がしかのきっかけを与えたわたしは、伝統的文化の保護に目をむけ、新しいものを否定しない彼の今後に、どこか期待をしている。これからも、わたしが何か指示をしたり、何かしてあげたりするというのではなく、あくまでお互いに触発されるものがあることを期待してかかわっていきたいと思っている。
山に雪が、人に齢が
ライフヒストリー
二○○二年の夏、わたしは中国内蒙古自治区の最西端にあるエズネーに赴き、年老いた女性たちばかりを訪ねて回っていた。おばあさんたちからその人生を語ってもらい、それを聞き書きするという仕事を始めたのである。
一般にこうした語りはその内容から「ライフヒストリー」とよばれる。語りはそもそも歴史のすべてではなく、いくつかの事象を選んで再構成する物語であるから「ライフストーリー」とよばれることもある。
一九二○年代、三○年代生まれの彼女たちは、子どものころに社会主義革命を体験し、壮年期に文化大革命を経験し、現在は飛躍的な経済発展を目の当たりにしている。人生の途上で彼らが得たものは多いが、失ったものも大きい。例えば、文化大革命という社会変動は人倫への信頼を破壊した。一方、開発という社会変容は、砂漠を潤してきた水環境を今も圧倒的な力で破壊しつつある。そうした破壊現象はつとに有名であり、それゆえにこちらが求めている調査事項なのである。
見えてくる生きざま
ただし、本当に大切なことはそうした情報収集活動の外側にあるとわたしは思う。だからわたしは彼らを「インフォーマント(情報提供者)」とはよばない。わたしの知らない時空について、自ら生きた人の経験としてナマのことばでわけてもらうというのは、たいそうぜいたくなごちそうであって、一緒に泣いたり笑ったりする時間がそこにあることが至福のように思われる。さらにまた、問答の向こう側に、彼らの生きざまや社会のありようが見えてくる。たとえば、
「母が生きていたとき、その面倒を見ることができませんでした。亡くなったあとも祈祷をしただけで、葬式に加わることができませんでした。一生、残念に思います。その代わり、姑についてはわたしが十分に世話をしました」
「自分の子を養子に出したり、ほかの人から養子をもらったりする場合がたくさんあります。子どもなら、産んだ子ももらった子も同様に扱います。子どもを育てるということは、自分が産んでも、人からもらっても同じですよ」
現代のように医療や福祉について制度依存できなかったとき、人びとは相互に築くネットワークで負担を分散してきたのだった。個々人がたくさんの他人とともに生きることによって、社会全体が自立していたのである。
彼女たちが好んで使うことわざに、「山に雪が、人に齢が」という表現がある。「降り積もる」という動詞が省略されることによって、意味の重みはいや増す。山に雪は美しい、その風景を思い起こせば、年齢を隠す化粧など要らないだろう。
二○○二年の夏、わたしは中国内蒙古自治区の最西端にあるエズネーに赴き、年老いた女性たちばかりを訪ねて回っていた。おばあさんたちからその人生を語ってもらい、それを聞き書きするという仕事を始めたのである。
一般にこうした語りはその内容から「ライフヒストリー」とよばれる。語りはそもそも歴史のすべてではなく、いくつかの事象を選んで再構成する物語であるから「ライフストーリー」とよばれることもある。
一九二○年代、三○年代生まれの彼女たちは、子どものころに社会主義革命を体験し、壮年期に文化大革命を経験し、現在は飛躍的な経済発展を目の当たりにしている。人生の途上で彼らが得たものは多いが、失ったものも大きい。例えば、文化大革命という社会変動は人倫への信頼を破壊した。一方、開発という社会変容は、砂漠を潤してきた水環境を今も圧倒的な力で破壊しつつある。そうした破壊現象はつとに有名であり、それゆえにこちらが求めている調査事項なのである。
見えてくる生きざま
ただし、本当に大切なことはそうした情報収集活動の外側にあるとわたしは思う。だからわたしは彼らを「インフォーマント(情報提供者)」とはよばない。わたしの知らない時空について、自ら生きた人の経験としてナマのことばでわけてもらうというのは、たいそうぜいたくなごちそうであって、一緒に泣いたり笑ったりする時間がそこにあることが至福のように思われる。さらにまた、問答の向こう側に、彼らの生きざまや社会のありようが見えてくる。たとえば、
「母が生きていたとき、その面倒を見ることができませんでした。亡くなったあとも祈祷をしただけで、葬式に加わることができませんでした。一生、残念に思います。その代わり、姑についてはわたしが十分に世話をしました」
「自分の子を養子に出したり、ほかの人から養子をもらったりする場合がたくさんあります。子どもなら、産んだ子ももらった子も同様に扱います。子どもを育てるということは、自分が産んでも、人からもらっても同じですよ」
現代のように医療や福祉について制度依存できなかったとき、人びとは相互に築くネットワークで負担を分散してきたのだった。個々人がたくさんの他人とともに生きることによって、社会全体が自立していたのである。
彼女たちが好んで使うことわざに、「山に雪が、人に齢が」という表現がある。「降り積もる」という動詞が省略されることによって、意味の重みはいや増す。山に雪は美しい、その風景を思い起こせば、年齢を隠す化粧など要らないだろう。
国際結婚移住者の「声」
横田 祥子(よこた さちこ) 東京都立大学大学院社会科学研究科
グエンさんのある一日
南国の昼下がり、台湾中部の田舎町、東勢鎮(とうせいちん)。ここは一八世紀後半中国広東省から移り住んだ客家人(はっかじん)(漢族の一集団)が作った町として有名だ。その目抜き通りのある家電店で、ベトナム出身のグエンさんは、午後娘と店番をしている。「家電」の字のとなりには「ベトナム雑貨あります」の文字。彼女は台湾人の夫が経営する家電店の一角に、ベトナムからもち帰った食品や雑貨を置き販売している。
町が昼寝から醒める午後三時、ふいにベトナム女性がバイクに幼子を乗せて、一人また一人とやって来る。お目当ては、ベトナム女性同士のおしゃべり。彼女たちは「電話が壊れたみたい」「携帯の電池をちょうだい」「電気コードあるかしら」と言いつつ、ついでにベトナムの実家に電話するための国際電話プリペイドカードと、母国からやってきた魚醤やフォー(ライスヌードル)、ココナッツジュースなどを買っていく。そして、甘いベトナム式コーヒーをすすりながら、しばし同じ田舎町に住む友人ベトナム人たちの近況を報告し合い、ときには台湾人の夫のこと、家族のことを相談し合う。
グエンさんは今年三一歳、ベトナム南部カントー省の出身だ。高校在学時、父親の事業が失敗し、家計を助けるため故郷の工場で働いてきた。その後ホーチミン市へ出て宝飾店で働いていた二〇〇〇年、台湾人である今の夫(_南人(びんなんじん)、五〇歳)と見合いをし、単身台湾へ嫁いできた。
生活指導教室で猛勉強
グエンさん夫婦のように、台湾人男性と外国人女性の結婚は一九九〇年代以降、年々増加しており、二〇〇四年には台湾人男性と外国人女性の国際結婚は、台湾の全結婚数の二五パーセントに上った。花嫁たちの出身国は、中国、ベトナム、インドネシア、タイ、カンボジアなどである。国際結婚の増加は一九八〇年代以降、台湾企業が当該地域に経済投資を増大したことにより、経済交流と人的交流が活発化したためである。一九九〇年代後半以降、ベトナム女性は中国系女性に次ぐ勢力となっており、二〇〇六年二月現在、七万四四二七人が居住している。
彼女たちの多くは、ベトナム南部メコンデルタ出身のキン族で、結婚前は台湾の地を踏んだこともなければ中国語を勉強したこともない。しかし、台湾では家から一歩出れば、迫り来るような漢字世界。夫や姑は、道に迷っては大変、誰かに連れさられては大変、と嫁を子どものように扱う。次第に彼女たち国際結婚移住者は家に閉じこもりがちになり、頼るは家族のみとなってしまう。結婚移住者のなかには、来台後数年経っても、自分の氏名すら漢字で記せない人もしばしば見かける。
しかし、グエンさんは違った。夫の強いすすめもあり、毎日「外国籍配偶者生活指導教室」へと通う。これは、いわば外国人配偶者のために開かれた中等教育クラスである。授業は、毎週月から金曜日まで夜六時半から九時半のあいだ、近所の中学校でおこなわれる。グエンさんは現在、中学二年生の授業を受けている。クラスメイトは、ベトナムのキン族、インドネシア出身の客家系華人のほか、学校を中途退学した台湾漢族やアミ族の学生一〇人だ。
グエンさんは国語、社会、理科、数学、体育、家庭、情報処理といった科目のなかで、体育がいちばん好きだという。バドミントンの授業では、同級生たちを打ち破り、最後はいつも先生と一騎打ちだ。体育の授業終了後、彼女は汗をぬぐう間もなく、次の国語の授業へと走る。その教科書を覗くとびっしりと書き込みがされていて、彼女が家で綿密に予習を済ませてきたことがわかる。
夜九時半に授業が終わると、学校近くのベトナム軽食店へ。ここにもベトナム女性が集まり、フォーをすすり「鴨仔蛋」(ヤーザイダン)(孵化直前のアヒルの卵)を食べながら、ひとしきりおしゃべりを楽しんでいる。ときには一曲故郷の歌を歌う。そして、客として来たベトナム人と知り合い、友人の輪を広げていく。近くの町に新しいベトナム料理店ができると、その情報は風の便りにのせて瞬く間に伝わり、彼女たちは子どもをバイクの後ろに乗せて颯爽(さっそう)と出かけていく。
「なぜ台湾に来たかって?親孝行したいから、と言いたいところだけれど、本当のところは自分の運を試してみたい気分だったのよ。台湾に嫁いだ人たちの暮らしぶりはなかなかよさそうだったし、人生をリセットしたくなって、単純にベトナムを離れてみようかって思ったの。まさかこんなに長くいるとは思わなかったわ。台湾に来てから、夫や義理の父母がわたしにすごくよくしてくれたの。義弟たちもわたしを『大嫂(ダーサオ)』(長男の嫁)として敬ってくれたしね。こんな誠実な人たちをがっかりさせたくない、と思って台湾に残ることにしたわ」と、グエンさんは結婚の理由を語ってくれた。「来年国籍(中華民国国籍)がとれれば、わたしはもうベトナム人じゃなくなるわ。台湾人になるのよ」。
前述した「外国籍配偶者生活指導教室」の中等部を卒業すると、通訳の仕事を斡旋(あっせん)してもらえる。グエンさんは通訳となり、台湾全土を飛び回る仕事を希望しており、中国語の微妙な表現の差異を学びとるために、日夜語学力を磨いている。
グエンさんのいちばんの心配は、一人娘の教育だ。彼女は去年九月幼稚園に入園した。これから大学卒業まで長い学校生活が始まる。「子どもの宿題を見てあげられるか心配なの。だからまずは、わたしがしっかり勉強しなくてはいけないわ」。親子二人三脚の勉強はこれからも続く。
「声」が一丸となるまで
国際結婚が増加しているとはいえ、結婚移住者は依然として台湾社会では異質な存在であり、さまざまな不利益、不平等をこうむっているのが現状である。不利な現状の是正には、言語の獲得とそれを通じ、外界の出来事を解釈し批判する能力が基盤となる。しかしながら、すべての結婚移住者が、体系的に中国語を学ぶ機会に恵まれているとはいえず、まだまだ社会生活を送るのがやっとという段階である。こうした状況のなか、すでに一部の結婚移住者は、台湾社会のなかで改めて主体性を確立しながら、人権の尊重や福祉の拡充を求めている。徐々に「声」を発してきた結婚移住者が増加し一丸となったとき、いかにしてそして何を台湾社会と対話していくのか、今後も目が離せない。
南国の昼下がり、台湾中部の田舎町、東勢鎮(とうせいちん)。ここは一八世紀後半中国広東省から移り住んだ客家人(はっかじん)(漢族の一集団)が作った町として有名だ。その目抜き通りのある家電店で、ベトナム出身のグエンさんは、午後娘と店番をしている。「家電」の字のとなりには「ベトナム雑貨あります」の文字。彼女は台湾人の夫が経営する家電店の一角に、ベトナムからもち帰った食品や雑貨を置き販売している。
町が昼寝から醒める午後三時、ふいにベトナム女性がバイクに幼子を乗せて、一人また一人とやって来る。お目当ては、ベトナム女性同士のおしゃべり。彼女たちは「電話が壊れたみたい」「携帯の電池をちょうだい」「電気コードあるかしら」と言いつつ、ついでにベトナムの実家に電話するための国際電話プリペイドカードと、母国からやってきた魚醤やフォー(ライスヌードル)、ココナッツジュースなどを買っていく。そして、甘いベトナム式コーヒーをすすりながら、しばし同じ田舎町に住む友人ベトナム人たちの近況を報告し合い、ときには台湾人の夫のこと、家族のことを相談し合う。
グエンさんは今年三一歳、ベトナム南部カントー省の出身だ。高校在学時、父親の事業が失敗し、家計を助けるため故郷の工場で働いてきた。その後ホーチミン市へ出て宝飾店で働いていた二〇〇〇年、台湾人である今の夫(_南人(びんなんじん)、五〇歳)と見合いをし、単身台湾へ嫁いできた。
生活指導教室で猛勉強
グエンさん夫婦のように、台湾人男性と外国人女性の結婚は一九九〇年代以降、年々増加しており、二〇〇四年には台湾人男性と外国人女性の国際結婚は、台湾の全結婚数の二五パーセントに上った。花嫁たちの出身国は、中国、ベトナム、インドネシア、タイ、カンボジアなどである。国際結婚の増加は一九八〇年代以降、台湾企業が当該地域に経済投資を増大したことにより、経済交流と人的交流が活発化したためである。一九九〇年代後半以降、ベトナム女性は中国系女性に次ぐ勢力となっており、二〇〇六年二月現在、七万四四二七人が居住している。
彼女たちの多くは、ベトナム南部メコンデルタ出身のキン族で、結婚前は台湾の地を踏んだこともなければ中国語を勉強したこともない。しかし、台湾では家から一歩出れば、迫り来るような漢字世界。夫や姑は、道に迷っては大変、誰かに連れさられては大変、と嫁を子どものように扱う。次第に彼女たち国際結婚移住者は家に閉じこもりがちになり、頼るは家族のみとなってしまう。結婚移住者のなかには、来台後数年経っても、自分の氏名すら漢字で記せない人もしばしば見かける。
しかし、グエンさんは違った。夫の強いすすめもあり、毎日「外国籍配偶者生活指導教室」へと通う。これは、いわば外国人配偶者のために開かれた中等教育クラスである。授業は、毎週月から金曜日まで夜六時半から九時半のあいだ、近所の中学校でおこなわれる。グエンさんは現在、中学二年生の授業を受けている。クラスメイトは、ベトナムのキン族、インドネシア出身の客家系華人のほか、学校を中途退学した台湾漢族やアミ族の学生一〇人だ。
グエンさんは国語、社会、理科、数学、体育、家庭、情報処理といった科目のなかで、体育がいちばん好きだという。バドミントンの授業では、同級生たちを打ち破り、最後はいつも先生と一騎打ちだ。体育の授業終了後、彼女は汗をぬぐう間もなく、次の国語の授業へと走る。その教科書を覗くとびっしりと書き込みがされていて、彼女が家で綿密に予習を済ませてきたことがわかる。
夜九時半に授業が終わると、学校近くのベトナム軽食店へ。ここにもベトナム女性が集まり、フォーをすすり「鴨仔蛋」(ヤーザイダン)(孵化直前のアヒルの卵)を食べながら、ひとしきりおしゃべりを楽しんでいる。ときには一曲故郷の歌を歌う。そして、客として来たベトナム人と知り合い、友人の輪を広げていく。近くの町に新しいベトナム料理店ができると、その情報は風の便りにのせて瞬く間に伝わり、彼女たちは子どもをバイクの後ろに乗せて颯爽(さっそう)と出かけていく。
「なぜ台湾に来たかって?親孝行したいから、と言いたいところだけれど、本当のところは自分の運を試してみたい気分だったのよ。台湾に嫁いだ人たちの暮らしぶりはなかなかよさそうだったし、人生をリセットしたくなって、単純にベトナムを離れてみようかって思ったの。まさかこんなに長くいるとは思わなかったわ。台湾に来てから、夫や義理の父母がわたしにすごくよくしてくれたの。義弟たちもわたしを『大嫂(ダーサオ)』(長男の嫁)として敬ってくれたしね。こんな誠実な人たちをがっかりさせたくない、と思って台湾に残ることにしたわ」と、グエンさんは結婚の理由を語ってくれた。「来年国籍(中華民国国籍)がとれれば、わたしはもうベトナム人じゃなくなるわ。台湾人になるのよ」。
前述した「外国籍配偶者生活指導教室」の中等部を卒業すると、通訳の仕事を斡旋(あっせん)してもらえる。グエンさんは通訳となり、台湾全土を飛び回る仕事を希望しており、中国語の微妙な表現の差異を学びとるために、日夜語学力を磨いている。
グエンさんのいちばんの心配は、一人娘の教育だ。彼女は去年九月幼稚園に入園した。これから大学卒業まで長い学校生活が始まる。「子どもの宿題を見てあげられるか心配なの。だからまずは、わたしがしっかり勉強しなくてはいけないわ」。親子二人三脚の勉強はこれからも続く。
「声」が一丸となるまで
国際結婚が増加しているとはいえ、結婚移住者は依然として台湾社会では異質な存在であり、さまざまな不利益、不平等をこうむっているのが現状である。不利な現状の是正には、言語の獲得とそれを通じ、外界の出来事を解釈し批判する能力が基盤となる。しかしながら、すべての結婚移住者が、体系的に中国語を学ぶ機会に恵まれているとはいえず、まだまだ社会生活を送るのがやっとという段階である。こうした状況のなか、すでに一部の結婚移住者は、台湾社会のなかで改めて主体性を確立しながら、人権の尊重や福祉の拡充を求めている。徐々に「声」を発してきた結婚移住者が増加し一丸となったとき、いかにしてそして何を台湾社会と対話していくのか、今後も目が離せない。
珍島(チンド)の甕(かめ)と喪輿(サンヨ)―館外の研究者との共同収集―
珍島と伊藤亜人先生
二〇〇五年七月、わたしは戦後の日本文化人類学における韓国研究の草分けの一人である伊藤亜人先生と珍島にいた。珍島は朝鮮半島の南端部に位置する島である。伊藤先生が初めて珍島を訪れたのは、一九七二年の七月のことであったという。そして、この島のひとつの村を調査地に定めた。それ以来、一九八〇年代にかけて、この村を何度も訪れ調査を続けてきた。また、その後もほとんど毎年のように珍島を訪れ、拠点を村から邑(小都市)に移すとともに研究テーマを広げてきた。この三〇余年にわたる伊藤先生の研究の足跡は、『韓国珍島の民俗紀行』(青丘文化社、一九九九年)に描かれている。
わたしが珍島に行ったのは、伊藤先生からの提案で、珍島の甕を収集するためだった。韓国の甕は、キムチや醤油・味噌などを入れる容器としてだけでなく、家庭の息災を願う信仰とも深くむすび付いている。伊藤先生は、かつて「甕と主婦」において、珍島の一家庭にある八二個の甕の種類と役割を調査し、甕が主婦の地位と領分・生活観の象徴としての側面を有していると指摘した。また、「韓国農村における土器の使用」に関わる記録でも、甕の種類、用途の広さ、屋敷における配置を示し、「珍島の農村においてこれほどまで多くの甕器(かめき)が用いられていることは、指摘されるまで現地の人々ばかりか民俗学者たちも気付かなかったようである」と述べている。
今回は、この甕だけでなく、珍島で一九八〇年代まで使われていた喪輿も収集できることになった。喪輿は、葬式の野辺送りで、死者を墓に運ぶために使われる輿である。民博の展示場には、慶尚道(キョンサンド)の喪輿が展示されているが、全羅道(チョルラド)の喪輿は形態が異なり、ぜひとも収集したいと思っていた。
「物」の価値を知らせる
収集の目的の第一は、失われゆくものを保存するということにあった。韓国では一九七〇年代から一九八〇年代にかけては、まだ伝統的な生活が残されていた。わたしが初めて韓国に行った、ほんの三〇年前でも、農村においては木と土と石と紙の住まいであったが、いまやステンレスやガラスをはじめ新建材が主流になっている。この三〇年で物質文化は急速に変化し、甕はプラスチック容器に、喪輿は担ぎ手がいなくなり霊柩車に変わっていった。
もうひとつの目的は、これらの生活用具を民博に収蔵することにあった。伊藤先生の言を借りれば「韓国では日本に比べると物に対する関心が一般に低いといわざるを得ない」。それは「『玩物喪志』という表現にあるように、物に執着することは内面の徳性の涵養(かんよう)のためにはむしろ妨げとなるとみなされ、戒められていたほどである」からだという。国立の博物館が収集することで、韓国の人たちに生活用具という「物」にも価値があることを知らせたいというのが、伊藤先生の心のなかにあったようだ。
韓国研究者のメッカに
今回の収集は、大学共同利用機関として館外の研究者である伊藤先生との共同でおこなったが、その作業は、朴柱彦(パク・チョオン)さんの協力を仰いだ。朴さんは、前述の『韓国珍島の民俗紀行』にも「その三〇年間近い今日に至るまで、私は邑内にいる時はいつも夜遅くまで朴柱彦氏から珍島について実に興味深いそして人間味あふれる話を聞いてきた」とあるように、伊藤先生の珍島における研究パートナーだ。朴さんは、島中をまわって、伊藤先生が調査した一家庭にあったものと同じ種類、形の甕を探し出してくれた。それらをあらかじめ借りておいてくれたかつての映画館に並べ、わたしと伊藤先生がひとつずつ、その名前と大きさを確かめていった。喪輿は、今では使われず、そのままに置かれていたものを一部補修してもらい、その組み立て方を教えてもらいながら、ビデオで撮影した。
わたしたちの収集作業の合間に、伊藤先生の弟子である全北(チョンブク)大学の林慶澤(イム・ギョンテク)さんと同志社大学の板垣竜太さんが、日韓の学生交流のかたわら、珍島に学生を連れて来た。伊藤先生は、ご自身が暮らされた家にも学生たちを案内し、ご主人の李隠鎮(イ・ウンジン)さんを紹介した。この村の会館には、伊藤先生が一九七〇年代にこの村で撮った写真が飾られている。それらの写真は、伊藤先生が東京大学を定年退職された二〇〇六年三月に『韓国夢幻―文化人類学者が見た七〇年代の情景』(新宿書房)というタイトルで刊行されている。そこには、朴柱彦さんと李隠鎮さんが、「珍島人」となった伊藤先生とのつながりを記した文章も寄稿されている。
モーゼの奇跡で有名な珍島だが、日本文化人類学の韓国研究者にとっては、この島がメッカになっているといっても過言ではないだろう。そして、その島の生活用具が民博の資料となっている。
二〇〇五年七月、わたしは戦後の日本文化人類学における韓国研究の草分けの一人である伊藤亜人先生と珍島にいた。珍島は朝鮮半島の南端部に位置する島である。伊藤先生が初めて珍島を訪れたのは、一九七二年の七月のことであったという。そして、この島のひとつの村を調査地に定めた。それ以来、一九八〇年代にかけて、この村を何度も訪れ調査を続けてきた。また、その後もほとんど毎年のように珍島を訪れ、拠点を村から邑(小都市)に移すとともに研究テーマを広げてきた。この三〇余年にわたる伊藤先生の研究の足跡は、『韓国珍島の民俗紀行』(青丘文化社、一九九九年)に描かれている。
わたしが珍島に行ったのは、伊藤先生からの提案で、珍島の甕を収集するためだった。韓国の甕は、キムチや醤油・味噌などを入れる容器としてだけでなく、家庭の息災を願う信仰とも深くむすび付いている。伊藤先生は、かつて「甕と主婦」において、珍島の一家庭にある八二個の甕の種類と役割を調査し、甕が主婦の地位と領分・生活観の象徴としての側面を有していると指摘した。また、「韓国農村における土器の使用」に関わる記録でも、甕の種類、用途の広さ、屋敷における配置を示し、「珍島の農村においてこれほどまで多くの甕器(かめき)が用いられていることは、指摘されるまで現地の人々ばかりか民俗学者たちも気付かなかったようである」と述べている。
今回は、この甕だけでなく、珍島で一九八〇年代まで使われていた喪輿も収集できることになった。喪輿は、葬式の野辺送りで、死者を墓に運ぶために使われる輿である。民博の展示場には、慶尚道(キョンサンド)の喪輿が展示されているが、全羅道(チョルラド)の喪輿は形態が異なり、ぜひとも収集したいと思っていた。
「物」の価値を知らせる
収集の目的の第一は、失われゆくものを保存するということにあった。韓国では一九七〇年代から一九八〇年代にかけては、まだ伝統的な生活が残されていた。わたしが初めて韓国に行った、ほんの三〇年前でも、農村においては木と土と石と紙の住まいであったが、いまやステンレスやガラスをはじめ新建材が主流になっている。この三〇年で物質文化は急速に変化し、甕はプラスチック容器に、喪輿は担ぎ手がいなくなり霊柩車に変わっていった。
もうひとつの目的は、これらの生活用具を民博に収蔵することにあった。伊藤先生の言を借りれば「韓国では日本に比べると物に対する関心が一般に低いといわざるを得ない」。それは「『玩物喪志』という表現にあるように、物に執着することは内面の徳性の涵養(かんよう)のためにはむしろ妨げとなるとみなされ、戒められていたほどである」からだという。国立の博物館が収集することで、韓国の人たちに生活用具という「物」にも価値があることを知らせたいというのが、伊藤先生の心のなかにあったようだ。
韓国研究者のメッカに
今回の収集は、大学共同利用機関として館外の研究者である伊藤先生との共同でおこなったが、その作業は、朴柱彦(パク・チョオン)さんの協力を仰いだ。朴さんは、前述の『韓国珍島の民俗紀行』にも「その三〇年間近い今日に至るまで、私は邑内にいる時はいつも夜遅くまで朴柱彦氏から珍島について実に興味深いそして人間味あふれる話を聞いてきた」とあるように、伊藤先生の珍島における研究パートナーだ。朴さんは、島中をまわって、伊藤先生が調査した一家庭にあったものと同じ種類、形の甕を探し出してくれた。それらをあらかじめ借りておいてくれたかつての映画館に並べ、わたしと伊藤先生がひとつずつ、その名前と大きさを確かめていった。喪輿は、今では使われず、そのままに置かれていたものを一部補修してもらい、その組み立て方を教えてもらいながら、ビデオで撮影した。
わたしたちの収集作業の合間に、伊藤先生の弟子である全北(チョンブク)大学の林慶澤(イム・ギョンテク)さんと同志社大学の板垣竜太さんが、日韓の学生交流のかたわら、珍島に学生を連れて来た。伊藤先生は、ご自身が暮らされた家にも学生たちを案内し、ご主人の李隠鎮(イ・ウンジン)さんを紹介した。この村の会館には、伊藤先生が一九七〇年代にこの村で撮った写真が飾られている。それらの写真は、伊藤先生が東京大学を定年退職された二〇〇六年三月に『韓国夢幻―文化人類学者が見た七〇年代の情景』(新宿書房)というタイトルで刊行されている。そこには、朴柱彦さんと李隠鎮さんが、「珍島人」となった伊藤先生とのつながりを記した文章も寄稿されている。
モーゼの奇跡で有名な珍島だが、日本文化人類学の韓国研究者にとっては、この島がメッカになっているといっても過言ではないだろう。そして、その島の生活用具が民博の資料となっている。
コタケネズミと焼畑民
竹田 晋也(たけだ しんや) 京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科准教授
賑やかな休閑地
焼畑耕作や野火による撹乱がくりかえされてきた東南アジア大陸山地では、竹の多い二次林、あるいは竹林が広く見られる。山棲みの人びとは、竹林に焼畑をひらいて陸稲を育て、次の年には休閑する。するとすぐさま竹が回復して数年も経つとまた焼畑がひらけるようになる。人びとは竹の旺盛な回復力を利用して生活を営んできたのである。
ミャンマーのヤンゴンとマンダレーのあいだに横たわるバゴー山地でも、カレンの人びとが竹の多い二次林で焼畑を営んでいる。休閑地にはチャタウンワ (Bambusa polymorpha) やタイワ(Bambusa tulda)などの竹が多い。
こうした竹林を歩いてみると、地表を掘り起こした土盛りが一面に広がっている。これは、カレン語でブイ、ビルマ語でプイとよばれるコタケネズミの仕業である。巣穴の入り口には、掘り出した土が盛り上がっている。コタケネズミはそこから土中を掘り進み、一定の間隔で土を地上に掃き出しているのである。こうして竹の根やタケノコを食べ、土のなかの巣で繁殖している。イノシシが地面を掘り起こした跡も加わって、特に若い休閑林の林床はまるで耕されたようになっている。こうした動物の耕耘(こううん)力は、休閑地の地力回復に大いに役立っている。休閑地というと静謐(せいひつ)な場所を思い描くが、実際には動物が活躍するずいぶんと賑やかな世界である。
コタケネズミの昔話
一一月の満月が森を照らす夜に、カレンの村でこんな昔話を聞いた。
「むかし、ブイ(コタケネズミ)は月まで行こうとして、竹の稈(かん)(中空な茎)のなかを登っていった。節をひとつひとつ破って登り詰めるころにはもう太陽が昇っていて、最後の節を破って顔を出したら、太陽のまぶしさで目がくらみ墜落してしまった。それ以来、ブイは土のなかで暮らし、目もよく見えなくなってしまったそうだ」。
オオタケネズミの場合には、実際に竹をよじ登ることがあるらしい。そのときに稈の表面をかじるので、それがフィールドサインになってオオタケネズミがいることがわかる。またタケネズミ類の小さな目は、土中での生活に適応したものだ。
森を耕すコタケネズミ
カレンのような焼畑民にとってコタケネズミは大切なタンパク源となっている。カレンの村の周囲は、水源や薪炭(しんたん)材を確保するために森が保たれている。その森のなかの沢の土手にコタケネズミの罠を仕掛けていた。チャタウンワの竹筒のなかに餌となる竹の根を入れて、その周囲に糸を投げ縄のように仕掛け土のなかに埋める。糸の端は地上のしならせた小枝に縛っておく。コタケネズミが餌を食べると止め金が外れて、土のなかから竹筒に体を突っ込んだコタケネズミが釣り上がってくる。
コタケネズミの体長は二〇センチメートルほどで、動きは思ったほど素速くない。土を掘り進める手足はとても短い。追い詰められると、鋭い門歯を見せて「ジー」と音を立てて威嚇(いかく)する。この鋭い前歯と短い手足で森を耕し、村人の日々の食卓を飾り、ときには祈りのために供犠(くぎ)されてきたのである。焼畑の撹乱が竹の多い二次林を生み、コタケネズミはその竹林を耕して棲息地を拡大してきた。森で焼畑耕作を営んできたカレンの人びととその焼畑の森を耕してきたコタケネズミとのつきあいは、深くて長いのである。
焼畑耕作や野火による撹乱がくりかえされてきた東南アジア大陸山地では、竹の多い二次林、あるいは竹林が広く見られる。山棲みの人びとは、竹林に焼畑をひらいて陸稲を育て、次の年には休閑する。するとすぐさま竹が回復して数年も経つとまた焼畑がひらけるようになる。人びとは竹の旺盛な回復力を利用して生活を営んできたのである。
ミャンマーのヤンゴンとマンダレーのあいだに横たわるバゴー山地でも、カレンの人びとが竹の多い二次林で焼畑を営んでいる。休閑地にはチャタウンワ (Bambusa polymorpha) やタイワ(Bambusa tulda)などの竹が多い。
こうした竹林を歩いてみると、地表を掘り起こした土盛りが一面に広がっている。これは、カレン語でブイ、ビルマ語でプイとよばれるコタケネズミの仕業である。巣穴の入り口には、掘り出した土が盛り上がっている。コタケネズミはそこから土中を掘り進み、一定の間隔で土を地上に掃き出しているのである。こうして竹の根やタケノコを食べ、土のなかの巣で繁殖している。イノシシが地面を掘り起こした跡も加わって、特に若い休閑林の林床はまるで耕されたようになっている。こうした動物の耕耘(こううん)力は、休閑地の地力回復に大いに役立っている。休閑地というと静謐(せいひつ)な場所を思い描くが、実際には動物が活躍するずいぶんと賑やかな世界である。
コタケネズミの昔話
一一月の満月が森を照らす夜に、カレンの村でこんな昔話を聞いた。
「むかし、ブイ(コタケネズミ)は月まで行こうとして、竹の稈(かん)(中空な茎)のなかを登っていった。節をひとつひとつ破って登り詰めるころにはもう太陽が昇っていて、最後の節を破って顔を出したら、太陽のまぶしさで目がくらみ墜落してしまった。それ以来、ブイは土のなかで暮らし、目もよく見えなくなってしまったそうだ」。
オオタケネズミの場合には、実際に竹をよじ登ることがあるらしい。そのときに稈の表面をかじるので、それがフィールドサインになってオオタケネズミがいることがわかる。またタケネズミ類の小さな目は、土中での生活に適応したものだ。
森を耕すコタケネズミ
カレンのような焼畑民にとってコタケネズミは大切なタンパク源となっている。カレンの村の周囲は、水源や薪炭(しんたん)材を確保するために森が保たれている。その森のなかの沢の土手にコタケネズミの罠を仕掛けていた。チャタウンワの竹筒のなかに餌となる竹の根を入れて、その周囲に糸を投げ縄のように仕掛け土のなかに埋める。糸の端は地上のしならせた小枝に縛っておく。コタケネズミが餌を食べると止め金が外れて、土のなかから竹筒に体を突っ込んだコタケネズミが釣り上がってくる。
コタケネズミの体長は二〇センチメートルほどで、動きは思ったほど素速くない。土を掘り進める手足はとても短い。追い詰められると、鋭い門歯を見せて「ジー」と音を立てて威嚇(いかく)する。この鋭い前歯と短い手足で森を耕し、村人の日々の食卓を飾り、ときには祈りのために供犠(くぎ)されてきたのである。焼畑の撹乱が竹の多い二次林を生み、コタケネズミはその竹林を耕して棲息地を拡大してきた。森で焼畑耕作を営んできたカレンの人びととその焼畑の森を耕してきたコタケネズミとのつきあいは、深くて長いのである。
コタケネズミ (学名:Cannomys badius)
コタケネズミ(Lesser Bamboo Rat)は、体長15~20センチメートル、体重0.5~0.8キログラムで、ネパール、アッサム、バングラデシュ北部、ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム北部に分布する。前頭に白斑があることが多い。アジア東部に分布している他のタケネズミ類(タケネズミ亜科Rhizomyinae)には、オオタケネズミ(Large Bamboo Rat, 学名: Rhizomys. sumatrensis)、シロゲタケネズミ(Hoary Bamboo Rat, 学名: R. pruinosus)、タケネズミ(Chinese Bamboo Rat, 学名:R. sinensis)がある。
コタケネズミ(Lesser Bamboo Rat)は、体長15~20センチメートル、体重0.5~0.8キログラムで、ネパール、アッサム、バングラデシュ北部、ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム北部に分布する。前頭に白斑があることが多い。アジア東部に分布している他のタケネズミ類(タケネズミ亜科Rhizomyinae)には、オオタケネズミ(Large Bamboo Rat, 学名: Rhizomys. sumatrensis)、シロゲタケネズミ(Hoary Bamboo Rat, 学名: R. pruinosus)、タケネズミ(Chinese Bamboo Rat, 学名:R. sinensis)がある。
また、夏がめぐってくると
高橋 絵里香(たかはし えりか) 東京大学大学院総合文化研究科
北欧の短い夏
フィンランドの夏は短い。
六月と七月、そして運よく天候がもてば八月は、フィンランド人が一年のうちでもっとも楽しみにしている季節だ。学生たちは「夏仕事」をすることで一年分の小遣い稼ぎをするし、森のなかや湖岸に建つ「夏小屋」とよばれる別荘に滞在する人も多い。
都会の喧騒を離れ、自然のなかで時間を過ごすのが大好きな彼らにとって、夏はキャンプのシーズンでもある。フィンランドの人口の八〇パーセント以上が所属する福音ルーテル派教会は、一四歳を迎えた少年少女たちを対象とする堅信礼キャンプの他に、若い母親、障害者、そして年金生活者向けのキャンプをそれぞれ開催している。キャンプといっても、テント生活を送るわけではない。キャンプセンターという郊外の施設で、寝泊りをするのである。
二人の同室者たち
フィンランド西南部の福祉施設で調査していたわたしは、地域の年金生活者のキャンプに毎年参加していた。ここでともに時間を過ごした人びとは、以後も何かとわたしを気にかけてくれた。祖父母が四〇人近くまとめてできたようなものである。だが、一年目と二年目のキャンプで同室だった二人のおばあさんは、わたしのことをもはや覚えてはいないだろう。
当時、ヒルダはその町の中心に位置する住宅街に一人で暮らし、エルマは「白樺の郷」という保護住宅に一人で暮らしていた。彼女たちは二人とも認知症を発していたのである。キャンプのスタッフがわたしに彼女たちと同室を割り当てたのは、ベッドメイキングなどの作業を手伝わせるだけでなく、何事か問題が起こったときのためだろう。
一瞬たりとも目を離してはいけない。わたしはそんな風に思い込んで、到着した彼女たちが荷物をほどくのを緊張しながら手伝った。最初のうち、わたしのつたないフィンランド語で会話する限りにおいて、彼女たちの受け答えに不自然な部分は見つからなかった。だが、すぐにおかしなことが起こった。
居室前の廊下に掃除用具置き場があったのだが、ヒルダとエルマはいつまでもその前に立っている。何をしているのかと尋ねてみると、エレベーターを待っているのだと言う。キャンプセンターは平屋で、掃除用具置き場の扉もごく普通のものだったのだが。
なるほど、これが「チホウ」というものか。以前にも、もっと深刻な認知症を抱える人びとと接する機会はあった。それでも彼女たちを間近に目にすると、胸がつまるような感覚におそわれる。例えば、一見すれば他のお年寄りたちと変わらない小奇麗な格好をしているが、じつは二人とも毎日同じブラウスとスカートなのだ。思い返してみれば、彼女たちの鞄は驚くほど小さく、他に服をもってきていなかった。キャンプに来る前に誰も荷造りを手伝ってくれる人がいなかったのだろうか。
フィンランドでは、お年寄りが自分の子ども世代と同居することは日本に比べて非常に少ない。たとえホームヘルパーが面倒を見ていて、昼間はデイケアに連れて行ってもらうとしても、彼らはふだん一人で暮らしている。わたしにはそれが、何だか気の毒なことに思われた。
月日が経つことの意味
しかし、キャンプの参加者たちはゲームや歌といったさまざまな娯楽をともに楽しむ。聖歌だけではなくさまざまなフォークソングを歌い、子どものころに覚えた詩を朗読する。詩をもっともよく暗誦していたのは、認知症のはずのエルマだった。
他のキャンプ参加者たちにとっても、二人は、毎日の献立を論評し合い、一緒に散歩をする同じキャンプの仲間だった。毎年顔を合わせるたびに、お互い少しずつ年を取り、メンバーの誰かが減っている。それでも彼らは、身体が許す限り皆で参加したいと、キャンプを一年でもっとも楽しみにしているのだ。
確かに、「老い」への不安は常に水面下にあって、キャンプの期間中にもときおりあらわれてくる。リディアというおばあさんが、蝋燭の消し忘れで最近アパートに小火(ぼや)を出したらしく、キャンプのスタッフに泣いて不安を打ち明けている姿を目にしたことがある。前年まで元気な様子でキャンプに参加していた様子と比べながら、彼らにとって月日が経つことの意味の重さをわたしは実感したものだ。
だが、わたしたちは皆、老いていく。誰もが不安を抱え、ときには独りで、ときには仲間と、日々を過ごしている。キャンプの期間中、お年寄りは「消化のために」と食後にセンターの周囲をぐるぐると行進する。施設を何周もする元気な人もいれば、すぐベンチに座り込んでお喋りを始める人もいる。それはまるで彼らの青春時代を想像させる情景で、「チホウ」や「健常」といったレッテルは場違いに思えた。
その後、ヒルダは老人ホームに入居し、エルマは今も「白樺の郷」に暮らしている。もうキャンプにも来なくなってしまった。彼女たちと顔を合わせても、わたしのことは忘れている。それでも、女学生のように顔を寄せ合って内緒話をしていた彼女たちの短い夏のことを、わたしは折に触れて思い出すのである。
フィンランドの夏は短い。
六月と七月、そして運よく天候がもてば八月は、フィンランド人が一年のうちでもっとも楽しみにしている季節だ。学生たちは「夏仕事」をすることで一年分の小遣い稼ぎをするし、森のなかや湖岸に建つ「夏小屋」とよばれる別荘に滞在する人も多い。
都会の喧騒を離れ、自然のなかで時間を過ごすのが大好きな彼らにとって、夏はキャンプのシーズンでもある。フィンランドの人口の八〇パーセント以上が所属する福音ルーテル派教会は、一四歳を迎えた少年少女たちを対象とする堅信礼キャンプの他に、若い母親、障害者、そして年金生活者向けのキャンプをそれぞれ開催している。キャンプといっても、テント生活を送るわけではない。キャンプセンターという郊外の施設で、寝泊りをするのである。
二人の同室者たち
フィンランド西南部の福祉施設で調査していたわたしは、地域の年金生活者のキャンプに毎年参加していた。ここでともに時間を過ごした人びとは、以後も何かとわたしを気にかけてくれた。祖父母が四〇人近くまとめてできたようなものである。だが、一年目と二年目のキャンプで同室だった二人のおばあさんは、わたしのことをもはや覚えてはいないだろう。
当時、ヒルダはその町の中心に位置する住宅街に一人で暮らし、エルマは「白樺の郷」という保護住宅に一人で暮らしていた。彼女たちは二人とも認知症を発していたのである。キャンプのスタッフがわたしに彼女たちと同室を割り当てたのは、ベッドメイキングなどの作業を手伝わせるだけでなく、何事か問題が起こったときのためだろう。
一瞬たりとも目を離してはいけない。わたしはそんな風に思い込んで、到着した彼女たちが荷物をほどくのを緊張しながら手伝った。最初のうち、わたしのつたないフィンランド語で会話する限りにおいて、彼女たちの受け答えに不自然な部分は見つからなかった。だが、すぐにおかしなことが起こった。
居室前の廊下に掃除用具置き場があったのだが、ヒルダとエルマはいつまでもその前に立っている。何をしているのかと尋ねてみると、エレベーターを待っているのだと言う。キャンプセンターは平屋で、掃除用具置き場の扉もごく普通のものだったのだが。
なるほど、これが「チホウ」というものか。以前にも、もっと深刻な認知症を抱える人びとと接する機会はあった。それでも彼女たちを間近に目にすると、胸がつまるような感覚におそわれる。例えば、一見すれば他のお年寄りたちと変わらない小奇麗な格好をしているが、じつは二人とも毎日同じブラウスとスカートなのだ。思い返してみれば、彼女たちの鞄は驚くほど小さく、他に服をもってきていなかった。キャンプに来る前に誰も荷造りを手伝ってくれる人がいなかったのだろうか。
フィンランドでは、お年寄りが自分の子ども世代と同居することは日本に比べて非常に少ない。たとえホームヘルパーが面倒を見ていて、昼間はデイケアに連れて行ってもらうとしても、彼らはふだん一人で暮らしている。わたしにはそれが、何だか気の毒なことに思われた。
月日が経つことの意味
しかし、キャンプの参加者たちはゲームや歌といったさまざまな娯楽をともに楽しむ。聖歌だけではなくさまざまなフォークソングを歌い、子どものころに覚えた詩を朗読する。詩をもっともよく暗誦していたのは、認知症のはずのエルマだった。
他のキャンプ参加者たちにとっても、二人は、毎日の献立を論評し合い、一緒に散歩をする同じキャンプの仲間だった。毎年顔を合わせるたびに、お互い少しずつ年を取り、メンバーの誰かが減っている。それでも彼らは、身体が許す限り皆で参加したいと、キャンプを一年でもっとも楽しみにしているのだ。
確かに、「老い」への不安は常に水面下にあって、キャンプの期間中にもときおりあらわれてくる。リディアというおばあさんが、蝋燭の消し忘れで最近アパートに小火(ぼや)を出したらしく、キャンプのスタッフに泣いて不安を打ち明けている姿を目にしたことがある。前年まで元気な様子でキャンプに参加していた様子と比べながら、彼らにとって月日が経つことの意味の重さをわたしは実感したものだ。
だが、わたしたちは皆、老いていく。誰もが不安を抱え、ときには独りで、ときには仲間と、日々を過ごしている。キャンプの期間中、お年寄りは「消化のために」と食後にセンターの周囲をぐるぐると行進する。施設を何周もする元気な人もいれば、すぐベンチに座り込んでお喋りを始める人もいる。それはまるで彼らの青春時代を想像させる情景で、「チホウ」や「健常」といったレッテルは場違いに思えた。
その後、ヒルダは老人ホームに入居し、エルマは今も「白樺の郷」に暮らしている。もうキャンプにも来なくなってしまった。彼女たちと顔を合わせても、わたしのことは忘れている。それでも、女学生のように顔を寄せ合って内緒話をしていた彼女たちの短い夏のことを、わたしは折に触れて思い出すのである。
編集後記
今年は民博開館30周年。今月の特集「森」の持つ長い歴史からみれば、わずかな時間である。しかし、森の木の1本1本を、これまで民博で活躍されてきた人びとにたとえるならば、民博にも森のような1個体だけではない、ひとつの共同体としての歴史がきざまれている。特集で山田氏が日本の森について指摘するように、民博もより存在感のある形にするために、さらなる模索を続けなければならないであろう。
昨年12月の30巻記念号に掲載された『月刊みんぱく』の350枚の表紙写真が、数倍の大きさに拡大されて、ポスターとして開館30周年のイベントなどで活躍している。館内では、この1年『月刊みんぱく』の内容や形に関する議論は続けられてきた。これまでのスタイルに満足せず、常に新たな形を追求しながら、とにかく走り続けなければならない。
民博にある約25万点の収蔵品が宝のもちぐされにならないように、今月号からシリーズ「モノ・グラフ」がスタートした。モノを中心に、そこからみえる人の生きかたの複雑さや面白さを紹介します。どうぞ御期待ください。(池谷和信)
昨年12月の30巻記念号に掲載された『月刊みんぱく』の350枚の表紙写真が、数倍の大きさに拡大されて、ポスターとして開館30周年のイベントなどで活躍している。館内では、この1年『月刊みんぱく』の内容や形に関する議論は続けられてきた。これまでのスタイルに満足せず、常に新たな形を追求しながら、とにかく走り続けなければならない。
民博にある約25万点の収蔵品が宝のもちぐされにならないように、今月号からシリーズ「モノ・グラフ」がスタートした。モノを中心に、そこからみえる人の生きかたの複雑さや面白さを紹介します。どうぞ御期待ください。(池谷和信)
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。