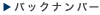月刊みんぱく 2008年5月号
2008年5月号
第32巻第5号通巻第368号
2008年5月5日発行
2008年5月5日発行
右? 左?
中野 不二男
ヘリコプターのローターの回転方向は、ヨーロッパ製の機種の場合、操縦席から見て時計回り(つまり右回り)。アメリカ製はその逆で、反時計回り(左回り)になっている。何故そうなのか、と聞かれたら「わかりません」としか答えられない。
ならば航空機のプロペラやジェット・エンジンもヘリと同じかというと、これがちがう。ヨーロッパ製(たとえばロールス・ロイス社等)は、エンジン本体の後部から見て反時計回り。アメリカ製(ジェネラル・ダイナミクス社等)なら時計回りになっている。ついでに日本も時計回りである。
こういう話を誰かにすると、かならず話題の連鎖がはじまる。まずはクルマの右ハンドルと左ハンドル、馬車の左側通行と右側通行。そして講釈と風呂敷の広げ合いだ。一般に御者は右手で鞭を振るから、右側を空けておきたい。だからイギリスでは馬車は左側通行、御者も右側に座っていた。それがクルマ文化に受け継がれ・・・。「じゃあ、アメリカは?」、「歩行者の場合は?」。で、エスカレータの立ち位置の、関西と関東のちがいに話がいたると、連鎖反応は振り出しにもどるのである。
どうして右文化と左文化にわかれるのか、たしかに不思議だ。江戸時代の日本では、右側通行だったという話もあるが、東海道五十三次に描かれている光景は、ほとんどごちゃごちゃとしか思えない。京都・三条大橋は右側通行のようにも見えるが、庄野や岡部、掛川の図は、左側通行だといわれても不思議ではない。武士の刀の鞘がぶつかるから、左側通行だったという話はよく耳にするが、伝統性を重視する剣道では、ふつう左側ですれちがう。つまり右側通行ということになる。
結局のところ、むかしはそれほどこだわりがなかったのではないだろうか。そういえば、ポンペイ遺跡の石畳に残る馬車の轍(わだち)も、車道の真ん中だったように思う。ならばジェット・エンジンの回転方向の、イギリスとアメリカのちがいは、どう説明づけられるのか。エンジン開発の現場技術者に聞いてみた。
「両国文化の、意地の張り合いですよ」
なるほど・・・。しかし自国の文化を考えると、やっぱり気になる。神社の参道は、真ん中が神様の通り道だ。そして手水舎(ちょうずや)はふつう左にある。ということは、日本は古来より左側通行だったのか・・・。また振り出しにもどってしまった。
なかの ふじお/1950年生まれ。科学・技術ジャーナリスト。宇宙航空研究開発機構(JAXA)招聘研究員。工学博士。1978年渡豪、シドニーのエンジニアリング会社技術部勤務のかたわら、連邦政府の委託・研究費援助のもとで、アボリジニーに関する調査研究をおこなう。1982年に帰国し執筆活動に入る。著作は『アボリジニーの国』(中央公論新社)など多数。
ならば航空機のプロペラやジェット・エンジンもヘリと同じかというと、これがちがう。ヨーロッパ製(たとえばロールス・ロイス社等)は、エンジン本体の後部から見て反時計回り。アメリカ製(ジェネラル・ダイナミクス社等)なら時計回りになっている。ついでに日本も時計回りである。
こういう話を誰かにすると、かならず話題の連鎖がはじまる。まずはクルマの右ハンドルと左ハンドル、馬車の左側通行と右側通行。そして講釈と風呂敷の広げ合いだ。一般に御者は右手で鞭を振るから、右側を空けておきたい。だからイギリスでは馬車は左側通行、御者も右側に座っていた。それがクルマ文化に受け継がれ・・・。「じゃあ、アメリカは?」、「歩行者の場合は?」。で、エスカレータの立ち位置の、関西と関東のちがいに話がいたると、連鎖反応は振り出しにもどるのである。
どうして右文化と左文化にわかれるのか、たしかに不思議だ。江戸時代の日本では、右側通行だったという話もあるが、東海道五十三次に描かれている光景は、ほとんどごちゃごちゃとしか思えない。京都・三条大橋は右側通行のようにも見えるが、庄野や岡部、掛川の図は、左側通行だといわれても不思議ではない。武士の刀の鞘がぶつかるから、左側通行だったという話はよく耳にするが、伝統性を重視する剣道では、ふつう左側ですれちがう。つまり右側通行ということになる。
結局のところ、むかしはそれほどこだわりがなかったのではないだろうか。そういえば、ポンペイ遺跡の石畳に残る馬車の轍(わだち)も、車道の真ん中だったように思う。ならばジェット・エンジンの回転方向の、イギリスとアメリカのちがいは、どう説明づけられるのか。エンジン開発の現場技術者に聞いてみた。
「両国文化の、意地の張り合いですよ」
なるほど・・・。しかし自国の文化を考えると、やっぱり気になる。神社の参道は、真ん中が神様の通り道だ。そして手水舎(ちょうずや)はふつう左にある。ということは、日本は古来より左側通行だったのか・・・。また振り出しにもどってしまった。
なかの ふじお/1950年生まれ。科学・技術ジャーナリスト。宇宙航空研究開発機構(JAXA)招聘研究員。工学博士。1978年渡豪、シドニーのエンジニアリング会社技術部勤務のかたわら、連邦政府の委託・研究費援助のもとで、アボリジニーに関する調査研究をおこなう。1982年に帰国し執筆活動に入る。著作は『アボリジニーの国』(中央公論新社)など多数。
開館三〇周年、そしてこれから(2)
先月号に引き続き、今月号では、開館三〇周年記念事業を踏まえ、今後どのように継承発展させていけばよいかを考えます。諸事業のなかで特に入館者に好評だった「ウィークエンド・サロン 研究者と話そう」を担当した韓敏先生、映画会・講演会に携わった飯田卓先生に、編集長がお話を伺いました。
韓 敏先生に聞く
―「ウィークエンド・サロン 研究者と話そう」はどのようにして始まったのですか?
推進企画実施部会では、まず、教職員全員からアンケートをとりました。あがってきた数十の提案のなかに、研究者が出てきて来館者に直接接して、自分の研究していることをアピールすれば良い、という提案が三件ほどあり、部会のなかで、関雄二先生とわたしが研究者主体のイベントを検討することになりました(のちに飯田卓先生が関先生の後任として加わっています)。
二人で相談していろいろ案を考えて、無料ゾーンのエントランス・ホールではなく、有料ゾーンの展示場の方が真剣な方が聞きに来るので効果がある、との意見を受けて、展示場でおこなうことになりました。そこで、入館者の気持ちがわかり、運営のノウハウをもっている千里文化財団にも協力してもらうことにしました。教員は五〇数名なので、来館者の多い週末で、映画会などとぶつからないよう六〇回開くことに決めました。実際には、新人の教員を含む五七名の教員全員、八名の名誉教授(加藤九祚、大給近達、藤井知昭、杉村棟、清水昭俊、栗田靖之、立川武蔵、藤井龍彦の各氏)と二人の外国人客員教授(韓福眞と劉明基の両氏)が参加して、計六二回を実施しました。
最初は、共通テーマを設定できないか、と提案がありましたが、教員それぞれのもちネタは異なるので、共通テーマでおこなうのは難しい。そこで、調査地の年中行事など季節感の出る話題や、収集・展示・研究にからんだテーマも含めることにしました。具体的な実施について、展示経験のある研究者なら展示場でやれば良いのですが、そうでない研究者でもできるパターン、例えば、パソコン画面を投影して講義する、休憩所でお茶を飲みながら話す、展示場にないモノを補うために収蔵庫から取り出した標本資料も組み合わせる、などさまざまなパターンを千里文化財団の方と一緒に考えました。収蔵庫から標本資料をもち出す際には、情報管理施設から大きな協力がえられて、とても助かりました。
―展示場にない資料を収蔵庫から補うのは、収蔵資料を活用するという点でも、意義があったと思います。名称が決まったのはどんないきさつですか?
週末におこなうので、「ウィークエンド・サロン」と関先生とわたしが最初に提案しました。わたしたちの感覚では、サロンは、一方的な講義とは違って語り合う場を指す、良い雰囲気のことばなのです。財団の方からは「研究者と話そう」が提案され、部会で投票してこれらを合わせた名称に決まりました。また記念事業の映像を記録することになり、この催し物については、大学院のRA(研究補助員)が担当することになりました。研究者の予定と同時進行でRAの予定を立てていきました。
―実施してみて、反応はどうでしたか?
以前からこうしたガイドツアー的な催しの必要性は論じられてきたようで、開館二〇周年では「民博周遊」を三日間したそうですが、その後なかなか定着しなかった。でも今回は三〇周年記念事業として、教員の全員参加で年間をとおしてやる、という大きな目標があったので実施したわけです。
でも実際にやってみると、三〇分程度で負担はあまり大きくないし、また講演会と違って、目の前で入館者と気楽に話せて、入館者の反応を見ながら話せるのは楽しい機会だったと、教員からは感想がありました。当初立てた予定が変更されたのは、後から企画されたシンポジウムのためなど、わずか四名だけで、教員の皆さん、とても協力的でした。入館者、教員の双方にとって良い企画だったのでしょう。
また、入館者の感想とアンケートからもわかるのですが、人類学・民族学に対する理解が深まった、研究者の顔がよく見えた、地域の様子がよくわかったなどの感想のほかに、今度の旅行の役に立つといった実用的な感想もありました。加藤九祚名誉教授のお話の際には、「先生のような研究者になるにはどうすればいいんですか」と質問する若者もおられました。その意味で、わたしの考えでは、「ウィークエンド・サロン」は、博物館をもつ研究機関としてのアピールのみならず、大学院入学者募集の宣伝にも生かせるのではないかと思います。
―「ウィークエンド・サロン」の映像記録をうまく使えれば良いですね。
藤井龍彦名誉教授のときは、土曜日の朝一番でしかも雨の日なのに、十数名も入館者があって、東京から建築関係の学生が駆けつけてくれました。その人が言うには、アンデスの服装の色使いが建築の色使いに相通じる点でとても参考になる、東京には、インスピレーションをえられる場所が少ない、関西ならこういう場所がある、と言っておられました。ですから、民博はもっと自信と自覚をもって文化の発信をおこなったら良いと思います。
―「ウィークエンド・サロン」は画期的な試みだったので、本年の四月以降も定例化することになったようですね。ありがとうございました。
推進企画実施部会では、まず、教職員全員からアンケートをとりました。あがってきた数十の提案のなかに、研究者が出てきて来館者に直接接して、自分の研究していることをアピールすれば良い、という提案が三件ほどあり、部会のなかで、関雄二先生とわたしが研究者主体のイベントを検討することになりました(のちに飯田卓先生が関先生の後任として加わっています)。
二人で相談していろいろ案を考えて、無料ゾーンのエントランス・ホールではなく、有料ゾーンの展示場の方が真剣な方が聞きに来るので効果がある、との意見を受けて、展示場でおこなうことになりました。そこで、入館者の気持ちがわかり、運営のノウハウをもっている千里文化財団にも協力してもらうことにしました。教員は五〇数名なので、来館者の多い週末で、映画会などとぶつからないよう六〇回開くことに決めました。実際には、新人の教員を含む五七名の教員全員、八名の名誉教授(加藤九祚、大給近達、藤井知昭、杉村棟、清水昭俊、栗田靖之、立川武蔵、藤井龍彦の各氏)と二人の外国人客員教授(韓福眞と劉明基の両氏)が参加して、計六二回を実施しました。
最初は、共通テーマを設定できないか、と提案がありましたが、教員それぞれのもちネタは異なるので、共通テーマでおこなうのは難しい。そこで、調査地の年中行事など季節感の出る話題や、収集・展示・研究にからんだテーマも含めることにしました。具体的な実施について、展示経験のある研究者なら展示場でやれば良いのですが、そうでない研究者でもできるパターン、例えば、パソコン画面を投影して講義する、休憩所でお茶を飲みながら話す、展示場にないモノを補うために収蔵庫から取り出した標本資料も組み合わせる、などさまざまなパターンを千里文化財団の方と一緒に考えました。収蔵庫から標本資料をもち出す際には、情報管理施設から大きな協力がえられて、とても助かりました。
―展示場にない資料を収蔵庫から補うのは、収蔵資料を活用するという点でも、意義があったと思います。名称が決まったのはどんないきさつですか?
週末におこなうので、「ウィークエンド・サロン」と関先生とわたしが最初に提案しました。わたしたちの感覚では、サロンは、一方的な講義とは違って語り合う場を指す、良い雰囲気のことばなのです。財団の方からは「研究者と話そう」が提案され、部会で投票してこれらを合わせた名称に決まりました。また記念事業の映像を記録することになり、この催し物については、大学院のRA(研究補助員)が担当することになりました。研究者の予定と同時進行でRAの予定を立てていきました。
―実施してみて、反応はどうでしたか?
以前からこうしたガイドツアー的な催しの必要性は論じられてきたようで、開館二〇周年では「民博周遊」を三日間したそうですが、その後なかなか定着しなかった。でも今回は三〇周年記念事業として、教員の全員参加で年間をとおしてやる、という大きな目標があったので実施したわけです。
でも実際にやってみると、三〇分程度で負担はあまり大きくないし、また講演会と違って、目の前で入館者と気楽に話せて、入館者の反応を見ながら話せるのは楽しい機会だったと、教員からは感想がありました。当初立てた予定が変更されたのは、後から企画されたシンポジウムのためなど、わずか四名だけで、教員の皆さん、とても協力的でした。入館者、教員の双方にとって良い企画だったのでしょう。
また、入館者の感想とアンケートからもわかるのですが、人類学・民族学に対する理解が深まった、研究者の顔がよく見えた、地域の様子がよくわかったなどの感想のほかに、今度の旅行の役に立つといった実用的な感想もありました。加藤九祚名誉教授のお話の際には、「先生のような研究者になるにはどうすればいいんですか」と質問する若者もおられました。その意味で、わたしの考えでは、「ウィークエンド・サロン」は、博物館をもつ研究機関としてのアピールのみならず、大学院入学者募集の宣伝にも生かせるのではないかと思います。
―「ウィークエンド・サロン」の映像記録をうまく使えれば良いですね。
藤井龍彦名誉教授のときは、土曜日の朝一番でしかも雨の日なのに、十数名も入館者があって、東京から建築関係の学生が駆けつけてくれました。その人が言うには、アンデスの服装の色使いが建築の色使いに相通じる点でとても参考になる、東京には、インスピレーションをえられる場所が少ない、関西ならこういう場所がある、と言っておられました。ですから、民博はもっと自信と自覚をもって文化の発信をおこなったら良いと思います。
―「ウィークエンド・サロン」は画期的な試みだったので、本年の四月以降も定例化することになったようですね。ありがとうございました。
飯田 卓先生に聞く
―飯田先生が中心的にかかわられたのはどんな事業でしたか?
二〇〇七年一〇月に東京でおこなった公開講演会「国際化時代の食文化」と、特別展「オセアニア大航海展」にちなんで一一月に開催した、みんぱく映画会「クラ―西太平洋の遠洋航海者」などです。映画会には、映像作家の市岡康子さんにも講演をお願いしました。そのほか、年間を通じた「ウィークエンド・サロン」にもかかわりましたが、これは教員全員と、それをとりまとめてくださった韓先生のおかげでできた事業です。
講演会は、毎年開催してきたものです。今年はとくに、開館三〇周年記念事業という冠を付けて、石毛直道先生(前館長)、朝倉敏夫先生(当時民族文化研究部長)、小長谷有紀先生(研究戦略センター長)に講演していただきました。いずれもとくにご多忙な先生方ですが、記念事業ということで無理を承諾していただけました。三〇周年だからこそ、例年の企画をとくに華やかにすることができました。
映画会も、例年おこなってきた催しです。今年は、秋に複数の映画会が連続して開かれたので、「みんぱくシネマ」という名称を与えて、一連のものとして位置づけました。博物館とは距離をおきがちな映画ファンに、民博に来てくださいと呼びかけたわけです。これも、偶然に出てきたアイデアとはいえ、三〇周年でなければ実現しにくい広報だったと思います。
文化人類学者と映像製作の三〇年
映画会「クラ」は、わたしがかかわっていた「オセアニア大航海展」の実行委員会で発案されたものです。展示期間中に、展示テーマにかかわる作品をぜひ上映したいというわけです。発案者はわたしではなかったのですが、わたしは、この映画を制作された市岡康子先生とお目にかかったことがあり、研究にかかわる連絡も続けていました。マスメディアや電子メディアについて研究会をわたしたちがおこなっていたとき、彼女を研究会にお招きしたことがあったのです。そこで、わたしが映画会と講演会のプランを立て、それを市岡先生にお話しして、映画会にあわせて民博に来ていただくことになりました。当日は、撮影時の状況などを、わたしとの掛け合いでお話しいただきました。そのなかでは、文化人類学の古典から制作を思い立ったこと、知り合いの文化人類学者にさまざまな協力をえたことなど、映像作りと文化人類学のさまざまな関係を伺うことができました。
この作品は、一九六六年から一九九〇年まで続いた長寿番組「すばらしい世界旅行」(日本テレビ系)で、一九七一年にはじめて放映されました。そして、その二年後に、国際人類学・民族学連合大会でも上映されました。「すばらしい世界旅行」は、民博が開館した三〇年前にも大きな影響力をもっていたので、「クラ」の上映は、文化人類学を三〇年間支えてきた民博の記念事業としてもふさわしい企画になったと思います。
―文化人類学者と映像を作る立場の連携は、その後の三〇年間にどのように変化したのですか?
別々の道にわかれてしまったと思います。市岡さんが仕事を始められたころは、文化人類学の調査に映画取材やテレビ取材が一緒について行くというやり方の名残があった。このやり方は、文化人類学者と映像制作者、双方にとって実利をもたらしていました。文化人類学者は、自分たちの活動を広報してもらえるし、資金の一部をまかなってもらうことができる。映像制作者は、取材のコーディネートをしてもらえるし、海外に出る許可を取りやすくなる。しかしその後、海外渡航が自由になると、映像制作者が文化人類学者に同行する意義が薄らいできて、どんどん独自取材に出るようになった。そのうちに、放映された独自取材番組の正確さに対して、一部の文化人類学者が文句をつけるということが始まった。そこで映像制作者側のガードがどんどん高くなって、文化人類学者に接触することがなくなった。今放映中のテレビ番組で、文化人類学者があてにされることはほとんどないと思います。
―そういう状況を見て、飯田さんは、もう一度、お互いに乗り入れできる下地を作りたいと考えておられるのではないですか?
作りたいとは思うのです。もう一度、協働を実現しないといけない。そういう意見を新聞で取り上げてもらったこともあります。しかし、そうなるまでには、いろいろなことをしなければと思います。とくに、お互いが何を目指しているか、文化人類学者も映像制作者も理解し合うことが必要なのですが、その土壌がまだ育っていないと思うんです。
難しいのは、視聴者や広告主の期待にこたえることがテレビ番組の最重要課題だということです。そのために、NHKも含めてテレビ番組にかかわる人たちは、成果を短期間で出さなければならない。そこが、長い時間幅で仕事をする研究者と大きく異なる点です。
―わたしがかかわった「科学映画祭」で招聘した海外の映画制作者に聞いたところによると、欧米では、商業ベースでなく研究者との共同での映画作りを支援するNPOや資金があったりするようです。日本でこうした仕組みが育っていないのは残念ですね。いくつもの大学が共同してファンドを作るなどの動きがあってもいいんでしょうが。
四〇周年、五〇周年につなげるアーカイブズ
―事業を振り返ってみて、今後につなげていくために、何か教訓はあるでしょうか?
推進企画実施部会が立ち上がった当初、その部会に入ったわたしは、何か特別なイベントを考えねばならないのだろうと考えていました。しかし、必ずしもそうではない。毎年やっている事業でも、予算や人員の制約のために、実現したくてもできないアイデアがあるはずです。そうしたアイデアのいくつかが、三〇周年の機会に実現できたのではないでしょうか。この考え方は、今後の四〇周年、五〇周年の記念事業を企画するうえで生かしていけばいい。ふだんからアイデアを蓄積しておくのが良い、と考えるに至りました。
―それこそ飯田先生は、四〇周年、五〇周年の際には活躍してもらわないといけない世代ですからね。この考えは、最初からあったんですか?
いえいえ、いろいろな事業が終わってから気づいたことなんです。そこで、五〇周年記念事業委員会を今から作っておこうと、何人かの同僚に提案したことがあります。今のところ、早すぎるためかあまり賛同をえられていませんが。
―今からやっておけば大変でなくなる、という訳ですね。
そう思いますね。梅棹忠夫先生たちが一九六四年ごろに「万国博を考える会」を立ち上げたときも、全体のテーマとなる文章を起草するなんて大それたことは全然考えてなくて、万博というのはどういうものやろうと、遊びながら考えるところから始めたと思うんです。それは結局、数年後に実現するけれども、それは結果です。最初は、時間的な目標は設定していなかったはずです。やりたいことを考えていれば、機会ができたときにあわてなくてすむ。遊び心も、大事なポイントです。遊び心がないと、長い期間、考えているあいだに疲れてしまうでしょう。
―メディア環境も含めて、今から二〇年後の状況はなかなか考えつかないし、そもそも民博が今のかたちであるかどうかもわからないですけどね。その他の教訓は?
わたしが当時、所属していた研究戦略センターとの関係で言えば、民博の外の研究者に対して、民博がはたしてきた役割をもっと打ち出せればよかった。とくに、三〇年間の活動を学会に印象づけるような企画を、三〇年前すでに現役だった研究者もまじえて開いていれば、もっとよかったと思います。もっとも、文化人類学会と公式なかたちで連携する動きは、始まって間がないので、無理もないのでしょう。これからの二〇年のあいだには、考えていかなければならないと思います。
五〇周年事業を考えるときには、民博の創設時に館員だった方々にご相談することはできないでしょう。五〇年間すべての蓄積を出すのは、難しいかもしれない。だからこそ、今から構想を練る必要があると思います。
―そのためにも、今回の事業の記録を、アーカイブズ化しておくのが良いでしょうね。
こうして『月刊みんぱく』で取り上げてもらうのも、その一手段だと思います。『月刊みんぱく』自体が貴重なアーカイブズです。ぼくの知らないむかしの民博のことも、この雑誌を開くといろいろ知ることができる。
―『月刊みんぱく』の三〇年という蓄積も、すごい意味があるかもしれませんね。
『月刊みんぱく』には、アーカイブズ機能を生かし続けてほしいですね。収蔵庫に入れない入館者に、どんなモノがあるか、三階のコンピュータ室や図書室がどうなっているか、どのように利用できるか、などを知らせることも、積極的に取り組んでほしいと思います。民博の裏方については、根強い民博ファンも興味をもつはずです。
最近、古本屋で、『博物館と情報』(中公新書)を手に入れました。これは、梅棹先生が『月刊みんぱく』でおこなった対談をまとめたもののひとつです。これを読むと、民博の広報では、個人の感想がくちコミで伝わっていくようなプロセスが重要だと書いてある(『月刊みんぱく』一九八一年九月号「博物館と広報活動」)。なるほどと思いました。博物館は、足を運んでもらってはじめて機能するメディアだから、足を運んでもらうために、どんな人がどんなふうにそれを面白がっているかが伝わらないといけない。そのためには、個人的な感想も含めて情報を伝えるくちコミは、とても重要です。
しかし、われわれ館員がくちコミだけで広報できるかというと、それは難しい。われわれがいちばん頼りにしている広報企画室では、職員が数年で異動してしまうので、効果的なくちコミを発信できない。そうなると、長期に在職する教員の役割が重要になりますが、本務である研究は尊重しないといけない。けっきょく、教員各人が現在おこなっている以上のくちコミ広報は難しい、それが大きな課題です。くちコミを業務化するというのは、そもそも無理なのかもしれませんが。
―将来へ向けての展望なども語っていただき、ありがとうございました。
二〇〇七年一〇月に東京でおこなった公開講演会「国際化時代の食文化」と、特別展「オセアニア大航海展」にちなんで一一月に開催した、みんぱく映画会「クラ―西太平洋の遠洋航海者」などです。映画会には、映像作家の市岡康子さんにも講演をお願いしました。そのほか、年間を通じた「ウィークエンド・サロン」にもかかわりましたが、これは教員全員と、それをとりまとめてくださった韓先生のおかげでできた事業です。
講演会は、毎年開催してきたものです。今年はとくに、開館三〇周年記念事業という冠を付けて、石毛直道先生(前館長)、朝倉敏夫先生(当時民族文化研究部長)、小長谷有紀先生(研究戦略センター長)に講演していただきました。いずれもとくにご多忙な先生方ですが、記念事業ということで無理を承諾していただけました。三〇周年だからこそ、例年の企画をとくに華やかにすることができました。
映画会も、例年おこなってきた催しです。今年は、秋に複数の映画会が連続して開かれたので、「みんぱくシネマ」という名称を与えて、一連のものとして位置づけました。博物館とは距離をおきがちな映画ファンに、民博に来てくださいと呼びかけたわけです。これも、偶然に出てきたアイデアとはいえ、三〇周年でなければ実現しにくい広報だったと思います。
文化人類学者と映像製作の三〇年
映画会「クラ」は、わたしがかかわっていた「オセアニア大航海展」の実行委員会で発案されたものです。展示期間中に、展示テーマにかかわる作品をぜひ上映したいというわけです。発案者はわたしではなかったのですが、わたしは、この映画を制作された市岡康子先生とお目にかかったことがあり、研究にかかわる連絡も続けていました。マスメディアや電子メディアについて研究会をわたしたちがおこなっていたとき、彼女を研究会にお招きしたことがあったのです。そこで、わたしが映画会と講演会のプランを立て、それを市岡先生にお話しして、映画会にあわせて民博に来ていただくことになりました。当日は、撮影時の状況などを、わたしとの掛け合いでお話しいただきました。そのなかでは、文化人類学の古典から制作を思い立ったこと、知り合いの文化人類学者にさまざまな協力をえたことなど、映像作りと文化人類学のさまざまな関係を伺うことができました。
この作品は、一九六六年から一九九〇年まで続いた長寿番組「すばらしい世界旅行」(日本テレビ系)で、一九七一年にはじめて放映されました。そして、その二年後に、国際人類学・民族学連合大会でも上映されました。「すばらしい世界旅行」は、民博が開館した三〇年前にも大きな影響力をもっていたので、「クラ」の上映は、文化人類学を三〇年間支えてきた民博の記念事業としてもふさわしい企画になったと思います。
―文化人類学者と映像を作る立場の連携は、その後の三〇年間にどのように変化したのですか?
別々の道にわかれてしまったと思います。市岡さんが仕事を始められたころは、文化人類学の調査に映画取材やテレビ取材が一緒について行くというやり方の名残があった。このやり方は、文化人類学者と映像制作者、双方にとって実利をもたらしていました。文化人類学者は、自分たちの活動を広報してもらえるし、資金の一部をまかなってもらうことができる。映像制作者は、取材のコーディネートをしてもらえるし、海外に出る許可を取りやすくなる。しかしその後、海外渡航が自由になると、映像制作者が文化人類学者に同行する意義が薄らいできて、どんどん独自取材に出るようになった。そのうちに、放映された独自取材番組の正確さに対して、一部の文化人類学者が文句をつけるということが始まった。そこで映像制作者側のガードがどんどん高くなって、文化人類学者に接触することがなくなった。今放映中のテレビ番組で、文化人類学者があてにされることはほとんどないと思います。
―そういう状況を見て、飯田さんは、もう一度、お互いに乗り入れできる下地を作りたいと考えておられるのではないですか?
作りたいとは思うのです。もう一度、協働を実現しないといけない。そういう意見を新聞で取り上げてもらったこともあります。しかし、そうなるまでには、いろいろなことをしなければと思います。とくに、お互いが何を目指しているか、文化人類学者も映像制作者も理解し合うことが必要なのですが、その土壌がまだ育っていないと思うんです。
難しいのは、視聴者や広告主の期待にこたえることがテレビ番組の最重要課題だということです。そのために、NHKも含めてテレビ番組にかかわる人たちは、成果を短期間で出さなければならない。そこが、長い時間幅で仕事をする研究者と大きく異なる点です。
―わたしがかかわった「科学映画祭」で招聘した海外の映画制作者に聞いたところによると、欧米では、商業ベースでなく研究者との共同での映画作りを支援するNPOや資金があったりするようです。日本でこうした仕組みが育っていないのは残念ですね。いくつもの大学が共同してファンドを作るなどの動きがあってもいいんでしょうが。
四〇周年、五〇周年につなげるアーカイブズ
―事業を振り返ってみて、今後につなげていくために、何か教訓はあるでしょうか?
推進企画実施部会が立ち上がった当初、その部会に入ったわたしは、何か特別なイベントを考えねばならないのだろうと考えていました。しかし、必ずしもそうではない。毎年やっている事業でも、予算や人員の制約のために、実現したくてもできないアイデアがあるはずです。そうしたアイデアのいくつかが、三〇周年の機会に実現できたのではないでしょうか。この考え方は、今後の四〇周年、五〇周年の記念事業を企画するうえで生かしていけばいい。ふだんからアイデアを蓄積しておくのが良い、と考えるに至りました。
―それこそ飯田先生は、四〇周年、五〇周年の際には活躍してもらわないといけない世代ですからね。この考えは、最初からあったんですか?
いえいえ、いろいろな事業が終わってから気づいたことなんです。そこで、五〇周年記念事業委員会を今から作っておこうと、何人かの同僚に提案したことがあります。今のところ、早すぎるためかあまり賛同をえられていませんが。
―今からやっておけば大変でなくなる、という訳ですね。
そう思いますね。梅棹忠夫先生たちが一九六四年ごろに「万国博を考える会」を立ち上げたときも、全体のテーマとなる文章を起草するなんて大それたことは全然考えてなくて、万博というのはどういうものやろうと、遊びながら考えるところから始めたと思うんです。それは結局、数年後に実現するけれども、それは結果です。最初は、時間的な目標は設定していなかったはずです。やりたいことを考えていれば、機会ができたときにあわてなくてすむ。遊び心も、大事なポイントです。遊び心がないと、長い期間、考えているあいだに疲れてしまうでしょう。
―メディア環境も含めて、今から二〇年後の状況はなかなか考えつかないし、そもそも民博が今のかたちであるかどうかもわからないですけどね。その他の教訓は?
わたしが当時、所属していた研究戦略センターとの関係で言えば、民博の外の研究者に対して、民博がはたしてきた役割をもっと打ち出せればよかった。とくに、三〇年間の活動を学会に印象づけるような企画を、三〇年前すでに現役だった研究者もまじえて開いていれば、もっとよかったと思います。もっとも、文化人類学会と公式なかたちで連携する動きは、始まって間がないので、無理もないのでしょう。これからの二〇年のあいだには、考えていかなければならないと思います。
五〇周年事業を考えるときには、民博の創設時に館員だった方々にご相談することはできないでしょう。五〇年間すべての蓄積を出すのは、難しいかもしれない。だからこそ、今から構想を練る必要があると思います。
―そのためにも、今回の事業の記録を、アーカイブズ化しておくのが良いでしょうね。
こうして『月刊みんぱく』で取り上げてもらうのも、その一手段だと思います。『月刊みんぱく』自体が貴重なアーカイブズです。ぼくの知らないむかしの民博のことも、この雑誌を開くといろいろ知ることができる。
―『月刊みんぱく』の三〇年という蓄積も、すごい意味があるかもしれませんね。
『月刊みんぱく』には、アーカイブズ機能を生かし続けてほしいですね。収蔵庫に入れない入館者に、どんなモノがあるか、三階のコンピュータ室や図書室がどうなっているか、どのように利用できるか、などを知らせることも、積極的に取り組んでほしいと思います。民博の裏方については、根強い民博ファンも興味をもつはずです。
最近、古本屋で、『博物館と情報』(中公新書)を手に入れました。これは、梅棹先生が『月刊みんぱく』でおこなった対談をまとめたもののひとつです。これを読むと、民博の広報では、個人の感想がくちコミで伝わっていくようなプロセスが重要だと書いてある(『月刊みんぱく』一九八一年九月号「博物館と広報活動」)。なるほどと思いました。博物館は、足を運んでもらってはじめて機能するメディアだから、足を運んでもらうために、どんな人がどんなふうにそれを面白がっているかが伝わらないといけない。そのためには、個人的な感想も含めて情報を伝えるくちコミは、とても重要です。
しかし、われわれ館員がくちコミだけで広報できるかというと、それは難しい。われわれがいちばん頼りにしている広報企画室では、職員が数年で異動してしまうので、効果的なくちコミを発信できない。そうなると、長期に在職する教員の役割が重要になりますが、本務である研究は尊重しないといけない。けっきょく、教員各人が現在おこなっている以上のくちコミ広報は難しい、それが大きな課題です。くちコミを業務化するというのは、そもそも無理なのかもしれませんが。
―将来へ向けての展望なども語っていただき、ありがとうございました。
熱帯地方で重ね着するヘレロ
舗装された道路が一直線に伸びている。あたりは地平線まで灌木と草からなる、雄大ではあるが単調なボツワナの大地。朝晩は涼しいが、日中の気温は四〇度近くになることもある。そんな暑さのなかで、厚着をしている女性たちを初めて見たときには驚いた。しかも、それが黄色やピンクなどのカラフルな服装なので、彼女らの存在はやけに目立っていた。彼女らは、ナミビアからボツワナにかけて暮らすヘレロ族の女性であり、いったいどのような理由で厚着をしているのであろうか。
アフリカの人びとは裸族と思われがちであるが、彼女らの衣服の文化を民博の展示をとおして紹介したいと思い、一九九六年にわたしはヘレロの暮らす地域を広くまわって衣装を集めたことがある。ナミビアの首都ウインドホックでは、その中心部で自らの民族衣装を身につけ、観光客相手にそれをかたちづくった人形を売っている人に出会った。彼女らは、周囲の人びとが洋式化するなかで、伝統的な衣装を身につけた人形に経済的な価値を見出していたのだ。また都市に住む若い女性ではその衣装を身につけている人は減ったものの、結婚式や祭りなどの際に着るために、家のなかに大切に保管しているのである。
ボツワナ北部に位置するマウンの町中では、さまざまな民族が暮らしているが、服装からヘレロの女性であることは一目でわかる。彼女らは、銀行や買い物に行くときや洗濯をする際にも衣装を身につけている。わたしは、町の一画で彼女らが集住している場所を訪ね、帽子や数枚の下着(オンドロ)を含めて、ある女性の服装をワンセット購入することができた。色彩豊かでゆったりとした長いドレスは、オシカイバとよばれる。これは、さまざまな色の布切れを組み合わせており、重量があり、洗濯が困難で、作るのに費用がかさむという。また、その模様はそれぞれの世代を反映するように、時代とともに変わってきているが、それを縫うことによって女性の創造力や技術を示しているという。さらにそれは既婚の印となり、女性が家の仕事に責任をもち、自分たちの文化を継承するように子どもを育てることをも意味しているのだ。
その一方で、歴史文献を渉猟(しょうりょう)して衣装の由来などを調べてみると、伝統的なかたちの衣装は一九世紀にまでさかのぼることができた。当時、ルター派の宣教師たちがヘレロの土地(現在のナミビア)にやってきた結果、多くのヘレロがキリスト教徒になった。そのころに、ルター派のドイツ人宣教師の妻の衣装をまねたことで、現在のヘレロの衣装が生まれたという。その後、彼女らの土地を支配しようとするドイツに対するヘレロの反乱が生じたこともあって、ドイツ軍はヘレロを虐殺し絶滅させようと企てたのである。その際に、ヘレロの一部がボツワナに逃げたが、どうもドイツ軍との戦争のなかで虐殺というヘレロ文化が危機に瀕しているときに、この衣装が広まっていったようなのである。
このように、ヘレロ女性の衣服は、単なるカラフルな衣装にとどまらず民族文化の継承と民族意識を示すシンボルとして使われてきた。一時はドイツ軍によって絶滅を余儀なくされつつあった民族ではあるが、苦難に満ちた歴史のなかで鮮やかな衣装が生まれたのである。
アフリカの人びとは裸族と思われがちであるが、彼女らの衣服の文化を民博の展示をとおして紹介したいと思い、一九九六年にわたしはヘレロの暮らす地域を広くまわって衣装を集めたことがある。ナミビアの首都ウインドホックでは、その中心部で自らの民族衣装を身につけ、観光客相手にそれをかたちづくった人形を売っている人に出会った。彼女らは、周囲の人びとが洋式化するなかで、伝統的な衣装を身につけた人形に経済的な価値を見出していたのだ。また都市に住む若い女性ではその衣装を身につけている人は減ったものの、結婚式や祭りなどの際に着るために、家のなかに大切に保管しているのである。
ボツワナ北部に位置するマウンの町中では、さまざまな民族が暮らしているが、服装からヘレロの女性であることは一目でわかる。彼女らは、銀行や買い物に行くときや洗濯をする際にも衣装を身につけている。わたしは、町の一画で彼女らが集住している場所を訪ね、帽子や数枚の下着(オンドロ)を含めて、ある女性の服装をワンセット購入することができた。色彩豊かでゆったりとした長いドレスは、オシカイバとよばれる。これは、さまざまな色の布切れを組み合わせており、重量があり、洗濯が困難で、作るのに費用がかさむという。また、その模様はそれぞれの世代を反映するように、時代とともに変わってきているが、それを縫うことによって女性の創造力や技術を示しているという。さらにそれは既婚の印となり、女性が家の仕事に責任をもち、自分たちの文化を継承するように子どもを育てることをも意味しているのだ。
その一方で、歴史文献を渉猟(しょうりょう)して衣装の由来などを調べてみると、伝統的なかたちの衣装は一九世紀にまでさかのぼることができた。当時、ルター派の宣教師たちがヘレロの土地(現在のナミビア)にやってきた結果、多くのヘレロがキリスト教徒になった。そのころに、ルター派のドイツ人宣教師の妻の衣装をまねたことで、現在のヘレロの衣装が生まれたという。その後、彼女らの土地を支配しようとするドイツに対するヘレロの反乱が生じたこともあって、ドイツ軍はヘレロを虐殺し絶滅させようと企てたのである。その際に、ヘレロの一部がボツワナに逃げたが、どうもドイツ軍との戦争のなかで虐殺というヘレロ文化が危機に瀕しているときに、この衣装が広まっていったようなのである。
このように、ヘレロ女性の衣服は、単なるカラフルな衣装にとどまらず民族文化の継承と民族意識を示すシンボルとして使われてきた。一時はドイツ軍によって絶滅を余儀なくされつつあった民族ではあるが、苦難に満ちた歴史のなかで鮮やかな衣装が生まれたのである。
向き合うふたつの博物館-公共空間の共有をめざして
台湾の博物館と聞いて、故宮(正式名称は国立故宮博物院)を思い浮かべる人は多いであろう。一九六五年、文化大革命の端緒とされる姚文元(ヤオウェンユェン)の評論が上海で発表された二日後、台北の郊外に故宮は完成した。さまざまな経緯の末、北京の紫禁城から台北まで運ばれた中国王朝の膨大なコレクションが、台湾はもとより世界を代表する博物館である故宮の根幹をなしてきた。
とはいえ、台湾の民主化、それにともなう台湾・中国関係の複雑化は、数多くの「宝物」をして中華文明を雄弁に語らしめてきた故宮の役割に少なからず影響を与えた。結果、故宮は約一〇年間の準備期間を経て、二〇〇六年一二月に大規模なリニューアルを完成させた。来館者が入場しやすい出入口、各国語への対応、中国史偏重から資料重視の展示構成、子どものための展示場とマルチメディア情報展示の整備計画等、来館者の存在を強く意識した変更が随所に取り入れられていった。リニューアルの前と後に故宮を訪れている筆者に言わせれば、「貴重な文物を見せてやる」から「大切な資料を見てもらう」へ態度が変化したということである。じっくりと時間をかけたリニューアルの結論は来館者を大切にするということだったのだろう。
文明の押し売りをやめた故宮から、道路をはさみ徒歩五分くらいの場所に台湾の別の顔を見せてくれる博物館がある。順益台湾原住民博物館(以下順益)である。順益は台湾の自動車関連企業のメセナ活動で作られた博物館で、先住民である台湾原住民の文化や社会の様子を、展示や社会連携活動をとおして伝えていくことを目的として一九九六年に開館した。常設展示だけでなく、企画展示会やDIY教室(ワークショップ)を重ね、来館者重視の姿勢を一貫して取り続けてきた。また、原住民学生への奨学金の支給、研究機関や大学への研究費の寄付、原住民関連出版物の発行など、原住民文化の振興や研究に与えた影響や貢献は大きい。
人口の大半を漢族系の住人がしめるものの、台湾独自の文化として漢文化をかかげることは大陸中国との関係において微妙なニュアンスをもつ。一方で、原住民文化は台湾で生まれ育まれてきたという考え方は社会のなかでも受け入れられやすい。そういった考えが政治目的にも利用されることもあるが、長いあいだ、マイノリティとして社会に位置づけられてきた台湾原住民が、台湾アイデンティティの一翼を担うようになったことは社会の変化を如実にあらわしている。
国宝級の文物を収蔵し展示する国立の故宮。総人口の二パーセントほどの原住民の人びとの伝統文化を日常の生活用具を中心に伝える企業メセナの順益。ある意味、非常に対照的なふたつの博物館は、両館をシャトルバスでつなぎ、共通の入場券を発行する計画を進めている。一人でも多くの人にどちらの博物館も見てもらいたい。一人でも多くの人が集える公共空間を共有しよう。そんな実践的な試みが向き合うふたつの博物館のあいだではじまっている。「博物館や学芸員の権威性」、「民族博物館のもつ排他性」といった議論とは縁遠い、博物館の現場に生きる人たちの本音をそこに感じることができる。
とはいえ、台湾の民主化、それにともなう台湾・中国関係の複雑化は、数多くの「宝物」をして中華文明を雄弁に語らしめてきた故宮の役割に少なからず影響を与えた。結果、故宮は約一〇年間の準備期間を経て、二〇〇六年一二月に大規模なリニューアルを完成させた。来館者が入場しやすい出入口、各国語への対応、中国史偏重から資料重視の展示構成、子どものための展示場とマルチメディア情報展示の整備計画等、来館者の存在を強く意識した変更が随所に取り入れられていった。リニューアルの前と後に故宮を訪れている筆者に言わせれば、「貴重な文物を見せてやる」から「大切な資料を見てもらう」へ態度が変化したということである。じっくりと時間をかけたリニューアルの結論は来館者を大切にするということだったのだろう。
文明の押し売りをやめた故宮から、道路をはさみ徒歩五分くらいの場所に台湾の別の顔を見せてくれる博物館がある。順益台湾原住民博物館(以下順益)である。順益は台湾の自動車関連企業のメセナ活動で作られた博物館で、先住民である台湾原住民の文化や社会の様子を、展示や社会連携活動をとおして伝えていくことを目的として一九九六年に開館した。常設展示だけでなく、企画展示会やDIY教室(ワークショップ)を重ね、来館者重視の姿勢を一貫して取り続けてきた。また、原住民学生への奨学金の支給、研究機関や大学への研究費の寄付、原住民関連出版物の発行など、原住民文化の振興や研究に与えた影響や貢献は大きい。
人口の大半を漢族系の住人がしめるものの、台湾独自の文化として漢文化をかかげることは大陸中国との関係において微妙なニュアンスをもつ。一方で、原住民文化は台湾で生まれ育まれてきたという考え方は社会のなかでも受け入れられやすい。そういった考えが政治目的にも利用されることもあるが、長いあいだ、マイノリティとして社会に位置づけられてきた台湾原住民が、台湾アイデンティティの一翼を担うようになったことは社会の変化を如実にあらわしている。
国宝級の文物を収蔵し展示する国立の故宮。総人口の二パーセントほどの原住民の人びとの伝統文化を日常の生活用具を中心に伝える企業メセナの順益。ある意味、非常に対照的なふたつの博物館は、両館をシャトルバスでつなぎ、共通の入場券を発行する計画を進めている。一人でも多くの人にどちらの博物館も見てもらいたい。一人でも多くの人が集える公共空間を共有しよう。そんな実践的な試みが向き合うふたつの博物館のあいだではじまっている。「博物館や学芸員の権威性」、「民族博物館のもつ排他性」といった議論とは縁遠い、博物館の現場に生きる人たちの本音をそこに感じることができる。
葫蘆絲(フルス)
ひょうたん笛(標本番号H236824、高さ/43cm 幅/14cm 奥行/6.5cm)中国
ひょうたん笛(標本番号H236824、高さ/43cm 幅/14cm 奥行/6.5cm)中国
フルス。ひょうたん笛ともよばれる。中国西南地区の少数民族に古くから愛用されてきたといわれている管楽器。このフルスには白キジの羽が四本付いており見た目にも愛らしい。
この楽器は、ひょうたんの部分を胴とし、竹を管とする。管の数は楽器によってさまざまで、通常は二管から三管ほど。それぞれの管に穴があけられ、それらを操りながら吹く。構造的には「バグパイプ」に近い。はじめてこの楽器を手にしたとき、どう演奏すればよいのか戸惑うだろう。ひょうたんに直接付いている細い部分が吹き口。わたしは逆さまに吹いてしまい音が出ずに、恥ずかしい経験をした。
演奏には循環奏法とよばれる方法が用いられることもあり、これは、オーストラリア・アボリジニの楽器「ディジュリドゥー」でも用いられる演奏方法だというと、ご存知の方もあるかと思う。
フルスは、達人の手にかかれば、柔らかく、やさしい音が流れ、それは雅楽の笙の音に似ている。うっとりさせられる音色は、愛情を伝えるのにぴったりだ。かつて、タイ族の男性は、自分が思いを寄せる女性に愛を伝えるため、フルスにその想いを託し、彼女が振り向いてくれるまで一晩中演奏し続けたという。心打たれた女性は口琴でその愛に応えた。小さなフルスは人びとの愛をつなぐ大きな役目を担ってきた。
西南中国少数民族にはメジャーなこの楽器、じつは漢族のあいだではあまりポピュラーな楽器とはいえない。知り合いの複数の漢族の人に「葫蘆絲を知っていますか」と質問をしたところ、「チンジャオロース(青椒肉絲)のような、ひょうたん料理の一種?」といわれてしまった。しかし、このどこか懐かしい音色の楽器は、最近、中国本土では流行の兆しがあるという。中国のCDショップにはフルスのCD/DVDが増えている。フルスの音色を聞いていると、少数民族たちの愛のメッセージが中国をやさしく包んでいくような気持ちになれる。
この楽器は、ひょうたんの部分を胴とし、竹を管とする。管の数は楽器によってさまざまで、通常は二管から三管ほど。それぞれの管に穴があけられ、それらを操りながら吹く。構造的には「バグパイプ」に近い。はじめてこの楽器を手にしたとき、どう演奏すればよいのか戸惑うだろう。ひょうたんに直接付いている細い部分が吹き口。わたしは逆さまに吹いてしまい音が出ずに、恥ずかしい経験をした。
演奏には循環奏法とよばれる方法が用いられることもあり、これは、オーストラリア・アボリジニの楽器「ディジュリドゥー」でも用いられる演奏方法だというと、ご存知の方もあるかと思う。
フルスは、達人の手にかかれば、柔らかく、やさしい音が流れ、それは雅楽の笙の音に似ている。うっとりさせられる音色は、愛情を伝えるのにぴったりだ。かつて、タイ族の男性は、自分が思いを寄せる女性に愛を伝えるため、フルスにその想いを託し、彼女が振り向いてくれるまで一晩中演奏し続けたという。心打たれた女性は口琴でその愛に応えた。小さなフルスは人びとの愛をつなぐ大きな役目を担ってきた。
西南中国少数民族にはメジャーなこの楽器、じつは漢族のあいだではあまりポピュラーな楽器とはいえない。知り合いの複数の漢族の人に「葫蘆絲を知っていますか」と質問をしたところ、「チンジャオロース(青椒肉絲)のような、ひょうたん料理の一種?」といわれてしまった。しかし、このどこか懐かしい音色の楽器は、最近、中国本土では流行の兆しがあるという。中国のCDショップにはフルスのCD/DVDが増えている。フルスの音色を聞いていると、少数民族たちの愛のメッセージが中国をやさしく包んでいくような気持ちになれる。
出稼ぎから学ぶ
好景気のネパール
二〇〇七年暮れ、一年ぶりに訪ねたカトマンズはかつてない好景気だった。銀行が競って融資するため不動産は高騰し、バイクや自家用車の数も増えた。高価な輸入品を売るデパートはネパール人の家族連れであふれている。好景気の背景には、マオイスト内乱(一九九六~二〇〇六年)以前の数にまで回復した観光客による経済効果や、停戦後の平和構築に向け莫大な資金と人員を投入する「国連ネパール政治ミッション(UNMIN)」の特需があろう。だが、それにも増して大きいのは海外への出稼ぎが定着し、送金による現金が広く市中に出回っていることだ。
ネパールのおもな出稼ぎ先は、サウジアラビア、マレーシア、カタール、アラブ首長国連邦である。その数は年に約二〇万人(二〇〇七年)で、一日平均約五五〇人の移住労働者がカトマンズの空港から出国している。わたしが調査するマガール人の村も例外ではない。二〇〇〇年、村ではじめてサウジアラビアに行った青年ダニヤは、体調を崩し二年の予定が三ヵ月で帰国した。だが、彼は出稼ぎの経験から、パスポート、飛行機、通貨価値や換算レートなど村の人が知らない世界を体得した。以来、彼は農業のかたわら海外に出稼ぎに行く村周辺の若者をガイドし、仲介する副業にいそしむ。カトマンズ滞在中、ここに月に二度はくるというダニヤに会った。
出稼ぎと「外の世界」
会うなりダニヤは「昨日、若者が飛行機に乗りそこねたが、カタール航空の市内オフィスに行って五〇ドルを払い、何とか今晩のフライトの席を確保してきた」と矢継ぎ早に話した。空港に入る若者に彼は、「鹿のマーク」を目印にカタール航空のカウンターに並ぶよう指示したそうだ。だが、若者はジェットライト航空のデリー行きの列に並び、そうしているあいだにドーハ行きのカタール航空便は離陸してしまったという。居合わせた若者にわたしは「何故これはカタール航空の列ですかと前の人に聞かなかったの?」と尋ねた。彼は落ち込む様子もなく「聞いたんだ。でも前の人がそうだといったし・・・、その人もドーハ行きの便に乗りそこねたんだ」という。申し訳ないが、吹きだしてしまった。さらに、ダニヤに「こんなことはじめてでしょう?」と聞くと、彼は「いや、この六年に四六人くらい送ってきたけど六、七回はあった」といって笑う。そして、若者に「ダニヤに五〇ドル分を返済してくれ」という父親宛の手紙を書かせ、預かった。
海外の出稼ぎに要する諸費用は約三〇万円である。村の人は借金でそれを工面し、出稼ぎ先で月に五、六万円稼ぐ仕事に就いて、二、三年滞在する。ちなみに、ダニヤの仲介料は一、二万円だ。最初は右も左もわからないような村の若者は、こうして渡航と出稼ぎの経験を積み、やがてダニヤのように「外の世界」に通じて帰国するはずだ。出稼ぎはとかく送金の額に関心が向く。だが、出稼ぎは村出身の移住労働者がカトマンズを一跳びして「外の世界」とつながり、それを肌身で学ぶ機会をもたらす。長い目で見たとき、当座の送金より経験や知識が重要なことは、ダニヤと若者の対比から明らかであろう。ネパールにおいて出稼ぎがもたらすものは、現金にとどまらないのだ。
二〇〇七年暮れ、一年ぶりに訪ねたカトマンズはかつてない好景気だった。銀行が競って融資するため不動産は高騰し、バイクや自家用車の数も増えた。高価な輸入品を売るデパートはネパール人の家族連れであふれている。好景気の背景には、マオイスト内乱(一九九六~二〇〇六年)以前の数にまで回復した観光客による経済効果や、停戦後の平和構築に向け莫大な資金と人員を投入する「国連ネパール政治ミッション(UNMIN)」の特需があろう。だが、それにも増して大きいのは海外への出稼ぎが定着し、送金による現金が広く市中に出回っていることだ。
ネパールのおもな出稼ぎ先は、サウジアラビア、マレーシア、カタール、アラブ首長国連邦である。その数は年に約二〇万人(二〇〇七年)で、一日平均約五五〇人の移住労働者がカトマンズの空港から出国している。わたしが調査するマガール人の村も例外ではない。二〇〇〇年、村ではじめてサウジアラビアに行った青年ダニヤは、体調を崩し二年の予定が三ヵ月で帰国した。だが、彼は出稼ぎの経験から、パスポート、飛行機、通貨価値や換算レートなど村の人が知らない世界を体得した。以来、彼は農業のかたわら海外に出稼ぎに行く村周辺の若者をガイドし、仲介する副業にいそしむ。カトマンズ滞在中、ここに月に二度はくるというダニヤに会った。
出稼ぎと「外の世界」
会うなりダニヤは「昨日、若者が飛行機に乗りそこねたが、カタール航空の市内オフィスに行って五〇ドルを払い、何とか今晩のフライトの席を確保してきた」と矢継ぎ早に話した。空港に入る若者に彼は、「鹿のマーク」を目印にカタール航空のカウンターに並ぶよう指示したそうだ。だが、若者はジェットライト航空のデリー行きの列に並び、そうしているあいだにドーハ行きのカタール航空便は離陸してしまったという。居合わせた若者にわたしは「何故これはカタール航空の列ですかと前の人に聞かなかったの?」と尋ねた。彼は落ち込む様子もなく「聞いたんだ。でも前の人がそうだといったし・・・、その人もドーハ行きの便に乗りそこねたんだ」という。申し訳ないが、吹きだしてしまった。さらに、ダニヤに「こんなことはじめてでしょう?」と聞くと、彼は「いや、この六年に四六人くらい送ってきたけど六、七回はあった」といって笑う。そして、若者に「ダニヤに五〇ドル分を返済してくれ」という父親宛の手紙を書かせ、預かった。
海外の出稼ぎに要する諸費用は約三〇万円である。村の人は借金でそれを工面し、出稼ぎ先で月に五、六万円稼ぐ仕事に就いて、二、三年滞在する。ちなみに、ダニヤの仲介料は一、二万円だ。最初は右も左もわからないような村の若者は、こうして渡航と出稼ぎの経験を積み、やがてダニヤのように「外の世界」に通じて帰国するはずだ。出稼ぎはとかく送金の額に関心が向く。だが、出稼ぎは村出身の移住労働者がカトマンズを一跳びして「外の世界」とつながり、それを肌身で学ぶ機会をもたらす。長い目で見たとき、当座の送金より経験や知識が重要なことは、ダニヤと若者の対比から明らかであろう。ネパールにおいて出稼ぎがもたらすものは、現金にとどまらないのだ。
生きたものへの執着
あずかり知らぬところ
一年の世相をあらわす漢字が「偽」であったことでも明らかなとおり、昨年は食品にかんする偽装の問題が相次いで発生、いや発覚した。そして、年が明けた二〇〇八年は、冷凍食品への薬物混入事件が世間を騒然とさせている。
食品を巡るこれらの問題の特徴は、その発生源の多くが生産や流通の過程、つまり従来であれば消費者があずかり知らぬとしていたところにあるということだ。例えば、自宅の冷蔵庫にあったタマネギを切ってみたらなかが茶色くなっていた。もったいないが、これは口に入れずに済ますことができる。けれど、パッケージに記された食品の産地や賞味期限が記載どおりであるか、あるいは人体に有害な物質がまぎれ込んでいないかどうかということは、よほど違和感のある味や異臭でもしない限り、普通判別することは難しい。われわれは、製造者や企業の信頼を担保に取引をおこなっているのである。
もちろん、加工食品や冷凍食品の大半は厳格な安全基準をクリアしたうえで店頭に並んでいるのであり、問題となったものは例外中の例外なのだろう。しかし一方で、先のタマネギの例からも明らかなとおり、われわれの口に入るまでに経る工程が多ければ多いほど、「あずかり知らぬところ」が増えてゆくということもまた事実である。こういった事件を機にハンド・メイドや地場産品が見直されているのも、不可視の工程のできる限り少ないものを口にしたいという意識のあらわれなのであろう。
生に満ちた市場
この食品加工の重層的で不可視的な工程について考えていたおり、その対極にあるものとして思い浮かんだのが、市場、とりわけかつて中国滞在中に毎日のように足を運んでいた広東のそれだ。もちろん最近では中国でもスーパーが増え、冷凍・加工食品も売られてはいるが(そして日本と同様に、偽装や異物混入の問題も起こっているが)、生の野菜や果物はもちろん、生きたトリやサカナやエビを売る市場は人びとの生活になくてはならないものだ。
統計的な数字ではなくあくまで実感だが、都市部ならば徒歩圏内に必ず二つか三つの市場があるし、農村部でも固定的な市場のほか、露天のものや、定期市に至るまで、規模も形態もさまざまな市場がある。この市場との濃密なかかわりは、われわれにはときに過剰とも思えるほどの、人びとの新鮮さ=生きたものへの執着によるものだ。人びとは、生きたトリやサカナやエビを自らの目で見て、卵などであればそれを一個一個手にとって、吟味したうえで買ってゆく。広東料理の代表格にして客人をもてなす際にも欠かすことのできない「白灼蝦(バッチョッハ)」は、こうして市場から買ってきた生きたエビを煮たった湯のなかに数秒くぐらせたあと、薬味を刻んだしょうゆにつけて食べるという、いたってシンプルな一品である。まさに「省工程的」な食品の極みとも言えるこの料理からは、生きたものへの人びとの執着が鮮明に見て取れるだろう。
生きたものを求められる市場は、だから、生のエネルギーで満ちている。市場に一歩足を踏み入れると、魚介類の生臭さと、家禽類(かきんるい)の動物臭さが鼻につくし、足もとはたった今さばかれたばかりのサカナやニワトリの血や羽や鱗やらでおおわれている。ごく正直な感覚として、衛生面についての不安が頭をもたげてしまうのは否めないし、また生きたものである以上、動物たちがウィルスなどの宿主となり、密集した檻のなかでそれを媒介してゆくことも考えられる。実際に、数年前に鳥インフルエンザが拡大した際には、市場のニワトリが一斉に処分され、しばらくのあいだは生きたニワトリの取引が禁じられた。
こうしてみると、生きたものであっても、安全な生産と流通のためには、加工食品と同等の厳格な管理とチェックが必要ということになるのだろう。確かに言えるのは、食の安全は一筋縄ではいかない主題だということか。
一年の世相をあらわす漢字が「偽」であったことでも明らかなとおり、昨年は食品にかんする偽装の問題が相次いで発生、いや発覚した。そして、年が明けた二〇〇八年は、冷凍食品への薬物混入事件が世間を騒然とさせている。
食品を巡るこれらの問題の特徴は、その発生源の多くが生産や流通の過程、つまり従来であれば消費者があずかり知らぬとしていたところにあるということだ。例えば、自宅の冷蔵庫にあったタマネギを切ってみたらなかが茶色くなっていた。もったいないが、これは口に入れずに済ますことができる。けれど、パッケージに記された食品の産地や賞味期限が記載どおりであるか、あるいは人体に有害な物質がまぎれ込んでいないかどうかということは、よほど違和感のある味や異臭でもしない限り、普通判別することは難しい。われわれは、製造者や企業の信頼を担保に取引をおこなっているのである。
もちろん、加工食品や冷凍食品の大半は厳格な安全基準をクリアしたうえで店頭に並んでいるのであり、問題となったものは例外中の例外なのだろう。しかし一方で、先のタマネギの例からも明らかなとおり、われわれの口に入るまでに経る工程が多ければ多いほど、「あずかり知らぬところ」が増えてゆくということもまた事実である。こういった事件を機にハンド・メイドや地場産品が見直されているのも、不可視の工程のできる限り少ないものを口にしたいという意識のあらわれなのであろう。
生に満ちた市場
この食品加工の重層的で不可視的な工程について考えていたおり、その対極にあるものとして思い浮かんだのが、市場、とりわけかつて中国滞在中に毎日のように足を運んでいた広東のそれだ。もちろん最近では中国でもスーパーが増え、冷凍・加工食品も売られてはいるが(そして日本と同様に、偽装や異物混入の問題も起こっているが)、生の野菜や果物はもちろん、生きたトリやサカナやエビを売る市場は人びとの生活になくてはならないものだ。
統計的な数字ではなくあくまで実感だが、都市部ならば徒歩圏内に必ず二つか三つの市場があるし、農村部でも固定的な市場のほか、露天のものや、定期市に至るまで、規模も形態もさまざまな市場がある。この市場との濃密なかかわりは、われわれにはときに過剰とも思えるほどの、人びとの新鮮さ=生きたものへの執着によるものだ。人びとは、生きたトリやサカナやエビを自らの目で見て、卵などであればそれを一個一個手にとって、吟味したうえで買ってゆく。広東料理の代表格にして客人をもてなす際にも欠かすことのできない「白灼蝦(バッチョッハ)」は、こうして市場から買ってきた生きたエビを煮たった湯のなかに数秒くぐらせたあと、薬味を刻んだしょうゆにつけて食べるという、いたってシンプルな一品である。まさに「省工程的」な食品の極みとも言えるこの料理からは、生きたものへの人びとの執着が鮮明に見て取れるだろう。
生きたものを求められる市場は、だから、生のエネルギーで満ちている。市場に一歩足を踏み入れると、魚介類の生臭さと、家禽類(かきんるい)の動物臭さが鼻につくし、足もとはたった今さばかれたばかりのサカナやニワトリの血や羽や鱗やらでおおわれている。ごく正直な感覚として、衛生面についての不安が頭をもたげてしまうのは否めないし、また生きたものである以上、動物たちがウィルスなどの宿主となり、密集した檻のなかでそれを媒介してゆくことも考えられる。実際に、数年前に鳥インフルエンザが拡大した際には、市場のニワトリが一斉に処分され、しばらくのあいだは生きたニワトリの取引が禁じられた。
こうしてみると、生きたものであっても、安全な生産と流通のためには、加工食品と同等の厳格な管理とチェックが必要ということになるのだろう。確かに言えるのは、食の安全は一筋縄ではいかない主題だということか。
写真家として日中間を生きる―中国帰国者三世・高部心成さん
南 誠(みなみ まこと)中国名:梁 雪江(りょう せつこう) 本館外来研究員
人びとの感動を呼ぶ
写真家・高部心成(たかべしんせい)さん(中国名:周成(しゅうせい))は、中国帰国者三世である。二〇〇二年のコニカフォトプレミオ入賞で新星の如くあらわれ、二〇〇三年にはビジュアルアーツフォトアワード大賞、二〇〇四年にはフォトシティさがみはら写真新人奨励賞と三年連続して受賞した。代表作『故郷 松花江 黒龍江省哈爾浜』は少年時代を送った中国の生まれ故郷を題材にしている。白黒の写真でのみ構成されているアルバムは、高部さんが写真家を目指してがむしゃらに打ち込んだ専門学校時代、幾度か中国にわたり撮り続けた、村の四季の生活を描く。中国帰国者のみならず、作品を見た人びとのほとんどが深い感動を覚えた。
中国帰国者というだけで、今の日本では、中国での差別や生活苦、日本の生活への適応障害、孤立…、というマスメディアの作りあげたイメージがしばしばつきまとう。日本社会を懸命に生きる中国帰国者の姿は見えにくくなっている。高齢になって来日し、さまざまな理由で日本社会から隔離されがちな一世や二世と異なり、努力次第で日本社会に適応でき、活躍する機会の多い三世は、一刻もはやく日本社会に溶け込み、できる限り目立たず生きようとする。中国帰国者や彼らの出身地に対して日本社会がいだく想像がうとましく、過去について語るのを避けようとしたり、語ったとしても自分とはかかわりのない別世界のようにあつかおうとする人びともすくなくない。しかし、高部さんは何故故郷の村、少年時代を自分から進んで写真によって描こうとしたのだろうか。
故郷松花江
高部さんが両親と二人の姉とともに大阪にやってきたのは、一九九五年、一五歳のときであった。彼が生まれるはるか以前になくなった祖母がいわゆる残留日本婦人であったこと以外、まったく普通の中国農村の少年であった。村では、他の子どもとわけ隔てなく育てられた。日本では日本語をしらぬまま、地元の中学で一年遅れの二年生に編入され、その後高校に入学した。当初は日本語も不自由で、日本人とは友人づきあいもほとんどなかった。もう学校をやめようかとも思ったころ、ふとしたきっかけで、勉強に打ち込み始めた高部さんは、成績がみるみる向上することにおどろいた。すこし自分の能力に自信がつくと、今度は自分の表情が柔らかくなっていくのを感じたという。まもなく友人の輪が広がり、生徒会や文化祭活動など充実した高校生活を送れたと思っている。
そして二年生のとき、ある先生の誘いで入部した美術部で、油絵の世界に魅了されたのである。ことばを超えた最高の表現手段は芸術にあると感じ、毎日のように美術部の活動に没頭した。そして多くの仲間と同様、大学の美術学科を受験したが、失敗してしまう。そこで選んだのが、写真家の道であった。自己を表現する手段として、写真も美術も同じだ。それに、何日も制作にかける絵画にくらべ、シャッターを押すだけの写真は簡単に撮れる、仕事も多そうだ、こんな気持ちもあった。しかし、写真家の道もそんなに易しいものであるはずはない。写真関係の専門学校ビジュアルアーツに入って写真のすごさにぶっとばされることになった。
毎日授業やハードな提出課題に取り組みながら、他人と同じものを撮っても面白くない、自分を表現するのに一体何を撮ればいいだろうかと高部さんは悩んだ。そこで思いついたのが「中国」であった。それまでの中国は自己を他人と「違う」者にしてしまう存在であった。高校三年生のときに日本国籍を取得した彼は中国の記憶を封印していた。しかし、この中国こそがむしろ他人と差異化を図るための特別な存在であることに気付いたのだ。彼は元気になり、その「強み」を活かすために中国行きを決心した。
約六年ぶりに戻った故郷、中国の高度経済成長の波のなかでその風景は一変していた。人びとの意識も大きく変化し、同世代の若者は高いビルが林立する大都市の風景に憧れていた。しかし、高部さんは自分の子どものころの風景、黒い大地、松花江で戯れる子ども、移り変わる村の四季…を求めた。記憶のなかにあり体験した自分の中国はまだそこにあった。叔母のうちに居候しながら、人びとと大自然とのかかわり方という角度から故郷の風景を写真に収めた。過去への単なる郷愁や村の現実を描こうとする作品にはしたくなかった。自分の原点が故郷にあることを確認し、そこから日本に住み続けようとする自分の生き方が見えた気がした。
写真家としての夢
二〇〇三年に結婚した高部さんは、今、東京都内に居住している。関西から関東に引越し新生活を始めた彼は、東京都内のある写真スタジオに所属し、写真家としての経験を積んでいる。「将来は独立して自分の事務所を開き、表現力をもっと追求していきたい」と抱負を語る。かつては出自を隠そうとしたり、自分が誰であるか悩んだりしたこともあった。写真によって、そんな自己を表現できるかと思ったりもした。しかし今、写真家の道を選び、作品が評価されたことで、逆に自分が形成されつつあるとも思っている。中国人か日本人か悩むより、その両方であることを受け入れ、それを生きる自分は、いつか日本の魅力も中国にも伝えていきたい、これが高部さんの今の目標である。
写真家・高部心成(たかべしんせい)さん(中国名:周成(しゅうせい))は、中国帰国者三世である。二〇〇二年のコニカフォトプレミオ入賞で新星の如くあらわれ、二〇〇三年にはビジュアルアーツフォトアワード大賞、二〇〇四年にはフォトシティさがみはら写真新人奨励賞と三年連続して受賞した。代表作『故郷 松花江 黒龍江省哈爾浜』は少年時代を送った中国の生まれ故郷を題材にしている。白黒の写真でのみ構成されているアルバムは、高部さんが写真家を目指してがむしゃらに打ち込んだ専門学校時代、幾度か中国にわたり撮り続けた、村の四季の生活を描く。中国帰国者のみならず、作品を見た人びとのほとんどが深い感動を覚えた。
中国帰国者というだけで、今の日本では、中国での差別や生活苦、日本の生活への適応障害、孤立…、というマスメディアの作りあげたイメージがしばしばつきまとう。日本社会を懸命に生きる中国帰国者の姿は見えにくくなっている。高齢になって来日し、さまざまな理由で日本社会から隔離されがちな一世や二世と異なり、努力次第で日本社会に適応でき、活躍する機会の多い三世は、一刻もはやく日本社会に溶け込み、できる限り目立たず生きようとする。中国帰国者や彼らの出身地に対して日本社会がいだく想像がうとましく、過去について語るのを避けようとしたり、語ったとしても自分とはかかわりのない別世界のようにあつかおうとする人びともすくなくない。しかし、高部さんは何故故郷の村、少年時代を自分から進んで写真によって描こうとしたのだろうか。
故郷松花江
高部さんが両親と二人の姉とともに大阪にやってきたのは、一九九五年、一五歳のときであった。彼が生まれるはるか以前になくなった祖母がいわゆる残留日本婦人であったこと以外、まったく普通の中国農村の少年であった。村では、他の子どもとわけ隔てなく育てられた。日本では日本語をしらぬまま、地元の中学で一年遅れの二年生に編入され、その後高校に入学した。当初は日本語も不自由で、日本人とは友人づきあいもほとんどなかった。もう学校をやめようかとも思ったころ、ふとしたきっかけで、勉強に打ち込み始めた高部さんは、成績がみるみる向上することにおどろいた。すこし自分の能力に自信がつくと、今度は自分の表情が柔らかくなっていくのを感じたという。まもなく友人の輪が広がり、生徒会や文化祭活動など充実した高校生活を送れたと思っている。
そして二年生のとき、ある先生の誘いで入部した美術部で、油絵の世界に魅了されたのである。ことばを超えた最高の表現手段は芸術にあると感じ、毎日のように美術部の活動に没頭した。そして多くの仲間と同様、大学の美術学科を受験したが、失敗してしまう。そこで選んだのが、写真家の道であった。自己を表現する手段として、写真も美術も同じだ。それに、何日も制作にかける絵画にくらべ、シャッターを押すだけの写真は簡単に撮れる、仕事も多そうだ、こんな気持ちもあった。しかし、写真家の道もそんなに易しいものであるはずはない。写真関係の専門学校ビジュアルアーツに入って写真のすごさにぶっとばされることになった。
毎日授業やハードな提出課題に取り組みながら、他人と同じものを撮っても面白くない、自分を表現するのに一体何を撮ればいいだろうかと高部さんは悩んだ。そこで思いついたのが「中国」であった。それまでの中国は自己を他人と「違う」者にしてしまう存在であった。高校三年生のときに日本国籍を取得した彼は中国の記憶を封印していた。しかし、この中国こそがむしろ他人と差異化を図るための特別な存在であることに気付いたのだ。彼は元気になり、その「強み」を活かすために中国行きを決心した。
約六年ぶりに戻った故郷、中国の高度経済成長の波のなかでその風景は一変していた。人びとの意識も大きく変化し、同世代の若者は高いビルが林立する大都市の風景に憧れていた。しかし、高部さんは自分の子どものころの風景、黒い大地、松花江で戯れる子ども、移り変わる村の四季…を求めた。記憶のなかにあり体験した自分の中国はまだそこにあった。叔母のうちに居候しながら、人びとと大自然とのかかわり方という角度から故郷の風景を写真に収めた。過去への単なる郷愁や村の現実を描こうとする作品にはしたくなかった。自分の原点が故郷にあることを確認し、そこから日本に住み続けようとする自分の生き方が見えた気がした。
写真家としての夢
二〇〇三年に結婚した高部さんは、今、東京都内に居住している。関西から関東に引越し新生活を始めた彼は、東京都内のある写真スタジオに所属し、写真家としての経験を積んでいる。「将来は独立して自分の事務所を開き、表現力をもっと追求していきたい」と抱負を語る。かつては出自を隠そうとしたり、自分が誰であるか悩んだりしたこともあった。写真によって、そんな自己を表現できるかと思ったりもした。しかし今、写真家の道を選び、作品が評価されたことで、逆に自分が形成されつつあるとも思っている。中国人か日本人か悩むより、その両方であることを受け入れ、それを生きる自分は、いつか日本の魅力も中国にも伝えていきたい、これが高部さんの今の目標である。
中国の五一(ウーイー)国際労働節
メーデーは中国では「五一(ウーイー)国際労働節」、あるいは「五一」ともよぶ。メーデーが世界労働者の日として確立されてから一二〇年近くになろうとしている。一八六六年に第一回インターナショナルがジュネーブで開催されたとき、八時間労働制度の主張が初めてなされた。一八八六年五月一日には合衆国・カナダ職能労働組合連盟がシカゴを中心にデモをおこなった。一八八九年パリで開催された第二回インターナショナルでは五月一日が労働者の日とさだめられ、以来、メーデーは各国で多様なかたちをとりながら展開されてきた。
中国のメーデーは一九〇七年のハルビンの記念イベントにさかのぼることができる。その後、北京、上海、広州、漢口、九江、唐山などの都市で労働者のデモがおこなわれ、一九二五年五月には労働組合の全国連合体である中華全国総工会が広州で創立された。
一九四九年に中華人民共和国政府政務院はメーデーを祝日に制定し、一日の休暇を設けた。社会主義政権になってからのメーデーは、労働者がその権利を要求するようなデモはなくなり、そのかわり政府主催の祝祭やパレード、中華全国総工会主催の優秀労働者の表彰式がおもな行事となった。メーデーは中国政府にとって社会主義諸国の連合、社会主義イデオロギーにふさわしい新しい労働観念と労働者の姿を宣伝する場となった。たとえば、一九五〇年に天津でおこなわれたパレードでは、大型トラックを運転する農民女性がいて、新しい時代の農村機械化と労働する女性の姿がアピールされた。
建国初期の政府はメーデーをきわめて重視していた。大都会に限らず、郷(ごう)・鎮(ちん)のような田舎でもパレードがおこなわれていた。わたしが調査した安徽省宿州市在住の退職した大学教員は次のように回顧している。
「当時、わたしは固鎮(こちん)中学校の生徒だった。一九五〇年代の中国は、国慶節よりメーデーのほうがずっと盛大であった。安徽省の郷・鎮レベルでは国慶節に関する行事は何もなかったのに対して、メーデーになると、固鎮では必ず祝典とパレードがおこなわれた。その祝典は朝八時から午後一、二時まで開催され、党、政府、組合、婦人会、商店の従業員、農民、学生などが五〇〇〇人ほど参加していた。各界の代表が次から次へと講壇に上ってスピーチをしていたが、下の人は真剣に聞いていなかった。長時間日に当たり、お腹もすいて、みんなふらふらしていた。祝典が終わると全員またパレードに加わらなければならなかった。こんなイベントに参加したいと思う人はあまりいなかった。学校は出席者を確保するために、メーデー祝典への不参加を、学校の無断欠席としてあつかっていた」。
パレードに参加したことのある当時の小学生と中学生は、スローガンのいくつかを覚えている。「全世界の圧迫された民族と人民が団結して、アメリカ帝国主義を打倒せよ!」、「われわれは断固としてソ連一辺倒で兄貴に学ぼう」、「アメリカに抵抗し、朝鮮を援助し、国を守ろう。生産を急げ、前線を応援しよう」、「毛沢東万歳!万歳!万々歳!」。
政治色がなくなって
一九六〇年代に入ると、中ソ関係の悪化、人民公社の失敗による飢饉の発生、文化大革命による社会秩序の混乱のため、郷・鎮レベルでのメーデーの祝典とパレードは中止されるようになった。都会ではメーデーの祝典はあったものの、その規模は建国初期とは比べるべくもなかった。パレードも激減した。もっとも「五一遊園会」という公園でおこなわれる交歓会は見られたが。
改革開放以降、労働者の範囲も、肉体労働者に限らず、教師、研究者などの頭脳労働者までも含むようになった。また、一九九一年のソ連の崩壊と冷戦の終焉にともない、政府主催のメーデー行事は、社会主義諸国や世界労働者の連合を表象する内容がなくなり、各界の優秀労働者を表彰する意味合いが強くなった。中華全国総工会の「五一しょう章」(勲章)の授与大会はその一例である。一九八五年から二〇〇六年のあいだに表彰された全国五一しょう章獲得者は一万六七四三人にのぼる。また、二〇〇一年からは三〇〇〇元(約四万五〇〇〇円)の賞金をもらうようになった。ローカル版の「五一しょう章」授与大会も省・市レベルで開催されている。
一方、グローバルな情勢変化と民衆の生活水準の向上にともない、中国政府は建国以来の祝日と記念日を調整した。一九九九年に国務院が公布した「全国祝日と記念日の休日」に関する規定のなかで、政府は観光市場と消費市場の景気刺激を目的として、五月のメーデーと一〇月の国慶節をそれぞれ一週間の休日とした。それは大きな経済効果をもたらしている。旧正月、メーデーと国慶節の三つのゴールデンウィークに出かける観光客は一億八七〇〇万人にのぼっている。
二〇世紀の初頭からはじまった中国のメーデーは、国際情勢と国内の経済的・政治的変化にともない、その目的、主催者と実施形態が徐々に変化している。二一世紀の中国民衆にとって、メーデーは政治色がなくなり、自由に使えるゆとりの時間になっている。
中国のメーデーは一九〇七年のハルビンの記念イベントにさかのぼることができる。その後、北京、上海、広州、漢口、九江、唐山などの都市で労働者のデモがおこなわれ、一九二五年五月には労働組合の全国連合体である中華全国総工会が広州で創立された。
一九四九年に中華人民共和国政府政務院はメーデーを祝日に制定し、一日の休暇を設けた。社会主義政権になってからのメーデーは、労働者がその権利を要求するようなデモはなくなり、そのかわり政府主催の祝祭やパレード、中華全国総工会主催の優秀労働者の表彰式がおもな行事となった。メーデーは中国政府にとって社会主義諸国の連合、社会主義イデオロギーにふさわしい新しい労働観念と労働者の姿を宣伝する場となった。たとえば、一九五〇年に天津でおこなわれたパレードでは、大型トラックを運転する農民女性がいて、新しい時代の農村機械化と労働する女性の姿がアピールされた。
建国初期の政府はメーデーをきわめて重視していた。大都会に限らず、郷(ごう)・鎮(ちん)のような田舎でもパレードがおこなわれていた。わたしが調査した安徽省宿州市在住の退職した大学教員は次のように回顧している。
「当時、わたしは固鎮(こちん)中学校の生徒だった。一九五〇年代の中国は、国慶節よりメーデーのほうがずっと盛大であった。安徽省の郷・鎮レベルでは国慶節に関する行事は何もなかったのに対して、メーデーになると、固鎮では必ず祝典とパレードがおこなわれた。その祝典は朝八時から午後一、二時まで開催され、党、政府、組合、婦人会、商店の従業員、農民、学生などが五〇〇〇人ほど参加していた。各界の代表が次から次へと講壇に上ってスピーチをしていたが、下の人は真剣に聞いていなかった。長時間日に当たり、お腹もすいて、みんなふらふらしていた。祝典が終わると全員またパレードに加わらなければならなかった。こんなイベントに参加したいと思う人はあまりいなかった。学校は出席者を確保するために、メーデー祝典への不参加を、学校の無断欠席としてあつかっていた」。
パレードに参加したことのある当時の小学生と中学生は、スローガンのいくつかを覚えている。「全世界の圧迫された民族と人民が団結して、アメリカ帝国主義を打倒せよ!」、「われわれは断固としてソ連一辺倒で兄貴に学ぼう」、「アメリカに抵抗し、朝鮮を援助し、国を守ろう。生産を急げ、前線を応援しよう」、「毛沢東万歳!万歳!万々歳!」。
政治色がなくなって
一九六〇年代に入ると、中ソ関係の悪化、人民公社の失敗による飢饉の発生、文化大革命による社会秩序の混乱のため、郷・鎮レベルでのメーデーの祝典とパレードは中止されるようになった。都会ではメーデーの祝典はあったものの、その規模は建国初期とは比べるべくもなかった。パレードも激減した。もっとも「五一遊園会」という公園でおこなわれる交歓会は見られたが。
改革開放以降、労働者の範囲も、肉体労働者に限らず、教師、研究者などの頭脳労働者までも含むようになった。また、一九九一年のソ連の崩壊と冷戦の終焉にともない、政府主催のメーデー行事は、社会主義諸国や世界労働者の連合を表象する内容がなくなり、各界の優秀労働者を表彰する意味合いが強くなった。中華全国総工会の「五一しょう章」(勲章)の授与大会はその一例である。一九八五年から二〇〇六年のあいだに表彰された全国五一しょう章獲得者は一万六七四三人にのぼる。また、二〇〇一年からは三〇〇〇元(約四万五〇〇〇円)の賞金をもらうようになった。ローカル版の「五一しょう章」授与大会も省・市レベルで開催されている。
一方、グローバルな情勢変化と民衆の生活水準の向上にともない、中国政府は建国以来の祝日と記念日を調整した。一九九九年に国務院が公布した「全国祝日と記念日の休日」に関する規定のなかで、政府は観光市場と消費市場の景気刺激を目的として、五月のメーデーと一〇月の国慶節をそれぞれ一週間の休日とした。それは大きな経済効果をもたらしている。旧正月、メーデーと国慶節の三つのゴールデンウィークに出かける観光客は一億八七〇〇万人にのぼっている。
二〇世紀の初頭からはじまった中国のメーデーは、国際情勢と国内の経済的・政治的変化にともない、その目的、主催者と実施形態が徐々に変化している。二一世紀の中国民衆にとって、メーデーは政治色がなくなり、自由に使えるゆとりの時間になっている。
精霊に捧げ食べる
聖地エヴォロン湖で
水田が広がる日本では、フナはコイと並んで、用水路や近くの湖沼、河川で簡単に捕れたもっとも身近な魚のひとつであった。しかし、この魚が日本だけのものでないことはいうまでもない。フナ属とよばれるコイ科の魚は広く西はヨーロッパから東は日本まで、ユーラシア大陸の中部、北部を横断するように分布する。わたしが調査をしているロシア極東地域のアムール川流域にもフナの名産地がある。アムールの支流のひとつであるゴリン川の流域にコンドンというナーナイ(極東ロシアの先住民族のひとつ)の村がある。その前を流れる川を四〇分ほどさかのぼると、エヴォロン湖とよばれる広大な湖があらわれる。そこがフナの一大産地なのである。かつてソ連時代には「エヴォロンのフナ」といえばモスクワの高級レストランにも名のとおった良質の食材であった。
エヴォロン湖はコンドン村のナーナイの人びとにとっては聖地でもある。この湖の西側の岸辺にはカダハチャンとよばれる岩場があり、湖の精霊をまつる場所がある。精霊をまつるといっても、湖を訪れるたびにそこで捕れた魚をその岩場で調理し、一杯のウォッカと料理した魚の一切れを岩場に捧げて大漁と人びとの幸福を祈願して、あとは人間が料理を平らげ、ウォッカを飲み干すだけである。ただし、このとき人びとが精霊に捧げ、そして食べるのはもっぱらこの湖で捕れたフナなのである。
浅瀬ならではの漁
エヴォロン湖のフナ漁には夏漁と冬漁がある。
夏場は、フナは湖に島状に浮かぶ水草の下に隠れていることが多い。漁師はフナが隠れていそうな水草の群落の周囲に半円状に網を張り、網を張ってない側から水面をたたいて魚を脅かして網に追い込む。ただし、この湖は広いわりには浅い。真ん中まで来ると、周囲の岸辺の山々が遙かにかすんで見えるほどなのだが、水深は人の腰ぐらいまでしかない。したがって、漁師たちは網を張った後、ボートから降りて、歩いて魚を追い立てるのである。網は刺し網なので小さな魚はかからない。フナでも体長三〇センチメートル程度の大物を中心に捕るのである。
この地方は真冬にはマイナス四〇度を下回る厳寒となる。水深が浅いエヴォロン湖はほとんど全面が底まで凍る。さすがに寒さに強いこの地方のフナでも、凍ってしまっては生きてはいられない。そのために、水深が深く、真冬でも底の方に凍らない部分が残る川の方に移動する。冬にはそのような川で氷に穴を開け、その下に網を張って、底の方で越冬しているフナを捕るのである。冬のフナはえさをとらないので肉に臭みがなく、もっともよい状態になるという。モスクワの高級レストランで人びとの舌を楽しませたのはこの「寒ブナ」なのである。
あばら骨に沿って切る
コンドンのナーナイたちのフナ料理には奇妙なところがある。まずフナを湖の水で洗い、ナイフで鱗を取り除いて、腹を割き、内臓を取り出す。続いてあばら骨に沿って身にナイフで丹念に切れ目を入れていくのである。切れ目は魚の両側に入れる。火をとおりやすくするため、細かい骨を切るため(骨断ち)等と説明されたが、本当の理由はわからない。そのように処理された魚を鍋に入れ、水を入れてゆでるだけである。味付けは塩と胡椒と若干の香草である。味は繊細ではないが、大味でもなく、どちらかといえば淡泊である。夏場は若干泥臭さがあるが気になるほどではなく、寒ブナはそれがまったくないという。わたしは箸を使って食べたが、ナーナイの人びとは手を使って骨だけ残してきれいに食べていた。骨は硬くて丈夫なのと、かたちがおもしろいので、子どもの玩具になるという。
フナ (学名:Carassiu)
アジアからヨーロッパまで広く分布するコイ科の魚。フナ属(Carassiu)の分類は諸説あるようだが、ヨーロッパから中央シベリアまで分布するヨーロッパブナ、東アジアを中心としたユーラシア東部に分布するギンブナ、日本各地や朝鮮半島にいるキンブナ、琵琶湖や淀川水系にいるニゴロブナやゲンゴロウブナなどがいる。観賞用に飼育される金魚はフナの突然変異種である。エヴォロンのフナは地域的にはギンブナの系統と思われるが、現在は、ヨーロッパブナの系統が入っているかもしれない。
水田が広がる日本では、フナはコイと並んで、用水路や近くの湖沼、河川で簡単に捕れたもっとも身近な魚のひとつであった。しかし、この魚が日本だけのものでないことはいうまでもない。フナ属とよばれるコイ科の魚は広く西はヨーロッパから東は日本まで、ユーラシア大陸の中部、北部を横断するように分布する。わたしが調査をしているロシア極東地域のアムール川流域にもフナの名産地がある。アムールの支流のひとつであるゴリン川の流域にコンドンというナーナイ(極東ロシアの先住民族のひとつ)の村がある。その前を流れる川を四〇分ほどさかのぼると、エヴォロン湖とよばれる広大な湖があらわれる。そこがフナの一大産地なのである。かつてソ連時代には「エヴォロンのフナ」といえばモスクワの高級レストランにも名のとおった良質の食材であった。
エヴォロン湖はコンドン村のナーナイの人びとにとっては聖地でもある。この湖の西側の岸辺にはカダハチャンとよばれる岩場があり、湖の精霊をまつる場所がある。精霊をまつるといっても、湖を訪れるたびにそこで捕れた魚をその岩場で調理し、一杯のウォッカと料理した魚の一切れを岩場に捧げて大漁と人びとの幸福を祈願して、あとは人間が料理を平らげ、ウォッカを飲み干すだけである。ただし、このとき人びとが精霊に捧げ、そして食べるのはもっぱらこの湖で捕れたフナなのである。
浅瀬ならではの漁
エヴォロン湖のフナ漁には夏漁と冬漁がある。
夏場は、フナは湖に島状に浮かぶ水草の下に隠れていることが多い。漁師はフナが隠れていそうな水草の群落の周囲に半円状に網を張り、網を張ってない側から水面をたたいて魚を脅かして網に追い込む。ただし、この湖は広いわりには浅い。真ん中まで来ると、周囲の岸辺の山々が遙かにかすんで見えるほどなのだが、水深は人の腰ぐらいまでしかない。したがって、漁師たちは網を張った後、ボートから降りて、歩いて魚を追い立てるのである。網は刺し網なので小さな魚はかからない。フナでも体長三〇センチメートル程度の大物を中心に捕るのである。
この地方は真冬にはマイナス四〇度を下回る厳寒となる。水深が浅いエヴォロン湖はほとんど全面が底まで凍る。さすがに寒さに強いこの地方のフナでも、凍ってしまっては生きてはいられない。そのために、水深が深く、真冬でも底の方に凍らない部分が残る川の方に移動する。冬にはそのような川で氷に穴を開け、その下に網を張って、底の方で越冬しているフナを捕るのである。冬のフナはえさをとらないので肉に臭みがなく、もっともよい状態になるという。モスクワの高級レストランで人びとの舌を楽しませたのはこの「寒ブナ」なのである。
あばら骨に沿って切る
コンドンのナーナイたちのフナ料理には奇妙なところがある。まずフナを湖の水で洗い、ナイフで鱗を取り除いて、腹を割き、内臓を取り出す。続いてあばら骨に沿って身にナイフで丹念に切れ目を入れていくのである。切れ目は魚の両側に入れる。火をとおりやすくするため、細かい骨を切るため(骨断ち)等と説明されたが、本当の理由はわからない。そのように処理された魚を鍋に入れ、水を入れてゆでるだけである。味付けは塩と胡椒と若干の香草である。味は繊細ではないが、大味でもなく、どちらかといえば淡泊である。夏場は若干泥臭さがあるが気になるほどではなく、寒ブナはそれがまったくないという。わたしは箸を使って食べたが、ナーナイの人びとは手を使って骨だけ残してきれいに食べていた。骨は硬くて丈夫なのと、かたちがおもしろいので、子どもの玩具になるという。
フナ (学名:Carassiu)
アジアからヨーロッパまで広く分布するコイ科の魚。フナ属(Carassiu)の分類は諸説あるようだが、ヨーロッパから中央シベリアまで分布するヨーロッパブナ、東アジアを中心としたユーラシア東部に分布するギンブナ、日本各地や朝鮮半島にいるキンブナ、琵琶湖や淀川水系にいるニゴロブナやゲンゴロウブナなどがいる。観賞用に飼育される金魚はフナの突然変異種である。エヴォロンのフナは地域的にはギンブナの系統と思われるが、現在は、ヨーロッパブナの系統が入っているかもしれない。
「書く」のは誰?
わたしが最初に入ったフィールドは韓国のキリスト教会だった。労働組合の活動が厳しく取り締まられていた「民主化」前の韓国では、教会がしばしば労働者たちの隠れ蓑となり、なかでもここは隣接する工業団地の組織闘争の支援体として名を馳せた。「民主化」後には労働運動が大幅に自由化されたため、この教会も性格を大きく変えて、日雇い労働者の支援など新しい活動に着手していた。
研究者失格!
調査期間も半ばにさしかかったある日のこと。仕事に追われる教会スタッフを尻目に、わたしはこの調査の中間報告の準備をしていた。ウォーラーステインの資本主義システム論を援用した報告内容だった。彼の議論を略説すれば、資本主義というものは、一定の地域に根ざすと、その周縁をさらに取り込んでいき、拡大していくことでのみ持続されるものだという。わたしはこの話を教会の活動に絡めようとしていた。机には彼の著作が山積みだった。
「あら?ウォーラーステインじゃない?」。女性スタッフが話しかけてきた。どんな発表をするのか聞きたがる彼女に、あらすじを説明する。結論をいえば、この種の教会は資本主義に抗しようとしているものの、資本主義が工場労働者のあいだで成熟していくと、今度はあらたな市場を工場の周縁(日雇い労働者)に求めていくことでしか維持されない―つまり、皮肉にも資本主義のシステムに取り込まれた存在であるという内容だった。
彼女の反応は意外の極みだった。ウォーラーステインを読んでいたのはわたしだけではなかったのだ。彼女は、わたしが知らなかった教会史の断片を、静かに語りだした。「民主化」後、教会の存在意義が揺らいだとき、彼/彼女らは勉強会をくり返した。その過程でウォーラーステインを読み、資本主義があらたに飲み込まんとしている周縁に救いの手を向けるべく、日雇い労働者の支援に踏み切ったのだそうだ。
たとえ研究者が「このミカンがよく売れるのは、甘くて安いからだ」と分析したとしても、もともとそのミカンがよく売れるように甘くて安く作られていたものならば、そんな分析は無意味だ。わたしの報告内容もそれと同じだった。
「研究者失格ね」。たいへん重い体験だった。そのときの中間報告は内容を大幅に変えてやり過ごしたが、それ以来わたしは書くことが恐ろしくなってきた。
研究者と研究対象のあいだで
ちょうど同じころ、あることに気付いた。教会の事務室は、当時わたしが現地で所属していた大学の院生室にそっくりだったのだ。同じような机に同じ韓国人がいて、同じような本が並んでいた。両者の違いは何だろう。思いをめぐらせてみた。もっとも大きく違うのは、他でもない、わたし自身がその場に向き合う態度ではないかと思った。大学の人びとには調査研究の結果を書いて見せ、助言を求めることがあったが、教会では書く材料を探すだけだったのだ。
教会の調査が終盤にさしかかったころ、わたしは思いきって、教会の人びとをおもな読者に想定した「論文」を書き上げてみた。そして、それを人びとに読んでもらったり、あらすじを話したりして、どう感じたか聞いてまわった。
反応は意外と生産的だった。たとえば、彼/彼女らの活動のうちわたしが重要だと思ったものが、彼/彼女らにとっては優先順位の低いものだったことがあった。「ここをこう変えたらどう?」と赤ペンを入れてきた人がいて、どちらの文章がしっくりくるかをその場にいた数名で検討したこともあった。自分でも気付かないうちに彼/彼女らに批判的な書き方をしていたこともあったが、「ムカつくなあ。でも、おまえが俺らを見る方法も、俺らが自分たちを見る方法のひとつだ。おまえも教友(教会の一員)だからな。ともかく、一杯おごれよ」で済んだ。わたしと彼/彼女らの距離も縮まった気がした。
それからというもの、わたしは他の調査対象にも同様の作業をおこなうようになった。書く材料が手に入るのをただ待つより、効率的で、刺激的で、充実感があった。調査対象の人びとと何度も推敲を重ねたこれらの「論文」は、やがて本当の論文として日本の学術誌に掲載された。
「書く」のはフィールドワーク!
われわれ研究者はフィールドワークと論文執筆を別の作業段階として考えがちだ。だが、フィールドワークをしながら論文を書いてもいい。論文を書く過程がフィールドワークになってもいい。さらに、願わくば、文化の書き手は「わたし」や現地の人びとというような恣意をもつ個々の人間ではなく、もっと間主体的な、「わたし」と彼/彼女らとが過ごす日々そのものであってほしくないか。これらすべての思いを込めた合いことば――「書くのはフィールドワーク!」。今でもときどきこう意気込んで、わたしはフィールドに出かけていく。
もちろんこうした調査研究の指針がつねに有効だとは思えない。ただ、このやり方があのときはうまくいったし、わたしの性格にも合っていたのだと思う。
研究者失格!
調査期間も半ばにさしかかったある日のこと。仕事に追われる教会スタッフを尻目に、わたしはこの調査の中間報告の準備をしていた。ウォーラーステインの資本主義システム論を援用した報告内容だった。彼の議論を略説すれば、資本主義というものは、一定の地域に根ざすと、その周縁をさらに取り込んでいき、拡大していくことでのみ持続されるものだという。わたしはこの話を教会の活動に絡めようとしていた。机には彼の著作が山積みだった。
「あら?ウォーラーステインじゃない?」。女性スタッフが話しかけてきた。どんな発表をするのか聞きたがる彼女に、あらすじを説明する。結論をいえば、この種の教会は資本主義に抗しようとしているものの、資本主義が工場労働者のあいだで成熟していくと、今度はあらたな市場を工場の周縁(日雇い労働者)に求めていくことでしか維持されない―つまり、皮肉にも資本主義のシステムに取り込まれた存在であるという内容だった。
彼女の反応は意外の極みだった。ウォーラーステインを読んでいたのはわたしだけではなかったのだ。彼女は、わたしが知らなかった教会史の断片を、静かに語りだした。「民主化」後、教会の存在意義が揺らいだとき、彼/彼女らは勉強会をくり返した。その過程でウォーラーステインを読み、資本主義があらたに飲み込まんとしている周縁に救いの手を向けるべく、日雇い労働者の支援に踏み切ったのだそうだ。
たとえ研究者が「このミカンがよく売れるのは、甘くて安いからだ」と分析したとしても、もともとそのミカンがよく売れるように甘くて安く作られていたものならば、そんな分析は無意味だ。わたしの報告内容もそれと同じだった。
「研究者失格ね」。たいへん重い体験だった。そのときの中間報告は内容を大幅に変えてやり過ごしたが、それ以来わたしは書くことが恐ろしくなってきた。
研究者と研究対象のあいだで
ちょうど同じころ、あることに気付いた。教会の事務室は、当時わたしが現地で所属していた大学の院生室にそっくりだったのだ。同じような机に同じ韓国人がいて、同じような本が並んでいた。両者の違いは何だろう。思いをめぐらせてみた。もっとも大きく違うのは、他でもない、わたし自身がその場に向き合う態度ではないかと思った。大学の人びとには調査研究の結果を書いて見せ、助言を求めることがあったが、教会では書く材料を探すだけだったのだ。
教会の調査が終盤にさしかかったころ、わたしは思いきって、教会の人びとをおもな読者に想定した「論文」を書き上げてみた。そして、それを人びとに読んでもらったり、あらすじを話したりして、どう感じたか聞いてまわった。
反応は意外と生産的だった。たとえば、彼/彼女らの活動のうちわたしが重要だと思ったものが、彼/彼女らにとっては優先順位の低いものだったことがあった。「ここをこう変えたらどう?」と赤ペンを入れてきた人がいて、どちらの文章がしっくりくるかをその場にいた数名で検討したこともあった。自分でも気付かないうちに彼/彼女らに批判的な書き方をしていたこともあったが、「ムカつくなあ。でも、おまえが俺らを見る方法も、俺らが自分たちを見る方法のひとつだ。おまえも教友(教会の一員)だからな。ともかく、一杯おごれよ」で済んだ。わたしと彼/彼女らの距離も縮まった気がした。
それからというもの、わたしは他の調査対象にも同様の作業をおこなうようになった。書く材料が手に入るのをただ待つより、効率的で、刺激的で、充実感があった。調査対象の人びとと何度も推敲を重ねたこれらの「論文」は、やがて本当の論文として日本の学術誌に掲載された。
「書く」のはフィールドワーク!
われわれ研究者はフィールドワークと論文執筆を別の作業段階として考えがちだ。だが、フィールドワークをしながら論文を書いてもいい。論文を書く過程がフィールドワークになってもいい。さらに、願わくば、文化の書き手は「わたし」や現地の人びとというような恣意をもつ個々の人間ではなく、もっと間主体的な、「わたし」と彼/彼女らとが過ごす日々そのものであってほしくないか。これらすべての思いを込めた合いことば――「書くのはフィールドワーク!」。今でもときどきこう意気込んで、わたしはフィールドに出かけていく。
もちろんこうした調査研究の指針がつねに有効だとは思えない。ただ、このやり方があのときはうまくいったし、わたしの性格にも合っていたのだと思う。
先月号に引き続き、今月も「開館30周年記念事業」関連のインタビューを特集した。事業の運営に携わった館員2人へのインタビューから、さまざまな記念行事の舞台裏や、これから先の民博に寄せる館員の思いを読み取っていただければ幸いである。わたしにとって「ウィークエンド・サロン」でたくさんの熱心な質問をいただき来場者の皆さんと交流する機会がもてたことは、新鮮で心躍る経験だった。同時に、めまぐるしく変わりつつある調査地の文化や社会のありさまをわかりやすく伝えることの難しさも実感した。幸い「ウィークエンド・サロン」はご好評をいただき継続されることになった。民博と社会をつなぐ新しいパイプが、記念行事で終わることなく、工夫を加えながら成長するよう願わずにはいられない。『月刊みんぱく』もそういうパイプの大切な1本だ。このパイプがより太くまた魅力的なものになるよう新米編集委員として知恵をしぼり、汗をかきながら頑張りたい。(三尾 稔)
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。