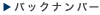月刊みんぱく 2008年7月号
2008年7月号
第32巻第7号通巻第370号
2008年7月1日発行
2008年7月1日発行
東洋の星物語
渡部 潤一
天文学者というと、数学と物理学の世界に浸る、完全な理系人間と思われがちだが、なかにはわたしのような変わり者もいる。少年時代は、近くの畑で石器や土器を掘るのに夢中だったし、今でもキトラ古墳の壁画が公開されるなどと聞けば、休みを取って駆けつける、いってみれば考古学ファンに属する。大学の教養時代の選択科目で「民族学」のゼミをとったなどという天文学者は、希少種のはずである。もちろん現在では、宇宙にうかぶ天体の正体を探るのが仕事であるから、理系的な手法・見方で真実に迫っているのはいうまでもない。しかし、その一方で、宇宙観の変遷や世界中のさまざまな民族が星をどのように眺めてきたのか、ということにも、研究とまではいかないものの、今まで興味をもち続けている。
プラネタリウムなどにいくと、よく聞かされるのがギリシア神話である。もともとメソポタミアあたりを起源とする星座物語が、ギリシアを経て現代に語り継がれているものだ。星座そのものに西洋星座を使うことが二〇世紀の初めに決まってしまったので、西洋文化に基づく星座物語が流布しているのは致し方ないことだろう。
だが、文明は多様であり、他の文化にも独特の星の見方があり、独自の星座がつくられていた。そしてユニークな星の物語が紡がれ、語り継がれてきたのである。キトラ古墳の天井に描かれた星座は中国起源の星座だし、七夕伝説や中秋の名月なども東洋独自の伝承だ。日本でも中国星座を用いつつも、各地方独自の星座や星の名前が使われ、豊かな伝承が残されていたことが野尻抱影らの先人によって明らかにされている。たとえば、冬に見えるオリオン座の三つ星をはさんで輝く白色の一等星リゲルと赤色の一等星ベテルギウス。このふたつを源氏と平家の旗の色に見立て、源氏星・平家星とよんでいたのは美濃地方であった。そんな民間伝承を、今でも拾い歩いている在野の研究者がいるのは心強い。
二〇〇九年はガリレオ・ガリレイが夜空に望遠鏡を向けてから四〇〇年目の節目ということで、国連は「世界天文年」と定めた。これを機会に、あまり顧みられなかった東洋の星物語を集めてみよう、という企画も進んでいる。確かに夜空に輝く星の正体は、天文学的にはひとつであり、ユニバーサルに定義できる。しかし、その星をどのようにとらえ、どんな物語を紡ぎ出すかは自由であり、それぞれの地域や文化、そして暮らしを反映しているという点で、とても面白いと思っている。
わたなべ じゅんいち/1960年福島県生まれ。天文学者。東京大学を経て、現在、自然科学研究機構国立天文台および総合研究大学院大学准教授、広報室長。理学博士。研究の傍ら、講演、執筆、メディア出演などで活躍。『新しい太陽系』(新潮社)、『太陽系の果てを探る』(東大出版)、『星の地図館』(小学館)など著書多数。
プラネタリウムなどにいくと、よく聞かされるのがギリシア神話である。もともとメソポタミアあたりを起源とする星座物語が、ギリシアを経て現代に語り継がれているものだ。星座そのものに西洋星座を使うことが二〇世紀の初めに決まってしまったので、西洋文化に基づく星座物語が流布しているのは致し方ないことだろう。
だが、文明は多様であり、他の文化にも独特の星の見方があり、独自の星座がつくられていた。そしてユニークな星の物語が紡がれ、語り継がれてきたのである。キトラ古墳の天井に描かれた星座は中国起源の星座だし、七夕伝説や中秋の名月なども東洋独自の伝承だ。日本でも中国星座を用いつつも、各地方独自の星座や星の名前が使われ、豊かな伝承が残されていたことが野尻抱影らの先人によって明らかにされている。たとえば、冬に見えるオリオン座の三つ星をはさんで輝く白色の一等星リゲルと赤色の一等星ベテルギウス。このふたつを源氏と平家の旗の色に見立て、源氏星・平家星とよんでいたのは美濃地方であった。そんな民間伝承を、今でも拾い歩いている在野の研究者がいるのは心強い。
二〇〇九年はガリレオ・ガリレイが夜空に望遠鏡を向けてから四〇〇年目の節目ということで、国連は「世界天文年」と定めた。これを機会に、あまり顧みられなかった東洋の星物語を集めてみよう、という企画も進んでいる。確かに夜空に輝く星の正体は、天文学的にはひとつであり、ユニバーサルに定義できる。しかし、その星をどのようにとらえ、どんな物語を紡ぎ出すかは自由であり、それぞれの地域や文化、そして暮らしを反映しているという点で、とても面白いと思っている。
わたなべ じゅんいち/1960年福島県生まれ。天文学者。東京大学を経て、現在、自然科学研究機構国立天文台および総合研究大学院大学准教授、広報室長。理学博士。研究の傍ら、講演、執筆、メディア出演などで活躍。『新しい太陽系』(新潮社)、『太陽系の果てを探る』(東大出版)、『星の地図館』(小学館)など著書多数。
レコードは、エジソンとベルリナーの発明以来、技術開発と素材発掘の競争のなかで、おおくの魅力あるジャンルを世に送り出してきた。録音された音を聴くという習慣を身につけた日本人は、「映画説明」をレコードで聴くという不思議なジャンルも生み出した。二〇世紀の音楽文化の原動力となったレコードの歩みを振り返ってみたい。
レコードが発展させた音楽文化
レコード発明の意味
レコードは、一九八〇年代にほぼCDにとってかわられ、今では触れたこともない人が増えている。しかし、ある世代から上の人びとにとって、レコードは音楽そのものだった。音楽を好きだということ、あるいは特定の歌手や音楽家のファンだということは、レコードをもっていることと同義だった。多くの人がレコードを買い、レコードをとおして音楽を聴くことで、そこに録音された音楽を発展させてきた。
二〇世紀前半、録音再生技術の発展とレコードの普及は、音楽のあり方を大きく変えた。音楽は、レコードという商品として流通するようになり、少数のパトロンや特定の共同体に属する人びとに支えられてきた音楽は、レコードを買う不特定多数の人びとのために演奏され録音されるようになった。人びとは、自分のものとなったレコードにより、何回も繰り返し同じ演奏を聴いた。同時に、次々と違う新しい音楽を自分のものとしたくなった。このようにして、新しい音楽が次々と生み出され、伝統的な音楽も大きく変化した。
外地録音と東アジアの音楽文化
東アジアでは、各地を支配下におさめた日本のレコード会社が、音楽産業と音楽の展開に大きな影響をおよぼした。日本の大手レコード会社だった日本コロムビア株式会社の場合、ソウル、台北、上海、ハルビン等に支社や子会社をかまえ、現地社会に向けてレコードを作り流通させた。これらのプレスは、本社川崎工場でおこなったため、レコード原盤が日本に残され、現在、民博に所蔵されている。そこには、民俗的な音楽、古典的な音楽、西洋芸術音楽、流行音楽など、幅広い音楽が録音され、当時の音楽文化研究の重要な資料となっている。
不思議なことに、わたしたちが「外地録音」と名付けたこれらの資料は、日本のレコード会社の歩みのなかでほとんど振り返られることがなかった。本社の人間は、中身にかかわっていなかったために忘れ去られたのだろうか。だとすれば、レコード・プレス自体は本社に頼んだものの、外地録音は、ある程度、自律的に制作されていたことを想像させる。政治経済的には一方的な支配を受けながら、音楽的には、ある程度の自律性をもって自分たちの表現を発展させてきたのだろうか。
一方で、よく資料を見ると、特に流行音楽の作曲や編曲、伴奏などに、しばしば日本人の音楽家が加わっていたことがわかる。欧米の流行を取り入れた音楽については、まだ各地に専門家が少なかったのだろう。その点において、東アジアの音楽家たちは、そうとはあまり意識せずに、交流しながらその技を磨いていったのかもしれない。
インターネットから音楽をダウンロードすることが当たり前になりつつある今日、レコードは忘れ去られようとしている。しかし、レコードとともにわたしたちがどのように音楽文化を発展させてきたのかを振り返ってみることは、今後の音楽文化を展望するうえでも必要なことではないだろうか。
レコードは、一九八〇年代にほぼCDにとってかわられ、今では触れたこともない人が増えている。しかし、ある世代から上の人びとにとって、レコードは音楽そのものだった。音楽を好きだということ、あるいは特定の歌手や音楽家のファンだということは、レコードをもっていることと同義だった。多くの人がレコードを買い、レコードをとおして音楽を聴くことで、そこに録音された音楽を発展させてきた。
二〇世紀前半、録音再生技術の発展とレコードの普及は、音楽のあり方を大きく変えた。音楽は、レコードという商品として流通するようになり、少数のパトロンや特定の共同体に属する人びとに支えられてきた音楽は、レコードを買う不特定多数の人びとのために演奏され録音されるようになった。人びとは、自分のものとなったレコードにより、何回も繰り返し同じ演奏を聴いた。同時に、次々と違う新しい音楽を自分のものとしたくなった。このようにして、新しい音楽が次々と生み出され、伝統的な音楽も大きく変化した。
外地録音と東アジアの音楽文化
東アジアでは、各地を支配下におさめた日本のレコード会社が、音楽産業と音楽の展開に大きな影響をおよぼした。日本の大手レコード会社だった日本コロムビア株式会社の場合、ソウル、台北、上海、ハルビン等に支社や子会社をかまえ、現地社会に向けてレコードを作り流通させた。これらのプレスは、本社川崎工場でおこなったため、レコード原盤が日本に残され、現在、民博に所蔵されている。そこには、民俗的な音楽、古典的な音楽、西洋芸術音楽、流行音楽など、幅広い音楽が録音され、当時の音楽文化研究の重要な資料となっている。
不思議なことに、わたしたちが「外地録音」と名付けたこれらの資料は、日本のレコード会社の歩みのなかでほとんど振り返られることがなかった。本社の人間は、中身にかかわっていなかったために忘れ去られたのだろうか。だとすれば、レコード・プレス自体は本社に頼んだものの、外地録音は、ある程度、自律的に制作されていたことを想像させる。政治経済的には一方的な支配を受けながら、音楽的には、ある程度の自律性をもって自分たちの表現を発展させてきたのだろうか。
一方で、よく資料を見ると、特に流行音楽の作曲や編曲、伴奏などに、しばしば日本人の音楽家が加わっていたことがわかる。欧米の流行を取り入れた音楽については、まだ各地に専門家が少なかったのだろう。その点において、東アジアの音楽家たちは、そうとはあまり意識せずに、交流しながらその技を磨いていったのかもしれない。
インターネットから音楽をダウンロードすることが当たり前になりつつある今日、レコードは忘れ去られようとしている。しかし、レコードとともにわたしたちがどのように音楽文化を発展させてきたのかを振り返ってみることは、今後の音楽文化を展望するうえでも必要なことではないだろうか。
円筒と円盤の攻防
坂野 博之(さかの ひろゆき) 音楽学者
誕生と競合
一八七七年のクリスマス・イヴに、ある装置の特許がアメリカで申請された。「フォノグラフ」と命名されたこの装置は、スズ箔を巻き付けた円筒を手でまわし、そこに針で音溝(おとみぞ)を刻みつけて音声を記録することができた。開発者は《発明王》エジソンである。蓄音機とレコードがこうして誕生した。
その後フォノグラフは改良され、記録媒体に硬質蝋を用いた改良型フォノグラフが一八八八年に完成する。これがいわゆるロウ管式蓄音機とよばれるものである。
ところが、レコードの誕生にはもうひとつの別な系譜があった。フォノグラフが改良されていた最中、同じアメリカでベルリナーが一八八七年に「グラモフォン」を考案した。フォノグラフの発明からちょうど一〇年後のことである。
縦と横
フォノグラフとグラモフォンとではその録音方式が異なっていた。記録媒体に対して、フォノグラフ方式は音溝を垂直方向に刻み(縦振動)、グラモフォン方式は音溝を水平方向に刻んだ(横振動)。つまり再生時に、フォノグラフの針は上下し、グラモフォンの針は左右に動いた。
しかし両者の決定的な違いは、そのレコードのかたちである。フォノグラフ用のレコードは円筒型で、長さが四インチあり二分間再生できた。一方、グラモフォン用のレコードは平円盤で、最初期は直径が五インチ(一二・七センチメートル。ちなみにCDは一二センチメートル)あり、その後七インチと大きくなり片面に約二分間再生できた。
フォノグラフは一台で録音と再生ができる録音機(レコーダー)なのに対して、グラモフォンは再生専用機(プレイヤー)であった。したがってグラモフォンは機械本体の販売とともに、レコードの販売が必要不可欠であった。
録音と複製
商品として録音された最初の円筒は一八八九年にノース・アメリカン・フォノグラフ社から発売された。一方、グラモフォンとそのレコードはドイツの玩具会社ケンメラー&ラインハルト社から一八九〇年に販売された。
当時の録音はマイクロフォンを用いなかった。録音の過程で電気的な増幅は一切なく、空気の振動をそのまま音溝に刻んだ。そのため録音スタジオにはマイクロフォンの代わりに大きな集音ホーン(ラッパ)が設置されていた。そのホーンの末端には振動板と針が取り付けられ、空気の振動を受けて針が動き、記録媒体を削り取って音溝を刻んだ。演奏者は録音の際、この集音ホーンに向かって音を吹き込んだことから、現在でも録音することを「吹込み」とよぶ。
円盤の場合、録音された原盤から型を取り、それをもとにしてプレスすれば、一回の録音で効率よく大量に複製が作れた。ところが円筒は容易に型が取れないため、複数の円筒を作るには同じ演奏を繰り返し何度も録音する必要があった。
タイトルの充実
ベルリナーは自ら一八九五年にベルリナー・グラモフォン社を設立して本格的な事業展開をおこなった。エジソンも一八九六年にナショナル・フォノグラフ社を設立し、さらにヨーロッパへと進出した。
ベルリナーも少し遅れてヨーロッパへと進出する。そのヨーロッパ本社とでも言うべき英グラモフォン社(現在のEMI)は、録音プロデューサーのガイズバーグが中心となり、まずヨーロッパでシャリアピンやカルーソといった大物歌手の録音をおこなった。
続いてガイズバーグ一行はアジアへの長期出張録音をおこなう。コルカタ(カルカッタ)、シンガポール、香港、上海を経て、一九〇三年に来日する。そして落語家の快楽亭ブラックを仲介者にして、二七三面分のレコード録音をおこなった。これらの録音は一一枚組のCD『全集日本吹き込み事始』として復刻されている。このCD一一枚という枚数はベートーヴェンの交響曲全集が二組も作れる分量である。
こうして、魅力的なタイトルが豊富にそろった録音カタログは円盤の人気をさらに高めたのである。
攻防の終焉とその後
二〇世紀に入り両面盤のレコードが発売されると、円盤と円筒の人気の差は急速に拡がった。これに対抗して、録音機能を省いてフォノグラフをプレイヤー化し、円筒の大量複製を実現したが、結局エジソンは一九一二年に円筒を放棄して縦振動方式の円盤制作へと転換する。しかしそのエジソンも一九二九年、ついに蓄音機事業から撤退し、一九世紀末からおよそ四〇年も続いた録音方式の競合はここに幕を閉じる。
ところが、エジソンがそもそも思い描いていた、録音してそれを再生する、というフォノグラフの基本構想は、その後テープレコーダーに継承され、エジソンの撤退から半世紀を経て携帯用小型カセットとして復活する。
一方、円盤レコードの制作現場では一九二五年からマイクロフォンを用いた電気録音技術が導入される。それまで歌手や器楽の演奏が中心だったジャンルに管弦楽のレパートリーが数多く加わり、レコードの新時代への幕が開いていった。
一八七七年のクリスマス・イヴに、ある装置の特許がアメリカで申請された。「フォノグラフ」と命名されたこの装置は、スズ箔を巻き付けた円筒を手でまわし、そこに針で音溝(おとみぞ)を刻みつけて音声を記録することができた。開発者は《発明王》エジソンである。蓄音機とレコードがこうして誕生した。
その後フォノグラフは改良され、記録媒体に硬質蝋を用いた改良型フォノグラフが一八八八年に完成する。これがいわゆるロウ管式蓄音機とよばれるものである。
ところが、レコードの誕生にはもうひとつの別な系譜があった。フォノグラフが改良されていた最中、同じアメリカでベルリナーが一八八七年に「グラモフォン」を考案した。フォノグラフの発明からちょうど一〇年後のことである。
縦と横
フォノグラフとグラモフォンとではその録音方式が異なっていた。記録媒体に対して、フォノグラフ方式は音溝を垂直方向に刻み(縦振動)、グラモフォン方式は音溝を水平方向に刻んだ(横振動)。つまり再生時に、フォノグラフの針は上下し、グラモフォンの針は左右に動いた。
しかし両者の決定的な違いは、そのレコードのかたちである。フォノグラフ用のレコードは円筒型で、長さが四インチあり二分間再生できた。一方、グラモフォン用のレコードは平円盤で、最初期は直径が五インチ(一二・七センチメートル。ちなみにCDは一二センチメートル)あり、その後七インチと大きくなり片面に約二分間再生できた。
フォノグラフは一台で録音と再生ができる録音機(レコーダー)なのに対して、グラモフォンは再生専用機(プレイヤー)であった。したがってグラモフォンは機械本体の販売とともに、レコードの販売が必要不可欠であった。
録音と複製
商品として録音された最初の円筒は一八八九年にノース・アメリカン・フォノグラフ社から発売された。一方、グラモフォンとそのレコードはドイツの玩具会社ケンメラー&ラインハルト社から一八九〇年に販売された。
当時の録音はマイクロフォンを用いなかった。録音の過程で電気的な増幅は一切なく、空気の振動をそのまま音溝に刻んだ。そのため録音スタジオにはマイクロフォンの代わりに大きな集音ホーン(ラッパ)が設置されていた。そのホーンの末端には振動板と針が取り付けられ、空気の振動を受けて針が動き、記録媒体を削り取って音溝を刻んだ。演奏者は録音の際、この集音ホーンに向かって音を吹き込んだことから、現在でも録音することを「吹込み」とよぶ。
円盤の場合、録音された原盤から型を取り、それをもとにしてプレスすれば、一回の録音で効率よく大量に複製が作れた。ところが円筒は容易に型が取れないため、複数の円筒を作るには同じ演奏を繰り返し何度も録音する必要があった。
タイトルの充実
ベルリナーは自ら一八九五年にベルリナー・グラモフォン社を設立して本格的な事業展開をおこなった。エジソンも一八九六年にナショナル・フォノグラフ社を設立し、さらにヨーロッパへと進出した。
ベルリナーも少し遅れてヨーロッパへと進出する。そのヨーロッパ本社とでも言うべき英グラモフォン社(現在のEMI)は、録音プロデューサーのガイズバーグが中心となり、まずヨーロッパでシャリアピンやカルーソといった大物歌手の録音をおこなった。
続いてガイズバーグ一行はアジアへの長期出張録音をおこなう。コルカタ(カルカッタ)、シンガポール、香港、上海を経て、一九〇三年に来日する。そして落語家の快楽亭ブラックを仲介者にして、二七三面分のレコード録音をおこなった。これらの録音は一一枚組のCD『全集日本吹き込み事始』として復刻されている。このCD一一枚という枚数はベートーヴェンの交響曲全集が二組も作れる分量である。
こうして、魅力的なタイトルが豊富にそろった録音カタログは円盤の人気をさらに高めたのである。
攻防の終焉とその後
二〇世紀に入り両面盤のレコードが発売されると、円盤と円筒の人気の差は急速に拡がった。これに対抗して、録音機能を省いてフォノグラフをプレイヤー化し、円筒の大量複製を実現したが、結局エジソンは一九一二年に円筒を放棄して縦振動方式の円盤制作へと転換する。しかしそのエジソンも一九二九年、ついに蓄音機事業から撤退し、一九世紀末からおよそ四〇年も続いた録音方式の競合はここに幕を閉じる。
ところが、エジソンがそもそも思い描いていた、録音してそれを再生する、というフォノグラフの基本構想は、その後テープレコーダーに継承され、エジソンの撤退から半世紀を経て携帯用小型カセットとして復活する。
一方、円盤レコードの制作現場では一九二五年からマイクロフォンを用いた電気録音技術が導入される。それまで歌手や器楽の演奏が中心だったジャンルに管弦楽のレパートリーが数多く加わり、レコードの新時代への幕が開いていった。
レコードになった「映画説明」
今田 健太郎(いまだ けんたろう) 京都市立芸術大学特別研究員
実演をもとに
日本におけるレコードの歴史をながめていると、「映画説明」という不思議な名前のジャンルを目にする。現在であれば、映画というものは映像と音声を総合した複製技術であり、そのまま楽しむのが普通である。その内容を抜き出して語るという行為が録音に値するとは考えにくいだろう。しかし、レコードという音声の複製技術とそれと向き合った芸能の関係を考えようとするとき、きわめて重要な示唆を与えてくれる。
映画説明とはもともと実演するパフォーマンスであった。映画には、現在のような録音された音声をともなうトーキー(発声)になる以前に、音声を実演で補う無声映画の時代があった。日本においては、こうした、映像にしたがってその内容を解説したり、声真似をしてせりふを入れたりする実演を「映画説明」あるいは「声色」といい、それをおこなう芸能者を「活動写真弁士(略して弁士あるいはカツベン)」「映画解説者」とよんだ。
一九〇〇年代から一九三〇年代にかけて、無声映画は日本全国において急速に普及する。映画館は各地の芝居小屋にとってかわり、映画説明の弁士たちは落語や浪花節の語り手をおしのけて大衆娯楽の花形となった。映画説明の実演そのものも、人気のあった浪花節や流行歌などともに、当時普及しつつあったレコードに、多数吹き込まれることになるのである。
型のないパフォーマンス
ところで映画説明は、実演するパフォーマンスとはいえ、従来の芸能とはまったく異なるところがある。それは、決まったかたちや演目をもっていないということだ。従来の芸能は、それぞれのジャンルごとに独特のパフォーマンスのかたちが確立されているため、それを見たり聞いたりすることでその芸能を特定できる。たとえば、落語には落語に特徴的な身体動作、音声、演目、舞台演出があるし、講談にしても浪花節にしても然(しか)りである。それに対して、映画説明というパフォーマンスは、極端にいえば、映画を上映にしたがって説明する語りであれば、何をやっても映画説明となるのである。
このため、物売りの口上や政治家の演説から、講談調、新劇調、歌舞伎の役者の声真似、浪花節よろしくフシをはさんだりといったものまで、さまざまな話芸・舌耕芸が凝らされることになった。そもそも弁士たちが、なんらかの芸の素養をもっている場合が多かったようである。たとえば、当時の映画雑誌の「弁士の得意と嗜好」という記事を見てみよう(写真1)。有名弁士たちの素顔をうわさ話として報告しているのだが、皆、歌や舞などの芸をもっていて(ファン雑誌なので鵜呑みにはできないとはいえ)、玄人はだしの腕前だと評されている。さらに注目すべきは、これらを映画説明に応用していたらしいということだ。たとえば、土屋松濤の項目を見ると、得意を「追分節」としており、それを映画説明のなかでしばしば披露したことがうかがえる。
トーキーさえも映画説明!?
さて、本題に戻ろう。この、いわば「なんでもあり」の映画説明がレコードに吹き込まれ、それが後世にまで残ると何がおこるのだろう?この実演が存在していた時代には、映画説明レコードは、他の語り芸や演劇とは区別された、ひとつのジャンルとして認識されていたことはおそらく間違いない。レコードのラベルもそのように記されているし、レコードに吹き込んだのは有名弁士たちであり、演目も映画のタイトルをそのままもってきているので、当時の人びとなら、映画説明という実演をもとにした録音であることをたやすく想像できただろう。
しかし、すでに述べたように、映画説明は確固としたパフォーマンスのかたちをもたない。それゆえか、映画説明レコードの録音は、実演の実態から離れてしまい、現在でいえばラジオドラマや歌謡ショーの司会者による前説のような、音声で完結するまとまった語りを志向するようになる。そのような工夫は、すでに無声映画の時代にはじまっていたが、映画のトーキー化によって弁士という生業がなりたたなくなり、さらに拍車がかかったようだ。つまり、実演としての映画説明という背景が失われたため、録音のみで完結せざるをえなくなったのである。
そうした映画説明レコードで代表的なのは、泉詩郎という弁士である。彼はトーキー化の後でも人気を保った数少ない弁士であるが、驚くべきことにトーキー映画の映画説明レコード(!)を多数残している。写真を見てほしい(写真2)。このラベルには「松竹蒲田オールトーキー」とあるとおり、この映画説明がすでに無声映画のものではないことがわかる。「船頭可愛いや」はもともと流行歌であり、この映画はそれを主題歌として劇中に登場させるべく製作された。だが、それをもとにしたこのレコードの売りは、映画の梗概(こうがい)や主題歌もさることながら、泉詩郎という弁士の話芸であることが、このラベルから見てとれるだろう。
泉詩郎という名前も、映画説明レコードというジャンルも、そして映画説明という実演の存在も忘れ去られてしまった現在、このレコードを聞いてわかることといえば、一人の人間によってナレーションとせりふが駆使されてドラマが構成されていることと、その見せ場では風流な七五調の語りをイントロにタイトル曲が挿入されるということである。これらは、現在のテレビの司会や声優などと似て、映画説明というものを知らなくてもなかなか楽しめるだろう。しかし、当時の実演としての映画説明や、そもそもこのトーキー映画とどのような関係をもっていたのかについて、教えてくれることはほとんどない。
すでに一世紀を超えるレコードの歴史のなかで、映画説明レコードというジャンルのあらわれる時期は非常に限られるし、これを成立させていた同時代の芸能やコンテクストもほとんど失われてしまっており、これを適切に評価することが難しくなっている。とはいえ、現在にも存在する、複製された声とそれによって紡がれるドラマや話芸の基盤となっていることは容易に推測できるだろう。さらにいえば、映画説明レコードを考えることによって、わたしたちの複製された声を理解するという行為が、いかに複雑な状況によってなりたっているかが見えてくるのである。
日本におけるレコードの歴史をながめていると、「映画説明」という不思議な名前のジャンルを目にする。現在であれば、映画というものは映像と音声を総合した複製技術であり、そのまま楽しむのが普通である。その内容を抜き出して語るという行為が録音に値するとは考えにくいだろう。しかし、レコードという音声の複製技術とそれと向き合った芸能の関係を考えようとするとき、きわめて重要な示唆を与えてくれる。
映画説明とはもともと実演するパフォーマンスであった。映画には、現在のような録音された音声をともなうトーキー(発声)になる以前に、音声を実演で補う無声映画の時代があった。日本においては、こうした、映像にしたがってその内容を解説したり、声真似をしてせりふを入れたりする実演を「映画説明」あるいは「声色」といい、それをおこなう芸能者を「活動写真弁士(略して弁士あるいはカツベン)」「映画解説者」とよんだ。
一九〇〇年代から一九三〇年代にかけて、無声映画は日本全国において急速に普及する。映画館は各地の芝居小屋にとってかわり、映画説明の弁士たちは落語や浪花節の語り手をおしのけて大衆娯楽の花形となった。映画説明の実演そのものも、人気のあった浪花節や流行歌などともに、当時普及しつつあったレコードに、多数吹き込まれることになるのである。
型のないパフォーマンス
ところで映画説明は、実演するパフォーマンスとはいえ、従来の芸能とはまったく異なるところがある。それは、決まったかたちや演目をもっていないということだ。従来の芸能は、それぞれのジャンルごとに独特のパフォーマンスのかたちが確立されているため、それを見たり聞いたりすることでその芸能を特定できる。たとえば、落語には落語に特徴的な身体動作、音声、演目、舞台演出があるし、講談にしても浪花節にしても然(しか)りである。それに対して、映画説明というパフォーマンスは、極端にいえば、映画を上映にしたがって説明する語りであれば、何をやっても映画説明となるのである。
このため、物売りの口上や政治家の演説から、講談調、新劇調、歌舞伎の役者の声真似、浪花節よろしくフシをはさんだりといったものまで、さまざまな話芸・舌耕芸が凝らされることになった。そもそも弁士たちが、なんらかの芸の素養をもっている場合が多かったようである。たとえば、当時の映画雑誌の「弁士の得意と嗜好」という記事を見てみよう(写真1)。有名弁士たちの素顔をうわさ話として報告しているのだが、皆、歌や舞などの芸をもっていて(ファン雑誌なので鵜呑みにはできないとはいえ)、玄人はだしの腕前だと評されている。さらに注目すべきは、これらを映画説明に応用していたらしいということだ。たとえば、土屋松濤の項目を見ると、得意を「追分節」としており、それを映画説明のなかでしばしば披露したことがうかがえる。
トーキーさえも映画説明!?
さて、本題に戻ろう。この、いわば「なんでもあり」の映画説明がレコードに吹き込まれ、それが後世にまで残ると何がおこるのだろう?この実演が存在していた時代には、映画説明レコードは、他の語り芸や演劇とは区別された、ひとつのジャンルとして認識されていたことはおそらく間違いない。レコードのラベルもそのように記されているし、レコードに吹き込んだのは有名弁士たちであり、演目も映画のタイトルをそのままもってきているので、当時の人びとなら、映画説明という実演をもとにした録音であることをたやすく想像できただろう。
しかし、すでに述べたように、映画説明は確固としたパフォーマンスのかたちをもたない。それゆえか、映画説明レコードの録音は、実演の実態から離れてしまい、現在でいえばラジオドラマや歌謡ショーの司会者による前説のような、音声で完結するまとまった語りを志向するようになる。そのような工夫は、すでに無声映画の時代にはじまっていたが、映画のトーキー化によって弁士という生業がなりたたなくなり、さらに拍車がかかったようだ。つまり、実演としての映画説明という背景が失われたため、録音のみで完結せざるをえなくなったのである。
そうした映画説明レコードで代表的なのは、泉詩郎という弁士である。彼はトーキー化の後でも人気を保った数少ない弁士であるが、驚くべきことにトーキー映画の映画説明レコード(!)を多数残している。写真を見てほしい(写真2)。このラベルには「松竹蒲田オールトーキー」とあるとおり、この映画説明がすでに無声映画のものではないことがわかる。「船頭可愛いや」はもともと流行歌であり、この映画はそれを主題歌として劇中に登場させるべく製作された。だが、それをもとにしたこのレコードの売りは、映画の梗概(こうがい)や主題歌もさることながら、泉詩郎という弁士の話芸であることが、このラベルから見てとれるだろう。
泉詩郎という名前も、映画説明レコードというジャンルも、そして映画説明という実演の存在も忘れ去られてしまった現在、このレコードを聞いてわかることといえば、一人の人間によってナレーションとせりふが駆使されてドラマが構成されていることと、その見せ場では風流な七五調の語りをイントロにタイトル曲が挿入されるということである。これらは、現在のテレビの司会や声優などと似て、映画説明というものを知らなくてもなかなか楽しめるだろう。しかし、当時の実演としての映画説明や、そもそもこのトーキー映画とどのような関係をもっていたのかについて、教えてくれることはほとんどない。
すでに一世紀を超えるレコードの歴史のなかで、映画説明レコードというジャンルのあらわれる時期は非常に限られるし、これを成立させていた同時代の芸能やコンテクストもほとんど失われてしまっており、これを適切に評価することが難しくなっている。とはいえ、現在にも存在する、複製された声とそれによって紡がれるドラマや話芸の基盤となっていることは容易に推測できるだろう。さらにいえば、映画説明レコードを考えることによって、わたしたちの複製された声を理解するという行為が、いかに複雑な状況によってなりたっているかが見えてくるのである。
穴があくほどものを見る
ここに一枚の袋がある。これは、インド西部のグジャラート州アフマダーバードの骨董品屋で購入した袋である(写真1)。これを購入した五年前、店主からの説明はグジャラート州西部のカッチ県に住むラバーリーの女性が、婚礼用の衣装や道具を入れて運ぶ袋「コトリィ」との説明を受けた。フムフムなるほどと、納得をしながら何年間は我が家のタンスで眠っていた。
先日、久しぶりにこの袋を手に取る機会があり、以前、説明を受けた婚礼用袋という目線でこの袋を見ると、何か不自然なことに気がついた。通常、ラバーリーの人びとは婚礼用に使用するものには、使い古した布を使用することはめったになく、新しい布を用いて制作をする。じっくりこの袋を見てみると、袋の上半分に用いられている布は、着古した男性の下衣を使用している。男性の下衣に用いられる木綿布にはボーダー部分に縞模様が織り込まれており、この袋の中央のタテ縞は、まさに下衣のボーダー部分を再利用して作られたことがよくわかる(写真2)。
また、この袋を裏返してみると、使われている下衣の布には、何度も何度も、継ぎ接ぎをした部分がある。きっと、一枚の布を大切に使うために、穴があいたら繕(つくろい)い、そしてまた穴があいたら繕うということが繰り返され、少しずつ異なった木綿布が何枚にも合わさっているのである(写真3)。さらに、袋には泥のような汚れもついており、明らかに儀礼でしか使われていない他の婚礼用袋とは異なっている。
きっと、この袋は婚礼用ではない。こんな、当たり前のことに何故、長いあいだ気がつかなかったのであろうか?わたしは一九九七年からカッチ県のラバーリーを調査対象として、彼らの刺繍布は見慣れてきたはずである。骨董品屋の店主があまりにも饒舌(じょうぜつ)であったことを差し引いても、わたしは彼らのものを見慣れすぎていて、ものをそのまま素直に見ることができていなかったのではないか。
改めて、わたしはこの袋がどうやって作られ、どのように使われるのかといったことを確認するために、この袋を片手にカッチ県を訪れた。カッチ県で生活をするラバーリーはラクダやヒツジ、ヤギなどの牧畜をおこなう人びとや、牧畜生活から離れてサービス業やトラックの運転手、アラブ諸国への出稼ぎなどで生計を立てている人もいる。牧畜生活から離れている人びとに、この袋のことを尋ねると、「婚礼用の袋」という返答がやはり多かった。
しかし、牧畜生活をしている人たちは、これは「ガラヌコトリィだ!」と口をそろえて答えた。この袋は、放牧中の晩に子ヒツジや子ヤギが逃げないようにつなげておく首輪・ガラヌを入れるための専門の袋であるという(写真4)。予想どおり、この袋は婚礼用ではなく、放牧用の袋であった。だが、同じような放牧用袋がたくさんあるなかで何故、この袋が首輪入れ専門の袋とわかるのであろうか。首を傾げているわたしを見て、彼らはタテヨコの袋の比率と使われている布の種類、施されている刺繍でわかる、そして、それをおまえが判断するにはもっともっとたくさんのものを見なければダメだという。
現在の牧畜生活で使われている同様の袋は、わずかな刺子のみの簡素なものとなっている(写真5)。改めて、この袋を見てみると、首輪を入れる袋にここまでの細かい刺繍を丁寧に施した人の手の動きまでを想像することはできても、彼らの言う微妙な差異を理解することはできなかった。
当然、ものを見るにはそのものが作られた社会や文化への理解が必要となる。しかし、ときには先入観をもたずに、素直にものと出合って、素直に感じ取ることも大切なことである。
ものときちんと向き合って、ものが語っていることを聞き取る。そして、もの全体を見てから細部を見る、そしてまた全体を見る。この一見、当たり前で愚鈍のような行為を繰り返すことによって、あらたな発見がある。昨年、民博にインド西部の刺繍布約三五〇点があらたに収蔵品として加えられた。これらの刺繍布を穴があくほど見てみたい。
先日、久しぶりにこの袋を手に取る機会があり、以前、説明を受けた婚礼用袋という目線でこの袋を見ると、何か不自然なことに気がついた。通常、ラバーリーの人びとは婚礼用に使用するものには、使い古した布を使用することはめったになく、新しい布を用いて制作をする。じっくりこの袋を見てみると、袋の上半分に用いられている布は、着古した男性の下衣を使用している。男性の下衣に用いられる木綿布にはボーダー部分に縞模様が織り込まれており、この袋の中央のタテ縞は、まさに下衣のボーダー部分を再利用して作られたことがよくわかる(写真2)。
また、この袋を裏返してみると、使われている下衣の布には、何度も何度も、継ぎ接ぎをした部分がある。きっと、一枚の布を大切に使うために、穴があいたら繕(つくろい)い、そしてまた穴があいたら繕うということが繰り返され、少しずつ異なった木綿布が何枚にも合わさっているのである(写真3)。さらに、袋には泥のような汚れもついており、明らかに儀礼でしか使われていない他の婚礼用袋とは異なっている。
きっと、この袋は婚礼用ではない。こんな、当たり前のことに何故、長いあいだ気がつかなかったのであろうか?わたしは一九九七年からカッチ県のラバーリーを調査対象として、彼らの刺繍布は見慣れてきたはずである。骨董品屋の店主があまりにも饒舌(じょうぜつ)であったことを差し引いても、わたしは彼らのものを見慣れすぎていて、ものをそのまま素直に見ることができていなかったのではないか。
改めて、わたしはこの袋がどうやって作られ、どのように使われるのかといったことを確認するために、この袋を片手にカッチ県を訪れた。カッチ県で生活をするラバーリーはラクダやヒツジ、ヤギなどの牧畜をおこなう人びとや、牧畜生活から離れてサービス業やトラックの運転手、アラブ諸国への出稼ぎなどで生計を立てている人もいる。牧畜生活から離れている人びとに、この袋のことを尋ねると、「婚礼用の袋」という返答がやはり多かった。
しかし、牧畜生活をしている人たちは、これは「ガラヌコトリィだ!」と口をそろえて答えた。この袋は、放牧中の晩に子ヒツジや子ヤギが逃げないようにつなげておく首輪・ガラヌを入れるための専門の袋であるという(写真4)。予想どおり、この袋は婚礼用ではなく、放牧用の袋であった。だが、同じような放牧用袋がたくさんあるなかで何故、この袋が首輪入れ専門の袋とわかるのであろうか。首を傾げているわたしを見て、彼らはタテヨコの袋の比率と使われている布の種類、施されている刺繍でわかる、そして、それをおまえが判断するにはもっともっとたくさんのものを見なければダメだという。
現在の牧畜生活で使われている同様の袋は、わずかな刺子のみの簡素なものとなっている(写真5)。改めて、この袋を見てみると、首輪を入れる袋にここまでの細かい刺繍を丁寧に施した人の手の動きまでを想像することはできても、彼らの言う微妙な差異を理解することはできなかった。
当然、ものを見るにはそのものが作られた社会や文化への理解が必要となる。しかし、ときには先入観をもたずに、素直にものと出合って、素直に感じ取ることも大切なことである。
ものときちんと向き合って、ものが語っていることを聞き取る。そして、もの全体を見てから細部を見る、そしてまた全体を見る。この一見、当たり前で愚鈍のような行為を繰り返すことによって、あらたな発見がある。昨年、民博にインド西部の刺繍布約三五〇点があらたに収蔵品として加えられた。これらの刺繍布を穴があくほど見てみたい。
取ってつけたような…-シドニーのミュージアムから
二〇〇八年一月末、わたしは真夏のシドニーを訪ねた。ミュージアムの展示が、どのような狙いに基づいてなされているかを調査するためである。
おもだったミュージアムを一通り見終わったあとで、わたしはチャイナ・タウンにほど近いパワーハウス博物館に足を運んでみた。ここは、その名のとおり、もとは市内を走るトラム・カーの発電所だった建物を改装し、サイエンスとデザインの博物館として一九八八年にオープンした。
展示は主として、一八世紀後半から現在までの、家具や衣装、陶磁器、装飾品などデザイン史と、機関車から自動車、飛行機、はては宇宙探査、原子力発電に至る科学技術の歴史で構成されている。一見して、幼稚園児から小、中学生ぐらいまでを意識していることが看て取れる。
圧巻は、一八世紀後半、産業革命の原動力となったワットの蒸気機関の再現展示である。高さ約一二、三メートル、しかもそれは実際に動く。そのちょうど前あたりに、一八世紀から一九世紀にかけてのイギリスの衣装と陶磁器のコーナーが拡がり、ウェッジウッドなどの食器類や、フロックコートに身を包んだ紳士とドレスを着た淑女が展示されている。世界に先駆けて産業革命を成し遂げ、一九世紀ヴィクトリア朝の繁栄を築いた大英帝国の栄光の歴史を、そのまま我われは引き継いでいる・・・そんなメッセージが、一帯の展示からは伝わってくる。でも、その我われとは誰のことだ、と思わず半畳を入れたくなるが、ここではそのことではなく、別の点を話題にしたい。
一八、一九世紀のイギリスは、たしかに世界に進出し、繁栄を謳歌した。しかし、底辺の人びと、とくに婦女子の生活は惨状を極めていたはずだ。そんなことを呟きながら、蒸気機関の壁の背後にある階段を一番上の四階まで上がっていくと、壁と壁に挟まれた狭い空間の一番端にひっそりと「一八世紀における底辺の暮らし」と題する小展示があった。画家ホガースの有名な銅版画「ジン横町」や「闘鶏場」の写真パネルが貼られており、「この時代、人びとは酒とどんちゃん騒ぎに明け暮れていた」という解説も付けられている。一応は史実を踏まえているという苦心の展示であろう。もちろん、「不都合な真実」にも目配りをしているというのは、それなりに良心的といえばいえる。ただ、どこか取ってつけたような印象が否めない。それにたぶん、この場所では誰の目にも触れないだろう。
帰る道すがら、シドニーでそれまでに見たすべての博物館、美術館の展示をわたしは思い返していた。そういえば、どこへいっても必ずアボリジナルをあつかった展示があったが、そのなかには、前後の脈絡にあまりなじんでいないように見えるものもあった。つまりは、取ってつけたような、不自然な感じを受けたのである。
たった一回、それも数日間いただけでそう言い切るのはいかにも乱暴に過ぎるけれども、さまざまな歴史観や主張を含み得るテーマについて、過不足なく、かつ、あるストーリーのなかに位置づけて展示することの難しさを、あらためて感じたことである。
おもだったミュージアムを一通り見終わったあとで、わたしはチャイナ・タウンにほど近いパワーハウス博物館に足を運んでみた。ここは、その名のとおり、もとは市内を走るトラム・カーの発電所だった建物を改装し、サイエンスとデザインの博物館として一九八八年にオープンした。
展示は主として、一八世紀後半から現在までの、家具や衣装、陶磁器、装飾品などデザイン史と、機関車から自動車、飛行機、はては宇宙探査、原子力発電に至る科学技術の歴史で構成されている。一見して、幼稚園児から小、中学生ぐらいまでを意識していることが看て取れる。
圧巻は、一八世紀後半、産業革命の原動力となったワットの蒸気機関の再現展示である。高さ約一二、三メートル、しかもそれは実際に動く。そのちょうど前あたりに、一八世紀から一九世紀にかけてのイギリスの衣装と陶磁器のコーナーが拡がり、ウェッジウッドなどの食器類や、フロックコートに身を包んだ紳士とドレスを着た淑女が展示されている。世界に先駆けて産業革命を成し遂げ、一九世紀ヴィクトリア朝の繁栄を築いた大英帝国の栄光の歴史を、そのまま我われは引き継いでいる・・・そんなメッセージが、一帯の展示からは伝わってくる。でも、その我われとは誰のことだ、と思わず半畳を入れたくなるが、ここではそのことではなく、別の点を話題にしたい。
一八、一九世紀のイギリスは、たしかに世界に進出し、繁栄を謳歌した。しかし、底辺の人びと、とくに婦女子の生活は惨状を極めていたはずだ。そんなことを呟きながら、蒸気機関の壁の背後にある階段を一番上の四階まで上がっていくと、壁と壁に挟まれた狭い空間の一番端にひっそりと「一八世紀における底辺の暮らし」と題する小展示があった。画家ホガースの有名な銅版画「ジン横町」や「闘鶏場」の写真パネルが貼られており、「この時代、人びとは酒とどんちゃん騒ぎに明け暮れていた」という解説も付けられている。一応は史実を踏まえているという苦心の展示であろう。もちろん、「不都合な真実」にも目配りをしているというのは、それなりに良心的といえばいえる。ただ、どこか取ってつけたような印象が否めない。それにたぶん、この場所では誰の目にも触れないだろう。
帰る道すがら、シドニーでそれまでに見たすべての博物館、美術館の展示をわたしは思い返していた。そういえば、どこへいっても必ずアボリジナルをあつかった展示があったが、そのなかには、前後の脈絡にあまりなじんでいないように見えるものもあった。つまりは、取ってつけたような、不自然な感じを受けたのである。
たった一回、それも数日間いただけでそう言い切るのはいかにも乱暴に過ぎるけれども、さまざまな歴史観や主張を含み得るテーマについて、過不足なく、かつ、あるストーリーのなかに位置づけて展示することの難しさを、あらためて感じたことである。
黒タイの蚊帳
蚊帳(標本番号H179219、高さ/162cm 幅/204cm 奥行/160cm)
蚊帳(標本番号H179219、高さ/162cm 幅/204cm 奥行/160cm)
藍で黒く染め抜いた胴部の上に、鮮やかな絹の縁飾りが付いている。織り柄から察するに、黒タイの蚊帳だろう。黒タイはベトナムとラオスの国境地域に住む盆地民である。
沢の水は、豊かな米の生産を約束するが、マラリア蚊をも発生させる。蚊帳の使用は予防に有効で、東南アジアでは、伝統的な蚊帳使用地域とマラリア地域はかなり合致しているようである。
日本では涼しげな薄い色の蚊帳が好まれた。中国やベトナムでも白が多い。しかし黒タイのものは総じて黒い。白を喪服の色として忌むのがひとつの理由である。くわえて、間仕切りのない家で、蚊帳の中が唯一のプライベート空間だからだろうか。
蚊帳は、なかで寝る人の行動をも物語る。蚊帳が開かれているのは、すでにふだん通りの活動が始まっているからである。しかし昼寝や着替えの際には、なかに戻ってくる。この開閉運動が、昼と夜を演出し、外からの視線をコントロールしているのである。
蚊帳はめったに取り外されることがない。なかで寝ていた人が死んだことを意味するからである。故人があの世に行っても安眠できるように祈って、墓所に建てる御霊屋に蚊帳を入れることもある。
近年、村では、巧みな意匠のものが減った。身の回りの衣料品を女性たちが手作りするような習慣が廃れてきたからである。かわって、ナイロン製の白い蚊帳が普及しつつある。一方で、北タイ、チェンマイのナイトバザールでは、手の込んだ縁飾りの古布が高額で取引されている。これが市場経済というものだろう。しかし筆者は、その綾錦を夜ごとに天蓋(てんがい)としていた人の魂の平安を、ひそかに念じる。葬礼が終わり、蚊帳が外された寝所の空虚さを思い出すからである。
沢の水は、豊かな米の生産を約束するが、マラリア蚊をも発生させる。蚊帳の使用は予防に有効で、東南アジアでは、伝統的な蚊帳使用地域とマラリア地域はかなり合致しているようである。
日本では涼しげな薄い色の蚊帳が好まれた。中国やベトナムでも白が多い。しかし黒タイのものは総じて黒い。白を喪服の色として忌むのがひとつの理由である。くわえて、間仕切りのない家で、蚊帳の中が唯一のプライベート空間だからだろうか。
蚊帳は、なかで寝る人の行動をも物語る。蚊帳が開かれているのは、すでにふだん通りの活動が始まっているからである。しかし昼寝や着替えの際には、なかに戻ってくる。この開閉運動が、昼と夜を演出し、外からの視線をコントロールしているのである。
蚊帳はめったに取り外されることがない。なかで寝ていた人が死んだことを意味するからである。故人があの世に行っても安眠できるように祈って、墓所に建てる御霊屋に蚊帳を入れることもある。
近年、村では、巧みな意匠のものが減った。身の回りの衣料品を女性たちが手作りするような習慣が廃れてきたからである。かわって、ナイロン製の白い蚊帳が普及しつつある。一方で、北タイ、チェンマイのナイトバザールでは、手の込んだ縁飾りの古布が高額で取引されている。これが市場経済というものだろう。しかし筆者は、その綾錦を夜ごとに天蓋(てんがい)としていた人の魂の平安を、ひそかに念じる。葬礼が終わり、蚊帳が外された寝所の空虚さを思い出すからである。
サトウキビ産業のたそがれ
フィジー人とインド人
フィジーのナンディ国際空港を出て、かつての調査地であったラウトカ方面のヤツメ村落に向かう。二〇〇七年一二月のことであった。二〇〇〇年の本格的な調査から何度目かの訪問となる。研究関心の変化に伴い古巣での滞在期間は減りつつあるが、フィジーに行くときには必ずかつて生活をともにした人びとの顔を拝みに行くことにしている。調査者の倫理とかいうおおげさなことではなく、むかしなじみに囲まれているのは過ごしやすいし、老人の消息を尋ね、子どもの成長を見るのはかけがえのない経験だからだ。
行くたびに目を引く変化は何も人間だけに起きているわけではない。周りのサトウキビ畑は叢(くさむら)となり、点在していたインド人サトウキビ農家の家屋のいくつかは、フィジー人に占拠されている。
背景には、地主として国土の八三パーセント以上の土地を所有するフィジー人、サトウキビ生産者として借地するインド人という植民地時代に培われた民族間関係が終焉を迎えたことがある。クーデタに代表される政治問題は、両民族の関係に水を差し土地のリース延長を阻害したし、先進国との経済協定に依存してきたフィジーのサトウキビ産業の構造自体も危機的状況にある。定年後の収入をサトウキビに頼っているインド人の一人はいった。「(サトウキビ産業の現状は)悪いとは言いたくない。とにかくできることをやっておくだけだ」。
土地を借りていたのは何もインド人だけではない。遠く離島カンダヴから、ヤツメ村落に移り住み、サトウキビ生産農家に特化したフィジー人もいる。四世代にわたってその村落にいたため子どもの多くはこの村落の方言しか解さない。そんな彼らもサトウキビ畑のリース切れに伴い、見知らぬ出身地へ帰郷しつつあるのだ。老人の一人は、新年会の席でこっそり話しかけてきた。「おれは今年で七〇だが、こんなに生活が厳しいなんて、これまでなかったことだ」。
時代の終わり
しかし、フィジー人、ことに農村部で生活している彼らはまだましな状況だともいえる。自分の土地でサトウキビ栽培をしている人も多く、仮にリース契約が切れたとしても、寝起きする場所だけならばなんとか確保できる。さらに厳しい現実に直面しなければならないのは、フィジーで土地をもつことがむずかしい他民族、ことにサトウキビとともに育ってきたインド人であろう。
年が明けてヤツメ村落を離れ、最近調査を始めたナウソリ近郊に向かった。そこでは、リースが切れ、また都会での職を求めて、ヴァヌアレヴ島から押し寄せている大量のインド人を目にした。たまたま知り合いになったインド人は語る。「このへんではフィジー人の畑の片隅に借地して大変だよ。借地料なんかフィジー人の言いなりだ」。
サトウキビ産業の再生に期待をかける人も多いが閉塞感はぬぐいきれない現状である。ひとつの産業の終焉は、ひとつの時代の終わりを象徴する。そこでは、これまでの関係が清算され、あらたな現実のなかでやりくりしていくよう人びとに迫る。ヤツメ村落を離れカンダヴに向かったもう老年期に当たる知人の姿を思い返しつつ、彼のこれからの生活がよきものであることを願わずにはいられなかった。
フィジーのナンディ国際空港を出て、かつての調査地であったラウトカ方面のヤツメ村落に向かう。二〇〇七年一二月のことであった。二〇〇〇年の本格的な調査から何度目かの訪問となる。研究関心の変化に伴い古巣での滞在期間は減りつつあるが、フィジーに行くときには必ずかつて生活をともにした人びとの顔を拝みに行くことにしている。調査者の倫理とかいうおおげさなことではなく、むかしなじみに囲まれているのは過ごしやすいし、老人の消息を尋ね、子どもの成長を見るのはかけがえのない経験だからだ。
行くたびに目を引く変化は何も人間だけに起きているわけではない。周りのサトウキビ畑は叢(くさむら)となり、点在していたインド人サトウキビ農家の家屋のいくつかは、フィジー人に占拠されている。
背景には、地主として国土の八三パーセント以上の土地を所有するフィジー人、サトウキビ生産者として借地するインド人という植民地時代に培われた民族間関係が終焉を迎えたことがある。クーデタに代表される政治問題は、両民族の関係に水を差し土地のリース延長を阻害したし、先進国との経済協定に依存してきたフィジーのサトウキビ産業の構造自体も危機的状況にある。定年後の収入をサトウキビに頼っているインド人の一人はいった。「(サトウキビ産業の現状は)悪いとは言いたくない。とにかくできることをやっておくだけだ」。
土地を借りていたのは何もインド人だけではない。遠く離島カンダヴから、ヤツメ村落に移り住み、サトウキビ生産農家に特化したフィジー人もいる。四世代にわたってその村落にいたため子どもの多くはこの村落の方言しか解さない。そんな彼らもサトウキビ畑のリース切れに伴い、見知らぬ出身地へ帰郷しつつあるのだ。老人の一人は、新年会の席でこっそり話しかけてきた。「おれは今年で七〇だが、こんなに生活が厳しいなんて、これまでなかったことだ」。
時代の終わり
しかし、フィジー人、ことに農村部で生活している彼らはまだましな状況だともいえる。自分の土地でサトウキビ栽培をしている人も多く、仮にリース契約が切れたとしても、寝起きする場所だけならばなんとか確保できる。さらに厳しい現実に直面しなければならないのは、フィジーで土地をもつことがむずかしい他民族、ことにサトウキビとともに育ってきたインド人であろう。
年が明けてヤツメ村落を離れ、最近調査を始めたナウソリ近郊に向かった。そこでは、リースが切れ、また都会での職を求めて、ヴァヌアレヴ島から押し寄せている大量のインド人を目にした。たまたま知り合いになったインド人は語る。「このへんではフィジー人の畑の片隅に借地して大変だよ。借地料なんかフィジー人の言いなりだ」。
サトウキビ産業の再生に期待をかける人も多いが閉塞感はぬぐいきれない現状である。ひとつの産業の終焉は、ひとつの時代の終わりを象徴する。そこでは、これまでの関係が清算され、あらたな現実のなかでやりくりしていくよう人びとに迫る。ヤツメ村落を離れカンダヴに向かったもう老年期に当たる知人の姿を思い返しつつ、彼のこれからの生活がよきものであることを願わずにはいられなかった。
残存デンプン研究のススメ
渋谷 綾子(しぶたに あやこ) 総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程
農耕が始まる前の食事
食べることは生きることである。現代の日本では非常にたくさんの食べ物があふれており、何を食べるか食べないか、自由に選ぶことが可能である。では、はるかむかしに生きていた人たち、たとえば旧石器時代や縄文時代の人びとはどんなものを食べていたのだろうか。彼らにも、現代のわたしたちのように食べ物を自由に選ぶことはできたのだろうか。
一般に、農耕が始まるまでは人びとは動物を狩り、魚介類を獲り、植物を採って、それらを食料にしていたと言われている。彼らがどんな動物や魚介類を食べていたのかについては、遺跡から見つかった骨や貝殻などから知ることができる。遺跡から出土した人骨の炭素・窒素アイソトープ値からは、陸上動物を多く食べていたのか、あるいは魚介類や海獣などの水産系資源が多かったのかなど、動物の種類を知ることができる。
ところが、人びとがどんな植物を食べていたのかを証明することは非常に難しい。クリやドングリなど堅い殻をもつ木の実や植物の種は土のなかでも残っており、それらは植物食の証拠になり得る。さらに、前述した人骨の炭素・窒素アイソトープ値からは、具体的な植物名まではわからないまでも、C3型植物(約九割の植物が該当)を多く食べていたか、C4型植物(トウモロコシ・サトウキビなど)の方が多いかを知ることができる。このC3型やC4型というのは、植物を光合成の働きのちがいによってわけたものである。
当然のことながら、こうした「目に見えるかたち」で残る植物ばかりが食べられていたわけではない。イモやワラビ、クズなどのように、腐りやすく土のなかでは残りにくいものについては、確かな証拠がないためにわかっていない。
デンプン粒で証明
そこで、これらの植物が利用されていた証拠を「目に見えるかたち」にするため、考古遺物の表面や遺跡土壌に残るデンプン粒からそれらの証拠を見つけ出すのが残存デンプン研究であり、これはわたしの博士論文研究の主題である。
植物のデンプンは高等植物の種子や茎(幹)、葉、根などの主要部分に蓄積されており、植物のエネルギー源として機能している。デンプンは非常に安定した化学構造をもっており、どのような環境でも残る。こうした特質を活かし、古植生の変化や食物の歴史を探究するのが残存デンプン研究である。
この研究は世界的に見ても比較的新しい分野であり、日本で研究に従事している者はわたしを含めて一〇人もいない。そのため、日本では研究事例の蓄積が第一に求められ、各分野の研究者たちが納得できるような実証性の確立が要求されている。多くの考古学者たちがこの研究の進展を望んでいることは確かだが、実際に始める研究者はほとんどおらず、多くの問題を解決するまでの道のりはとても遠い。
とにもかくにも、日本における研究事例を蓄積し、各方面へ研究成果の報告をおこなうことがわたしの現在のつとめである。多くの人たちに研究への関心をもってもらい、研究の仲間が増えてくれることを切に願っている。
食べることは生きることである。現代の日本では非常にたくさんの食べ物があふれており、何を食べるか食べないか、自由に選ぶことが可能である。では、はるかむかしに生きていた人たち、たとえば旧石器時代や縄文時代の人びとはどんなものを食べていたのだろうか。彼らにも、現代のわたしたちのように食べ物を自由に選ぶことはできたのだろうか。
一般に、農耕が始まるまでは人びとは動物を狩り、魚介類を獲り、植物を採って、それらを食料にしていたと言われている。彼らがどんな動物や魚介類を食べていたのかについては、遺跡から見つかった骨や貝殻などから知ることができる。遺跡から出土した人骨の炭素・窒素アイソトープ値からは、陸上動物を多く食べていたのか、あるいは魚介類や海獣などの水産系資源が多かったのかなど、動物の種類を知ることができる。
ところが、人びとがどんな植物を食べていたのかを証明することは非常に難しい。クリやドングリなど堅い殻をもつ木の実や植物の種は土のなかでも残っており、それらは植物食の証拠になり得る。さらに、前述した人骨の炭素・窒素アイソトープ値からは、具体的な植物名まではわからないまでも、C3型植物(約九割の植物が該当)を多く食べていたか、C4型植物(トウモロコシ・サトウキビなど)の方が多いかを知ることができる。このC3型やC4型というのは、植物を光合成の働きのちがいによってわけたものである。
当然のことながら、こうした「目に見えるかたち」で残る植物ばかりが食べられていたわけではない。イモやワラビ、クズなどのように、腐りやすく土のなかでは残りにくいものについては、確かな証拠がないためにわかっていない。
デンプン粒で証明
そこで、これらの植物が利用されていた証拠を「目に見えるかたち」にするため、考古遺物の表面や遺跡土壌に残るデンプン粒からそれらの証拠を見つけ出すのが残存デンプン研究であり、これはわたしの博士論文研究の主題である。
植物のデンプンは高等植物の種子や茎(幹)、葉、根などの主要部分に蓄積されており、植物のエネルギー源として機能している。デンプンは非常に安定した化学構造をもっており、どのような環境でも残る。こうした特質を活かし、古植生の変化や食物の歴史を探究するのが残存デンプン研究である。
この研究は世界的に見ても比較的新しい分野であり、日本で研究に従事している者はわたしを含めて一〇人もいない。そのため、日本では研究事例の蓄積が第一に求められ、各分野の研究者たちが納得できるような実証性の確立が要求されている。多くの考古学者たちがこの研究の進展を望んでいることは確かだが、実際に始める研究者はほとんどおらず、多くの問題を解決するまでの道のりはとても遠い。
とにもかくにも、日本における研究事例を蓄積し、各方面へ研究成果の報告をおこなうことがわたしの現在のつとめである。多くの人たちに研究への関心をもってもらい、研究の仲間が増えてくれることを切に願っている。
「ハーフ」であることに誇りをもつ、100年に一人の「ミス・ブラジル日本」
アンジェロ・イシ 武蔵大学准教授
望まれる東洋系ハーフ
二〇〇八年は日本からブラジルに最初の移民船が渡ってちょうど一〇〇年になる。この移民一〇〇周年を記念して、出港地の神戸と横浜では、さまざまな記念イベントがおこなわれてきた。そのひとつが、横浜の大桟橋ホールで五月三日に開催された「百周年記念ミス・ブラジル日本」である。このコンテストには日本全国から約七〇人が応募し、優勝者への副賞として新車一台が贈られた。そして、そのミスに輝いたのは、日系三世のアドリアーナ・ラヴィーネ・イナガキである。
アドリアーナはブラジルの最南部、リオグランデドスール州出身。同州はもっとも多くの世界的トップモデルを輩出する「美人の地」として知られ、ファッション界の女王とさえ言われるジゼルの出身地としても有名である。当地の若い女性たちが一度はモデルを夢見るのは当然のことでもある。じつはアドリアーナより一歳年上の姉、イアーナも、早くからモデルとしてのキャリアを実現しようと、積極的にオーディションを受けていたほどだ。「当時ちょっと太っていたので、自分もモデルになれるとは思えなかった」というアドリアーナにとってもそれは大きな夢であった。
アドリアーナの父親はブラジルでは電話会社の事務所に勤務していた。しかし家計事情は思わしくなく、日本へのデカセギを決心した。当初両親だけが来日して、娘たちはブラジルで勉強を続けさせる計画だったが、どうしてもと親に泣きついた二人は結局、ともに来日することになった。二〇〇五年のことであった。
来日後、姉妹は工場でも少し働いたが、日本にもブラジル人学校があることを知り、入学した。学校のレベルに不満で二度も転校したが、二〇〇七年、無事にブラジル人の高校を卒業した。公文式の塾にも通い、日本語の勉強にも力をいれた。
アドリアーナは父親が日系人で、いわゆる「メスチーサ」(混血児)である。日本では、その外見のため、コンビニや電車のなかで幾度か冷たい視線を浴びた。しかし、笑顔が消えなかったのは、日本人と違う顔をしていることが、一方で肯定的に評価される社会でもあったからだ。彼女いわく、自分は背が高くないのでブラジルではあまり目立たなかったが、ここでは「東洋系のハーフ」であることがモデル業界でとても望まれる存在であった。
最初に転機を迎えたのは姉のイアーナだった。彼女は二〇〇六年、在日ブラジル人の二大ミスコンテストのひとつである「ミス・ニッケイ」でいきなり優勝し、モデルとして働き始めた。アドリアーナはバルバラ・ナカツガサというプロモーターが手がけた「ミス・ブラジル日本」に応募し、予選を通過した時点でさっそくある事務所から声がかかり、モデルとしてデビューできた。そして今回のコンテストでの優勝はきっと彼女に飛躍の機会をもたらすだろう。
モデルは一握り
それにしても、何故、三〇万人を超える在日ブラジル人社会において、これほどまでに美人コンテストが盛り上がるのだろうか。それは、何よりもまず、ブラジル出身の日系人女性たちにとっては、モデル業こそが、日本人との差異がプラス評価になる数少ない業界であるからだ。世界でも有数のセレブリティになったジゼルの成功物語が、多くの少女やその保護者たちを刺激していることはいうまでもない。しかし、第二のジゼルを目指す人がこれだけ多いのは、それだけ日本での進学の可能性に寄せる期待が低いということの裏返しだとも言える。
わたしはブラジル出身者に向けた講演や執筆活動のなかで、「モデルになれるのはごく一握りの人だから、きちんと勉強もしましょう」との主張を重ねてきた。アドリアーナの話を聞いて感心したのは、彼女がモデルとして順調な滑り出しを遂げているにもかかわらず、勉学に対する意欲を失っていないことである。彼女は日本語をもっと勉強して、日本の大学でエコツーリズムを勉強するという選択肢も考えたことがある。現時点では、ブラジルを拠点とする通信制の大学で経営学か教育学を勉強することになりそうだが、遠隔教育を実施する複数のブラジルの大学が日本に進出しており、在日ブラジル人のあいだで大きな注目を集めている。
カラオケからコンテストへ
ミスコンテスト全盛期を理解するためのもうひとつのキーワードは、日本におけるブラジル系エスニックビジネスの成熟である。ミスコンテストでは毎回、新車などの豪華賞品を提供する数十のスポンサーの企業名が延々とあげられる。それだけ力のあるスポンサーが存在しなければ、このような大規模なイベントは実現できるはずがない。じつは、一九九〇年代をとおして、同じく一等賞に新車を提供し話題を集めてきたのが、在日ブラジル人のいわゆる「のど自慢」、カラオケ大会であった。移民の第一世代が主役であったカラオケに代わって、移民の第二世代が主役であるミスコンテストがコミュニティでもっとも注目されるイベントに発展したことは、移民社会の変貌を象徴しているともいえる。
アドリアーナの晴れ舞台となったファッションショーは、日本に根を下ろしたブラジル人デザイナー、Linda K.のデザインによるものであった。モデルたちはそこで美貌を披露すると同時に、「あなたは移民一〇〇周年についてどう思いますか?」という質問で知性が試された。アドリアーナの答えは次のようなものであった。「日本からブラジルに渡った祖父母の頑張りこそが、今のわたしにインスピレーションを与えてくれている」。
優勝を手にした五月三日は、奇しくも彼女の一七歳の誕生日でもあった。
二〇〇八年は日本からブラジルに最初の移民船が渡ってちょうど一〇〇年になる。この移民一〇〇周年を記念して、出港地の神戸と横浜では、さまざまな記念イベントがおこなわれてきた。そのひとつが、横浜の大桟橋ホールで五月三日に開催された「百周年記念ミス・ブラジル日本」である。このコンテストには日本全国から約七〇人が応募し、優勝者への副賞として新車一台が贈られた。そして、そのミスに輝いたのは、日系三世のアドリアーナ・ラヴィーネ・イナガキである。
アドリアーナはブラジルの最南部、リオグランデドスール州出身。同州はもっとも多くの世界的トップモデルを輩出する「美人の地」として知られ、ファッション界の女王とさえ言われるジゼルの出身地としても有名である。当地の若い女性たちが一度はモデルを夢見るのは当然のことでもある。じつはアドリアーナより一歳年上の姉、イアーナも、早くからモデルとしてのキャリアを実現しようと、積極的にオーディションを受けていたほどだ。「当時ちょっと太っていたので、自分もモデルになれるとは思えなかった」というアドリアーナにとってもそれは大きな夢であった。
アドリアーナの父親はブラジルでは電話会社の事務所に勤務していた。しかし家計事情は思わしくなく、日本へのデカセギを決心した。当初両親だけが来日して、娘たちはブラジルで勉強を続けさせる計画だったが、どうしてもと親に泣きついた二人は結局、ともに来日することになった。二〇〇五年のことであった。
来日後、姉妹は工場でも少し働いたが、日本にもブラジル人学校があることを知り、入学した。学校のレベルに不満で二度も転校したが、二〇〇七年、無事にブラジル人の高校を卒業した。公文式の塾にも通い、日本語の勉強にも力をいれた。
アドリアーナは父親が日系人で、いわゆる「メスチーサ」(混血児)である。日本では、その外見のため、コンビニや電車のなかで幾度か冷たい視線を浴びた。しかし、笑顔が消えなかったのは、日本人と違う顔をしていることが、一方で肯定的に評価される社会でもあったからだ。彼女いわく、自分は背が高くないのでブラジルではあまり目立たなかったが、ここでは「東洋系のハーフ」であることがモデル業界でとても望まれる存在であった。
最初に転機を迎えたのは姉のイアーナだった。彼女は二〇〇六年、在日ブラジル人の二大ミスコンテストのひとつである「ミス・ニッケイ」でいきなり優勝し、モデルとして働き始めた。アドリアーナはバルバラ・ナカツガサというプロモーターが手がけた「ミス・ブラジル日本」に応募し、予選を通過した時点でさっそくある事務所から声がかかり、モデルとしてデビューできた。そして今回のコンテストでの優勝はきっと彼女に飛躍の機会をもたらすだろう。
モデルは一握り
それにしても、何故、三〇万人を超える在日ブラジル人社会において、これほどまでに美人コンテストが盛り上がるのだろうか。それは、何よりもまず、ブラジル出身の日系人女性たちにとっては、モデル業こそが、日本人との差異がプラス評価になる数少ない業界であるからだ。世界でも有数のセレブリティになったジゼルの成功物語が、多くの少女やその保護者たちを刺激していることはいうまでもない。しかし、第二のジゼルを目指す人がこれだけ多いのは、それだけ日本での進学の可能性に寄せる期待が低いということの裏返しだとも言える。
わたしはブラジル出身者に向けた講演や執筆活動のなかで、「モデルになれるのはごく一握りの人だから、きちんと勉強もしましょう」との主張を重ねてきた。アドリアーナの話を聞いて感心したのは、彼女がモデルとして順調な滑り出しを遂げているにもかかわらず、勉学に対する意欲を失っていないことである。彼女は日本語をもっと勉強して、日本の大学でエコツーリズムを勉強するという選択肢も考えたことがある。現時点では、ブラジルを拠点とする通信制の大学で経営学か教育学を勉強することになりそうだが、遠隔教育を実施する複数のブラジルの大学が日本に進出しており、在日ブラジル人のあいだで大きな注目を集めている。
カラオケからコンテストへ
ミスコンテスト全盛期を理解するためのもうひとつのキーワードは、日本におけるブラジル系エスニックビジネスの成熟である。ミスコンテストでは毎回、新車などの豪華賞品を提供する数十のスポンサーの企業名が延々とあげられる。それだけ力のあるスポンサーが存在しなければ、このような大規模なイベントは実現できるはずがない。じつは、一九九〇年代をとおして、同じく一等賞に新車を提供し話題を集めてきたのが、在日ブラジル人のいわゆる「のど自慢」、カラオケ大会であった。移民の第一世代が主役であったカラオケに代わって、移民の第二世代が主役であるミスコンテストがコミュニティでもっとも注目されるイベントに発展したことは、移民社会の変貌を象徴しているともいえる。
アドリアーナの晴れ舞台となったファッションショーは、日本に根を下ろしたブラジル人デザイナー、Linda K.のデザインによるものであった。モデルたちはそこで美貌を披露すると同時に、「あなたは移民一〇〇周年についてどう思いますか?」という質問で知性が試された。アドリアーナの答えは次のようなものであった。「日本からブラジルに渡った祖父母の頑張りこそが、今のわたしにインスピレーションを与えてくれている」。
優勝を手にした五月三日は、奇しくも彼女の一七歳の誕生日でもあった。
ラオスの若者が出家する理由
ラオスなどの東南アジア大陸部では、六月から一〇月が雨季である。海から大陸に向かって湿潤な南西の季節風が吹き、毎日雨を降らせる。
日本で梅雨が好きな人は少ないだろうが、ラオスの雨季はけっこう人気がある。多くの人があげる理由はふたつ。まず、食材が豊富なこと。農村で暮らしていると、雨季にはいろいろな味が楽しめる。山でタケノコ、キノコ、野菜が採れ、川や沼でサカナやエビ、カエルが獲れる。腕さえあれば。またイネの生育にも雨季の降り続く雨は不可欠だ。この地域の主食はコメなのだから。
もうひとつの理由は、単純に、家のなかが涼しいこと。ラオスでは、三月終わりから五月にかけてがもっとも暑い。昼は四〇度近く、夜でも三〇度前後ある。一日中、鼻の奥に何かがつまっている感じで、息苦しい。頭はまったく働かない。扇風機は熱風をかき回すだけで、夜眠れない。一気にクールダウンしてくれる雨が待ち遠しい。
雨季のあいだ、上座部仏教の僧侶は僧院にこもって修行する。本来、出家者とは諸国を遍歴して修行する者。托鉢して布施を受け、ボロ切れをまとい、樹下で眠り、簡素な生活を送る。しかし雨季の遊行は不便である。疫病にかかりやすい。布施を受けるのが困難。草木の若芽や虫を踏んでしまう。あるいは、百姓が植えたイネを踏んでしまう。ブッダは修行僧に雨季の定住を勧めた、と『大パリニッパーナ経』にある。これが雨安居(うあんご)(パンサー)だ。
一生に一度は出家せよ
現在、雨安居とは、暦のうえで雨季にあたるラオスの陰暦八月一六日から一一月一五日(二〇〇八年は太陽暦で七月一八日から一〇月一四日)のことを指す。僧侶が三ヵ月間集団生活しながら修行に専念する大切な時期だ。雨安居を何回経験したかが、僧侶としての経歴年数とされ、これによって教団内の地位が決められる。ちなみに明確な雨季のない日本でも、禅宗には雨安居の習慣があるそうだ。
上座部仏教を信仰する社会には、男子たるもの一生に一度、家を出て、解脱を求めて修行せよ、という教えがある。出家経験が社会的な信頼をえることにつながる。これがないと未熟者だ。女性にもてたければ、出家しろ。責任感や道徳心、礼儀作法などが身につく。かつて僧院は唯一の教育機関であり、読み書きをはじめ、知識を学ぶ場でもあった。
出家は本人の信心しだいでいつしてもよい。飽きたらいつでも還俗できる。しかしもっとも一般的な出家期間は三ヵ月、時期はこの雨安居である。結果、毎年雨安居になると、ラオスの僧院ではどこも人口が二、三倍にふくらんでいる。
修行で何を学ぶのか
それでは僧院にこもって何をするか。特別な荒行や断食などするわけではない。ふつうに暮らすだけ。三時半に起きて朝の読経をし、夜が明けたら近くの村まで托鉢に行く。日に一度の食事を済ませ、掃除や菜園の手入れ、僧坊の建設などの雑役をする。水浴びの後、午後四時から夕方の読経に出る。これが一日のおもな日課だ。あとは空いた時間を利用して、経を覚えたり瞑想したり。
月に一回、僧侶全員が参加して、布薩(ふさつ)(ウポーサタ)儀礼が開かれる。シーマとよばれる神聖な場所をもつ本堂に集まり、過去一ヵ月分の自分の行動を反省し、犯した罪を懺悔(ざんげ)する。それから、あらためて僧侶の守るべきパーティモッカ(二二七条の戒律)の全文が読み上げられるのを聴き、各自誓いをあらたにする。
こうした修行を経て何を学ぶか。仏教の教え。人生について。自分について。答え方はいろいろあるが、具体的に説明するのはむずかしい。仏教の教えとは、テキストを覚えれば済むようなものではない。各人が瞑想するなかで自ら悟るほかないのである。
わたしが学んだことを少しだけ紹介しよう。まず、集中力の大切さ。一所懸命食べたり、歩いたりすることがいかに大事か。これが生きるということだ。もうひとつは煩悩について。過去の苦しかった経験をひとつひとつ取り上げ、経典や説法を導き手としながら、何が原因かをとことんまで考え抜く。すると、おぼろげながらつかめてくる。苦しみの原因はいつも自分にあるということが。
出家の新しい意味
現在、ラオスの農村では、雨安居にあわせて出家する若者がぐっと減ってしまった。教育機関としての機能が学校に取って代わられたためだ。学歴が僧歴より高く評価されるようになった。元僧より大卒の方が女性にもてる。
皮肉なことに、都市では若い出家者が増えている。地方の貧困地域から多数の少年が都市にやって来て、僧坊に起居しながら高校や大学へ通うのである。出家が、ただで高等教育を受ける手段になっているのだ。
日本で梅雨が好きな人は少ないだろうが、ラオスの雨季はけっこう人気がある。多くの人があげる理由はふたつ。まず、食材が豊富なこと。農村で暮らしていると、雨季にはいろいろな味が楽しめる。山でタケノコ、キノコ、野菜が採れ、川や沼でサカナやエビ、カエルが獲れる。腕さえあれば。またイネの生育にも雨季の降り続く雨は不可欠だ。この地域の主食はコメなのだから。
もうひとつの理由は、単純に、家のなかが涼しいこと。ラオスでは、三月終わりから五月にかけてがもっとも暑い。昼は四〇度近く、夜でも三〇度前後ある。一日中、鼻の奥に何かがつまっている感じで、息苦しい。頭はまったく働かない。扇風機は熱風をかき回すだけで、夜眠れない。一気にクールダウンしてくれる雨が待ち遠しい。
雨季のあいだ、上座部仏教の僧侶は僧院にこもって修行する。本来、出家者とは諸国を遍歴して修行する者。托鉢して布施を受け、ボロ切れをまとい、樹下で眠り、簡素な生活を送る。しかし雨季の遊行は不便である。疫病にかかりやすい。布施を受けるのが困難。草木の若芽や虫を踏んでしまう。あるいは、百姓が植えたイネを踏んでしまう。ブッダは修行僧に雨季の定住を勧めた、と『大パリニッパーナ経』にある。これが雨安居(うあんご)(パンサー)だ。
一生に一度は出家せよ
現在、雨安居とは、暦のうえで雨季にあたるラオスの陰暦八月一六日から一一月一五日(二〇〇八年は太陽暦で七月一八日から一〇月一四日)のことを指す。僧侶が三ヵ月間集団生活しながら修行に専念する大切な時期だ。雨安居を何回経験したかが、僧侶としての経歴年数とされ、これによって教団内の地位が決められる。ちなみに明確な雨季のない日本でも、禅宗には雨安居の習慣があるそうだ。
上座部仏教を信仰する社会には、男子たるもの一生に一度、家を出て、解脱を求めて修行せよ、という教えがある。出家経験が社会的な信頼をえることにつながる。これがないと未熟者だ。女性にもてたければ、出家しろ。責任感や道徳心、礼儀作法などが身につく。かつて僧院は唯一の教育機関であり、読み書きをはじめ、知識を学ぶ場でもあった。
出家は本人の信心しだいでいつしてもよい。飽きたらいつでも還俗できる。しかしもっとも一般的な出家期間は三ヵ月、時期はこの雨安居である。結果、毎年雨安居になると、ラオスの僧院ではどこも人口が二、三倍にふくらんでいる。
修行で何を学ぶのか
それでは僧院にこもって何をするか。特別な荒行や断食などするわけではない。ふつうに暮らすだけ。三時半に起きて朝の読経をし、夜が明けたら近くの村まで托鉢に行く。日に一度の食事を済ませ、掃除や菜園の手入れ、僧坊の建設などの雑役をする。水浴びの後、午後四時から夕方の読経に出る。これが一日のおもな日課だ。あとは空いた時間を利用して、経を覚えたり瞑想したり。
月に一回、僧侶全員が参加して、布薩(ふさつ)(ウポーサタ)儀礼が開かれる。シーマとよばれる神聖な場所をもつ本堂に集まり、過去一ヵ月分の自分の行動を反省し、犯した罪を懺悔(ざんげ)する。それから、あらためて僧侶の守るべきパーティモッカ(二二七条の戒律)の全文が読み上げられるのを聴き、各自誓いをあらたにする。
こうした修行を経て何を学ぶか。仏教の教え。人生について。自分について。答え方はいろいろあるが、具体的に説明するのはむずかしい。仏教の教えとは、テキストを覚えれば済むようなものではない。各人が瞑想するなかで自ら悟るほかないのである。
わたしが学んだことを少しだけ紹介しよう。まず、集中力の大切さ。一所懸命食べたり、歩いたりすることがいかに大事か。これが生きるということだ。もうひとつは煩悩について。過去の苦しかった経験をひとつひとつ取り上げ、経典や説法を導き手としながら、何が原因かをとことんまで考え抜く。すると、おぼろげながらつかめてくる。苦しみの原因はいつも自分にあるということが。
出家の新しい意味
現在、ラオスの農村では、雨安居にあわせて出家する若者がぐっと減ってしまった。教育機関としての機能が学校に取って代わられたためだ。学歴が僧歴より高く評価されるようになった。元僧より大卒の方が女性にもてる。
皮肉なことに、都市では若い出家者が増えている。地方の貧困地域から多数の少年が都市にやって来て、僧坊に起居しながら高校や大学へ通うのである。出家が、ただで高等教育を受ける手段になっているのだ。
博物館のいたずら虫たち(1)
生物界で最大のグループ
コウチュウ目の体は角質化した表皮で覆われており、昆虫のなかで唯一、手で握りしめてもつぶれない。コウチュウ目の種類は全動植物の四分の一を占めるといわれ、生物界で最大のグループである。このうちヒラタキクイムシ科には木像などに害をおよぼす文化財害虫の種が多数含まれており、その代表的なものにヒラタキクイムシがある。ヒラタキクイムシの幼虫は、木材に含まれるでんぷんを栄養分とする。幼虫は木材の内部を食べながら成長し、羽化するときに孔をあけて脱出する。木材の表面に直径二ミリメートル程度の脱出孔が多数あらわれ、その下に虫粉(糞とかじり屑)が落ちているのを見てはじめて、被害に気づくことが多い。
博物館資料のなかでも虫害にあいやすい材質が多く使われているのが民族資料である。そのため民博では、防虫対策にとくに注意を払ってきているが、二〇〇一年夏、南アジア展示場のインドの木造漁船(写真1)にヒラタキクイムシの被害が発生してしまった。この漁船はインド、オリッサ州プーリー市で使用されていたもので、直径三〇センチメートルほどの丸太を組み合わせてできており、長さは八メートル近くある。この大きさを考えると、展示場から簡単に動かすことはできない。漁船を保存処理するにあたっては、安全優先の考え方から、化学薬剤を用いる手法は避けることにした。国内の博物館では、薬剤を用いない殺虫処理として二酸化炭素処理がすでに実用段階に入っていたが、処理日数が二週間ほど必要となるので、土曜日や日曜日にかかってしまう。そこで、当時の森田恒之教授(現・名誉教授)の共同研究会で基礎実験をおこなった結果、準備期間も含めて三日以内に処理が完了する高温処理を採用することにした
人と資料にやさしい虫害対策
展示場で安全かつ効率的に高温処理がおこなえるようにと考案したのが、漁船を防湿プラスチックシートで包み込み、断熱箱のなかで加温するという方法(写真2、3、4)である。漁船をシートで密封したのは、木が乾燥し過ぎて変形するのを防ぐためである。漁船を包み込んだ後、シート内を脱気し僅かの空気しか残していないので、温度が上がっても木から水分が失われることはほとんどない。あたためられた空気は、熱発生装置からパイプをとおして断熱箱に送られ、断熱箱内の漁船をあたためた後、別系統のパイプで熱発生装置に戻るため、展示場の温度と湿度には影響を与えない。漁船をかたちづくっている丸太の芯まで効果的に殺虫できる温度に達しているかは、同じ直径の実験用丸太を漁船のなかに配置し、その中央部分の温度を計測することで確認した(写真5)。二〇〇二年と二〇〇三年、展示場で漁船の高温処理をおこなった際には、必要最小部分のみ通行止めとしながらも、すべて公開とし、観覧者の方々に博物館の舞台裏を見ていただいた。この処理は、二〇〇八年三月まで開催されていた企画展「世界を集める―研究者の選んだみんぱくコレクション」でも紹介したので、みなさまの記憶に新しい。
ヒラタキクイムシは熱帯~温帯に広く分布し、南方からの移入種とされている。北日本の屋外では越冬できなかったのが、暖房の普及によって、全国的に被害が発生するようになったという。人間の生活が快適になるのは良いが、思わぬところでマイナスの副産物が出てくるものである。
コウチュウ目 (Stephens) ヒラタキクイムシ科 (Lyctidae)
ヒラタキクイムシ(学名:Lyctus brunneus〈Stephens〉)
成虫は体長2.2~7.0mm、体は赤褐色で、やや扁平な細長いかたちをしている。幼虫の体長は4~5mmで、腹方へ曲がった勾玉形をしている。卵は長さ1mm程度で長円筒形である。日本では古くは本州中部以西であったが、現在は北海道まで国内全土に分布。成虫は春から夏に出現し、広葉樹の辺材の導管や割れ目に産卵する。幼虫は食害しながら成長し、被害材から直径1~2mmの虫孔を穿って脱出する。そのとき、虫粉が小さな山をなすので、英名powder-post beetleと名づけられている。
コウチュウ目の体は角質化した表皮で覆われており、昆虫のなかで唯一、手で握りしめてもつぶれない。コウチュウ目の種類は全動植物の四分の一を占めるといわれ、生物界で最大のグループである。このうちヒラタキクイムシ科には木像などに害をおよぼす文化財害虫の種が多数含まれており、その代表的なものにヒラタキクイムシがある。ヒラタキクイムシの幼虫は、木材に含まれるでんぷんを栄養分とする。幼虫は木材の内部を食べながら成長し、羽化するときに孔をあけて脱出する。木材の表面に直径二ミリメートル程度の脱出孔が多数あらわれ、その下に虫粉(糞とかじり屑)が落ちているのを見てはじめて、被害に気づくことが多い。
博物館資料のなかでも虫害にあいやすい材質が多く使われているのが民族資料である。そのため民博では、防虫対策にとくに注意を払ってきているが、二〇〇一年夏、南アジア展示場のインドの木造漁船(写真1)にヒラタキクイムシの被害が発生してしまった。この漁船はインド、オリッサ州プーリー市で使用されていたもので、直径三〇センチメートルほどの丸太を組み合わせてできており、長さは八メートル近くある。この大きさを考えると、展示場から簡単に動かすことはできない。漁船を保存処理するにあたっては、安全優先の考え方から、化学薬剤を用いる手法は避けることにした。国内の博物館では、薬剤を用いない殺虫処理として二酸化炭素処理がすでに実用段階に入っていたが、処理日数が二週間ほど必要となるので、土曜日や日曜日にかかってしまう。そこで、当時の森田恒之教授(現・名誉教授)の共同研究会で基礎実験をおこなった結果、準備期間も含めて三日以内に処理が完了する高温処理を採用することにした
人と資料にやさしい虫害対策
展示場で安全かつ効率的に高温処理がおこなえるようにと考案したのが、漁船を防湿プラスチックシートで包み込み、断熱箱のなかで加温するという方法(写真2、3、4)である。漁船をシートで密封したのは、木が乾燥し過ぎて変形するのを防ぐためである。漁船を包み込んだ後、シート内を脱気し僅かの空気しか残していないので、温度が上がっても木から水分が失われることはほとんどない。あたためられた空気は、熱発生装置からパイプをとおして断熱箱に送られ、断熱箱内の漁船をあたためた後、別系統のパイプで熱発生装置に戻るため、展示場の温度と湿度には影響を与えない。漁船をかたちづくっている丸太の芯まで効果的に殺虫できる温度に達しているかは、同じ直径の実験用丸太を漁船のなかに配置し、その中央部分の温度を計測することで確認した(写真5)。二〇〇二年と二〇〇三年、展示場で漁船の高温処理をおこなった際には、必要最小部分のみ通行止めとしながらも、すべて公開とし、観覧者の方々に博物館の舞台裏を見ていただいた。この処理は、二〇〇八年三月まで開催されていた企画展「世界を集める―研究者の選んだみんぱくコレクション」でも紹介したので、みなさまの記憶に新しい。
ヒラタキクイムシは熱帯~温帯に広く分布し、南方からの移入種とされている。北日本の屋外では越冬できなかったのが、暖房の普及によって、全国的に被害が発生するようになったという。人間の生活が快適になるのは良いが、思わぬところでマイナスの副産物が出てくるものである。
コウチュウ目 (Stephens) ヒラタキクイムシ科 (Lyctidae)
ヒラタキクイムシ(学名:Lyctus brunneus〈Stephens〉)
成虫は体長2.2~7.0mm、体は赤褐色で、やや扁平な細長いかたちをしている。幼虫の体長は4~5mmで、腹方へ曲がった勾玉形をしている。卵は長さ1mm程度で長円筒形である。日本では古くは本州中部以西であったが、現在は北海道まで国内全土に分布。成虫は春から夏に出現し、広葉樹の辺材の導管や割れ目に産卵する。幼虫は食害しながら成長し、被害材から直径1~2mmの虫孔を穿って脱出する。そのとき、虫粉が小さな山をなすので、英名powder-post beetleと名づけられている。
本音の在りか
集まってきた女性たち
二〇〇六年八月二二日、メキシコはチアパス州のある農村を初めて訪問した。日本の国際協力機構が実施した農村開発プロジェクト(PAPROSOC)を、現地の女性たちがどのように受け止めているか聞き取り調査するためだ。リーダーのグアダルーペさんを訪ねると、プロジェクトに参加した女性たちが村の公民館に集まってくるという。それはありがたいが、手回しが良すぎる。わたしは個別インタビューを望んでいたのだ。まずリーダーと世間話から始めて、少しずつプロジェクトの話を聞き、他の仲間を紹介してもらって、そこでもおしゃべり・・・と、段取りを踏んで聞き取りを進めるはずだった。かといって集まった人びとを解散させるわけにもいかず、わたしはほどなく一八人の主婦の前で、冷や汗をかきながら自己紹介を始めた。アドリブで芸を披露することになった漫才師の気分とでもいったらよいだろうか。
何故こんなことになってしまったのか。事前に国際協力機構に便宜供与をお願いし、この村への訪問を伝えていた。それに対し「万事アレンジしておきますよ」というメールをもらっていた。おそらくプロジェクトのスタッフかグアダルーペさん自身が「日本人が調査に来るから皆を集めよう」と発想したのだろう。
開発援助のツール
じつはこうした集会は開発援助活動ではめずらしいことではない。途上国の農村開発を始めるには、農民の暮らしについてよく調べることが大切だ。そのために農家を一軒一軒訪問する方法もあるが、皆に集まってもらって一度に尋ねる方が効率的と考えられている。また重要な情報を聞き出すときに、村長など一部の人から意見を聞くよりも、なるべく多くの村人と相談した方が、あとあと皆が協力的になると期待されている。
わたしがかかわることになったこの日の集会は、援助の専門用語でフォーカス・グループ・ディスカッションという。村人のなかからプロジェクトに参加した経験をもつ者に集まってもらい、その人たちのあいだで共通に理解されている考えを探る調査ツールだ。終了した援助プロジェクトを受益者の視点で評価するときによく用いられる。研究者というよりもプロジェクト関係者としてわたしを認識した村人にとって、この集会の開催はきわめて自然な流れだったのだろう。
人びとの本音
村の女性たちはこの種の集会に慣れていた。出身地、学歴、子どもの数など客観的な情報については、はきはきと答えてくれた。しかも他の人の前なので、嘘をつくこともない。なるほど個別訪問よりは時間を節約できるとわたしも納得した。しかしもっと主観的な問題はどうだろうか。わたしはプロジェクトの印象を聞いてみた。
「お金をもらってもすぐなくなるが、プロジェクトで学んだ技術は残る」という意見。グループで野菜づくりを学んだ女性の模範解答だ。このプロジェクトの公式の評価報告書にも同様の意見が書かれていた。それを確認できたことはわたしにとって収穫だが、もっと違う意見もあるはずだ。そこでグループ活動の難しさについて尋ねてみた。
「皆の合意をとりつけること」と一人の女性。「それではそれをどう解決しましたか」とつっこむわたし。しばしの沈黙。顔を見あわせる女性たち。やがて別の一人が「皆で働くと仕事が早くすむ」というもうひとつの模範解答。その発言でわたしの質問はそらされてしまった。
集会後、再びグアダルーペさんの家へ。ジュースを飲みながらさらに小一時間ほどプロジェクトに関する個人的な意見を尋ねた。帰り際、彼女は同行していたメキシコ人技師に相談をもちかけた。「グループ活動をやめたがっている人から、これまで積み立てたお金を返してほしいといわれて困っている」。わたしはこれこそグループ活動の難しさを伝えるエピソードだと気付いた。しかし同時にグアダルーペさんが集会でも個人面接でもこのことをわたしに話してくれなかったことが気になった。
この事例から、集会の模範解答を建て前、技師への相談を本音とみなすことはたやすい。そう考えると建て前しか聞けないフォーカス・グループ・ディスカッションは調査方法としては信頼がおけず、それに依拠するプロジェクト評価にも疑問がわいてくる。しかしわたしは両方とも彼女たちの本音なのだと思う。この日の集会は、問題を訴えて解決策をえる場というよりも、援助供与国の日本からはるばるやってきたわたしをもてなす場だったのだ。村の女性たちは、自分たちがどれだけがんばったかを伝えることによりわたしを安心させ、あわよくばさらなる援助を引き出したいと願ったのだろう。だからフォーカス・グループ・ディスカッションはけして無駄ではない。援助の受益者たちが、援助の提供者に本音を伝える有効な手段なのだから。
ただしフォーカス・グループ・ディスカッションを受益者の本音を聞く唯一の手段とみなすことは間違いだ。人びとは他の方法でも本音をいう。そういう本音を聞き洩らさないためには、効率は悪くともたくさんの時間をフィールドですごすことが不可欠だ。文化人類学者が開発を研究することの意義はこのあたりにあるのだろう
『月刊みんぱく』の「外国人として生きる」を担当して、もう2年経った。このあいだ、さまざまな分野で活動する外国出身者の生き方を個人名や写真とともに紹介してきた。本来この企画は、日本で生活する外国人(移民)の元気で積極的な生き方を紹介することにあった。街角や商店では毎日のように目にし、マスコミでもしばしば取り上げられるようになった外国人だが、そこで描かれる苦労、差別、違法など問題をかかえた対象としての暗く受動的なイメージはぬぐいがたい。たしかに日本での生活には多くの困難をともなうのが普通だが、彼らがそれぞれ個人として目標や生き甲斐をもち、人生を楽しもうとする姿はみおとされがちであった。
そして今年の春からは、日本在住の移民、外国人の二世を取り上げている。彼らのなかには、社会へその一員として積極的に働きかけることで、一世が経験した苦労や限界を克服し、場合によってはそれらを自分の可能性に転化しようとするものも少なくない。彼らの姿が、日本人の外国人イメージを再考するきっかけになり、さらに日本人や外国人、双方の生きかたに参考になればと思う。今後もどのような若者が登場するか楽しみである。(庄司 博史)
そして今年の春からは、日本在住の移民、外国人の二世を取り上げている。彼らのなかには、社会へその一員として積極的に働きかけることで、一世が経験した苦労や限界を克服し、場合によってはそれらを自分の可能性に転化しようとするものも少なくない。彼らの姿が、日本人の外国人イメージを再考するきっかけになり、さらに日本人や外国人、双方の生きかたに参考になればと思う。今後もどのような若者が登場するか楽しみである。(庄司 博史)
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。