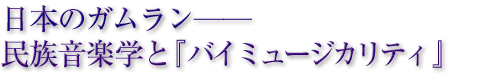研究テーマ・トピックス|福岡正太
北米の民族音楽学者マントル・フッドは、1950年代末、「バイミュージカリティ」という概念を提唱し、民族音楽学的研究方法の一つとして、世界各地の異なる音楽を同時に身につけることを積極的に押し進めた。1970年代前半には、そうした北米の民族音楽学の影響のもと、東京芸術大学にジャワのガムランが導入され、それ以来、日本においてもガムランの演奏を楽しむ人々が増えてきている。異なる文化の音楽を実践することは、従来、ある「民族」に属するものとして音楽を捉えてきた民族音楽学の視点に大きな転換を促さざるを得ない。現在、私は、日本におけるジャワのガムランの実践の歴史を振り返りながら、「バイミュージカリティ」という概念が民族音楽学に対してもつ含意を再検討し、グローバリゼーションの時代において人々が音楽的アイデンティティの構築する過程を捉えるための新しい視点を探っている。
はじめに
私は、ここで、私自身が長年かかわってきた日本におけるジャワのガムランの実践について振り返りながら、民族音楽学のひとつの課題について展望してみたいと思います。
約20年前、私は大学でジャワのガムランに出会い、それ以来その音楽を学び、演奏し、ときには教えてきました。ジャワのガムランは、私の人生において重要な位置を占めるようになり、しばしば、日本のさまざまな伝統音楽に比べて私にとって近しい自分の音楽として感じられるようになりました。このように、異なる文化が生み出した音楽を身につけ、それを自分の音楽と感じるようになるということは、インドネシアの音楽を研究する者に特殊な現象なのでしょうか。
しかし、周りを見まわしてみると、音楽研究に特別にかかわりをもたない人びとのあいだでも、異なる文化の音楽を実践することが珍しいことではなくなってきているようです。
民族音楽学は、音楽をある特定の民族集団と結びつけて取り扱ってきました。ある民族に属するものとして、研究対象の音楽を規定してきたのです。その前提には、民族は音楽的に同質であるという仮定があります。ところが民族音楽学から生まれた「バイミュージカリティ」というコンセプトに基づく実践は、そうした民族音楽学の前提を突き崩す可能性をはらんでいました。異文化の音楽を学ぶ人々は一体どのような音楽的アイデンティティをもつことになるのでしょうか。そしてまた、民族音楽学はそれをどのように捉えていったらよいのでしょうか。こうした問題について、私はここて考えてみたいと思います。
1.バイミュージカル
北米の民族音楽学者マントル・フッドさんは、1950年代末、「バイミュージカリティ」という概念を提唱し、民族音楽学的研究をすすめるにあたり、実際に異なる文化の音楽を身につけることを積極的に押し進めました。1960年に雑誌ethnomusicology誌上に発表された「バイミュージカリティの挑戦」と題された彼の論文をもとに、「バイミュージカリティ」の考え方を概観してみましょう。
彼は、音楽研究は「音楽性」に支えられるべきだと主張します。それは、音楽研究において、「音楽性」を伸ばす音楽の基本的な学習や訓練を省略することはできないということを意味します。少し引用してみます。「耳、目、手、そして声の訓練と、それらの技能の発達は、理論的研究の真の理解を確実なものとする。そしてさらに、それは演奏家、作曲家、音楽学者、そして音楽教育家としての専門的な活動への道を開く。」こういうふうに彼は述べています。異文化の音楽の研究においても、音楽研究は「音楽性」に支えられるべきであり、そのためには、実際にその音楽を学ぶべきであるというのが彼の主張の骨子です。
一方、ある民族の音楽は、他の民族には習得できないとしばしば考えられてきました。それに対してフッドさんは、宮内庁の楽人の例をあげて、異なる文化の音楽は習得できないという議論は成り立たないとしました。宮内庁の楽人は、雅楽と西洋のクラシック音楽の両方を専門的に身につけているからです。同じように、異なる文化の音楽の研究を志す人は、バイミュージカリティの挑戦にさらされている、つまり、ふたつの異なる音楽性を身につけることを要求されているのです。
フッドさんは、こうした考え方に基づき、カリフォルニア大学ロサンジェルス校で、民族音楽学研究所を創設し、世界各地から音楽家を招いて、さまざまな音楽を学ぶ活動を始めました。そこで取り上げられた音楽のひとつに、ジャワのガムランがありました。さらに、彼の教えを受けた多くの民族音楽学者が、アメリカ各地の大学などで同様の試みを始め、各地にジャワのガムランを学ぶグループが形成されていきました。
そして、アメリカにおけるこうした動きに大なり小なり影響を受けながら、日本でもジャワのガムランの実践が広まってきました。
2.バイミュージカルの実践と小泉文夫
日本において、同様の動きに先鞭をつけたのは、民族音楽学者の小泉文夫さんでした。彼は、1960年代後半にウェスリアン大学の客員準教授としてアメリカに滞在し、そこでインド音楽とともにジャワのガムランのクラスに参加しました。そこで、強いインパクトを受け、日本にも同様の教育プログラムを導入しようと努力するようになります。
ただし、小泉さん自身は、必ずしもアメリカの民族音楽学の影響だけで、こうした教育プログラムに関心をもつようになったとは言い切れません。彼は、1950年代後半にインドに留学し、実際にインド音楽を学んでいます。これはちょうどフッドさんがバイミュージカリティの概念を提唱し、実践し始めたのとほぼ時を同じくしています。インドでは、フッドさんの弟子であるロバート・ブラウンさんに出会い親交を深め、それがのちにウェスリアン大学に招かれるきっかけとなっています。小泉さんがどのような経緯でインドの音楽を実際に学ぶことを思い立つようになったのか、今のところ私にははっきりわかりません。フッドさんの実践についてどこかで情報を得ていたのかもしれませんし、あるいはほかのきっかけがあったのかもしれません。
いずれにしても、アメリカで実際にジャワのガムランに触れた小泉さんは、帰国後、東京芸術大学にガムランを導入する努力を始めました。紆余曲折はあったものの、1973年に東京芸術大学は、ジャワのガムラン1セットを購入し、翌1974年、小泉さんは自らがうけもつ演習の中でガムランを教え始めます。
3.日本におけるジャワのガムランの歩み(東京を中心に)
ここで日本におけるジャワのガムランの実践の歩みについて、東京を中心にごく簡単に振り返っておきたいと思います。大阪にも、1970年代の終わりに大阪大学を拠点とするジャワのガムラン・グループが作られ、独自の活動を展開してきましたが、ここではあまり触れないことをおことわりしておきます。
1970年代はじめ、小泉さんは自宅にガムランを購入し、小泉さんの指導するゼミの学生や関係者が小泉さん宅でガムランを習い始めました。1973年、東京芸術大学がガムラン購入し、翌1974年、小泉さんがガムランを教え始めます。同時に、ごく少数ですが、小泉さんの影響を受けた学生がジャワに留学しはじめます。以後しばらくの間は、東京芸術大学関係者のあいだで、一時帰国する留学生が持ち帰る情報や録音テープなどをたよりに、ジャワのガムランを学ぶ試みが進められます。
そして、1979年、小泉さんの努力が実り、中部ジャワのソロという町から音楽家サプトノさんを客員講師として招くことができました。サプトノさんは、結局5年間日本に滞在し、芸大その他でガムランを教えました。この時期、サプトノさんの教えを受けたグループは、急速に演奏技能が向上し、レパートリーも増え、演奏活動も盛んに行うようになりました。この5年の間に、日本におけるガムラン活動はひとつの頂点をむかえたと言ってよいでしょう。
しかし、1983年、小泉さんが亡くなり、翌1984年には、サプトノさんが帰国します。それまでは、大学がジャワのガムランの拠点となっていましたが、それぞれの卒業生が大学を離れると同時に、少しずつ大学の外にもガムランの拠点が作られるようになります。いくつかの例をあげますと、1986年、国際児童年を記念して、厚生省系の児童福祉手当協会が東京青山にこどもの城をオープンさせました。その音楽事業部では、子供向けにさまざまな音楽講座を開きましたが、その中にジャワのガムラン講座が含まれていました。また、1987年、ジャワの音楽舞踊を長く実践、研究してきた田村史さんが東京都大田区にガムラン・スタジオ、音工場HANEDAをオープンさせました。このようにして、1980年代後半には、こどもを含めて、音楽の専門家ではない人々のにあいだにもジャワのガムランが浸透していきます。同時に、ジャワに音楽や舞踊を学びに留学する人々も急速に増えてきました。
1980年代終わりから1990年代前半にかけてのワールドミュージックのブームなども背景としながら、世界の様々な音楽に対してより気軽にアプローチする態度も定着してきました。ジャワの音楽や舞踊を学ぶ人々も、必ずしも研究者となることを目的とせずに、芸能の魅力に導かれ、とにかく音楽や舞踊に触れ、それを習得することを第一の目的とする人々が増えてきたようにみえます。
そして、近年の流れで特筆すべきことは、ジャワのガムランの活動の地方への広がりと地域に溶け込んだ活動の模索です。1970年代から80年代にかけて東京や大阪でガムランを学び始めた人々の一部が地方の大学などに職を得て、各地でジャワのガムランの活動の拠点を作り始めています。たとえば、沖縄、福岡、新潟などの例をあげることができます。また、ガムランの活動を地域社会に根付かせようとする試みもみられるようになってきました。たとえば大阪府豊能町での中川真さんの試みや、新潟県東頸城郡安塚町での植村幸生さんの試みなどを挙げることができます。
一方、ジャワ社会では、何人かの日本人がガムランの音楽家として活躍しています。たとえば、ワヤンとよばれる影絵芝居のある有名なグループでは、2人の日本人が音楽家として演奏に加わっています。
4.音楽とアイデンティティ
さて、日本でガムランを学ぶ人々にインタビューしてみると、ガムランを自分の生きがいとする人々が着実に増え、ガムランのコミュニティを形成していることがわかります。今日のグローバル化する世界で、私たちは世界のあらゆる音楽と出会う可能性をもっています。民族音楽学は、意図する/しないにかかわらず、その手助けともなってきました。様々な理由から、無数の音楽のうちのある音楽に惹かれ、その音楽の世界に参加していくことを、もはや拒むことはできません。
では、異文化の音楽を習得する人々の音楽的アイデンティティについて、私たちはどのように考えたら良いのでしょうか。日本でガムランを実践する人々のあいだには様々な態度がありますが、一方の極端には、ジャワのガムランを深く習得し、限りなくジャワ人に近づいていきたいという考え方があります。もう一方には、日本人として、日本独自のガムランを生み出して行きたいという考え方があります。これらの考え方は、ときとして、ジャワなのか、日本なのか、という二者択一の問いに結びついて行きます。この問いの背景には、民族は音楽的に同質であり、民族の枠組みと身につける音楽は一致すべきであるという無言の前提があります。その前提にたてば、異なる文化の音楽を実践することは、逸脱であり非正統的な音楽実践であるということになってしまいます。
しかし、ここでバイミュージカリティという造語のもとになった、バイリンガルであることとの対比で考えてみましょう。バイリンガルであるということは、どちらか一方という二者択一ではなく、二つの言語を同時に身につけているという状態です。フッドさんも1960年の論文の中で、バイミュージカリティは二者択一的なオールターナティブ・ミュージカリティとは区別されるべきものだとしています。バイミュージカリティの実践としてのジャワのガムランの習得は、日本人の音楽性を捨て去りジャワ人の音楽性を身につけるのではなく、両方の音楽性を同時に身につけることを目指すものなのです。
5.ネットワークの中のガムラン
世界の様々な音楽を受け入れ、実際にそれらの音楽を学ぶことを強く動機づけるコンセプトとして、バイミュージカリティは提唱されてきたわけですが、一方で、そこには重大な問題も隠されています。
本来、音楽を身につけるという過程には、技能の習得ばかりでなく、その音楽の世界のしきたりを身につけながら、次第にその世界に受け入れられていくという社会的な過程が含まれています。しかし、バイミュージカリティの考え方に基づきジャワのガムランを学ぶ試みは、北米においても、日本においても、ジャワの社会からは切り離された状態で、ガムラン・コミュニティを形成する過程でした。
今日、世界中にガムラン・ネットワークが形成されつつあります。そして、これらの海外のガムラン・コミュニティの活動は、いまや「本場」であるジャワのガムランの世界にも大きな影響を及ぼし始めています。ある意味では、ジャワの人々が築いてきたガムランをめぐる社会的秩序や文化が、そうしたものとは無関係に外国人によって形成されたガムラン・コミュニティによって侵食されつつあるのです。たとえば、海外でより積極的にすすめられてきた、現代的なガムラン作品の創作という分野では、ジャワの人々はオーソリティとしての権威を主張できない状況になっています。次にご紹介する中川真さんの話は、この点で非常に示唆的です。
中川真さんは、大阪でジャワのガムラングループを長いあいだ率いてきました。そして、伝統的なガムランのレパートリーに加えて、日本や欧米の作曲家によるガムラン作品を積極的に演奏してきました。2年ほどまえ、インタビューで彼は次のような話をしてくれました。
彼は、あるとき、日本人作曲家によるガムラン作品をジャワの音楽家に演奏してもらおうと試みたそうです。それは、中川さんの考えでは、ジャワの音楽家にとっても比較的演奏しやすいと思われた曲だったにもかかわらず、実際にはジャワの音楽家はその作品を全く演奏することができませんでした。中川さんはそれに非常にショックを受け、ジャワの人々が演奏できないガムラン作品を作ることに本当に意味があるのだろうかと思い悩んだそうです。そして、自身も再びジャワの古典を学び直すとともに、ジャワの音楽家との協同作業を重視する活動を目指すようになりました。彼によれば、こちらも再びジャワの伝統を学ぶけれども、それと同時にあちらにも一歩でてきてもらって、協同作業しながら新しい音楽を作り出すことを今は考えているそうです。
今日、世界のガムラン・ネットワークは、一層緊密化しつつあり、国際ガムラン・フェスティバル等の催しも、頻繁に開かれるようになってきました。グローバル化の中で、お互いの相対的距離感はどんどん小さくなってきています。しかし、政治的、経済的理由などにより、それぞれの立場からみた相互の距離感は、必ずしも同じではありません。世界中にはりめぐらされるネットワークはまた、複雑な力関係の網目であることを忘れてはならないでしょう。
ジャワの社会と自分の社会を行き来しながらガムランを学ぶ人々は、すでに実践的にはこのような問題に気づき、それに対処する行動を様々にとってきました。今度は、そうした実践を民族音楽学の体系の中に意識的に取りこんでいくことが必要になっています。それは、民族音楽学の立場からの共生の論理と倫理の模索であると言うことができます。
これまで、民族音楽学でも、研究成果をどのように研究の対象とした社会に還元して行くのかという議論はありました。しかし、これからは、さらに一歩進めて、グローバル化する世界において音楽的にどう共生して行くのかを考えるべきだと私は考えます。
「共生の民族音楽学」、これをスローガンに個々の実践の中で培ってきた知恵をもちより、民族音楽学における共生の論理と倫理を確立することを私は提唱したいと思います。
インドネシアの民族音楽。ここでは福岡がジャワのガムランという楽器の演奏をビデオクリップでご紹介します。