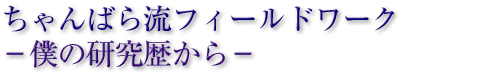研究テーマ・トピックス|広瀬浩二郎
幼い頃からちゃんばら好きだった僕は、「どうにかして合法的にちゃんばらをやってみたい」との単純かつ熱烈な動機で日本史学科への進学を決めた。「ちゃんばらの歴史でも調べてみるか」という本人にとっては重大なテーマは未だに「ライフワーク」(?)として残されているが、研究スタイルの面でちゃんばらは僕に少なからぬ影響を与え続けている。

- 京都合気道場にて
京都大学入学後、僕は勉強は二の次でクラブ活動に熱中した。所属したのは「居合道部」だった。居合道は、抜刀術を中心としたさまざまな「型」に従って刀を操作する古武道である。心に仮想敵を思い浮かべ、あたかも相手がいるかのごとく「斬る」。ただ漫然と刀を「振る」のでなく「斬る」というのは、きわめて精神性の強い(悪く言えば独りよがりの)武道哲学だ。我がクラブは「国立大学最強」と自称していたが、実は国立大学に居合道部は一つしかなかった。最強=最弱とは、これまた独りよがりの笑うに笑えぬお話である。
居合は一人で行うちゃんばらともいえる。初めて模擬刀を持ち、それを空に向かって振った時、ちゃんばらをしたいとの長年の夢がかなえられた感動を味わった。しかし、全盲である僕が居合道の「型」を習い覚えるためには健常者以上の時間が必要だ。「百聞は一見に如かず」との成語を実感させられるのも度々だった。粘り強く手取り足取りの指導をしてくれた先輩や師範には今でも感謝している。マイナーな居合道部は男ばかり10人前後という部員構成だったが、アットホームな雰囲気の中で僕はちゃんばら仲間のサポートを得て、卒業時には二段を取得することができた。
居合道部で培った「何事もやればできる」と考える自信(あつかましさ)は、その後、太極拳・テコンドー・ヨガなどに挑戦するバイタリティとなった。いろいろな武道を体験してみて、僕なりに気づいたことがある。前述のように、第一段階では目が見えないという「障害」は圧倒的にハンディとなる。ところが、ある程度の稽古を積むと、必ずしも「障害」はマイナスにばかり働かない。むしろプラスになることもある、というのが僕の発見なのだ。
日本の芸道や武道の世界では「守・破・離」といわれる教えがある。最初は師範や上級者の「型」や動きを真似る所から稽古はスタートし、忠実に伝統的な「型」を守っていく。次に伝統を打ち破って自分なりのオリジナリティを模索していく。最終的には「型」を離れ、「道」の奥義に到達する。武道を少しばかり齧っただけの僕に「離」の深遠な境地を知ることはできないが、「守」と「破」の相違は漠然とながら理解している(つもりである)。「守」の段階では模範演武を見ることのできなかった僕だが、「破」の段階では逆に先輩の動きにとらわれることなく、のびのびと個性を発揮できるのだ。
具体的な例を挙げれば、先の「振る」と「斬る」の違い。仮想敵を思い浮かべる点においては、周りの景色や師範の顔つきに惑わされることのない全盲者は有利かもしれない(雑念だらけの僕が言っても、あまり説得力はないが…)。最近僕が稽古している合気道の「気」なども、目には見えないものを体で「感じる」世界である。第六感により「気」の流れを体得しようとすれば、視覚は邪魔になることが多い。便利なようで不便なのが視覚である、という「気」がする。ちゃんばら道を歩む僕の目下の課題は合気道での二段取得だ。これは論文を書き上げるより難しいかもしれないが…。(なお、合気道については『民博通信』第94号にも少し書いているので、参照していただきたい)。
さて、武道修行で得た「ちゃんばら哲学」、マイナスをプラスに転じる発想を、どのように研究に活かしていけるのだろうか。「守」(膨大な史料や先行研究を吸収する)の段階を脱して、いかにして「破」(オリジナリティ溢れるユニークな研究)に到れるのか。そして「離」とは・・・?
大量の史料を読み解いていくという点では晴眼者に太刀打ちできない僕が、曲がりなりにも研究を続けてこれたのは、聞き取り調査の可能性を知ったことに由来している(無論、たくさんの友人やボランティアの協力も忘れることはできない)。大学3年生の夏休に体験した羽黒山での山伏修行は、文献とは違った角度からの研究方法を教えてくれた。
もともとは「山伏って昔のウルトラマンみたいな存在だ、ちゃんばらも強かったのかな」といった発想から興味本位で参加した峰入りだったが、修行者から話を聞いたり断食などの「荒行」を経験する中で、書物からは知りえない山伏の具体像をつかむことができた。僕は日本民衆の「記録よりも記憶に残る」民俗宗教の世界に引かれていった。
僕が卒業論文でとりあげたのは中世の盲人史だった。九州地方に現存する地神盲僧に取材し、その宗教・芸能が混在した独自の宇宙に中世の琵琶法師の姿を求めた。琵琶法師も修行により超人的なパワーを獲得するという面で山伏との類似性を持っており、また生業でも共通する部分が多い。『平家物語』に代表されるように、琵琶法師は文化の創造者・伝播者として日本史を支えてきた。民俗宗教の世界では、「盲目」=別世界の存在であることに積極的な価値が付与されていた。琵琶法師とは、目が見えない「からこそ」できる職業だったといえよう。僕はマイナスをプラスに転じる琵琶法師たちの生き方、およびそれを支援した民衆の暗黙の相互扶助観念を、現代の福祉を構築していくヒントとして位置付けた。
修士論文では恐山のイタコなど東北地方の盲巫女を調査し、九州との比較を念頭に置きながら全国的な視野に立って盲人宗教者の活動を分析した。近代化=能力主義的な考えの流布により、盲僧・盲巫女を育んだ日本の多元的な価値観、豊かな人間観は失われていった。別世界から差別への転換である。彼らが伝承してきた芸能や宗教儀礼は、後継者不足で滅びつつある。しかし、琵琶法師・イタコたちを生み育てた精神風土は、21世紀の新たな文化を築いていくためにも再評価されるべきものだ、というのが僕の結論だった。
「僕に音楽的な才能があれば、琵琶法師の修行をしてみたいな」、「指と耳を駆使して論文を書く僕は、現代版の座頭市をめざそう」などと思いながら卒論・修論を中心にまとめたのが、『障害者の宗教民俗学』(明石書店、1997年)である。本書では「バリア・フリー」等の今日的な課題についても言及した。
フィールドワークと文献研究をミックスさせ幅広い視野(大風呂敷を広げるともいう)から日本文化について論じる僕のスタイルは、95~96年のカリフォルニア大学バークレー校への留学で一歩前進した。とはいうものの、1年間のみの留学では十分な勉強もできなかったが、一人でアパート捜しからアメリカ国内の調査旅行を経験する中で、「何事もやればできる」というちゃんばら精神(ある種のずうずうしさ)は、さらに鍛えられた。英語がわからないなりにネイティヴ・アメリカンのコミュニティを訪ねたり、障害者関係の国際会議に参加し、大学での講義以外から生きた「人類学」を学ぶことができた。
アメリカから帰国後の僕の現在に到るまでの主要なテーマは、近代日本の新宗教史である。とくに、新宗教の代表例として明治中期の京都に起こった「大本教」に注目している。大本の教祖・出口王仁三郎は、芸術・武道・農業・エスペラント語などの普及活動を通じて、人類愛善(地上天国)をめざした個性的な思想家だ。
巨人・大化物とも称される彼が、近代日本にあって何を語ろうとしていたのか、「われよし」・「つよいものがち」の発想をどう崩していこうとしたのか。弾圧事件や複雑な時代状況もあって、わかったようでわからない部分が多いのだが、僕なりに王仁三郎と格闘しながら書き上げたのが、『人間解放の福祉論-出口王仁三郎と近代日本-』(解放出版社、2001年)だった。執筆中は王仁三郎の和歌「耳で見て目できき鼻でものくうて 口で嗅がねば神は判らず」にずいぶん励まされた。
本書は僕が京都大学に提出した博士論文の一部に加筆したものである。博論は「宗教に顕れる日本民衆の福祉意識に関する歴史的研究」という小難しい題目だった。「福祉」を広義に解釈し、それを媒介としつつ盲僧などの民俗宗教や新宗教に示される民衆のユートピア願望を多角的に論じた。我ながら継ぎ接ぎだらけの「大風呂敷」といった感じだが、学部生時代からの「ちゃんばら流研究」の一応のまとめ、中間発表でもあった。
一人でさまざまなフィールドに飛び込み、全盲である僕の眼に映った世界を楽しむ。とくに、宗教、つまり目に見えないもの(第六感や記憶)を尊ぶ「超論理の論理」を体感し、そこから「なにか」を感じ取る。そして、その「なにか」と切り結びながら論文を完成させていく。「百聞は一見に如かず」という常識的な「型」に挑戦する我が研究の道は、「破」から「離」へと、ちゃんちゃんばらばらと続いていく。