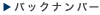月刊みんぱく 2005年5月号
2005年5月号
第29巻第5号通巻第332号
2005年5月1日発行
2005年5月1日発行
困った時はお互い様──アジアのNGO
菅波茂
国連難民高等弁務官事務所本部で開催されたNGO会議で、欧米の国際NGOが理解できる「アジアのNGOの特徴」についてスピーチをした。何故にアジアのNGOは人を助けるのか。「フレンドシップ」のためと説明した。友とは幸せも不幸せも共にする。友が不幸せになった時にこれを助けるのは当然である。「フレンドシップ」無くして支援活動は始まりにくい。支援活動が始まると、苦労を共にする人間関係である「パートナーシップ」になる。「フレンドシップ」が「パートナーシップ」に変化することを『相互扶助』という。「パートナーシップとは困難を共にする尊敬と信頼の人間関係」と定義した。尊敬と信頼の人間関係は民族、宗教そして文化の壁を超えることができる。私はこうしたアジア生活共同体の理論のもとに、国際ネットワーク(AMDAインターナショナル)を組織すべくアジア、さらにはアフリカ、中南米へと人的ネットワークを拡充してきた。その活動の基本はローカルイニシアチブ、つまり地元に精通した支部を中心に活動を進める現地主導型としてきた。
二〇〇四年一二月二六日。二〇〇年に一度と言われる規模の大災害がインド洋沿岸の国々を襲った。災害発生当初より国際社会の救援活動に先駆けて、AMDAインターナショナルのうち九支部と岡山本部がAMDA多国籍医師団を編成して、インドネシア、インド、スリランカにおいて大規模広範囲緊急救援活動を開始した。被災国に一〇〇名近い医療スタッフ(他に現地医学生約二〇〇名が参加)を送りこんで、巡回診療や保健衛生教育、子ども達への予防接種、破損した病院の再構築等を実施している。インドネシア、インド、スリランカ各支部が多大なイニシアチブを発揮してくれたことは言うまでもない。こうした理想的な緊急救援活動を可能にしたのは、AMDAインターナショナルメンバー相互の信頼関係である。その精神は「困った時はお互い様」という『相互扶助』であった。まさにアジアのNGOの真骨頂が示されたと自負している。
二〇世紀の戦争に代わり、二一世紀は災害により多くの尊い人達が命を失う可能性がある。「救える命があればどこへでも行く」というAMDAのスローガンを確実に実現するために、相互扶助にもとづく「フレンドシップ」の国際ネットワークの拡充に、今後も一層の努力をしたい。
すがなみ しげる/1946年生まれ。医師。岡山県に本部を置く特定非営利活動法人AMDA(アムダ)の理事長として、医療支援と生活状態の改善をはかるための国際協力活動を展開中。
二〇〇四年一二月二六日。二〇〇年に一度と言われる規模の大災害がインド洋沿岸の国々を襲った。災害発生当初より国際社会の救援活動に先駆けて、AMDAインターナショナルのうち九支部と岡山本部がAMDA多国籍医師団を編成して、インドネシア、インド、スリランカにおいて大規模広範囲緊急救援活動を開始した。被災国に一〇〇名近い医療スタッフ(他に現地医学生約二〇〇名が参加)を送りこんで、巡回診療や保健衛生教育、子ども達への予防接種、破損した病院の再構築等を実施している。インドネシア、インド、スリランカ各支部が多大なイニシアチブを発揮してくれたことは言うまでもない。こうした理想的な緊急救援活動を可能にしたのは、AMDAインターナショナルメンバー相互の信頼関係である。その精神は「困った時はお互い様」という『相互扶助』であった。まさにアジアのNGOの真骨頂が示されたと自負している。
二〇世紀の戦争に代わり、二一世紀は災害により多くの尊い人達が命を失う可能性がある。「救える命があればどこへでも行く」というAMDAのスローガンを確実に実現するために、相互扶助にもとづく「フレンドシップ」の国際ネットワークの拡充に、今後も一層の努力をしたい。
すがなみ しげる/1946年生まれ。医師。岡山県に本部を置く特定非営利活動法人AMDA(アムダ)の理事長として、医療支援と生活状態の改善をはかるための国際協力活動を展開中。
社交の茶、もてなしの茶、薬用の茶、美容の茶、闘いの茶、くつろぎの茶……。
茶をはじめ、コーヒーなどの嗜好飲料には、単にのどの渇きを癒し、水分を補給するという機能だけでなく、生を養う効能と生活を豊かにする愉しみがある。だからこそ、人類の喫茶の歴史には文化の香りがただようのである。
茶の活きた旨みを読んで味わいあれ。
茶をはじめ、コーヒーなどの嗜好飲料には、単にのどの渇きを癒し、水分を補給するという機能だけでなく、生を養う効能と生活を豊かにする愉しみがある。だからこそ、人類の喫茶の歴史には文化の香りがただようのである。
茶の活きた旨みを読んで味わいあれ。
トルコの嗜好飲料──チャイとコーヒー
トルコのチャイ
トルコの村では、よくお茶をのむ。お茶は、紅茶である。紅茶は、トルコ語でチャイとよばれる。チャイは、二段がさねのやかんをつかってたてる。したのおおぶりのやかんで湯をわかし、うえのこぶりのやかんにいれた紅茶の葉をむす。湯が沸騰してくると、こぶりのやかんにいれた紅茶の葉に少量の湯をそそぐ。しばらくのあいだ、したのやかんの蒸気でうえのやかんの紅茶の葉を煮だす。
紅茶の葉をじゅうぶんに煮だすと、茶こしを通してガラス製のコップにそそぐ。ガラス製のコップは、胴の中央部がくびれた小型のものである。ガラス製のコップに煮だした茶を少量そそいだうえに、湯を適宜くわえる。くわえる湯の量によって、茶の濃淡がきまる。各人のこのみに応じて、茶の濃淡を調整することが可能なわけである。
おおくの場合、ガラス製のコップにはこのみに応じた量の砂糖が茶をそそぐまえにいれられている。茶をそそぐと、ちいさなスプーンで砂糖をかきまぜる。スプーンとコップの内壁がふれあって、たかく澄んだ音があたりにひびきわたる。このとき、多数の人びとがチャイを飲む至福の瞬間を感じる。コップのくびれを柔らかく掌につつみ、チャイを口にふくむ。トルコにおいては、チャイは日常的なレベルで色や香り、味、肌さわり、音など総合的に楽しまれているといえる。
現在、トルコの村ではすくなくとも日に七~八回チャイを飲む。村の家々では、朝のおきがけや朝食時、昼食後、畑仕事の合間、夕食後、来客など多様な時間帯にチャイを用意する。これらのほかに、おおくの男性たちは村のチャイ・ハネ(喫茶店)でチャイを飲む。チャイは、トルコの村の生活には不可欠な要素となっている。チャイなしの生活は、想像もできないくらいである。
これほど村の人びとのなかに深く根づいたチャイであるが、村への普及の歴史はそれほど古いことではない。アナトリア(トルコ共和国の国土の九割以上を占める小アジア半島)中央部南縁の村々では、チャイが日常生活のなかにゆきわたりはじめるのは一九五〇年代中ごろになる。チャイが占める現在の状況をみれば、おどろくほど短期間での普及といってよいだろう。ひとつの文化のなかで不可欠とみられる要素が意外にあたらしいという事象は、比較的ひろくみられるものである。
アナトリア中央部南縁の村々においてチャイが五〇年代中ごろに急速にひろがりはじめた直接的な契機は、砂糖の入手が飛躍的に容易になったことにある。五〇年代にはいって、トルコの各地に国の主導による砂糖工場が二〇カ所以上たてられる。これらの砂糖工場では、周辺の農家と砂糖の原料となるサトウダイコン栽培の契約をむすぶ。栽培契約の代償の一部として、製品となった砂糖の現物支給がはじまったのである。これによって、村々におけるチャイの消費が爆発的に拡大した。
チャイが日常生活に浸透してくるまえには、アナトリア中央部南縁の村々においてどのような飲料がもちいられていたのか。おおくの家庭では、嗜好品としての飲料はほとんどみられなかったというのが実情である。白湯やセージなどの植物を煮だした薬湯は、古くから広範に利用されていた。
トルコ・コーヒー
トルコにおけるチャイ以前の代表的な嗜好飲料は、コーヒーである。コーヒーの原産地であるエチオピアにおいては、はやくからコーヒーの葉や豆を煎じて薬用とする習慣があった。コーヒーがアラビアの地をこえてひろく嗜好飲料として世界に拡大してゆくのは、オスマン帝国の時代である。オスマン帝国は、一六世紀にアラビア半島からエジプトにかけての地域を支配下におさめる。一七世紀初頭には、オスマン帝国の首都コンスタンチノープル(イスタンブル)に世界最初のコーヒーハウスが出現する。
オスマン帝国のなかでは、嗜好品としてのコーヒーの飲用が徐々にひろまってゆく。ここでは、一貫してコーヒーは客もてなしの重要な素材としての位置があたえられている。村々では、父系血縁集団の単位で所有する客室(ミサフィル・ハネ)において賓客にコーヒーが供された。一九五〇年代まで、トルコにおいてはコーヒーと砂糖は貴重品であった。
トルコ・コーヒーは、客となった個人のこのみにこまやかに対応したいれかたで提供される。トルコにおけるチャイのいれかたの原形が、ここにある。トルコ・コーヒーは、砂糖なし(サーデ)や砂糖量の多少についての個別的な要望をきいたうえでひとりひとりにむけてたてる。これは、究極の客もてなし法のひとつといえるだろう。
トルコ・コーヒーにおいても、チャイの場合とおなじように、味や香り、色彩、容器の手ざわりなど総合的な楽しみかたがなされる。飲用後は、コーヒー茶碗を裏がえして占いをおこなう。コーヒーの澱(おり)がなす紋様から、ひとの運命を占うのである。これも、トルコ・コーヒーの楽しみのひとつといえる。
嗜好飲料の意味
トルコにおけるチャイとコーヒーのとりあつかいかたを通して、人類史における嗜好飲料の意味がいくつかうかびあがってくるのではないだろうか。
ひとつは、嗜好飲料のおおくが薬用に起源するということである。エチオピアに起源したコーヒーがはじめ薬として飲用されたと同様に、中国に起源した茶も薬としてもちいられた。人類史における飲料は、薬用から嗜好品として歴史的展開をとげたのである。薬用から嗜好品への歴史的展開をとげた場は、個別の文明のなかであった。茶は中国文明のなかで、コーヒーは地中海文明のなかで、それぞれ嗜好品化した。のちに、嗜好品化の基盤のうえに茶やコーヒーは重要な市場商品となってゆく。
もうひとつは、嗜好飲料のおおくが客もてなしの重要な機能を担っていることである。チャイとコーヒーは、その典型的な事例といえる。人類史のなかで嗜好飲料が客もてなしの機能を担いはじめた時期は、世界の地域によって同一ではない。地域による時代的差異はあるにしても、嗜好飲料が客もてなしの機能をもちはじめたのは比較的あたらしい時代といってよいだろう。とくに、トルコをふくむユーラシア西部においては、その傾向がつよい。それは、嗜好飲料と砂糖とのむすびつきが強固であったためであろう。中国や日本をふくむユーラシア東部においては、すくなくとも茶と砂糖との結合関係はそれほど強固ではない。
人類史における飲料のなかで、茶やコーヒーとは別系統とみられるものがある。それは、アルコール飲料である。アルコール飲料は、本来的にカミガミとの交流の機能を担ったものであった。人類史のなかで、アルコール飲料も嗜好品化した。嗜好品化したアルコール飲料は、重要な客もてなしの機能を付与されている。今後、嗜好品化される飲料はさらに増加するだろう。それによって、人類の楽しみはひろがってゆくのだろうか。
トルコの村では、よくお茶をのむ。お茶は、紅茶である。紅茶は、トルコ語でチャイとよばれる。チャイは、二段がさねのやかんをつかってたてる。したのおおぶりのやかんで湯をわかし、うえのこぶりのやかんにいれた紅茶の葉をむす。湯が沸騰してくると、こぶりのやかんにいれた紅茶の葉に少量の湯をそそぐ。しばらくのあいだ、したのやかんの蒸気でうえのやかんの紅茶の葉を煮だす。
紅茶の葉をじゅうぶんに煮だすと、茶こしを通してガラス製のコップにそそぐ。ガラス製のコップは、胴の中央部がくびれた小型のものである。ガラス製のコップに煮だした茶を少量そそいだうえに、湯を適宜くわえる。くわえる湯の量によって、茶の濃淡がきまる。各人のこのみに応じて、茶の濃淡を調整することが可能なわけである。
おおくの場合、ガラス製のコップにはこのみに応じた量の砂糖が茶をそそぐまえにいれられている。茶をそそぐと、ちいさなスプーンで砂糖をかきまぜる。スプーンとコップの内壁がふれあって、たかく澄んだ音があたりにひびきわたる。このとき、多数の人びとがチャイを飲む至福の瞬間を感じる。コップのくびれを柔らかく掌につつみ、チャイを口にふくむ。トルコにおいては、チャイは日常的なレベルで色や香り、味、肌さわり、音など総合的に楽しまれているといえる。
現在、トルコの村ではすくなくとも日に七~八回チャイを飲む。村の家々では、朝のおきがけや朝食時、昼食後、畑仕事の合間、夕食後、来客など多様な時間帯にチャイを用意する。これらのほかに、おおくの男性たちは村のチャイ・ハネ(喫茶店)でチャイを飲む。チャイは、トルコの村の生活には不可欠な要素となっている。チャイなしの生活は、想像もできないくらいである。
これほど村の人びとのなかに深く根づいたチャイであるが、村への普及の歴史はそれほど古いことではない。アナトリア(トルコ共和国の国土の九割以上を占める小アジア半島)中央部南縁の村々では、チャイが日常生活のなかにゆきわたりはじめるのは一九五〇年代中ごろになる。チャイが占める現在の状況をみれば、おどろくほど短期間での普及といってよいだろう。ひとつの文化のなかで不可欠とみられる要素が意外にあたらしいという事象は、比較的ひろくみられるものである。
アナトリア中央部南縁の村々においてチャイが五〇年代中ごろに急速にひろがりはじめた直接的な契機は、砂糖の入手が飛躍的に容易になったことにある。五〇年代にはいって、トルコの各地に国の主導による砂糖工場が二〇カ所以上たてられる。これらの砂糖工場では、周辺の農家と砂糖の原料となるサトウダイコン栽培の契約をむすぶ。栽培契約の代償の一部として、製品となった砂糖の現物支給がはじまったのである。これによって、村々におけるチャイの消費が爆発的に拡大した。
チャイが日常生活に浸透してくるまえには、アナトリア中央部南縁の村々においてどのような飲料がもちいられていたのか。おおくの家庭では、嗜好品としての飲料はほとんどみられなかったというのが実情である。白湯やセージなどの植物を煮だした薬湯は、古くから広範に利用されていた。
トルコ・コーヒー
トルコにおけるチャイ以前の代表的な嗜好飲料は、コーヒーである。コーヒーの原産地であるエチオピアにおいては、はやくからコーヒーの葉や豆を煎じて薬用とする習慣があった。コーヒーがアラビアの地をこえてひろく嗜好飲料として世界に拡大してゆくのは、オスマン帝国の時代である。オスマン帝国は、一六世紀にアラビア半島からエジプトにかけての地域を支配下におさめる。一七世紀初頭には、オスマン帝国の首都コンスタンチノープル(イスタンブル)に世界最初のコーヒーハウスが出現する。
オスマン帝国のなかでは、嗜好品としてのコーヒーの飲用が徐々にひろまってゆく。ここでは、一貫してコーヒーは客もてなしの重要な素材としての位置があたえられている。村々では、父系血縁集団の単位で所有する客室(ミサフィル・ハネ)において賓客にコーヒーが供された。一九五〇年代まで、トルコにおいてはコーヒーと砂糖は貴重品であった。
トルコ・コーヒーは、客となった個人のこのみにこまやかに対応したいれかたで提供される。トルコにおけるチャイのいれかたの原形が、ここにある。トルコ・コーヒーは、砂糖なし(サーデ)や砂糖量の多少についての個別的な要望をきいたうえでひとりひとりにむけてたてる。これは、究極の客もてなし法のひとつといえるだろう。
トルコ・コーヒーにおいても、チャイの場合とおなじように、味や香り、色彩、容器の手ざわりなど総合的な楽しみかたがなされる。飲用後は、コーヒー茶碗を裏がえして占いをおこなう。コーヒーの澱(おり)がなす紋様から、ひとの運命を占うのである。これも、トルコ・コーヒーの楽しみのひとつといえる。
嗜好飲料の意味
トルコにおけるチャイとコーヒーのとりあつかいかたを通して、人類史における嗜好飲料の意味がいくつかうかびあがってくるのではないだろうか。
ひとつは、嗜好飲料のおおくが薬用に起源するということである。エチオピアに起源したコーヒーがはじめ薬として飲用されたと同様に、中国に起源した茶も薬としてもちいられた。人類史における飲料は、薬用から嗜好品として歴史的展開をとげたのである。薬用から嗜好品への歴史的展開をとげた場は、個別の文明のなかであった。茶は中国文明のなかで、コーヒーは地中海文明のなかで、それぞれ嗜好品化した。のちに、嗜好品化の基盤のうえに茶やコーヒーは重要な市場商品となってゆく。
もうひとつは、嗜好飲料のおおくが客もてなしの重要な機能を担っていることである。チャイとコーヒーは、その典型的な事例といえる。人類史のなかで嗜好飲料が客もてなしの機能を担いはじめた時期は、世界の地域によって同一ではない。地域による時代的差異はあるにしても、嗜好飲料が客もてなしの機能をもちはじめたのは比較的あたらしい時代といってよいだろう。とくに、トルコをふくむユーラシア西部においては、その傾向がつよい。それは、嗜好飲料と砂糖とのむすびつきが強固であったためであろう。中国や日本をふくむユーラシア東部においては、すくなくとも茶と砂糖との結合関係はそれほど強固ではない。
人類史における飲料のなかで、茶やコーヒーとは別系統とみられるものがある。それは、アルコール飲料である。アルコール飲料は、本来的にカミガミとの交流の機能を担ったものであった。人類史のなかで、アルコール飲料も嗜好品化した。嗜好品化したアルコール飲料は、重要な客もてなしの機能を付与されている。今後、嗜好品化される飲料はさらに増加するだろう。それによって、人類の楽しみはひろがってゆくのだろうか。
医食同源の思想と茶
小松かつ子
薬効が謳われる漢民族の茶
私の専門は生薬学で、生薬資源を探索し、品質を評価し、薬としての有効性を調べる研究が主体であるが、それとともに、各地の民族薬物を比較することにより、民族間の交流の軌跡を明らかにする比較民族薬物学にも興味をもっており、中国を中心としてアジア各地を調査している。
フィールドワークでは現地の諸民族とのコミュニケーションがもっとも大切である。「郷に入れば郷に従え」で、何でも食べ何でも飲んで、飲食をともにしながら薬用植物の産地とそれらの使用方法を調べる。したがって、「飲む」機会はひじょうに多く、日中であれば茶、夜であれば酒となる。
漢民族は基本的に葉茶を飲むが、茶の種類はたいへんバラエティーに富んでいる。茶葉の発酵の有無、発酵方法やその程度によって名称が変わる。緑茶、烏龍茶、普 (ぷーある)茶あたりまでは誰もが知っていると思われるが、その他に茉莉花(まりか)茶、菊花(きっか)茶、苦丁(くてい)茶などがあり、さらに私の知識外の茶もたくさん存在する。四川省の
(ぷーある)茶あたりまでは誰もが知っていると思われるが、その他に茉莉花(まりか)茶、菊花(きっか)茶、苦丁(くてい)茶などがあり、さらに私の知識外の茶もたくさん存在する。四川省の 為(けんい)県へウコンの調査に行った時のことである。普通の茶はカフェインが入っているため、夜間飲むと眠りをさまたげられることがあるが、薬材公司の方に案内された店で、夜間眠れないことがない茶だと言って「老人茶」を勧められた。深みのある味わいでたいへん飲みやすかった。その原材料を見せてもらって驚いたのは、モチノキ科植物につく虫の糞だったのである。何でも試して飲むという漢民族の習慣は、漢方の湯液(煎じ薬)発展の根底にある思想であったのかもしれない。
為(けんい)県へウコンの調査に行った時のことである。普通の茶はカフェインが入っているため、夜間飲むと眠りをさまたげられることがあるが、薬材公司の方に案内された店で、夜間眠れないことがない茶だと言って「老人茶」を勧められた。深みのある味わいでたいへん飲みやすかった。その原材料を見せてもらって驚いたのは、モチノキ科植物につく虫の糞だったのである。何でも試して飲むという漢民族の習慣は、漢方の湯液(煎じ薬)発展の根底にある思想であったのかもしれない。
中国で茶として飲用されるものには、たいてい薬効が謳われている。茶葉は、清熱、除煩、解毒、止瀉(ししゃ)、利尿、消化薬として、頭痛、めまい、目の充血、多眠症、心煩、口渇、下痢、胃腸炎などに応用される。漢方では、宋代に著された『和剤局方』に収載される「川 (せんきゅう)茶調散」に配合され、白
(せんきゅう)茶調散」に配合され、白 (びゃくし)、甘草(かんぞう)、羌活(きょうかつ)、荊芥(けいがい)、川
(びゃくし)、甘草(かんぞう)、羌活(きょうかつ)、荊芥(けいがい)、川 、防風(ぼうふう)、香附子(こうぶし)、薄荷葉(はっかよう)と合わせて散剤にし、風邪症候群、血の道症の筋緊張性頭痛、常習性頭痛などに応用される。現在では生活習慣病予防薬として茶の効能が注目され、多くの薬理研究がなされて、タンニン成分のエピガロカテキンガレートなどに抗酸化、血圧降下作用などが報告されている。
、防風(ぼうふう)、香附子(こうぶし)、薄荷葉(はっかよう)と合わせて散剤にし、風邪症候群、血の道症の筋緊張性頭痛、常習性頭痛などに応用される。現在では生活習慣病予防薬として茶の効能が注目され、多くの薬理研究がなされて、タンニン成分のエピガロカテキンガレートなどに抗酸化、血圧降下作用などが報告されている。
バターやミルク、生薬を混ぜて飲むことも
チベット族、ウイグル族などは茶葉を蒸して圧搾し、それに麹菌を発酵させて作った磚茶(だんちゃ)を使用する。大黄(だいおう)の資源調査でチベット族に会うこともしばしばであったが、彼らの茶は酥油茶(そゆちゃ)(バター茶)または 茶(だいちゃ)(ミルク茶)であった。酥油茶または
茶(だいちゃ)(ミルク茶)であった。酥油茶または 茶では、磚茶を削って湯に入れ、よく煮沸させてからバターまたは新鮮な牛乳(ヤクの乳も使われる)、
茶では、磚茶を削って湯に入れ、よく煮沸させてからバターまたは新鮮な牛乳(ヤクの乳も使われる)、 酪(だいらく)(一種のヨーグルト)及び若干の塩を加えて茶が作られる。肉食中心のチベット族では、バター茶や
酪(だいらく)(一種のヨーグルト)及び若干の塩を加えて茶が作られる。肉食中心のチベット族では、バター茶や 茶の飲用はビタミンCやフラボノイドの補給の上で最たるものであり、高山帯における乾燥や紫外線から身を守る上でも重要であると思われる。
茶の飲用はビタミンCやフラボノイドの補給の上で最たるものであり、高山帯における乾燥や紫外線から身を守る上でも重要であると思われる。
青海省で出された 茶に使われていた磚茶には、意外なことに、便秘や消化不良の治療に用いられる大黄が入れられていた。
茶に使われていた磚茶には、意外なことに、便秘や消化不良の治療に用いられる大黄が入れられていた。 茶を飲みながらそのことを話すと、胃腸障害のときは磚茶の量を倍にするとの返事が返ってきた。このような、飲食物と薬の区別がない用法を見るたびに、中国では医食同源の思想が隅々まで浸透していることに感心させられる。しかしながら、茶とは嗜好品としての飲用の趣が強い。
茶を飲みながらそのことを話すと、胃腸障害のときは磚茶の量を倍にするとの返事が返ってきた。このような、飲食物と薬の区別がない用法を見るたびに、中国では医食同源の思想が隅々まで浸透していることに感心させられる。しかしながら、茶とは嗜好品としての飲用の趣が強い。
喫茶の起源は四川省とされ、前漢には茶が商品になっていた記録がある。その形態と喫茶法は、三国から東晋の記述にも、「荊巴(けいは)の間、葉を採(つ)みて餅(へい)と作す。…茗(めい)(茶)を煮て飲まんと欲すれば、先ず炙(あぶ)りて赤色ならしめ、末に搗(つ)き瓷器(じき)の中に置き、湯を以ってこれを澆覆(ぎょうふく)し、葱(そう)、薑(きょう)、橘子(きつし)を用いてこれを (ま)ぜる」とある。また、唐代に著された『茶経』の中で陸羽(りくう)は、「葱、薑、棗(そう)、橘皮(きっぴ)、茱萸(しゅゆ)、薄荷などを茶にまぜて、百沸する」と当時の喫茶法を紹介する。ただし、その後でこの方法は排撃すべき喫茶法であると述べている(陸羽の主張は茶だけの飲用を勧めるものであった)。茶に混ぜるとされたものはそれぞれ、葱白(そうはく)、生姜(しょうきょう)、大棗(たいそう)、陳皮(ちんぴ)、呉茱萸(ごしゅゆ)、薄荷で、漢方でも使われる生薬である。しかしこれらは茶の香味付けに加えられたものと見なした方が無難であろう。
(ま)ぜる」とある。また、唐代に著された『茶経』の中で陸羽(りくう)は、「葱、薑、棗(そう)、橘皮(きっぴ)、茱萸(しゅゆ)、薄荷などを茶にまぜて、百沸する」と当時の喫茶法を紹介する。ただし、その後でこの方法は排撃すべき喫茶法であると述べている(陸羽の主張は茶だけの飲用を勧めるものであった)。茶に混ぜるとされたものはそれぞれ、葱白(そうはく)、生姜(しょうきょう)、大棗(たいそう)、陳皮(ちんぴ)、呉茱萸(ごしゅゆ)、薄荷で、漢方でも使われる生薬である。しかしこれらは茶の香味付けに加えられたものと見なした方が無難であろう。
漢方薬はこれと同じように生薬を混ぜ、煎じてから飲むのであるが、配合の仕方には一定の法則がある。『傷寒論』(後漢)に収載されている風邪の初期に用いられる葛根湯を例にとれば、葛根は君薬(主薬)、麻黄は臣薬(主薬に準じる)、桂枝と芍薬は佐薬(君薬の働きを補助)、甘草、生姜、大棗は使薬(君臣佐薬の補助)である。葛根は、麻黄、桂枝と組んで発汗解熱し、また芍薬と組んで筋肉の攣縮(れんしゅく)を和らげ、大棗は上部を潤し、生姜は身体表層部の気を順(な)らし、甘草は諸薬を調和する、というように作用に偏りがないように作られている。漢方薬は治療を目的にしており、医食同源における生薬の使い方とは異なっている。
漢方薬は医師や薬剤師にお任せするとして、私たちは健康の維持や病気の予防のために、食材に近い生薬を選んで茶葉とブレンドし、飲んでみるのもよいかもしれない。
私の専門は生薬学で、生薬資源を探索し、品質を評価し、薬としての有効性を調べる研究が主体であるが、それとともに、各地の民族薬物を比較することにより、民族間の交流の軌跡を明らかにする比較民族薬物学にも興味をもっており、中国を中心としてアジア各地を調査している。
フィールドワークでは現地の諸民族とのコミュニケーションがもっとも大切である。「郷に入れば郷に従え」で、何でも食べ何でも飲んで、飲食をともにしながら薬用植物の産地とそれらの使用方法を調べる。したがって、「飲む」機会はひじょうに多く、日中であれば茶、夜であれば酒となる。
漢民族は基本的に葉茶を飲むが、茶の種類はたいへんバラエティーに富んでいる。茶葉の発酵の有無、発酵方法やその程度によって名称が変わる。緑茶、烏龍茶、普
 (ぷーある)茶あたりまでは誰もが知っていると思われるが、その他に茉莉花(まりか)茶、菊花(きっか)茶、苦丁(くてい)茶などがあり、さらに私の知識外の茶もたくさん存在する。四川省の
(ぷーある)茶あたりまでは誰もが知っていると思われるが、その他に茉莉花(まりか)茶、菊花(きっか)茶、苦丁(くてい)茶などがあり、さらに私の知識外の茶もたくさん存在する。四川省の 為(けんい)県へウコンの調査に行った時のことである。普通の茶はカフェインが入っているため、夜間飲むと眠りをさまたげられることがあるが、薬材公司の方に案内された店で、夜間眠れないことがない茶だと言って「老人茶」を勧められた。深みのある味わいでたいへん飲みやすかった。その原材料を見せてもらって驚いたのは、モチノキ科植物につく虫の糞だったのである。何でも試して飲むという漢民族の習慣は、漢方の湯液(煎じ薬)発展の根底にある思想であったのかもしれない。
為(けんい)県へウコンの調査に行った時のことである。普通の茶はカフェインが入っているため、夜間飲むと眠りをさまたげられることがあるが、薬材公司の方に案内された店で、夜間眠れないことがない茶だと言って「老人茶」を勧められた。深みのある味わいでたいへん飲みやすかった。その原材料を見せてもらって驚いたのは、モチノキ科植物につく虫の糞だったのである。何でも試して飲むという漢民族の習慣は、漢方の湯液(煎じ薬)発展の根底にある思想であったのかもしれない。中国で茶として飲用されるものには、たいてい薬効が謳われている。茶葉は、清熱、除煩、解毒、止瀉(ししゃ)、利尿、消化薬として、頭痛、めまい、目の充血、多眠症、心煩、口渇、下痢、胃腸炎などに応用される。漢方では、宋代に著された『和剤局方』に収載される「川
 (せんきゅう)茶調散」に配合され、白
(せんきゅう)茶調散」に配合され、白 (びゃくし)、甘草(かんぞう)、羌活(きょうかつ)、荊芥(けいがい)、川
(びゃくし)、甘草(かんぞう)、羌活(きょうかつ)、荊芥(けいがい)、川 、防風(ぼうふう)、香附子(こうぶし)、薄荷葉(はっかよう)と合わせて散剤にし、風邪症候群、血の道症の筋緊張性頭痛、常習性頭痛などに応用される。現在では生活習慣病予防薬として茶の効能が注目され、多くの薬理研究がなされて、タンニン成分のエピガロカテキンガレートなどに抗酸化、血圧降下作用などが報告されている。
、防風(ぼうふう)、香附子(こうぶし)、薄荷葉(はっかよう)と合わせて散剤にし、風邪症候群、血の道症の筋緊張性頭痛、常習性頭痛などに応用される。現在では生活習慣病予防薬として茶の効能が注目され、多くの薬理研究がなされて、タンニン成分のエピガロカテキンガレートなどに抗酸化、血圧降下作用などが報告されている。バターやミルク、生薬を混ぜて飲むことも
チベット族、ウイグル族などは茶葉を蒸して圧搾し、それに麹菌を発酵させて作った磚茶(だんちゃ)を使用する。大黄(だいおう)の資源調査でチベット族に会うこともしばしばであったが、彼らの茶は酥油茶(そゆちゃ)(バター茶)または
 茶(だいちゃ)(ミルク茶)であった。酥油茶または
茶(だいちゃ)(ミルク茶)であった。酥油茶または 茶では、磚茶を削って湯に入れ、よく煮沸させてからバターまたは新鮮な牛乳(ヤクの乳も使われる)、
茶では、磚茶を削って湯に入れ、よく煮沸させてからバターまたは新鮮な牛乳(ヤクの乳も使われる)、 酪(だいらく)(一種のヨーグルト)及び若干の塩を加えて茶が作られる。肉食中心のチベット族では、バター茶や
酪(だいらく)(一種のヨーグルト)及び若干の塩を加えて茶が作られる。肉食中心のチベット族では、バター茶や 茶の飲用はビタミンCやフラボノイドの補給の上で最たるものであり、高山帯における乾燥や紫外線から身を守る上でも重要であると思われる。
茶の飲用はビタミンCやフラボノイドの補給の上で最たるものであり、高山帯における乾燥や紫外線から身を守る上でも重要であると思われる。青海省で出された
 茶に使われていた磚茶には、意外なことに、便秘や消化不良の治療に用いられる大黄が入れられていた。
茶に使われていた磚茶には、意外なことに、便秘や消化不良の治療に用いられる大黄が入れられていた。 茶を飲みながらそのことを話すと、胃腸障害のときは磚茶の量を倍にするとの返事が返ってきた。このような、飲食物と薬の区別がない用法を見るたびに、中国では医食同源の思想が隅々まで浸透していることに感心させられる。しかしながら、茶とは嗜好品としての飲用の趣が強い。
茶を飲みながらそのことを話すと、胃腸障害のときは磚茶の量を倍にするとの返事が返ってきた。このような、飲食物と薬の区別がない用法を見るたびに、中国では医食同源の思想が隅々まで浸透していることに感心させられる。しかしながら、茶とは嗜好品としての飲用の趣が強い。喫茶の起源は四川省とされ、前漢には茶が商品になっていた記録がある。その形態と喫茶法は、三国から東晋の記述にも、「荊巴(けいは)の間、葉を採(つ)みて餅(へい)と作す。…茗(めい)(茶)を煮て飲まんと欲すれば、先ず炙(あぶ)りて赤色ならしめ、末に搗(つ)き瓷器(じき)の中に置き、湯を以ってこれを澆覆(ぎょうふく)し、葱(そう)、薑(きょう)、橘子(きつし)を用いてこれを
 (ま)ぜる」とある。また、唐代に著された『茶経』の中で陸羽(りくう)は、「葱、薑、棗(そう)、橘皮(きっぴ)、茱萸(しゅゆ)、薄荷などを茶にまぜて、百沸する」と当時の喫茶法を紹介する。ただし、その後でこの方法は排撃すべき喫茶法であると述べている(陸羽の主張は茶だけの飲用を勧めるものであった)。茶に混ぜるとされたものはそれぞれ、葱白(そうはく)、生姜(しょうきょう)、大棗(たいそう)、陳皮(ちんぴ)、呉茱萸(ごしゅゆ)、薄荷で、漢方でも使われる生薬である。しかしこれらは茶の香味付けに加えられたものと見なした方が無難であろう。
(ま)ぜる」とある。また、唐代に著された『茶経』の中で陸羽(りくう)は、「葱、薑、棗(そう)、橘皮(きっぴ)、茱萸(しゅゆ)、薄荷などを茶にまぜて、百沸する」と当時の喫茶法を紹介する。ただし、その後でこの方法は排撃すべき喫茶法であると述べている(陸羽の主張は茶だけの飲用を勧めるものであった)。茶に混ぜるとされたものはそれぞれ、葱白(そうはく)、生姜(しょうきょう)、大棗(たいそう)、陳皮(ちんぴ)、呉茱萸(ごしゅゆ)、薄荷で、漢方でも使われる生薬である。しかしこれらは茶の香味付けに加えられたものと見なした方が無難であろう。漢方薬はこれと同じように生薬を混ぜ、煎じてから飲むのであるが、配合の仕方には一定の法則がある。『傷寒論』(後漢)に収載されている風邪の初期に用いられる葛根湯を例にとれば、葛根は君薬(主薬)、麻黄は臣薬(主薬に準じる)、桂枝と芍薬は佐薬(君薬の働きを補助)、甘草、生姜、大棗は使薬(君臣佐薬の補助)である。葛根は、麻黄、桂枝と組んで発汗解熱し、また芍薬と組んで筋肉の攣縮(れんしゅく)を和らげ、大棗は上部を潤し、生姜は身体表層部の気を順(な)らし、甘草は諸薬を調和する、というように作用に偏りがないように作られている。漢方薬は治療を目的にしており、医食同源における生薬の使い方とは異なっている。
漢方薬は医師や薬剤師にお任せするとして、私たちは健康の維持や病気の予防のために、食材に近い生薬を選んで茶葉とブレンドし、飲んでみるのもよいかもしれない。
安渓の茶の韻
「荼を得て解毒」
中国は茶の発祥地である。四〇〇〇年余り前、炎帝である神農が茶を発見したという。「百草をなめてためし、七二種の毒に出会うが、荼を得て解毒した」と伝えられる。この「荼」とは茶のことである。解毒の効能によって知られるところとなり、後に飲料となった。
唐代陸羽の『茶経』が世に出てから、喫茶は次第に中国全土に広がり、徐々に中国人の伝統生活できわめて特徴のある習俗のひとつとなった。中国人が茶を好むのは、おいしさと、高尚な精神的享受になることのほかに、養生と長生にも効果があるからである。明代の著名な医学者である李時珍は『本草綱目』で、茶は苦く、冷える性のものであり、のぼせをいやすのにもっとも効きめがあると記している。さらに現代の科学者たちは、茶葉から豊富な蛋白質、アミノ酸、多種類のビタミンのほかに、カフェイン、ポリフェノール、クロロフィル、カロチンなどの薬効成分を発見している。だからこそ茶は、世界の人びとにことのほか愛される健康飲料のひとつとなったのである。
「茶中の王」鉄観音
今日の中国の茶ブームを語るとき、福建省泉州市の安渓県に言及しないわけにはいかない。このウーロン茶の産地で始まった「鉄観音ブーム」が今すさまじい勢いで広がっているからである。安渓のウーロン茶は五四種類あり、鉄観音はそのうちの極上品で、「茶中の王」と言われ、一八世紀に当地で発見された。言い伝えによると、魏姓の男が毎日観音さまに焼香し、茶を供えていたところ、観音さまの夢を見て、その導きによって、家の裏にある崖の上の岩間から蘭の香りのする茶樹をみつけたという。男は三年を経て、茶樹の苗を移植し、栽培に成功し、その木に「鉄観音」と名づけた。
信憑性に欠ける伝説だが、鉄観音は確かに他の品種より魅力的である。それで入れた茶は黄金色で澄み切っている。湯を含んでふくれた茶葉は厚みがあり、絹のように柔かく、光沢がある。茶は香りが高く、茶杯を持ち上げて近づけると芳香が広がり、しばらく漂って、いい気持ちにさせてくれる。一口含むと、すぐにこくと甘みが口中に広がり、唾液の分泌が促進され、歯と頬の間に香りが残るような気がする。ゆっくり飲みほすと、蜂蜜のような甘みがのどに残り、余韻が尽きない。色、香り、味のすべてがすばらしい。
「韻」は、安渓で鉄観音を賞味する際の高雅な感覚を形容して用いられる。宋代の詩人、陸游(りくゆう)が「舌根に常に残り、甘みが一日も尽きぬ」と書いた。それはまた、すばらしい詩歌を読んだときのように、余韻が長く残り、心に刻まれる。中国の銘茶の鑑定士たちは、安渓の鉄観音だけにこのような天然純真の味があると評価する。鉄観音の香りは茶葉そのもののもつ自然の香りであり、それが独特の韻を生み出している。
鉄観音の妙はさまざまに異なる香りがあることである。木犀(もくせい)、クチナシ、あるいはフルーツやミルクのキャンディ、大豆の香りなど、数百種類にものぼる。飲む人の生活体験、花や植物に対する思いによって、香りの感じ方も違ってくる。このような千変万化の香りと情趣があるからこそ、人びとに無限の楽しみを与えてくれるのである。
茶俗さまざま
安渓では多くの「茶俗」が形成されてきた。茶を以って客をもてなすのは伝統的作法である。親戚や友人同士の贈答にもよく特産の銘茶が用いられる。婚約時の結納品のなかには、かならず地元産の上等の茶が入っている。婚礼で新婦は義理の親と上の世代の親戚たちに、まず、茶を差し上げて、礼をする。そのお返しの装飾品は新婦が茶を出したお盆に置かれる。結婚後の里帰りから新婦が婚家へ戻るとき、元気な茶の苗を選んで持ち帰り、夫の家で栽培する。これは「帯青」(ダイチン)という。結婚前の若い男女も茶畑で歌垣をして、互いの気持ちを伝え合い、気が合えば、結婚に至る。葬式でも、喪主側が親戚や友人を茶で接待する。清明節の墓参りでは、先祖に三杯の茶をささげる。旧暦の毎月一日と一五日の朝、茶を作る農家は三杯の上等の茶を神像の前に供え、加護を祈願する。
茶俗のなかで特におもしろいのは「茶王戦」である。古代の「闘茶」の名残りだが、今は昔より盛んになっている。この一〇年、安渓の人びとは村・郷鎮・県レベルのほか、広州、上海、香港、アモイなどの都市でも盛大な「茶王戦」を開催して、「鉄観音」の旋風を巻き起こしている。「茶王戦」には、製茶の名手や製茶工場が上等の茶を持ち寄り、はせ参じる。季節ごとの各品種の「茶王」がその場で選出され、優勝者に賞牌と賞金が授与される。鉄観音の茶王が最高の栄誉とされ、その優勝者は「茶王の御輿」に乗って、銅鑼(どら)や太鼓の音のなかで街をパレードする。これは昔、科挙試験で「進士」の首席合格者が街を練り歩いたのとよく似ている。
喫茶は社交の一様式でもある。最近はやっている「闘茶」では、数人の茶の愛好者が集まり、誰がもってきた茶が一番おいしいかを競い合う。優勝者は得意満面になる。このような「闘茶」が流行となっている。
文化人の間の「闘茶」はいっそう情趣に満ちている。宋代の著名な文豪、蘇東坡(そとうば)は茶の達人であった。彼は茶を賛美する数々の詩を書いた。いちばんよく知られているのは「従来佳茗似佳人」(ツォンライジャー ミン スー ジャーレン)――そもそも名茶は美人に似ているという詩句である。現代の文人たちも美辞麗句で鉄観音のすばらしさを形容すると同時に、異なるタイプの女性に喩(たと)える。この茶は少女のように純潔でかわいらしい、あの茶は貴婦人のようにあでやかでゴージャスだ、これはまたしなやかで、気品があるとか、あの茶は少しも包み隠さず、セクシーで悩ましいなど。このように彼らは陽気にはしゃぎ、盛り上がると、いつの間にかその場の雰囲気は熱気であふれる。
安渓では、上等な茶を味わえるだけでなく、茶にまつわる秀逸な詩や歌、聯(れん)(一対の文句を二枚の掛け軸に書いたもの)、ことわざ、踊り、さらに独特な作法をもつ茶芸なども鑑賞することができる。そこは芳香漂う、中国で茶の文化がもっとも豊かで多彩な土地である。
中国は茶の発祥地である。四〇〇〇年余り前、炎帝である神農が茶を発見したという。「百草をなめてためし、七二種の毒に出会うが、荼を得て解毒した」と伝えられる。この「荼」とは茶のことである。解毒の効能によって知られるところとなり、後に飲料となった。
唐代陸羽の『茶経』が世に出てから、喫茶は次第に中国全土に広がり、徐々に中国人の伝統生活できわめて特徴のある習俗のひとつとなった。中国人が茶を好むのは、おいしさと、高尚な精神的享受になることのほかに、養生と長生にも効果があるからである。明代の著名な医学者である李時珍は『本草綱目』で、茶は苦く、冷える性のものであり、のぼせをいやすのにもっとも効きめがあると記している。さらに現代の科学者たちは、茶葉から豊富な蛋白質、アミノ酸、多種類のビタミンのほかに、カフェイン、ポリフェノール、クロロフィル、カロチンなどの薬効成分を発見している。だからこそ茶は、世界の人びとにことのほか愛される健康飲料のひとつとなったのである。
「茶中の王」鉄観音
今日の中国の茶ブームを語るとき、福建省泉州市の安渓県に言及しないわけにはいかない。このウーロン茶の産地で始まった「鉄観音ブーム」が今すさまじい勢いで広がっているからである。安渓のウーロン茶は五四種類あり、鉄観音はそのうちの極上品で、「茶中の王」と言われ、一八世紀に当地で発見された。言い伝えによると、魏姓の男が毎日観音さまに焼香し、茶を供えていたところ、観音さまの夢を見て、その導きによって、家の裏にある崖の上の岩間から蘭の香りのする茶樹をみつけたという。男は三年を経て、茶樹の苗を移植し、栽培に成功し、その木に「鉄観音」と名づけた。
信憑性に欠ける伝説だが、鉄観音は確かに他の品種より魅力的である。それで入れた茶は黄金色で澄み切っている。湯を含んでふくれた茶葉は厚みがあり、絹のように柔かく、光沢がある。茶は香りが高く、茶杯を持ち上げて近づけると芳香が広がり、しばらく漂って、いい気持ちにさせてくれる。一口含むと、すぐにこくと甘みが口中に広がり、唾液の分泌が促進され、歯と頬の間に香りが残るような気がする。ゆっくり飲みほすと、蜂蜜のような甘みがのどに残り、余韻が尽きない。色、香り、味のすべてがすばらしい。
「韻」は、安渓で鉄観音を賞味する際の高雅な感覚を形容して用いられる。宋代の詩人、陸游(りくゆう)が「舌根に常に残り、甘みが一日も尽きぬ」と書いた。それはまた、すばらしい詩歌を読んだときのように、余韻が長く残り、心に刻まれる。中国の銘茶の鑑定士たちは、安渓の鉄観音だけにこのような天然純真の味があると評価する。鉄観音の香りは茶葉そのもののもつ自然の香りであり、それが独特の韻を生み出している。
鉄観音の妙はさまざまに異なる香りがあることである。木犀(もくせい)、クチナシ、あるいはフルーツやミルクのキャンディ、大豆の香りなど、数百種類にものぼる。飲む人の生活体験、花や植物に対する思いによって、香りの感じ方も違ってくる。このような千変万化の香りと情趣があるからこそ、人びとに無限の楽しみを与えてくれるのである。
茶俗さまざま
安渓では多くの「茶俗」が形成されてきた。茶を以って客をもてなすのは伝統的作法である。親戚や友人同士の贈答にもよく特産の銘茶が用いられる。婚約時の結納品のなかには、かならず地元産の上等の茶が入っている。婚礼で新婦は義理の親と上の世代の親戚たちに、まず、茶を差し上げて、礼をする。そのお返しの装飾品は新婦が茶を出したお盆に置かれる。結婚後の里帰りから新婦が婚家へ戻るとき、元気な茶の苗を選んで持ち帰り、夫の家で栽培する。これは「帯青」(ダイチン)という。結婚前の若い男女も茶畑で歌垣をして、互いの気持ちを伝え合い、気が合えば、結婚に至る。葬式でも、喪主側が親戚や友人を茶で接待する。清明節の墓参りでは、先祖に三杯の茶をささげる。旧暦の毎月一日と一五日の朝、茶を作る農家は三杯の上等の茶を神像の前に供え、加護を祈願する。
茶俗のなかで特におもしろいのは「茶王戦」である。古代の「闘茶」の名残りだが、今は昔より盛んになっている。この一〇年、安渓の人びとは村・郷鎮・県レベルのほか、広州、上海、香港、アモイなどの都市でも盛大な「茶王戦」を開催して、「鉄観音」の旋風を巻き起こしている。「茶王戦」には、製茶の名手や製茶工場が上等の茶を持ち寄り、はせ参じる。季節ごとの各品種の「茶王」がその場で選出され、優勝者に賞牌と賞金が授与される。鉄観音の茶王が最高の栄誉とされ、その優勝者は「茶王の御輿」に乗って、銅鑼(どら)や太鼓の音のなかで街をパレードする。これは昔、科挙試験で「進士」の首席合格者が街を練り歩いたのとよく似ている。
喫茶は社交の一様式でもある。最近はやっている「闘茶」では、数人の茶の愛好者が集まり、誰がもってきた茶が一番おいしいかを競い合う。優勝者は得意満面になる。このような「闘茶」が流行となっている。
文化人の間の「闘茶」はいっそう情趣に満ちている。宋代の著名な文豪、蘇東坡(そとうば)は茶の達人であった。彼は茶を賛美する数々の詩を書いた。いちばんよく知られているのは「従来佳茗似佳人」(ツォンライジャー ミン スー ジャーレン)――そもそも名茶は美人に似ているという詩句である。現代の文人たちも美辞麗句で鉄観音のすばらしさを形容すると同時に、異なるタイプの女性に喩(たと)える。この茶は少女のように純潔でかわいらしい、あの茶は貴婦人のようにあでやかでゴージャスだ、これはまたしなやかで、気品があるとか、あの茶は少しも包み隠さず、セクシーで悩ましいなど。このように彼らは陽気にはしゃぎ、盛り上がると、いつの間にかその場の雰囲気は熱気であふれる。
安渓では、上等な茶を味わえるだけでなく、茶にまつわる秀逸な詩や歌、聯(れん)(一対の文句を二枚の掛け軸に書いたもの)、ことわざ、踊り、さらに独特な作法をもつ茶芸なども鑑賞することができる。そこは芳香漂う、中国で茶の文化がもっとも豊かで多彩な土地である。
無形文化遺産の映像記録
カンボジアの名影絵師ティー・チアン座長。
生前のレパートリーとともに、彼の芸と技を記録した映像は貴重な文化遺産となった。
人間の知識、技術、行為など、無形の伝統を伝える映像記録は、いまや重要な博物館資料のひとつ。
博物館が古いモノを残すところから、新しい創造の装置へ変わるかもしれない。
生前のレパートリーとともに、彼の芸と技を記録した映像は貴重な文化遺産となった。
人間の知識、技術、行為など、無形の伝統を伝える映像記録は、いまや重要な博物館資料のひとつ。
博物館が古いモノを残すところから、新しい創造の装置へ変わるかもしれない。
人間の営みと技を残す
博物館にとって映像が重要な資料になりつつある。
人類が、うごく映像を記録できるようになってから一世紀あまり。人間生活のさまざまな側面が映像で記録されてきた。とくに小型のビデオカメラが普及してからは、手軽に映像記録が可能になり、私たちは身の回りのあらゆるものを撮影するようになった。失われつつある生活習慣やまつり、伝統的な芸能、職人の技など、文字や写真だけでは描ききれない「無形文化遺産」も、私たちは映像で記録に残すことができる。
博物館は長らくモノを収集、保管し、展示するところだと考えられてきた。もちろん、これまでもモノと一緒に、さまざまな情報を集めて蓄積していた。しかし、これからは、積極的に映像による記録資料を残していくことが求められるだろう。モノを生み出し、使う人びとの姿を映像に残すことで、モノと人の関係をより具体的に記録することができる。人間の社会や文化への理解を深めることを目的とする博物館にとっては、映像はモノと同じように重要な資料である。
一方、映像が身近になったからこそ、いかなる目的で何をどのように撮影するか、どんな映像をどのように残していくか、そしてその映像をどのように利用するかについて考えることがいっそう大事になってきている。博物館は、モノについて同じことをやってきた。何を収集するか、どのように保存するか、そしてどのように展示するかについて、博物館で働く人びとはつねに考えているはずだ。
モノの資料と映像資料は、性質がまったく異なるので、同じようにとりあつかうことはできない。しかし、どちらも人間の社会や文化について理解を深めるために不可欠のものであり、密接に関連づけていく必要がある。調査研究をおこない、モノや情報を収集して保存管理し、展示などをとおして研究成果を公開する博物館に、映像記録を作成することが期待されるのは当然のことだろう。
カンボジアの「失われゆく」芸能
国立民族学博物館は、一九七七年の開館以来、一貫して、映像を重要な研究の手段、そして世界の文化について理解を深めるためのメディアとして位置づけてきた。国内外で、独自の映像取材も頻繁におこなっている。
一九九九年暮れと二〇〇〇年の春先、私は、同僚の寺田吉孝さん、そして映像スタッフとともにカンボジアを訪れた。カンボジアの伝統芸能の映像取材と関連する資料の収集をおこなうためである。首都プノンペンでは、寺田さんの昔からの友人である音楽研究者サムアン・サムさんにコーディネートをお願いし、文化芸術省や王立芸術大学の協力を得て、さまざまな演劇・舞踊・音楽を映像に収めた。一方、アンコール・ワットで有名なシエムリアップでは、伝統的な影絵の復興に尽力する福富友子さんの協力を得て、二種類の伝統的な影絵などを記録した(一〇ページ写真参照)。
カンボジアでは、ポル・ポトがひきいるクメール・ルージュの時代(一九七五年~一九七九年)に、知識人、芸術家、技術者など、多くの人びとが殺された。その後も、さまざまな政治勢力の抗争がつづいてきた。この間、カンボジアの伝統芸能は壊滅的な打撃を受けた。社会の混乱で芸能を上演する機会が失われただけでなく、演者の命がうばわれ、芸能に用いる道具や衣装も破壊された。
一九九〇年代に入って、多くの国の協力によって、ようやく和平への道がひらかれた。私たちが訪れたときには、復興のための努力が軌道に乗りはじめていた。生き残ったひとにぎりの芸術家たちやそれを助ける人びとの努力によって、伝統芸能も息を吹き返しつつあった。アンコール・ワットの壁に刻まれた天女アプサラを思い起こさせる優雅な舞踊、インドに起源をもつ物語ラーマーヤナを題材とした仮面劇などを撮影していると、私たちはカンボジアが苦しんだ時代を忘れてしまいそうだった。
しかし、シエムリアップで大型影絵スバエク・トムの撮影にのぞんだときには、カンボジアの伝統芸能が直面する大きな課題をつよく意識せざるをえなかった。スバエク・トムの一座をひきいる長老ティー・チアンさんは、すでに八〇歳をこえていた。かつてティー・チアンさんと一緒に影絵を演じた経験をもつごくわずかの人びとが彼を支え、若いメンバーを指導していた。若者たちは、すでにスバエク・トムの上演をみたこともない世代だ。
福富さんに通訳をお願いしてティー・チアンさんから話をうかがうと、自分の芸をなかなか若者に伝えられないもどかしさがひしひしと伝わってきた。スバエク・トムのかなめとなるのは語りだ。人形の操作も音楽も、この語りに合わせて進行する。語りには、伝えられたとおり語る部分と、自分なりに工夫を加えて語る部分がある。七夜分あるレパートリーすべての語りをおぼえ、さらに自分なりの語りをつむぎだす技をみがくには、時間がかかって当然だ。
しかし、すでに時間が足りないようにみえた。ティー・チアンさんの体調は思わしくない。もし彼に何かあれば、その芸は永遠に失われてしまうだろう。何としても、今のうちに彼の語りを中心とした上演を記録しておきたい。結局、私たちはスバエク・トムのレパートリーすべてを七日間かけて撮影した。毎晩、約二時間ほどの上演だった。
その年の夏、ティー・チアンさんはシエムリアップの自宅で亡くなった。皆が病院に行くことを勧めても、「精霊の思し召しだから」と言ってきかなかったという。私たちの手元に残った映像は、非常に貴重なものになった。それと同時に、私たちの責任もそれだけ重くなったといえるだろう。
文化の担い手を育てる
現在、世界中の伝統的な芸能が、大きな変化や伝承の危機にさらされているといわれ、そうした芸能を保護し振興する必要性がさけばれている。「無形文化遺産」という考え方が浸透してきたことも、その流れに拍車をかけている。
二〇〇三年一〇月、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)総会において「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択された。昨年、ソウルでおこなわれた世界博物館会議も、それを受けて「博物館と無形遺産」をテーマとするなど、無形文化遺産への注目は世界の博物館にも波及している。
「無形」文化遺産は、モノとしてそこに存在するものではない。人の行為とともに立ち現れてくる。人間の営みそのものといってもいい。だから、継承する人がいなければ消えてしまう。知識や習慣、伝承、さまざまな技や芸などがそれにふくまれ、「伝統」とか「文化」という言葉でよばれるものとも重なり合っている。
今、多くの人が心配しているのが、若者の伝統文化ばなれである。無形文化遺産が、それをになう人とともに存在するとすれば、人を育てられるかどうかが、無形文化遺産の保護の決め手となる。しかし、継承を強制することはできない。それはあくまでもそれぞれの人の選択にかかっている。教育の充実や環境整備をすすめて、若者が伝統文化を知り、学びたいときに学べるようにすることが大切なのだろう。そのためにも、現在の無形文化遺産の姿を映像で記録しておくことが求められている。
創造の連鎖へ
私たちは、ティー・チアンさんが亡くなる前に、彼の上演を撮影することができた。しかし、もちろん、映像さえあれば、演者がいなくなってもいいというわけではない。映像に記された芸能は、ある特定の時と場所における上演の「記録」に過ぎない。記録を残すことは、芸能を残すのとは別のことだ。では、すぐれない体調をおして、全レパートリーを演じてくれたティー・チアンさんにこたえるために、私たちに何ができるのだろうか。
もっとも大事なことは、この映像を、関心をもつ人びとに利用してもらえるようにすることだろう。たとえば、スバエク・トムを学ぶカンボジアの若者たちは、この映像から多くのことを得るにちがいない。あらためてティー・チアンさんの芸のすばらしさを発見し、自分たちの芸をみがく刺激となるかもしれない。そうなれば、この映像は単なる記録をこえて、スバエク・トムという芸能を発展させることにつながるだろう。
さらに、芸能の研究者に、研究用の資料を提供することになるかもしれない。スバエク・トムをしらない人びとに、そのおもしろさを伝えることもできるだろう。あるいは、芸術家たちがつくる作品にインスピレーションをあたえるかもしれない。そうなれば、この映像は、よりたくさんの人びとの文化的活動へとつながっていくことになる。
博物館がモノを収集するということは、本来おかれていた文脈から切り離してモノをもってくることを意味する。映像で芸能を記録することも、特定の時と場所における上演を、切りとってくるという点で、芸能を本来の文脈から引き離してくることになる。しかし同時に、博物館は、モノと人とのつながりを再び築く場所でもある。資料や情報の活用を通して、博物館は新しい文化活動の触媒となることもできる。ティー・チアンさんの映像についても、博物館が積極的に、伝承、教育、研究、あるいは創作など、広い意味での創造的な活動における活用を可能にすることで、新たな創造的意味をあたえることができるだろう。
博物館の資料は、しまっているだけでは何も生みださないが、それを多くの人に公開することで創造の連鎖を生みだしていくことができる。私たちはその可能性を認識し、積極的にこの映像を多くの人に利用してもらうべきなのだろう。それがティー・チアンさんにこたえることになるのではないだろうか。
博物館にとって映像が重要な資料になりつつある。
人類が、うごく映像を記録できるようになってから一世紀あまり。人間生活のさまざまな側面が映像で記録されてきた。とくに小型のビデオカメラが普及してからは、手軽に映像記録が可能になり、私たちは身の回りのあらゆるものを撮影するようになった。失われつつある生活習慣やまつり、伝統的な芸能、職人の技など、文字や写真だけでは描ききれない「無形文化遺産」も、私たちは映像で記録に残すことができる。
博物館は長らくモノを収集、保管し、展示するところだと考えられてきた。もちろん、これまでもモノと一緒に、さまざまな情報を集めて蓄積していた。しかし、これからは、積極的に映像による記録資料を残していくことが求められるだろう。モノを生み出し、使う人びとの姿を映像に残すことで、モノと人の関係をより具体的に記録することができる。人間の社会や文化への理解を深めることを目的とする博物館にとっては、映像はモノと同じように重要な資料である。
一方、映像が身近になったからこそ、いかなる目的で何をどのように撮影するか、どんな映像をどのように残していくか、そしてその映像をどのように利用するかについて考えることがいっそう大事になってきている。博物館は、モノについて同じことをやってきた。何を収集するか、どのように保存するか、そしてどのように展示するかについて、博物館で働く人びとはつねに考えているはずだ。
モノの資料と映像資料は、性質がまったく異なるので、同じようにとりあつかうことはできない。しかし、どちらも人間の社会や文化について理解を深めるために不可欠のものであり、密接に関連づけていく必要がある。調査研究をおこない、モノや情報を収集して保存管理し、展示などをとおして研究成果を公開する博物館に、映像記録を作成することが期待されるのは当然のことだろう。
カンボジアの「失われゆく」芸能
国立民族学博物館は、一九七七年の開館以来、一貫して、映像を重要な研究の手段、そして世界の文化について理解を深めるためのメディアとして位置づけてきた。国内外で、独自の映像取材も頻繁におこなっている。
一九九九年暮れと二〇〇〇年の春先、私は、同僚の寺田吉孝さん、そして映像スタッフとともにカンボジアを訪れた。カンボジアの伝統芸能の映像取材と関連する資料の収集をおこなうためである。首都プノンペンでは、寺田さんの昔からの友人である音楽研究者サムアン・サムさんにコーディネートをお願いし、文化芸術省や王立芸術大学の協力を得て、さまざまな演劇・舞踊・音楽を映像に収めた。一方、アンコール・ワットで有名なシエムリアップでは、伝統的な影絵の復興に尽力する福富友子さんの協力を得て、二種類の伝統的な影絵などを記録した(一〇ページ写真参照)。
カンボジアでは、ポル・ポトがひきいるクメール・ルージュの時代(一九七五年~一九七九年)に、知識人、芸術家、技術者など、多くの人びとが殺された。その後も、さまざまな政治勢力の抗争がつづいてきた。この間、カンボジアの伝統芸能は壊滅的な打撃を受けた。社会の混乱で芸能を上演する機会が失われただけでなく、演者の命がうばわれ、芸能に用いる道具や衣装も破壊された。
一九九〇年代に入って、多くの国の協力によって、ようやく和平への道がひらかれた。私たちが訪れたときには、復興のための努力が軌道に乗りはじめていた。生き残ったひとにぎりの芸術家たちやそれを助ける人びとの努力によって、伝統芸能も息を吹き返しつつあった。アンコール・ワットの壁に刻まれた天女アプサラを思い起こさせる優雅な舞踊、インドに起源をもつ物語ラーマーヤナを題材とした仮面劇などを撮影していると、私たちはカンボジアが苦しんだ時代を忘れてしまいそうだった。
しかし、シエムリアップで大型影絵スバエク・トムの撮影にのぞんだときには、カンボジアの伝統芸能が直面する大きな課題をつよく意識せざるをえなかった。スバエク・トムの一座をひきいる長老ティー・チアンさんは、すでに八〇歳をこえていた。かつてティー・チアンさんと一緒に影絵を演じた経験をもつごくわずかの人びとが彼を支え、若いメンバーを指導していた。若者たちは、すでにスバエク・トムの上演をみたこともない世代だ。
福富さんに通訳をお願いしてティー・チアンさんから話をうかがうと、自分の芸をなかなか若者に伝えられないもどかしさがひしひしと伝わってきた。スバエク・トムのかなめとなるのは語りだ。人形の操作も音楽も、この語りに合わせて進行する。語りには、伝えられたとおり語る部分と、自分なりに工夫を加えて語る部分がある。七夜分あるレパートリーすべての語りをおぼえ、さらに自分なりの語りをつむぎだす技をみがくには、時間がかかって当然だ。
しかし、すでに時間が足りないようにみえた。ティー・チアンさんの体調は思わしくない。もし彼に何かあれば、その芸は永遠に失われてしまうだろう。何としても、今のうちに彼の語りを中心とした上演を記録しておきたい。結局、私たちはスバエク・トムのレパートリーすべてを七日間かけて撮影した。毎晩、約二時間ほどの上演だった。
その年の夏、ティー・チアンさんはシエムリアップの自宅で亡くなった。皆が病院に行くことを勧めても、「精霊の思し召しだから」と言ってきかなかったという。私たちの手元に残った映像は、非常に貴重なものになった。それと同時に、私たちの責任もそれだけ重くなったといえるだろう。
文化の担い手を育てる
現在、世界中の伝統的な芸能が、大きな変化や伝承の危機にさらされているといわれ、そうした芸能を保護し振興する必要性がさけばれている。「無形文化遺産」という考え方が浸透してきたことも、その流れに拍車をかけている。
二〇〇三年一〇月、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)総会において「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択された。昨年、ソウルでおこなわれた世界博物館会議も、それを受けて「博物館と無形遺産」をテーマとするなど、無形文化遺産への注目は世界の博物館にも波及している。
「無形」文化遺産は、モノとしてそこに存在するものではない。人の行為とともに立ち現れてくる。人間の営みそのものといってもいい。だから、継承する人がいなければ消えてしまう。知識や習慣、伝承、さまざまな技や芸などがそれにふくまれ、「伝統」とか「文化」という言葉でよばれるものとも重なり合っている。
今、多くの人が心配しているのが、若者の伝統文化ばなれである。無形文化遺産が、それをになう人とともに存在するとすれば、人を育てられるかどうかが、無形文化遺産の保護の決め手となる。しかし、継承を強制することはできない。それはあくまでもそれぞれの人の選択にかかっている。教育の充実や環境整備をすすめて、若者が伝統文化を知り、学びたいときに学べるようにすることが大切なのだろう。そのためにも、現在の無形文化遺産の姿を映像で記録しておくことが求められている。
創造の連鎖へ
私たちは、ティー・チアンさんが亡くなる前に、彼の上演を撮影することができた。しかし、もちろん、映像さえあれば、演者がいなくなってもいいというわけではない。映像に記された芸能は、ある特定の時と場所における上演の「記録」に過ぎない。記録を残すことは、芸能を残すのとは別のことだ。では、すぐれない体調をおして、全レパートリーを演じてくれたティー・チアンさんにこたえるために、私たちに何ができるのだろうか。
もっとも大事なことは、この映像を、関心をもつ人びとに利用してもらえるようにすることだろう。たとえば、スバエク・トムを学ぶカンボジアの若者たちは、この映像から多くのことを得るにちがいない。あらためてティー・チアンさんの芸のすばらしさを発見し、自分たちの芸をみがく刺激となるかもしれない。そうなれば、この映像は単なる記録をこえて、スバエク・トムという芸能を発展させることにつながるだろう。
さらに、芸能の研究者に、研究用の資料を提供することになるかもしれない。スバエク・トムをしらない人びとに、そのおもしろさを伝えることもできるだろう。あるいは、芸術家たちがつくる作品にインスピレーションをあたえるかもしれない。そうなれば、この映像は、よりたくさんの人びとの文化的活動へとつながっていくことになる。
博物館がモノを収集するということは、本来おかれていた文脈から切り離してモノをもってくることを意味する。映像で芸能を記録することも、特定の時と場所における上演を、切りとってくるという点で、芸能を本来の文脈から引き離してくることになる。しかし同時に、博物館は、モノと人とのつながりを再び築く場所でもある。資料や情報の活用を通して、博物館は新しい文化活動の触媒となることもできる。ティー・チアンさんの映像についても、博物館が積極的に、伝承、教育、研究、あるいは創作など、広い意味での創造的な活動における活用を可能にすることで、新たな創造的意味をあたえることができるだろう。
博物館の資料は、しまっているだけでは何も生みださないが、それを多くの人に公開することで創造の連鎖を生みだしていくことができる。私たちはその可能性を認識し、積極的にこの映像を多くの人に利用してもらうべきなのだろう。それがティー・チアンさんにこたえることになるのではないだろうか。
空き缶ハウス
特別展「きのうよりワクワクしてきた。」 出展作品/増岡巽 作 幅/415cm 奥行/315cm 高さ/360cm
特別展「きのうよりワクワクしてきた。」 出展作品/増岡巽 作 幅/415cm 奥行/315cm 高さ/360cm
この空き缶ハウスをつくるのにもちいたアルミ缶の総数はおよそ一万八〇〇〇個におよぶ。たったひとりの男が、三カ月以上をついやして廃品のなかからこれらのアルミ缶をあつめ、それ以上の日数をかけて建設した。空き缶を組みあわせた柱と梁からなる立派なラーメン構造をもち、軒先や窓枠などのディテールにはそれぞれ別種の空き缶をもちいる徹底ぶりだ。
アルミ缶は中身の商品を容れるためにあり、中身を消費してしまえばゴミとして捨てられる運命にある。その空き缶がゴミにならずに巨大な量塊となって自身の存在を主張する。それはたしかに驚嘆すべきことにはちがいないが、空き缶ハウスの衝撃はもっと別のところにある。
男は線路沿いのビニールテントでくらしている。いわゆる路上生活をはじめて二年になる。最初に空き缶ハウスの建設をおもいたったのは、いまの生活をはじめてから半年後。アルミ缶は男の身の回りに無尽蔵にあった。路上生活者の多くは生活の糧をアルミ缶の回収によって得ていたからだ。男にはもともと建設業にかかわっていた経験があり、ありあまるアルミ缶から家づくりを思いたつのに大それた野心は必要なかった。問題はその先だ。毎朝四時半に起きる生活のかたわら、傷んでいない缶をあつめ、つなぎあわせるという単調な仕事を何カ月にもわたって継続する。それは信念とか、思想といった言葉が似つかわしい事件にみえる。空き缶ハウスをつくる可能性は誰にでもひらかれている。しかし、いまだかつて、それをあえて実現した者は彼をおいてなかったのだ。そのようなとき、われわれは男の夢の実現をすなおに祝福する言葉をもてるだろうか?(写真は特別展のために制作された二代目である)
アルミ缶は中身の商品を容れるためにあり、中身を消費してしまえばゴミとして捨てられる運命にある。その空き缶がゴミにならずに巨大な量塊となって自身の存在を主張する。それはたしかに驚嘆すべきことにはちがいないが、空き缶ハウスの衝撃はもっと別のところにある。
男は線路沿いのビニールテントでくらしている。いわゆる路上生活をはじめて二年になる。最初に空き缶ハウスの建設をおもいたったのは、いまの生活をはじめてから半年後。アルミ缶は男の身の回りに無尽蔵にあった。路上生活者の多くは生活の糧をアルミ缶の回収によって得ていたからだ。男にはもともと建設業にかかわっていた経験があり、ありあまるアルミ缶から家づくりを思いたつのに大それた野心は必要なかった。問題はその先だ。毎朝四時半に起きる生活のかたわら、傷んでいない缶をあつめ、つなぎあわせるという単調な仕事を何カ月にもわたって継続する。それは信念とか、思想といった言葉が似つかわしい事件にみえる。空き缶ハウスをつくる可能性は誰にでもひらかれている。しかし、いまだかつて、それをあえて実現した者は彼をおいてなかったのだ。そのようなとき、われわれは男の夢の実現をすなおに祝福する言葉をもてるだろうか?(写真は特別展のために制作された二代目である)
友の会とミュージアム・ショップからのご案内
あるネパール人の日本経験
ここ数年、日本に超過滞在し働いているネパール人のことを調べている。彼/彼女らの経験談は実に愉快で、戸惑いや生活感覚がにじみでているが、他方で、私たちが気づかない「日本」を露わにしてくれる。調査の過程で、あるネパール人の友人から聞いた、そんな話を紹介したい。
友人が仕事からアパートに戻ると、来日して間もなくまだ就労していない居候がいった。「今日は近くのスーパーで安い米を見つけたから買っておいたよ」。自慢げに見せる大きな袋は、犬の絵が描かれたドッグフードである。世の中にドッグフードなるものがあることを知らない人にとって、それは「犬印の米」に映ったとしても無理からぬことだ。しかも、日ごろから彼/彼女らは、日本では中身と包装のデザインが一致しないと感じているのだ。「それで返品したの?」と私が聞くと、友人はそんな恥ずかしいことはできないという。「それじゃ犬を飼っている日本人の同僚にでもあげれば?」というと、「とんでもない、そんなことをしたら『お前、犬も飼ってないのに何でこんなもの買ったんだ』と馬鹿にされるに決まってる」という。こうして、ドッグフードは押入れにしまわれた。
職場の日本人から見下されたくない、という気持ちは強い。たとえば、同僚に「ネパール人は大便の後で、水で拭くんだってな」といわれると、すかさず「そうだけど、日本人はトイレットペーパーができる前は何で拭いていたの?」と尋ね返す。
「チリ紙」
「じゃその前は?」
「新聞紙だろう」
「じゃ新聞紙ができる前は?」
「知るか!」
挙句は「ウォシュレットを先取りしていたのがネパールなのだ」と言い負かす。
こんな話も聞いた。JICA(国際協力機構)の研修で、ネパールの元の職場の同僚女性が来日し、東京を案内したときのことだ。昼食に偶然入ったレストランは、お好み焼きを自ら鉄板で焼く店であった。いきなり生卵がのったものが出てきて、女性は「えっ、これ食べるの?」という。友人もさすがにギョッとしたらしいが、ここでひるんでは格好わるい。日本人は生卵を食べるし、これは付け合せのサラダだろうと思い口に入れようとした。間一髪、店員が慌てふためいて飛んできて、止めたそうだ。それからは「日本通」のメッキがはげ、せっかくのデートが台なしになったことはいうまでもない。
送還されて帰国しても話はつきない。せっかく覚えた日本語を忘れないようにと、友人は日本語学校の門をたたいた。クラスを決める日本語でのインタビューに応じると「あなたはこの学校の生徒ではありません、先生です」といわれ、日本の最新事情や文化に詳しいことから、短期で日本を訪問する人の個人レッスンを任される。ある日、生徒が「先生、『ものさし』って何ですか?」と尋ねてきた。さて、「花をさす」とか「モノをさす」というし、何かモノをさしておく容器だろうと思ってそう答える。だが、後で辞書をひいて驚いたらしい。「生徒に正解は伝えたの?」と私が聞くと、どうせしばらくしたら忘れるだろうから、そのうち「前にもいったでしょう。『ものさし』とはルーラー(定規)のことですよ」とシラを切るのだそうだ。
あっぱれ。さすがは、危ない作業のときには日本語がわからないふりをして、日本人に交代してもらっていたという友人である。みんな健康にだけは気をつけて、それぞれの夢をかなえて帰ってもらいたいと思う。
友人が仕事からアパートに戻ると、来日して間もなくまだ就労していない居候がいった。「今日は近くのスーパーで安い米を見つけたから買っておいたよ」。自慢げに見せる大きな袋は、犬の絵が描かれたドッグフードである。世の中にドッグフードなるものがあることを知らない人にとって、それは「犬印の米」に映ったとしても無理からぬことだ。しかも、日ごろから彼/彼女らは、日本では中身と包装のデザインが一致しないと感じているのだ。「それで返品したの?」と私が聞くと、友人はそんな恥ずかしいことはできないという。「それじゃ犬を飼っている日本人の同僚にでもあげれば?」というと、「とんでもない、そんなことをしたら『お前、犬も飼ってないのに何でこんなもの買ったんだ』と馬鹿にされるに決まってる」という。こうして、ドッグフードは押入れにしまわれた。
職場の日本人から見下されたくない、という気持ちは強い。たとえば、同僚に「ネパール人は大便の後で、水で拭くんだってな」といわれると、すかさず「そうだけど、日本人はトイレットペーパーができる前は何で拭いていたの?」と尋ね返す。
「チリ紙」
「じゃその前は?」
「新聞紙だろう」
「じゃ新聞紙ができる前は?」
「知るか!」
挙句は「ウォシュレットを先取りしていたのがネパールなのだ」と言い負かす。
こんな話も聞いた。JICA(国際協力機構)の研修で、ネパールの元の職場の同僚女性が来日し、東京を案内したときのことだ。昼食に偶然入ったレストランは、お好み焼きを自ら鉄板で焼く店であった。いきなり生卵がのったものが出てきて、女性は「えっ、これ食べるの?」という。友人もさすがにギョッとしたらしいが、ここでひるんでは格好わるい。日本人は生卵を食べるし、これは付け合せのサラダだろうと思い口に入れようとした。間一髪、店員が慌てふためいて飛んできて、止めたそうだ。それからは「日本通」のメッキがはげ、せっかくのデートが台なしになったことはいうまでもない。
送還されて帰国しても話はつきない。せっかく覚えた日本語を忘れないようにと、友人は日本語学校の門をたたいた。クラスを決める日本語でのインタビューに応じると「あなたはこの学校の生徒ではありません、先生です」といわれ、日本の最新事情や文化に詳しいことから、短期で日本を訪問する人の個人レッスンを任される。ある日、生徒が「先生、『ものさし』って何ですか?」と尋ねてきた。さて、「花をさす」とか「モノをさす」というし、何かモノをさしておく容器だろうと思ってそう答える。だが、後で辞書をひいて驚いたらしい。「生徒に正解は伝えたの?」と私が聞くと、どうせしばらくしたら忘れるだろうから、そのうち「前にもいったでしょう。『ものさし』とはルーラー(定規)のことですよ」とシラを切るのだそうだ。
あっぱれ。さすがは、危ない作業のときには日本語がわからないふりをして、日本人に交代してもらっていたという友人である。みんな健康にだけは気をつけて、それぞれの夢をかなえて帰ってもらいたいと思う。
ブリコラージュと『アポロ13』
いま民博で開催されている特別展「きのうよりワクワクしてきた。」のキーワードは「ブリコラージュ」である。これはフランス語で、身の回りのありあわせの材料や道具を使って、自分の手でものを作ることを意味する。
さて、ブリコラージュで思いだすのが、去年たまたまテレビで見た『アポロ13(サーティーン)』という映画である。実話をもとに作られたこの映画のストーリーを簡単に紹介しよう。
一九七〇年四月、人類三度目の月着陸をめざして、アポロ13号は順調に飛行を続けていた。しかし、月まであと少しというところで、突然何かの爆発音とともに激しい振動に見舞われた。アポロ宇宙船は、司令船・機械船・月着陸船という三つの部分でできているが、機械船の液体酸素タンクのひとつが破裂したのである。このままでは三人の宇宙飛行士たちは死んでしまう。地上からの指示で彼らは急遽(きゅうきょ)司令船の機能をすべて停止して、月着陸船へと避難した。
月着陸を中止して、なんとか地球までたどりつけるかにみえたアポロ13号に、新たな問題が発生した。月着陸船で二酸化炭素濃度の異常を示す黄色いランプが点灯したのである。密室の宇宙船内では、人がはきだす二酸化炭素はフィルタで吸収する。本来二人乗りの月着陸船に三人が長時間乗りこんだため、予想以上に早くフィルタの容量を超えてしまったのだ。司令船で使っている四角いフィルタは、月着陸船の丸いものとは形が合わず使えない。
この問題に対処するため、NASA(米航空宇宙局)の地上スタッフは宇宙船に積みこんであるのとまったく同じあらゆるものをテーブルの上に広げ、解決策を考えはじめた。そしてついに、司令船用の水酸化リチウム入りのケースに粘着テープ、廃棄物用の袋、宇宙服のホース、飛行計画書の表紙、それにソックスを組みあわせて、月着陸船で使える二酸化炭素吸着フィルタを作りだした。これは、まさにブリコラージュである。
ところでこのシーンの少し前に、こんなやりとりがある。アポロ13号を地球帰還軌道に乗せるため、故障しているかもしれない機械船のメインエンジンの代わりに、月着陸船のエンジンを噴射するという案を地上スタッフは考えた。
「何の保証もできません。月着陸船は月に着陸するために設計されているので」
意見を求められたグラマン社の技術者は答えた。それに対して、飛行実施責任者のジーン・クランツが言ったことばはこうだ。
「何のために作られたかなんて、この際どうでもいい。何のために使えるかが問題なんだ」
これこそ、ブリコラージュの精神を言いあてているのではなかろうか。
地上スタッフと宇宙飛行士たちの必死の努力の結果、三人は奇跡的に無事地球に帰還することができた。ハイテク技術の粋をあつめた宇宙船の中でさえ、生死にかかわる予想もできない事態から飛行士たちを救ったのは、ローテクなブリコラージュの方法だった。既存の知識や技術の体系を越えて未知の領域に踏みこんだとき、ふと顔をだすのは、人間が昔からもちつづけているこんな「野生の思考」なのかもしれない。
さて、ブリコラージュで思いだすのが、去年たまたまテレビで見た『アポロ13(サーティーン)』という映画である。実話をもとに作られたこの映画のストーリーを簡単に紹介しよう。
一九七〇年四月、人類三度目の月着陸をめざして、アポロ13号は順調に飛行を続けていた。しかし、月まであと少しというところで、突然何かの爆発音とともに激しい振動に見舞われた。アポロ宇宙船は、司令船・機械船・月着陸船という三つの部分でできているが、機械船の液体酸素タンクのひとつが破裂したのである。このままでは三人の宇宙飛行士たちは死んでしまう。地上からの指示で彼らは急遽(きゅうきょ)司令船の機能をすべて停止して、月着陸船へと避難した。
月着陸を中止して、なんとか地球までたどりつけるかにみえたアポロ13号に、新たな問題が発生した。月着陸船で二酸化炭素濃度の異常を示す黄色いランプが点灯したのである。密室の宇宙船内では、人がはきだす二酸化炭素はフィルタで吸収する。本来二人乗りの月着陸船に三人が長時間乗りこんだため、予想以上に早くフィルタの容量を超えてしまったのだ。司令船で使っている四角いフィルタは、月着陸船の丸いものとは形が合わず使えない。
この問題に対処するため、NASA(米航空宇宙局)の地上スタッフは宇宙船に積みこんであるのとまったく同じあらゆるものをテーブルの上に広げ、解決策を考えはじめた。そしてついに、司令船用の水酸化リチウム入りのケースに粘着テープ、廃棄物用の袋、宇宙服のホース、飛行計画書の表紙、それにソックスを組みあわせて、月着陸船で使える二酸化炭素吸着フィルタを作りだした。これは、まさにブリコラージュである。
ところでこのシーンの少し前に、こんなやりとりがある。アポロ13号を地球帰還軌道に乗せるため、故障しているかもしれない機械船のメインエンジンの代わりに、月着陸船のエンジンを噴射するという案を地上スタッフは考えた。
「何の保証もできません。月着陸船は月に着陸するために設計されているので」
意見を求められたグラマン社の技術者は答えた。それに対して、飛行実施責任者のジーン・クランツが言ったことばはこうだ。
「何のために作られたかなんて、この際どうでもいい。何のために使えるかが問題なんだ」
これこそ、ブリコラージュの精神を言いあてているのではなかろうか。
地上スタッフと宇宙飛行士たちの必死の努力の結果、三人は奇跡的に無事地球に帰還することができた。ハイテク技術の粋をあつめた宇宙船の中でさえ、生死にかかわる予想もできない事態から飛行士たちを救ったのは、ローテクなブリコラージュの方法だった。既存の知識や技術の体系を越えて未知の領域に踏みこんだとき、ふと顔をだすのは、人間が昔からもちつづけているこんな「野生の思考」なのかもしれない。
点字で読み書き2 指先で触れる文字
米国に留学していたころ「日本の点字はアメリカより小さいし、用紙だってB5サイズだ。アメリカの点字本は持ち運びに不便だろう」と友人に質問した。彼いわく「アメリカ人は身体などすべてが大きいから点字もビッグなのさ」。小さい点字でスペース節約というのは、やはり日本人的な発想なのだろうか。点の大きさや用紙サイズに違いはあるものの、点字が六点(縦三点で横二列)により構成されているのは世界共通である。六点の組み合わせは、二の六乗で六四種類しかない。だから数字やアルファベットを表現するためには、数符、外字符などの記号を前置する。1・4・5の点の組み合わせは日本語なら「る」であるが、「四」とも「d」ともなりうる。少ない点で多くの文字や符号を区別することができるのが、点字の単純にして複雑なおもしろさなのだ。
僕はいくつかの大学や市民サークルで点字を教えた経験をもつが、点字学習の第一歩は自分の名前を書いてみることだろう。漢字、カタカナ、ひらがなを柔軟かつ適当に使い分けているわれわれ日本人は、点字という「もうひとつの手段」で書き表された自分の名前を見て驚く。「このよくわからないボツボツがわが名前なのか!?」ここから単純にして複雑な異文化体験がスタートする。
点字を書くためには点字器が必要だ。点字タイプライター、パソコンを使って点字を書くことも可能だが、点字学習、異文化体験の基礎は、点をひとつずつぼつぼつと打つことであろう。点字器も多種多様だが、基本は定規と点筆のセットである。定規を開いて紙を間に挟み、点筆を紙に対し垂直に当てて、右から左へひとマスずつ書き進める。なお点字器の入手を希望される際は最寄りの点字図書館、福祉センターなどにお問い合わせいただきたい。
点字は現代仮名遣いに準じて表記する。ただし、助詞の「は」「へ」は発音どおりに「わ」「え」と書き、「う」列「お」列の長音(普通文字では「う」と表記する伸びる音)には長音符を用いる。つまり「ぼくわ ひろせ こーじろーです」となる。凹面と凸面、長音符……。この辺で点字が容「易」なものでないことに気づき、異文化を学ぶ気持ちが「萎」縮してしまう晴眼者も多い。でも、異文化コミュニケーションは「易」でも「萎」でもなく、まずは相手に身を「委」ねることから始まる。「よくわからん」「変なルール」など呟(つぶや)きながら、点字の単純にして複雑な世界に身を委ねてみよう。
漢字もなく符号類にも限りがある点字。ケータイの絵文字も楽しいが、あえて今シンプルな点字を使って、「中身」で勝負できる文章を書いてみたい。六点の組み合わせから紡ぎ出される「点字力」を求めて、ぜひみなさんにもちょっと変わった「委」文化体験を味わってほしい。
*本紙P17「読み(凸面)、書き(凹面)は左右対称」は、画像データでご覧下さい。
僕はいくつかの大学や市民サークルで点字を教えた経験をもつが、点字学習の第一歩は自分の名前を書いてみることだろう。漢字、カタカナ、ひらがなを柔軟かつ適当に使い分けているわれわれ日本人は、点字という「もうひとつの手段」で書き表された自分の名前を見て驚く。「このよくわからないボツボツがわが名前なのか!?」ここから単純にして複雑な異文化体験がスタートする。
点字を書くためには点字器が必要だ。点字タイプライター、パソコンを使って点字を書くことも可能だが、点字学習、異文化体験の基礎は、点をひとつずつぼつぼつと打つことであろう。点字器も多種多様だが、基本は定規と点筆のセットである。定規を開いて紙を間に挟み、点筆を紙に対し垂直に当てて、右から左へひとマスずつ書き進める。なお点字器の入手を希望される際は最寄りの点字図書館、福祉センターなどにお問い合わせいただきたい。
点字は現代仮名遣いに準じて表記する。ただし、助詞の「は」「へ」は発音どおりに「わ」「え」と書き、「う」列「お」列の長音(普通文字では「う」と表記する伸びる音)には長音符を用いる。つまり「ぼくわ ひろせ こーじろーです」となる。凹面と凸面、長音符……。この辺で点字が容「易」なものでないことに気づき、異文化を学ぶ気持ちが「萎」縮してしまう晴眼者も多い。でも、異文化コミュニケーションは「易」でも「萎」でもなく、まずは相手に身を「委」ねることから始まる。「よくわからん」「変なルール」など呟(つぶや)きながら、点字の単純にして複雑な世界に身を委ねてみよう。
漢字もなく符号類にも限りがある点字。ケータイの絵文字も楽しいが、あえて今シンプルな点字を使って、「中身」で勝負できる文章を書いてみたい。六点の組み合わせから紡ぎ出される「点字力」を求めて、ぜひみなさんにもちょっと変わった「委」文化体験を味わってほしい。
*本紙P17「読み(凸面)、書き(凹面)は左右対称」は、画像データでご覧下さい。
中国収集工作的三大原則
其の一 適正価格を知る可し
桂林の名所の奇峰の一つに畳彩山(ディエツァイ)というところがある。切り立った岩山に階段がつくられており、頂上にのぼると桂林の景色を一望することができる。急斜面の階段を上ると汗が噴きだしてくる。山を下りたところには土産物や飲み物を売る店や屋台が並んでいる。そこに、リヤカーでライチを売るおじさんがいて、片言の日本語を使って「ヤスイヨー」と日本人とおぼしき観光客に声を掛けていた。それが一粒、一〇元(約一三〇円!)。市場に行くと一粒ではなく優に一房は買える金額だ。おじさんはわたしにも声を掛けてきたが、実勢価格を知っているわたしは買う気はなかった。試しに値切ってみようと思った。しかし、おじさんは実にしぶとく、値切りに応じない。そのうちに別の日本人観光客が来たのでおじさんはそちらにターゲットを変えた。中国ではモノの値段交渉はかように精力を使う仕事なのだ。
ライチ一粒だけならともかく、数百点もの標本資料になると価格の交渉だけでたいへんな労力が必要だ。こちらは一定の時間内で仕事をすませなければならないが、先方は時間の制約がない。かくして先方は少しでも高く売ろうとねばることになる。しかも、市場価格のわかる商品ならともかく、少数民族地域の農民の家でなにかを買うときは価格自体がわからない。また、はじめてで事情がわからない場所に外国人が一人で入ると村人に疑われて公安に目をつけられる危険性もある。そもそも、とかく保守的な農民は初対面の見知らぬ外国人に容易にモノを売らないし、また農民が経済に「目覚め」てきている最近では、エスニックなものの人気の高まりともあいまって、とくに観光地やその近くでは外国人とみるとかえって法外な値段で売りつけてひと儲けしようとする場合もある。
其の二 事前調査と現物確認を怠る可からず
かりに農村でモノを買ったとしても、それらを通関させるのはまたたいへんだ。しかるべき博物館や研究所がその資料を「文化用品であって商品でない」旨を証明してくれる書類や、中国が輸出を禁止しているものではないという文物局による鑑定の書類が必要だ。少数民族女性の銀製装飾品などの貴金属製品についても国外への持ち出しの可能な重量が決められており、その証明もいる。わたしは中国で収集するときには、多くは省や自治区の博物館や研究所などを通して購入している。その際に、前もって購入候補をリストアップし相手側に代行して集めてもらう方式と、相手側に同行してもらって直接、現地で購入する方式の、二つの方式を併用している。農具・生活用具など使い方がわかりやすいものは前者の方式で、民族衣装など着付けの過程や使い方をビデオに収録する必要があるものは後者の方式を用いている。いずれの場合でも購入資料は事前調査を十分にして必ず自分の目で確認したものに限られるが、こうした方式をとる理由は前に述べたところにある。信頼できる相手側機関に農民との「取り引き」を依頼することによって、よいモノを適正な価格で購入し、手際よく通関手続きをしてモノを確実に送る、ということなのである。
こうした事情のほかに中国での収集の歴史的経緯もある。民博が、中国に赴き標本資料を購入するようになったのは、一九七九年以降のことである。当初は民博が中国側の窓口である北京の民族文化宮に希望を出して、民族文化宮が資料の収集を代行しておこなうシステムをとっていた。
当時は改革開放政策がとられ始めてまだ日も浅く、資料を現地で購入するどころか調査に入ることさえも困難な時代で、中央の政府機関に収集を依存せざるを得なかった。そもそも民族文化宮に依頼することになったのも当時の国務院副総理の口利きによるほどだ。当時、中央政府の力は絶大で、本当かどうかはさだかではないが、大型の船を購入して運搬するときにたまたま細い道にかかって電信柱が行く手をふさいだので邪魔だとばかり切り倒して船を運んだとか、銀製装身具を着用した少数民族の女性を見かけたときにその場で強制的に供出させた、などという話が伝えられている。
其の三 友との交誼を育む可し
わたしが収集に関わりはじめた一九八〇年代末のころは、まだ輸送体制に不安があって日本の港につくまでは心配だった。契約にもとづいて仕事をするという観念が完全に根付いてはいなかったのだ。また、お役所仕事的なところもあって、就労時間が終わると、重要な作業の途中でも「今日の仕事は終わり」ということもあった。八〇年代のように国営商店の店員が堂々と客の前で居眠りしていたり、人びとが店で買い物をするにもバスに乗るにも並ばずに先を争ったりといった見苦しい光景はさすがになくなったが、それでも九〇年代前半の頃は効率の悪さと不安から、収集に行くつど胃潰瘍や胃炎を患って帰国後に病院通いをしたものだった。北京では宴会に必ず出る六〇度近い焼酎も、弱った胃に追い討ちをかけた。しかし、九〇年代後半以降になると、地方でも収集できるようになった。中国は経済的な発展を遂げるとともに、大都市では契約の観念も根付き、輸送面でほとんど心配することがなくなった。一九九三年までは二重価格制度をとっており、外国人が銀行で両替すると「外氵匯兌換券(ワイホイドイホァンジュエン)」という専用の紙幣を手にしたが、それは農村では通用しない代物だった。私的な旅行で小遣い銭程度なら友人と換える方法もあったが、公務の場合はそうはいかない。それも人民元に一本化されて便利になった。わたしの胃も痛むことが少なくなった。
中国での収集を通じて痛感するのは人間関係の重要さである。中国では、友人や知り合いの人のネットワークを重視する国民性がある。一旦相手を信用すると、体を張って仕事に協力してくれるところがある。収集した資料の登録作業をしていたとき、夜遅くまで手伝ってくれたこと、友人の頼みだからということで、文献の収集の際に、残業どころか一晩かけて数千枚以上も複写してくれたこと、一緒に残業し夜食をともにしたうえ「寝酒に飲め」といってケースごと缶ビールを差し入れてくれたことなど、友人から受けた好意は数知れない。そうした友人たちが各地にできた今、わたしの中国通いはまだ終わりそうにもない。
桂林の名所の奇峰の一つに畳彩山(ディエツァイ)というところがある。切り立った岩山に階段がつくられており、頂上にのぼると桂林の景色を一望することができる。急斜面の階段を上ると汗が噴きだしてくる。山を下りたところには土産物や飲み物を売る店や屋台が並んでいる。そこに、リヤカーでライチを売るおじさんがいて、片言の日本語を使って「ヤスイヨー」と日本人とおぼしき観光客に声を掛けていた。それが一粒、一〇元(約一三〇円!)。市場に行くと一粒ではなく優に一房は買える金額だ。おじさんはわたしにも声を掛けてきたが、実勢価格を知っているわたしは買う気はなかった。試しに値切ってみようと思った。しかし、おじさんは実にしぶとく、値切りに応じない。そのうちに別の日本人観光客が来たのでおじさんはそちらにターゲットを変えた。中国ではモノの値段交渉はかように精力を使う仕事なのだ。
ライチ一粒だけならともかく、数百点もの標本資料になると価格の交渉だけでたいへんな労力が必要だ。こちらは一定の時間内で仕事をすませなければならないが、先方は時間の制約がない。かくして先方は少しでも高く売ろうとねばることになる。しかも、市場価格のわかる商品ならともかく、少数民族地域の農民の家でなにかを買うときは価格自体がわからない。また、はじめてで事情がわからない場所に外国人が一人で入ると村人に疑われて公安に目をつけられる危険性もある。そもそも、とかく保守的な農民は初対面の見知らぬ外国人に容易にモノを売らないし、また農民が経済に「目覚め」てきている最近では、エスニックなものの人気の高まりともあいまって、とくに観光地やその近くでは外国人とみるとかえって法外な値段で売りつけてひと儲けしようとする場合もある。
其の二 事前調査と現物確認を怠る可からず
かりに農村でモノを買ったとしても、それらを通関させるのはまたたいへんだ。しかるべき博物館や研究所がその資料を「文化用品であって商品でない」旨を証明してくれる書類や、中国が輸出を禁止しているものではないという文物局による鑑定の書類が必要だ。少数民族女性の銀製装飾品などの貴金属製品についても国外への持ち出しの可能な重量が決められており、その証明もいる。わたしは中国で収集するときには、多くは省や自治区の博物館や研究所などを通して購入している。その際に、前もって購入候補をリストアップし相手側に代行して集めてもらう方式と、相手側に同行してもらって直接、現地で購入する方式の、二つの方式を併用している。農具・生活用具など使い方がわかりやすいものは前者の方式で、民族衣装など着付けの過程や使い方をビデオに収録する必要があるものは後者の方式を用いている。いずれの場合でも購入資料は事前調査を十分にして必ず自分の目で確認したものに限られるが、こうした方式をとる理由は前に述べたところにある。信頼できる相手側機関に農民との「取り引き」を依頼することによって、よいモノを適正な価格で購入し、手際よく通関手続きをしてモノを確実に送る、ということなのである。
こうした事情のほかに中国での収集の歴史的経緯もある。民博が、中国に赴き標本資料を購入するようになったのは、一九七九年以降のことである。当初は民博が中国側の窓口である北京の民族文化宮に希望を出して、民族文化宮が資料の収集を代行しておこなうシステムをとっていた。
当時は改革開放政策がとられ始めてまだ日も浅く、資料を現地で購入するどころか調査に入ることさえも困難な時代で、中央の政府機関に収集を依存せざるを得なかった。そもそも民族文化宮に依頼することになったのも当時の国務院副総理の口利きによるほどだ。当時、中央政府の力は絶大で、本当かどうかはさだかではないが、大型の船を購入して運搬するときにたまたま細い道にかかって電信柱が行く手をふさいだので邪魔だとばかり切り倒して船を運んだとか、銀製装身具を着用した少数民族の女性を見かけたときにその場で強制的に供出させた、などという話が伝えられている。
其の三 友との交誼を育む可し
わたしが収集に関わりはじめた一九八〇年代末のころは、まだ輸送体制に不安があって日本の港につくまでは心配だった。契約にもとづいて仕事をするという観念が完全に根付いてはいなかったのだ。また、お役所仕事的なところもあって、就労時間が終わると、重要な作業の途中でも「今日の仕事は終わり」ということもあった。八〇年代のように国営商店の店員が堂々と客の前で居眠りしていたり、人びとが店で買い物をするにもバスに乗るにも並ばずに先を争ったりといった見苦しい光景はさすがになくなったが、それでも九〇年代前半の頃は効率の悪さと不安から、収集に行くつど胃潰瘍や胃炎を患って帰国後に病院通いをしたものだった。北京では宴会に必ず出る六〇度近い焼酎も、弱った胃に追い討ちをかけた。しかし、九〇年代後半以降になると、地方でも収集できるようになった。中国は経済的な発展を遂げるとともに、大都市では契約の観念も根付き、輸送面でほとんど心配することがなくなった。一九九三年までは二重価格制度をとっており、外国人が銀行で両替すると「外氵匯兌換券(ワイホイドイホァンジュエン)」という専用の紙幣を手にしたが、それは農村では通用しない代物だった。私的な旅行で小遣い銭程度なら友人と換える方法もあったが、公務の場合はそうはいかない。それも人民元に一本化されて便利になった。わたしの胃も痛むことが少なくなった。
中国での収集を通じて痛感するのは人間関係の重要さである。中国では、友人や知り合いの人のネットワークを重視する国民性がある。一旦相手を信用すると、体を張って仕事に協力してくれるところがある。収集した資料の登録作業をしていたとき、夜遅くまで手伝ってくれたこと、友人の頼みだからということで、文献の収集の際に、残業どころか一晩かけて数千枚以上も複写してくれたこと、一緒に残業し夜食をともにしたうえ「寝酒に飲め」といってケースごと缶ビールを差し入れてくれたことなど、友人から受けた好意は数知れない。そうした友人たちが各地にできた今、わたしの中国通いはまだ終わりそうにもない。
村の救世主サトウヤシ
原田一宏
樹液から砂糖を精製
インドネシア・西ジャワに位置するスンダ人の村はうっそうとした森林に囲まれ、水田の畦や畑にはサトウヤシが生えている。スンダ人は、周囲に自生する多くの植物をじつにうまく暮らしに役立てているが、なかでもサトウヤシは、村人にとってなくてはならない植物である。特に、花柄から出る樹液は、グラメラと呼ばれる砂糖の原料として大切にされている。
村では、サトウヤシをたたくリズミカルな音が、朝夕響きわたる。村人は花柄の根元を、一週間に一回たたいて刺激しているのだ。その後、村人は、花柄の先端を切り落とし、三日間ほど放置しておく。すると樹液が流れ出てくる。それを長さ一メートルほどのロドンと呼ばれる竹筒の中に受けて、たまった樹液を毎朝回収する。樹液を大きななべに入れて火にかけ煮詰めた後、容器に流し込んで固まれば、砂糖のできあがりである。
砂糖のかたまりは口に入れると、ぼろぼろと崩れ、舌ざわりは少々粗いものの、控えめな甘さが口の中にひろがる。もっとも、村ではあまり食されず、貴重な現金収入源となっている。この砂糖は、甘辛いアシナンといわれる漬物など、都市によくみられる料理の材料として欠かせない。そのため、市場で出回っている白砂糖に取って代わられることはなく、いまだに重宝がられている。
村おこしと森林保全を両立
村人は自分の農地にサトウヤシがあるかどうかは自然任せで、意図的に植えようとはしていない。村人一人あたりの農地には、自生したサトウヤシが、一本から、せいぜい五本ほどあるだけだ。村の慣習では、他人の畑にある雑草や樹木を勝手に取ってもよいことになっているが、サトウヤシではそれが許されない。一方で、水田の利用者は、収穫した稲をすべて自分のものにできるが、畦に生えているサトウヤシから精製された砂糖は、所有者と利用者の間で折半しなければならない。村人にとって、サトウヤシはそれほど貴重なものなのだ。
近年、地元の研究者やNGOが、このサトウヤシを使って、村おこしと森林保全を両立しようとしている。研究者は、村人に苗を配って、村人が苗を植える活動を支援し、NGOの人びとは、精製した砂糖を海外で販売する支援をしている。両者ともに、このような活動を通じて、村人の現金収入が増加すると同時に、それによって、彼らの森林への依存が減り、村の周りの森林破壊が食い止められることを願っている。村の人びとの現金獲得と、村を越えた地球環境保全とが、同時に実現できる新たな試みが始まっている。
インドネシア・西ジャワに位置するスンダ人の村はうっそうとした森林に囲まれ、水田の畦や畑にはサトウヤシが生えている。スンダ人は、周囲に自生する多くの植物をじつにうまく暮らしに役立てているが、なかでもサトウヤシは、村人にとってなくてはならない植物である。特に、花柄から出る樹液は、グラメラと呼ばれる砂糖の原料として大切にされている。
村では、サトウヤシをたたくリズミカルな音が、朝夕響きわたる。村人は花柄の根元を、一週間に一回たたいて刺激しているのだ。その後、村人は、花柄の先端を切り落とし、三日間ほど放置しておく。すると樹液が流れ出てくる。それを長さ一メートルほどのロドンと呼ばれる竹筒の中に受けて、たまった樹液を毎朝回収する。樹液を大きななべに入れて火にかけ煮詰めた後、容器に流し込んで固まれば、砂糖のできあがりである。
砂糖のかたまりは口に入れると、ぼろぼろと崩れ、舌ざわりは少々粗いものの、控えめな甘さが口の中にひろがる。もっとも、村ではあまり食されず、貴重な現金収入源となっている。この砂糖は、甘辛いアシナンといわれる漬物など、都市によくみられる料理の材料として欠かせない。そのため、市場で出回っている白砂糖に取って代わられることはなく、いまだに重宝がられている。
村おこしと森林保全を両立
村人は自分の農地にサトウヤシがあるかどうかは自然任せで、意図的に植えようとはしていない。村人一人あたりの農地には、自生したサトウヤシが、一本から、せいぜい五本ほどあるだけだ。村の慣習では、他人の畑にある雑草や樹木を勝手に取ってもよいことになっているが、サトウヤシではそれが許されない。一方で、水田の利用者は、収穫した稲をすべて自分のものにできるが、畦に生えているサトウヤシから精製された砂糖は、所有者と利用者の間で折半しなければならない。村人にとって、サトウヤシはそれほど貴重なものなのだ。
近年、地元の研究者やNGOが、このサトウヤシを使って、村おこしと森林保全を両立しようとしている。研究者は、村人に苗を配って、村人が苗を植える活動を支援し、NGOの人びとは、精製した砂糖を海外で販売する支援をしている。両者ともに、このような活動を通じて、村人の現金収入が増加すると同時に、それによって、彼らの森林への依存が減り、村の周りの森林破壊が食い止められることを願っている。村の人びとの現金獲得と、村を越えた地球環境保全とが、同時に実現できる新たな試みが始まっている。
サトウヤシ(学名:Arenga pinnata)
ジャワではアレン(Aren) またはカウン(Kawung)と呼ばれ、東南アジア全域に広く分布。低地から標高1,000mにかけての二次林や農地に自生している。樹高は10m以上で、幹の太さは50cm前後の雌雄同株の植物である。サトウヤシは多目的な利用植物である。根は、強壮剤や産後の薬の原料になる。葉柄は家の屋根葺き材として利用され、10年以上もの間、村人を雨風から守り続ける。葉はタバコとして、果実は食用として利用される。また、樹液は砂糖の原料として利用される以外に、取れたての樹液はジュースとして、木の幹に吊り下げられた容器の中で自然発酵した樹液は、ヤシ酒として飲まれる。
ジャワではアレン(Aren) またはカウン(Kawung)と呼ばれ、東南アジア全域に広く分布。低地から標高1,000mにかけての二次林や農地に自生している。樹高は10m以上で、幹の太さは50cm前後の雌雄同株の植物である。サトウヤシは多目的な利用植物である。根は、強壮剤や産後の薬の原料になる。葉柄は家の屋根葺き材として利用され、10年以上もの間、村人を雨風から守り続ける。葉はタバコとして、果実は食用として利用される。また、樹液は砂糖の原料として利用される以外に、取れたての樹液はジュースとして、木の幹に吊り下げられた容器の中で自然発酵した樹液は、ヤシ酒として飲まれる。
かわりゆく村、かわれない人……
トイは家にいなかった
ハノイから一四〇キロ西方にあるマイチャウに、染織物と少数民族観光で有名になった白タイの村がある。観光村の奥手にある高床式のトイの家を、一九九七年以来わたしは何度訪ねたろうか。トイはわたしの訪問を知ると、「おー、マサオ、元気か」と繰り返しながら、わたしの背丈ほどもある床上からはしごを下りてくる。バイクで急な峠道を越えてきたばかりのわたしは、黒い口ひげを蓄え、人なつっこい表情のトイをみると安堵する。
前回トイの家を訪ねてから、二年がたとうか。わたしが友人のヤスオ氏と着いたとき、はしごの上に姿を見せたのはトイではなく奥さんのニーであった。ニーはわれわれが落ち着くのを待って、正座を崩した姿勢でお茶をわれわれにすすめてくれる。ハノイやら日本やら、われわれが語る世間の話に彼女は静かな相づちをうつ。いっぽう、われわれは彼女の村や家族の変化を知る。中学生になる一人息子が勉強と学校が大好きで本ばかり読んでいて心配だと、ぜいたくにも思える悩みを吐露していた。自慢げでもないそのようすが印象的であった。
観光村の昼と夜
村を訪ねる観光客はふつう、おみやげの手織物を買ったり、ピクニックに行ったりして日中を忙しく過ごし、夜は夜で村が主催している民族舞踊を見て楽しむ。しかし、われわれはニーに夕飯でなにを食べたいかだけ告げると、あとは近所の人たちと会話を楽しむほか、布団と枕をかりてニーの家でゴロゴロしていた。
夕餉(ゆうげ)に、おこわと囲炉裏であぶった鶏肉を腹が苦しくなるほど食べると、われわれは散歩に出た。各家の窓辺からの光、舞踊の音楽や歌声が漏れている村から外に踏み出せば、田んぼには闇が垂れこめ、近くの明かりといえばホタルの明滅くらいである。語らいの声がどこからともなくきこえてくるのは、村の若者たちが橋の欄干(らんかん)やどこかしらで静寂を楽しんでいるからであろう。
村の中に戻ってくると、モチ米を発酵させた壺酒を売っている家の床下で酒を飲んでいる男たちの中にわれわれを呼び招くものがいる。見るとトイであった。酔っぱらっているらしい。つきあえば泥酔は必至だろうから、われわれは適当に笑ってやり過ごした。
トイはそんなに酒を飲む人だったっけ、とわれわれは首をかしげた。そういえば夕飯の支度の時にもトイはいなくて、ニーからは「遊びに行った」としかきかなかった。その晩、トイが帰ってきたのは遅かった。
トイの家は奥まっているので宿泊客は多くない。それでも外国人一人につき、宿泊費と食事代だけで一〇〇〇円くらいの収入が一晩で手に入る。しかも、ふつう織物もお土産に買っていくので、さらに数百円から数千円の収入が加わる。ニーに聞いたところ、一九九〇年代後半から観光客がたくさん来るようになって、野菜はほとんど買うようになったし、いまでは米も市場からある程度買うことができる。こうして焼き畑の労働から解放され、森林の不法伐採の必要もなくなったという。ニーの家にはすでにテレビとバイクもある。村の中には冷蔵庫までもっている家が一〇軒以上ある。
それでもハードなニーの一日
観光化は村に多大な現金収入をもたらした。しかし、女性の労働は楽になったのだろうか。ニーの一日はなかなかハードである。朝は早起きして家畜にえさをやり、たきぎ取りに行くか、田んぼに出て野良仕事をする。昼間は床下で販売用の綿織物も織り、そして売る。食事の支度は、トイや七四歳にもなるトイの母親も手伝ってくれるが、ひとつの囲炉裏で自分たちの食事と、それとは別メニューの観光客の食事を作るのは楽ではない。しかも夕飯が一段落したら、今度は民族衣装で着飾り、化粧もして民族舞踊への出演である。そのためには、つぎつぎ新しく作られる演目を日々の労働の合間に練習しておかなくてはならない。
トイが酒を飲んでたわむれを言っていたころ、ニーはまだ観光客のために踊っていた。しかし、「ニーは一日中働いているのに」と彼女に同情しトイの怠惰を憂えるのではなく、わたしには村の男たちの気持ちの変化が気になった。
機織りも舞踊も商いも、多くは女性の手による。つまり、観光収入を作り出しているのはほとんど女性である。しかも白タイの家族で財布の紐を握っているのもしばしば女性である。より自給的な生活をしていたときは、男女の労働時間の配分はもっと平等に近かったし、財布は女性でも権威は男性の側にあった。観光業で手にしたお金によって自給のための生産労働の負担が軽くなると、とくに男性の側の労働負担が減った。しかし同時に男性たちは権威も失ったかもしれない。
村では近年、風紀が乱れたという話を聞く。女性たちが観光客相手に売春に手を出してHIVが蔓延しているという話は眉唾だとしても、つれづれなるままにヘロインに手を出す男性が増えたとか、夫婦の不和やいさかいがたえないという噂には、さもありなんという気がする。酒を飲みながら手招きしていたトイの姿は、文化の担い手として、家族の柱として誇りを失った男の姿であったのだろうか。あれは一時の気晴らしであったのだと確信できる再会を、わたしは待ち望んでいる。
ハノイから一四〇キロ西方にあるマイチャウに、染織物と少数民族観光で有名になった白タイの村がある。観光村の奥手にある高床式のトイの家を、一九九七年以来わたしは何度訪ねたろうか。トイはわたしの訪問を知ると、「おー、マサオ、元気か」と繰り返しながら、わたしの背丈ほどもある床上からはしごを下りてくる。バイクで急な峠道を越えてきたばかりのわたしは、黒い口ひげを蓄え、人なつっこい表情のトイをみると安堵する。
前回トイの家を訪ねてから、二年がたとうか。わたしが友人のヤスオ氏と着いたとき、はしごの上に姿を見せたのはトイではなく奥さんのニーであった。ニーはわれわれが落ち着くのを待って、正座を崩した姿勢でお茶をわれわれにすすめてくれる。ハノイやら日本やら、われわれが語る世間の話に彼女は静かな相づちをうつ。いっぽう、われわれは彼女の村や家族の変化を知る。中学生になる一人息子が勉強と学校が大好きで本ばかり読んでいて心配だと、ぜいたくにも思える悩みを吐露していた。自慢げでもないそのようすが印象的であった。
観光村の昼と夜
村を訪ねる観光客はふつう、おみやげの手織物を買ったり、ピクニックに行ったりして日中を忙しく過ごし、夜は夜で村が主催している民族舞踊を見て楽しむ。しかし、われわれはニーに夕飯でなにを食べたいかだけ告げると、あとは近所の人たちと会話を楽しむほか、布団と枕をかりてニーの家でゴロゴロしていた。
夕餉(ゆうげ)に、おこわと囲炉裏であぶった鶏肉を腹が苦しくなるほど食べると、われわれは散歩に出た。各家の窓辺からの光、舞踊の音楽や歌声が漏れている村から外に踏み出せば、田んぼには闇が垂れこめ、近くの明かりといえばホタルの明滅くらいである。語らいの声がどこからともなくきこえてくるのは、村の若者たちが橋の欄干(らんかん)やどこかしらで静寂を楽しんでいるからであろう。
村の中に戻ってくると、モチ米を発酵させた壺酒を売っている家の床下で酒を飲んでいる男たちの中にわれわれを呼び招くものがいる。見るとトイであった。酔っぱらっているらしい。つきあえば泥酔は必至だろうから、われわれは適当に笑ってやり過ごした。
トイはそんなに酒を飲む人だったっけ、とわれわれは首をかしげた。そういえば夕飯の支度の時にもトイはいなくて、ニーからは「遊びに行った」としかきかなかった。その晩、トイが帰ってきたのは遅かった。
トイの家は奥まっているので宿泊客は多くない。それでも外国人一人につき、宿泊費と食事代だけで一〇〇〇円くらいの収入が一晩で手に入る。しかも、ふつう織物もお土産に買っていくので、さらに数百円から数千円の収入が加わる。ニーに聞いたところ、一九九〇年代後半から観光客がたくさん来るようになって、野菜はほとんど買うようになったし、いまでは米も市場からある程度買うことができる。こうして焼き畑の労働から解放され、森林の不法伐採の必要もなくなったという。ニーの家にはすでにテレビとバイクもある。村の中には冷蔵庫までもっている家が一〇軒以上ある。
それでもハードなニーの一日
観光化は村に多大な現金収入をもたらした。しかし、女性の労働は楽になったのだろうか。ニーの一日はなかなかハードである。朝は早起きして家畜にえさをやり、たきぎ取りに行くか、田んぼに出て野良仕事をする。昼間は床下で販売用の綿織物も織り、そして売る。食事の支度は、トイや七四歳にもなるトイの母親も手伝ってくれるが、ひとつの囲炉裏で自分たちの食事と、それとは別メニューの観光客の食事を作るのは楽ではない。しかも夕飯が一段落したら、今度は民族衣装で着飾り、化粧もして民族舞踊への出演である。そのためには、つぎつぎ新しく作られる演目を日々の労働の合間に練習しておかなくてはならない。
トイが酒を飲んでたわむれを言っていたころ、ニーはまだ観光客のために踊っていた。しかし、「ニーは一日中働いているのに」と彼女に同情しトイの怠惰を憂えるのではなく、わたしには村の男たちの気持ちの変化が気になった。
機織りも舞踊も商いも、多くは女性の手による。つまり、観光収入を作り出しているのはほとんど女性である。しかも白タイの家族で財布の紐を握っているのもしばしば女性である。より自給的な生活をしていたときは、男女の労働時間の配分はもっと平等に近かったし、財布は女性でも権威は男性の側にあった。観光業で手にしたお金によって自給のための生産労働の負担が軽くなると、とくに男性の側の労働負担が減った。しかし同時に男性たちは権威も失ったかもしれない。
村では近年、風紀が乱れたという話を聞く。女性たちが観光客相手に売春に手を出してHIVが蔓延しているという話は眉唾だとしても、つれづれなるままにヘロインに手を出す男性が増えたとか、夫婦の不和やいさかいがたえないという噂には、さもありなんという気がする。酒を飲みながら手招きしていたトイの姿は、文化の担い手として、家族の柱として誇りを失った男の姿であったのだろうか。あれは一時の気晴らしであったのだと確信できる再会を、わたしは待ち望んでいる。
「きのうよりワクワクしてきた。」
次号予告・編集後記
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。
本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。
本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。