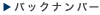月刊みんぱく 2006年2月号
2006年2月号
第30巻第2号通巻第341号
2006年2月1日発行
2006年2月1日発行
国家という名の「怪物」
加藤 九祚
アメリカは広島と長崎に原子爆弾を落としたでしょう。それなのに、どうして日本はアメリカとそんなに仲よくするのですか」
中央アジアの一国、タジキスタンの一学生から受けた質問である。私は言った。「世間の大人たちの関係、とりわけ国家間では『昨日の敵が今日の友』になるのはよくある話だよ」
これが質問の返事にならないことは自分でもよく承知している。しかし、このようにはぐらかすしか手はない。たしかに日本とアメリカの密着度は尋常ではないほどすすんでいるようだ。靖国神社参拝と憲法改変にたいする執着度は、この密着度に正比例しているように思うのは私だけだろうか。過去六〇年間の平和がこの上なく尊く思われる。
中国の反日デモがウズベキスタンのテレビに伝えられたとき、ある若者が言った。
「中国もつまらないことをするものだ。日本から援助をもらっているのだから、そんなことをしないで黙っていれは、もっともらえるのに」
うがったことを言うと思った。私は何もコメントできなかった。
人類史上、二〇世紀ほど新国家の誕生した時期はなかったのではないか。国家とは多くの場合「独立」と結びついている。そもそも、現代において「独立」は可能なのか。中央アジアでも一九九一年ソ連崩壊後、五つの独立国が誕生した。これらの国々でも、地下資源のある国とない国では、経済の格差が出ている。地上資源(水)があってもだめである。地下資源(石油、ガス)でなければ国の利益にならない。中央アジアの一国、トルクメニスタン(人口約五〇〇万)では地下資源が豊富で、電気、水道、ガス、塩は無料、ガソリンは一ドルで六〇リッター、ウォッカも自国産、外国産を問わず安い。ただしニヤゾフ大統領にたいする個人崇拝は群を抜いている。貨幣にも町にも彼の肖像があふれている。
各国とも愛国心の鼓吹はさかんである。人はみな「誰か故郷を思わざる」であると思うが、その上になお、「これでもか」の鼓吹である。
二一世紀もまた、国家という名の「怪物」が人びとの意識と生活を支配しつづけることであろう。
かとう きゅうぞう/国立民族学博物館名誉教授。1922年、韓国慶尚北道生まれ。上智大学文学部卒業。陸軍工兵少尉。戦後4年8カ月シベリア抑留。学術博士。1998年からウズベキスタンで仏教遺跡を発掘中。
中央アジアの一国、タジキスタンの一学生から受けた質問である。私は言った。「世間の大人たちの関係、とりわけ国家間では『昨日の敵が今日の友』になるのはよくある話だよ」
これが質問の返事にならないことは自分でもよく承知している。しかし、このようにはぐらかすしか手はない。たしかに日本とアメリカの密着度は尋常ではないほどすすんでいるようだ。靖国神社参拝と憲法改変にたいする執着度は、この密着度に正比例しているように思うのは私だけだろうか。過去六〇年間の平和がこの上なく尊く思われる。
中国の反日デモがウズベキスタンのテレビに伝えられたとき、ある若者が言った。
「中国もつまらないことをするものだ。日本から援助をもらっているのだから、そんなことをしないで黙っていれは、もっともらえるのに」
うがったことを言うと思った。私は何もコメントできなかった。
人類史上、二〇世紀ほど新国家の誕生した時期はなかったのではないか。国家とは多くの場合「独立」と結びついている。そもそも、現代において「独立」は可能なのか。中央アジアでも一九九一年ソ連崩壊後、五つの独立国が誕生した。これらの国々でも、地下資源のある国とない国では、経済の格差が出ている。地上資源(水)があってもだめである。地下資源(石油、ガス)でなければ国の利益にならない。中央アジアの一国、トルクメニスタン(人口約五〇〇万)では地下資源が豊富で、電気、水道、ガス、塩は無料、ガソリンは一ドルで六〇リッター、ウォッカも自国産、外国産を問わず安い。ただしニヤゾフ大統領にたいする個人崇拝は群を抜いている。貨幣にも町にも彼の肖像があふれている。
各国とも愛国心の鼓吹はさかんである。人はみな「誰か故郷を思わざる」であると思うが、その上になお、「これでもか」の鼓吹である。
二一世紀もまた、国家という名の「怪物」が人びとの意識と生活を支配しつづけることであろう。
かとう きゅうぞう/国立民族学博物館名誉教授。1922年、韓国慶尚北道生まれ。上智大学文学部卒業。陸軍工兵少尉。戦後4年8カ月シベリア抑留。学術博士。1998年からウズベキスタンで仏教遺跡を発掘中。
産む、産まない、産めない、
産ませる、産むかもしれない……。
医療が発達し、種の保存が多様化すると同時に
家族が核化し、個人の選択肢が増えた。
少子化といわれる時代に生殖の問題は、
個人個人、特に女性にふりかかっている。
共同体が築いてきた
「産む」をめぐる文化と、科学の進歩と、
個人・家族のかかわり方について考える。
産ませる、産むかもしれない……。
医療が発達し、種の保存が多様化すると同時に
家族が核化し、個人の選択肢が増えた。
少子化といわれる時代に生殖の問題は、
個人個人、特に女性にふりかかっている。
共同体が築いてきた
「産む」をめぐる文化と、科学の進歩と、
個人・家族のかかわり方について考える。
産むこと・生まれること
松岡 悦子
「あなたはどんなふうにこの世に生まれましたか」と聞かれても自分がどうやって生まれてきたかを思い出せる人はいないと思う(たぶん)。今生きている私たちはみんな、この世への境界を越えて生まれてきた。文化人類学(民族学)では、産むこと、生まれることを通過儀礼ととらえている。産む人は出産によって母の地位へと移行し、生まれる子どもはあの世の存在からこの世の存在へ、すなわち名もない存在から共同体の新たな仲間へと変身を遂げる。民俗学では、お産を介助するトリアゲバアサンが取りあげるのは、あの世からやってきた魂だとされていたし、北海道に住むアイヌのシャーマン兼産婆は、誕生と死の両方の場面によばれて、魂がこの世とあの世の境界を越えるのを見届けた。こんなふうに、どの文化でも出産は生と死の両方にまたがる危険なときとされて、出産前後にはいくつもの儀礼やタブーが用意され、共同体の人びとは力を合わせてこの変化のときを乗り切ろうとしてきた。
子どもがどうやって生まれるのかという民俗生殖観はさまざまだ。卵子と精子が受精して子どもができるという科学的な生殖観は、体外受精や顕微授精などの生殖技術を産み出した。ところが科学的知識が行き渡った社会ほど不妊の人が増え、そんな知識をもたない社会ほど簡単に子どもができるのは何とも奇妙なことだ、と南米アマゾンのヤノマミ族を研究する人類学者のガブリエルはいった。生殖の知識が子どもを作るわけではないのだ。
産むことには、生物学と文化の両方がかかわる。女性の体から赤ん坊が生まれるのは、今までのところ世界共通のことだが、その女性がどこで、どんな格好で、誰に介助され、どんな道具を用いて出産し、産後どんな過ごし方をするのかは文化によって異なる。たとえば先進国の多くで、いまマタニティーブルーや産後うつ病が話題になっているが、生理的には同じ出産のプロセスなのに、そんなことばがまったく存在しない社会もある。体は同じ生理的プロセスを経て赤ん坊を産み出しても、女性の出産の経験は文化的に形作られていることになる。
さて、目下の出産の話題のひとつは高い帝王切開率だ。少し前までアメリカの帝王切開率は四人に一人で高いといわれていた。でも今高さを誇っているのは、中国や韓国やベトナムなどの少し前まで途上国といわれた国々だ。韓国の農村部で四六・八パーセント、全国平均で三七・八パーセント(二〇〇〇年)、中国の南寧のふたつの病院ではいずれも約半分が帝王切開だった(二〇〇五年)。中国では、帝王切開の方が安全でよい分娩と考える女性が多いらしい。ヨーロッパでは、帝王切開は大切な性器を傷めない出産法として、セレブや女性産科医に選ばれている。
出産も子育ても、その文化のメンバーを再生産する営みだから、その文化に合った人間を作るのが目的だ。子育てにグローバルスタンダードなどあり得ない。子どもは親やまわりを見習って自然に一人前になるような社会なら、子育ての悩みは少ないだろう。でも私たちの社会では、育児は前人未踏の困難な仕事になっている。なぜそうなってしまうのかは謎だ。これまでどこにでも当たり前のようにあった水や空気が、今では貴重な資源になりつつあるように、これまで問題化されることのなかった、産むこと、生まれることや子どもを育てることが稀少価値になりつつあるのだろうか。
子どもがどうやって生まれるのかという民俗生殖観はさまざまだ。卵子と精子が受精して子どもができるという科学的な生殖観は、体外受精や顕微授精などの生殖技術を産み出した。ところが科学的知識が行き渡った社会ほど不妊の人が増え、そんな知識をもたない社会ほど簡単に子どもができるのは何とも奇妙なことだ、と南米アマゾンのヤノマミ族を研究する人類学者のガブリエルはいった。生殖の知識が子どもを作るわけではないのだ。
産むことには、生物学と文化の両方がかかわる。女性の体から赤ん坊が生まれるのは、今までのところ世界共通のことだが、その女性がどこで、どんな格好で、誰に介助され、どんな道具を用いて出産し、産後どんな過ごし方をするのかは文化によって異なる。たとえば先進国の多くで、いまマタニティーブルーや産後うつ病が話題になっているが、生理的には同じ出産のプロセスなのに、そんなことばがまったく存在しない社会もある。体は同じ生理的プロセスを経て赤ん坊を産み出しても、女性の出産の経験は文化的に形作られていることになる。
さて、目下の出産の話題のひとつは高い帝王切開率だ。少し前までアメリカの帝王切開率は四人に一人で高いといわれていた。でも今高さを誇っているのは、中国や韓国やベトナムなどの少し前まで途上国といわれた国々だ。韓国の農村部で四六・八パーセント、全国平均で三七・八パーセント(二〇〇〇年)、中国の南寧のふたつの病院ではいずれも約半分が帝王切開だった(二〇〇五年)。中国では、帝王切開の方が安全でよい分娩と考える女性が多いらしい。ヨーロッパでは、帝王切開は大切な性器を傷めない出産法として、セレブや女性産科医に選ばれている。
出産も子育ても、その文化のメンバーを再生産する営みだから、その文化に合った人間を作るのが目的だ。子育てにグローバルスタンダードなどあり得ない。子どもは親やまわりを見習って自然に一人前になるような社会なら、子育ての悩みは少ないだろう。でも私たちの社会では、育児は前人未踏の困難な仕事になっている。なぜそうなってしまうのかは謎だ。これまでどこにでも当たり前のようにあった水や空気が、今では貴重な資源になりつつあるように、これまで問題化されることのなかった、産むこと、生まれることや子どもを育てることが稀少価値になりつつあるのだろうか。
死と再生の物語 ── 現代に生きる禁忌と呪詛
中村 和恵
オーストラリア北端、アラフラ湿原に臨む中央アーネムランドの先住民コミュニティ・ラミンギンニンで、昨年一〇月、画家ピーター・ミングルルの話を聞いた。アート・センターの庇に飾られた彼の絵の下でピーターの解説を聞くのは、じつは二度目だ。四匹のウィティチとよばれる大ヘビの間に、双頭のヘビ形がふたつ平行に並ぶ絵。だが今回、以前はいわなかったことをピーターは語りだした。ヘビの間にあるのは、「あれはミルキィウェイなんだ」という。「天の川だから、魚が流れているんだ」。
ウィティチは、この地域の物語としてよく知られるワギラグ姉妹の話に登場する。水場にやってきた姉妹の一人が出産(月経とも)の血で水を汚し、怒ったヘビは彼女らを飲みこむ。その声は雷、舌は稲妻、そして雨が降る。ヘビは天から落ち、姉妹と子を吐き出し、また飲みこみ、水に戻っていく。飲みこみと吐き出し、雨の開始と停止、死と再生。再生する魂は、魚の姿をしているという。この世から離れていった魚/魂は捕まえられ、また放たれて、新しい生命が誕生する。
今や「現代」美術として世界的に評価されるアボリジナル・アートだが、ある種の絵の「内側」(深層)の意味は部外者に不用意に公開されるべきではないとされており、出版や展示の現場で問題化することも少なくない。「秘密」の多くは何らかの意味で、生殖活動を含む死と再生の事象にかかわっている。どうやらピーター・ミングルルの絵/物語の「内側」は相当に深遠である。私はやっとその一端を教えてもらったにすぎない。
多くの文化において「産む」ことは、数々の禁忌や呪詛と結びついている。古くからそうであり、じつは現在もそうである。最近の少子化をめぐる議論にも、論理的分析だけでは理解しきれない側面がある。産まない女、女しか産まない女を罵る日本のことばは、暗く恐ろしい。石女(うまずめ)、女腹(おんなばら)、地獄腹。その一方で、多胎や多産の女を貶(けな)す畜生腹という語もある。
産まない女、許されぬ出産を描いた物語なら、世界中、枚挙に暇がない。典型的なのはスペインのフェデリコ・ガルシア・ロルカの戯曲『イエルマ』だろうか。子どもを望まない、おそらくつくれない夫に対し、子どもがほしくて気も狂いそうな、でもほかの男と逃げることはできない、因習に縛られた女。南アフリカのロレッタ・ゴッボの小説『でも彼らは死ななかった』(邦訳題『女たちの絆』)は、もっと具体的かつ政治的である。アパルトヘイト政策下で夫と一年に一度しか会えず、子どもができなくて姑にいびられる妻。やっとできても待っているのは貧困と迫害、さらに白人による強姦と混血児の出産、村八分だ。映画『クジラの島の少女』の原作であるニュージーランドのマオリ作家ウィティ・イヒマエラの小説では、双子の出産に際し、男の子のほうが死んでしまい、女の子が生き残る。祖父であるマオリの首長は嘆き悲しむ。女では後継者になれないからだ。逆の例もある。双子を忌避する北オーストラリア・ティウイ島の人びとは、男女の双子なら女を残すという。
現代日本ではこうした「迷信」は薄れているように見える。能力の高低や障害の有無、また性別を問わず、生まれた子どもは尊重されるべきであるし、生殖行為が暴力や強制によってなされても妨げられてもいけない、結婚や出産経験の有無を問わず女性の人権は守られなくてはならない――こうした原則に多くの方は賛同されるだろう。ただ、どうやらあくまで原則としてである。人間という生き物は、じつはかなり非合理的だ。「産む」をめぐる禁忌と呪詛がまったく消失するほどに合理的な社会というのは、おそらくない。死と再生の謎は、いかに科学が進歩しても、いや進歩するにつれ、むしろ深まっている。
不妊治療の最先端では、精子や卵子、幹細胞をも操り、クローン技術による人間誕生を規制する法律が論じられている。同時に、記憶の彼方から続く死と再生の謎への畏怖も、私たちのなかにまちがいなく生きている。産むという行為の現場には、最新医療技術、個人の希望や家族の理想、それらすべてを可能にも不可能にもするかにみえる経済の力、さらに神話と宗教までが、混沌と渦を巻いている。これは科学的理性だけで解き明かせる領域ではない――「物語」は深く長く、私たちに影響を及ぼしつづけている。
ウィティチは、この地域の物語としてよく知られるワギラグ姉妹の話に登場する。水場にやってきた姉妹の一人が出産(月経とも)の血で水を汚し、怒ったヘビは彼女らを飲みこむ。その声は雷、舌は稲妻、そして雨が降る。ヘビは天から落ち、姉妹と子を吐き出し、また飲みこみ、水に戻っていく。飲みこみと吐き出し、雨の開始と停止、死と再生。再生する魂は、魚の姿をしているという。この世から離れていった魚/魂は捕まえられ、また放たれて、新しい生命が誕生する。
今や「現代」美術として世界的に評価されるアボリジナル・アートだが、ある種の絵の「内側」(深層)の意味は部外者に不用意に公開されるべきではないとされており、出版や展示の現場で問題化することも少なくない。「秘密」の多くは何らかの意味で、生殖活動を含む死と再生の事象にかかわっている。どうやらピーター・ミングルルの絵/物語の「内側」は相当に深遠である。私はやっとその一端を教えてもらったにすぎない。
多くの文化において「産む」ことは、数々の禁忌や呪詛と結びついている。古くからそうであり、じつは現在もそうである。最近の少子化をめぐる議論にも、論理的分析だけでは理解しきれない側面がある。産まない女、女しか産まない女を罵る日本のことばは、暗く恐ろしい。石女(うまずめ)、女腹(おんなばら)、地獄腹。その一方で、多胎や多産の女を貶(けな)す畜生腹という語もある。
産まない女、許されぬ出産を描いた物語なら、世界中、枚挙に暇がない。典型的なのはスペインのフェデリコ・ガルシア・ロルカの戯曲『イエルマ』だろうか。子どもを望まない、おそらくつくれない夫に対し、子どもがほしくて気も狂いそうな、でもほかの男と逃げることはできない、因習に縛られた女。南アフリカのロレッタ・ゴッボの小説『でも彼らは死ななかった』(邦訳題『女たちの絆』)は、もっと具体的かつ政治的である。アパルトヘイト政策下で夫と一年に一度しか会えず、子どもができなくて姑にいびられる妻。やっとできても待っているのは貧困と迫害、さらに白人による強姦と混血児の出産、村八分だ。映画『クジラの島の少女』の原作であるニュージーランドのマオリ作家ウィティ・イヒマエラの小説では、双子の出産に際し、男の子のほうが死んでしまい、女の子が生き残る。祖父であるマオリの首長は嘆き悲しむ。女では後継者になれないからだ。逆の例もある。双子を忌避する北オーストラリア・ティウイ島の人びとは、男女の双子なら女を残すという。
現代日本ではこうした「迷信」は薄れているように見える。能力の高低や障害の有無、また性別を問わず、生まれた子どもは尊重されるべきであるし、生殖行為が暴力や強制によってなされても妨げられてもいけない、結婚や出産経験の有無を問わず女性の人権は守られなくてはならない――こうした原則に多くの方は賛同されるだろう。ただ、どうやらあくまで原則としてである。人間という生き物は、じつはかなり非合理的だ。「産む」をめぐる禁忌と呪詛がまったく消失するほどに合理的な社会というのは、おそらくない。死と再生の謎は、いかに科学が進歩しても、いや進歩するにつれ、むしろ深まっている。
不妊治療の最先端では、精子や卵子、幹細胞をも操り、クローン技術による人間誕生を規制する法律が論じられている。同時に、記憶の彼方から続く死と再生の謎への畏怖も、私たちのなかにまちがいなく生きている。産むという行為の現場には、最新医療技術、個人の希望や家族の理想、それらすべてを可能にも不可能にもするかにみえる経済の力、さらに神話と宗教までが、混沌と渦を巻いている。これは科学的理性だけで解き明かせる領域ではない――「物語」は深く長く、私たちに影響を及ぼしつづけている。
胎児・胚・卵をめぐる科学に文化の知を
齋藤 有紀子
「子どもの胞衣(えな)、入手いたしました。このすばらしい自然の産物が、それを所持して陸海を旅する人びとを一切の災難事故から守ってくれる驚くべき効果については、すでに多くの人びとが体験ずみで、世界中から絶賛されております」(一八二〇年三月九日タイムズ広告、中沢新一『精霊の王』より)
一九世紀のイギリスでは、胞衣(胎盤や羊膜。ここではおそらく胎盤)を、頭にかぶって生まれた子どもは特別な力をもつとされ、その胞衣は水難除けの魔力があると、船乗りに珍重されたらしい。そのような胞衣は、先のような広告とともに、社会に売りに出されたという。
もちろんヨーロッパだけでなく、日本にも、胞衣をめぐる言い伝えや風習は多くある。生命の誕生と、その附属物・副産物に、私たちの社会は、さまざまな意味や価値や用途を見いだし、畏怖や敬意を抱きながら、歴史をつづってきた。しかし今、そのような文脈と接点をもたないまま、新しい医療技術が、ヒトの胎盤や生殖細胞、中絶後の胎児に実用的価値を見いだし、リサイクルを試みはじめている。
からだのあらゆる組織から取り出すことのできる幹細胞(ステムセル)が、また新しくからだの組織や臓器を形づくる能力をもつことが、近年明らかにされてきた。ステムセルを、目的の臓器に分化・誘導することができれば、病気や事故で失った機能を取り戻したり、脳死判定や拒絶反応に悩む移植医療から解放される日が来るかもしれない。今、パーキンソン病、脊椎損傷、慢性心臓病など、さまざまな患者の期待を背負って、幹細胞研究(一般に再生医療ともよばれる)が進んでいる。
「人助け」の材料となるのは、胚(不妊治療のカップルが凍結保存し、のちに廃棄を決断したもの)や、中絶胎児、卵子や卵巣(不妊治療や婦人科手術で摘出され、廃棄予定のもの)など。これらを提供・入手するために必要なのは「新聞広告」ではなく、提供者による同意(インフォームド・コンセント)であり、細胞は売りに出されるのでなく、無償提供だ。
日本では今、胚を使用する「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」(二〇〇一年)のみ規定が存在する。他は関連省庁が、現在も指針を策定中だ。議論の過程で完全に抜け落ちているのが、日本の民俗学・文化人類学的視点である。これをこのまま看過していいのか、筆者はとても危惧している。
私たちの社会が、これまで、胎児、胞衣、堕胎、不妊にどのように向き合い、どのような意味を与えてきたのか。また、細胞の提供者も、受けとる人も、双方が患者として医療の対象であることを思うとき、ここでは病気観、身体観も問われることになるだろう。個人と社会の意識の深層に有形無形に影響を及ぼすこれらへの検証なくして、日本の「幹細胞研究」のあり方を見極めるのは、難しいのではないだろうか。
提供者・患者と科学を真にとり結ぶ日本の制度づくりのために、「産み」や「病い」の周辺の伝承に耳を傾けてきた学問の「知」が求められていると思う。
一九世紀のイギリスでは、胞衣(胎盤や羊膜。ここではおそらく胎盤)を、頭にかぶって生まれた子どもは特別な力をもつとされ、その胞衣は水難除けの魔力があると、船乗りに珍重されたらしい。そのような胞衣は、先のような広告とともに、社会に売りに出されたという。
もちろんヨーロッパだけでなく、日本にも、胞衣をめぐる言い伝えや風習は多くある。生命の誕生と、その附属物・副産物に、私たちの社会は、さまざまな意味や価値や用途を見いだし、畏怖や敬意を抱きながら、歴史をつづってきた。しかし今、そのような文脈と接点をもたないまま、新しい医療技術が、ヒトの胎盤や生殖細胞、中絶後の胎児に実用的価値を見いだし、リサイクルを試みはじめている。
からだのあらゆる組織から取り出すことのできる幹細胞(ステムセル)が、また新しくからだの組織や臓器を形づくる能力をもつことが、近年明らかにされてきた。ステムセルを、目的の臓器に分化・誘導することができれば、病気や事故で失った機能を取り戻したり、脳死判定や拒絶反応に悩む移植医療から解放される日が来るかもしれない。今、パーキンソン病、脊椎損傷、慢性心臓病など、さまざまな患者の期待を背負って、幹細胞研究(一般に再生医療ともよばれる)が進んでいる。
「人助け」の材料となるのは、胚(不妊治療のカップルが凍結保存し、のちに廃棄を決断したもの)や、中絶胎児、卵子や卵巣(不妊治療や婦人科手術で摘出され、廃棄予定のもの)など。これらを提供・入手するために必要なのは「新聞広告」ではなく、提供者による同意(インフォームド・コンセント)であり、細胞は売りに出されるのでなく、無償提供だ。
日本では今、胚を使用する「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」(二〇〇一年)のみ規定が存在する。他は関連省庁が、現在も指針を策定中だ。議論の過程で完全に抜け落ちているのが、日本の民俗学・文化人類学的視点である。これをこのまま看過していいのか、筆者はとても危惧している。
私たちの社会が、これまで、胎児、胞衣、堕胎、不妊にどのように向き合い、どのような意味を与えてきたのか。また、細胞の提供者も、受けとる人も、双方が患者として医療の対象であることを思うとき、ここでは病気観、身体観も問われることになるだろう。個人と社会の意識の深層に有形無形に影響を及ぼすこれらへの検証なくして、日本の「幹細胞研究」のあり方を見極めるのは、難しいのではないだろうか。
提供者・患者と科学を真にとり結ぶ日本の制度づくりのために、「産み」や「病い」の周辺の伝承に耳を傾けてきた学問の「知」が求められていると思う。
特集 産む フィールドから
ファティマのお産──モロッコ・ベルベル人の村より
井家 晴子
村の無料診療所の看護師がいった臨月から二週間過ぎても、ファティマに出産のきざしは見られなかった。ファティマは長びく妊娠にそれほど恐れる様子はない。そして、今回の妊娠期間や腰痛の感じ方が今までの四人の娘たちとは違うことを私に告げ、無事に生まれればどちらだっていいけれど、男の子なのかもしれないとうれしそうにいった。
村の女性たちは、ファティマのなかなか生まれない子どもが、じつはアムグーン(胎児が妊娠初期に胎内で成長を止めて眠るという信仰)になっていたのではないかと噂をしはじめた。そして三週目も過ぎ、みんなが忘れたころ、ファティマは出産したのである。
お産の場には、どこからか噂を聞きつけた女たちが集まってきた。彼女たちはお茶を飲み、自分たちの体験や見聞きした出産の話題に花を咲かせながら陣痛に苦しむファティマを励まし、伝統的出産介助者ウッダにあれこれアドバイスをする。ファティマは、にぎわう女たちに自分が今必要としているのは笑いではないと怒り、女たちはそんなファティマをおもしろがった。
ファティマは、いきみはじめてから半時間ほどで出産した。女たちは、赤ん坊の性別を知ろうとファティマの足元に集まった。「女でも男でもどちらでもいいじゃないの」。ウッダは、のぞきこんだ女たちを制して言った。だれも今見た赤ん坊の性別を言おうとはしない。ファティマの目に涙があふれる。女たちは、今度は女児のよさ、男児のつまらなさについて話をにぎわせはじめた。
出産を外で待っていた夫が部屋に入ってきた。女たちは口々に祝福のことばを贈る。夫は生まれた子を抱き上げた。「この子は五人いる私の娘のなかでいちばん美しいじゃないか」
夫が出て行った後、ファティマはため息をつき、母が用意した、魔術(イムクラール*)を解くクドゥラーンとよばれる黒い液と草刈鎌を眺めていた。「まだ産むつもりなのか」「女でも男でもどっちでもいいじゃないか」「私には男の子ばかりしか生まれなくて女の子が欲しいのに」という女たちの非難のなか、ファティマは鎌の先に黒い液をつけてなめた。「神がこの出産を望んだのなら、感謝する。だけど、誰かが私にイムクラールをかけたのなら、神は絶対にその人を許さないでしょうよ」と言って。
村の女性たちは、ファティマのなかなか生まれない子どもが、じつはアムグーン(胎児が妊娠初期に胎内で成長を止めて眠るという信仰)になっていたのではないかと噂をしはじめた。そして三週目も過ぎ、みんなが忘れたころ、ファティマは出産したのである。
お産の場には、どこからか噂を聞きつけた女たちが集まってきた。彼女たちはお茶を飲み、自分たちの体験や見聞きした出産の話題に花を咲かせながら陣痛に苦しむファティマを励まし、伝統的出産介助者ウッダにあれこれアドバイスをする。ファティマは、にぎわう女たちに自分が今必要としているのは笑いではないと怒り、女たちはそんなファティマをおもしろがった。
ファティマは、いきみはじめてから半時間ほどで出産した。女たちは、赤ん坊の性別を知ろうとファティマの足元に集まった。「女でも男でもどちらでもいいじゃないの」。ウッダは、のぞきこんだ女たちを制して言った。だれも今見た赤ん坊の性別を言おうとはしない。ファティマの目に涙があふれる。女たちは、今度は女児のよさ、男児のつまらなさについて話をにぎわせはじめた。
出産を外で待っていた夫が部屋に入ってきた。女たちは口々に祝福のことばを贈る。夫は生まれた子を抱き上げた。「この子は五人いる私の娘のなかでいちばん美しいじゃないか」
夫が出て行った後、ファティマはため息をつき、母が用意した、魔術(イムクラール*)を解くクドゥラーンとよばれる黒い液と草刈鎌を眺めていた。「まだ産むつもりなのか」「女でも男でもどっちでもいいじゃないか」「私には男の子ばかりしか生まれなくて女の子が欲しいのに」という女たちの非難のなか、ファティマは鎌の先に黒い液をつけてなめた。「神がこの出産を望んだのなら、感謝する。だけど、誰かが私にイムクラールをかけたのなら、神は絶対にその人を許さないでしょうよ」と言って。
* 人びとの日常生活から「魔術(イムクラール)」は切り離せない。イムクラールとは単なる魔術「スフル」だけでなく、妬みを含んだ魔術全般を指している。何かよくないことが起こると、人びとは誰かに妬まれ魔術をかけられたためだと考え、イムクラールを解くためにさまざまな方法を試みる。ファティマに関しては、結婚できない女性、あるいは子どものいない女性やそういった女性の母親から妬みをかい、女ばかり産むイムクラールをかけられたと考えていた。
「他の人を娶ってください」──インド農村部の複婚
松尾 瑞穂
「私が両親と相談して決めたのよ、妹と夫を結婚させようってね」
結婚して一五年たっても子どもができなかったラタさんは、一〇歳以上年の離れた末の妹を夫に嫁がせて、今は三人で暮らしている。体外受精を含む生殖医療技術があるとはいえ、いまだ都市の富裕層に限られており、普通の人びとにはとても手が届かない。かつては父系親族内での養子縁組もみられたが、家族計画の普及で子どもはみんな一人か二人。そもそも養子にもらえるような子どもがいないのだ。
そんな夫婦にとっての解決法は、夫がもう一人、妻を娶(めと)ること。一夫一妻が決まりで、結婚が聖なるものとされるヒンドゥー社会では、法律でも複婚は禁止されている。しかし、子どもができない夫婦に対しては、公ではないにしても「仕方がない」と共同体でゆるやかに認められている。二人目、三人目の妻であっても「結婚」といい、決して俗にいうお妾さん、というわけでもない。通常は子どもができないことにしびれを切らした夫側が、ほかの女性を連れてくることが多い。結婚が聖なるものである以上、妻としては離婚だけは何としても避けたいし、そのためならば夫に「他の人を娶ってください」と自らもちかけることもある。子どもができないことは「女性の責任」だとして、夫も姑もそれを当然と受け止め、自分から言い出さない妻に周囲の女性たちは「あんたも強情ねえ、旦那に結婚させなさいよ」と口出しをする。それで体調を崩し、痩せていく女性たちに私は何人も会った。
しかし当の女性たちも意外としたたかである。既に六〇歳を超えているマランさんは、以前、出身村から知的障害のある女性を連れてきて夫に娶らせたことがある。このような場合は、子どもができた後妻に追い出される心配はなく、自分が第一妻として君臨することができる。しかし、長い目でみると、このような婚姻形態は持続的な「家族」を形成するものではなさそうである。多くの場合は、どちらか一方が婚家を去っていったり、別居したりして、最終的には一夫一妻に落ち着くようだ。このあたりが、必要に迫られて場当たり的におこなわれているヒンドゥー社会の複婚の不安定さを示しているのだろう。
ラタさんの妹は妊娠した。「子どもは私たちのもの。これからは私が二人を守る」と、妹の競争相手ではなく保護者としてふるまうことを選んだラタさんの「家族」がどのような軌跡をたどるのか、見守りたい。
結婚して一五年たっても子どもができなかったラタさんは、一〇歳以上年の離れた末の妹を夫に嫁がせて、今は三人で暮らしている。体外受精を含む生殖医療技術があるとはいえ、いまだ都市の富裕層に限られており、普通の人びとにはとても手が届かない。かつては父系親族内での養子縁組もみられたが、家族計画の普及で子どもはみんな一人か二人。そもそも養子にもらえるような子どもがいないのだ。
そんな夫婦にとっての解決法は、夫がもう一人、妻を娶(めと)ること。一夫一妻が決まりで、結婚が聖なるものとされるヒンドゥー社会では、法律でも複婚は禁止されている。しかし、子どもができない夫婦に対しては、公ではないにしても「仕方がない」と共同体でゆるやかに認められている。二人目、三人目の妻であっても「結婚」といい、決して俗にいうお妾さん、というわけでもない。通常は子どもができないことにしびれを切らした夫側が、ほかの女性を連れてくることが多い。結婚が聖なるものである以上、妻としては離婚だけは何としても避けたいし、そのためならば夫に「他の人を娶ってください」と自らもちかけることもある。子どもができないことは「女性の責任」だとして、夫も姑もそれを当然と受け止め、自分から言い出さない妻に周囲の女性たちは「あんたも強情ねえ、旦那に結婚させなさいよ」と口出しをする。それで体調を崩し、痩せていく女性たちに私は何人も会った。
しかし当の女性たちも意外としたたかである。既に六〇歳を超えているマランさんは、以前、出身村から知的障害のある女性を連れてきて夫に娶らせたことがある。このような場合は、子どもができた後妻に追い出される心配はなく、自分が第一妻として君臨することができる。しかし、長い目でみると、このような婚姻形態は持続的な「家族」を形成するものではなさそうである。多くの場合は、どちらか一方が婚家を去っていったり、別居したりして、最終的には一夫一妻に落ち着くようだ。このあたりが、必要に迫られて場当たり的におこなわれているヒンドゥー社会の複婚の不安定さを示しているのだろう。
ラタさんの妹は妊娠した。「子どもは私たちのもの。これからは私が二人を守る」と、妹の競争相手ではなく保護者としてふるまうことを選んだラタさんの「家族」がどのような軌跡をたどるのか、見守りたい。
立ち入れなかった世界──ビルマの農村
若いころの「失敗」である。
ビルマ(現ミャンマー)の農村でフィールドワークをおこなっていたある朝、起きて向かいの家を見ると、高床式家屋の床下のところに、竹を編んだものが張りめぐらされており、村の産婆がなかに入っているという。産婦の夫は、いささか所在なげに、落ち着きなく家まわりの仕事をしていた。そうこうするうちに、近所の男性が私のもとに駆け寄ってきて時計をもった私に今の時刻を尋ね、答えるとまた飛ぶように引き返していった。
ビルマでは子どもが誕生すると出生票ともいうべきものが作られる。ヤシの葉を乾燥したものに、名前や生まれた年月日、何時何分何秒かまでが刻んで記されてあり、人生の節目の大切な儀式を受けるときなど、それをもとにもっとも吉兆の時が占われる。
時刻を尋ねた件(くだん)の男が、私に「(なかに入って)見るか」といってくれたのに、私は「いや」と答えてしまった。思い返すに調査の貴重な機会を逃したようで残念である。そのとき、ビルマでは出産が不浄なものとされ、関わると男性の生来もつ徳を減らすことになるといわれていることが頭に浮かんだのは事実である。だが、それ以上に、どのような態度で生命の誕生という事態に臨めばよいか、三〇代前半の私にはわからなかった。あれから四半世紀たち、私は年をとった。しかし、今同じ状況になったとしても、どのような態度がとれるであろうか。私には自信がない。
ビルマ(現ミャンマー)の農村でフィールドワークをおこなっていたある朝、起きて向かいの家を見ると、高床式家屋の床下のところに、竹を編んだものが張りめぐらされており、村の産婆がなかに入っているという。産婦の夫は、いささか所在なげに、落ち着きなく家まわりの仕事をしていた。そうこうするうちに、近所の男性が私のもとに駆け寄ってきて時計をもった私に今の時刻を尋ね、答えるとまた飛ぶように引き返していった。
ビルマでは子どもが誕生すると出生票ともいうべきものが作られる。ヤシの葉を乾燥したものに、名前や生まれた年月日、何時何分何秒かまでが刻んで記されてあり、人生の節目の大切な儀式を受けるときなど、それをもとにもっとも吉兆の時が占われる。
時刻を尋ねた件(くだん)の男が、私に「(なかに入って)見るか」といってくれたのに、私は「いや」と答えてしまった。思い返すに調査の貴重な機会を逃したようで残念である。そのとき、ビルマでは出産が不浄なものとされ、関わると男性の生来もつ徳を減らすことになるといわれていることが頭に浮かんだのは事実である。だが、それ以上に、どのような態度で生命の誕生という事態に臨めばよいか、三〇代前半の私にはわからなかった。あれから四半世紀たち、私は年をとった。しかし、今同じ状況になったとしても、どのような態度がとれるであろうか。私には自信がない。
特集 産む お産を見守る人びと
家族にやさしいお産
北島 博之
日本の歴史上初めて医療施設分娩がほとんどを占めるようになってから四〇年が経った。今三〇歳台の母親たちを生んだ女性たちは、この大きな変化を体験した最初の世代である。医師と見知らぬ助産師による分娩台を用いたお産で、完全母子異室制であった。
最近、職場で助産所のような分娩を試み始め、懇意にしている看護師の第二子、第三子のお産に立ち会うことができた。第二子のときは家族皆が見守るなか、産婦の母がひときわ真剣にお産を見つめていた。じつは産婦の母はかつて第一子の妊娠・出産を喜ばず、このお産の立ち会いも拒否していたが、夫妻の説得でやっと参加したのであった。結果、産婦の母は生まれた第二子をかわいがり、子育てが楽になったという。第三子のときには、最初から笑顔で立ち会ってくれ、夫や上の子どもたちとともに気持ちのよいお産ができた。その後、これまで一五年以上つきあってきた彼女が、自分の母とうまくゆかなかった少女時代を、初めて話してくれた。
成育医療センター研究では、初産の母子で児が一歳半の心理検査中にビデオ撮影し、動物行動学的に解析した。助産院・BHF(赤ちゃんに優しい病院)と一般産科病院・市民病院・総合周産期センターといった分娩施設別に、母子関係を探るためであった。入室時の児の啼泣の少なさ・児の発話総量・母の共鳴や共感の行動から、ほかの施設に比べて助産院とBHF産科病院は双方ともに安定度が高いことがわかった。これは母子支援(出生時の長い早期接触・家族立ち会い・既知の助産師・母子同室)にその多くが起因すると思われた。
正常なお産において、医療者は安全なお産を目指すとともに、人生で初めての大きな試練を乗り越えようとする母親を見守る親代わりの人であってほしいと思う。
最近、職場で助産所のような分娩を試み始め、懇意にしている看護師の第二子、第三子のお産に立ち会うことができた。第二子のときは家族皆が見守るなか、産婦の母がひときわ真剣にお産を見つめていた。じつは産婦の母はかつて第一子の妊娠・出産を喜ばず、このお産の立ち会いも拒否していたが、夫妻の説得でやっと参加したのであった。結果、産婦の母は生まれた第二子をかわいがり、子育てが楽になったという。第三子のときには、最初から笑顔で立ち会ってくれ、夫や上の子どもたちとともに気持ちのよいお産ができた。その後、これまで一五年以上つきあってきた彼女が、自分の母とうまくゆかなかった少女時代を、初めて話してくれた。
成育医療センター研究では、初産の母子で児が一歳半の心理検査中にビデオ撮影し、動物行動学的に解析した。助産院・BHF(赤ちゃんに優しい病院)と一般産科病院・市民病院・総合周産期センターといった分娩施設別に、母子関係を探るためであった。入室時の児の啼泣の少なさ・児の発話総量・母の共鳴や共感の行動から、ほかの施設に比べて助産院とBHF産科病院は双方ともに安定度が高いことがわかった。これは母子支援(出生時の長い早期接触・家族立ち会い・既知の助産師・母子同室)にその多くが起因すると思われた。
正常なお産において、医療者は安全なお産を目指すとともに、人生で初めての大きな試練を乗り越えようとする母親を見守る親代わりの人であってほしいと思う。
助産師の出番を
日隈 ふみ子
医療化されすぎた出産への反動からか、助産院出産や自宅出産への関心も高まっている。と同時に、病院では、産科医師不足の理由で、助産師を活用することなく産科病棟の閉鎖現象が起きている。このようなニーズ、ギャップを埋めるべく助産師の活躍が期待されるのだが、妊娠出産ケアを医師の指示なく実践できる独立開業権が与えられているにもかかわらず、助産師が十分に活用されていないという現状がある。その理由と打開策を考えてみたい。
まず原因のひとつは教育にある。看護学教育の上に一年間あった助産学教育は、大学化にともない、選択制が主流となりつつあり、十分な教育とはいえない。また、病院の助産師は、看護師と同じユニフォームで三交代制の勤務形態である。外来では妊婦健診を医師が担当し、出産の現場では、陣痛中の持続モニター管理や点滴、会陰切開など医療介入の多いなか、助産師は医師の主導のもとで出産介助をおこなう。助産師に自立した役割が任されていないのである。助産師として妊娠期から関われてこそ、その意識も能力も養われるが、これでは力が育ちもせず、発揮もできずに助産師は産科看護師と化している。
一方、開業助産師は、妊娠中から出産、母乳育児まで継続的なケアを提供し、出産中は女性をそばで温かく見守り、家族とともに出産できる環境のなかでケアを実施していている。このような出産を体験した女性は、自分で産んだという大きな自信と満足を得ている。ただ、このようなケアを受けられる女性は全出産者のわずか二パーセント弱でしかない。若手の助産師も開業しつつあるが、開業助産師の高齢化も進んでいる。
現状打開のために、一部ではあるが、開業助産師の指導のもとで病院内に助産師主導の妊娠出産ケアシステムが作られ、一昨年より、自立した助産活動ができる助産学の専門職大学院もできた。
よいケアを受けた女性たちがもっと助産師の出番をと求めている。助産学教育のさらなる充実、病院と地域助産師の連携、潜在助産師の再教育などが望まれる。そして、助産師主導の出産ケアシステムの拡大を図ることは、女性にとっても、助産師にとっても、不足している産科医にとっても急務である。
まず原因のひとつは教育にある。看護学教育の上に一年間あった助産学教育は、大学化にともない、選択制が主流となりつつあり、十分な教育とはいえない。また、病院の助産師は、看護師と同じユニフォームで三交代制の勤務形態である。外来では妊婦健診を医師が担当し、出産の現場では、陣痛中の持続モニター管理や点滴、会陰切開など医療介入の多いなか、助産師は医師の主導のもとで出産介助をおこなう。助産師に自立した役割が任されていないのである。助産師として妊娠期から関われてこそ、その意識も能力も養われるが、これでは力が育ちもせず、発揮もできずに助産師は産科看護師と化している。
一方、開業助産師は、妊娠中から出産、母乳育児まで継続的なケアを提供し、出産中は女性をそばで温かく見守り、家族とともに出産できる環境のなかでケアを実施していている。このような出産を体験した女性は、自分で産んだという大きな自信と満足を得ている。ただ、このようなケアを受けられる女性は全出産者のわずか二パーセント弱でしかない。若手の助産師も開業しつつあるが、開業助産師の高齢化も進んでいる。
現状打開のために、一部ではあるが、開業助産師の指導のもとで病院内に助産師主導の妊娠出産ケアシステムが作られ、一昨年より、自立した助産活動ができる助産学の専門職大学院もできた。
よいケアを受けた女性たちがもっと助産師の出番をと求めている。助産学教育のさらなる充実、病院と地域助産師の連携、潜在助産師の再教育などが望まれる。そして、助産師主導の出産ケアシステムの拡大を図ることは、女性にとっても、助産師にとっても、不足している産科医にとっても急務である。
女の戦いからイベントへ
宮崎 亮一郎
古事記には、伊邪那美命(いざなみのみこと)が火の神を出産するときに炎によって外陰部が焼かれてしまい、それがもとで死んでしまうという記述がある。この炎を出血と読み替えることはできないであろうか。出産後の出血は見たものでなければわからないほど激しく、まるで炎のような勢いで出てくる。
男は戦で生死を分けて戦うが、女は出産を、生死を分ける一生の仕事としていた。一九〇〇年の日本の妊産婦死亡率は、人口一〇万に対して四三六・五人、現在の六~七人とは比較にならないほど高い死亡率であった。産婆を中心とした自宅、あるいは特別に設けられた出産場所では、まさに生死を分ける女の戦いが繰り広げられていた。そこには男が入る余地などなかった。
妊産婦死亡率が劇的に低下したのは一九七〇年台以降、出産場所を自宅から施設(診療所・病院など)で出産するようになってからのことであり、今からたかだか三〇年ほど前にすぎない。比較的安全に出産ができるようになり、新生児死亡率も低下しため、出産回数も少なくなり、無事に出産するのが当たりまえになっていった。
安全性が確保されると、いつのまにか女の一生の仕事というよりイベント的感覚で捉えられるようになった。出産を快適で充実したものにしたい。そう願う妊婦の選択肢のひとつとして注目されるのが自宅分娩であろう。施設での出産に莫大な費用がかかる諸外国では、出産場所は自宅・助産所しかない。あるいは自宅分娩では妊産婦死亡率が低下しない一部の先進国では、施設分娩へと誘導するために、快適性を重視した分娩へ移行させようとした状況がある。こういった状況が知らされないまま、一部の女性の経験談が集団を動かし、人はそれに共感する。しかし、年齢、健康状態、家庭の環境など、人それぞれ条件が異なるといったことを十分に考えているのだろうか。あの人ができるなら私にもといったイメージが強いのでは……。
男は戦で生死を分けて戦うが、女は出産を、生死を分ける一生の仕事としていた。一九〇〇年の日本の妊産婦死亡率は、人口一〇万に対して四三六・五人、現在の六~七人とは比較にならないほど高い死亡率であった。産婆を中心とした自宅、あるいは特別に設けられた出産場所では、まさに生死を分ける女の戦いが繰り広げられていた。そこには男が入る余地などなかった。
妊産婦死亡率が劇的に低下したのは一九七〇年台以降、出産場所を自宅から施設(診療所・病院など)で出産するようになってからのことであり、今からたかだか三〇年ほど前にすぎない。比較的安全に出産ができるようになり、新生児死亡率も低下しため、出産回数も少なくなり、無事に出産するのが当たりまえになっていった。
安全性が確保されると、いつのまにか女の一生の仕事というよりイベント的感覚で捉えられるようになった。出産を快適で充実したものにしたい。そう願う妊婦の選択肢のひとつとして注目されるのが自宅分娩であろう。施設での出産に莫大な費用がかかる諸外国では、出産場所は自宅・助産所しかない。あるいは自宅分娩では妊産婦死亡率が低下しない一部の先進国では、施設分娩へと誘導するために、快適性を重視した分娩へ移行させようとした状況がある。こういった状況が知らされないまま、一部の女性の経験談が集団を動かし、人はそれに共感する。しかし、年齢、健康状態、家庭の環境など、人それぞれ条件が異なるといったことを十分に考えているのだろうか。あの人ができるなら私にもといったイメージが強いのでは……。
ミュージアムは『聲の森』
西 洋子
昨年11月、民博で開催された
公開ワークショップ「ダンスで出会う・ダンスでつながる」。
モノたちの声が響き合う展示会場で得たイメージを創作ダンスで表現した。
障害のある人やない人、女性や男性、子どもや大人、
ずっと踊ってきた人や初めてダンスをする人……。
さまざまな個性をもつ人びとが集まり、ともに創り、ともに踊った2日間。
未来のユニヴァーサル社会の
ヒントを秘めた活動を紹介する。
楽しい予感
ミュージアムにでかけるとき、あなたは何を期待しますか。怖いくらいに静かで、ちょっと薄暗い館内には、ライトに照らし出され行儀よく並んだモノたちが待っています。こうしたモノとの出会いは、ときにとても鮮烈です。目にする形の不思議さや色の鮮やかさ。そこから過去の知識や経験が喚起され、ミュージアムで新たに得た情報も加わって、私たちは遠い世界の人びとの営みやその歴史、見たこともない、想像さえできなかった風景に思いを馳せます。
モノを通して自分や世界と向き合うという、知的で静かな作業をおこなうミュージアムという空間と、感性をフルに発揮し、ダイナミックにからだで創造し表現するダンスが出会ったら、そこには何が生まれるのでしょうか。しかも、その場に集う人びとが、とても個性的だったら。つまりは、ワイワイ、がやがや、バラバラ、ごたごたの状況のなかからどんなできごとが浮かび上がってくるのか。いえいえ、こうした出会いと状況だからこそ、おもしろいコトが起こりそうな楽しい予感がするのです。
ワークショップに響く声
公開ワークショップ「ダンスで出会う・ダンスでつながる」は、ミュージアムにとってはもちろん、ダンスにとっても、とても刺激的で実験的な試みでした。
一風かわった今回のワークショップ。館内のいろいろなモノたちからは、さまざまな声が聞こえてくるかのようです。まさに、「ミュージアムは『聲(こえ)の森』」です。まずは、参加者を迎える入り口あたりの声に、耳を傾けてみることにしましょう。
公開ワークショップ「ダンスで出会う・ダンスでつながる」。
モノたちの声が響き合う展示会場で得たイメージを創作ダンスで表現した。
障害のある人やない人、女性や男性、子どもや大人、
ずっと踊ってきた人や初めてダンスをする人……。
さまざまな個性をもつ人びとが集まり、ともに創り、ともに踊った2日間。
未来のユニヴァーサル社会の
ヒントを秘めた活動を紹介する。
楽しい予感
ミュージアムにでかけるとき、あなたは何を期待しますか。怖いくらいに静かで、ちょっと薄暗い館内には、ライトに照らし出され行儀よく並んだモノたちが待っています。こうしたモノとの出会いは、ときにとても鮮烈です。目にする形の不思議さや色の鮮やかさ。そこから過去の知識や経験が喚起され、ミュージアムで新たに得た情報も加わって、私たちは遠い世界の人びとの営みやその歴史、見たこともない、想像さえできなかった風景に思いを馳せます。
モノを通して自分や世界と向き合うという、知的で静かな作業をおこなうミュージアムという空間と、感性をフルに発揮し、ダイナミックにからだで創造し表現するダンスが出会ったら、そこには何が生まれるのでしょうか。しかも、その場に集う人びとが、とても個性的だったら。つまりは、ワイワイ、がやがや、バラバラ、ごたごたの状況のなかからどんなできごとが浮かび上がってくるのか。いえいえ、こうした出会いと状況だからこそ、おもしろいコトが起こりそうな楽しい予感がするのです。
ワークショップに響く声
公開ワークショップ「ダンスで出会う・ダンスでつながる」は、ミュージアムにとってはもちろん、ダンスにとっても、とても刺激的で実験的な試みでした。
一風かわった今回のワークショップ。館内のいろいろなモノたちからは、さまざまな声が聞こえてくるかのようです。まさに、「ミュージアムは『聲(こえ)の森』」です。まずは、参加者を迎える入り口あたりの声に、耳を傾けてみることにしましょう。
モノたちの声 いろんな足がやってきた
今日のお客は本当ににぎやかだ。もうすでにふたつのグループが通りすぎていった。今度のグループは、まだ遠くのようだから声は聞こえないけれど、響いてくる足音の、何とまあ雑多なこと。全部で二〇人くらいかな。大きい足、小さい足、ハイヒールもスニーカーも革靴もいる。おっと、車いすの車輪が頭の上を一瞬で走り去った。その後ろからはゆっくりとベビーカー。どちらも、似たような感触だ。
いろんな足の間から見上げれば、おじさんは肩をまわし、女の子は腕をぐにゃぐにゃさせて踊っている。肘と手でつながる女性たちは、ゆったりと談笑しながら優雅に過ぎていく。
何だかいつもと様子が違う。ミュージアムの入り口では、誰もがちょっと緊張するはずなのに。随分とリラックスしたからだや空気。そう、お風呂あがりのような、直前まで、みんなで遊んでいたような。いったいこの人たちって、なんだろう。
今日のお客は本当ににぎやかだ。もうすでにふたつのグループが通りすぎていった。今度のグループは、まだ遠くのようだから声は聞こえないけれど、響いてくる足音の、何とまあ雑多なこと。全部で二〇人くらいかな。大きい足、小さい足、ハイヒールもスニーカーも革靴もいる。おっと、車いすの車輪が頭の上を一瞬で走り去った。その後ろからはゆっくりとベビーカー。どちらも、似たような感触だ。
いろんな足の間から見上げれば、おじさんは肩をまわし、女の子は腕をぐにゃぐにゃさせて踊っている。肘と手でつながる女性たちは、ゆったりと談笑しながら優雅に過ぎていく。
何だかいつもと様子が違う。ミュージアムの入り口では、誰もがちょっと緊張するはずなのに。随分とリラックスしたからだや空気。そう、お風呂あがりのような、直前まで、みんなで遊んでいたような。いったいこの人たちって、なんだろう。
出会いのためのウォームアップ
ワークショップの参加者、約五〇名は、『音』『形』『色』の三つのグループにわかれて、まずは、人やモノに出会うためのウォームアップをおこないました。自己紹介をしたり、よび名を名札に書いたりと、言葉の世界で他者と出会うと同時に、ちょっとした動きを通して、からだの世界での出会いも試してみたのです。初めて出会ったパートナーの背骨あたりを上から下へ、下から上へと、思い思いのリズムでとんとん叩くと、相手は「あ、あああ、あ」や「ほ~、ほほ、ほ、ほほ」と音声で返してくれます。向かい合って手をとり、相手の腕を好きなように動かしてみると「タコみたいやな」とか、「肩こりが楽になるよ」とか、いろんな声が聞こえてきます。最初は少しはずかしそう。でも笑顔、時々大爆笑。からだと心が温まり、つながりが柔らかになったら、さあ、モノたちに会いにでかけましょう。
このワークショップの参加者は、さまざまなからだのもち主です。子どもや大人、車いすに乗る人や、車いすではない人。女性や男性、目でみて知る人や、からだでさわって知る人。さまざまなからだが、それぞれのやり方でミュージアムのモノたちとかかわります。説明を聞いたり、解説を読んだりは、普通のミュージアム鑑賞と同じです。それに加えて、手や頬でさわったり、顔やからだで形を真似たり、声をだしたり、動きに置き換えたりと、自分のからだでモノと出会い、そのイメージを、自分の内側に取り込んでいきます。それぞれの状況に合った、自由なやり方で構わないのです。
一方で、決まっていることもあります。それは、展示場をまわった後には、グループの仲間とからだでの表現活動をはじめて、二日目にはミュージアムのエントランスホールで発表するということです。発表までの活動時間は約四時間。とても短い時間です。ですから参加者は、楽しいけれど、ちょっと大変でもあります。もっとゆっくり、じっくり見たい、さわりたい、つくりたい。ホントそうですね。次回は必ずそうしましょう。
さて、いよいよ「形」グループが展示場に入っていくようです。ミュージアムのモノたちからは、どんな声が響いてくるのでしょうか。
テーマにもとづく展示の鑑賞
ワークショップの参加者、約五〇名は、『音』『形』『色』の三つのグループにわかれて、まずは、人やモノに出会うためのウォームアップをおこないました。自己紹介をしたり、よび名を名札に書いたりと、言葉の世界で他者と出会うと同時に、ちょっとした動きを通して、からだの世界での出会いも試してみたのです。初めて出会ったパートナーの背骨あたりを上から下へ、下から上へと、思い思いのリズムでとんとん叩くと、相手は「あ、あああ、あ」や「ほ~、ほほ、ほ、ほほ」と音声で返してくれます。向かい合って手をとり、相手の腕を好きなように動かしてみると「タコみたいやな」とか、「肩こりが楽になるよ」とか、いろんな声が聞こえてきます。最初は少しはずかしそう。でも笑顔、時々大爆笑。からだと心が温まり、つながりが柔らかになったら、さあ、モノたちに会いにでかけましょう。
このワークショップの参加者は、さまざまなからだのもち主です。子どもや大人、車いすに乗る人や、車いすではない人。女性や男性、目でみて知る人や、からだでさわって知る人。さまざまなからだが、それぞれのやり方でミュージアムのモノたちとかかわります。説明を聞いたり、解説を読んだりは、普通のミュージアム鑑賞と同じです。それに加えて、手や頬でさわったり、顔やからだで形を真似たり、声をだしたり、動きに置き換えたりと、自分のからだでモノと出会い、そのイメージを、自分の内側に取り込んでいきます。それぞれの状況に合った、自由なやり方で構わないのです。
一方で、決まっていることもあります。それは、展示場をまわった後には、グループの仲間とからだでの表現活動をはじめて、二日目にはミュージアムのエントランスホールで発表するということです。発表までの活動時間は約四時間。とても短い時間です。ですから参加者は、楽しいけれど、ちょっと大変でもあります。もっとゆっくり、じっくり見たい、さわりたい、つくりたい。ホントそうですね。次回は必ずそうしましょう。
さて、いよいよ「形」グループが展示場に入っていくようです。ミュージアムのモノたちからは、どんな声が響いてくるのでしょうか。
テーマにもとづく展示の鑑賞
モノたちの声 からだでみる
こちらをじっと見ていたかと思うと、ぼくと同じ顔をつくるんだ。目も口も斜めになっているぼくの顔。ゆがんだこころを見透かすようでしょう。そうかと思うと、次は隣の奴の真似をしている。口をタコみたいにすぼめて、ひょうきんな表情だなあ。「ほっ、ほっ、ほっ」と妙な声までだしはじめた。その声に合わせて、おなかを揺らしている。何だ、こいつは。
「顔を動かしすぎて疲れた」、そんなこというなよ。ぼくらはもう何十年も、ここで静かにしているんだ(その方がずっと疲れるよ)。それにしても、こうして真似てもらうと、同じ壁に並ぶ仲間は個性的だなあ。そこの男の子、たくさん見せてくれてありがとう。今度は仲間同士が向き合って、世間話でもできる気楽な展示がいいな。ところで君の乗り物は何? お返しに、大きなタイヤを真似したいけれど、ぼくは壁から離れられないからねえ。
こちらをじっと見ていたかと思うと、ぼくと同じ顔をつくるんだ。目も口も斜めになっているぼくの顔。ゆがんだこころを見透かすようでしょう。そうかと思うと、次は隣の奴の真似をしている。口をタコみたいにすぼめて、ひょうきんな表情だなあ。「ほっ、ほっ、ほっ」と妙な声までだしはじめた。その声に合わせて、おなかを揺らしている。何だ、こいつは。
「顔を動かしすぎて疲れた」、そんなこというなよ。ぼくらはもう何十年も、ここで静かにしているんだ(その方がずっと疲れるよ)。それにしても、こうして真似てもらうと、同じ壁に並ぶ仲間は個性的だなあ。そこの男の子、たくさん見せてくれてありがとう。今度は仲間同士が向き合って、世間話でもできる気楽な展示がいいな。ところで君の乗り物は何? お返しに、大きなタイヤを真似したいけれど、ぼくは壁から離れられないからねえ。
モノたちの声 さわって知る
「このトーテムポールは、親子の熊と鮭……」、ふー、今日も、おきまりの説明がはじまったわ。どうせみんなで上を見上げて「大きい~」と言うだけでしょう。
「……とされていますが、本当はよくわからないんです」「へー!!」
どうしてここで感心するのよ。もしかしてこの子、わからないということがおもしろいのかな、オモロイナ。
あれ、誰かが私をゆっくりさわっている。「鮭の尻尾ね」。そうそう、私は尻尾なの。親子熊の下にいる私に気づいてくれるなんて。丁寧にさわってもらって、あったかくなってきた。あらら、ほっぺまで寄せて。ふんわかといい気分。故郷の匂いを伝えられるといいけれど(防虫剤の匂いだわ、なんていわれたらどうしましょう)。
さっきのオモロイ子が「おばさんのご先祖様はシャケなの、ぼくは上の熊がいい。爪がスゲーから」と指を爪の形にひらいている。二階の熊親子も、爪形の手でさわってもらえればいいのに。でも、いつだって私の上にいるから無理よね。突っ立っている私たちが、ゆっくりと横に寝そべれば、自分の祖先を心に描く人びとと、大きさ比べができて楽しいかな。勝つのは決まって私たちだけどね。何といっても、ご先祖様だからねえ。
「このトーテムポールは、親子の熊と鮭……」、ふー、今日も、おきまりの説明がはじまったわ。どうせみんなで上を見上げて「大きい~」と言うだけでしょう。
「……とされていますが、本当はよくわからないんです」「へー!!」
どうしてここで感心するのよ。もしかしてこの子、わからないということがおもしろいのかな、オモロイナ。
あれ、誰かが私をゆっくりさわっている。「鮭の尻尾ね」。そうそう、私は尻尾なの。親子熊の下にいる私に気づいてくれるなんて。丁寧にさわってもらって、あったかくなってきた。あらら、ほっぺまで寄せて。ふんわかといい気分。故郷の匂いを伝えられるといいけれど(防虫剤の匂いだわ、なんていわれたらどうしましょう)。
さっきのオモロイ子が「おばさんのご先祖様はシャケなの、ぼくは上の熊がいい。爪がスゲーから」と指を爪の形にひらいている。二階の熊親子も、爪形の手でさわってもらえればいいのに。でも、いつだって私の上にいるから無理よね。突っ立っている私たちが、ゆっくりと横に寝そべれば、自分の祖先を心に描く人びとと、大きさ比べができて楽しいかな。勝つのは決まって私たちだけどね。何といっても、ご先祖様だからねえ。
モノたちのこんな声に出会いながら、各グループは、展示鑑賞を終えました。そして今度は、動きながら、自分のからだが発する声を、仲間と交わしていくようです。
イメージをからだで表現する
「アフリカの成人式のスカートのようにふくらんで動きましょう」「あ~あのワラっぽいやつね、がさごそって」
「今度は木彫像の人間ピラミッド」「横に長くつながって、次は縦にのびていこうか。I君の車いすの上にHちゃんが乗って、一番軽いK君、このおじさんの肩の上にあがってみたら……」「おー高いぞ。てっぺんのおじいさんになった気分」
「ちがうちがう、あっちからも、こっちからも顔がでてたよ。だからおばさんの顔は、こっちに向けてね。みんな、どこかがつながっている感じだったよ」「H先生、ぼくの頭をさわっててね、そう」「ふむふむ、こんな感じだったね、これはやっぱり家族ってことかな」
「そしたら最後は……」「人間ピラミッドが、サバンナの木にかわっていくのはどう」「木が揺れて、そこから人びとが、自分の好きな方に向かって歩き出す、ゆっくりと」「あら、すごく素敵な表現」
ワークショップ作品『聲の森』
こうして参加者は、モノたちの背後にある奥深い世界と出会うことで、それぞれのからだの内側に豊かなイメージを芽生えさせました。それを創造の源として、さらに仲間と声を交わしながら、自分たちの表現へと練り上げていったのです。そして二日目には、ワークショップ作品『聲の森』と題して、三グループが共同でひとつの作品を発表しました。パフォーマンスの場所は、ミュージアムのエントランスホール。長い階段には、たくさんのお客さまが集まって、とてもにぎやかなパフォーマンスになりました。ミュージアムを取り巻く木々や、すぐそばの水辺の景色に、今ではすっかりうちとけた参加者の生き生きとした表情と動きが、くっきりと浮かび上がりました。
どんなダンスに仕上がったのかって。それはもういろいろで、楽しすぎて。
パフォーマンスを観てくださったお客さまには、ワークショップの参加者とミュージアムのモノたちとが「ダンスで出会い、ダンスでつながる」プロセスが伝わったでしょうか。それとも、まったく新しい、独自の表現として受け取られたのでしょうか。見る人の心の動きまでは、わかりません。それでも、さまざまな声を響かせるモノたちと、そこから生まれた新たな表現とが、一緒に展示されているような、そんな未来のミュージアムがあったなら、とても素晴らしいと思いませんか。
イメージをからだで表現する
「アフリカの成人式のスカートのようにふくらんで動きましょう」「あ~あのワラっぽいやつね、がさごそって」
「今度は木彫像の人間ピラミッド」「横に長くつながって、次は縦にのびていこうか。I君の車いすの上にHちゃんが乗って、一番軽いK君、このおじさんの肩の上にあがってみたら……」「おー高いぞ。てっぺんのおじいさんになった気分」
「ちがうちがう、あっちからも、こっちからも顔がでてたよ。だからおばさんの顔は、こっちに向けてね。みんな、どこかがつながっている感じだったよ」「H先生、ぼくの頭をさわっててね、そう」「ふむふむ、こんな感じだったね、これはやっぱり家族ってことかな」
「そしたら最後は……」「人間ピラミッドが、サバンナの木にかわっていくのはどう」「木が揺れて、そこから人びとが、自分の好きな方に向かって歩き出す、ゆっくりと」「あら、すごく素敵な表現」
ワークショップ作品『聲の森』
こうして参加者は、モノたちの背後にある奥深い世界と出会うことで、それぞれのからだの内側に豊かなイメージを芽生えさせました。それを創造の源として、さらに仲間と声を交わしながら、自分たちの表現へと練り上げていったのです。そして二日目には、ワークショップ作品『聲の森』と題して、三グループが共同でひとつの作品を発表しました。パフォーマンスの場所は、ミュージアムのエントランスホール。長い階段には、たくさんのお客さまが集まって、とてもにぎやかなパフォーマンスになりました。ミュージアムを取り巻く木々や、すぐそばの水辺の景色に、今ではすっかりうちとけた参加者の生き生きとした表情と動きが、くっきりと浮かび上がりました。
どんなダンスに仕上がったのかって。それはもういろいろで、楽しすぎて。
パフォーマンスを観てくださったお客さまには、ワークショップの参加者とミュージアムのモノたちとが「ダンスで出会い、ダンスでつながる」プロセスが伝わったでしょうか。それとも、まったく新しい、独自の表現として受け取られたのでしょうか。見る人の心の動きまでは、わかりません。それでも、さまざまな声を響かせるモノたちと、そこから生まれた新たな表現とが、一緒に展示されているような、そんな未来のミュージアムがあったなら、とても素晴らしいと思いませんか。
ヒョウタンから「おぎゃあ!」(標本番号H210155、高さ22cm 幅14cm 奥行14cm)
南米アンデス地帯は、原産地だけあって、文様を施したヒョウタンは、じつに四五〇〇年も前から知られている。その後、ヒョウタンは漁網につける浮きとしても利用されたが、一九世紀になってから、この作品のように民衆芸術作品の素材として注目され、また観光土産として流通するようになる。乾燥させたヒョウタンの表面を磨き、下絵に彫刻刀で刻みを入れ、地の明褐色と芯の白い部分、そして燃えさしをあて、焦がしてできる黒色部分とを対比させ、祭りや日常生活などさまざまな場面を表現する。技術こそ単純だが、描く図案は緻密である。
表紙写真では、ベッドに横たわる農民女性の出産前の場面が描かれている。しかし周囲にはアンデスの儀礼的要素もちりばめられている。まずは、腹をさわっている夫らしき人物の傍らに立つ、黒めがねをかけた怪しげな男性を見てみよう。手につかむ動物は、やや大きめながら、世界で唯一家畜化された食用モルモットであるクイ(テンジクネズミ)のようだ。クイは、料理のほか、呪術でもよく用いられ、解剖して、病気の原因などを突き止めることが知られている。つまりこの男性は呪医ということになろう。
ベッドの際に座る女性も祈りを捧げている。足下に広げた布には、乾燥させたコカ(コカノキ科の植物)の葉が見える。コカの葉はアンデスの儀礼には欠かせず、口に含んだり、他の用具とともに布の上に広げられ、儀礼に供せられることが多い。いずれも安産を祈願しての行為であろう。
ここに揚げた写真は、裏面の出産後の場面。いずれも上部には、トウモロコシの醸造酒であるチチャを保存するための壺が見える。チチャ酒も、アンデスの祭りや儀礼に不可欠な存在である。めでたいときに酒、というのは、どこでも変わらぬ習慣らしい。
表紙写真では、ベッドに横たわる農民女性の出産前の場面が描かれている。しかし周囲にはアンデスの儀礼的要素もちりばめられている。まずは、腹をさわっている夫らしき人物の傍らに立つ、黒めがねをかけた怪しげな男性を見てみよう。手につかむ動物は、やや大きめながら、世界で唯一家畜化された食用モルモットであるクイ(テンジクネズミ)のようだ。クイは、料理のほか、呪術でもよく用いられ、解剖して、病気の原因などを突き止めることが知られている。つまりこの男性は呪医ということになろう。
ベッドの際に座る女性も祈りを捧げている。足下に広げた布には、乾燥させたコカ(コカノキ科の植物)の葉が見える。コカの葉はアンデスの儀礼には欠かせず、口に含んだり、他の用具とともに布の上に広げられ、儀礼に供せられることが多い。いずれも安産を祈願しての行為であろう。
ここに揚げた写真は、裏面の出産後の場面。いずれも上部には、トウモロコシの醸造酒であるチチャを保存するための壺が見える。チチャ酒も、アンデスの祭りや儀礼に不可欠な存在である。めでたいときに酒、というのは、どこでも変わらぬ習慣らしい。
友の会とミュージアム・ショップからのご案内
プーケットは元気──インド洋大津波と風評災害
市野澤 潤平
二〇〇四年一二月二六日にインド洋沿岸を襲った大津波は、合計三〇万人を超す犠牲者を出した。タイにおいても、特にアンダマン海側の南部六県が津波の直撃を受け、数万人が被災した。そうした事態を受け、津波の被害と復興への課題を探るべく、世界中から多数の研究者が被災地入りした。ボランティアの申し出や寄付金も、続々と集まった。
当時、私は日本で被災状況の報道を追っていた。津波襲来の直後、正月休みのためか日本のマスコミの動きは鈍かったが、年明けになってようやく詳しい情報が伝えられるようになると、被害の深刻さに驚かされるばかりだった。テレビニュースでは連日、まるでマッチ箱のように津波に押し流される建造物の映像が、繰り返し放映される。その多くが、観光客が偶然ビデオカメラに収めたものだったため、観光地が被災したタイ南部の映像が必然的に目立つことになった。タイ観光の研究者の端くれである私は、つい数カ月前に訪れたここもあそこも、流されて無くなってしまった、と目を疑うばかりだった。
タイ南部の被災地は、国際的に有名なビーチリゾートの、プーケット島、ピピ島、カオラックを含む。日本人にとっても、プーケットはバリと並ぶアジアン・リゾートの定番で、ピピ島はかのレオナルド・ディカプリオ主演の映画『ザ・ビーチ』の舞台としてなじみが深い。二月の後半になって、私はそれらの被災地を視察に行くことになった。国立民族学博物館による研究の一環である。実際に足を踏み入れてみると、ピピ島とカオラックは確かに建物があらかた破壊されていて被害が甚大なのだが、タイ南部最大の観光地であるプーケットのパトンビーチにやって来て、逆の意味で驚いた。日本でニュース映像を見ていた印象とはまったく異なり、ホテルも土産物屋も通常通り営業していたからだ。津波の爪痕がないといえば嘘になり、海岸沿いの一部のホテルや商店は閉鎖されているものの、ビーチリゾートとしては大きな問題なく機能している。そのわりには、人影がまばらなのが寂しかった。
現地の人たちによると、年が明けるとすぐに、住民総出で瓦礫の撤去や清掃作業をおこない、観光客を受け入れる体勢を整えたのだという。ところが、待てど暮らせど観光客は一向に戻ってこない。パトンビーチ全体が観光収入に頼っているだけに、これは死活問題だ。地域のイメージが悪化して、観光客に敬遠される「風評災害」。何とかプーケットは元気だということを日本のみなさんにも訴えたいと、住民たちは口をそろえる。しかし、マスコミ報道は被害の悲惨さばかりを強調し、続々と訪れる学術関係者もプーケットは素通りして、近隣の壊滅した漁村や被災者キャンプへと行ってしまう。その方が衆目を集める報告ができるからだ。
物理的な被害だけが災害ではない。経済の落ちこみなど、災害の二次被害は、ときに大きなダメージを地域社会に与え、しかも対策を立てるのが難しい。物理的な一次被害のインパクトの陰に隠れがちな、二次被害の問題に目を向けることの必要性を、痛感させられた。
当時、私は日本で被災状況の報道を追っていた。津波襲来の直後、正月休みのためか日本のマスコミの動きは鈍かったが、年明けになってようやく詳しい情報が伝えられるようになると、被害の深刻さに驚かされるばかりだった。テレビニュースでは連日、まるでマッチ箱のように津波に押し流される建造物の映像が、繰り返し放映される。その多くが、観光客が偶然ビデオカメラに収めたものだったため、観光地が被災したタイ南部の映像が必然的に目立つことになった。タイ観光の研究者の端くれである私は、つい数カ月前に訪れたここもあそこも、流されて無くなってしまった、と目を疑うばかりだった。
タイ南部の被災地は、国際的に有名なビーチリゾートの、プーケット島、ピピ島、カオラックを含む。日本人にとっても、プーケットはバリと並ぶアジアン・リゾートの定番で、ピピ島はかのレオナルド・ディカプリオ主演の映画『ザ・ビーチ』の舞台としてなじみが深い。二月の後半になって、私はそれらの被災地を視察に行くことになった。国立民族学博物館による研究の一環である。実際に足を踏み入れてみると、ピピ島とカオラックは確かに建物があらかた破壊されていて被害が甚大なのだが、タイ南部最大の観光地であるプーケットのパトンビーチにやって来て、逆の意味で驚いた。日本でニュース映像を見ていた印象とはまったく異なり、ホテルも土産物屋も通常通り営業していたからだ。津波の爪痕がないといえば嘘になり、海岸沿いの一部のホテルや商店は閉鎖されているものの、ビーチリゾートとしては大きな問題なく機能している。そのわりには、人影がまばらなのが寂しかった。
現地の人たちによると、年が明けるとすぐに、住民総出で瓦礫の撤去や清掃作業をおこない、観光客を受け入れる体勢を整えたのだという。ところが、待てど暮らせど観光客は一向に戻ってこない。パトンビーチ全体が観光収入に頼っているだけに、これは死活問題だ。地域のイメージが悪化して、観光客に敬遠される「風評災害」。何とかプーケットは元気だということを日本のみなさんにも訴えたいと、住民たちは口をそろえる。しかし、マスコミ報道は被害の悲惨さばかりを強調し、続々と訪れる学術関係者もプーケットは素通りして、近隣の壊滅した漁村や被災者キャンプへと行ってしまう。その方が衆目を集める報告ができるからだ。
物理的な被害だけが災害ではない。経済の落ちこみなど、災害の二次被害は、ときに大きなダメージを地域社会に与え、しかも対策を立てるのが難しい。物理的な一次被害のインパクトの陰に隠れがちな、二次被害の問題に目を向けることの必要性を、痛感させられた。
奥様、お手をどうぞ
どこかの国では作法とか敬語とかいうものが忘れさられて久しい。もし、まだあるとすれば、どこかの町のお稽古事の集まりのなかだけではないかと思われるほどだ。ところが、ヨーロッパの東の果てに過去の作法から生まれた言葉が日常生活のなかに、まったりと息づいている地域がある。
男性が女性に挨拶をするとき、優雅に腰をかがめ、そっと両手で女性の手を取って口づけをする。そのとき、”Sarut mâna“(サルート・ムーナ、だが私には、いつもサラムーナときこえた)という。意味は、お手にキスを、である。これは、男性が女性に挨拶するときにだけ用いられる。ふつうは、手にキスをするしぐさより、頬へのキスの場合が多いのだが。
挨拶である以上、この身体行為は習慣化していて、その意味を問い直す人はいない。だが、この”Sarut mâna“という挨拶は、外国人である筆者がルーマニア滞在中、なかなか身につけることができなかった言葉であった。
どこが難しかったのか。”Sarut mâna“という言葉で挨拶をするだけなら、「こんにちは」に当たるルーマニア語のBuna ziua、またフランス語のBonjourやイタリア語のBuòn giórnoと同じである。たとえ、それが頬へのキスや抱擁をともなっていても心理的な抵抗はない。だが、”Sarut mâna“にはちょっと違う語感がある。あの優雅なしぐさが脳裏に焼きついていて、照れくさい気分を生んでしまうのだ。時代錯誤も甚だしい社交儀礼の名残りではないか。ときおり、優雅に女性の手をとり、サラムーナとのたまう、しゃれた紳士をみかけるのでなおさらである。
ここで疑問が生じる。なぜ、東南ヨーロッパのルーマニアで、ヨーロッパ中世の封建的礼儀作法が今でも見られるのか。
その答えは、ルーマニアとヨーロッパとの密接な歴史的関係のなかに見出される。現在はルーマニアの一地方であるトランシルヴァニア地方は、近世初頭からハプスブルグ帝国の支配下にあった。近代にはいると帝国に対する独立運動の過程で、フランスから民族解放の思想的な影響ばかりでなく文化的影響を強く受けた。さらに独立後には新しく国王をドイツからよび寄せた。これがルーマニア王室のはじまり。王族の首を切ったフランスの影響を受けながらも、ドイツから王家をかりてくるというのがルーマニアらしくてよい。そして、宮廷貴族やら地主の子弟が西欧のマナーを取り入れて、悦にいっていたのである。
ちなみに社会主義体制下でも、”Sarut mâna“は生き残っていた。男女同権、労働者の権利を声高に叫びながらも女性のあり方は、旧体制とあまりかわらなかったとみえる。現在のルーマニアでも、男性に対する女性の立場がじつに強い! 思春期の男女関係はいうに及ばず、家庭生活においても女性の主導権は明らかである。マッチョな男性中心主義など、どこを探しても見つけられない。もちろん、政財界ともほとんど男性が指導的地位を占めるのだが、その内情は興味深いものであろう。
男性が女性に挨拶をするとき、優雅に腰をかがめ、そっと両手で女性の手を取って口づけをする。そのとき、”Sarut mâna“(サルート・ムーナ、だが私には、いつもサラムーナときこえた)という。意味は、お手にキスを、である。これは、男性が女性に挨拶するときにだけ用いられる。ふつうは、手にキスをするしぐさより、頬へのキスの場合が多いのだが。
挨拶である以上、この身体行為は習慣化していて、その意味を問い直す人はいない。だが、この”Sarut mâna“という挨拶は、外国人である筆者がルーマニア滞在中、なかなか身につけることができなかった言葉であった。
どこが難しかったのか。”Sarut mâna“という言葉で挨拶をするだけなら、「こんにちは」に当たるルーマニア語のBuna ziua、またフランス語のBonjourやイタリア語のBuòn giórnoと同じである。たとえ、それが頬へのキスや抱擁をともなっていても心理的な抵抗はない。だが、”Sarut mâna“にはちょっと違う語感がある。あの優雅なしぐさが脳裏に焼きついていて、照れくさい気分を生んでしまうのだ。時代錯誤も甚だしい社交儀礼の名残りではないか。ときおり、優雅に女性の手をとり、サラムーナとのたまう、しゃれた紳士をみかけるのでなおさらである。
ここで疑問が生じる。なぜ、東南ヨーロッパのルーマニアで、ヨーロッパ中世の封建的礼儀作法が今でも見られるのか。
その答えは、ルーマニアとヨーロッパとの密接な歴史的関係のなかに見出される。現在はルーマニアの一地方であるトランシルヴァニア地方は、近世初頭からハプスブルグ帝国の支配下にあった。近代にはいると帝国に対する独立運動の過程で、フランスから民族解放の思想的な影響ばかりでなく文化的影響を強く受けた。さらに独立後には新しく国王をドイツからよび寄せた。これがルーマニア王室のはじまり。王族の首を切ったフランスの影響を受けながらも、ドイツから王家をかりてくるというのがルーマニアらしくてよい。そして、宮廷貴族やら地主の子弟が西欧のマナーを取り入れて、悦にいっていたのである。
ちなみに社会主義体制下でも、”Sarut mâna“は生き残っていた。男女同権、労働者の権利を声高に叫びながらも女性のあり方は、旧体制とあまりかわらなかったとみえる。現在のルーマニアでも、男性に対する女性の立場がじつに強い! 思春期の男女関係はいうに及ばず、家庭生活においても女性の主導権は明らかである。マッチョな男性中心主義など、どこを探しても見つけられない。もちろん、政財界ともほとんど男性が指導的地位を占めるのだが、その内情は興味深いものであろう。
エチオピア文字で名前を書く 1
柘植 洋一
エチオピア文字は、アフリカ北東部のアムハラ語(エチオピア)およびティグリニア語(エチオピア、エリトリア)の表記に使われている。本来はこの地域に話されていたゲエズ語(今は死語)表記のために生まれた文字で、四世紀には、それまでのアルファベットから母音がついた音節文字に変わり、その基本的組織、字形が確立した。このようにアフリカにはめずらしく古くから使われてきた文字であるが、一般の人にまではなかなか行き渡らず、エチオピアの識字率は一九七〇年代初頭には一〇パーセントに満たなかった。しかし、その後大規模な識字キャンペーンが展開され、現在ではかなりの向上をみている。私が最初にエチオピアを訪れた一九八〇年は、この運動の真最中で、大人も年寄りも識字学級に通い、一生懸命文字を学ぶ姿が見られたことを思い出す。
エチオピア文字は、原則的に日本語のカナと同様、音節文字である。音節文字とは、たとえば「カ」のように、ローマ字では子音k+母音aの二字になる音を一字であらわす文字である。ただ、アムハラ語の方が日本語よりも子音も母音も数が多いので、文字の総数は二〇〇以上と、カナよりも多くなる。字形は大文字と小文字の区別はないし、アラビア文字のように単語のなかでの位置によって変わることもない。
日本語の五〇音図と同じく、エチオピア文字表も横が母音、縦が子音で構成される。カ行を例にとって示してみよう(例1)。母音の配列はä-u-i-a-e-ə-oとなっている。六番目の文字は、kəのほかに、母音を伴わない子音kだけの表記の役割も果たす。初めて知らない文字に接したので、ヘンテコな記号が並んでいると思われるだろうが、よく字形を眺めていただきたい。同じ行に属する文字は基本的に共通した字形であることにすぐ気がつかれるだろう。つまり1が基本形で、それ以外は1に右に小さい横棒をつけたり、右を伸ばしたりといった方法で手を加えてできた文字なのである。この方法はだいたいどの行でも同じである。日本語の場合、「カキクケコ/かきくけこ」のように字形間に共通点がないことを考えれば、規則性があるエチオピア文字の方が覚えやすいかもしれない。
さて、日本語のア、イ、ウ、エ、オに対してはそれぞれこの発音に近い4、3、2、5、7、の字形をあてればよい。このようにして五〇音図を作ると図のようになる。なお、エチオピア文字で日本語を書くには、カナのそれぞれに対応するエチオピア文字をそのまま左から右へと並べればよい。
例2・3では日本人の姓名と書き順を紹介した。 ところで、エチオピア人の人名は名字+個人名ではなく、自分の名+父親の名という構造をもつ。偉大なマラソンランナーであったアベベ・ビキラは、アベベが自分の名前で、ビキラはお父さんの名前である。女性ランナーのファトゥマ・ロバもロバさんではなく、ファトゥマさんとよばなければならない。したがって、みなさんがエチオピア人に名乗るときは注意が必要である。ヤマダ・ハナコと名乗れば、相手は「ああこの人はヤマダさんで、お父さんはハナコさんか」と思うし、ハナコ・ヤマダといえば「ああこの人はハナコさんで、お父さんはヤマダさんか」ととられることになる。次回は拗音などの場合の書き方を学ぶ。
エチオピア文字は、原則的に日本語のカナと同様、音節文字である。音節文字とは、たとえば「カ」のように、ローマ字では子音k+母音aの二字になる音を一字であらわす文字である。ただ、アムハラ語の方が日本語よりも子音も母音も数が多いので、文字の総数は二〇〇以上と、カナよりも多くなる。字形は大文字と小文字の区別はないし、アラビア文字のように単語のなかでの位置によって変わることもない。
日本語の五〇音図と同じく、エチオピア文字表も横が母音、縦が子音で構成される。カ行を例にとって示してみよう(例1)。母音の配列はä-u-i-a-e-ə-oとなっている。六番目の文字は、kəのほかに、母音を伴わない子音kだけの表記の役割も果たす。初めて知らない文字に接したので、ヘンテコな記号が並んでいると思われるだろうが、よく字形を眺めていただきたい。同じ行に属する文字は基本的に共通した字形であることにすぐ気がつかれるだろう。つまり1が基本形で、それ以外は1に右に小さい横棒をつけたり、右を伸ばしたりといった方法で手を加えてできた文字なのである。この方法はだいたいどの行でも同じである。日本語の場合、「カキクケコ/かきくけこ」のように字形間に共通点がないことを考えれば、規則性があるエチオピア文字の方が覚えやすいかもしれない。
さて、日本語のア、イ、ウ、エ、オに対してはそれぞれこの発音に近い4、3、2、5、7、の字形をあてればよい。このようにして五〇音図を作ると図のようになる。なお、エチオピア文字で日本語を書くには、カナのそれぞれに対応するエチオピア文字をそのまま左から右へと並べればよい。
例2・3では日本人の姓名と書き順を紹介した。 ところで、エチオピア人の人名は名字+個人名ではなく、自分の名+父親の名という構造をもつ。偉大なマラソンランナーであったアベベ・ビキラは、アベベが自分の名前で、ビキラはお父さんの名前である。女性ランナーのファトゥマ・ロバもロバさんではなく、ファトゥマさんとよばなければならない。したがって、みなさんがエチオピア人に名乗るときは注意が必要である。ヤマダ・ハナコと名乗れば、相手は「ああこの人はヤマダさんで、お父さんはハナコさんか」と思うし、ハナコ・ヤマダといえば「ああこの人はハナコさんで、お父さんはヤマダさんか」ととられることになる。次回は拗音などの場合の書き方を学ぶ。
*「エチオピア文字による50音図」「例1」「例2」「例3」は、画像データの本紙P19でご覧下さい。
ワカメ漁場と海女の暮らし
李 善愛
くじびきで決まる岩の主
毎年、誕生日になると母親から国際電話がかかってくる。
「今日はあなたの誕生日だからワカメ汁を食べなさい」
そのころ韓国では、ワカメ漁場であるワカメ岩の掃除がおこなわれている。
韓国の東海岸に位置する蔚山(ウルサン)市内から、バスで四〇分ほどかけて峠を越えると、南北に広がる集落の真ん中にある「漁村契事務所」に着く。漁村契とは、村の共同漁場を管理する漁業組織のことである。旧暦の八月一六日、漁村契員一六〇人が集まり、ワカメ漁場の区画割り当てのために、みな真剣な顔でくじびきに臨む。岩の大きさ、ワカメの収穫量に合わせて人数配分をし、くじびきで一年間の岩の主が決まるのだ。くじに外れた人は大きなため息をつき、がっかりする。岩の主は同じ漁村契員の海女たちにワカメ漁場を売ったり、岩掃除や翌年のワカメ採取を頼んだりする。また、新しい岩の主は昨年の岩の主から、自分の岩の境界を教えてもらう。そして天気がよく、潮の流れのよい秋の日を選んで岩を掃除する。
一般的に、漁業は男性主体の活動だが、東アジアでは古くから女性が潜水漁に携わっている。特に韓国では、済州島を中心に、ヘニョとよばれる海女の活躍がめざましく、日本へも出稼ぎに来ているほどである。
春になると、海女たちは海でワカメを採り、岸では海女の家族がリヤカーなどをもって収穫を待っている。集落の広場では、海女たちが採ってきたワカメを乾燥台に並べて干す。ワカメは天日によくさらして色が黒いものがよい品とされる。日当たりや風通しが悪いときに乾燥させた赤いものは商品価値が半減する。そのため、ワカメの採取は一週間の天気予報をみてからおこなう。気温が高すぎると、表面は乾燥していても裏は乾燥せず腐ってしまい、風がないとなかまで乾燥しないので、北西風が吹くときを選んで採取し、三、四日間天日にさらす。そのため、年に二、三回しか漁には出られない。干しワカメは海女の家族や親戚のネットワークを通して、一キロ一〇万ウォン(約一万円)以上の高値で売られる。特に九〇年代以後、健康ブームにのって、養殖ワカメの大量生産で沈滞していた天然ワカメの商品価値が高まりつつある。
韓国の暮らしの必需品
ワカメは韓国語でミヨクという。一一二三年に宋の使者、徐兢が編纂した見聞録『高麗図経』には、「ワカメは身分の貴賤にかかわらず、好んで食されている」と記されている。現在も大量に消費されていて、干しワカメは、産神膳の供物として欠かせない。また、産婦が汁にして食べると、乳の出がよくなるといわれ、お産の準備物としても必需品である。さらに、韓国人は誕生日にワカメ汁を食べないと福に恵まれないといわれる。また、ワカメがぬるぬるしているところから試験に落ちたり、解雇されたりしたとき、「ワカメ汁を食べた」という。このように韓国では、ワカメといえば自動的に誕生日、産後の肥立ち、試験を連想する。
ワカメの生息条件、村の立地条件、社会、経済変化などによって村固有のワカメ漁場利用の慣行が形成されてきた。しかし、こうした漁場慣行は、村外の人や都会の人にはほとんど知られていない。リゾート観光地、工業団地建設などによる開発により、ワカメ漁場の面積はだんだん少なくなっており、天然ワカメの生産量も減りつつある。
毎年、誕生日になると母親から国際電話がかかってくる。
「今日はあなたの誕生日だからワカメ汁を食べなさい」
そのころ韓国では、ワカメ漁場であるワカメ岩の掃除がおこなわれている。
韓国の東海岸に位置する蔚山(ウルサン)市内から、バスで四〇分ほどかけて峠を越えると、南北に広がる集落の真ん中にある「漁村契事務所」に着く。漁村契とは、村の共同漁場を管理する漁業組織のことである。旧暦の八月一六日、漁村契員一六〇人が集まり、ワカメ漁場の区画割り当てのために、みな真剣な顔でくじびきに臨む。岩の大きさ、ワカメの収穫量に合わせて人数配分をし、くじびきで一年間の岩の主が決まるのだ。くじに外れた人は大きなため息をつき、がっかりする。岩の主は同じ漁村契員の海女たちにワカメ漁場を売ったり、岩掃除や翌年のワカメ採取を頼んだりする。また、新しい岩の主は昨年の岩の主から、自分の岩の境界を教えてもらう。そして天気がよく、潮の流れのよい秋の日を選んで岩を掃除する。
一般的に、漁業は男性主体の活動だが、東アジアでは古くから女性が潜水漁に携わっている。特に韓国では、済州島を中心に、ヘニョとよばれる海女の活躍がめざましく、日本へも出稼ぎに来ているほどである。
春になると、海女たちは海でワカメを採り、岸では海女の家族がリヤカーなどをもって収穫を待っている。集落の広場では、海女たちが採ってきたワカメを乾燥台に並べて干す。ワカメは天日によくさらして色が黒いものがよい品とされる。日当たりや風通しが悪いときに乾燥させた赤いものは商品価値が半減する。そのため、ワカメの採取は一週間の天気予報をみてからおこなう。気温が高すぎると、表面は乾燥していても裏は乾燥せず腐ってしまい、風がないとなかまで乾燥しないので、北西風が吹くときを選んで採取し、三、四日間天日にさらす。そのため、年に二、三回しか漁には出られない。干しワカメは海女の家族や親戚のネットワークを通して、一キロ一〇万ウォン(約一万円)以上の高値で売られる。特に九〇年代以後、健康ブームにのって、養殖ワカメの大量生産で沈滞していた天然ワカメの商品価値が高まりつつある。
韓国の暮らしの必需品
ワカメは韓国語でミヨクという。一一二三年に宋の使者、徐兢が編纂した見聞録『高麗図経』には、「ワカメは身分の貴賤にかかわらず、好んで食されている」と記されている。現在も大量に消費されていて、干しワカメは、産神膳の供物として欠かせない。また、産婦が汁にして食べると、乳の出がよくなるといわれ、お産の準備物としても必需品である。さらに、韓国人は誕生日にワカメ汁を食べないと福に恵まれないといわれる。また、ワカメがぬるぬるしているところから試験に落ちたり、解雇されたりしたとき、「ワカメ汁を食べた」という。このように韓国では、ワカメといえば自動的に誕生日、産後の肥立ち、試験を連想する。
ワカメの生息条件、村の立地条件、社会、経済変化などによって村固有のワカメ漁場利用の慣行が形成されてきた。しかし、こうした漁場慣行は、村外の人や都会の人にはほとんど知られていない。リゾート観光地、工業団地建設などによる開発により、ワカメ漁場の面積はだんだん少なくなっており、天然ワカメの生産量も減りつつある。
ワカメ(学名:Undaria pinnatifida)
ワカメは、低潮線付近から漸深帯(2~5m)の岩礁に着生している1年生植物で、日本や韓国、中国沿岸に分布している。ワカメの胞子葉から出た遊走子は岩などに付着して芽を出し、糸状に発育していく。夏を越し、秋になると糸状の体の細胞のいくつかは、生殖器官にかわり、卵と精子ができはじめる。精子は泳いで卵にくっついて受精する。受精卵は細胞分裂を繰り返して、水温が20度まで下がる秋ごろ、肉眼で見られる幼体に発育してくる。そして冬のあいだに生長したワカメを3月から5月に採取する。
ワカメは、低潮線付近から漸深帯(2~5m)の岩礁に着生している1年生植物で、日本や韓国、中国沿岸に分布している。ワカメの胞子葉から出た遊走子は岩などに付着して芽を出し、糸状に発育していく。夏を越し、秋になると糸状の体の細胞のいくつかは、生殖器官にかわり、卵と精子ができはじめる。精子は泳いで卵にくっついて受精する。受精卵は細胞分裂を繰り返して、水温が20度まで下がる秋ごろ、肉眼で見られる幼体に発育してくる。そして冬のあいだに生長したワカメを3月から5月に採取する。
モントリオールの酔いどれ天使
暮らしの二極化
カナダのモントリオールは、北アメリカにありながらフランス系カナダ人が多数を占める独特の雰囲気が漂う街である。最近、ダウンタウンの目抜き通りであるセント・キャサリン通りを歩くと、イヌイットが道に座り、小銭を乞うている姿をよく目にするようになった。
カナダ・イヌイットの総人口は四万五〇〇〇人あまりであるが、そのうちの約五〇〇〇人が極北の村を離れ、南の都市部に住んでいる。モントリオールのイヌイット人口は推定八〇〇人あまりで、大半が女性である。モントリオールのイヌイットのなかには、先住民関連企業や政府関連団体で仕事をしている人もいれば、福祉金や失業手当に頼りながら生活をしている人やホームレスの人もいる。このほかに短大や大学の学生や病気治療のための専門病院に通っている人がいる。
都市在住のイヌイットの女性については、どのような生活を送っているのかほとんど知られていない。ここでは、仕事をもつ女性とホームレスの女性という対照的な生活を紹介しよう。
シェーラ(仮名)は、二三歳のイヌイットの女性。彼女は、数年前に短大を卒業し、「ジェームズ湾および北ケベック協定」の補償金を管理・運用するマキヴィクというイヌイットの政治・経済団体に事務員として就職した。月収は二四〇〇カナダドルだ。彼女は、月七五〇カナダドル支払いのローンを組んで郊外にマンションの一室を購入し、自家用車で通勤している。趣味は、ビデオを借りてアクション映画やコメディー映画をみることである。彼女は、ほぼ毎日、故郷のクージュアックにいる母親や彼氏に電話連絡をとっている。また、年二度の長期休暇のたびに帰省している。彼女は、仕事を続けるかたわら、さらに専門的な知識を身につけ、よりよい仕事に就くために大学に通いたいと考えている。職場でイヌイット語を話すこと、ときどき故郷から送られてくるホッキョクイワナやカリブーの肉を食べることを除けば、彼女のライフスタイルは、モントリオールの中流階級のものと大差がない。
酒と麻薬と男と女
一方、モントリオールに住むイヌイットの女性の大半は無職である。しかも飲酒や麻薬の問題を抱えている人が多いうえに、ホームレスの女性も少なくない。
リジー(仮名)は、ウンガバ湾地域出身の三五歳の女性である。彼女はフランス系カナダ人と結婚し、二児をもうけたが、彼女の飲酒が原因で一〇カ月前に離婚した。子どもは前夫が引き取った。それ以来、彼女はホームレスとなり、街頭で通行人から小銭を乞う日々を送っている。一日五カナダドル以上の稼ぎになるが、これだけでは食べていけないから、先住民友好センターや女性用シェルター(一時的な緊急避難施設)で無料の昼食を、先住民女性専用のシェルターなどで無料の夕食をとることが多い。当然ながら、カリブーの肉といったイヌイット料理を食べる機会はほとんどない。
夜になると公園などの野外で寝ることが多いが、たまにはシェルターや友人の家に泊まることもある。教会の慈善施設やシェルターに行けば、シャワーを浴びることもできるので、彼女は週に四回はシャワーを浴び、二回は衣服を洗濯する。また、季節の衣服は先住民友好センターや女性用シェルターでもらうことができる。このように住む場所がないということや、雨風や冬の寒さに耐えなければならないということを除けば、衣食はなんとかまかなえる。
月に一度、前夫は子どもたちを彼女に会わせるために、待ち合わせの場所である先住民友好センターにやってくる。子どもと過ごすことのできるこの数時間だけが彼女にとっての生きがいだ。子どもたちと一緒に住むことができない今、彼女は故郷に戻ることを考えているが、この前起こした喧嘩の裁判が続いており、街を離れることはできない。彼女にとって、モントリオールは地獄のようなところだ。
彼女の地獄は、酒や麻薬からはじまった。今も毎日、ビールを飲んでいる。また、大麻もやっている。朝から公園で紙袋に隠したビールの大瓶を仲間と回し飲みをすることもあれば、友人のアパートで明け方までドンちゃん騒ぎをすることもある。彼女らは金を出し合ってビールを買い、金がなくなるまで飲み続ける。バーでは金がなくても男性客がビールをふるまってくれるから、酒を欠かすことはない。酔ったあげくけんかをしたり、路上やバス、地下鉄のなかで大声でわめいたりするため、地元住民からは嫌われがちだ。彼女自身もよくない生活であるとわかってはいるが、抜け出せないでいる。また、イヌイットの女性のなかにはビールや大麻を手に入れる金欲しさに売春をする者もいる。彼女らは、心が純粋な分だけ、だまされることも多い。
都会のチャンスと危険
極北の村で生まれたイヌイットの女性は、仕事のため、勉学のため、病気治療のため、夫やボーイフレンドに同行するため、家庭内暴力や性的虐待から逃れるためなどといったさまざまな理由で、モントリオールをはじめとする都市部へと移住する。そして移住して一カ月もたたないうちに勝ち組と負け組に別れ、負け組は底なしの貧困のなかであえぎ苦しむ生活を余儀なくさせられる。また、勝ち組であった女性が、酒や麻薬、離婚などを契機として負け組に転落することもある。その逆は、きわめて少ない。
モントリオールのような大都会は、少数の勝ち組のイヌイットを作り出す一方で、数多くの酔いどれ天使を作り出す。イヌイットの女性にとって異郷の未知なる大都会は、チャンスと危険にみちた場所といえようか。現在、私は都市イヌイットのコミュニティ開発に関する応用的な研究に従事している。
カナダのモントリオールは、北アメリカにありながらフランス系カナダ人が多数を占める独特の雰囲気が漂う街である。最近、ダウンタウンの目抜き通りであるセント・キャサリン通りを歩くと、イヌイットが道に座り、小銭を乞うている姿をよく目にするようになった。
カナダ・イヌイットの総人口は四万五〇〇〇人あまりであるが、そのうちの約五〇〇〇人が極北の村を離れ、南の都市部に住んでいる。モントリオールのイヌイット人口は推定八〇〇人あまりで、大半が女性である。モントリオールのイヌイットのなかには、先住民関連企業や政府関連団体で仕事をしている人もいれば、福祉金や失業手当に頼りながら生活をしている人やホームレスの人もいる。このほかに短大や大学の学生や病気治療のための専門病院に通っている人がいる。
都市在住のイヌイットの女性については、どのような生活を送っているのかほとんど知られていない。ここでは、仕事をもつ女性とホームレスの女性という対照的な生活を紹介しよう。
シェーラ(仮名)は、二三歳のイヌイットの女性。彼女は、数年前に短大を卒業し、「ジェームズ湾および北ケベック協定」の補償金を管理・運用するマキヴィクというイヌイットの政治・経済団体に事務員として就職した。月収は二四〇〇カナダドルだ。彼女は、月七五〇カナダドル支払いのローンを組んで郊外にマンションの一室を購入し、自家用車で通勤している。趣味は、ビデオを借りてアクション映画やコメディー映画をみることである。彼女は、ほぼ毎日、故郷のクージュアックにいる母親や彼氏に電話連絡をとっている。また、年二度の長期休暇のたびに帰省している。彼女は、仕事を続けるかたわら、さらに専門的な知識を身につけ、よりよい仕事に就くために大学に通いたいと考えている。職場でイヌイット語を話すこと、ときどき故郷から送られてくるホッキョクイワナやカリブーの肉を食べることを除けば、彼女のライフスタイルは、モントリオールの中流階級のものと大差がない。
酒と麻薬と男と女
一方、モントリオールに住むイヌイットの女性の大半は無職である。しかも飲酒や麻薬の問題を抱えている人が多いうえに、ホームレスの女性も少なくない。
リジー(仮名)は、ウンガバ湾地域出身の三五歳の女性である。彼女はフランス系カナダ人と結婚し、二児をもうけたが、彼女の飲酒が原因で一〇カ月前に離婚した。子どもは前夫が引き取った。それ以来、彼女はホームレスとなり、街頭で通行人から小銭を乞う日々を送っている。一日五カナダドル以上の稼ぎになるが、これだけでは食べていけないから、先住民友好センターや女性用シェルター(一時的な緊急避難施設)で無料の昼食を、先住民女性専用のシェルターなどで無料の夕食をとることが多い。当然ながら、カリブーの肉といったイヌイット料理を食べる機会はほとんどない。
夜になると公園などの野外で寝ることが多いが、たまにはシェルターや友人の家に泊まることもある。教会の慈善施設やシェルターに行けば、シャワーを浴びることもできるので、彼女は週に四回はシャワーを浴び、二回は衣服を洗濯する。また、季節の衣服は先住民友好センターや女性用シェルターでもらうことができる。このように住む場所がないということや、雨風や冬の寒さに耐えなければならないということを除けば、衣食はなんとかまかなえる。
月に一度、前夫は子どもたちを彼女に会わせるために、待ち合わせの場所である先住民友好センターにやってくる。子どもと過ごすことのできるこの数時間だけが彼女にとっての生きがいだ。子どもたちと一緒に住むことができない今、彼女は故郷に戻ることを考えているが、この前起こした喧嘩の裁判が続いており、街を離れることはできない。彼女にとって、モントリオールは地獄のようなところだ。
彼女の地獄は、酒や麻薬からはじまった。今も毎日、ビールを飲んでいる。また、大麻もやっている。朝から公園で紙袋に隠したビールの大瓶を仲間と回し飲みをすることもあれば、友人のアパートで明け方までドンちゃん騒ぎをすることもある。彼女らは金を出し合ってビールを買い、金がなくなるまで飲み続ける。バーでは金がなくても男性客がビールをふるまってくれるから、酒を欠かすことはない。酔ったあげくけんかをしたり、路上やバス、地下鉄のなかで大声でわめいたりするため、地元住民からは嫌われがちだ。彼女自身もよくない生活であるとわかってはいるが、抜け出せないでいる。また、イヌイットの女性のなかにはビールや大麻を手に入れる金欲しさに売春をする者もいる。彼女らは、心が純粋な分だけ、だまされることも多い。
都会のチャンスと危険
極北の村で生まれたイヌイットの女性は、仕事のため、勉学のため、病気治療のため、夫やボーイフレンドに同行するため、家庭内暴力や性的虐待から逃れるためなどといったさまざまな理由で、モントリオールをはじめとする都市部へと移住する。そして移住して一カ月もたたないうちに勝ち組と負け組に別れ、負け組は底なしの貧困のなかであえぎ苦しむ生活を余儀なくさせられる。また、勝ち組であった女性が、酒や麻薬、離婚などを契機として負け組に転落することもある。その逆は、きわめて少ない。
モントリオールのような大都会は、少数の勝ち組のイヌイットを作り出す一方で、数多くの酔いどれ天使を作り出す。イヌイットの女性にとって異郷の未知なる大都会は、チャンスと危険にみちた場所といえようか。現在、私は都市イヌイットのコミュニティ開発に関する応用的な研究に従事している。
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。