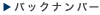月刊みんぱく 2006年8月号
2006年8月号
第30巻第8号通巻第347号
2006年8月1日発行
2006年8月1日発行
沖縄言葉
石川 文洋
わたしは一九四三年、五歳のときに家族とともに沖縄から本土に移住した。それまではずっと沖縄言葉で生活していた。沖縄言葉と共通語はずいぶんと違う。翌年、千葉県船橋市の小学校に入学した。子どもなので共通語にはすぐ慣れたが、それでもあやしい言葉を使ったようだ。「やわらかい」を「やはらかい」と言って先生や生徒たちに笑われたことを今でも覚えている。
わたしは次男だったが母方に養子に行くことになっていたので、中学三年生までは安里(あさと)姓を名乗っていた。そういうこともあって小学校時代は「オキナワ」というニックネームをつけられていた。沖縄生まれということに引け目は感じていなかったが、両親が沖縄言葉で話し合っているところを人に聞かれたら恥ずかしいと思ったことがある。
今は沖縄言葉は素晴らしい文化だと思っている。共通語では表現できないニュアンスを含んだ言葉が多い。わたしは本土の生活が長いので今では話すことはできないが、聞く分には八〇パーセントは理解できると思っている。沖縄言葉は喜怒哀楽を表現する点で、特に心情があらわれているように思う。
わたしが沖縄へ帰ったときは、祖母は沖縄言葉、わたしは共通語で会話が成立していた。しかし、現在は世代が変わって、子どもをもつ親たちも沖縄言葉が話せなくなっている。
原因は沖縄言葉を話していたお年寄りたちが亡くなってきたこと、共通語による学校での会話、家庭に定着したテレビの影響などによる。以前、読谷(よみたん)村長をしていた山内徳信さんにお会いしたとき、役場では、受付、職員の会話も含め、全て沖縄言葉にしてはいかがでしょうと提案したことがある。
父は沖縄の時代小説や芝居の脚本を書いていた。昨年一一月、日本橋の三越劇場で父の作品「与那国ションガネー」が上演された。沖縄から公演にきた主演の大城光子さんほか、沖縄芝居の役者の方々が全て沖縄言葉で演じた。本土に住む沖縄県人会の人びとは久し振りに沖縄芝居を楽しんだようだった。
戦前、戦後は沖縄芝居の全盛時代だった。今では、沖縄言葉で脚本を書く作家、演じる役者も少なくなった。言葉は子ども時代に覚える。沖縄ではせめて学校生活のなかで週に二、三時間は、沖縄言葉の時間を設けることができないものだろうかと思っている。
いしかわ ぶんよう/1938年沖縄県那覇市生まれ。写真家。毎日映画社、香港のスタジオ、朝日新聞社勤務などを経て、現在はフリーカメラマンとして活躍。1998年ベトナム・ホーチミン市戦争証跡博物館内に「石川文洋ベトナム報道35年 戦争と平和」常設室開設。著書に『ベトナム戦争と平和』(岩波書店)、『戦場カメラマン』(朝日新聞社)などがある。
わたしは次男だったが母方に養子に行くことになっていたので、中学三年生までは安里(あさと)姓を名乗っていた。そういうこともあって小学校時代は「オキナワ」というニックネームをつけられていた。沖縄生まれということに引け目は感じていなかったが、両親が沖縄言葉で話し合っているところを人に聞かれたら恥ずかしいと思ったことがある。
今は沖縄言葉は素晴らしい文化だと思っている。共通語では表現できないニュアンスを含んだ言葉が多い。わたしは本土の生活が長いので今では話すことはできないが、聞く分には八〇パーセントは理解できると思っている。沖縄言葉は喜怒哀楽を表現する点で、特に心情があらわれているように思う。
わたしが沖縄へ帰ったときは、祖母は沖縄言葉、わたしは共通語で会話が成立していた。しかし、現在は世代が変わって、子どもをもつ親たちも沖縄言葉が話せなくなっている。
原因は沖縄言葉を話していたお年寄りたちが亡くなってきたこと、共通語による学校での会話、家庭に定着したテレビの影響などによる。以前、読谷(よみたん)村長をしていた山内徳信さんにお会いしたとき、役場では、受付、職員の会話も含め、全て沖縄言葉にしてはいかがでしょうと提案したことがある。
父は沖縄の時代小説や芝居の脚本を書いていた。昨年一一月、日本橋の三越劇場で父の作品「与那国ションガネー」が上演された。沖縄から公演にきた主演の大城光子さんほか、沖縄芝居の役者の方々が全て沖縄言葉で演じた。本土に住む沖縄県人会の人びとは久し振りに沖縄芝居を楽しんだようだった。
戦前、戦後は沖縄芝居の全盛時代だった。今では、沖縄言葉で脚本を書く作家、演じる役者も少なくなった。言葉は子ども時代に覚える。沖縄ではせめて学校生活のなかで週に二、三時間は、沖縄言葉の時間を設けることができないものだろうかと思っている。
いしかわ ぶんよう/1938年沖縄県那覇市生まれ。写真家。毎日映画社、香港のスタジオ、朝日新聞社勤務などを経て、現在はフリーカメラマンとして活躍。1998年ベトナム・ホーチミン市戦争証跡博物館内に「石川文洋ベトナム報道35年 戦争と平和」常設室開設。著書に『ベトナム戦争と平和』(岩波書店)、『戦場カメラマン』(朝日新聞社)などがある。
わたしたちの生活は写真であふれ、
ときに写真は記憶を喚起するものとなる。
探検の時代であれ、植民地の時代であれ、
写真は人びとの過去の記憶を蘇らせる。
フィールドで撮影した写真、フィールドで発見した写真をとおし、
現代のわたしたちは過去の写真から何を読みとることができるのか、
考えてみたい。
ときに写真は記憶を喚起するものとなる。
探検の時代であれ、植民地の時代であれ、
写真は人びとの過去の記憶を蘇らせる。
フィールドで撮影した写真、フィールドで発見した写真をとおし、
現代のわたしたちは過去の写真から何を読みとることができるのか、
考えてみたい。
受信される記憶
港 千尋
ポストカードの世界
パリに住み始めたのは一九八〇年代でいちばん印象に残っているのは、サン・ジャック通りにあるアパルトマンである。六階建ての建物の最上階だった。一九世紀の建築で、当時もまだエレベーターはなかった。日本の七階に当たり、しかもずっと天井が高かったから、今思えば毎日よく上り下りをしていたものである。窓からの眺めが良かったのが救いだったのかもしれないが、この住みかのことを覚えているのは、たぶん屋根裏のせいだ。
踊り場の上に梯子(はしご)をかけ、小さな扉をあけて入ったそこは、自分の部屋からは想像のできない別世界だった。長いあいだにわたって住人たちが押し込み、忘れていったモノたちがひしめいていたが、粉雪のような埃(ほこり)がふり積もり、何があるのか判然としない。靴箱くらいの大きさの木箱がいくつか転がっている。舞い上がる埃(ほこり)を払ってあけてみると、なかにぎっしり詰まったポストカードがあった。モノクローム写真が印刷されたカードで、おそらく二〇世紀初頭のものである。ヨーロッパ各地の建物や公園の写真にまじって、アフリカの写真もふくまれている。これが、それまで知らなかった、ポストカードの世界との出合いだった。
セーヌ河岸の古本屋をのぞけば、こうした古いポストカードが吊るされているのが目に入る。コレクターがいるからで、たいてい地名やテーマ別に分類されて売られている。ポストカード専門の古物商にも会ったが、彼らが扱う量は膨大である。興味をもったのは、美術館や博物館に収集されている写真や、写真集の出版とは明らかに異質の世界を感じたからであった。
個人が送受信できるメディア
今日、写真家が写真をポストカードにするのは、展覧会の案内を送るときぐらいであろう。しかし一九世紀末から二〇世紀前半にかけて、ポストカードはひとつの独立したメディアだった。その量があまりに膨大であるのと、写真史のなかに体系的に位置づけられているわけではないという理由で、見過ごされてはいるが、写真の流通という点では、今日のインターネットと比較することができるほどの重要性をもっている。郵便制度の確立を背景にして爆発的に流行したポストカードは、国境を超えて飛び交う写真というイメージの世界を形成したからである。
失われたときへの郷愁に彩られることもあれば、記録としての重要性を認められて、一冊の写真集になることもあるが、ポストカードの研究にとって大切なのは、写っている被写体だけではない。写真家たちの眼差しが、送信と受信を通じて共有される。いい換えれば近代社会のなかにあらたなイメージの記憶がいかにして生まれたか。写真は、個人が送信し受信することのできるメディアとして発達してきたのだ。匿名の眼差しが共有され、ある時代の記憶となってゆく、そのプロセスを知ることは、ケータイ写真の時代に生きるわたしたちにとっても、十分に意味をもっていると思う。
パリに住み始めたのは一九八〇年代でいちばん印象に残っているのは、サン・ジャック通りにあるアパルトマンである。六階建ての建物の最上階だった。一九世紀の建築で、当時もまだエレベーターはなかった。日本の七階に当たり、しかもずっと天井が高かったから、今思えば毎日よく上り下りをしていたものである。窓からの眺めが良かったのが救いだったのかもしれないが、この住みかのことを覚えているのは、たぶん屋根裏のせいだ。
踊り場の上に梯子(はしご)をかけ、小さな扉をあけて入ったそこは、自分の部屋からは想像のできない別世界だった。長いあいだにわたって住人たちが押し込み、忘れていったモノたちがひしめいていたが、粉雪のような埃(ほこり)がふり積もり、何があるのか判然としない。靴箱くらいの大きさの木箱がいくつか転がっている。舞い上がる埃(ほこり)を払ってあけてみると、なかにぎっしり詰まったポストカードがあった。モノクローム写真が印刷されたカードで、おそらく二〇世紀初頭のものである。ヨーロッパ各地の建物や公園の写真にまじって、アフリカの写真もふくまれている。これが、それまで知らなかった、ポストカードの世界との出合いだった。
セーヌ河岸の古本屋をのぞけば、こうした古いポストカードが吊るされているのが目に入る。コレクターがいるからで、たいてい地名やテーマ別に分類されて売られている。ポストカード専門の古物商にも会ったが、彼らが扱う量は膨大である。興味をもったのは、美術館や博物館に収集されている写真や、写真集の出版とは明らかに異質の世界を感じたからであった。
個人が送受信できるメディア
今日、写真家が写真をポストカードにするのは、展覧会の案内を送るときぐらいであろう。しかし一九世紀末から二〇世紀前半にかけて、ポストカードはひとつの独立したメディアだった。その量があまりに膨大であるのと、写真史のなかに体系的に位置づけられているわけではないという理由で、見過ごされてはいるが、写真の流通という点では、今日のインターネットと比較することができるほどの重要性をもっている。郵便制度の確立を背景にして爆発的に流行したポストカードは、国境を超えて飛び交う写真というイメージの世界を形成したからである。
失われたときへの郷愁に彩られることもあれば、記録としての重要性を認められて、一冊の写真集になることもあるが、ポストカードの研究にとって大切なのは、写っている被写体だけではない。写真家たちの眼差しが、送信と受信を通じて共有される。いい換えれば近代社会のなかにあらたなイメージの記憶がいかにして生まれたか。写真は、個人が送信し受信することのできるメディアとして発達してきたのだ。匿名の眼差しが共有され、ある時代の記憶となってゆく、そのプロセスを知ることは、ケータイ写真の時代に生きるわたしたちにとっても、十分に意味をもっていると思う。
「華僑の故郷」の歴史表象
二〇〇〇年と二〇〇一年、雲南の「華僑の故郷」といわれる保山市騰衝県(ほざんしとうしょうけん)の和順郷(わじゅんごう)で、国境地域の漢族文化の動態の調査をおこなったとき、数多くの一九三〇年代、一九四〇年代の古写真と出合った。中国では一般的に農家が写真をもつようになったのは一九四九年建国以降のことなので、今回の発見は非常にめずらしいものである。
わたしを驚かせたのは写真を作成した年代の古さだけではなく、その保存状態の良さ、とくに写真の内容の豊富さである。個人や家族の写真から、和順郷出身の日本の留学生たち、留学生たちが創設した小中学校の入学式と卒業式。和順郷の人びとが演じた新劇の場面、村の「洞経会」のメンバーが伝統的な儒教・道教・仏教の音楽である洞経を演奏する場面や遠足の風景、村の自然風景・市場・壇廟(だんびょう)の写真まである。これらは二〇世紀前半の中国とミャンマーの国境地域の日常生活のさまざまな側面、華僑の故郷としての和順郷の歴史をリアルに記録している。
数百枚の写真の多くは、わたしのインフォーマント(資料・情報提供者)であった張孝仲氏の父親の張溶氏が撮ったものである。張溶氏は一九二〇年代の初期に和順郷に移住してきて、一九二七年に和順郷で初めての写真館「耀光撮影室(ようこうさつえいしつ)」を開いた。現在、その写真館は「僑光照像館(きょうこうしょうぞうかん)」という名前に変更され、張溶氏の六〇歳過ぎの娘二人によって運営されている。
和順郷の人びとは、これらの古い写真を大切に家に飾っており、写真に記録されている彼らの祖先が作った和順郷の歴史を誇りに思っている。近年、彼らは和順郷の観光スポットで古い写真展を開催し、写真をとおして観光客に「華僑の故郷」の歴史を語っている。こうして二一世紀の観光産業化のもと、古い写真は和順郷の人びとにとって自分たちの郷土の歴史と文化を表象する手段のひとつとなっている。
「僑光照像館」のオーナーの話によると、古い写真は和順郷在住の人びとだけの宝物ではなく、一時帰国の華人華僑や観光客もよくそれらをお土産として買って帰るそうである。観光客たちは古い写真をとおして二〇世紀の初頭における中国農村の近代化のリアリティを想像する。海外にいる華人華僑たちにとっては、和順郷の古い写真は彼らの家族、故郷への想いと記憶を具現化するものであり、彼らのアイデンティティの確立の媒介でもあるといえよう。
わたしを驚かせたのは写真を作成した年代の古さだけではなく、その保存状態の良さ、とくに写真の内容の豊富さである。個人や家族の写真から、和順郷出身の日本の留学生たち、留学生たちが創設した小中学校の入学式と卒業式。和順郷の人びとが演じた新劇の場面、村の「洞経会」のメンバーが伝統的な儒教・道教・仏教の音楽である洞経を演奏する場面や遠足の風景、村の自然風景・市場・壇廟(だんびょう)の写真まである。これらは二〇世紀前半の中国とミャンマーの国境地域の日常生活のさまざまな側面、華僑の故郷としての和順郷の歴史をリアルに記録している。
数百枚の写真の多くは、わたしのインフォーマント(資料・情報提供者)であった張孝仲氏の父親の張溶氏が撮ったものである。張溶氏は一九二〇年代の初期に和順郷に移住してきて、一九二七年に和順郷で初めての写真館「耀光撮影室(ようこうさつえいしつ)」を開いた。現在、その写真館は「僑光照像館(きょうこうしょうぞうかん)」という名前に変更され、張溶氏の六〇歳過ぎの娘二人によって運営されている。
和順郷の人びとは、これらの古い写真を大切に家に飾っており、写真に記録されている彼らの祖先が作った和順郷の歴史を誇りに思っている。近年、彼らは和順郷の観光スポットで古い写真展を開催し、写真をとおして観光客に「華僑の故郷」の歴史を語っている。こうして二一世紀の観光産業化のもと、古い写真は和順郷の人びとにとって自分たちの郷土の歴史と文化を表象する手段のひとつとなっている。
「僑光照像館」のオーナーの話によると、古い写真は和順郷在住の人びとだけの宝物ではなく、一時帰国の華人華僑や観光客もよくそれらをお土産として買って帰るそうである。観光客たちは古い写真をとおして二〇世紀の初頭における中国農村の近代化のリアリティを想像する。海外にいる華人華僑たちにとっては、和順郷の古い写真は彼らの家族、故郷への想いと記憶を具現化するものであり、彼らのアイデンティティの確立の媒介でもあるといえよう。
世界の屋根の村での撮影
高山 龍三
民博データベースとして、一九五八年わたしたちが撮ったヒマラヤの写真がネット上に公開された。ひじょうにうまく構成されていて、研究者のみならず一般の方も興味をもって見ていただけるのではないかと思う。地図上でネパールのツァルカ村をクリックすると、いくつかのテーマが出る。「人物」を押してみると、そこに懐かしいチベット人の顔が並んでいる。この村は民族調査のために、わたしたちが三ヵ月住みこんだ村だ。高さはもっていった高度計で四二五〇メートル、おそらくこの辺でもっとも高い定住村と思う。農耕限界ぎりぎりの高さでオオムギの単作をしていた。しかし生業の主力は牧畜とキャラバン交易であった。というよりその三つの生業をうまく組み合わせて、この厳しい環境に生きてきたのである。
データベースに出ているパルジョー君は、よいインフォーマントであった。じつにいろいろなことを教えてくれた。チベット人社会における「骨と肉」のシステムを見つけたのも、彼のおかげだ。彼と兄さんで、一人の奥さんをもっている。一妻多夫のことも聞いた。
チベット人村の住み込み調査も、初めから順調に進んだのではない。まずことばが通じない。初めはもっぱら耳をならすことにし、それより目を使っての仕事を進めていった。すなわち写真で、一軒一軒の家、村人の顔、家畜囲い、農地、寺を撮っていった。もちろん行事や作業があるとそこに駆けつけ、写真に撮るとともに、聞き取りをした。そして家の配置と集落の地図を作り、家族関係を聞き、それをまとめて、全家族の系図を作った。その結果、村の人口も、社会システムのルールも明らかになったのである。統計や地図があるわけでないフィールドでは、このように基本的なことからひとつずつやる必要があった。
おもにこの村で集めた民族資料の写真も見られ、さらに「使用状況」をクリックするとそれを使っていたり、身につけている写真が出てくる。
データベースに出ているパルジョー君は、よいインフォーマントであった。じつにいろいろなことを教えてくれた。チベット人社会における「骨と肉」のシステムを見つけたのも、彼のおかげだ。彼と兄さんで、一人の奥さんをもっている。一妻多夫のことも聞いた。
チベット人村の住み込み調査も、初めから順調に進んだのではない。まずことばが通じない。初めはもっぱら耳をならすことにし、それより目を使っての仕事を進めていった。すなわち写真で、一軒一軒の家、村人の顔、家畜囲い、農地、寺を撮っていった。もちろん行事や作業があるとそこに駆けつけ、写真に撮るとともに、聞き取りをした。そして家の配置と集落の地図を作り、家族関係を聞き、それをまとめて、全家族の系図を作った。その結果、村の人口も、社会システムのルールも明らかになったのである。統計や地図があるわけでないフィールドでは、このように基本的なことからひとつずつやる必要があった。
おもにこの村で集めた民族資料の写真も見られ、さらに「使用状況」をクリックするとそれを使っていたり、身につけている写真が出てくる。
撮影後記
わたしのカメラはカラーとモノクロの2台あり、モノクロについては現像タンクと薬剤を持参、現地で現像して、ネガを日本に送ったこともある。貧乏隊のため、日本のフィルム会社から提供してもらった。日本を出て帰るまで約半年、防湿に気を遣ったが保管が完全でなく、そのためカラーは良くない。モノクロは比較的良く保存され、データベースとして役立ったことは嬉しい。
わたしのカメラはカラーとモノクロの2台あり、モノクロについては現像タンクと薬剤を持参、現地で現像して、ネガを日本に送ったこともある。貧乏隊のため、日本のフィルム会社から提供してもらった。日本を出て帰るまで約半年、防湿に気を遣ったが保管が完全でなく、そのためカラーは良くない。モノクロは比較的良く保存され、データベースとして役立ったことは嬉しい。
撮影者の「立ち位置」
竹内 潔
二〇世紀が生んだ優れた報道写真家の一人、ロバート・キャパが一九三〇年代のスペイン内戦を取材して撮った写真のなかに、日差しを浴びながら寄り添って椅子に座っている民兵とその恋人とおぼしき女性の写真がある。写真を撮られることに対する含羞(がんしゅう)と二人で写ることの晴れがましさといった日常的な感情が見る者に伝わってくると同時に、共和国側に立った民衆の内戦初期の高揚感が写真から静かに迫ってくる。そして、スペイン内戦の経緯を知る者にとっては、女性の胸に落ちている男性の銃の影は、その後の二人と共和国側の民衆の苛酷な運命を暗示しているかのようだ。
報道写真が出来事や時代の一瞬を凝縮して表現するものであるのに対して、わたしたちフィールド・ワーカーが撮る写真は現地の人たちにとってみれば何ということもない日常を切りとって記録するものであって、両者の目的はまったく異なる。しかし、報道写真にせよ、フィールド写真にせよ、見る者に迫真の力を感じさせる写真は、一定の距離を置きながらも、写っている人びとと撮影者が時間と場をしっかりと共有していることがわかるような写真だと思う。キャパの写真がわたしたちに衝撃を与えるのは、写し込まれた光景や運命のその現場に彼が実際に立っていたことが確実に伝わってくるからだ。事件であれ、あるいは「異文化」であれ、被写体の内側に踏み込んだ撮影者の「立ち位置」がわかる写真ほど、写真は「リアリティ」を描く。
大学院時代の指導教官であった故伊谷純一郎先生は、「スライドを見るとなあ、写ってない周りの風景とか人物とか、そのときの自分の感情とかまで蘇ってくるんや」とよくおっしゃっていた。わたしは二〇年ほどアフリカの熱帯森林で調査を続けてきて、写真もたくさん撮ったが、恥ずかしいことに、いつ撮ったのかさえすぐには思い出せない写真が多い。フィールド写真については撮影者と被写体のあいだの権力関係をめぐってさまざまな議論があるが、わたしは、自分の「立ち位置」を静かに語れるような一枚の写真を撮りたい。
報道写真が出来事や時代の一瞬を凝縮して表現するものであるのに対して、わたしたちフィールド・ワーカーが撮る写真は現地の人たちにとってみれば何ということもない日常を切りとって記録するものであって、両者の目的はまったく異なる。しかし、報道写真にせよ、フィールド写真にせよ、見る者に迫真の力を感じさせる写真は、一定の距離を置きながらも、写っている人びとと撮影者が時間と場をしっかりと共有していることがわかるような写真だと思う。キャパの写真がわたしたちに衝撃を与えるのは、写し込まれた光景や運命のその現場に彼が実際に立っていたことが確実に伝わってくるからだ。事件であれ、あるいは「異文化」であれ、被写体の内側に踏み込んだ撮影者の「立ち位置」がわかる写真ほど、写真は「リアリティ」を描く。
大学院時代の指導教官であった故伊谷純一郎先生は、「スライドを見るとなあ、写ってない周りの風景とか人物とか、そのときの自分の感情とかまで蘇ってくるんや」とよくおっしゃっていた。わたしは二〇年ほどアフリカの熱帯森林で調査を続けてきて、写真もたくさん撮ったが、恥ずかしいことに、いつ撮ったのかさえすぐには思い出せない写真が多い。フィールド写真については撮影者と被写体のあいだの権力関係をめぐってさまざまな議論があるが、わたしは、自分の「立ち位置」を静かに語れるような一枚の写真を撮りたい。
写真とアウラ
写真界の老舗、コニカミノルタ・グループが本年三月末でカメラとフィルム事業から撤退、というニュースは、光学フィルム対デジタル・メモリという蓄積メディア戦争の行方を示すものだった。さまざまなメディアの発達史は、これと同様、新興メディアと既存メディアとのあいだの進化論的なニッチ争いの歴史でもある。この事態に対し、フィルム擁護派、デジタル活用派、それぞれからの意見が新聞などで紹介され、例えば赤瀬川原平氏は、フィルム撮影の作り出す思いがけない「一回性」の有り難みがデジカメにはない、と述べている。この世のある時間・ある場所で一回限り生じる現象や、この世に唯一存在するものに対し、人は特別な感情を抱く。一九三〇年代、文化社会学者W・ベンヤミンは、それを「アウラ(aura)」とよんだ。
印刷、写真、映画など機械的な大量複製技術は、情報のあいだにオリジナルとコピーという関係を作り出す。ベンヤミンは、風、香り、輝きを意味するこのラテン語(「オーラ」と同義)を転用し、一回性やオリジナルのもつ有り難みをアウラと定義した。発明当初、絵画、あるいは自然や風物の複製手段として出発した写真は、アウラを失わせるメディアだと非難される一方、それらを一般人に解放する役割をもつこととなった、と彼は言う。アナログ対デジタルをめぐる現代の議論にも、写真発明当時と同様の意見分布が見える。
しかし、よく考えてみると、アナログ・メディアにしろデジタル・メディアにしろ、その編集・再生過程でさまざまな変更や修正が可能だ。フィルムであっても、現像・焼きつけによって結果は個々異なる。そこで写真家のなかには、自分が撮ったフィルムではなく、自信作のプリントをオリジナルと見なして保存対象とする人もいる。
であるならば、どこにアウラを感じるかは、人それぞれの立場によって異なるのが当然だ。いや、人為的・機械的を問わず、何らかの操作の結果ではなく、個々の操作自体がすべて、アウラを生起するのかも知れない。と考えると、種々の蓄積メディア上に記録された写真資料のうち、どれをオリジナルとして保存すべきか、という民博の抱える宿題にまで、アウラの問題がかかわってくるようだ。
印刷、写真、映画など機械的な大量複製技術は、情報のあいだにオリジナルとコピーという関係を作り出す。ベンヤミンは、風、香り、輝きを意味するこのラテン語(「オーラ」と同義)を転用し、一回性やオリジナルのもつ有り難みをアウラと定義した。発明当初、絵画、あるいは自然や風物の複製手段として出発した写真は、アウラを失わせるメディアだと非難される一方、それらを一般人に解放する役割をもつこととなった、と彼は言う。アナログ対デジタルをめぐる現代の議論にも、写真発明当時と同様の意見分布が見える。
しかし、よく考えてみると、アナログ・メディアにしろデジタル・メディアにしろ、その編集・再生過程でさまざまな変更や修正が可能だ。フィルムであっても、現像・焼きつけによって結果は個々異なる。そこで写真家のなかには、自分が撮ったフィルムではなく、自信作のプリントをオリジナルと見なして保存対象とする人もいる。
であるならば、どこにアウラを感じるかは、人それぞれの立場によって異なるのが当然だ。いや、人為的・機械的を問わず、何らかの操作の結果ではなく、個々の操作自体がすべて、アウラを生起するのかも知れない。と考えると、種々の蓄積メディア上に記録された写真資料のうち、どれをオリジナルとして保存すべきか、という民博の抱える宿題にまで、アウラの問題がかかわってくるようだ。
スラムで生きる人
北森 絵里
現地調査では人に会って話すことが多い。わたしは、一五年前からブラジルの都市リオデジャネイロのスラムで調査をおこなってきたが、何人かの人とは家族ぐるみの長いつきあいだ。ここで紹介するシコはそのような友人の一人だ。
シコ(フランシスコ)が生まれたのは一九二九年、ブラジル北東部セアラ州の農村だった。若いころリオデジャネイロにやってきてスラムに住み、三〇歳くらいのとき、スラム・クリアランスに伴って建設された低所得者向け住宅地に移り住んだ。彼は、子供のころは畑仕事を、リオデジャネイロにきてからは左官やペンキ塗り、自動車修理などの仕事をこなしてきた。ずっと働き続けながら三〇年の住宅ローンを払い終わり、妻と子ども三人を養ってきた。彼は長年胃を患っており、二〇〇〇年四月に七〇歳の人生を終えた。
シコは胃から吐血して体調の悪い日以外は、日曜日でも働いていた。わたしにとってシコはいつも「働いている」人だった。彼は「死ぬまで働く」と言っていた。リオ社会は貧富の格差が著しく、富裕層は低所得の人びとに対して「怠け者」として偏見をもったり、「貧しいが健気に生きる人」として理想化したりする。また、わたしは「働く」というとつい「苦労して稼ぐ」とか「仕事を生き甲斐にする」といったことを連想してしまう。シコはこうしたステレオタイプのイメージを払拭(ふっしょく)した。彼から「苦労した」や「辛い」といった言葉は聞いたことがないし、彼は自分のことを「貧しい」と言ったこともない。リオ社会全体から見れば彼は低所得者であり、彼もそのことを自覚している。しかし「貧しい」わけではない。彼によれば「貧しさ」とは広場で通行人からの施(ほどこ)しを受けるように怠けて何もしないことであり、働くことは好きでも嫌いでもなく必要なことなのだ。
シコのような無名の人がどのような人生を送り、それをどのようにとらえているのか。スラムで出会った人びとの話を聞くたびに、その人の思いがわたしの心に入り込み沈澱する。最後にシコに会ったのは一九九九年八月だった。写真を見るとわたしの心の中で、彼の思いが、いやわたしの彼への思いが動き出すのだ。
シコ(フランシスコ)が生まれたのは一九二九年、ブラジル北東部セアラ州の農村だった。若いころリオデジャネイロにやってきてスラムに住み、三〇歳くらいのとき、スラム・クリアランスに伴って建設された低所得者向け住宅地に移り住んだ。彼は、子供のころは畑仕事を、リオデジャネイロにきてからは左官やペンキ塗り、自動車修理などの仕事をこなしてきた。ずっと働き続けながら三〇年の住宅ローンを払い終わり、妻と子ども三人を養ってきた。彼は長年胃を患っており、二〇〇〇年四月に七〇歳の人生を終えた。
シコは胃から吐血して体調の悪い日以外は、日曜日でも働いていた。わたしにとってシコはいつも「働いている」人だった。彼は「死ぬまで働く」と言っていた。リオ社会は貧富の格差が著しく、富裕層は低所得の人びとに対して「怠け者」として偏見をもったり、「貧しいが健気に生きる人」として理想化したりする。また、わたしは「働く」というとつい「苦労して稼ぐ」とか「仕事を生き甲斐にする」といったことを連想してしまう。シコはこうしたステレオタイプのイメージを払拭(ふっしょく)した。彼から「苦労した」や「辛い」といった言葉は聞いたことがないし、彼は自分のことを「貧しい」と言ったこともない。リオ社会全体から見れば彼は低所得者であり、彼もそのことを自覚している。しかし「貧しい」わけではない。彼によれば「貧しさ」とは広場で通行人からの施(ほどこ)しを受けるように怠けて何もしないことであり、働くことは好きでも嫌いでもなく必要なことなのだ。
シコのような無名の人がどのような人生を送り、それをどのようにとらえているのか。スラムで出会った人びとの話を聞くたびに、その人の思いがわたしの心に入り込み沈澱する。最後にシコに会ったのは一九九九年八月だった。写真を見るとわたしの心の中で、彼の思いが、いやわたしの彼への思いが動き出すのだ。
民族学とアートの融合
―パリの新しい博物館 ケ・ブランリー―
―パリの新しい博物館 ケ・ブランリー―
パリに新しい博物館
ケ・ブランリーが誕生した。
アートという視点からの
展示を実現させたという
この博物館をめぐる動きを追いながら、
パリの博物館事情を探ってみよう。
ケ・ブランリーが誕生した。
アートという視点からの
展示を実現させたという
この博物館をめぐる動きを追いながら、
パリの博物館事情を探ってみよう。
二〇〇六年六月二三日、パリに新しい博物館が誕生した。その名は「ケ・ブランリー博物館」、といってもほとんどの人が聞いたことがないのではなかろうか。
一九九五年フランス共和国の大統領選挙でジャック・シラクが当選すると、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカに関する芸術性の高いものや新しい美術品を展示する博物館の構想を打ち上げた。美術というからには、ほとんどアートに関係するものを展示すると考えられて構想が練られた。そしてこの新博物館に、トロカデロのシャイヨー宮にある「人類博物館」や、パリの東にある「アフリカ・オセアニア芸術博物館」などに収集されていた三〇万点以上の所蔵品から選別した三五〇〇点あまりが移されることになった。
これにともない、二〇〇四年暮れには、一部の展示をのぞき、両博物館とも展示場の大部分が縮小を余儀なくされた。それらの収蔵品は国の保管庫に収められ、新しい展示に向けて選別を待つこととなったのである。
民族・民俗展示のあゆみ
パリには二年ほど前まで民族学に関してふたつの博物館と、民俗学に関するひとつの博物館が一般に公開されていた。
ひとつは、パリ東部のヴァンセーヌの森、動物園近くのポルト・ドレに一九三五年に「海外フランス博物館」として大きく建てられ、その後に「アフリカ・オセアニア芸術博物館」となったものである。
初期の展示内容はフランス文学や美術における異国趣味、土着芸術、植民地領土についての博物館であった。当時のフランス植民地政策に役立ったとされている。
一九六〇年代に植民地の独立が世界的に進むとアンドレ・マルローによって博物館の名称と内容も変更された。アフリカ・オセアニアの芸術工芸品や民族美術とされる資料などを中心に展示した。収蔵品に関して「人類博物館」の協力を得て整理されるはずであったが、十分に実行されないまま新しい「ケ・ブランリー博物館」に入ってしまう。
ふたつ目の博物館は、観光名所として知られるトロカデロの丘に立つシャイヨー宮のなかの「人類博物館」である。その歴史は、一六三五年に、セーヌ左岸のオステルリッツ駅近くの植物園内に「自然史博物館」として建築され、医学の実験と教育の場としてスタートしたことに始まる。一七三〇年代からは医学に自然科学、化学、物理学などが加えられた。そして二〇世紀に入って、万国博覧会のために建設されたシャイヨー宮のなかに、「旧民族誌博物館」の館長をしていた民族学者のポール・リヴェが考古学、民族学の講座のために収集したものと「自然史博物館」の形質人類関連の収蔵品と一体化させ、一九三七年に「人類博物館」を構成した。
この「人類博物館」の展示は、形質人類学、考古学そして民族学という三つのコンセプトでできていた。しかし、それぞれの物質にあった保存と展示が一致していないなどの問題が残されてしまった。今回オープンした「ケ・ブランリー博物館」に統合されたのは、おもに民族学の資料である。ところが「人類博物館」には依然として、形質人類学の展示は居残って人類の発達史や人種学などの展示が続いている。何も展示されていないホールの空間と人類誕生についてのわずかな展示は、来館者に統合の背後にある政治的な問題を感じさせるようだ。
三つ目は、今回の「ケ・ブランリー博物館」と直接関係ないものの、二一世紀に入って急速に研究も展示も不活発になり、二〇〇一年に閉館されたパリ西部のブローニュの森に建つ「民衆芸術・伝統博物館」(A・T・P)である。同館は、いわばフランス民俗博物館とでもいうべきもので、長きに渡る設置要請ののち一九七五年にやっと開館されたのだが、その後わずか二五年あまりで閉館されたことになる。
この博物館は一九三七年に先の「人類博物館」のなかで、当時革新的な博物館作りに貢献していた民族学者のジョルジュ・アンリ・リヴィエールがフランス中心のコレクションを集めて展示することをポール・リヴェから依頼されたことに始まる。彼は展示紹介と保存をする博物館学芸員の仕事と、収集品に関する国立科学研究センター(CNRS)の民族学者の研究とを連結させることにした。研究者と学芸員との連携・共同作業は、現実にはそれぞれの思わくどおりに進まず、資料の活用をめざした整備もうまく実施できなかったといわれている。リヴィエールが退任した後は展示の改良も進まず来館者も減少した。この博物館の特徴であった展示品の背景となる環境も展示されてあり、フランスの伝統的生活様式がひと目で理解できるめずらしいものであった。しかしレヴィ=ストロースを中心とする民族学的芸術理論に基づく展示の難しさは、一般大衆には遠ざけられてしまったようだ。
美学の視点をとり入れた展示
ポール・リヴェのもとで「人類博物館」の副館長をしていたジョルジュ・アンリ・リヴィエールは、民族学と美学の視点から収蔵品を選択して展示することを念頭においていた。したがって「人類博物館」からフランスの民俗資料を独立させて展示することを考え、ついに「民衆芸術・伝統博物館」の展示構想において物質文化そのままの展示ではなく、美的な視点からの展示を実現した。彼の人脈からしてもそれは明らかであった。彼の組織する調査隊には、ミッシェル・レリス、レオ・フロベニウス、ジョルジュ・バタイユなどが関係していたのだ。
こうした歴史的影響を受けてか、新しい「ケ・ブランリー博物館」では、構想段階より美的な視点からの展示をかかげていた。それはアール・プルミエと称するいわゆる原初的あるいは初期の芸術というものに焦点を当てようとしたことにあらわれている。しかもこれを博物館の名称にしようとしたとの噂もある。これにはたちまち多くの批判が浴びせられ、数年にして取り下げられた。そこで人類芸術文明博物館などの名称も考えられたが、いずれも適当ではないと批判された。
リヴィエールのめざした民族の織り成すさまざまなモノ造りの展示とは、そのモノの有効性や活用目的に付加されている美的な形態を展示によって引き出すことであった。
こうして新しい博物館の名称は建築現場の住所名「ケ・ブランリー」ということに落ち着いた。しかしかつてのように民族学的に比較できるモノの展示はなされないであろう。それは民族学自体が時代の流れに適さないことが指摘されているからである。いったい誰の基準で、調査、研究、展示の対象とすべきものを判断するのか、西洋からみた民族観でよいのか、といった疑問が投げかけられているのである。二年近くも開館が遅れた背景には、歴代大統領の一大企画の実現に際して、人事、経費、そして何よりも政治的な状況が次々と変化する、フランス文化の特色が見えている。
一九九五年フランス共和国の大統領選挙でジャック・シラクが当選すると、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカに関する芸術性の高いものや新しい美術品を展示する博物館の構想を打ち上げた。美術というからには、ほとんどアートに関係するものを展示すると考えられて構想が練られた。そしてこの新博物館に、トロカデロのシャイヨー宮にある「人類博物館」や、パリの東にある「アフリカ・オセアニア芸術博物館」などに収集されていた三〇万点以上の所蔵品から選別した三五〇〇点あまりが移されることになった。
これにともない、二〇〇四年暮れには、一部の展示をのぞき、両博物館とも展示場の大部分が縮小を余儀なくされた。それらの収蔵品は国の保管庫に収められ、新しい展示に向けて選別を待つこととなったのである。
民族・民俗展示のあゆみ
パリには二年ほど前まで民族学に関してふたつの博物館と、民俗学に関するひとつの博物館が一般に公開されていた。
ひとつは、パリ東部のヴァンセーヌの森、動物園近くのポルト・ドレに一九三五年に「海外フランス博物館」として大きく建てられ、その後に「アフリカ・オセアニア芸術博物館」となったものである。
初期の展示内容はフランス文学や美術における異国趣味、土着芸術、植民地領土についての博物館であった。当時のフランス植民地政策に役立ったとされている。
一九六〇年代に植民地の独立が世界的に進むとアンドレ・マルローによって博物館の名称と内容も変更された。アフリカ・オセアニアの芸術工芸品や民族美術とされる資料などを中心に展示した。収蔵品に関して「人類博物館」の協力を得て整理されるはずであったが、十分に実行されないまま新しい「ケ・ブランリー博物館」に入ってしまう。
ふたつ目の博物館は、観光名所として知られるトロカデロの丘に立つシャイヨー宮のなかの「人類博物館」である。その歴史は、一六三五年に、セーヌ左岸のオステルリッツ駅近くの植物園内に「自然史博物館」として建築され、医学の実験と教育の場としてスタートしたことに始まる。一七三〇年代からは医学に自然科学、化学、物理学などが加えられた。そして二〇世紀に入って、万国博覧会のために建設されたシャイヨー宮のなかに、「旧民族誌博物館」の館長をしていた民族学者のポール・リヴェが考古学、民族学の講座のために収集したものと「自然史博物館」の形質人類関連の収蔵品と一体化させ、一九三七年に「人類博物館」を構成した。
この「人類博物館」の展示は、形質人類学、考古学そして民族学という三つのコンセプトでできていた。しかし、それぞれの物質にあった保存と展示が一致していないなどの問題が残されてしまった。今回オープンした「ケ・ブランリー博物館」に統合されたのは、おもに民族学の資料である。ところが「人類博物館」には依然として、形質人類学の展示は居残って人類の発達史や人種学などの展示が続いている。何も展示されていないホールの空間と人類誕生についてのわずかな展示は、来館者に統合の背後にある政治的な問題を感じさせるようだ。
三つ目は、今回の「ケ・ブランリー博物館」と直接関係ないものの、二一世紀に入って急速に研究も展示も不活発になり、二〇〇一年に閉館されたパリ西部のブローニュの森に建つ「民衆芸術・伝統博物館」(A・T・P)である。同館は、いわばフランス民俗博物館とでもいうべきもので、長きに渡る設置要請ののち一九七五年にやっと開館されたのだが、その後わずか二五年あまりで閉館されたことになる。
この博物館は一九三七年に先の「人類博物館」のなかで、当時革新的な博物館作りに貢献していた民族学者のジョルジュ・アンリ・リヴィエールがフランス中心のコレクションを集めて展示することをポール・リヴェから依頼されたことに始まる。彼は展示紹介と保存をする博物館学芸員の仕事と、収集品に関する国立科学研究センター(CNRS)の民族学者の研究とを連結させることにした。研究者と学芸員との連携・共同作業は、現実にはそれぞれの思わくどおりに進まず、資料の活用をめざした整備もうまく実施できなかったといわれている。リヴィエールが退任した後は展示の改良も進まず来館者も減少した。この博物館の特徴であった展示品の背景となる環境も展示されてあり、フランスの伝統的生活様式がひと目で理解できるめずらしいものであった。しかしレヴィ=ストロースを中心とする民族学的芸術理論に基づく展示の難しさは、一般大衆には遠ざけられてしまったようだ。
美学の視点をとり入れた展示
ポール・リヴェのもとで「人類博物館」の副館長をしていたジョルジュ・アンリ・リヴィエールは、民族学と美学の視点から収蔵品を選択して展示することを念頭においていた。したがって「人類博物館」からフランスの民俗資料を独立させて展示することを考え、ついに「民衆芸術・伝統博物館」の展示構想において物質文化そのままの展示ではなく、美的な視点からの展示を実現した。彼の人脈からしてもそれは明らかであった。彼の組織する調査隊には、ミッシェル・レリス、レオ・フロベニウス、ジョルジュ・バタイユなどが関係していたのだ。
こうした歴史的影響を受けてか、新しい「ケ・ブランリー博物館」では、構想段階より美的な視点からの展示をかかげていた。それはアール・プルミエと称するいわゆる原初的あるいは初期の芸術というものに焦点を当てようとしたことにあらわれている。しかもこれを博物館の名称にしようとしたとの噂もある。これにはたちまち多くの批判が浴びせられ、数年にして取り下げられた。そこで人類芸術文明博物館などの名称も考えられたが、いずれも適当ではないと批判された。
リヴィエールのめざした民族の織り成すさまざまなモノ造りの展示とは、そのモノの有効性や活用目的に付加されている美的な形態を展示によって引き出すことであった。
こうして新しい博物館の名称は建築現場の住所名「ケ・ブランリー」ということに落ち着いた。しかしかつてのように民族学的に比較できるモノの展示はなされないであろう。それは民族学自体が時代の流れに適さないことが指摘されているからである。いったい誰の基準で、調査、研究、展示の対象とすべきものを判断するのか、西洋からみた民族観でよいのか、といった疑問が投げかけられているのである。二年近くも開館が遅れた背景には、歴代大統領の一大企画の実現に際して、人事、経費、そして何よりも政治的な状況が次々と変化する、フランス文化の特色が見えている。
奇妙な楽器―マトラカ―
楽器(標本番号H196376、高さ/17.0cm 幅/20.0cm 奥行/16.0cm)
楽器(標本番号H196376、高さ/17.0cm 幅/20.0cm 奥行/16.0cm)
ラテンアメリカには奇妙な楽器が少なくない。ちょっと見たところ楽器とはとても思えないものも楽器として利用している。このマトラカもそんな楽器のひとつかもしれない。マトラカは、専門用語では擦奏楽器、一般的には歯車のガラガラ(ラチェット)として知られているものである。すなわち、歯車状に彫った木の軸を回転させ、それに薄い木片をひっかけてガラガラという音が出るようになっている楽器である。しかし、これは、もともとはキリスト教の教会で使われていたものであり、しかも楽器としてではなく、教会の鐘のかわりの音を出す道具として使われていたらしい。キリスト教ではセマナ・サンタとよばれる聖週間の三日間は鐘が鳴らせないので、そのとき鐘のかわりにマトラカが使われていたのである。
ところが、現在、ラテンアメリカではこのマトラカを楽器としてさかんに利用するところがある。なかでもボリビアのラパス地方ではマトラカの人気は大変なもので、黒人を模したモレーノという踊りにはマトラカが欠かせない。奇抜なマスクをつけ、派手なマントをまとった人物が数十人、ときには一〇〇人以上もの多数の人がマトラカを「ガラッ、ガラッ」と鳴らしながら踊るのである。また、このラパスでは、マトラカの歯車部分を箱に入れ、その箱を共鳴体とするだけでなく、箱の上にしばしば動物や植物、乗り物などをかたどったものを乗せる。写真はソニーのビデオ・カメラを飾りにしたマトラカ。
ところが、現在、ラテンアメリカではこのマトラカを楽器としてさかんに利用するところがある。なかでもボリビアのラパス地方ではマトラカの人気は大変なもので、黒人を模したモレーノという踊りにはマトラカが欠かせない。奇抜なマスクをつけ、派手なマントをまとった人物が数十人、ときには一〇〇人以上もの多数の人がマトラカを「ガラッ、ガラッ」と鳴らしながら踊るのである。また、このラパスでは、マトラカの歯車部分を箱に入れ、その箱を共鳴体とするだけでなく、箱の上にしばしば動物や植物、乗り物などをかたどったものを乗せる。写真はソニーのビデオ・カメラを飾りにしたマトラカ。
友の会とミュージアム・ショップからのご案内
「テヘランゼルス」のノウルーズ
椿原 敦子
年末は踊って大騒ぎ
イラン暦の元日ノウルーズは、春分の日に当たる。人びとは新年を迎えるための準備として、家の大掃除や墓参り、来客用の食材の用意や、七つの縁起物を中心とする正月飾り、ハフト・スィーンの飾りつけなどをおこなう。イラン国外で最大の集住地域であり、イラン人のあいだで「テヘランゼルス」ともよばれるアメリカのロサンゼルス(LA)でも、人びとはノウルーズの準備に忙しい。LAには難民・亡命者から留学生まで出国の動機を異にするイラン人が暮らしている。一九七九年のイラン革命以来、アメリカとイランのあいだには国交がないが、人の往来は続いている。
わたしは、留学してきたばかりのS君と彼の母方の伯父とともに、海岸で催されたチャハールシャンベ・スーリーに参加した。年末最後の水曜日の夜に焚き火をし、その上を飛び越えて新年の無病息災を願う行事である。数年前までイランでは非合法とされていたこの行事だが、S君はLAと比べてテヘランの方が人びとは派手に大騒ぎしていると感想を漏らした。焚き火の傍には音響機材が運び込まれ、周りはペルシア語ポップスに乗って踊る人でごった返す。LAは亡命したポピュラー歌手たちの活動拠点であり、音楽への規制が厳しいイランへと海賊盤の流入が現在まで続いている。イランでは不特定多数の人が集まって踊る場はないため、S君にとって初めての機会である。踊っているS君の携帯にテヘランの母親から電話が入った。S君は母親に、テヘランとは違う祭りの光景を熱心に話していた。
イラン人の「口コミ社会」
この行事が終わると新年の準備が本格的に始まる。イラン系の食料品店にはこの時期だけ、ハフト・スィーンの飾りつけに欠かせないサブゼ(大麦などの新芽)や金魚が店頭に並ぶ。ゾロアスター教徒であるBさんの食料品店に飾られているハフト・スィーンには聖典アヴェスターが供えられていた。本国イランではコーランを飾るのが一般的だが、ハーフェズやルーミーの詩集を供えている家庭もあった。また、ノウルーズはバハーイー教の暦でも新年に当たる。Bさんの店で働くバハーイー教徒のFさんは、新年になるまでの一九日間は教義に従い断食をおこなっていた。
新年には、人びとは家族や友人の家を互いに訪問し合う。イラン系の商店が立ち並ぶウェストウッド通りで開かれた祭りには、一万人近い観客が集まった。そして連日、親戚や友人の家への訪問は続く。おしゃべりのなかでしばしば、新年の一三日目に外出する行事「スィーズダ・ベ・ダル」はどこに行くか、という話題が出た。そこで、行き先として皆がそろって口にするのがカリフォルニア南部のとある公園なのである。残念ながらその日まで滞在する事ができなかったが、さぞかし多くの人が集まっただろう。家庭を訪問しての交流があらたな人間関係を作り、それが大規模な人の集まりを作る。「口コミ社会」といわれるLAのイラン人社会のからくりを見た気がした。
イラン暦の元日ノウルーズは、春分の日に当たる。人びとは新年を迎えるための準備として、家の大掃除や墓参り、来客用の食材の用意や、七つの縁起物を中心とする正月飾り、ハフト・スィーンの飾りつけなどをおこなう。イラン国外で最大の集住地域であり、イラン人のあいだで「テヘランゼルス」ともよばれるアメリカのロサンゼルス(LA)でも、人びとはノウルーズの準備に忙しい。LAには難民・亡命者から留学生まで出国の動機を異にするイラン人が暮らしている。一九七九年のイラン革命以来、アメリカとイランのあいだには国交がないが、人の往来は続いている。
わたしは、留学してきたばかりのS君と彼の母方の伯父とともに、海岸で催されたチャハールシャンベ・スーリーに参加した。年末最後の水曜日の夜に焚き火をし、その上を飛び越えて新年の無病息災を願う行事である。数年前までイランでは非合法とされていたこの行事だが、S君はLAと比べてテヘランの方が人びとは派手に大騒ぎしていると感想を漏らした。焚き火の傍には音響機材が運び込まれ、周りはペルシア語ポップスに乗って踊る人でごった返す。LAは亡命したポピュラー歌手たちの活動拠点であり、音楽への規制が厳しいイランへと海賊盤の流入が現在まで続いている。イランでは不特定多数の人が集まって踊る場はないため、S君にとって初めての機会である。踊っているS君の携帯にテヘランの母親から電話が入った。S君は母親に、テヘランとは違う祭りの光景を熱心に話していた。
イラン人の「口コミ社会」
この行事が終わると新年の準備が本格的に始まる。イラン系の食料品店にはこの時期だけ、ハフト・スィーンの飾りつけに欠かせないサブゼ(大麦などの新芽)や金魚が店頭に並ぶ。ゾロアスター教徒であるBさんの食料品店に飾られているハフト・スィーンには聖典アヴェスターが供えられていた。本国イランではコーランを飾るのが一般的だが、ハーフェズやルーミーの詩集を供えている家庭もあった。また、ノウルーズはバハーイー教の暦でも新年に当たる。Bさんの店で働くバハーイー教徒のFさんは、新年になるまでの一九日間は教義に従い断食をおこなっていた。
新年には、人びとは家族や友人の家を互いに訪問し合う。イラン系の商店が立ち並ぶウェストウッド通りで開かれた祭りには、一万人近い観客が集まった。そして連日、親戚や友人の家への訪問は続く。おしゃべりのなかでしばしば、新年の一三日目に外出する行事「スィーズダ・ベ・ダル」はどこに行くか、という話題が出た。そこで、行き先として皆がそろって口にするのがカリフォルニア南部のとある公園なのである。残念ながらその日まで滞在する事ができなかったが、さぞかし多くの人が集まっただろう。家庭を訪問しての交流があらたな人間関係を作り、それが大規模な人の集まりを作る。「口コミ社会」といわれるLAのイラン人社会のからくりを見た気がした。
島嶼(とうしょ)国の民主主義とストライキ
須藤 健一
ソロモンでの外国糾弾
二〇世紀末、インドネシアでは東ティモールやパプア州の独立紛争、フィジーのクーデター、そしてソロモンの民族対立があいついで起きた。これらは、独立運動と土地・資源・経済開発をめぐる住民の「不満」や「妬み」が民族の争いへと発展したものである。オーストラリアは、これらの地域を「オセアニアの不安定弧」とよび、平和維持軍を派遣するなど治安の回復に努力してきた。
しかし、今年四月にソロモンの人びとが騒動を起こした。中国から経済支援(賄賂?)を受けた首相を辞任させ、中国人の企業や商店を襲撃したのである。この動きは、二〇〇〇年の土地と経済開発をめぐる島・民族間の対立とは様相を異にする。「外国からの不正」を糾弾するナショナリズム的な動きといえよう。
トンガの公務員がストライキ
一方、人口およそ一〇万人のトンガでは、昨年七月に五〇〇〇人の公務員が七週間におよぶストライキを決行した。トンガは、一八七五年に憲法を制定して近代国家の建設を進めた。その憲法は、わが国の明治憲法と同じ「欽定憲法」。現国王、ツポウ四世は「現人神」ではないが、元首、元帥、枢密院議長で司法・立法・行政の長を任命する。三〇名の国会議員のうち民選議員は九名、あとは王の指名。ツポウ王朝は王族・貴族・平民の身分制をしいて、表面上「平安な国家」を運営しているかに見える。
ストライキの主目的は、二〇年間据え置かれた給料の賃上げである。同時に、国家資源の公平分配、憲法改正による王権力の規制、普通選挙の実施など、国民の民主化を求める積年の不満が背景にある。最下級の公務員年収は一二万円、次官クラスでも二四〇万円。それに対し国王の俸給は一四〇〇万円。その他、王族は携帯電話や通信、電気事業などの経営権を独占し、広大な王族地を所有する。王に忠誠を誓い、平和国家の公僕であれとはいえ、公務員の給料はあまりにも低い。
公務員のストライキには、高校生もキリスト教の聖職者も参加し、企業家も多額の資金と食糧を寄付し、海外のトンガ人も支援した。結局、政府はその弾圧をあきらめ、公務員の給料の平均七〇パーセントのアップと「憲法改正委員会」設置の要求を受け入れた。ストライキに対応できなかった首相(王の三男)は解任。現在、トンガ初の平民首相が誕生し、憲法改正案の骨子もできつつある。
オセアニアの島嶼国は、近代的な政治体制を導入し、かつ伝統首長の地位と役割を温存してきた。かつての首長は、現在の「民主主義」よりも「住民主体」の統治をしたといわれる。独立後、首長も国家エリートも、欧米の政治と「伝統の政治」との接合に苦心している。しかし、彼らの多くは、権力者としての「利権」を当然とみなすと批判される。ソロモンとトンガの昨年来の出来事は、住民が権力者の「不正」や開発独裁ぶりをただし、自分たちとの格差を是正するための新しい自己主張の兆しであるといえよう。
二〇世紀末、インドネシアでは東ティモールやパプア州の独立紛争、フィジーのクーデター、そしてソロモンの民族対立があいついで起きた。これらは、独立運動と土地・資源・経済開発をめぐる住民の「不満」や「妬み」が民族の争いへと発展したものである。オーストラリアは、これらの地域を「オセアニアの不安定弧」とよび、平和維持軍を派遣するなど治安の回復に努力してきた。
しかし、今年四月にソロモンの人びとが騒動を起こした。中国から経済支援(賄賂?)を受けた首相を辞任させ、中国人の企業や商店を襲撃したのである。この動きは、二〇〇〇年の土地と経済開発をめぐる島・民族間の対立とは様相を異にする。「外国からの不正」を糾弾するナショナリズム的な動きといえよう。
トンガの公務員がストライキ
一方、人口およそ一〇万人のトンガでは、昨年七月に五〇〇〇人の公務員が七週間におよぶストライキを決行した。トンガは、一八七五年に憲法を制定して近代国家の建設を進めた。その憲法は、わが国の明治憲法と同じ「欽定憲法」。現国王、ツポウ四世は「現人神」ではないが、元首、元帥、枢密院議長で司法・立法・行政の長を任命する。三〇名の国会議員のうち民選議員は九名、あとは王の指名。ツポウ王朝は王族・貴族・平民の身分制をしいて、表面上「平安な国家」を運営しているかに見える。
ストライキの主目的は、二〇年間据え置かれた給料の賃上げである。同時に、国家資源の公平分配、憲法改正による王権力の規制、普通選挙の実施など、国民の民主化を求める積年の不満が背景にある。最下級の公務員年収は一二万円、次官クラスでも二四〇万円。それに対し国王の俸給は一四〇〇万円。その他、王族は携帯電話や通信、電気事業などの経営権を独占し、広大な王族地を所有する。王に忠誠を誓い、平和国家の公僕であれとはいえ、公務員の給料はあまりにも低い。
公務員のストライキには、高校生もキリスト教の聖職者も参加し、企業家も多額の資金と食糧を寄付し、海外のトンガ人も支援した。結局、政府はその弾圧をあきらめ、公務員の給料の平均七〇パーセントのアップと「憲法改正委員会」設置の要求を受け入れた。ストライキに対応できなかった首相(王の三男)は解任。現在、トンガ初の平民首相が誕生し、憲法改正案の骨子もできつつある。
オセアニアの島嶼国は、近代的な政治体制を導入し、かつ伝統首長の地位と役割を温存してきた。かつての首長は、現在の「民主主義」よりも「住民主体」の統治をしたといわれる。独立後、首長も国家エリートも、欧米の政治と「伝統の政治」との接合に苦心している。しかし、彼らの多くは、権力者としての「利権」を当然とみなすと批判される。ソロモンとトンガの昨年来の出来事は、住民が権力者の「不正」や開発独裁ぶりをただし、自分たちとの格差を是正するための新しい自己主張の兆しであるといえよう。
ラジャブザーデさんの引越し
藤元 優子
日本人になったイラン人
ハーシェム・ラジャブザーデさんとわたしとの同僚としてのおつきあいは、もうかれこれ二〇年にもなる。外国語大学という職場の性格上、外国人の先生は数多くお見かけするが、彼ほど手のかからない人はほとんどいないだろう。大阪に赴任する前に、東京の大使館で四年、大学で二年半過ごしたので、日本語の日常会話には問題ない。独り身の身軽さもあってかフットワークが軽く、外交官時代の友人知己を含め、日本人との交友関係もわたしなどより何倍も広い。そのうえ、分厚い『日本史』をまとめたほか、『徒然草』や『坊っちゃん』など、日本文学のペルシア語翻訳も出版しているほどの日本通である。日常生活の援助などほとんど必要ないどころか、例えば京都の古道具屋はたぶん踏破しているし、良質の和紙はどの店にある、などと教えていただいたりする。
わたしはよく学生に、「イラン人がみんなラジャブザーデ先生みたいだと思っていると、イランに行ってびっくりするからね」と冗談めかして言う。彼の小柄な痩身からは、几帳面、律儀、生真面目、勤勉、それに謙譲という美徳のオーラが放たれている。約束厳守、研究一筋、休講皆無。イランやペルシア語について一言質問すれば、出典のコピーつきで詳細に答えてくれる。さまざまな書類も本も、どのように整理されているのか、必要とあればたちどころに出てくる。交渉事は粘り強くおこなって最後までやり遂げるが、自己顕示欲は強くない。十把一絡げの危険性は承知のうえで言わせてもらえば、彼は「イラン人らしく」ない。と言うより、これじゃあまるで「昔の日本人」の美点のオンパレードだ。彼自身、「あんまり長く日本にいたので、日本人になってしまいました」などと言ったりもする。
終の棲み家を北摂へ
そんなラジャブザーデさんが、来年三月の停年を前に、二〇年以上暮らした大学宿舎の小さなアパートを出て、北摂(大阪府北部)に家を建てた。一九七九年のイスラーム革命後、お上に召し上げられてしまった土地の対価を大統領に直訴してようやくとり返したお蔭とはいえ、ローンまで組んで臨んだ大きな買い物である。彼は何を思って、家族も親戚もいない大阪の新興住宅地に終の棲み家を求めたのだろうか。彼は奥ゆかしくてあまり自分の思いを語らないので、根掘り葉掘り聞いてみた。
ひとつは、理想の追求。イランと日本の文化交流に半生を捧げてきた者として、彼は自宅に私設図書館を作り、イランの美術品も展示して、研究者や学生に提供したいと考えていた。実際、歴史や旅行記を中心とする五〇〇〇冊余りの蔵書は、個人蔵としては国内で稀有のコレクションである。将来的には、どこかの大学と契約を結んで、付属の研究所にしてもらえたら、と彼は願う。じつは過去に、古代ペルシアと縁のある奈良の明日香村に土地を求めようと動いた時期もあって、村長との面会も果たしたのだが、うまくいかなかった。そうでなくてもよそ者を受け入れにくい土地柄に加え、イランといえば「怖いところ」という固定観念が植えつけられてしまっているのを感じたと言う。苦い思い出である。
ふたつめは、引退後の生活の安寧。授業に縛られる生活から解き放たれて、研究に没頭したいが、イランは騒がし過ぎる。図書館兼ギャラリーの運営も問題が多いし、第一、友人知人とのつきあいに疲れるに違いない、と彼は思う。要するに、しがらみがない日本に軍配が上がったのである。
そして、日本への思い入れの強さ。四半世紀のあいだ日本で暮らして、日本社会の変化も目撃してきたが、「それでも日本人の誠実さ、忍耐強さ、礼儀正しさ、秩序正しさは、世界に類を見ない」と彼は言い切る。三年前、外国人登録の更新に行った際、担当官に永住許可申請を勧められ、とんとん拍子に手続きが終わったことも、彼の背中を押した。
日本体験の正念場
こうして、大手ハウスメーカーと契約したものの、今年一月の完成までには紆余曲折があったと思われる。凝り性だから、型にはまった製品を使いたがるメーカーとのあいだの溝を埋めるために苦労したそうだ。面倒な契約などには東京から日本人の友人が駆けつけ、イランからは妹さん親子がこだわりのタイル類など一〇〇キログラムもの荷物を運んできた。新居の扉を開ければ、床はペルシア絨毯の花園、作りつけの書架にはペルシア語の本が並べられているが、天井には日本の古い灯りが吊るされ、部屋の隅の行灯には、ペルシア書道で古典詩が書かれた和紙が貼られている。家の契約から造作・装飾まで、まさに日イの合作、折衷の賜物なのだ。
もしかすると、これからが彼の「日本体験」の正念場なのかもしれない、とわたしは思う。外国人恩給生活者に、ローンは、税金は、保険料は、重くのしかからないか。人間関係の希薄なニュータウンで孤立してしまわないか。心配は尽きない。どうか前庭に植えたシンボルツリーの柘榴(ざくろ)の木が豊かな実をつけ、千客万来の「ペルシア文庫」がイラン研究者のオアシスになりますように。
ハーシェム・ラジャブザーデさんとわたしとの同僚としてのおつきあいは、もうかれこれ二〇年にもなる。外国語大学という職場の性格上、外国人の先生は数多くお見かけするが、彼ほど手のかからない人はほとんどいないだろう。大阪に赴任する前に、東京の大使館で四年、大学で二年半過ごしたので、日本語の日常会話には問題ない。独り身の身軽さもあってかフットワークが軽く、外交官時代の友人知己を含め、日本人との交友関係もわたしなどより何倍も広い。そのうえ、分厚い『日本史』をまとめたほか、『徒然草』や『坊っちゃん』など、日本文学のペルシア語翻訳も出版しているほどの日本通である。日常生活の援助などほとんど必要ないどころか、例えば京都の古道具屋はたぶん踏破しているし、良質の和紙はどの店にある、などと教えていただいたりする。
わたしはよく学生に、「イラン人がみんなラジャブザーデ先生みたいだと思っていると、イランに行ってびっくりするからね」と冗談めかして言う。彼の小柄な痩身からは、几帳面、律儀、生真面目、勤勉、それに謙譲という美徳のオーラが放たれている。約束厳守、研究一筋、休講皆無。イランやペルシア語について一言質問すれば、出典のコピーつきで詳細に答えてくれる。さまざまな書類も本も、どのように整理されているのか、必要とあればたちどころに出てくる。交渉事は粘り強くおこなって最後までやり遂げるが、自己顕示欲は強くない。十把一絡げの危険性は承知のうえで言わせてもらえば、彼は「イラン人らしく」ない。と言うより、これじゃあまるで「昔の日本人」の美点のオンパレードだ。彼自身、「あんまり長く日本にいたので、日本人になってしまいました」などと言ったりもする。
終の棲み家を北摂へ
そんなラジャブザーデさんが、来年三月の停年を前に、二〇年以上暮らした大学宿舎の小さなアパートを出て、北摂(大阪府北部)に家を建てた。一九七九年のイスラーム革命後、お上に召し上げられてしまった土地の対価を大統領に直訴してようやくとり返したお蔭とはいえ、ローンまで組んで臨んだ大きな買い物である。彼は何を思って、家族も親戚もいない大阪の新興住宅地に終の棲み家を求めたのだろうか。彼は奥ゆかしくてあまり自分の思いを語らないので、根掘り葉掘り聞いてみた。
ひとつは、理想の追求。イランと日本の文化交流に半生を捧げてきた者として、彼は自宅に私設図書館を作り、イランの美術品も展示して、研究者や学生に提供したいと考えていた。実際、歴史や旅行記を中心とする五〇〇〇冊余りの蔵書は、個人蔵としては国内で稀有のコレクションである。将来的には、どこかの大学と契約を結んで、付属の研究所にしてもらえたら、と彼は願う。じつは過去に、古代ペルシアと縁のある奈良の明日香村に土地を求めようと動いた時期もあって、村長との面会も果たしたのだが、うまくいかなかった。そうでなくてもよそ者を受け入れにくい土地柄に加え、イランといえば「怖いところ」という固定観念が植えつけられてしまっているのを感じたと言う。苦い思い出である。
ふたつめは、引退後の生活の安寧。授業に縛られる生活から解き放たれて、研究に没頭したいが、イランは騒がし過ぎる。図書館兼ギャラリーの運営も問題が多いし、第一、友人知人とのつきあいに疲れるに違いない、と彼は思う。要するに、しがらみがない日本に軍配が上がったのである。
そして、日本への思い入れの強さ。四半世紀のあいだ日本で暮らして、日本社会の変化も目撃してきたが、「それでも日本人の誠実さ、忍耐強さ、礼儀正しさ、秩序正しさは、世界に類を見ない」と彼は言い切る。三年前、外国人登録の更新に行った際、担当官に永住許可申請を勧められ、とんとん拍子に手続きが終わったことも、彼の背中を押した。
日本体験の正念場
こうして、大手ハウスメーカーと契約したものの、今年一月の完成までには紆余曲折があったと思われる。凝り性だから、型にはまった製品を使いたがるメーカーとのあいだの溝を埋めるために苦労したそうだ。面倒な契約などには東京から日本人の友人が駆けつけ、イランからは妹さん親子がこだわりのタイル類など一〇〇キログラムもの荷物を運んできた。新居の扉を開ければ、床はペルシア絨毯の花園、作りつけの書架にはペルシア語の本が並べられているが、天井には日本の古い灯りが吊るされ、部屋の隅の行灯には、ペルシア書道で古典詩が書かれた和紙が貼られている。家の契約から造作・装飾まで、まさに日イの合作、折衷の賜物なのだ。
もしかすると、これからが彼の「日本体験」の正念場なのかもしれない、とわたしは思う。外国人恩給生活者に、ローンは、税金は、保険料は、重くのしかからないか。人間関係の希薄なニュータウンで孤立してしまわないか。心配は尽きない。どうか前庭に植えたシンボルツリーの柘榴(ざくろ)の木が豊かな実をつけ、千客万来の「ペルシア文庫」がイラン研究者のオアシスになりますように。
物は町に、情報は村に―反比例の関係―
メキシコ大地震に遭遇
たくさんのお金をもって、たくさんの品物を買い求め、安全に日本まで輸送するという作業は、日ごろの研究生活とはおよそかけ離れた行為である。だから問題なくことを運ぼうと思うほうがどだい無理な話である。それにもかかわらず、中米の民族資料の充実を図るために、わたしは収集を、それも懲りもせず、三回もおこなった。幸い現地での多くの人の協力のお蔭で、無事に収集をおこなうことができたが、地震にあったり、大雨にあったり、車がエンストしたり、小さなトラブルは数え切れない。
地球が活発期に入ったのか、グアテマラやメキシコでも大きな地震が起こっている。なかでも一九八五年九月一九日の朝に起こったメキシコ大地震は忘れがたい。ゆるやかな揺れがなかなか止まらない。地震には慣れっこになっているので、地震が起きたときにはベッドの下や机の下に隠れろとかいっていたなとのんきに構えているうちに、戸は開く、天井や壁がバラバラ落ちてくる。どうもふつうの地震とは違う。さすがにこれはやばいと思い、ホテルの六階から瓦礫だらけとなった階段をあわてて降りた。町に出てみると、ビルが至るところで崩壊している。二〇日近く収集した物を倉庫を借りて入れていたが、その一帯はひどい被害で、すぐさま立ち入り禁止になってしまい、近づけない。どうしようもないので、先にグアテマラの収集をおこなうべく、メキシコをあとにした。幸い倉庫も品物も無事であったが、倉庫が潰れていたら、違うホテルに泊まっていたら、と思うと、今さらながら運の良さを感じる。
べリーズでは大雨に立ち往生
一九九三年に行ったベリーズでは、なぜかトラブル続きであった。南に住むモパン人の町サン・アントニオをたずねるために、ベリーズ市でジープを借りて出発したとたん、エンジンの調子が悪く、引き返さざるをえなくなった。時間をロスしないよう、車を換えてもらい、すぐ再出発した。ところが今度は途中でパンクである。これはよくあることで、レンチを出してタイヤを交換しようとしたところ、レンチが摩耗していて、困ったことにボルトがはずれない。ベリーズは、近畿五府県を足したほどの面積に、たった二〇万人ほどしか住人がいない。だからベリーズ市を出ると、ほとんど人に会うことがない。二時間経っても、三時間経っても、車は一台もとおらない。どうしようもないので、覚悟を決めて野宿するしかないかと考え始めた矢先、幸運の女神が一台のジープをよこした。事情を話し、レンチを借りるとなんとぴったり合うではないか。次の町で、パンクを修理して、ガリフナ人の資料を集めた後、目的地のプンタ・ゴルダに着いたのは、夜中であった。
次の日、サン・アントニオに行き、モパン人の家をたずね歩いたが、どこも留守。やっと出会った人の家で、お目当ての衣服のほか、椅子や道具など、目につくものいっさいがっさい求めようとしたが、わずかしか集まらなかった。その夜戻ったプンタ・ゴルダでは、激しい雨が降った。次の日、帰ろうと思って出発すると、道路が冠水して、どこにあるやらわからぬ状態である。すぐ水が引くであろうと思って待つが、なかなか引かない。このままもう一晩泊まって、また夜に雨が降ると事態はさらに悪くなる。何しろ雨季の真っ最中である。幸い昼過ぎになってやっと道路が見え出したので、そろそろと前の車の後について帰路に着く。ところが途中で、来るとき渡ったほんの数メートルの小川が、マヤ山地の水を集め濁流と化しているではないか。ずっと先に出発したバスが立ち往生して、長い列ができている。無理して渡る車がよく流されるのだという。夕方になって流れが少しは緩やかになり、バスが出発する。しかし小さな車なので、なかなか踏ん切りがつかず、さらに待つ。夕闇が迫るころ、意を決して渡ることにした。こわごわ窓の外を見ると座席上あたりまで浸水しているではないか。何とか渡り切ったものの、もうへとへとである。それからベリーズ市まではまだまだ距離があったが、何とか深夜にたどり着いた。
データを集めながら収集を
祭りや市が立つ日には、風呂敷に物を包んで背負い、片手にはラジオ、もう一方には山刀姿の男たちをよく見かける。女たちはというと、頭に風呂敷包みを乗せ、背に子どもを背負った姿が一般的である。おそらくもち歩いている物は大切な家財道具一式であろう。だから村に収集に行くと、使われている状況や物についての情報は確かに集まるが、苦労して村に行ったわりには、物は少ししか集まらない。たくさん物を集めようと思うと、町にかぎるが、物の情報はそれに反比例する。
最近の博物館や美術館は、休憩スペースがふんだんにとってあって、ゆったりしている。それに引き替え、民博の展示場では、物がところ狭しと並んでいる。日本が元気のいいときに展示されたためで、休憩スペースなど考えもしなかった。収集も、展示を充実させるために、まずは基本的な物をできるだけたくさん集めることが必要であった。
外国のあるチームが一年かけて土器を丹念に収集したという本を手にし、羨望(せんぼう)に駆られたことがある。わたしの収集はそれとは対極的な収集であった。基本的な資料が集まった現在、半年とか一年をかけて、じっくりとデータを集めながら収集をすることが望ましい。そんな提案を何年も前にしたのであるが、実現していない。効率とか成果とかが優先され、まだまだゆったりした考えが浸透していない。それはまだ日本が元気のいい証拠なのであろうか。
たくさんのお金をもって、たくさんの品物を買い求め、安全に日本まで輸送するという作業は、日ごろの研究生活とはおよそかけ離れた行為である。だから問題なくことを運ぼうと思うほうがどだい無理な話である。それにもかかわらず、中米の民族資料の充実を図るために、わたしは収集を、それも懲りもせず、三回もおこなった。幸い現地での多くの人の協力のお蔭で、無事に収集をおこなうことができたが、地震にあったり、大雨にあったり、車がエンストしたり、小さなトラブルは数え切れない。
地球が活発期に入ったのか、グアテマラやメキシコでも大きな地震が起こっている。なかでも一九八五年九月一九日の朝に起こったメキシコ大地震は忘れがたい。ゆるやかな揺れがなかなか止まらない。地震には慣れっこになっているので、地震が起きたときにはベッドの下や机の下に隠れろとかいっていたなとのんきに構えているうちに、戸は開く、天井や壁がバラバラ落ちてくる。どうもふつうの地震とは違う。さすがにこれはやばいと思い、ホテルの六階から瓦礫だらけとなった階段をあわてて降りた。町に出てみると、ビルが至るところで崩壊している。二〇日近く収集した物を倉庫を借りて入れていたが、その一帯はひどい被害で、すぐさま立ち入り禁止になってしまい、近づけない。どうしようもないので、先にグアテマラの収集をおこなうべく、メキシコをあとにした。幸い倉庫も品物も無事であったが、倉庫が潰れていたら、違うホテルに泊まっていたら、と思うと、今さらながら運の良さを感じる。
べリーズでは大雨に立ち往生
一九九三年に行ったベリーズでは、なぜかトラブル続きであった。南に住むモパン人の町サン・アントニオをたずねるために、ベリーズ市でジープを借りて出発したとたん、エンジンの調子が悪く、引き返さざるをえなくなった。時間をロスしないよう、車を換えてもらい、すぐ再出発した。ところが今度は途中でパンクである。これはよくあることで、レンチを出してタイヤを交換しようとしたところ、レンチが摩耗していて、困ったことにボルトがはずれない。ベリーズは、近畿五府県を足したほどの面積に、たった二〇万人ほどしか住人がいない。だからベリーズ市を出ると、ほとんど人に会うことがない。二時間経っても、三時間経っても、車は一台もとおらない。どうしようもないので、覚悟を決めて野宿するしかないかと考え始めた矢先、幸運の女神が一台のジープをよこした。事情を話し、レンチを借りるとなんとぴったり合うではないか。次の町で、パンクを修理して、ガリフナ人の資料を集めた後、目的地のプンタ・ゴルダに着いたのは、夜中であった。
次の日、サン・アントニオに行き、モパン人の家をたずね歩いたが、どこも留守。やっと出会った人の家で、お目当ての衣服のほか、椅子や道具など、目につくものいっさいがっさい求めようとしたが、わずかしか集まらなかった。その夜戻ったプンタ・ゴルダでは、激しい雨が降った。次の日、帰ろうと思って出発すると、道路が冠水して、どこにあるやらわからぬ状態である。すぐ水が引くであろうと思って待つが、なかなか引かない。このままもう一晩泊まって、また夜に雨が降ると事態はさらに悪くなる。何しろ雨季の真っ最中である。幸い昼過ぎになってやっと道路が見え出したので、そろそろと前の車の後について帰路に着く。ところが途中で、来るとき渡ったほんの数メートルの小川が、マヤ山地の水を集め濁流と化しているではないか。ずっと先に出発したバスが立ち往生して、長い列ができている。無理して渡る車がよく流されるのだという。夕方になって流れが少しは緩やかになり、バスが出発する。しかし小さな車なので、なかなか踏ん切りがつかず、さらに待つ。夕闇が迫るころ、意を決して渡ることにした。こわごわ窓の外を見ると座席上あたりまで浸水しているではないか。何とか渡り切ったものの、もうへとへとである。それからベリーズ市まではまだまだ距離があったが、何とか深夜にたどり着いた。
データを集めながら収集を
祭りや市が立つ日には、風呂敷に物を包んで背負い、片手にはラジオ、もう一方には山刀姿の男たちをよく見かける。女たちはというと、頭に風呂敷包みを乗せ、背に子どもを背負った姿が一般的である。おそらくもち歩いている物は大切な家財道具一式であろう。だから村に収集に行くと、使われている状況や物についての情報は確かに集まるが、苦労して村に行ったわりには、物は少ししか集まらない。たくさん物を集めようと思うと、町にかぎるが、物の情報はそれに反比例する。
最近の博物館や美術館は、休憩スペースがふんだんにとってあって、ゆったりしている。それに引き替え、民博の展示場では、物がところ狭しと並んでいる。日本が元気のいいときに展示されたためで、休憩スペースなど考えもしなかった。収集も、展示を充実させるために、まずは基本的な物をできるだけたくさん集めることが必要であった。
外国のあるチームが一年かけて土器を丹念に収集したという本を手にし、羨望(せんぼう)に駆られたことがある。わたしの収集はそれとは対極的な収集であった。基本的な資料が集まった現在、半年とか一年をかけて、じっくりとデータを集めながら収集をすることが望ましい。そんな提案を何年も前にしたのであるが、実現していない。効率とか成果とかが優先され、まだまだゆったりした考えが浸透していない。それはまだ日本が元気のいい証拠なのであろうか。
トウモロコシから生まれたマヤ文明
青山 和夫
マヤ文明の原動力のひとつ
わたしは、中米のホンジュラスで一〇年間マヤ文明の調査に従事した。主食は、何といってもトウモロコシである。トウモロコシは、乾燥・貯蔵が容易であり、その余剰生産は、マヤ文明を生み出した原動力のひとつであった。日本の天皇が稲作の儀礼に深くかかわってきたのと同様に、トウモロコシは、古代マヤの王権や精神世界においても重要であった。古代マヤの王は、宗教儀礼においてトウモロコシの神をはじめ、さまざまな神の仮面・衣装・装飾品を着用して、しばしば神の役割を果たした。古代マヤの東西南北の色は、それぞれ、赤、黒、黄、白で古代中国の概念と酷似するが、マヤの場合は四種類のトウモロコシの色と対応した。トウモロコシは、スペイン人が一六世紀に侵略した後も、現在に至るまで中米の主作物である。ホンジュラスにあるマヤ文明の大都市遺跡コパン(ユネスコ世界遺産)でも、発掘作業員兼農民のマヤ系先住民の話題の中心は、トウモロコシの発育状況とサッカーである。
できたてトルティーヤのおいしさ
ホンジュラスは、わたしの妻ビルマと長女さくらが生まれた国である。トウモロコシを製粉して、さまざまな料理を作るのが一般的である(日本と同様に、トウモロコシをそのままゆでたり、炭火で焼いて食べることもある)。食用の石灰水に一晩漬けたトウモロコシの粒を、伝統的な調理法では、製粉用の石盤メタテと紡錘形の石棒マノを使って挽き潰し、マサとよばれる練り粉の玉を作る。そこから必要量をとり、薄く平たい円形にして、土製板や鉄板の上で焼いたのが、トルティーヤである。挽き立ての練り粉で手作りした、分厚く、ほかほかのトルティーヤほどおいしいものはないといつも思う。首都のテグシガルパ市でも、昼時になると、できたてのトルティーヤを大きな籠に入れた女性が、「トルティーヤはいりませんか! できたてだよ! わたしのトルティーヤはもっと大きいよ」と大声で叫びながら家々を回っていく光景が見られる。
多様でハイブリッドな料理法
トルティーヤが広まる以前のマヤ文明では、トウモロコシは、トウモロコシの粉を水にとかして飲むポソレやアトレ、蒸し団子のタマルとして食用されていた。一六世紀以降に旧大陸起源の食材を取り入れた現代のタマルは、ハイブリッドな食文化を反映する。マサを砂糖や塩で味つけしてトウモロコシの苞葉で包んで蒸した小型タマルのタマリート・デ・エロテや、鶏や豚の肉をマサでくるみトウモロコシの苞葉(ほうよう)で包んで蒸したモントゥーカ、マサのなかに鶏や豚の肉を入れてプランテン・バナナの葉に包んで蒸したタマル、そしてホンジュラスの「タマルの王様」といえる、クリスマスに欠かせない大型のナカタマルなどがある。
トルティーヤは、タコ(複数形はタコス)の皮でもある。ホンジュラスのタコスは、鶏肉か牛肉に、みじん切りにしたジャガイモやタマネギを加えて炒めトルティーヤで巻き、油で揚げるのが特徴である。ぱりぱりとした食感で、ビールのつまみにも合う。トルティーヤにチーズを挟んで焼いたケサディーヤや、マサにチーズを加えてドーナツ型にしてオーブンで焼いたロスキーヤは、朝食やおやつとして好まれる。
わたしは、中米のホンジュラスで一〇年間マヤ文明の調査に従事した。主食は、何といってもトウモロコシである。トウモロコシは、乾燥・貯蔵が容易であり、その余剰生産は、マヤ文明を生み出した原動力のひとつであった。日本の天皇が稲作の儀礼に深くかかわってきたのと同様に、トウモロコシは、古代マヤの王権や精神世界においても重要であった。古代マヤの王は、宗教儀礼においてトウモロコシの神をはじめ、さまざまな神の仮面・衣装・装飾品を着用して、しばしば神の役割を果たした。古代マヤの東西南北の色は、それぞれ、赤、黒、黄、白で古代中国の概念と酷似するが、マヤの場合は四種類のトウモロコシの色と対応した。トウモロコシは、スペイン人が一六世紀に侵略した後も、現在に至るまで中米の主作物である。ホンジュラスにあるマヤ文明の大都市遺跡コパン(ユネスコ世界遺産)でも、発掘作業員兼農民のマヤ系先住民の話題の中心は、トウモロコシの発育状況とサッカーである。
できたてトルティーヤのおいしさ
ホンジュラスは、わたしの妻ビルマと長女さくらが生まれた国である。トウモロコシを製粉して、さまざまな料理を作るのが一般的である(日本と同様に、トウモロコシをそのままゆでたり、炭火で焼いて食べることもある)。食用の石灰水に一晩漬けたトウモロコシの粒を、伝統的な調理法では、製粉用の石盤メタテと紡錘形の石棒マノを使って挽き潰し、マサとよばれる練り粉の玉を作る。そこから必要量をとり、薄く平たい円形にして、土製板や鉄板の上で焼いたのが、トルティーヤである。挽き立ての練り粉で手作りした、分厚く、ほかほかのトルティーヤほどおいしいものはないといつも思う。首都のテグシガルパ市でも、昼時になると、できたてのトルティーヤを大きな籠に入れた女性が、「トルティーヤはいりませんか! できたてだよ! わたしのトルティーヤはもっと大きいよ」と大声で叫びながら家々を回っていく光景が見られる。
多様でハイブリッドな料理法
トルティーヤが広まる以前のマヤ文明では、トウモロコシは、トウモロコシの粉を水にとかして飲むポソレやアトレ、蒸し団子のタマルとして食用されていた。一六世紀以降に旧大陸起源の食材を取り入れた現代のタマルは、ハイブリッドな食文化を反映する。マサを砂糖や塩で味つけしてトウモロコシの苞葉で包んで蒸した小型タマルのタマリート・デ・エロテや、鶏や豚の肉をマサでくるみトウモロコシの苞葉(ほうよう)で包んで蒸したモントゥーカ、マサのなかに鶏や豚の肉を入れてプランテン・バナナの葉に包んで蒸したタマル、そしてホンジュラスの「タマルの王様」といえる、クリスマスに欠かせない大型のナカタマルなどがある。
トルティーヤは、タコ(複数形はタコス)の皮でもある。ホンジュラスのタコスは、鶏肉か牛肉に、みじん切りにしたジャガイモやタマネギを加えて炒めトルティーヤで巻き、油で揚げるのが特徴である。ぱりぱりとした食感で、ビールのつまみにも合う。トルティーヤにチーズを挟んで焼いたケサディーヤや、マサにチーズを加えてドーナツ型にしてオーブンで焼いたロスキーヤは、朝食やおやつとして好まれる。
トウモロコシ (学名:Zea Mays)
メキシコ原産のイネ科の一年草で、世界三大穀物のひとつ。イネ科の野生植物テオシンテ(1本の穂に6~ 10粒の種子をつける)が、採集利用された過程で突然変異してトウモロコシの先祖になった、という説が有力。メキシコ高地のテワカン盆地にあるコシュカトラン岩陰遺跡から出土した最古のトウモロコシ遺存体(前5000年頃)は、穂軸の長さがわずか2センチメートルほどの小さなもので、穀粒は平均55粒であった。モンゴロイドの先住民たちが、数千年にわたって品種改良を重ねた結果、現在では何枚もの苞葉に包まれ穂軸に数百の穀粒をつけるものとなり、人の手なしには生存できない植物になっている。
メキシコ原産のイネ科の一年草で、世界三大穀物のひとつ。イネ科の野生植物テオシンテ(1本の穂に6~ 10粒の種子をつける)が、採集利用された過程で突然変異してトウモロコシの先祖になった、という説が有力。メキシコ高地のテワカン盆地にあるコシュカトラン岩陰遺跡から出土した最古のトウモロコシ遺存体(前5000年頃)は、穂軸の長さがわずか2センチメートルほどの小さなもので、穀粒は平均55粒であった。モンゴロイドの先住民たちが、数千年にわたって品種改良を重ねた結果、現在では何枚もの苞葉に包まれ穂軸に数百の穀粒をつけるものとなり、人の手なしには生存できない植物になっている。
ビルマで歌を学ぶ
井上 さゆり
教えたくなるまで待つ
ビルマの文化大学は、ヤンゴン市内の人もほとんど訪れないような郊外にある。建物と人が密集したヤンゴン市の中心部の方がまだ緑が多いと感じるくらい木が少なく、雨季にはぬかるみに、他の季節には埃と日差しの強さに悩まされた。大学の校舎は二棟でさほど大きくない。しかし敷地自体は広く、藪や沼も広がっている。そして、一部の教職員が住むために建てられた家もある。わたしの歌の先生の家も、そのうちのひとつであった。
大学のカリキュラムを消化するには授業では足りず、多くの学生が同じ教師にプライベートでも教えを請う。わたしは一九九九年から二〇〇一年のあいだ唯一の留学生だった。授業はビルマ人学生とは別に個人で受けていたが、それでも授業時間だけでは足りず、数名の先生に交渉してプライベートでも教わることにした。
四時に授業が終わり、歌の先生の気がむきさえすれば、家に来いと言われる。しかし、その前に、大学内の食堂で先生と一緒に紅茶を飲んだり、そこに他の人が加わっておしゃべりが始まったり、先生が教えたくなるまで待つのがふつうである。
師と家族ぐるみのつきあい
ビルマの古典音楽は、楽譜を用いず口承で伝えられる。古典音楽とはすなわち歌謡である。有名な竪琴をはじめとして楽器は、歌とともに奏されるためにある。そのため、歌手も楽器奏者もまず歌を覚える必要がある。歌を学ぶ者も、楽器の奏法を学ぶ者も、先生が一フレーズずつ演奏して聞かせる曲を真似して覚えていく。完全に暗記し、考えなくても口や手が動くようになるまで練習を重ねる。わたしの教師たちも、最初はそのまた師の家に住み込んで雑用をしたり、一緒に演奏活動について行ったり、とにかく師とともに過ごすことで、曲や演奏技術を学んできた。師とは自然、家族ぐるみのつきあいとなる。こうして師から知識を授かって、それが自分の財産となる。
ビルマの古典音楽の歌唱を学ぶには、歌詞だけが記された歌謡集が教科書である。歌詞をそれに頼りながら、先生が歌って聞かせる各フレーズをすぐに繰り返し、間違えれば直される。その繰り返しで旋律と歌唱法を覚える。同じ旋律が他の作品に用いられている場合も多いので、きちんと覚えていないと、いつのまにか他の作品を歌い始めていたりする。大学では毎日一時間ほど歌のレッスンを受けていたが、一度は覚えても次の日になると忘れていることも多く、とにかく先生に密着して訓練してもらうしかない。わたしは歌と竪琴を大学で学んでおり、土日に竪琴のプライベート・レッスンを受け、平日の放課後はほとんど歌の先生の家に行っていた。
先生は五〇歳前後の女性で踊りも教えており、いつも綺麗にお化粧をし、きちんと身だしなみを整えていた。家族構成は、ご主人と高校生の息子一人、小学生の娘一人、結婚した長女とその夫と子どもであった。
歌の先生の家では、ビニールのシートを敷いた木の床に、小さなちゃぶ台を置き、先生と対面してレッスンを受けた。スィーという小さいシンバルとワーというカスタネットを両手にもってリズムをとりながら歌う。スィーとワーの打ち方、順番は、歌ごとに決まっているので、これも覚えなければならない。ちゃぶ台の上においた歌謡集にスィーとワーの箇所をメモしながら練習する。
お漏らしを誘う迷唱
先生の唯一の孫である長女の息子は、当時四歳だった。生まれてすぐにかかった高熱のために麻痺が残り、ことばが話せず寝たきりだった。家族全員からとても可愛がられていた。愛くるしくいつも笑っている。わたしのことを気に入ってくれたようで、行くと顔をほころばせて喜んでくれた。そのうち、わたしが歌い始めると必ず小便をするようになった。ビルマでは、ふつうオムツは使用せず、そのまま垂れ流しである。先生の膝の上で抱かれていればそこに、床に寝かせられていればそこに流れる。わたしが先生の歌を真似て歌い始めてしばらくすると、その子が小便をする。先生の膝の上でした場合は、先生は「わっ」と言いながらも笑って着替えに行く。床にした場合も、その子の着替えをしなければならない。そんなことで、しばしばレッスンが中断する。ふだんはあまり小便をしなくて困っていたそうであるが、わたしが歌うと三回くらい同じことが繰り返される。わたしはすっかりその子の小便催し係として絶大な信頼を置かれるようになった。
その子は話せないが、言われることは理解していた。わたしの歌が下手なため、先生がわざとその子の前で「こんなにできないなんて、インインエー(わたしの名)を叩いてやる」と言ったり、実際にわたしのお尻を叩いたりすると、目にいっぱい涙を浮かべて悲しい顔をして泣き始める。自分はいくら怒られても、軽く叩かれたりしてもニコニコしているのに、他の人が意地悪されたり嫌な目にあったりしていると泣き出すと言う。先生が「大丈夫、叩かないよ」と言って慰めると安心して泣き止む。小さな子を泣かせるまでからかうのにもびっくりしたが、その子の優しさが心に響いた。
二年間の留学を終え帰国して一年後、その子が亡くなったと聞いた。それから二年ほどして訪ねたら、一歳になるそっくりの男の子がいた。その後生まれた先生の孫だと言う。健康に育ち、よちよち歩きをしていた。皆が、あの子の生まれ変わりだと言った。あの子そっくりの利発そうな表情と優しい笑顔に、わたしもそう思った。
ビルマの文化大学は、ヤンゴン市内の人もほとんど訪れないような郊外にある。建物と人が密集したヤンゴン市の中心部の方がまだ緑が多いと感じるくらい木が少なく、雨季にはぬかるみに、他の季節には埃と日差しの強さに悩まされた。大学の校舎は二棟でさほど大きくない。しかし敷地自体は広く、藪や沼も広がっている。そして、一部の教職員が住むために建てられた家もある。わたしの歌の先生の家も、そのうちのひとつであった。
大学のカリキュラムを消化するには授業では足りず、多くの学生が同じ教師にプライベートでも教えを請う。わたしは一九九九年から二〇〇一年のあいだ唯一の留学生だった。授業はビルマ人学生とは別に個人で受けていたが、それでも授業時間だけでは足りず、数名の先生に交渉してプライベートでも教わることにした。
四時に授業が終わり、歌の先生の気がむきさえすれば、家に来いと言われる。しかし、その前に、大学内の食堂で先生と一緒に紅茶を飲んだり、そこに他の人が加わっておしゃべりが始まったり、先生が教えたくなるまで待つのがふつうである。
師と家族ぐるみのつきあい
ビルマの古典音楽は、楽譜を用いず口承で伝えられる。古典音楽とはすなわち歌謡である。有名な竪琴をはじめとして楽器は、歌とともに奏されるためにある。そのため、歌手も楽器奏者もまず歌を覚える必要がある。歌を学ぶ者も、楽器の奏法を学ぶ者も、先生が一フレーズずつ演奏して聞かせる曲を真似して覚えていく。完全に暗記し、考えなくても口や手が動くようになるまで練習を重ねる。わたしの教師たちも、最初はそのまた師の家に住み込んで雑用をしたり、一緒に演奏活動について行ったり、とにかく師とともに過ごすことで、曲や演奏技術を学んできた。師とは自然、家族ぐるみのつきあいとなる。こうして師から知識を授かって、それが自分の財産となる。
ビルマの古典音楽の歌唱を学ぶには、歌詞だけが記された歌謡集が教科書である。歌詞をそれに頼りながら、先生が歌って聞かせる各フレーズをすぐに繰り返し、間違えれば直される。その繰り返しで旋律と歌唱法を覚える。同じ旋律が他の作品に用いられている場合も多いので、きちんと覚えていないと、いつのまにか他の作品を歌い始めていたりする。大学では毎日一時間ほど歌のレッスンを受けていたが、一度は覚えても次の日になると忘れていることも多く、とにかく先生に密着して訓練してもらうしかない。わたしは歌と竪琴を大学で学んでおり、土日に竪琴のプライベート・レッスンを受け、平日の放課後はほとんど歌の先生の家に行っていた。
先生は五〇歳前後の女性で踊りも教えており、いつも綺麗にお化粧をし、きちんと身だしなみを整えていた。家族構成は、ご主人と高校生の息子一人、小学生の娘一人、結婚した長女とその夫と子どもであった。
歌の先生の家では、ビニールのシートを敷いた木の床に、小さなちゃぶ台を置き、先生と対面してレッスンを受けた。スィーという小さいシンバルとワーというカスタネットを両手にもってリズムをとりながら歌う。スィーとワーの打ち方、順番は、歌ごとに決まっているので、これも覚えなければならない。ちゃぶ台の上においた歌謡集にスィーとワーの箇所をメモしながら練習する。
お漏らしを誘う迷唱
先生の唯一の孫である長女の息子は、当時四歳だった。生まれてすぐにかかった高熱のために麻痺が残り、ことばが話せず寝たきりだった。家族全員からとても可愛がられていた。愛くるしくいつも笑っている。わたしのことを気に入ってくれたようで、行くと顔をほころばせて喜んでくれた。そのうち、わたしが歌い始めると必ず小便をするようになった。ビルマでは、ふつうオムツは使用せず、そのまま垂れ流しである。先生の膝の上で抱かれていればそこに、床に寝かせられていればそこに流れる。わたしが先生の歌を真似て歌い始めてしばらくすると、その子が小便をする。先生の膝の上でした場合は、先生は「わっ」と言いながらも笑って着替えに行く。床にした場合も、その子の着替えをしなければならない。そんなことで、しばしばレッスンが中断する。ふだんはあまり小便をしなくて困っていたそうであるが、わたしが歌うと三回くらい同じことが繰り返される。わたしはすっかりその子の小便催し係として絶大な信頼を置かれるようになった。
その子は話せないが、言われることは理解していた。わたしの歌が下手なため、先生がわざとその子の前で「こんなにできないなんて、インインエー(わたしの名)を叩いてやる」と言ったり、実際にわたしのお尻を叩いたりすると、目にいっぱい涙を浮かべて悲しい顔をして泣き始める。自分はいくら怒られても、軽く叩かれたりしてもニコニコしているのに、他の人が意地悪されたり嫌な目にあったりしていると泣き出すと言う。先生が「大丈夫、叩かないよ」と言って慰めると安心して泣き止む。小さな子を泣かせるまでからかうのにもびっくりしたが、その子の優しさが心に響いた。
二年間の留学を終え帰国して一年後、その子が亡くなったと聞いた。それから二年ほどして訪ねたら、一歳になるそっくりの男の子がいた。その後生まれた先生の孫だと言う。健康に育ち、よちよち歩きをしていた。皆が、あの子の生まれ変わりだと言った。あの子そっくりの利発そうな表情と優しい笑顔に、わたしもそう思った。
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。