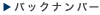月刊みんぱく 2008年1月号
2008年1月号
第32巻第1号通巻第364号
2008年1月1日発行
2008年1月1日発行
残りの文化
曾野 綾子
わたしは小説以外のことには何も積極的になったことがないのだが、さまざまな偶然から、アフリカで働くカトリックのシスターたちに対して経済的支援をするというNGOを始めて三五年が経った。
わたしには疑い深い性格があって、援助のお金を出すと、自分の目でそれが使われているかどうかを自費で確かめに行かねば気が済まなくなった。貧しい組織にお金を出すのだから、泥棒をしようという人も多いし、「査察」する土地も田舎ばかりになる。おかげでわたしは、アフリカのほんとうの僻地に入る機会ができたのである。一九九五年末から九年半勤めた日本財団でも、やがてアフリカの極貧地帯を専門に見る調査団を出すようになり、わたしが毎回その旅に初めから終わりまでつき合った。
結果的にアフリカは、わたしにとって偉大な教師になった。日本人は、鋪装していない大地が目の前に続くとき、どこを歩くかもわからない。低いところ、砂漠なら涸川(ワディ)の川床を行くのが常道だ。しかしとにかく未鋪装の土地を移動したことがないような暮らしをしていると、四駆を使っても時速二〇キロメートルも出ない悪路、水深のわからない川を渡る時期の選定、マラリア蚊を避ける才覚、けちなゲリラまでカラシニコフだけはもっている不気味な時代の危険を回避する方法、など何ひとつ教えられていない。
パリやロンドンで航空会社に預けた荷物は必ず目的地で出て来ると信じているお坊っちゃまとお嬢ちゃまが育っていた。そんな場合を予測して手荷物に必要な品を一式もっているのでまったく不自由しなかったのは、自衛隊からの参加者とわたしだけだったこともある。
ホテルもレストランもないところでは、食事をどうするか。考えればじつに簡単なことだ。石三個と燃料、鍋と原材料と水さえあればたちどころに煮炊きができる。アフリカでは大地のあらゆる場所がキッチンになる。
電気のないところには民主主義はない、という関係も、わたしはすぐに気がつくようになった。地球上のどこででも民主主義が可能だと信じているアメリカ人や日本人は、電気がない暮らしをしている約二〇億人分の心理がわからないのである。民主主義に代わるのは、じつに奥が深い族長支配の文化である。アメリカがイラク政策をしくじったのも、つまりは、民主主義でない残りの文化を理解しなかったからだ、とわかった。救急車が無料の国、生活保護のある国など、天国の境地だ。そうした国に生まれた幸運も日本人の多くは理解しないらしい。
その あやこ/1931年東京都生まれ。作家。1954年『遠来の客たち』が芥川賞候補となり文壇デビュー。幅広い分野で小説やエッセイを発表。一方で各種審議会委員や日本財団の会長を務めるなどの社会活動を展開。1979年ローマ法王庁よりヴァチカン有功十字勲章を受賞。おもな著書に『日本人が知らない世界の歩き方』(PHP研究所)『貧困の光景』(新潮社)『平和とは非凡な幸運』(講談社)など多数。
わたしには疑い深い性格があって、援助のお金を出すと、自分の目でそれが使われているかどうかを自費で確かめに行かねば気が済まなくなった。貧しい組織にお金を出すのだから、泥棒をしようという人も多いし、「査察」する土地も田舎ばかりになる。おかげでわたしは、アフリカのほんとうの僻地に入る機会ができたのである。一九九五年末から九年半勤めた日本財団でも、やがてアフリカの極貧地帯を専門に見る調査団を出すようになり、わたしが毎回その旅に初めから終わりまでつき合った。
結果的にアフリカは、わたしにとって偉大な教師になった。日本人は、鋪装していない大地が目の前に続くとき、どこを歩くかもわからない。低いところ、砂漠なら涸川(ワディ)の川床を行くのが常道だ。しかしとにかく未鋪装の土地を移動したことがないような暮らしをしていると、四駆を使っても時速二〇キロメートルも出ない悪路、水深のわからない川を渡る時期の選定、マラリア蚊を避ける才覚、けちなゲリラまでカラシニコフだけはもっている不気味な時代の危険を回避する方法、など何ひとつ教えられていない。
パリやロンドンで航空会社に預けた荷物は必ず目的地で出て来ると信じているお坊っちゃまとお嬢ちゃまが育っていた。そんな場合を予測して手荷物に必要な品を一式もっているのでまったく不自由しなかったのは、自衛隊からの参加者とわたしだけだったこともある。
ホテルもレストランもないところでは、食事をどうするか。考えればじつに簡単なことだ。石三個と燃料、鍋と原材料と水さえあればたちどころに煮炊きができる。アフリカでは大地のあらゆる場所がキッチンになる。
電気のないところには民主主義はない、という関係も、わたしはすぐに気がつくようになった。地球上のどこででも民主主義が可能だと信じているアメリカ人や日本人は、電気がない暮らしをしている約二〇億人分の心理がわからないのである。民主主義に代わるのは、じつに奥が深い族長支配の文化である。アメリカがイラク政策をしくじったのも、つまりは、民主主義でない残りの文化を理解しなかったからだ、とわかった。救急車が無料の国、生活保護のある国など、天国の境地だ。そうした国に生まれた幸運も日本人の多くは理解しないらしい。
その あやこ/1931年東京都生まれ。作家。1954年『遠来の客たち』が芥川賞候補となり文壇デビュー。幅広い分野で小説やエッセイを発表。一方で各種審議会委員や日本財団の会長を務めるなどの社会活動を展開。1979年ローマ法王庁よりヴァチカン有功十字勲章を受賞。おもな著書に『日本人が知らない世界の歩き方』(PHP研究所)『貧困の光景』(新潮社)『平和とは非凡な幸運』(講談社)など多数。
今年の干支はネズミ。日本の昔話に登場したり、人とともに海を移動したりと、ネズミと人との関係は深く長い。農作物への害や伝染病の媒介などのマイナス面もあるが、食用や家畜などとして利用する人びともいる。特集では、ネズミと文化とのかかわりについて紹介したい。
にくくもあり、いとおしくもあり
駆除と食用
ベトナムの山間部の村で、うっかり食べ物を置きっぱなしにしたまま寝てしまってはたいへんである。清少納言も悪(にく)んだゲリラどもが「走りあり」き、皿を返し、ものをかじり、夜の森閑をずたずたに引き破る。密室性の高い住宅が発達するごく最近まで、われわれに寄り添って住みたがるネズミを、どうやって遠ざけるか、彼らの放縦をどうやって取り締まるかは、人類にとって大いなる課題であったに違いない。大げさな話ではない。
数年前に、ベトナムのメコン・デルタの農民が酒に漬けるためにコブラを乱獲した結果、ネズミによる農作物被害がひどくなってたいへん困ったという話を聞いた。ネズミは田畑の稔りを掠(かす)め、家にあがり込んで財を弄ぶとして憎まれてきた。ましてや、ペストなど、彼らのまき散らす病原体で人が死ぬかもしれないとなれば、ますます憎まれた。だから罠、飛び道具、毒、呪文など、人知の限りを尽くして、ネズミはしばしば駆除されようとしてきたのである。
じつは、人のまわりにいくらでもいるネズミの肉は、淡泊でまずくない。アンデスではテンジクネズミ(クイ)を、食用として何百年も前から養殖している。にっくきネズミ奴(め)を捕らえたからには皮ひんむいて食べてやらん、という地域なら、世界中にたくさんあるし、日本や中国などでは、糞まで薬にした。
伝承のネズミ
伝承の世界にも、わずかな隙間さえあればネズミは入り込んでいる。大国主命(おおくにのみこと)を火中から救ったのはネズミの知恵で、ゆえにインド起源の大黒の従者にまで昇格した。また、あっぱれ、足で描いた涙のネズミは雪舟の罰を解かせたし、東南アジアの山地で大洪水から人類の始祖を救ったのはネズミの予知であった。このような伝承のなかでもち上げてみたのは、知恵と数でわれわれを圧倒するやんちゃ屋に対する、苦渋の和解策であったろうか。
人間を救う
二〇世紀になって、ネズミは産業社会の都市生活では次第に視界から消えた。そのためか、アメリカ生まれのミッキーマウスは愛らしいキャラクターとして、今や世界中の人気者である。ネズミとの長い戦いの歴史を、先進国の多くの人は忘れた。
さらに、目立たないところでネズミは立派に社会貢献もしている。世界中で生体実験用にネズミは飼われている。あるいは火災などの予知能力が高いとされ、防災にも役立てられようとしている。もはやネズミに人間が救われるのも、おとぎ話の世界ではなくなるかもしれない。
ベトナムの山間部の村で、うっかり食べ物を置きっぱなしにしたまま寝てしまってはたいへんである。清少納言も悪(にく)んだゲリラどもが「走りあり」き、皿を返し、ものをかじり、夜の森閑をずたずたに引き破る。密室性の高い住宅が発達するごく最近まで、われわれに寄り添って住みたがるネズミを、どうやって遠ざけるか、彼らの放縦をどうやって取り締まるかは、人類にとって大いなる課題であったに違いない。大げさな話ではない。
数年前に、ベトナムのメコン・デルタの農民が酒に漬けるためにコブラを乱獲した結果、ネズミによる農作物被害がひどくなってたいへん困ったという話を聞いた。ネズミは田畑の稔りを掠(かす)め、家にあがり込んで財を弄ぶとして憎まれてきた。ましてや、ペストなど、彼らのまき散らす病原体で人が死ぬかもしれないとなれば、ますます憎まれた。だから罠、飛び道具、毒、呪文など、人知の限りを尽くして、ネズミはしばしば駆除されようとしてきたのである。
じつは、人のまわりにいくらでもいるネズミの肉は、淡泊でまずくない。アンデスではテンジクネズミ(クイ)を、食用として何百年も前から養殖している。にっくきネズミ奴(め)を捕らえたからには皮ひんむいて食べてやらん、という地域なら、世界中にたくさんあるし、日本や中国などでは、糞まで薬にした。
伝承のネズミ
伝承の世界にも、わずかな隙間さえあればネズミは入り込んでいる。大国主命(おおくにのみこと)を火中から救ったのはネズミの知恵で、ゆえにインド起源の大黒の従者にまで昇格した。また、あっぱれ、足で描いた涙のネズミは雪舟の罰を解かせたし、東南アジアの山地で大洪水から人類の始祖を救ったのはネズミの予知であった。このような伝承のなかでもち上げてみたのは、知恵と数でわれわれを圧倒するやんちゃ屋に対する、苦渋の和解策であったろうか。
人間を救う
二〇世紀になって、ネズミは産業社会の都市生活では次第に視界から消えた。そのためか、アメリカ生まれのミッキーマウスは愛らしいキャラクターとして、今や世界中の人気者である。ネズミとの長い戦いの歴史を、先進国の多くの人は忘れた。
さらに、目立たないところでネズミは立派に社会貢献もしている。世界中で生体実験用にネズミは飼われている。あるいは火災などの予知能力が高いとされ、防災にも役立てられようとしている。もはやネズミに人間が救われるのも、おとぎ話の世界ではなくなるかもしれない。
アンデスで飼う
鵜澤 和宏(うざわ かずひろ) 東亜大学准教授
ネズミを食べる
医療実験に使われるモルモットは、もともと南米アンデスで家畜化された食用のネズミである。現地ではその鳴き声からクイとよばれ、現在も、エクアドル、ペルー、ボリビアを中心にアンデス一帯で飼育されている。
食習慣とは保守的なもので、どれほど栄養になるといわれても口に運ぶのがためらわれるものがある。ネズミは心理的障壁が高い。小学生のころ、ボールを拾おうと顔を突っ込んだ側溝でドブネズミに襲われかけて以来、わたしはネズミ恐怖症である。想像するのも遠慮したい。
ところが、アンデス文明の起源を研究する調査団の一員として、ペルーで遺跡から出土する動物骨の分析を担当することになった。研究テーマとしてもネズミに近づかぬよう注意深く遠ざけてきたにもかかわらず、ペルーでは研究と食卓の両方で幼少期以来のトラウマと向き合うことになった。
アンデスのクイ
ペルーの山岳地域では、現在も伝統的なクイ飼育を見ることができる。家々ではカマドに火がともる暖かい台所にクイがなかば放し飼いにされている。ネズミ算式に増えるとはいえ、日々の食卓にのぼるほどの数ではない。祝い事など特別な機会に振る舞うため、大切に育てられている。そして、日本から来た珍客は、心優しいアンデスの人びとにクイでもてなされる機会に事欠かないのである。
ところで、クイは食用としてだけでなく、儀礼や呪術的な医療行為にも用いられている。遺跡からはクイのミイラや、クイを象(かたど)った土器なども見つかっており、インカに先立つアンデスの先史社会でも人の暮らしに密接に結びついた動物として重要視されていたことがうかがわれる。
クイの家畜化は約六〇〇〇年前ごろと推定される。寒冷な山岳地域で寒さを逃れ、餌を求めて人家に住み着いた個体が飼い慣らされたと考えられるが、祖先種や家畜の起源地について詳しいことはわかっていない。
齧歯類(げっしるい)の系統分類は学問上不明な点の多い領域なのだが、クイとその祖先種はテンジクネズミ科に分類される。ネズミ類の進化のなかでも初期に分岐した独立性の高いグループの一員だ。ネズミ科と異なり、ゴム管のような長くヌメヌメとした尻尾をもたない。一匹まるごとを素揚げにしたクイが目の前に出されるたび、わたしはお尻のあたりを凝視して、耳の短いウサギだと自らに言い聞かせて口に運ぶ。いったん口に入れてしまえば、ニワトリよりもくせがなく淡泊な味わいはなかなか美味しい。つくづく食習慣は文化的なものだと実感するのである。
医療実験に使われるモルモットは、もともと南米アンデスで家畜化された食用のネズミである。現地ではその鳴き声からクイとよばれ、現在も、エクアドル、ペルー、ボリビアを中心にアンデス一帯で飼育されている。
食習慣とは保守的なもので、どれほど栄養になるといわれても口に運ぶのがためらわれるものがある。ネズミは心理的障壁が高い。小学生のころ、ボールを拾おうと顔を突っ込んだ側溝でドブネズミに襲われかけて以来、わたしはネズミ恐怖症である。想像するのも遠慮したい。
ところが、アンデス文明の起源を研究する調査団の一員として、ペルーで遺跡から出土する動物骨の分析を担当することになった。研究テーマとしてもネズミに近づかぬよう注意深く遠ざけてきたにもかかわらず、ペルーでは研究と食卓の両方で幼少期以来のトラウマと向き合うことになった。
アンデスのクイ
ペルーの山岳地域では、現在も伝統的なクイ飼育を見ることができる。家々ではカマドに火がともる暖かい台所にクイがなかば放し飼いにされている。ネズミ算式に増えるとはいえ、日々の食卓にのぼるほどの数ではない。祝い事など特別な機会に振る舞うため、大切に育てられている。そして、日本から来た珍客は、心優しいアンデスの人びとにクイでもてなされる機会に事欠かないのである。
ところで、クイは食用としてだけでなく、儀礼や呪術的な医療行為にも用いられている。遺跡からはクイのミイラや、クイを象(かたど)った土器なども見つかっており、インカに先立つアンデスの先史社会でも人の暮らしに密接に結びついた動物として重要視されていたことがうかがわれる。
クイの家畜化は約六〇〇〇年前ごろと推定される。寒冷な山岳地域で寒さを逃れ、餌を求めて人家に住み着いた個体が飼い慣らされたと考えられるが、祖先種や家畜の起源地について詳しいことはわかっていない。
齧歯類(げっしるい)の系統分類は学問上不明な点の多い領域なのだが、クイとその祖先種はテンジクネズミ科に分類される。ネズミ類の進化のなかでも初期に分岐した独立性の高いグループの一員だ。ネズミ科と異なり、ゴム管のような長くヌメヌメとした尻尾をもたない。一匹まるごとを素揚げにしたクイが目の前に出されるたび、わたしはお尻のあたりを凝視して、耳の短いウサギだと自らに言い聞かせて口に運ぶ。いったん口に入れてしまえば、ニワトリよりもくせがなく淡泊な味わいはなかなか美味しい。つくづく食習慣は文化的なものだと実感するのである。
昔話とネズミ
小池 淳一(こいけ じゅんいち) 国立歴史民俗博物館准教授
豊かさ、幸福のイメージ
ネズミのことを俳句の世界では正月のあいだだけ「嫁が君」という。この季語はもともと、日本各地でヨメジョ、オクサン、オヒメサン、などと正月にはネズミということばを口にせず、言い換える忌みことばからきているという。害獣のように考えられるネズミを敬称でよぶことで、新しい年を豊かな時間にしたいという願望が込められているのだろう。方言ではねずみをフクタロウ(福太郎)とか、オフクサン(お福さん)などともよんだというから、この小さな動物が福と結びつく観念があったことを示している。
日本の昔話伝承のなかでもネズミは豊かさや幸福、あるいは勤勉のイメージと結びついている。
「ねずみ浄土」という話では、地下の世界にネズミたちの世界があり、よいおこないをしたおじいさんはその世界で楽しく過ごしたのち、たくさんの宝物を獲得することになっている。「ねずみの嫁入り」は、ネズミが娘の嫁入り先を探し求めて、お日様がいい、いや、お日様の光をさえぎる雲がいい、いやいや、その雲を吹き飛ばす風の方がいい、いやそうでなくて、風をさえぎる壁がいい、と迷った末に、壁に穴をあけることのできるネズミが、やはりいちばんいい、という話であって、結末が幸福な結婚に結びついている。
中世に盛んに作られたお伽草子という短編の文学作品のなかにも、ネズミが幸福な結婚を願う『鼠の草子』とよばれるものがあり、そこで描かれるネズミの世界も春の景色がのどかに広がる理想郷であった。
ネズミに託す
一方、「ねずみ経」という話では、家のなかに住んでいるネズミの行動を、お経のようにそれらしく唱えることで泥棒を追いはらい、危険から逃れた、と語られ、ふだんの生活のなかでネズミとともに生き、その行動を細やかに観察する視点がかつての日本人の生活にあったことを示している。以前は日本全国でよく聞かれた「昼間に昔話をするとネズミに笑われる」とか「小便をかけられる」という戒めのことばも、昼間にのんびりと昔話などしていないで働きなさい、という戒めをネズミに託しているようにも思われる。そうすることで幸福で豊かな生活が可能になるという意識があったのかもしれない。
ネズミと日本人の求めてきた豊かさや幸福とは意外に深い関係があるように思われる。それは人間の近くで生息してきたこの小さな動物に投影された大きな問題である。
ネズミのことを俳句の世界では正月のあいだだけ「嫁が君」という。この季語はもともと、日本各地でヨメジョ、オクサン、オヒメサン、などと正月にはネズミということばを口にせず、言い換える忌みことばからきているという。害獣のように考えられるネズミを敬称でよぶことで、新しい年を豊かな時間にしたいという願望が込められているのだろう。方言ではねずみをフクタロウ(福太郎)とか、オフクサン(お福さん)などともよんだというから、この小さな動物が福と結びつく観念があったことを示している。
日本の昔話伝承のなかでもネズミは豊かさや幸福、あるいは勤勉のイメージと結びついている。
「ねずみ浄土」という話では、地下の世界にネズミたちの世界があり、よいおこないをしたおじいさんはその世界で楽しく過ごしたのち、たくさんの宝物を獲得することになっている。「ねずみの嫁入り」は、ネズミが娘の嫁入り先を探し求めて、お日様がいい、いや、お日様の光をさえぎる雲がいい、いやいや、その雲を吹き飛ばす風の方がいい、いやそうでなくて、風をさえぎる壁がいい、と迷った末に、壁に穴をあけることのできるネズミが、やはりいちばんいい、という話であって、結末が幸福な結婚に結びついている。
中世に盛んに作られたお伽草子という短編の文学作品のなかにも、ネズミが幸福な結婚を願う『鼠の草子』とよばれるものがあり、そこで描かれるネズミの世界も春の景色がのどかに広がる理想郷であった。
ネズミに託す
一方、「ねずみ経」という話では、家のなかに住んでいるネズミの行動を、お経のようにそれらしく唱えることで泥棒を追いはらい、危険から逃れた、と語られ、ふだんの生活のなかでネズミとともに生き、その行動を細やかに観察する視点がかつての日本人の生活にあったことを示している。以前は日本全国でよく聞かれた「昼間に昔話をするとネズミに笑われる」とか「小便をかけられる」という戒めのことばも、昼間にのんびりと昔話などしていないで働きなさい、という戒めをネズミに託しているようにも思われる。そうすることで幸福で豊かな生活が可能になるという意識があったのかもしれない。
ネズミと日本人の求めてきた豊かさや幸福とは意外に深い関係があるように思われる。それは人間の近くで生息してきたこの小さな動物に投影された大きな問題である。
人の移動とネズミ
ナンヨウネズミは、ポリネシアのほとんどの島に分布する。原産地である東南アジアからこれらの島へは泳いで渡れる距離ではなく、人間が移動する際に、ともにカヌーに乗って島から島へと広まったと考えられてきた。これは、人間が島での居住をはじめるやいなや、ネズミの骨が見つかることからも明らかである。
かつて、オセアニアのネズミは、ブタやイヌのように人間が意図して連れ運んだのではなく、「こっそりと」カヌーに乗り込んだ、つまり、歓迎されざる客としてオセアニアに広まったと考えられていた。ところが、オセアニアのネズミを遺伝学的に研究しているニュージーランド・オークランド大学のエリザベス・マティスー=スミス准教授は、ナンヨウネズミは湿った環境を嫌う習性があるため、隠れてカヌーに乗ったことは考えられない、その証拠に、ポリネシアの島々へ寄港したヨーロッパ船にナンヨウネズミが乗り込んだ証拠はないと指摘する。つまり、オセアニアへ人類とともに移動したネズミは、食用にするために意図的に人間が連れ運んだ可能性が高いという。
さらに、ネズミのDNAを分析すれば人間の移動の様子も明らかになるだろうと考えた同准教授は、東南アジアからオセアニアにかけて分布するナンヨウネズミのミトコンドリアDNAを分析した。その結果、三つのハプロタイプ(遺伝子型)が存在し、それぞれ①東南アジア島嶼部のみ、②東南アジア島嶼部からソロモン諸島まで、③ソロモン諸島以東のみ、という限られた分布を示すことがわかった。ポリネシアに広まったナンヨウネズミは、ポリネシア人の故郷と目されているフィリピンには分布しておらず、②と③の両方が分布しているのはインドネシアのハルマヘラ島のみであった。このことは、オセアニアへ拡散してきた人びとの移動の様子がそれほど単純ではなかったことを示しており、今後もネズミの研究から目が離せない。
かつて、オセアニアのネズミは、ブタやイヌのように人間が意図して連れ運んだのではなく、「こっそりと」カヌーに乗り込んだ、つまり、歓迎されざる客としてオセアニアに広まったと考えられていた。ところが、オセアニアのネズミを遺伝学的に研究しているニュージーランド・オークランド大学のエリザベス・マティスー=スミス准教授は、ナンヨウネズミは湿った環境を嫌う習性があるため、隠れてカヌーに乗ったことは考えられない、その証拠に、ポリネシアの島々へ寄港したヨーロッパ船にナンヨウネズミが乗り込んだ証拠はないと指摘する。つまり、オセアニアへ人類とともに移動したネズミは、食用にするために意図的に人間が連れ運んだ可能性が高いという。
さらに、ネズミのDNAを分析すれば人間の移動の様子も明らかになるだろうと考えた同准教授は、東南アジアからオセアニアにかけて分布するナンヨウネズミのミトコンドリアDNAを分析した。その結果、三つのハプロタイプ(遺伝子型)が存在し、それぞれ①東南アジア島嶼部のみ、②東南アジア島嶼部からソロモン諸島まで、③ソロモン諸島以東のみ、という限られた分布を示すことがわかった。ポリネシアに広まったナンヨウネズミは、ポリネシア人の故郷と目されているフィリピンには分布しておらず、②と③の両方が分布しているのはインドネシアのハルマヘラ島のみであった。このことは、オセアニアへ拡散してきた人びとの移動の様子がそれほど単純ではなかったことを示しており、今後もネズミの研究から目が離せない。
焼畑とネズミ
中辻 享(なかつじ すすむ) 福島大学准教授
ラオス北部は山また山の地であり、人びとは森を刈り払って火を入れ、稲を栽培する焼畑をおこない生活している。森に住む彼らにとって重要なタンパク源となっているのが、イノシシ、リス、ネズミなどの野生動物である。彼らのなかには家畜よりも野生動物の肉の方がおいしいと考える人が多く、今でも狩猟は重要な生業である。なかでもネズミは捕獲しやすいこともあって、よく食されている。
ネズミといって我々が思い起こすのは町中のいわゆる「ドブネズミ」だろう。ラオスの人びとも町や村など人家周辺に住むネズミは汚いと考え、まず捕獲しようとはしない。彼らが追い求めるのは森に住むネズミである。これは味にコクがあり、非常においしいと考えられている。はらわたを抜いて串焼きにしたり、スープに入れたり、いろんな調理法がある。一〇月~一月にかけてラオス北部の山中ではこのようなネズミ料理が食卓にのぼる。
ネズミの狩猟場所として重要なのが焼畑である。焼畑の米が実る収穫期には、それを狙って多くのネズミが周囲の森から焼畑にやってくる。そこで、人びとはこの時期になると焼畑の周囲に罠を張りめぐらせておく。一〇~一月にネズミの捕獲量が多くなるのはこの時期がちょうど焼畑の収穫期前後にあたるためである。
伝統的な罠はタケ製であるが、近年は鉄製の罠が普及している。ネズミがおもに活動するのは夜である。人びとは焼畑の周辺にこの罠を四〇~五〇個仕掛け、一晩中見回る。獲物がかかった罠は餌を付け替えてもう一度仕掛け直す。このようにして一晩でも多くのネズミが捕獲できる。人びとのネズミに対する執念は深く、わたしの調査村では焼畑を大規模におこなうため、他村の者までが泊まり込みで罠猟に来る。
ネズミは米を食らう害獣である。しかし、ラオスの人びとはこれを逆手にとり、罠で捕獲し、重要な食材としているのである。
ネズミといって我々が思い起こすのは町中のいわゆる「ドブネズミ」だろう。ラオスの人びとも町や村など人家周辺に住むネズミは汚いと考え、まず捕獲しようとはしない。彼らが追い求めるのは森に住むネズミである。これは味にコクがあり、非常においしいと考えられている。はらわたを抜いて串焼きにしたり、スープに入れたり、いろんな調理法がある。一〇月~一月にかけてラオス北部の山中ではこのようなネズミ料理が食卓にのぼる。
ネズミの狩猟場所として重要なのが焼畑である。焼畑の米が実る収穫期には、それを狙って多くのネズミが周囲の森から焼畑にやってくる。そこで、人びとはこの時期になると焼畑の周囲に罠を張りめぐらせておく。一〇~一月にネズミの捕獲量が多くなるのはこの時期がちょうど焼畑の収穫期前後にあたるためである。
伝統的な罠はタケ製であるが、近年は鉄製の罠が普及している。ネズミがおもに活動するのは夜である。人びとは焼畑の周辺にこの罠を四〇~五〇個仕掛け、一晩中見回る。獲物がかかった罠は餌を付け替えてもう一度仕掛け直す。このようにして一晩でも多くのネズミが捕獲できる。人びとのネズミに対する執念は深く、わたしの調査村では焼畑を大規模におこなうため、他村の者までが泊まり込みで罠猟に来る。
ネズミは米を食らう害獣である。しかし、ラオスの人びとはこれを逆手にとり、罠で捕獲し、重要な食材としているのである。
砂漠に生命の種をまく
谷本 和子(たにもと かずこ) 関西外国語大学准教授
アメリカ南西部は砂漠であるが、冬は寒さが厳しく積雪がある。冬の朝、戸外を見渡すと雪上のあちこちに残されたシカネズミの小さな足跡に気づく。ハムスターに近い種だが、夜行性で冬眠をせず、冬も活発に動き回るのだ。カナダから南米諸国にいたる多様な生態系に生息していることから、その環境への適応力の高さをうかがい知ることができよう。
シカネズミのメスは春から秋にかけて四度も出産し、一度の出産で五、六匹もの仔ネズミをもうける。仔ネズミは生後三週間で離乳し、五週間ほどで生殖を始める。まるでネズミ算のように、爆発的に増えていくのだ。驚異的な繁殖力を誇るシカネズミだが、生息環境を脅かすほど過密にはならない。それは、捕食されるからである。コヨーテやヤマネコ、猛禽(もうきん)類の主要な餌となるシカネズミは、食物連鎖の底辺を支える大変重要な役目を果たしているのだ。また、他のどんな野生動物よりも数が多く、木々や草花の実を食べて種をあちこちにまき散らす。そうして芽吹いた植物は、砂漠の厳しい自然に生息するたくさんの動物の生命を支えているのだ。
この地に暮らす先住民ナヴァホは、シカネズミを生命の種をまく存在として崇拝するとともに、闇の世界に君臨する死の精霊として恐れてきた。この地域の風土病に、シカネズミが媒介するハンタウイルス肺症候群がある。ネズミの排泄物から人に感染し高熱と肺水腫(はいすいしゅ)を引き起こすのだ。ナヴァホの伝承には、この病気を予防する教えがあり、ネズミとの接触を厳しく禁じている。ネズミを駆除せず、程よい距離をとりながらともに暮らしてきたのだ。小さな生命(いのち)を尊重するナヴァホの教えは、ほかの生命とともに生きることの大切さを教えてくれる。そしてネズミは、自然と生命が繰り広げるダイナミックな営みをわたしたちに気づかせてくれる。今年はネズミ年。砂漠のシカネズミに想いを馳せながら、今一度自然とともに生きることについて考えてみたい
シカネズミのメスは春から秋にかけて四度も出産し、一度の出産で五、六匹もの仔ネズミをもうける。仔ネズミは生後三週間で離乳し、五週間ほどで生殖を始める。まるでネズミ算のように、爆発的に増えていくのだ。驚異的な繁殖力を誇るシカネズミだが、生息環境を脅かすほど過密にはならない。それは、捕食されるからである。コヨーテやヤマネコ、猛禽(もうきん)類の主要な餌となるシカネズミは、食物連鎖の底辺を支える大変重要な役目を果たしているのだ。また、他のどんな野生動物よりも数が多く、木々や草花の実を食べて種をあちこちにまき散らす。そうして芽吹いた植物は、砂漠の厳しい自然に生息するたくさんの動物の生命を支えているのだ。
この地に暮らす先住民ナヴァホは、シカネズミを生命の種をまく存在として崇拝するとともに、闇の世界に君臨する死の精霊として恐れてきた。この地域の風土病に、シカネズミが媒介するハンタウイルス肺症候群がある。ネズミの排泄物から人に感染し高熱と肺水腫(はいすいしゅ)を引き起こすのだ。ナヴァホの伝承には、この病気を予防する教えがあり、ネズミとの接触を厳しく禁じている。ネズミを駆除せず、程よい距離をとりながらともに暮らしてきたのだ。小さな生命(いのち)を尊重するナヴァホの教えは、ほかの生命とともに生きることの大切さを教えてくれる。そしてネズミは、自然と生命が繰り広げるダイナミックな営みをわたしたちに気づかせてくれる。今年はネズミ年。砂漠のシカネズミに想いを馳せながら、今一度自然とともに生きることについて考えてみたい
複数館の資料を一体化して企画展を作る
吉田 裕彦(よしだ ひろひこ) 天理大学附属天理参考館 学芸員
天理大学附属天理参考館(以下、天理参考館)で開催中の第五六回企画展「モチゴメの国ラオスーメコン河流域の暮らしー」(以下、企画展またはラオス展)〈二〇〇七年一〇月一七日~ニ〇〇八年一月七日〉も、好評の内にまもなくその会期を終えようとしている。
この企画展は、総合地球環境学研究所(以下、地球研)の生態史プロジェクトによる研究成果公開の一環として、地球研と民博および天理参考館の三者による共催で、天理参考館を会場として実施したものである。本展実施にあたって、多大な理解と協力をいただいた共催、協賛諸機関それぞれの多くにとっても、はじめての試みとなり、準備の過程では、関係者の手を煩わせることも少なからずあった。ただ、お互いの試行錯誤も、博物館連携の難しさや今後の可能性、あるいは研究成果の社会的還元の方法、過去の調査研究による遺産の活かし方、メコン河流域の地域特性などを、改めて考え直す機会ともなった。
今回のラオス展の企画に携わったのは、地球研で生態史プロジェクトを構成する九研究班の内のモノと情報班(以下、モノ班)であった。モノ班では、一九四五年以後にラオスを中心とするメコン河流域から収集された生活文化資料を所蔵する日本の博物館から資料情報を入手し、横断検索の手法を導入すれば、国内に分散する資料の再統合が可能になると判断した。そこで、研究者間で資料の利活用を図るのに資することを目的に各博物館ごとで所蔵されているメコン河流域からの資料のデータベース作成を試みた。その結果、モノ班ではモノをとおしてラオスの人びとの暮らしを理解するとともに、いくつかの部分でその変化を見極めることができるようになった。また、第二次世界大戦後におこなわれた日本の学術調査団による調査史を辿ることにより、知ることができる写真資料情報の整理と、ラオスが政変により鎖国状態に入った一九七五年前後におこなわれた天理教によるラオス伝道と、巡回医療隊派遣にかかわる写真・文書資料の収集にも携わった。
ラオス展はモノ班がおこなったこれらの研究成果をもとにして、他の研究班の方々の協力もえて準備することができた。各研究者が実施した現地での調査成果をもち寄り、民博、奄美大島の原野農芸博物館、天理参考館の収蔵資料や鹿児島県歴史資料センター黎明館の川野和昭氏の個人コレクションなどを活用して、立体的にラオス各地の暮らしと暮らしぶりの変化を紹介した。
今回の展示では、国内にある有数の博物館や個人研究者が所蔵する、ラオス関係の資料をもち寄ることにより、ひとつの博物館だけでは表現することができない展示が可能となった。一例をあげよう。
展示室入口で来場者を迎えるように展示されている「ラオ・ハイの吸酒(再現展示)」コーナーがある。企画展のタイトルとした「モチゴメの国ラオス」を象徴するコーナー展示としたいとのモノ班の意向を受けて、モチゴメで作った酒ラオ・ハイ(醸造酒)を竹のストローで飲み合うシーンを展示してみようとなった。ところが、ラオ・ハイの吸酒というテーマをもって収集した博物館はなく、それぞれが個別の視点で収集していた資料をドッキングさせて一体化させることにした。まず、吸酒器(酒壺とストロー)は飲酒の道具として収集していた原野農芸博物館から、吸酒する三人の衣装と腰掛けは天理参考館の資料を使い、酒壺のラオ・ハイを水で薄めるのに用いられる角杯型容器は班メンバーの個人コレクションをあてるというコラボレーションが成立した。
また、昨年一一月一〇日におこなったラオスのモチ稲の展示に関連するワークショップ「モチゴメ観察会」では、モチゴメの遺伝的性質を研究している農学研究者から、実際に栽培したラオスのモチゴメを示しながら、遺伝的に生じる多様な稲穂の性質と収穫方法や収穫用具との関係が解説された。このように、物質文化研究と自然科学研究のコラボレーションも実現し、道具は人間が環境に働きかけるメディアであることが改めて明らかになった。
他館の資料や個人コレクションを借用して、展示に充てるという手法はよくなされているところだが、複数館の資料を一体化させて展示するという発想は思いもよらなかった。関連する博物館や研究機関、研究者が互いに連携し、情報を共有すれば、一博物館ではなしえない展示を可能とし、フィールド研究でえた成果や情報を展示という表現で、社会に還元することができることを改めて認識させてくれた展示企画となったのはいうまでもないことであろう。
この企画展は、総合地球環境学研究所(以下、地球研)の生態史プロジェクトによる研究成果公開の一環として、地球研と民博および天理参考館の三者による共催で、天理参考館を会場として実施したものである。本展実施にあたって、多大な理解と協力をいただいた共催、協賛諸機関それぞれの多くにとっても、はじめての試みとなり、準備の過程では、関係者の手を煩わせることも少なからずあった。ただ、お互いの試行錯誤も、博物館連携の難しさや今後の可能性、あるいは研究成果の社会的還元の方法、過去の調査研究による遺産の活かし方、メコン河流域の地域特性などを、改めて考え直す機会ともなった。
今回のラオス展の企画に携わったのは、地球研で生態史プロジェクトを構成する九研究班の内のモノと情報班(以下、モノ班)であった。モノ班では、一九四五年以後にラオスを中心とするメコン河流域から収集された生活文化資料を所蔵する日本の博物館から資料情報を入手し、横断検索の手法を導入すれば、国内に分散する資料の再統合が可能になると判断した。そこで、研究者間で資料の利活用を図るのに資することを目的に各博物館ごとで所蔵されているメコン河流域からの資料のデータベース作成を試みた。その結果、モノ班ではモノをとおしてラオスの人びとの暮らしを理解するとともに、いくつかの部分でその変化を見極めることができるようになった。また、第二次世界大戦後におこなわれた日本の学術調査団による調査史を辿ることにより、知ることができる写真資料情報の整理と、ラオスが政変により鎖国状態に入った一九七五年前後におこなわれた天理教によるラオス伝道と、巡回医療隊派遣にかかわる写真・文書資料の収集にも携わった。
ラオス展はモノ班がおこなったこれらの研究成果をもとにして、他の研究班の方々の協力もえて準備することができた。各研究者が実施した現地での調査成果をもち寄り、民博、奄美大島の原野農芸博物館、天理参考館の収蔵資料や鹿児島県歴史資料センター黎明館の川野和昭氏の個人コレクションなどを活用して、立体的にラオス各地の暮らしと暮らしぶりの変化を紹介した。
今回の展示では、国内にある有数の博物館や個人研究者が所蔵する、ラオス関係の資料をもち寄ることにより、ひとつの博物館だけでは表現することができない展示が可能となった。一例をあげよう。
展示室入口で来場者を迎えるように展示されている「ラオ・ハイの吸酒(再現展示)」コーナーがある。企画展のタイトルとした「モチゴメの国ラオス」を象徴するコーナー展示としたいとのモノ班の意向を受けて、モチゴメで作った酒ラオ・ハイ(醸造酒)を竹のストローで飲み合うシーンを展示してみようとなった。ところが、ラオ・ハイの吸酒というテーマをもって収集した博物館はなく、それぞれが個別の視点で収集していた資料をドッキングさせて一体化させることにした。まず、吸酒器(酒壺とストロー)は飲酒の道具として収集していた原野農芸博物館から、吸酒する三人の衣装と腰掛けは天理参考館の資料を使い、酒壺のラオ・ハイを水で薄めるのに用いられる角杯型容器は班メンバーの個人コレクションをあてるというコラボレーションが成立した。
また、昨年一一月一〇日におこなったラオスのモチ稲の展示に関連するワークショップ「モチゴメ観察会」では、モチゴメの遺伝的性質を研究している農学研究者から、実際に栽培したラオスのモチゴメを示しながら、遺伝的に生じる多様な稲穂の性質と収穫方法や収穫用具との関係が解説された。このように、物質文化研究と自然科学研究のコラボレーションも実現し、道具は人間が環境に働きかけるメディアであることが改めて明らかになった。
他館の資料や個人コレクションを借用して、展示に充てるという手法はよくなされているところだが、複数館の資料を一体化させて展示するという発想は思いもよらなかった。関連する博物館や研究機関、研究者が互いに連携し、情報を共有すれば、一博物館ではなしえない展示を可能とし、フィールド研究でえた成果や情報を展示という表現で、社会に還元することができることを改めて認識させてくれた展示企画となったのはいうまでもないことであろう。
資料に向き合う博物館
博物館がさまざまなイベントを盛んに催したり、開館時間を延長したり、パーティー会場に貸し出したりといったことが目に付きだしたのは、それがカタカナの「ミュージアム」とよばれ始めたころだったように思う。確かに、同時代の人びとのさまざまな利用に供し、開かれた施設となることは重要である。しかしその一方で、わたしは何となく違和感を覚えていた。
先日、長崎歴史文化博物館を訪れた。二〇〇五年開館のこの博物館は、二〇〇六年一〇月号の本誌でも紹介されていたように、長崎県と長崎市が収蔵資料・費用・人員などさまざまな面で協力して作り、管理運営に民間企業による指定管理者制度を採用した新しいかたちの博物館として話題を呼んだ。しかし、実際に訪れてみると、単に新しさだけが取り柄の「ミュージアム」ではなく、大変いい勉強をすることができた。
この博物館には「資料閲覧室/長崎学相談コーナー」があり、博物館が所蔵する長崎関係資料を閲覧することができる。資料は書庫にある図書に止まらない。収蔵庫にある古文書や絵図なども、事前申請が必要な一部を除けば、行ったその場で閲覧が可能である。その日は月曜日で、隣接する県立図書館が休みだったので、わたしはそこで、資料の出し入れで係の人の手を煩わせて終日調べものをおこなった。
収蔵庫にある大正時代に作成されたある島の郷土誌の原本を閲覧したが、コンピュータで検索すると、近年刊行の同名の図書があった。そこでそれを見せてもらうと、その島に住む人が原本を翻刻したものだった。その人によれば、原本は島には存在せずそこに唯一残されていたので、それを基に翻刻することができたという。そこに原本が大事に保管されていたことが、島の人びとが自らの歴史を知ることを可能にしたのは、まさに、博物館冥利に尽きるといったところであろうか。
また、戦後間もなく刊行された壱岐に関するある図書には、「壱岐郷土研究所」のラベルとそれを主宰していた山口麻太郎への著者の献詞が貼り付けてあった。山口は、壱岐にあって中央の研究者の地方軽視の調査研究を厳しく批判したことで知られる民俗学者である。そんな山口の旧蔵書に直接触れることができたのは、これから長崎の島々について学ぼうとしているわたしにとって、非常に感慨深かった。
やはり、博物館は積極的な収集による潤沢な資料の蓄積と保管があってこそとつくづく思う。利用者に向き合っていても、資料に十分向き合っているのだろうか。わたしが近年の「ミュージアム」に対して抱く違和感は、その辺りに起因していたのかも知れない。
先日、長崎歴史文化博物館を訪れた。二〇〇五年開館のこの博物館は、二〇〇六年一〇月号の本誌でも紹介されていたように、長崎県と長崎市が収蔵資料・費用・人員などさまざまな面で協力して作り、管理運営に民間企業による指定管理者制度を採用した新しいかたちの博物館として話題を呼んだ。しかし、実際に訪れてみると、単に新しさだけが取り柄の「ミュージアム」ではなく、大変いい勉強をすることができた。
この博物館には「資料閲覧室/長崎学相談コーナー」があり、博物館が所蔵する長崎関係資料を閲覧することができる。資料は書庫にある図書に止まらない。収蔵庫にある古文書や絵図なども、事前申請が必要な一部を除けば、行ったその場で閲覧が可能である。その日は月曜日で、隣接する県立図書館が休みだったので、わたしはそこで、資料の出し入れで係の人の手を煩わせて終日調べものをおこなった。
収蔵庫にある大正時代に作成されたある島の郷土誌の原本を閲覧したが、コンピュータで検索すると、近年刊行の同名の図書があった。そこでそれを見せてもらうと、その島に住む人が原本を翻刻したものだった。その人によれば、原本は島には存在せずそこに唯一残されていたので、それを基に翻刻することができたという。そこに原本が大事に保管されていたことが、島の人びとが自らの歴史を知ることを可能にしたのは、まさに、博物館冥利に尽きるといったところであろうか。
また、戦後間もなく刊行された壱岐に関するある図書には、「壱岐郷土研究所」のラベルとそれを主宰していた山口麻太郎への著者の献詞が貼り付けてあった。山口は、壱岐にあって中央の研究者の地方軽視の調査研究を厳しく批判したことで知られる民俗学者である。そんな山口の旧蔵書に直接触れることができたのは、これから長崎の島々について学ぼうとしているわたしにとって、非常に感慨深かった。
やはり、博物館は積極的な収集による潤沢な資料の蓄積と保管があってこそとつくづく思う。利用者に向き合っていても、資料に十分向き合っているのだろうか。わたしが近年の「ミュージアム」に対して抱く違和感は、その辺りに起因していたのかも知れない。
ネズミの彫刻
上の彫像(標本番号H180684、長さ/51cm)
下の彫像(標本番号H102389、長さ/36cm)
上の彫像(標本番号H180684、長さ/51cm)
下の彫像(標本番号H102389、長さ/36cm)
オーストラリアには、特徴的な動植物が多い。写真上(表紙)のネズミは、オーストラリア大陸中央部から西部にかけての砂漠とその周辺の乾燥地域にすむトビネズミである。長い尾と発達した後ろ足をもつネズミで、名前のとおり後ろ足でジャンプし、長い尾でバランスをとってすばやく移動する。前足は小さくて、穴を掘るなどのほかはほとんど使わない。おもに植物の種子や根を食べ、地下の穴に生活するという。
砂漠に住む先住民ピチャンチャチャラをはじめとする人たちは、一九八〇年代半ば以降、焼き針金で模様を施したこのネズミの彫刻を、土産品として制作し観光客に販売してきた。素材には砂漠に生えるユーカリやアカシアの木の根が使われる。写真は一九九二年に収集した作品で、彫刻では長い尾とともに、大きな目と耳をもつことが強調されている。
また、大陸北部のアーネムランドに住むヨロンゴの人たちも、ネズミの彫刻を土産品に制作する。ここに示したのはノネズミの彫刻で(写真下)、砂漠の作品とはちがいオーカー(顔料)で彩色されている。このほかアーネムランドの川や沼には、泳ぐために水かきをもつミズネズミもすんでいる。さまざまなネズミの彫刻は、オーストラリアにおけるこの動物の多様さを反映しているのだろう。
砂漠に住む先住民ピチャンチャチャラをはじめとする人たちは、一九八〇年代半ば以降、焼き針金で模様を施したこのネズミの彫刻を、土産品として制作し観光客に販売してきた。素材には砂漠に生えるユーカリやアカシアの木の根が使われる。写真は一九九二年に収集した作品で、彫刻では長い尾とともに、大きな目と耳をもつことが強調されている。
また、大陸北部のアーネムランドに住むヨロンゴの人たちも、ネズミの彫刻を土産品に制作する。ここに示したのはノネズミの彫刻で(写真下)、砂漠の作品とはちがいオーカー(顔料)で彩色されている。このほかアーネムランドの川や沼には、泳ぐために水かきをもつミズネズミもすんでいる。さまざまなネズミの彫刻は、オーストラリアにおけるこの動物の多様さを反映しているのだろう。
ハパオ村の植林活動
清水 展(しみず ひろむ) 京都大学東南アジア研究所教授
棚田と原材木を守るため
一九九七年の夏からだから、もう丸一〇年になる。毎年の春休みか夏休みに、フィリピン・ルソン島北部山地イフガオ州のハパオ村を訪れて二、三週間の調査を続けている。その理由は村で、ロペス・ナウヤックさんが中心となって進める植林運動がすごく面白いからだ。初めは彼が言い出しっぺとなって手弁当で始め、親戚友人たちを巻き込み、村人を説得し、運動が大きくなっていった。やがてIKGSという日本のNPO団体と連携協力して、イオン環境財団や環境事業団、JICAなどから資金援助を受け、村の周囲に総計で約三〇万本の苗木を植えてきた。日本からの援助額の総額は五〇〇〇万円ほどになる。
ロペスさんは、青年期にハパオ村から移住したバギオ市にて、木彫りの製作・販売・仲買で小さな成功をおさめた。四人の子どもたちが結婚して独立したのを機に、一九九六年にハパオ村に戻り、植林活動に専念し始めた。ハパオ村は、一九九五年にユネスコの世界遺産として登録されたイフガオの四ヵ所の棚田群のひとつで、観光土産の木彫り製作の中心的な村として有名である。四〇〇世帯のうち半分ほどの家で木彫りをしている。ロペスさんの植林の目的は、先祖伝来の棚田を土砂崩れなどから守るとともに木彫りの原材木を確保するためという。
グローバルの理由
日本との関係でいえば、ハパオ村の一帯は、第二次世界大戦の末期に、比島方面軍総司令官の山下奉文将軍が、主力部隊を率いてたてこもった地区である。中央から遠く離れた深い山奥だからこそ、日本軍が最後に逃げ込んだのだ。けれども、今では逆にこの一〇年で、村から一〇〇人以上が海外へ出稼ぎに出ている。多くは香港やシンガポールでお手伝いとして働く女性だ。彼女たちの送金で家が新築改築されたり、弟妹が大学に行ったり、豚を買って伝統的な儀礼を活発におこなったりしている。
ロペスさんは、植林を進める住民団体を、イフガオ・グローバル森林都市運動と名づけた。この団体は村のなかで「グローバル」とよばれている。グローバルと名づけた理由は、ハパオ村は第二次世界大戦の日米最終決戦の舞台となるはずだったが、森の霊気に荒ぶる心をなだめられた山下将軍が降服を決意した、それで戦争が終わり世界の平和がこの地に「降誕」したからだ、という。一方、日本軍が畑の作物をすべて奪って飢餓をもたらし、山中の避難生活で伝染病が流行ったために多くの村人が命を落とした。
そうした過去を忘れずにいてほしい、そしてこの村の子どもたちの未来のために、お前もこの植林運動に手を貸してほしいと強く頼まれた。それで噴火後のピナトゥボ山で植林活動をしていたIKGSにお願いし、イフガオでもプロジェクトを始めてもらった次第である。一〇年を振り返って、一定の距離を保ち客観的な参与観察を心がける人類学者というよりも、運動にコミットする同伴レポーターとなった感がある。同時に、辺境から、あるいは草の根からのグローバリゼーションを考えるための、いろいろな刺激を受けている。
一九九七年の夏からだから、もう丸一〇年になる。毎年の春休みか夏休みに、フィリピン・ルソン島北部山地イフガオ州のハパオ村を訪れて二、三週間の調査を続けている。その理由は村で、ロペス・ナウヤックさんが中心となって進める植林運動がすごく面白いからだ。初めは彼が言い出しっぺとなって手弁当で始め、親戚友人たちを巻き込み、村人を説得し、運動が大きくなっていった。やがてIKGSという日本のNPO団体と連携協力して、イオン環境財団や環境事業団、JICAなどから資金援助を受け、村の周囲に総計で約三〇万本の苗木を植えてきた。日本からの援助額の総額は五〇〇〇万円ほどになる。
ロペスさんは、青年期にハパオ村から移住したバギオ市にて、木彫りの製作・販売・仲買で小さな成功をおさめた。四人の子どもたちが結婚して独立したのを機に、一九九六年にハパオ村に戻り、植林活動に専念し始めた。ハパオ村は、一九九五年にユネスコの世界遺産として登録されたイフガオの四ヵ所の棚田群のひとつで、観光土産の木彫り製作の中心的な村として有名である。四〇〇世帯のうち半分ほどの家で木彫りをしている。ロペスさんの植林の目的は、先祖伝来の棚田を土砂崩れなどから守るとともに木彫りの原材木を確保するためという。
グローバルの理由
日本との関係でいえば、ハパオ村の一帯は、第二次世界大戦の末期に、比島方面軍総司令官の山下奉文将軍が、主力部隊を率いてたてこもった地区である。中央から遠く離れた深い山奥だからこそ、日本軍が最後に逃げ込んだのだ。けれども、今では逆にこの一〇年で、村から一〇〇人以上が海外へ出稼ぎに出ている。多くは香港やシンガポールでお手伝いとして働く女性だ。彼女たちの送金で家が新築改築されたり、弟妹が大学に行ったり、豚を買って伝統的な儀礼を活発におこなったりしている。
ロペスさんは、植林を進める住民団体を、イフガオ・グローバル森林都市運動と名づけた。この団体は村のなかで「グローバル」とよばれている。グローバルと名づけた理由は、ハパオ村は第二次世界大戦の日米最終決戦の舞台となるはずだったが、森の霊気に荒ぶる心をなだめられた山下将軍が降服を決意した、それで戦争が終わり世界の平和がこの地に「降誕」したからだ、という。一方、日本軍が畑の作物をすべて奪って飢餓をもたらし、山中の避難生活で伝染病が流行ったために多くの村人が命を落とした。
そうした過去を忘れずにいてほしい、そしてこの村の子どもたちの未来のために、お前もこの植林運動に手を貸してほしいと強く頼まれた。それで噴火後のピナトゥボ山で植林活動をしていたIKGSにお願いし、イフガオでもプロジェクトを始めてもらった次第である。一〇年を振り返って、一定の距離を保ち客観的な参与観察を心がける人類学者というよりも、運動にコミットする同伴レポーターとなった感がある。同時に、辺境から、あるいは草の根からのグローバリゼーションを考えるための、いろいろな刺激を受けている。
文化と国民国家
文化による差別
食う。飲む。寝る。歩く。これらは文化の一部である。
会話する。交わる。抱く。眺める。聴く。これも文化の一部である。
わたしは自分をグルメ(食通)でありグルマン(食いしん坊)であると思っており、ほとんどなんでも口に入れる。日本料理はもちろん、中華料理、フランス料理、無国籍の料理。
料理に垣根があると、誰が思うだろう。ところが、文化には垣根があり、境界があると、誰もが思っている。その垣根とは何か。そうした垣根があると、何故思い込まされているのか。
外国に行ってみよう。たしかに人びとは違ったことばを喋り、違ったお金を使い、食事やあいさつの仕方も違っている。あなたは心細く思うかもしれない。しかしその心細さは、日本国内の見知らぬ土地を旅するときと、どれほど違っているだろう。その心細さは、文化の違いに由来するのだろうか。
こんなことをいうのは、同じ国に住みながら、文化が違うという理由で排除されている人びとが、世界にはたくさんいるためである。たとえばわたしが研究しているフランスでは、ムスリムの人びとが全人口の一〇パーセント近く住んでいる。彼らの多くは、北アフリカや熱帯アフリカ、中東から来た両親から生まれた第二世代、第三世代の若者たちである。
彼らはフランスで教育を受け、フランス語を喋り、フランスのポップスに夢中になり、フランスの法律にしたがって生きている。しかし、彼らは「移民」「ムスリム」などとよばれ、「フランス人」とは明確な一線が引かれている。その彼らに対して、学業、就職、居住において厳しい差別がなされている
国民国家との関係
このような文化の名による差別ないし区別は、日本を含めたどこの国でもおこなわれていることである。文化とは、人間が日々生活していくうえで不可欠の要素であり、他者との交流を可能にするための媒体であるはずだ。それなのに、それは何故排除と差別の道具にされているのだろうか。
わたしたち人類学者の多くは、個別の文化を尊重し、文化的差異に対して敏感でありたいと願ってきた。その文化が排除のための道具として用いられるなどとは、考えもしなかったのである。しかし、現実がこのようであるとすれば、認識を改めることが必要だろう。
グローバル化が進行するなかで、国家はどのように変容してきたのか。国民国家と文化はどのような関係にあるのか。文化的同質性をもたない国家を考えることは可能なのか。二〇〇八年三月一、二日に、そうしたテーマで、民博と国立歴史民俗博物館共同で国際シンポジウムを実施する。関心のある方は、ぜひお問い合わせ、ご参加ください。
食う。飲む。寝る。歩く。これらは文化の一部である。
会話する。交わる。抱く。眺める。聴く。これも文化の一部である。
わたしは自分をグルメ(食通)でありグルマン(食いしん坊)であると思っており、ほとんどなんでも口に入れる。日本料理はもちろん、中華料理、フランス料理、無国籍の料理。
料理に垣根があると、誰が思うだろう。ところが、文化には垣根があり、境界があると、誰もが思っている。その垣根とは何か。そうした垣根があると、何故思い込まされているのか。
外国に行ってみよう。たしかに人びとは違ったことばを喋り、違ったお金を使い、食事やあいさつの仕方も違っている。あなたは心細く思うかもしれない。しかしその心細さは、日本国内の見知らぬ土地を旅するときと、どれほど違っているだろう。その心細さは、文化の違いに由来するのだろうか。
こんなことをいうのは、同じ国に住みながら、文化が違うという理由で排除されている人びとが、世界にはたくさんいるためである。たとえばわたしが研究しているフランスでは、ムスリムの人びとが全人口の一〇パーセント近く住んでいる。彼らの多くは、北アフリカや熱帯アフリカ、中東から来た両親から生まれた第二世代、第三世代の若者たちである。
彼らはフランスで教育を受け、フランス語を喋り、フランスのポップスに夢中になり、フランスの法律にしたがって生きている。しかし、彼らは「移民」「ムスリム」などとよばれ、「フランス人」とは明確な一線が引かれている。その彼らに対して、学業、就職、居住において厳しい差別がなされている
国民国家との関係
このような文化の名による差別ないし区別は、日本を含めたどこの国でもおこなわれていることである。文化とは、人間が日々生活していくうえで不可欠の要素であり、他者との交流を可能にするための媒体であるはずだ。それなのに、それは何故排除と差別の道具にされているのだろうか。
わたしたち人類学者の多くは、個別の文化を尊重し、文化的差異に対して敏感でありたいと願ってきた。その文化が排除のための道具として用いられるなどとは、考えもしなかったのである。しかし、現実がこのようであるとすれば、認識を改めることが必要だろう。
グローバル化が進行するなかで、国家はどのように変容してきたのか。国民国家と文化はどのような関係にあるのか。文化的同質性をもたない国家を考えることは可能なのか。二〇〇八年三月一、二日に、そうしたテーマで、民博と国立歴史民俗博物館共同で国際シンポジウムを実施する。関心のある方は、ぜひお問い合わせ、ご参加ください。
「単一民族国家」のなかで華僑として生きていること
劉 明基(ユ・ミョンギ) 韓国・慶北大学校教授
チャヂャン麺で韓国に根付く
青友坊(チョンウバン)。韓国大邱市隣近の小都市慶山にある小さな中国料理の店、華僑による「本当の中華料理店」である。インタビュー当日、筆者にこの店の主人を紹介してくれた嶺南大学の朴賢洙(パクヒョンス)教授も同席した。その理由は、じつはこの店の名物であるチャヂャン麺を食べたかったからだ。チャヂャン麺はチュンヂャンという黒味噌を入れて炒めた具をかけた麺である。中国のザーザンミェン(炸醤麺)に由来をもち、韓国人の口に合うように改良された韓国の代表的な庶民食である。
青友坊の主人である王樹○(ワンチュウチン)さんは今年七〇歳。台湾出身の妻の陳翠梅(チュンチュウエイメイ)さん、長男の慶龍(チンロン)さん夫婦と小学校に通う二人の孫たちと一緒に住んでいる。青友坊は徹底した家族経営体制で運営され、厨房の仕事は奥さんと長男の担当、長男のお嫁さんはホールやカウンターの仕事をしている。王さん自身は総監督だが、店が忙しいときは配達を手伝う。
王さんの父親は中国山東省から一九二〇年代に朝鮮半島へ移住した。王さんは韓国生まれの二世である。王さん夫婦の三人の息子は、同居している長男のほかに、漢医師の次男と三男である。韓国で漢医師は高所得で誰もが羨望する職業だ。王さんは、息子たちが地元の漢医大で漢医師資格をえて、台湾で一年間鍼術(しんじゅつ)を習得した「正統」な漢方医であることに大きな自負心を感じている。
王さん一家や王さんの四人の兄弟姉妹の家族が集まるのは祖先への祭祀、旧正月と秋夕(旧盆)などの韓国の名節日だ。王さんはこのような家族の集まりをとても大事に思っている。王さんがキリスト教に改宗しない理由のひとつもこのためだ。クリスチャンとして教会の活動に参加すれば、社交の幅がずっと広くなり商売に役に立つだろうとは思う。でもクリスチャンになれば祖先祭祀ができなくなる。王さんはクリスチャンとして教会に出ることで商売の利益を上げるよりは、祖上祭祀をつうじて一家が集まる機会をもつことがもっと大切なことだと思っている。
華僑の苦難
韓国の華僑は数々の苦難を経験しながら今まで生き残ってきた。彼らの歴史は一八八二年、朝鮮内乱の鎮圧のため清の軍隊にしたがって来た商人集団によって始まった。現在約二万人を数える韓国華僑の生活は朝鮮半島の政治的状況に大きな影響を受けてきた。朝鮮半島が分断された後、韓国が反共政策をとったため中国山東省出身が大部分である華僑たちも台湾国籍をもつようになった。また、韓国政府は華僑に対して非同化政策をとり、韓国籍への帰化を難しくした。
韓国政府は一九六〇年代から外国人の土地所有制限と重課税政策を実施したので華僑は財産権行使や就職の際、大変な思いをした。それによって彼らは海外に再移住するか、あるいは小資本と家族労働力で運営できる中華料理店を開くなど、業種をかえることを余儀なくされた。その結果、一九六〇年代末には華僑人口の七〇パーセントが飲食業に従事するようになった。しかし華僑から料理の技術を学んだ韓国人たちの進出によって、華僑たちの「中華料理店」は激減し、現在は探すのが難しいほどになってしまった。
韓国生活の生きがい
王さんもほかの華僑らと同じく、韓国に暮しながら「外国人」として多くの差別を受けた。しかしそれはもうむかしのことで忘れたい、何よりここでチャヂャン麺を売って、子どもたちに大学教育を受けさせることができたからそれで満足だと言う。
日常生活のなかで、彼は自分が韓国人だと思っている。国籍取得の手続きがとても複雑なため、王さんの国籍は依然として台湾だが、彼の韓国への思いは韓国人以上かもしれない。次男のお嫁さんは韓国人で、王さんは彼女が両班の出身だと誇りに思っている。韓国の国家有功者やお年寄りを大切にする王さんは、近所の国家有功者支援施設などからは、料金の三〇パーセントくらいを割引して注文を受けている。
友人も華僑よりは韓国人が多く、社交の舞台は地域の商工人の集まりだ。現在も慶山国際ロータリークラブの創立メンバーとしても活発に活動しており、ロータリーをつうじて、貧しい人びとを助けたり、奨学金を支援するなどの社会奉仕活動をおこなうことに、大きなやりがいを感じている。王さんの自宅のリビングには、いちばんよく見える場所に奉仕活動で受けた数十個の感謝牌(はい)や功労牌が誇らしく陳列されている。
変わる韓国の華僑政策
「韓国-チャイナタウンのない世界で唯一の国。もっとも強靭な生活力をもつ華僑たちも根付くことができずに去らなければならない国」。
以前は韓国人たちが誇りにしたフレーズだ。しかし、最近は韓国社会の閉鎖的な「単一民族意識」に反省をうながす意味でよく使われるようになった。今日の韓国社会で「華僑」ということばはグローバリゼーションの激流のなかで、韓国がいかに多文化・多民族共生の社会を作れるのかを論ずる象徴的なことばになってきている。
実際、韓国政府の外国人政策、特に華僑政策は最近、確実に大きな変化を見せている。二〇〇二年には永住権制度が実施され、二〇〇六年には永住権をもった外国人らに地方区の選挙権が与えられた。中国と交流が多い仁川市には数年前にチャイナタウンが新しく作られた。
しかし、このような努力にもかかわらず多文化の共存はいまだに達成されているとは言いがたい。仁川のチャイナタウンにしても、華僑たちは観光客を誘致する目的で作ったもので、華僑との社会的、文化的共存のために作られたものではないと批判する。王さんの孫たちが彼らの祖父のようにこれからもずっと韓国で暮らしていくかどうか、それは韓国社会が多文化共生の環境をどのように作るかにかかってくるだろう。
青友坊(チョンウバン)。韓国大邱市隣近の小都市慶山にある小さな中国料理の店、華僑による「本当の中華料理店」である。インタビュー当日、筆者にこの店の主人を紹介してくれた嶺南大学の朴賢洙(パクヒョンス)教授も同席した。その理由は、じつはこの店の名物であるチャヂャン麺を食べたかったからだ。チャヂャン麺はチュンヂャンという黒味噌を入れて炒めた具をかけた麺である。中国のザーザンミェン(炸醤麺)に由来をもち、韓国人の口に合うように改良された韓国の代表的な庶民食である。
青友坊の主人である王樹○(ワンチュウチン)さんは今年七〇歳。台湾出身の妻の陳翠梅(チュンチュウエイメイ)さん、長男の慶龍(チンロン)さん夫婦と小学校に通う二人の孫たちと一緒に住んでいる。青友坊は徹底した家族経営体制で運営され、厨房の仕事は奥さんと長男の担当、長男のお嫁さんはホールやカウンターの仕事をしている。王さん自身は総監督だが、店が忙しいときは配達を手伝う。
王さんの父親は中国山東省から一九二〇年代に朝鮮半島へ移住した。王さんは韓国生まれの二世である。王さん夫婦の三人の息子は、同居している長男のほかに、漢医師の次男と三男である。韓国で漢医師は高所得で誰もが羨望する職業だ。王さんは、息子たちが地元の漢医大で漢医師資格をえて、台湾で一年間鍼術(しんじゅつ)を習得した「正統」な漢方医であることに大きな自負心を感じている。
王さん一家や王さんの四人の兄弟姉妹の家族が集まるのは祖先への祭祀、旧正月と秋夕(旧盆)などの韓国の名節日だ。王さんはこのような家族の集まりをとても大事に思っている。王さんがキリスト教に改宗しない理由のひとつもこのためだ。クリスチャンとして教会の活動に参加すれば、社交の幅がずっと広くなり商売に役に立つだろうとは思う。でもクリスチャンになれば祖先祭祀ができなくなる。王さんはクリスチャンとして教会に出ることで商売の利益を上げるよりは、祖上祭祀をつうじて一家が集まる機会をもつことがもっと大切なことだと思っている。
華僑の苦難
韓国の華僑は数々の苦難を経験しながら今まで生き残ってきた。彼らの歴史は一八八二年、朝鮮内乱の鎮圧のため清の軍隊にしたがって来た商人集団によって始まった。現在約二万人を数える韓国華僑の生活は朝鮮半島の政治的状況に大きな影響を受けてきた。朝鮮半島が分断された後、韓国が反共政策をとったため中国山東省出身が大部分である華僑たちも台湾国籍をもつようになった。また、韓国政府は華僑に対して非同化政策をとり、韓国籍への帰化を難しくした。
韓国政府は一九六〇年代から外国人の土地所有制限と重課税政策を実施したので華僑は財産権行使や就職の際、大変な思いをした。それによって彼らは海外に再移住するか、あるいは小資本と家族労働力で運営できる中華料理店を開くなど、業種をかえることを余儀なくされた。その結果、一九六〇年代末には華僑人口の七〇パーセントが飲食業に従事するようになった。しかし華僑から料理の技術を学んだ韓国人たちの進出によって、華僑たちの「中華料理店」は激減し、現在は探すのが難しいほどになってしまった。
韓国生活の生きがい
王さんもほかの華僑らと同じく、韓国に暮しながら「外国人」として多くの差別を受けた。しかしそれはもうむかしのことで忘れたい、何よりここでチャヂャン麺を売って、子どもたちに大学教育を受けさせることができたからそれで満足だと言う。
日常生活のなかで、彼は自分が韓国人だと思っている。国籍取得の手続きがとても複雑なため、王さんの国籍は依然として台湾だが、彼の韓国への思いは韓国人以上かもしれない。次男のお嫁さんは韓国人で、王さんは彼女が両班の出身だと誇りに思っている。韓国の国家有功者やお年寄りを大切にする王さんは、近所の国家有功者支援施設などからは、料金の三〇パーセントくらいを割引して注文を受けている。
友人も華僑よりは韓国人が多く、社交の舞台は地域の商工人の集まりだ。現在も慶山国際ロータリークラブの創立メンバーとしても活発に活動しており、ロータリーをつうじて、貧しい人びとを助けたり、奨学金を支援するなどの社会奉仕活動をおこなうことに、大きなやりがいを感じている。王さんの自宅のリビングには、いちばんよく見える場所に奉仕活動で受けた数十個の感謝牌(はい)や功労牌が誇らしく陳列されている。
変わる韓国の華僑政策
「韓国-チャイナタウンのない世界で唯一の国。もっとも強靭な生活力をもつ華僑たちも根付くことができずに去らなければならない国」。
以前は韓国人たちが誇りにしたフレーズだ。しかし、最近は韓国社会の閉鎖的な「単一民族意識」に反省をうながす意味でよく使われるようになった。今日の韓国社会で「華僑」ということばはグローバリゼーションの激流のなかで、韓国がいかに多文化・多民族共生の社会を作れるのかを論ずる象徴的なことばになってきている。
実際、韓国政府の外国人政策、特に華僑政策は最近、確実に大きな変化を見せている。二〇〇二年には永住権制度が実施され、二〇〇六年には永住権をもった外国人らに地方区の選挙権が与えられた。中国と交流が多い仁川市には数年前にチャイナタウンが新しく作られた。
しかし、このような努力にもかかわらず多文化の共存はいまだに達成されているとは言いがたい。仁川のチャイナタウンにしても、華僑たちは観光客を誘致する目的で作ったもので、華僑との社会的、文化的共存のために作られたものではないと批判する。王さんの孫たちが彼らの祖父のようにこれからもずっと韓国で暮らしていくかどうか、それは韓国社会が多文化共生の環境をどのように作るかにかかってくるだろう。
海の仕事の映像収集
知覚と運動の役割分担
二〇〇七年七月九日、われわれ一行は、関西空港から帯広空港に向かった。一行とは、わたしと田上仁志さん、そして、アシスタントの北畠和明さんと中村伸夫さんの四人である。
田上さんは、民博の研究スタッフと共同して資料を収集・保存する情報管理施設の専門職員である。民博創立のころから映像収集を担当し、数々の撮影取材をこなしてきた。プロのカメラマンとして、民博になくてはならない人の一人である。
北畠さんは、マイクが担当。カメラが写す映像に無関係な音を拾わないよう、カメラの動きに注意しながら、ヘッドホンに耳をすます。中村さんは、照明が本来の担当だが、カメラやマイクから離れられない二人にかわり、他にもさまざまな作業をこなす。バッテリーやテープの交換、三脚の移動、カメラマンの足場の支持、車の運転などである。
こうした役割分担においては、「目」の役割をはたす田上さんと、「耳」である北畠さん、さらに両者をサポートする中村さんとのあいだで、息が合っていなければならない。テレビ取材よりも少人数だから、各人がそれぞれ瞬時の判断をしつつ、お互いをカバーし合う。三人はいわば、ひとつの知覚系統となって、記録を進めていくのである。
一方わたしは、機材に拘束されない点で、中村さんと同じ立場にある。ただ、中村さんが知覚系統の一部であるのに対し、わたしは、撮影地の人たちに対して積極的に働きかける。カメラに写る人から撮影許可をえたり、カメラの前で話しやすい雰囲気を作ったり、といった根回しがわたしの分担である。知覚系統がよりよい情報を拾えるよう、運動系統として周囲に働きかけるわけだ。
とはいえ、知覚系統が最大限に機能するよう、わたしもまた三人の動きを理解するよう努力している。映像取材とは、そうしたチームワークのもとで進む共同作業なのである。
裏切られた予想
今回の取材の主目的は、関西であまり知られていない北海道日高地方のコンブ採取の現場を記録することだった。しかし、コンブ採取シーズンをねらって取材地に滞在した一〇日間のうち、コンブを採取したのは一日だけだった。しかも、採取した時間も短く、収穫を喜ぶ場面は撮影できなかった。採取条件のよい日と悪い日、そのコントラストを一〇日間のうちに撮影しようというわたしの見通しは、みごとに裏切られてしまった。
ただ、取材が無駄だったわけではない。天気が悪くてコンブを採取しない日にも、撮影すべきことがあった。たとえば、こうした日には、村の誰かが抜け駆けして採取することのないよう、役職についた人が、漁港の旗竿に赤旗を掲げて合図する。この役職は「旗持ち」とよばれ、漁業組合の話し合いで選ばれる。この人が自らの役目を語る場面は、コンブ採取の状況を理解してもらううえで重要だった。
少し早い時間に、まず、わたし一人で旗持ちの家を訪ねてみる。今日は採取をおこなわない、二〇分ほどしたら漁港に行って赤旗を上げるというので、わたしは、携帯電話で田上さんに連絡をとった。そして、赤旗を上げるところを撮影し、その後にインタビューさせてもらうよう、旗持ちに頼み込んだ。
われわれは、旗持ちよりひと足早く漁港で落ち合うと、すばやくカメラ位置をさだめ、三脚にカメラを装着した。北畠さんが、車からとり出してきた白い板を胸のあたりに掲げ、田上さんは、その板にレンズを向ける。ホワイトバランスを調整しているのである。中村さんは、カメラの画角に取材班の車が写らないよう、建物のかげに車を移動している。
ほどなく旗持ちが車で漁港に到着し、赤旗を上げた。打ち合わせに反して帰ろうとする旗持ちを、わたしはあわてて引きとめ、五分ほどインタビューをおこなう。それが終わり、車に乗り込んだ旗持ちが港から遠ざかるまで、田上さんは、カメラを止めることなく旗持ちを追い続けた。
アーカイヴのための映像作り
テレビ取材なら、取材前に予期した場面を撮り逃すことは、致命的な失敗だろう。番組の主張に沿うような場面を、台本どおりに集めることが取材目的だからだ。場合によっては、「絵になる」場面を確実に撮影するため、複数のカメラを準備することもある。
いっぽう、民博の映像制作は、まったくちがった点を重視する。ビデオテーク番組では、絵になる場面を「いいとこどり」することもあるが、それは民博の映像制作のごく一部にすぎない。民博が収集した映像の価値は、ひとつの場面をえんえんと撮る「長回し」を多用していることにある。長回しは、テレビ取材では無駄なものとして切り捨てられるが、現地で何が起こったか理解するうえでは、貴重な手がかりを提供する。
たとえば、テレビ撮影なら、旗持ちへのインタビューが終わってから車を撮り続ける必要はない。しかし、インタビュー前後の場面があれば、粗編集の映像を研究資料としたり、一〇〇年経って史料として使ったりするときも、撮影時の状況を理解しやすくなる。いいかえれば、放送でなくアーカイヴ利用を想定して、映像作りがおこなわれているのだ。だいたい、絵になる場面を撮ろうとするなら、カメラ一台の少人数体制がテレビ取材に太刀打ちできる見込みはない。
一〇〇年後の二次利用まで見越して映像資料を残す点で、民博は、日本の最先端をきっている。NHKが公開している映像アーカイヴにしても、放送前に粗編集した映像ではなく、撮影状況を解釈するための材料に乏しい。民博の映像は、完璧ではないにしろ解釈の手がかりが豊富だし、関連した文字資料も残されている。開館三〇年を経て、その価値は、確実に増している。
収穫の喜びは撮影できなかったが、天気を心配する漁師の声や、雨の日の仕事はふんだんに撮影できた。そして何より、採取を待ち焦がれる漁師たちの気持ちを、われわれ撮影班が親身に理解できた。この結果、絵になる場面の寄せ集めではわからない、時間の流れに根ざした生活実感を記録できたと思う。この利点を生かして、番組編集にもとり組んでみたい。
なお、編集の実務は、田上さんの担当である。研究スタッフが提案した多数の取材をこなす合間に、彼は、ひたすらモニターに向かっている。民博の映像制作環境は、けっして優雅ではない。
二〇〇七年七月九日、われわれ一行は、関西空港から帯広空港に向かった。一行とは、わたしと田上仁志さん、そして、アシスタントの北畠和明さんと中村伸夫さんの四人である。
田上さんは、民博の研究スタッフと共同して資料を収集・保存する情報管理施設の専門職員である。民博創立のころから映像収集を担当し、数々の撮影取材をこなしてきた。プロのカメラマンとして、民博になくてはならない人の一人である。
北畠さんは、マイクが担当。カメラが写す映像に無関係な音を拾わないよう、カメラの動きに注意しながら、ヘッドホンに耳をすます。中村さんは、照明が本来の担当だが、カメラやマイクから離れられない二人にかわり、他にもさまざまな作業をこなす。バッテリーやテープの交換、三脚の移動、カメラマンの足場の支持、車の運転などである。
こうした役割分担においては、「目」の役割をはたす田上さんと、「耳」である北畠さん、さらに両者をサポートする中村さんとのあいだで、息が合っていなければならない。テレビ取材よりも少人数だから、各人がそれぞれ瞬時の判断をしつつ、お互いをカバーし合う。三人はいわば、ひとつの知覚系統となって、記録を進めていくのである。
一方わたしは、機材に拘束されない点で、中村さんと同じ立場にある。ただ、中村さんが知覚系統の一部であるのに対し、わたしは、撮影地の人たちに対して積極的に働きかける。カメラに写る人から撮影許可をえたり、カメラの前で話しやすい雰囲気を作ったり、といった根回しがわたしの分担である。知覚系統がよりよい情報を拾えるよう、運動系統として周囲に働きかけるわけだ。
とはいえ、知覚系統が最大限に機能するよう、わたしもまた三人の動きを理解するよう努力している。映像取材とは、そうしたチームワークのもとで進む共同作業なのである。
裏切られた予想
今回の取材の主目的は、関西であまり知られていない北海道日高地方のコンブ採取の現場を記録することだった。しかし、コンブ採取シーズンをねらって取材地に滞在した一〇日間のうち、コンブを採取したのは一日だけだった。しかも、採取した時間も短く、収穫を喜ぶ場面は撮影できなかった。採取条件のよい日と悪い日、そのコントラストを一〇日間のうちに撮影しようというわたしの見通しは、みごとに裏切られてしまった。
ただ、取材が無駄だったわけではない。天気が悪くてコンブを採取しない日にも、撮影すべきことがあった。たとえば、こうした日には、村の誰かが抜け駆けして採取することのないよう、役職についた人が、漁港の旗竿に赤旗を掲げて合図する。この役職は「旗持ち」とよばれ、漁業組合の話し合いで選ばれる。この人が自らの役目を語る場面は、コンブ採取の状況を理解してもらううえで重要だった。
少し早い時間に、まず、わたし一人で旗持ちの家を訪ねてみる。今日は採取をおこなわない、二〇分ほどしたら漁港に行って赤旗を上げるというので、わたしは、携帯電話で田上さんに連絡をとった。そして、赤旗を上げるところを撮影し、その後にインタビューさせてもらうよう、旗持ちに頼み込んだ。
われわれは、旗持ちよりひと足早く漁港で落ち合うと、すばやくカメラ位置をさだめ、三脚にカメラを装着した。北畠さんが、車からとり出してきた白い板を胸のあたりに掲げ、田上さんは、その板にレンズを向ける。ホワイトバランスを調整しているのである。中村さんは、カメラの画角に取材班の車が写らないよう、建物のかげに車を移動している。
ほどなく旗持ちが車で漁港に到着し、赤旗を上げた。打ち合わせに反して帰ろうとする旗持ちを、わたしはあわてて引きとめ、五分ほどインタビューをおこなう。それが終わり、車に乗り込んだ旗持ちが港から遠ざかるまで、田上さんは、カメラを止めることなく旗持ちを追い続けた。
アーカイヴのための映像作り
テレビ取材なら、取材前に予期した場面を撮り逃すことは、致命的な失敗だろう。番組の主張に沿うような場面を、台本どおりに集めることが取材目的だからだ。場合によっては、「絵になる」場面を確実に撮影するため、複数のカメラを準備することもある。
いっぽう、民博の映像制作は、まったくちがった点を重視する。ビデオテーク番組では、絵になる場面を「いいとこどり」することもあるが、それは民博の映像制作のごく一部にすぎない。民博が収集した映像の価値は、ひとつの場面をえんえんと撮る「長回し」を多用していることにある。長回しは、テレビ取材では無駄なものとして切り捨てられるが、現地で何が起こったか理解するうえでは、貴重な手がかりを提供する。
たとえば、テレビ撮影なら、旗持ちへのインタビューが終わってから車を撮り続ける必要はない。しかし、インタビュー前後の場面があれば、粗編集の映像を研究資料としたり、一〇〇年経って史料として使ったりするときも、撮影時の状況を理解しやすくなる。いいかえれば、放送でなくアーカイヴ利用を想定して、映像作りがおこなわれているのだ。だいたい、絵になる場面を撮ろうとするなら、カメラ一台の少人数体制がテレビ取材に太刀打ちできる見込みはない。
一〇〇年後の二次利用まで見越して映像資料を残す点で、民博は、日本の最先端をきっている。NHKが公開している映像アーカイヴにしても、放送前に粗編集した映像ではなく、撮影状況を解釈するための材料に乏しい。民博の映像は、完璧ではないにしろ解釈の手がかりが豊富だし、関連した文字資料も残されている。開館三〇年を経て、その価値は、確実に増している。
収穫の喜びは撮影できなかったが、天気を心配する漁師の声や、雨の日の仕事はふんだんに撮影できた。そして何より、採取を待ち焦がれる漁師たちの気持ちを、われわれ撮影班が親身に理解できた。この結果、絵になる場面の寄せ集めではわからない、時間の流れに根ざした生活実感を記録できたと思う。この利点を生かして、番組編集にもとり組んでみたい。
なお、編集の実務は、田上さんの担当である。研究スタッフが提案した多数の取材をこなす合間に、彼は、ひたすらモニターに向かっている。民博の映像制作環境は、けっして優雅ではない。
タブーの島のトビウオ漁
竹川 大介(たけかわ だいすけ) 北九州市立大学教授
大型回遊魚を連れてくる
南の島というと、常夏のイメージを思い浮かべる人が多いだろう。しかし実際には、赤道から離れるにしたがい島々に周期的な気候の変化があらわれ、作物や海産物にもそれぞれの旬が生じる。
南太平洋バヌアツ共和国の南部にフツナ島という小さな島がある。直径わずか四キロメートル、しかし標高が六六六メートルもあるプリン型をしたこの隆起珊瑚礁の島は、もっとも近い隣島から九〇キロメートルもはなれた濃紺の外洋に浮かんでいる。想像できるだろうか、そんな島に数百人あまりの人びとが、少なくとも六〇〇年以上も前から生活してきたのである。
この島の暮らしにとって欠かすことができない海洋資源が、季節的に島を訪れるトビウオたちである。八月から翌年の一月にかけてトビウオは島の風下に集まってくる。村の男たちは、月のない夜にカヌーの上から明かりを使って、トビウオをおびき寄せ、タモ網で捕獲する。
トビウオの群れはマグロやサワラ、シイラ、カマスなどの大型回遊魚を連れてくる。三時間ほどのトビウオ漁が終わると、朝方まで大型回遊魚釣りが続けられる。ラマガとよばれるこの漁は、数ある漁法のなかでももっとも重要なものとされ、多くのタブーによって成り立っている。
そうタブー、つまり禁忌(きんき)である。そもそもタブーということばはポリネシア語に由来する。ポリネシア文化の影響を受けたフツナ島にも、生活の端々までさまざまなタブーが張りめぐらされている。
たとえば、ラマガの期間、漁に出かける男たちは浜で寝起きをともにしなければならない。またこの時期の魚は農作物と相性が悪い。とくにヤムイモとタロイモは精霊の力を多く宿している重要な食料とされ、漁のときに海にもって行ってはならないし、漁に出る人は焼畑作りにすら参加できない。
ラマガの主要捕獲対象であるマグロやサワラの仲間は「男の魚」とよばれ、とりわけ丁重にあつかわれる。魚は浜でウロコを取ることすら許されず、大きかろうが重かろうが、かならず丸のまま村にもち帰られる。
さらに不思議なことに、漁に出る男たちはこの「男の魚」を食べてはならないのである。「男の魚」は老人や子ども、そして漁に出ない女たちのための食料なのだ。
エコロジーよりタブー
ところでわたしは大学院生のころに台湾の南東沖にある蘭嶼(らんゆい)に滞在したことがある。蘭嶼もまたトビウオ漁が有名な島で、カヌーを使った魚灯漁をおこない、トビウオを餌に大型回遊魚を捕獲し、そして男女によって異なる魚の食物禁忌があった。
七五〇〇キロメートルも離れたふたつの小島で、トビウオにまつわるとてもよく似た文化が守られている。これが偶然なのか、はたまた同じ太平洋文化の流れをくむものなのか、興味は尽きない。
蘭嶼は北緯二二度、フツナ島は南緯一九度、最初に述べたように、年間をとおして周期的な季節変化が見られる地域である。
フツナの人びとは、雨期と乾期をつかさどる精霊が半年ごとに海と島を行き来すると語る。精霊は乾期に海の魚を繁殖させ、雨期には畑に豊饒をもたらす。もしその循環が乱れると、島に暮らす人びとには死活問題となる。
トビウオの群れは季節周期の象徴である。彼らはタブーということばを用いて、人知を超えた自然のサイクルを畏れ敬ってきた。かたやわたしたちは、地球レベルの気候変化にすら鈍感になってしまったようだ。現代人に必要なのはエコロジーよりタブーなのかもしれない。
南の島というと、常夏のイメージを思い浮かべる人が多いだろう。しかし実際には、赤道から離れるにしたがい島々に周期的な気候の変化があらわれ、作物や海産物にもそれぞれの旬が生じる。
南太平洋バヌアツ共和国の南部にフツナ島という小さな島がある。直径わずか四キロメートル、しかし標高が六六六メートルもあるプリン型をしたこの隆起珊瑚礁の島は、もっとも近い隣島から九〇キロメートルもはなれた濃紺の外洋に浮かんでいる。想像できるだろうか、そんな島に数百人あまりの人びとが、少なくとも六〇〇年以上も前から生活してきたのである。
この島の暮らしにとって欠かすことができない海洋資源が、季節的に島を訪れるトビウオたちである。八月から翌年の一月にかけてトビウオは島の風下に集まってくる。村の男たちは、月のない夜にカヌーの上から明かりを使って、トビウオをおびき寄せ、タモ網で捕獲する。
トビウオの群れはマグロやサワラ、シイラ、カマスなどの大型回遊魚を連れてくる。三時間ほどのトビウオ漁が終わると、朝方まで大型回遊魚釣りが続けられる。ラマガとよばれるこの漁は、数ある漁法のなかでももっとも重要なものとされ、多くのタブーによって成り立っている。
そうタブー、つまり禁忌(きんき)である。そもそもタブーということばはポリネシア語に由来する。ポリネシア文化の影響を受けたフツナ島にも、生活の端々までさまざまなタブーが張りめぐらされている。
たとえば、ラマガの期間、漁に出かける男たちは浜で寝起きをともにしなければならない。またこの時期の魚は農作物と相性が悪い。とくにヤムイモとタロイモは精霊の力を多く宿している重要な食料とされ、漁のときに海にもって行ってはならないし、漁に出る人は焼畑作りにすら参加できない。
ラマガの主要捕獲対象であるマグロやサワラの仲間は「男の魚」とよばれ、とりわけ丁重にあつかわれる。魚は浜でウロコを取ることすら許されず、大きかろうが重かろうが、かならず丸のまま村にもち帰られる。
さらに不思議なことに、漁に出る男たちはこの「男の魚」を食べてはならないのである。「男の魚」は老人や子ども、そして漁に出ない女たちのための食料なのだ。
エコロジーよりタブー
ところでわたしは大学院生のころに台湾の南東沖にある蘭嶼(らんゆい)に滞在したことがある。蘭嶼もまたトビウオ漁が有名な島で、カヌーを使った魚灯漁をおこない、トビウオを餌に大型回遊魚を捕獲し、そして男女によって異なる魚の食物禁忌があった。
七五〇〇キロメートルも離れたふたつの小島で、トビウオにまつわるとてもよく似た文化が守られている。これが偶然なのか、はたまた同じ太平洋文化の流れをくむものなのか、興味は尽きない。
蘭嶼は北緯二二度、フツナ島は南緯一九度、最初に述べたように、年間をとおして周期的な季節変化が見られる地域である。
フツナの人びとは、雨期と乾期をつかさどる精霊が半年ごとに海と島を行き来すると語る。精霊は乾期に海の魚を繁殖させ、雨期には畑に豊饒をもたらす。もしその循環が乱れると、島に暮らす人びとには死活問題となる。
トビウオの群れは季節周期の象徴である。彼らはタブーということばを用いて、人知を超えた自然のサイクルを畏れ敬ってきた。かたやわたしたちは、地球レベルの気候変化にすら鈍感になってしまったようだ。現代人に必要なのはエコロジーよりタブーなのかもしれない。
トビウオ (学名:Exocoetidae)
捕食者である大型回遊魚から逃れる際に海面を滑空することからこの名がある。日本では沖縄列島から、太平洋の黒潮流域、日本海の対馬海流域の沿岸部を回遊する。刺網や定置網によって群れ単位で大量に捕獲されることが多く、各地で干物などの保存食やダシとして利用されている。またトビウオの特産地である屋久島では、伝統的なトビウオ招きの儀礼がある。
フツナ島ではハマトビウオ属(Cypselurus spp.)の7種のトビウオが確認された。
捕食者である大型回遊魚から逃れる際に海面を滑空することからこの名がある。日本では沖縄列島から、太平洋の黒潮流域、日本海の対馬海流域の沿岸部を回遊する。刺網や定置網によって群れ単位で大量に捕獲されることが多く、各地で干物などの保存食やダシとして利用されている。またトビウオの特産地である屋久島では、伝統的なトビウオ招きの儀礼がある。
フツナ島ではハマトビウオ属(Cypselurus spp.)の7種のトビウオが確認された。
アナ・ボトルのクジ遊び
森田 良成(もりた よしなり) 大阪大学大学院人間科学研究科
ぱっとしない景品
インドネシア、西ティモールの町クパン。ある朝、一軒のキオスクの店先にクジが吊るされた。ふたつ折りになった小さな厚紙が、シートにびっしりとホチキスで留めてある。二五〇ルピア(日本円で三円程度)を払って一本引きちぎる。なかに何も書かれていなかったら「はずれ」で、数字が書かれてあれば「当たり」。数字に応じて、プラスティック製の掛け時計、Tシャツ、石鹸、ハミガキ、インスタントラーメン、いくつかの銘柄のタバコといった景品のどれかが手に入る。
当たりは一〇〇〇本のうち五〇本程度で、しかも景品の半分以上は、タバコ一本。これなら目の前のキオスクで、クジ一回分と同じ二五〇ルピアで買えてしまう。他の景品のほとんどもキオスクで手に入る日用品だ。しかし、ラーメンは一袋一〇〇〇ルピアが定価だし、三〇〇〇~九〇〇〇ルピアするタバコ一箱を一回で引き当てたりすればかなりお得である。とはいえ、やはり空クジが多いし、景品の品ぞろえもいまひとつぱっとしない。遊び半分に一、二回引いてみるにはいいかもしれないが、こんなクジが果たして人をどれほど惹きつけるだろう。クジを作ってキオスクに売り歩いていたジャワ人の男も、「人の多いジャワの町でならともかく、こんな小さな町のキオスクでは、シート一枚分のクジが売り切れるまで早くても二週間はかかる」と踏んでいた。
クジを買い尽くす
だがその夜までに、一〇〇〇本のクジはもう残り四〇本ほどに減っていた。年配の者や少年たち三〇人ほどがクジを取り囲んでいる。あたりにふしぎな活気と緊張感が漂っていて、地面には紙ふぶきを撒いたあとのように空クジが散っている。アナ・ボトル(瓶の子)とよばれる、キオスクの周りで寝起きし、町で空き瓶などの廃品回収をして収入をえている出稼ぎの男たちだ。彼らの仕事は、空き瓶一本につきやっと一〇〇ルピアの儲けをえるというものである。そんな彼らが一〇〇〇ルピア、二〇〇〇ルピアと金を払い、次々にクジを引いていく。
少年サルスが「おーっ」と叫んだ。最後まで残っていた「タバコ一箱」を引き当てたのだ。彼はクジと引き換えにタバコをつかみとると、足早にキオスクの裏へ消えた。同郷のオビ、オノ、イバの三人が浮かれた表情で彼を追った。この場にいるサルスの同郷者は彼らだけで、他にはタバコのわけ前を求める者はいない。幕切れは案外あっけないものだった。キオスクのもち主はやれやれといった表情でだいぶ遅くなった店じまいをし、男たちもそれぞれの寝場所へ散っていった。
こうして、ジャワ人が二週間と踏んだクジは一晩と経たないうちにアナ・ボトルたちによって買い尽くされてしまった。みなで一気に買い尽くせば、何人かは当たりを引くが、大量のはずれもみなで引き受けねばならない。何度目かでやっと当たりを引いたとしても、安物の景品だったら差し引きでは損をしたままだ。なぜアナ・ボトルたちはこんなことをしたのだろう。彼らは結局、むやみに金を捨ててしまっただけではないだろうか。
誰かは当たりを
将来の計画を立て、それに沿って行動し、問題が生じればその都度調整する。先見性、自己規律、地道な努力。これらこそが望ましい未来をもたらしてくれると、われわれは思っている。
だが一方でわれわれは、偶然に舞い込む幸運への期待をどこか拭いきれないでいる。自分や特定の誰かのことになると、めったにない偶然がまるで当たり前のように起こると思ってしまうことはないだろうか。自分の買った一枚きりの宝くじがみごと当選するのではという希望にとりつかれたり、あるいはドラマでしかありえないような突然の「運命的な出会い」を期待してしまったり。
アナ・ボトルたちは、廃品回収のルートを互いに申し合わせて、予め重ならないようにしていない。そのため、同じ道を一日に何人ものアナ・ボトルがとおることになる。粗末な荷車を押しながら、何人かが昨日もその道をとおったろうし、翌日もやはりそうだろう。限られた量しかない廃品を手に入れるのは、彼らのうちの一人か二人だけだ。これではあまりに非効率的である。しかし彼らにとって重要なのは、こうした非効率を無くすことよりも、その道でたしかに誰かが廃品を手に入れることであり、かつその誰かとは自分かもしれないということなのである。この可能性を維持するために、彼らは歩き続けるのだ。
アナ・ボトルの多くが、景品にありつけずにただ金を失った。だがそれは後になって言えることだ。クジを引く前にはそんなことはわからなかった。多くの者はたしかにはずれを引く。だが、誰かは間違いなく当たりを引く。その誰かが自分でないとは限らない。いやそれはもう自分なのではないか。
わたしは結局クジを一本も引かなかった。景品に魅力を感じられなかったのだ。だがもし引いていたら、タバコ一箱くらいはあっさり当てて、みんなの喝采を浴びていただろう。
インドネシア、西ティモールの町クパン。ある朝、一軒のキオスクの店先にクジが吊るされた。ふたつ折りになった小さな厚紙が、シートにびっしりとホチキスで留めてある。二五〇ルピア(日本円で三円程度)を払って一本引きちぎる。なかに何も書かれていなかったら「はずれ」で、数字が書かれてあれば「当たり」。数字に応じて、プラスティック製の掛け時計、Tシャツ、石鹸、ハミガキ、インスタントラーメン、いくつかの銘柄のタバコといった景品のどれかが手に入る。
当たりは一〇〇〇本のうち五〇本程度で、しかも景品の半分以上は、タバコ一本。これなら目の前のキオスクで、クジ一回分と同じ二五〇ルピアで買えてしまう。他の景品のほとんどもキオスクで手に入る日用品だ。しかし、ラーメンは一袋一〇〇〇ルピアが定価だし、三〇〇〇~九〇〇〇ルピアするタバコ一箱を一回で引き当てたりすればかなりお得である。とはいえ、やはり空クジが多いし、景品の品ぞろえもいまひとつぱっとしない。遊び半分に一、二回引いてみるにはいいかもしれないが、こんなクジが果たして人をどれほど惹きつけるだろう。クジを作ってキオスクに売り歩いていたジャワ人の男も、「人の多いジャワの町でならともかく、こんな小さな町のキオスクでは、シート一枚分のクジが売り切れるまで早くても二週間はかかる」と踏んでいた。
クジを買い尽くす
だがその夜までに、一〇〇〇本のクジはもう残り四〇本ほどに減っていた。年配の者や少年たち三〇人ほどがクジを取り囲んでいる。あたりにふしぎな活気と緊張感が漂っていて、地面には紙ふぶきを撒いたあとのように空クジが散っている。アナ・ボトル(瓶の子)とよばれる、キオスクの周りで寝起きし、町で空き瓶などの廃品回収をして収入をえている出稼ぎの男たちだ。彼らの仕事は、空き瓶一本につきやっと一〇〇ルピアの儲けをえるというものである。そんな彼らが一〇〇〇ルピア、二〇〇〇ルピアと金を払い、次々にクジを引いていく。
少年サルスが「おーっ」と叫んだ。最後まで残っていた「タバコ一箱」を引き当てたのだ。彼はクジと引き換えにタバコをつかみとると、足早にキオスクの裏へ消えた。同郷のオビ、オノ、イバの三人が浮かれた表情で彼を追った。この場にいるサルスの同郷者は彼らだけで、他にはタバコのわけ前を求める者はいない。幕切れは案外あっけないものだった。キオスクのもち主はやれやれといった表情でだいぶ遅くなった店じまいをし、男たちもそれぞれの寝場所へ散っていった。
こうして、ジャワ人が二週間と踏んだクジは一晩と経たないうちにアナ・ボトルたちによって買い尽くされてしまった。みなで一気に買い尽くせば、何人かは当たりを引くが、大量のはずれもみなで引き受けねばならない。何度目かでやっと当たりを引いたとしても、安物の景品だったら差し引きでは損をしたままだ。なぜアナ・ボトルたちはこんなことをしたのだろう。彼らは結局、むやみに金を捨ててしまっただけではないだろうか。
誰かは当たりを
将来の計画を立て、それに沿って行動し、問題が生じればその都度調整する。先見性、自己規律、地道な努力。これらこそが望ましい未来をもたらしてくれると、われわれは思っている。
だが一方でわれわれは、偶然に舞い込む幸運への期待をどこか拭いきれないでいる。自分や特定の誰かのことになると、めったにない偶然がまるで当たり前のように起こると思ってしまうことはないだろうか。自分の買った一枚きりの宝くじがみごと当選するのではという希望にとりつかれたり、あるいはドラマでしかありえないような突然の「運命的な出会い」を期待してしまったり。
アナ・ボトルたちは、廃品回収のルートを互いに申し合わせて、予め重ならないようにしていない。そのため、同じ道を一日に何人ものアナ・ボトルがとおることになる。粗末な荷車を押しながら、何人かが昨日もその道をとおったろうし、翌日もやはりそうだろう。限られた量しかない廃品を手に入れるのは、彼らのうちの一人か二人だけだ。これではあまりに非効率的である。しかし彼らにとって重要なのは、こうした非効率を無くすことよりも、その道でたしかに誰かが廃品を手に入れることであり、かつその誰かとは自分かもしれないということなのである。この可能性を維持するために、彼らは歩き続けるのだ。
アナ・ボトルの多くが、景品にありつけずにただ金を失った。だがそれは後になって言えることだ。クジを引く前にはそんなことはわからなかった。多くの者はたしかにはずれを引く。だが、誰かは間違いなく当たりを引く。その誰かが自分でないとは限らない。いやそれはもう自分なのではないか。
わたしは結局クジを一本も引かなかった。景品に魅力を感じられなかったのだ。だがもし引いていたら、タバコ一箱くらいはあっさり当てて、みんなの喝采を浴びていただろう。
編集後記
人間様の食料をかすめ、疫病さえもたらすネズミは十二支のなかでももっとも嫌われ者の動物かもしれない。「巳」も苦手な人は多いだろうが、蛇は神妙なオーラを宿している。ネズミは身近すぎて、小さすぎて、ちょこまかしすぎて、それほど神秘を感じさせない。
しかし人びとの生活圏に密着した動物だからこそ、民話やアニメのキャラクターとして親しみを覚えるのであろう。「都会のねずみと田舎のねずみ」や「ねずみの嫁入り」の話には人間社会の縮図を見出すことができるし、ミッキーマウスは擬人化されて、イヌまで飼っているではないか。
それにしても、同じく身近にいる嫌われ者であるゴキブリの民話はあまり聞いたことがない。気になってざっとネット検索してみたら、沖縄、ロシア、イラン、アフリカ、キューバなどにゴキブリが登場する民話はあるようだ。しかも沖縄の民話は、ノミ、シラミ、ゴキブリの害虫トリオが繰り広げる、「食い物の恨み」に絡んだなんとも人間くさい話だ。
正月早々、おせち料理の箸休めにネズミの丸焼きだの串焼きだのについてお読みくださいという雑誌は『月刊みんぱく』ぐらいであろう。
今年もよろしくお付き合いのほどをお願い申し上げます。(山中由里子)
しかし人びとの生活圏に密着した動物だからこそ、民話やアニメのキャラクターとして親しみを覚えるのであろう。「都会のねずみと田舎のねずみ」や「ねずみの嫁入り」の話には人間社会の縮図を見出すことができるし、ミッキーマウスは擬人化されて、イヌまで飼っているではないか。
それにしても、同じく身近にいる嫌われ者であるゴキブリの民話はあまり聞いたことがない。気になってざっとネット検索してみたら、沖縄、ロシア、イラン、アフリカ、キューバなどにゴキブリが登場する民話はあるようだ。しかも沖縄の民話は、ノミ、シラミ、ゴキブリの害虫トリオが繰り広げる、「食い物の恨み」に絡んだなんとも人間くさい話だ。
正月早々、おせち料理の箸休めにネズミの丸焼きだの串焼きだのについてお読みくださいという雑誌は『月刊みんぱく』ぐらいであろう。
今年もよろしくお付き合いのほどをお願い申し上げます。(山中由里子)
定期購読についてのお問い合わせは、ミュージアムショップまで。 本誌の内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。