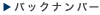月刊みんぱく 2009年3月号
2009年3月1日発行
第一に「すべてのインド人が数学の天才である」という事実はない。確かにインド人はゼロを発見し、ラマヌジャンのような天才数学者を輩出したが、数学に弱い市井の人はたくさんいる。
第二に、インド数学の本当の凄さは「九十九の段のかけ算ができる」といった表面的なことではなく、彼らの思考の深さにある。論より証拠で、インドで最も広く使われている算数教科書『Math-Magic』(小学一年生用)を見てみよう。第一章「形と空間」は、次のような物語で始まっている。
ある冬の日、ラクダで旅をしていたアラブ人が砂漠で野営をすることになった。しかしテントが小さく、中にはアラブ人しか入れない。あまりの寒さに外のラクダが「首だけ中に入れていいですか」と問うと、アラブ人は承諾する。暫くするとラクダは「まだ寒いので前脚も入れていいですか」と問い、アラブ人は再び承諾する。これを繰り返すうち、やがてラクダはまんまと全身をテントの中に入れることに成功し、アラブ人はテントの外に追い出されてしまうという内容だ。
子どもたちは大笑いしながら物語を楽しむわけだが、注目すべきは、インドでは算数教育のいちばん初めに「内側と外側」の空間認識が教えられている点である。
教科書はこのあと「より遠い」と「より近い」、「いちばん上」と「いちばん下」など位置や距離の概念について、これでもかこれでもかと(しかし楽しいイラスト付きで)徹底的に教えているのだ。
これに対して日本の標準的な教科書では、1から9までのアラビア数字(これもインド人が考案した文字である)が最初に教えられ、数字の書き順の練習がそのあとに続く。
どちらの教科書がより優れているかと比較するつもりはないが、インドの教科書のほうが深くものを考えさせてくれることは間違いないだろう。
もう一つ特筆すべきは、インドの算数教科書の多くが英語で書かれていることである。念のために言っておくが、これはエリート層を対象に作られた教科書ではなく、ごく普通の庶民の子も使う一般教科書だ。人生最初の数学へのアプローチが、日本では技術的・方法的であるのに対し、インドではいきなり哲学の核心部分に触れている感がある。この違いはまことに興味深い。
「最初からインド数学に勝負あり!」と思うのは私だけだろうか。
やまだ まみ/1960年長野市生まれ。作家、日印芸術研究所言語センター長。3ヵ国4大学で経済学・海洋学・インド哲学・密教学を学ぶ。著書多数。インド文化、カウラ事件、バイリンガル教育などに造詣が深い。2007年、ドクター・アーナンダ・クマラスワミ・フェロー(インド国立文学アカデミー)。日本文化デザインフォーラム、日本蜘蛛学会、宇宙作家クラブ会員。
http://yamadamami.com/
研究者は調査や研究の過程でたくさんのモノをため込んでおり、論文や本などのかたちで公表されるモノはその一部に過ぎない。公にならない膨大かつ雑多な知識をそのまま墓場にもっていくといっていい。民博の収蔵品も展示に供されたり、研究用に活用されるのもそのほんの一部にすぎない。その豊かな文化資源は、研究資料として使うことは当然のことだが、我々だけでなく、外部の人にもさまざまな異なる観点から利用形態を考えて提案してもらうことで、もっと活きてくるはずである。民博は、大きく叩くと大きく響く、そんな可能性を秘めている組織でいたい。
「千家十職×みんぱく―茶の湯のものづくりと世界のわざ」展は、民博の資料が、研究資料を越えて、さまざまなかたちで利用されることを千家十職の人と試みようとしたものである。千家十職は三〇〇年から四〇〇年をこえる長い歴史のなかで、利休好みのかたちや色を守ってきただけでなく、その時代時代に合わせ、創意工夫して新しい道具を制作してきた集団である。アーチストとよんだ方がよい人から職人気質の人まで、いろいろな人がそろっている。そのためうまくいけば、民博の資料が、研究のためだけでなく、さまざまな職種の人にとって創造の源泉になりうる実例を示すことができる。そう思って交渉を開始したのである。とはいえ、まさか十職の人たちが、こんな風変わりな企画を受け入れるとは思ってもみなかった。ところがモノを作る人たちである。この企画が実現したのも、その人たちにとって、民博は創造を刺激してあまりある資料をたくさん抱え込んでいる宝庫であったから、と信じたい。
日本の伝統と世界の出合い
二〇〇七年二月に十職の方々に展示場を、そして、二〇〇八年に入って、収蔵庫の資料を見てもらった。それは彼らの目を通して深い眠りについているモノたちを揺り起こす作業であった。民博の収蔵資料は収集時期順に棚に収められている。そのため、アフリカの壺の横にメキシコの人形があったりして、調査する者にとってはコンピュータの補助がないと目的にあった必要なモノに出合うことができない。見る者にとって渾沌を極めた世界といってよい。それがかえって創造者には刺激を与える。
彼らが選んだ資料は、大げさに言えば、世界を切り取ったものである。そのなかで特に創造を刺激する資料をもとにして、作品が作られた。茶道具を作るという制限のなかで作られた作品が、選ばれたモノたちとともに並んでいる。
十職が民博を活用した成果の展示が一階なら、民博が十職に応えようとしたのが二階の展示である。我々は十職の手仕事を動詞で考えてみた。民博にあるほとんどの資料も手仕事によるものであり、「叩く」「塗る」などの動詞を利用して、素材や民族によって、どれだけ異なるものが生み出され、多様性があるかを示すことにした。
その風景はいかなるものか。ぜひご覧いただきたい。
博物館を見学者としての立場から一言でいえば、まずは未知の知識をえ、あるいは既知の知識を確認できる場のひとつ、となるだろう。
または構想を練ったり発想をえたり、あらたな創作や創造活動の手がかりをつかむ、といった利用もあろう。
「千家十職×みんぱく」は、このうち創出という意図を深く込めて企画している。十職の方々が民博の資料を実際に手にして、どのように作品を創作するのか。これがこの特別展の目玉である。それは同時に、民博が創造への契機、発想の源泉となりうることの証明である。特別展の第三のテーマである「手仕事を動詞で考える」は、その答えの一部である。
資料の選択にあたって十職の方々は、展示場と収蔵庫をじっくり目で見ながら探していった。直感や直観のよる選択である。そして、資料の名称、つまり名詞を基にコンピューターで検索したリストも参照した。
動詞で検索
見方を変えると見えてくる内容も変わる可能性があるならば、見方は多様な方が展望は開けやすいだろう。そこでわたしたちは動詞を検索語として試みた。十職の仕事内容にふさわしい動詞として、叩く、鋳こむ、捏(つく)ねる、削る、描く、塗る、張る、組む、曲げる、切る、縫うの、十一語を選び出した。そしてそれらの動詞を軸に、関連する動詞を含めて四八語(活用形はその幾倍かはあった)を全件、制作法・材料、用途使用法といった項目から検索していった。民博の収蔵標本資料は二〇〇八年四月現在、二五万七八六〇点を数えるが、そのなかから検索語に一致したのは二二万件余。ここから展示内容に適したほぼ一万九〇〇〇件を詳細に確認し、さらに展示にふさわしいものとして一一〇四件を抽出した。
結果は予想どおり、動詞を使わないと選ばれにくい資料が数多く登場してきた。代表例は樹皮布、スティールドラム、教会の置物、竹製ハープ、毛糸絵、竜骨車、樹皮製カヌー、影絵人形、サケ皮の靴などである。
例えば樹皮布の場合、これは金物師の仕事にあたる「叩く」という動詞に関連している。金物師は端的にいえば金属を叩き伸ばして容器を作り、樹皮布は樹皮を叩き伸ばして作る布である。金属とか容器といった名詞だけの検索では引っかかってこない。これはあらたに視点を設けたことの成果であり、この展示が今後の創造のキッカケにつながっていけば、なによりである。
それにしても、作業中に考えたことは、博物館に蓄積された情報はまだまだ足りないのではないかということである。博物館に資料を提供した制作者の方々や博物館の利用者の方々が、自らの経験や知識、思いなどをどしどし寄せて、関連する資料の情報を豊富にし、また別の利用者がその情報をえて、活用するという機能は、博物館にはおおいに必要なことだろう。実際に足を運ぶ来館者に限らず、インターネットなども利用して、情報を相互に活用できるようにするというのは、まさに開かれた情報集積回路の整備といえる。集まる情報の正確さの確保という問題点はあるにせよ、今後、積極的に挑戦すべき課題だろう。
今回の展示をご覧になる方のなかには、ある種の戸惑いを感じられる方が少なからずいらっしゃると思う。その戸惑いとは、露出展示とケース内展示とが截然(せつぜん)とされ、しかも前者はほとんどが民博の所蔵品であるということではなかったろうか。民博の品物はなぜケースにいれないの?と。
じつはこれはわたくし自身の戸惑いでもあった。わたくしは古いタイプの博物館員である。だから、というわけではないが、油絵や彫刻作品を除けば、展示という行為には常にケースが伴っていた。ケースは展示品の安全を守ると同時に、展示品のもつさまざまな価値をその空間のなかで充分にひき出すことができる、と教えられもし実践もしてきたつもりである。
ところが民博では、あまりケースを重要視しないようだ。それは展示する品物の質にもよるということであろうか。民博で展示に使用する品物を含め、収蔵品を「標本」と称している。辞書によれば「標本」というのは「実物を採取・保存しておいて見本として示すもの」とある。そしてそれは民博の職員がみずからの研究目的とその視点とにより収集したもので、あくまで研究の対象としてなのである。創立の当初から民博には「おたから」はないのである。この考え方は日本の博物館では民俗資料の展示にもつながっている。
ケースを利用しての展示は多くの博物館・美術館でおこなわれている方法である。この場合、展示の対象品は資料であり、文化財である。そして多くは美術工芸品に分類される品物である。なかには文化財保護法により国宝や重要文化財に指定されたものもある。また法律の指定はなくとも、これらはいわば「おたから」である。十職のお家では代々伝えられた家宝でもある。当然、取扱は慎重でなければならない。しかしこうした品物は、展示環境さえ整えてあれば、展示は意外に楽である。なんとなれば、品物みずからがその存在を主張しているからだ。わたくしはこうも教えられた。すなわち「ものをして語らしめよ」と(じつはこれが一番むつかしいのだけれども…)。
やはりケースに
露出展示にはもちろん露出展示のよさがあり、ケース内展示にはまたそのよさもある。それらを一緒にしたかたちでの展示もまた面白いといえる。しかし、ケースの内側の品物は外に出たいとは思わないだろうし、外にある品物もそのままでいいとは思わないかもしれない。標本であっても、その素材はケース内の品物と同様に脆弱(ぜいじゃく)なものも少なくないし、第一、集められてから充分の時間を経ている。かれらは疲れている。そして、もはや「おたから」の地位さえ得ているものも少なくない。
「やはりすべてをケースにいれてほしかった」と老いたる古き博物館員はつぶやくのである。
しかし、何よりも興味深かったのは、職人たちの手仕事の技そのものであった。ある鍛冶職人によれば、「鉄が動く」という。鉄の塊を製品にするには、鉄をうまく動かさなくてはいけない。思ったように動かせるようにならないと、製品は作れないというのである。わたしは「なるほど、そうですよね」などと軽く相づちをうち、メモを取りながら、堅い鉄が動くなんてたとえ話だろうと高をくくっていた。しかし、そうではなかったのである。
実際に作業が始まると、彼は鉄の塊を鋏でつかみ、ふいごであおった炉の炎に入れて十分熱し、金床にのせて金鎚で叩き始めた。叩くたびに火花が飛び散り、表面に黒ずんだ不純物が浮かんではがれ落ち、そのうち、堅かったはずの塊が次第にかたちを変え始めた。彼はそれを、まるで飴細工のように延ばしては折りたたみ、それを何度も繰り返す。そして、あるときは更に延ばし、あるときは広げ、またあるときは細く尖らせる。すると、さまざまな製品が次第にかたちをあらわしてくる。それは、確かに「鉄が動く」としかいいようがない光景だった。わたしは、動く鉄の姿に思わず魅入って目をそらすことができなくなっていた。
一般の人びとには幻術や魔術としか思えないような、思いもよらない素材の可塑性を巧みに引き出す手仕事の技は、鉄に限らず木や土や紙をあつかう職人たちにも共通する。人びとが彼らの技に訳もなく魅せられてしまうのも、そのあたりに由来しているのかも知れない。
一週間に一度ほど、マイ氏は夕方暗くなってから窯焼きにとりかかる。作業は四、五時間かけて、窯の入り口に少しずつ薪である木の枝を突っ込むことから始まる。窯が高温に達すると、蓋を閉めて蒸らした状態で数日おく。窯の温度は最高で一二〇〇度にも達する。煙突から立ち上る煙やのぞき窓から温度の確認をする。
この「煙を読む」作業には、素人にはわからない熟練の勘が必要である。焼成は、季節や天候に左右されるため、微妙な調整をしなければならない。焼成した土器の全てがうまく焼けているとは限らず、一部はヒビが入っていたりする。マイ氏は、九〇%以上の土器がうまく焼けていれば上出来であるという。以前に一度だけ、作業の途中で眠ってしまい、失敗したことがあった。そんな彼の必須アイテムが缶コーヒーである。焼成の日は、雑貨店で数本の缶コーヒーを購入する。
火のそばでの作業は汗だくになる。六〇歳代のマイ氏にとって、決して楽ではない仕事である。彼は、以前、成形の職人をしていたことがあるが、今では窯焼きの仕事をするようになった。一晩集中して、一気に土器を焼き上げて終了、そんな焼成作業が自分の性分にあっているのだという。
仕事の報酬は一回五〇〇バーツ。決して高くはないが、子どもが独立した彼が生きていくのに足る値段である。焼成が終わった日、一眠りをしたあと、外に出てきたマイ氏は必ずビールを買う。やはり仕事後のビールは格別の味だ。
今も時折思い出すのは、農村地帯の暗闇のなかで、煙突から出る煙をじっと見つめながら、缶コーヒーを飲む彼の姿である。
わたしが修復を担当したのは、黒漆塗金蒔絵女乗物(くろうるしぬりきんまきえおんなのりもの)という大名家の婚礼等で用いられた女性専用の駕籠(かご)である。漆工品の文化財の保存修復は漆芸家が漆を用いておこなうことが多いが、この修復では、例えば再修復の際、除去できる材料を用いることが方針であった。そこで、除去の難しい漆は用いず、除去の可能な合成樹脂や膠(にわか)、小麦でんぷん糊などで修復することとなり、わたしが担当することになったのである。
しかし、女乗物が大名家の調度品である以上、仕上がりの美しさは当然求められる。わたしは手持ちの材料でそこまでできるのかと困った挙句、奈良在住の漆芸家であり、また数多くの漆工品の修復を手掛けられている北村昭斎先生、繁先生のもとに教えを乞いにうかがった。ここでは漆芸技法の知識だけではなく、実際に漆塗りの技術を体感しようと手板作成のご指導をいただいた。
経験してみたところ漆塗りは本当に難しい。天然の樹液である漆は粘りが強く、それを均一に塗るのは至難の業である。ただ、先生方は漆以上に粘り強くわたしにつきあってくださり、そのおかげで約半年をかけて一枚の手板を仕上げることができた。突然押し掛けたうえ、不器用なわたしに対して親身になって教えてくださった先生方には感謝のことばもみつからないが、ここでの貴重な経験は女乗物の修復に活かされた。
それから二年後、わたしが担当した女乗物はなんとか無事に修復を終えることができた。この仕事は民俗文化財の保存修復家と漆芸家の協同作業でおこなえたものだと感謝しているし、このときのご縁は今でも続いている。このような協同作業もまた、手仕事の大きな魅力でもあろう。
紙は人類文化の発達に多大な貢献をした。また、紙なくして今日の人類文明は成り立たなかったと思う。紙は、人類の発明したもののなかでもっとも素晴らしいものといえる。
そして、紙はわたしたちの毎日の生活のすみずみまでに入り込み、まるで空気や水のような存在であり、なにげなく無造作に使っているが、紙一枚を手作業で作ろうとすると大変な労力を必要とする。
紙は、植物繊維を水のなかでバラバラにほぐして、薄く平に漉き上げて乾かしたものである。織物とは違い、短い繊維を絡ませ、その繊維間に水素結合が生じて紙になる。繊維の個々の結合は弱いが、まとまると強い力になるのである。
紙は薄くて平で、適当な強さをもっている。加工がしやすく、書いたり印刷しやすい。また、原料が再生可能な植物繊維であるので、大きな木はもちろん、小さな木でも竹や草でも十分利用できるのである。
約二〇〇〇年前に中国で紙が発明され、最初は麻や樹皮などが使われたが、その後、製紙技術の進歩によって竹の紙ができるようになった。さらに、九世紀ごろから紙の需要が多くなるにつれて、中国に豊富な竹を原料に紙が作られるようになった。
中国の製紙技術は、中国で竹の紙が作られる前、奈良時代の六一〇年に、朝鮮から高句麗の僧侶によって日本に伝わった。その後、日本は独特の和紙の文化を開花させたものの、竹紙の製紙技術は中国から伝わらなかったので、近年まで日本では竹の紙が作られなかった。
日本での竹パルプや製紙の研究と実用化が始まったのは二〇世紀に入ってからで、機械化された製紙技術が日本に伝わって以降のことである。じつは、それが世界で最初にできた竹の製紙工場であった。その歴史は次の通りであるが、残念ながら日本では長続きしなかった。
一九〇一年 東京農科大学で小泉昇平氏がクマザサのパルプを作った。
一九〇九年 三菱製紙が台湾林内庄に世界初の近代的な竹パルプ工場(台湾製紙所)を設立した。しかし、操業開始後まもなく原料の竹の集荷不足やパルプ生産にかかわる技術的な問題と原料高、そして製品の販売不振から、一九一六年に事業放棄する。
一九三〇年 家田政男氏が竹や笹の紙作りを試み、岐阜に竹パルプ工場を設立した。しかし、竹の集荷が思うように行かず、竹林を全伐したため、タケノコが出なくなり他の原料へ転換せざるをえなくなった。
一九四五年 敗戦により、樺太材に八〇パーセントも依存していた針葉樹が入らなくなり、紙パルプの原料が不足したことを相談した進駐軍司令部から「木よりも生長の早い竹をなぜ紙パルプに利用しないのか」と指摘された。
一九四六年 藤山愛一郎氏が山口県萩市に年産七〇〇〇トンの竹パルプ工場(日東製紙)を設立した。しかし、日産一五トンと生産規模が小さく大規模な木材パルプ工場と対抗できなくなった。資金難に加え、各地からの原料の竹が入手困難となり、一九六二年にやむなく竹パルプの生産を休止せざるをえなくなった。
一九五五年 北海道大学林産科と林業試験場で、笹パルプに関する基礎研究が完成した。 一九八七年 北海道幌加内で笹パルプで紙漉きを始め、小規模ではあるが現在も製造している。 一九九九年 鹿児島県の中越パルプ(株)川内工場は豊富な地元のモウソウチクを使い、竹パルプを使用した紙製品まで一貫生産を確立。
現在は創作的な手漉きの竹紙を作る方が全国におられるが、日本の竹から紙を作っている製紙会社はほとんどなく、竹パルプを外国から輸入して竹紙を作っている。竹の豊富なインド、中国、タイでは紙の需要の増加によって竹紙の生産が増えている。しかし、日本は技術力がありながら山の木や竹が生かされずに放置されている。
竹パルプの特徴である吸水性と吸油性を生かした多方面での用途が考えられると思う。環境という点でも、竹の紙が里山の環境と生活環境を守る可能性があると思う。過去の失敗を教訓に日本の竹資源を有効に活用する方法を国をあげて取り組むべきではないだろうか。
-セックス・ミュージアム/アメリカ-
-エロティシズム・ミュージアム/フランス-
こうした博物館に関心のあるわたしが最近訪れた、海外の博物館をふたつ紹介しよう。ニューヨークのセックス・ミュージアムとパリのエロティシズム・ミュージアムである。
前者は五番街、後者はムーラン・ルージュのそば、ともに見かけは普通の五階建てビルの全階を占める。いずれも、興味本位の扇情的な展示館ではなく本格的博物館だが、それぞれ展示趣旨が異なるうえ、米と仏の文化の違いを感じさせる点でも面白い。
ニューヨークの博物館は、性にかかわるあらゆるアイテムを展示しているが、なかでも、映像産業大国らしく、映像展示が面白い。性にかかわる映像の歴史を一九世紀末から説き起こし、それらが取り上げてきたさまざまな傾向と変化を解説するとともに、時代を画した作品群もビデオ画面で流している。その他、性教育や衛生思想の観点からの教科書なども歴史をおって展示され、見応えがある。
企画展も積極的に催しており、わたしが訪れた二〇〇七年春には、「Erotic Roadmap」が開催されていた。これは、あらゆる性の嗜好の関係図を大パネルで示したうえで、個々の説明を展示したもので、セクソロジー研究にも参考になりそうな意欲的なものであった。ここで関係図を示すのは憚られるが、全体を総括すれば「エロティック方程式:欲望+障壁=興奮」が成り立つ、という解説には、なるほどと納得した。
他方、パリのエロティシズム・ミュージアムは、古今の美術・工芸作品を女性美の観点で集めたもので、各種の造形、絵画、凹版や平版の版画、写真、映像、マンガなど諸メディアによる作品が、階段の壁も使って目一杯展示されている。日本の浮世絵などもあり、欧州のエキゾチシズムもこの分野発展に寄与したことを示す。また、写真も含め発明された諸メディアをいち早く使って作家たちが匿名や変名で作品を発表してきたのを見て、ニューメディアの普及を促したのがじつはこのジャンルであったことを、再確認させられた。ただし、各展示間での脈絡は感じられず、歴史的な背景説明も少ない点に不満が残る。純粋にアートとして鑑賞して欲しい、というメッセージなのであろう。
このあたり、やや即物的なニューヨークの博物館的な展示と、美を基本とする美術館的な展示との相違を反映しており、近年議論されている、ふたつの系統の違いを反映している点でも、面白い比較ができるのではなかろうか。
屋根瓦(標本番号H165890、高さ/35cm 幅/43cm 奥行/35cm)
当時、ジャワ島の田舎では、屋根の多くがヤシの葉や草で葺かれていたが、赤い素焼きの瓦葺きの屋根が増えつつあった。この屋根飾りは、そうした瓦葺きの屋根の棟瓦として使われていたもので、首を横向きにして胸をそらせたアヒルの土偶がリアルに表現されている。
一九八八年にわたしがバリ島で、この屋根飾りを収集したさいの記録によると、製作地と使用地は、ジャワ島北岸の古い港町テガルの南方一五キロほどのところにあるジャワ人の村(ケドゥンバンテン)で、製作時期は一九四〇年代(推定)となっている。
このような屋根飾りは、素焼きの屋根瓦が各地で手作りされていた時代に、左右一対のものとして作られていた。そうしたことから、このアヒルの土偶も一対のものとして作られたはずであり、屋根に飾られていたときには、二羽が屋根の上で向き合うようにして胸をそらせていたと見られる。
工場で大量生産される釉薬をかけて焼成された屋根瓦が主流となった現在、このような屋根飾りはもはや作られておらず、むかしながらの屋根飾りのある家を探すこともむずかしくなっている。
僕が足しげく通うイランの古都ゴムは、現在ではシーア派の総本山のひとつであり、マルジャエ・タグリード(法学権威)がこぞって事務所を構えている。法学権威とは、シーア派イスラーム法学の最高権威であり、老成し、卓越した法学者である。
イランは、国民の約九割がイスラームの一派シーア派の信徒である。シーア派にも、多数派であるスンナ派同様に、神学や法学といった学問がある。神学が信仰者の内面の規則である一方、法学は外面の規則であり、例えば、毎日の礼拝の前に、どうお清めすればいいかといった日常生活にかかわる側面が多い。そのため法学権威は信徒向けに信仰生活の手引書を著している。大抵の問題はそれを読めば解決するが、解決できないときには、信徒は法学権威の事務所に相談する。
事務所は特有の構えもなく、よくある町の建物であり、僕は探すのにずいぶん骨を折ったものだ。しかし信徒のあいだでは、どこが事務所かは周知の事実である。訪問者に振舞われる紅茶をご馳走になりながら、そこで一日を過ごしていると、悩みを抱えた信徒が頻繁に訪れ、清々しい顔で帰っていく。相談は電話、書面、ウェブサイトを通じてもおこなわれる。通常スタッフが先述の手引書に沿って答えるが、難題の場合には、法学権威自らが答える。このように法学権威は法学の卓越した専門家であるが、それに加えて「法力」の持ち主との考えもある。
交通事故に遭うが
法学の知識は、神の啓示と先達による果てしない努力の上に成り立っている。それを継承・発展させる彼らに、どうすればそれほどの知識をもてるのか、という純粋な尊崇の念を、信徒は抱いている。ときにはそれが極限まで高められ、彼らに法力があると考える信徒もいる。法力はつまり日本語でいう「御利益(ごりやく)」のようなもので、病気や怪我を治癒するなどさまざまな奇跡を起こすと信じられており、奇跡譚を集めた本まで出版されている。書店で本を手にしたときには、まさか僕自身が法学権威の法力を体験するとは夢にも思わなかった。
ある日ゴムへの帰り道、僕の乗った乗り合いタクシーは猛スピードで町を目指していた。突然、「バンッ」という破裂音とともに横滑りに回転し、道路脇の路肩を踏み切り台代わりに車ごと飛んだかと思うと、次の瞬間には見事に着地していた。あまりのことでことばを失っていたが、我に返って自分の安全を確認して、ほかの乗客を確認したが、誰も怪我すらしていない。車外に出るとさらに驚いた。車もなんとほぼ無傷だ。
一同暫く唖然としていたが、助手席に座っていた女性の号泣をきっかけに、何故助かったのかと話が始まった。思い当たる節を話し合ったが、納得する答えではなかった。そのとき、僕が何気なくその日法学権威と面会したと言った瞬間、その場にいた全員が、「ああ、そうか。彼の法力のおかげだ」と納得した。これが法学権威の法力かと実感するとともに、僕の研究がみんなの役に立って本当によかったと思えた。
米国のバラク・オバマ大統領の大統領就任式が終わった。歴史的な就任式であっただけに、多くの人びとの関心を呼んだ。この就任式にあたって、日本でも、じつは、「歴史的なこと」が起きていたことにお気づきだろうか? 一月二一日付朝日新聞朝刊(最終版)は、就任式の演説要旨を日本語とともに、英文でも掲載したのである。さらに一面の社名下のおもな記事の紹介覧に、「Inaugural Address英文要旨」と表記した。これもまた、かつてない歴史的なことである。もちろん、日刊紙が英文を解説するときに、必然的に英文を掲載することはこれまでにもあったが、大統領就任演説要旨をそのまま英文で記載したり、「大統領就任演説要旨」と表記すればよい箇所において、「Inaugural Address英文要旨」という英字日本字混合の表記を使ったりしたという日本史的な重さは、初の黒人大統領の誕生という米国史的な重さに勝るとも劣らない。
このことは、日本の日刊紙が「日本語で記載する」という慣習を破ったことだともいえるだろう。また、ローマ字はすでに、GDPやNPOなどの略号として、日本語中に取り込まれていることを考えて、過激な言い方をすれば、「英文を日本語のなかに取り込んだ」、という逆の言い方が可能かもしれない。近年、インターネット時代に「日本語」をめぐる議論は活発化してきている。『日本語が亡びるとき 英語の世紀の中で』(水村美苗著)などがベストセラーになっていることも、背景にはあるのだろう。
変換の問題
さて、表題の南アフリカとサウスカロライナ。この不釣合いさに何か感じるだろうか?
このふたつの地名、「南アフリカ」は South Africaで、また、「サウスカロライナ」はSouth Carolinaである。
ここまで書けば、おわかりの通り、管見の関心は、なぜ南アフリカは「南」アフリカで、サウスカロライナは「サウス」カロライナなのか、という点である。
地名の「一部を翻訳」するというルールを仮に認めて、それを日本の地名に置き換えて考えてみたらどうなるだろうか。「東」の英訳は「イースト」だから、「東京」の英語が「East Kyo」ということになるだろうか。
単語と単語の変換に生じるハイブリッド化や不規則変化は、「日本語」と「英語」という軸だけではなく、例えば「墨字」(点字に対しての一般の文字のこと)と「点字」という軸でも生じている。もっと身近で言えば、「文字」と「コンピュータ文字コード」の変換でも起こっている。
さらに、視野を広げると、数式、化学式、音符などさまざまな表記方法のなかに、この種の変換の問題が存在しており、しかも、インターネット時代に顕在化してきていることも指摘しておきたい。
バラク・オバマ大統領誕生の新聞報道を見ながら、「チェンジ」というメッセージは、いつの日か日本の新聞には、文字通り「change」として掲載されるのではないかという思いを強くした。
パクキョンオク(朴敬玉)さん。一九八八年、在日コリアン四世として日本でもっとも在日コリアンの多い大阪市生野区に生まれ、ずっとそこで育った。生粋の生野っ子、と冗談を飛ばし自己紹介する小柄で笑顔の可愛い彼女だが、ちょっと不釣り合いなたくましさも漂う。
現在関西大学二回生に在学中の彼女が小学校から高校まで通ったのは朝鮮学校だった。両親と姉も小学校から高校まで朝鮮学校だったが、四人とも通った学校はすべて同じ、つまり先輩後輩の関係なのだ。キョンオクさんの曾祖父母は韓国の済州島出身だが、心を寄せる祖国はずっと北朝鮮と決めてきた。彼女には済州島にも北朝鮮にも親戚がいる。一世が国に残した親戚と帰国事業で北朝鮮に渡った親戚である。済州島の親戚には一度もあったことがないが、北朝鮮の親戚には、高校の修学旅行に行った際会ったことがある。初めて会った親戚が彼女の顔を見て泣き出し、彼女も涙が出たという。それを聞いてわたしも思わずもらい泣きしそうになった。そもそも、故郷と生活する国が異なって当たり前の在日コリアンであるが、さらに祖国が異なることを心に秘めてきた緊張感で、少しの刺激にも感情がもろくなってしまうのである。
民族学校とウリマル
低年齢の子どもの場合、学校の選択は、通常、親世代の意思が決定権をもつが、彼女が朝鮮学校に通ったのも、親の意思であった。朝鮮学校は設立をめぐり日本社会といろんな面で衝突し、その後も、民族差別の大海のなかで孤島のように、朝鮮民族のシンボル的存在を堅持してきた。そんな民族学校に彼女や彼女の親が求めていたのは何だったのだろう。キョンオクさんにとって民族学校は、「胸を張って自分が自分であることが可能な場」であったという。朝鮮学校は彼女たちにとって、多文化の概念がなかった日本社会において癒しの場でもあり、解放された民族空間でもあった。その面で朝鮮学校は異国民としてくらす彼女たちの疎外感に家庭、社会、国が凝縮されたマルチ空間を提供してくれたかもしれない。
彼女は民族学校で、自分と自分の存在の証しである名前を隠さず生活できたことに誇りをもっている。なかでも彼女にとって財産となったのは、日本語と朝鮮語のバイリンガル能力であった。朝鮮学校ではウリマル(朝鮮語)教育を民族教育の核心として取り入れ、日本語以外の授業はすべてが朝鮮語でおこなわれた。先生も全員朝鮮語が話せるバイリンガルである。そのような教育をうけたためか、在日コリアンの多くが日本語のみを使っている今、彼女は、四世でありながら、朝鮮語ネイティブであるわたしの朝鮮語の不注意さを指摘できるほど、立派な朝鮮語能力をもっていた。
それでも彼女自身、いちばん使い易いのは日本語だという。同じく朝鮮学校出身の家族や友達との会話も日本語になる場合が多いのだ。朝鮮語の能力に問題はないが今は大学で朝鮮語の授業をとっている。、レベルは合わないができるだけ朝鮮語と接していたいからである。かつては朝鮮学校を卒業しても朝鮮語を続ける場はあまりなかったが、最近は韓流ドラマがいい刺激になっている。学校で習った硬い朝鮮語に比べ、日常生活の生身の朝鮮語が聞ける機会が増えたことを、彼女は嬉しく思っている。
大学生活とこれから
大学は彼女にとって初めて接する日本の学校空間である。経済学を専攻し、テニスのサークルに属している。バイトやサークルで忙しい毎日を過ごすのも他の大学生と変わらない。パクキョンオクという名前からか最初は留学生と思われ、日本語の不自由さを心配されたりしたこともある。在日コリアンの多くが通名を使い、本名を使うことにあまりなれていない日本人にとって、本名は新しく来日したコリアンを連想させるらしい。やがて、会話のなかで友達はすぐに彼女が彼らとあまり変わりのない日本の若者であることに気付いてくれるが、在日コリアンのことがまだあまり知られていないのを残念に思っている。
みんなと同様に、日本に生まれ日本に生活しているにもかかわらず、いちいち説明しなければいけないのは煩わしい。彼女にとって在日であることは「非日本」的なことではない。朝鮮的要素は、みんなと同じ日常の存在への「プラスワン」なのである。
それでもわたしは彼女に限りなく「非日本人」らしさを求めていたのだが、彼女はありふれた日本の若者であった。ことばやしぐさから、ファッションなど最新の流行感覚にいたるまで。
卒業後のことについて聞いてみた。普通の会社に就職するという。日本社会で資産的価値がかつてより向上している朝鮮語を特に生かせる職業を選んだりする気はあまりないらしい。しかし、国籍にはこだわりたいという。数年前に朝鮮籍から韓国籍に変えたが、日本国籍をとることには違和感があるようである。
「日本は好き?」、日本に生活する外国人に会うとよく聞く質問である。最後に彼女にも投げかけてみたかったが、踏みとどまった。よく考えてみれば、わたしも在日外国人である。その質問をわたしにむけたら、どう答えるのだろうか。
イスラームの暦で第三月一二日は、ジャワ島でムルダンとよばれる預言者ムハンマドの生誕祭である。イスラームの暦は、月の満ち欠けに基づく太陰暦で、一年は三五四日、約三年に一度のうるう年は三五五日となる。わたしたちが参照している太陽暦よりも一年が短いため、イスラームの祝祭日は毎年少しずつ早まっていく。西暦一九八九年、わたしが初めてチルボンで体験したムルダンは、一〇月一二日だった。二〇年後の今年は三月九日にあたる。
インドネシア・ジャワ島西部北海岸の町チルボンに残る三つの王宮のうちの一つカノマン王宮では、この日の五日前から毎日、スカテンとよばれるガムランを演奏する。ガムランは、大小さまざまなゴングのセットや鉄琴類等を中心とするアンサンブルである。ジャワ島やバリ島にはさまざまな種類のガムランが存在するが、スカテンはそのなかでも比較的古い歴史をもつ神聖なガムランである。
スカテンの由来
ジャワ島の本格的なイスラーム化は、一五世紀末、ジャワ島北岸の町から始まった。これらの地域を拠点とするワリ・ソンゴとよばれる九聖人が、神に授かった力により人びとを救い、神秘主義的なイスラームを広めたとされる。彼らの力は、今も墓所や聖遺物に残されていると信じられている。九聖人の一人スナン・グヌンジャティは、チルボン王国の創始者であり、彼と代々のチルボンの王族を祀る廟には、今も多くの人びとが訪れて礼拝や祈願をおこなう。
一説によると、スカテンは、中部ジャワ北岸のドゥマック王国において、やはり九聖人の一人であるスナン・カリジャガが作り、イスラーム布教のために利用した。ドゥマック王国に嫁いだスナン・グヌンジャティの娘により、チルボンにもたらされたと言われている。その後、チルボン王家は、カスプハンとカノマンの両家にわかれたが、両者がスカテンをわけ合った。現在、カスプハン王宮のスカテンは、断食明けの大祭に際して演奏されるのに対し、カノマン王宮では、ムルダンに演奏されている。
神聖にして犯すべからず
一九八九年一〇月八日、朝、カノマン王宮のスカテンは一年ぶりに王宮の蔵から運び出され、水で清められた。スカテンを清めた水は、水田にたらすと豊作をもたらしたり、飲むとさまざまな病が治ると信じられている。そのため、スカテンの清めが終わると、人びとは争ってこの水を求める。スカテンは、また、権威と力の源泉として、王にとっても大切なものである。最初の演奏の開始には必ず王自らが立ち会うことになっている。
わたしは、その演奏をビデオに収めようと思い、事前に許可を願い出たが、許されなかった。スカテンは、聖なるガムランとして、ムルダン以外の時期にその音を響かせてはならない。録音や録画をすれば、再生するたびにその音が響くことになるというのがその理由だった。わたしは、しかたなく一日七回、それぞれ一時間一〇分ほどの演奏に通いつめ、演奏を聴きながら数字譜でその旋律を書き留めた。
新世代のスカテン
二〇〇八年三月、わたしは再びカノマン王宮のスカテンの演奏を見た。王も代が替わり、演奏者の顔ぶれもだいぶ変わっていた。だめでもともとと思いながら、ビデオで演奏を撮影してもよいか尋ねてみたところ、今回はあっさりと撮影が許された。実際に演奏が始まってみるとあちらでもこちらでも、小型のビデオカメラをまわしたり、デジカメや携帯電話で動画撮影をしている若者の姿が目についた。もはや録音や録画を規制することは難しいのだろう。以前、「聖なるものの写真を撮ってみたが何も写っていなかった」とか、「聖なる音楽を録音してみたが何の音も入っていなかった」という話をよく聞いた。日進月歩の現代のテクノロジーは、聖人の力をもしのぎつつあるのだろうか。
一方、若いスカテン演奏者のリーダーと話をしていると、彼は代々受け継がれてきた文化的な遺産だから、スカテンを守らなければならないと強調していた。「真正な」イスラームへの回帰を目指す動きは、インドネシアでも知識人を中心に広まりつつある。その立場からは、聖人崇拝は邪道である。神秘主義的な信仰のゆえではなく、歴史的文化的に重要なものだからスカテンを伝えていくのだという理屈の立て方は、こうした動向とも関係しているのだろう。スカテンを清めた水を求めて争う人びとは減っているようには見えない。しかし、見えないところで少しずつ、聖人の力への信仰が変化し始めているのかもしれない。
乱獲の歴史
見た目がかわいらしく、またその動作も愛らしいオコジョは、日本でもしばしば昔話に登場し、また漫画やアニメの主人公にもされたことがある。仲間のイタチなどと比べると全体に小型で、吻(鼻から口にかけての部分)が短く、かわいい顔をしているが、結構気性が荒く、勇猛果敢で、自分より大きいウサギやトリもおそって食べてしまう。
しかしこのオコジョには人間による乱獲の歴史が影を落としている。現在世界各地で軽度懸念の希少種とされており、日本では準絶滅危惧種とされている。夏は背中が茶色でお腹が白い夏毛で覆われているが、冬になると全身真っ白な美しい冬毛に変わる。しかも、尾の先端だけが黒く、それが毛皮全体の美しさを引き立てる。このオコジョの冬毛が、ヨーロッパや中国の王侯貴族の美意識をくすぐってしまったのである。
国王や貴族に愛される
例えば、フランス王ルイ一四世(太陽王)の肖像画のひとつ(リゴー作、ルーブル美術館蔵)は、羽織ったローブの裏地をこれ見よがしに翻した姿で描かれている。そこには白地に黒い点が規則正しく並んでおり、裏地がすべてオコジョの毛皮であることがわかる。黒い点はもちろん冬毛のオコジョの尾の先端部分である。
オコジョ毛皮のローブをまとうのはルイ一四世だけではない。フランス王ではルイ一三世から一六世まで、オコジョのローブを身につけた姿で描かれた肖像画があり、アングルやダヴィッドが描く皇帝ナポレオンの肖像もオコジョのローブをまとっている。フランス王以外でも、イギリス、プロイセン、バイエルン、スペインなどの国王や貴族の肖像画にもオコジョのローブが描かれている。冬毛のオコジョの白さは純粋さや純潔をあらわしているといい(ダ・ヴィンチの「白貂を抱く貴婦人」など)、多くの王侯たちに愛されたのもそのためだろうが、そのローブは事実上王権あるいは権力の象徴である。
その王侯たちの嗜好を満足させるために、オコジョの受難はヨーロッパからシベリアへと拡大した。一六世紀にロシアがシベリア征服を始めると、オコジョの供給地もユーラシア大陸の東へと広がったのである。ロシアのシベリア征服の原動力として「柔らかい金」とよばれたクロテンの毛皮が注目されているが、じつはオコジョの需要もかなり高かったのではないかと思われる。クロテンはシベリアでも森林が密な地域に多いが、オコジョは森林ツンドラ地帯のような寒冷な疎林地域にも多い。そのために、東シベリア北部では主要な毛皮がクロテンではなくオコジョだった。この地域のオコジョは体格が大きく、毛並みも美しく、尾の黒い部分が際だつ。零下五〇度以下にも達する酷寒の北シベリアで、エヴェンキやエヴェンといったこの地域の先住民の祖先たちはせっせとこのオコジョを捕っていたのである。ルイ一四世がまとっていたローブにも、シベリアで捕らえられたオコジョが入っていた可能性がなくもない。
オコジョ(学名:Mustela erminea)
ユーラシア大陸北部から北アメリカ大陸北部の森林地帯、疎林地帯に生息する食肉目イタチ科イタチ属の動物。日本にもホンドオコジョ(M.e.nippon)とエゾオコジョ(M.e.orientalis)の2種類の亜種が生息する。日本のオコジョは胴長が10数センチメートルから20数センチメートルと小型だが、シベリアのオコジョは30センチメートルをこえるなどかなり大型である。夏は背中が茶色で腹が白い毛で覆われているが、冬になると全身真っ白な長い毛で覆われ、尾の先端にだけ黒い毛が残る。餌は、ネズミ、小鳥、昆虫などが中心だが、自分より大きいノウサギやライチョウなどをおそって食べることがある。
「わたしの来歴を知りたいと言うのか!お前は遠く外国から来た者だな。知りたいと言うのなら教えよう!しかと聞け!」
あぐらをかき、抜き身の剣をもった腕を震わせて、数百年前の戦死者の霊が憑依した女性霊媒師が目を剥き、わたしに向かって咆哮する。昨秋、調査で訪れたインド・ラージャスターン州の古都ウダイプルの旧市街にある小さな居宅を改修した神霊の社でのことである。
神や死霊を霊媒に憑依させ、さまざまな願いごとをかなえるという信仰は、この地方には古くからある。かつて支配層であったラージプートというカーストの武人の戦死者の霊も信仰の対象のひとつとなってきた。致命傷を負ってなお戦い、亡くなった武人には超人的な力が宿ると信じられるからである。憑依霊信仰は一時人気を失っていたが、近年多くの信者を集める社が街のあちこちにあらたにできてきた。武人の霊の社でもその傾向が強いらしい。その背景を探り、今この時代に憑依霊信仰が都市部の人びとのあいだで復活している理由を考えることが、最近のわたしの調査テーマのひとつになっている。
六〇〇年の孤独
冒頭のことばは、治病や願いごとの成就に効くことで急速に人気の出ているラージプートの武人の霊が発したものだ。
とある学校に、誰が祭られているのかわからない、いわくありげな祭壇があり、代々の用務員が朝夕灯明をお供えしていた。すると二年前突然、用務員をしている部族民の中年女性に社の霊が憑依し、自らを六〇〇年前に戦死したラージプートであると明かし、祭祀を求めた。女性宅に霊を勧請(かんじょう)して祭祀を始めると憑依が定期的に起こるようになり、人びとの願いに応えるようになったという。今は憑依のある日の夕方には敷地の外にまであふれるほど多数の参拝者が訪れるようになっている。
夕方信者が集まると、武人霊やその他の神々を讃える歌を皆が唄い、祭壇に線香や灯明が供えられる。そのあいだ霊媒となる女性は武人の絵を凝視する。と、憑依が起こり女性は激しく体を震わせ、祭壇に供えてあった剣を取って振り回す。半ば失神状態の彼女を祭壇の前に座らせると振る舞いががらりと変わり、身分の高い男性が使うことばを居丈高に話しだす。この社では憑依中の写真撮影が厳禁されているが、その威厳は真の領主と見まがうばかり。顔色は生気にあふれ、光り輝いている。霊は彼女を介して信者と深夜まで対話する。普段、ともすれば差別の眼差しを向けられる階層の女性を、人びとはあたかもかつての領主のようにあつかい、最大限の敬意を込めて額ずき、自分の悩みや願いを包み隠さず話し、それに対する答えをありがたく聞くのである。
なぜこの霊は六〇〇年間の沈黙を破り、部族民の女性を介して再びこの世にあらわれる気になったのだろう。そんな素朴な疑問がわき、霊との対話が始まると真っ先にストレートに質問をぶつけてみた。それに対して冒頭のことばが返ってきたというわけである。
人びとは話の切れ目ごとに「カンマーガニー」(閣下万歳、という意味の古語)とつぶやき、かしこまって霊の物語を聞く。霊は自らが戦死した合戦の模様をつぶさに語り、敵の剣で切られて飛んだ頭が落ちた地点が元の祭壇になったこと、その近くにトイレが造られ聖なる場所が汚されて不満をもったこと、霊媒は元の祭壇でも潔斎をしてから仕えるなど誠意が見られたので、彼女に取り憑きふさわしい祭祀を求めたことなどを述べた。この話から霊の側には人びとの信心がうすれることに危機感を抱いて出現したという動機がうかがえる。
復活する武人の霊
このラージプートの領地はウダイプルからかなり離れたところに実在し、農地のなかに埋もれるように記念碑が残っている。しかし、霊媒も周囲の人びともそのことは憑依が起こるまで知らなかった。六〇〇年もむかしの、遠く離れたところの領主の事跡が明かされたことは、願いをかなえる効力と相まって霊の憑依の真実性の証になっている。参拝者たちも霊媒を領主であるかのようにあつかうことで、その真実味をいっそう増すように振る舞っている。
霊と霊媒、それに参拝者が気持ちを働かせ合って憑依のリアリティがつくられる。このパターンは、調査している他の武人の霊の社にも共通する。社に持ち込まれる悩みや願いごとは、さまざまな病気から始まって不妊、夫婦や親子の不和、試験合格、事業の成功など人びとの日常に根ざしている。霊の前でそれらが語られることで個人の苦悩や欲望はその場にいる者全てに共有される。熱心な参拝者は憑依のたびに社に集まり、互いに顔見知りになって、憑依の前後に世間話をするようになり、日常的にもつきあうようになってゆく。社は霊と霊媒と人とがあらたな絆を築く場なのである。社は、経済発展が急速に進むインドの都市で失われつつある近隣関係を補う存在なのだろう。
不思議なのは、ラージャスターンでは信仰に基づく絆をつくるきっかけとなる神や霊にはことかかないのに、あえて武人の霊が呼び起こされていることである。王や領主が支配者だった時代は遠い記憶の彼方に消え去りつつある。そのなかで武人の霊が復活し、わざわざ人びとが集まってそのリアリティを確かめ合うことをどう考えればいいのだろう。これは「伝統の逆襲」なのだろうか。数百年をへだてた霊との対話のなかで何が伝えられているのだろう。インドの都市の喧噪のただなかにある社を訪れては自問する日々を続けている。