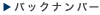月刊みんぱく 2008年10月号
第32巻第10号通巻第373号
2008年10月1日発行
現在、その地位は非常な危機に瀕しています。これはお手元に情報雑誌のひとつもあればすぐ実感して頂けます。エンタメ紹介コーナーで、活字本の定位置は大抵最後のページです。これが活字に対する世間の評価を如実にあらわしています。
ぶっちゃけまして、もう活字のライバルは活字じゃないんです。映画でありテレビであり漫画でありレジャーでありコスメであり(以下略)、およそ「娯楽」となり得る全てのものが活字のライバルです。現在、お財布のなかに「書籍費」を取りわけて下さるお客様は絶滅危惧種に認定されてもいい。ヴィトンのお財布八万円なら買ってくれる人が単行本一冊一六〇〇円を「高い」と仰る。これが活字の現状です。これ、どんだけ絶望的な戦況かおわかり頂けますでしょうか。―まともにやってて勝てるわけねーだろこんなもん!
活字はもうこれまでの伝統を守ってるだけじゃ勝てないんです。伝統として残るべきところは残るべきでしょうが、しかし奇襲を選ぶ活字があってもそれは容認されていいのではないかと(容認されるとわたしのような日本語の汚い物書きも生きやすくなって助かります)。
例えばケータイ小説。これを頭ごなしにバカにする人は、どんなにその方が活字を愛しているとしても「活字の潜在敵」と言って過言ではない。もしかしたらケータイ小説を入り口に「活字」の世界にもお出で下さる方がいるかもしれないのに、その可能性を根こそぎ刈ってしまうからです。だって自分の好きなものバカにした奴の「オススメ」に手を出そうって人がいますか?いるわきゃねえ。「活字ってお高く止まって感じ悪ーい」って思いますわな、フツーに。
活字は既に上から目線でモノ言えるほど立場の強いエンタメ媒体じゃありません。しかし活字業界の体質は中々変わろうとしません。
例えば一般文芸の世界では「短編集は売れない」と判で押したように言われます。しかし「活字層」を広げていくなら、これからはむしろ短編集でしょう。活字になじみがない方でも気軽に手に取りやすいのは短編集、あるいは連作短編です。短編集が売れない、とは従来の傾向しか見ていない発言です。出版界の体力があるうちに重厚な長編も押さえつつ短編集にも力を入れ、間口を広く取るのが長期的戦略と言えましょう。
お客様の開拓を放棄した業界は衰退します。限定されたパイを奪い合うより、パイそのものを広げる戦略のほうが建設的だと思うんですが―取り敢えず、「こうあるべき」な校則だらけの学校はつまんないよね、ってなところをひとつ呟いてみんとします。
ありかわ ひろ/高知県生まれ。作家。『塩の街』で第10回電撃小説大賞<大賞>を受賞し作家デビュー。累計110万部突破の『図書館戦争』シリーズはコミカライズの他、プロダクションI.G制作のアニメDVDが好評発売中。また、阪急今津線を舞台にした短編連作集『阪急電車』(幻冬舍)もwebコミック「MAGNA」でコミカライズ連載中。
インド映画の本格的な海外への進出は、独立後の一九五〇年代からのことである。いわゆるネルー型社会主義の理想に共鳴した社会派娯楽映画のチャンピオン、ラージ・カプールが監督・主演した「放浪者(Awara,1951)」などが当時のソ連に輸出され、「おいらは放浪者(Awara Hoon)」のようなヒンディー語の挿入歌も大ヒットした。現在でも、ロシアだけでなくウズべキスタン、クルグズスタンなどでもロシア映画と人気を二分している。
一九八〇年代後半には暗殺された母インディラーのあとを襲ったラジーヴ・ガンディー首相がインド文化を積極的に海外へ広めようとしたが、映画もその一環として世界に輸出された。このころ中国ではインド映画ブームが起こり、日本でも一九八八年に大インド映画祭が催されて多くのコアなファンを獲得している。
インド映画の世界への広がりは、ことばの問題があるので、まずはインド人が多く暮らしている地域に偏っている。海外在住のインド系の人びとは数千万にたっし、近隣のネパール、スリランカからイギリス、アメリカ、カナダ、湾岸諸国、シンガポール、マレーシアなどへと広がって、映画も、合法非合法の手段を問わず、広く受け入れられている。
しかし、インド映画の真の不思議は、ことばのわからない地域でもかなり受け入れられているところにある。たとえば、かつてインド人移民が多くいた東アフリカだけでなく、ほとんどインド人のいない西アフリカやインドネシアなどでも受け入れられている。さらに衛星放送の普及がそれに拍車をかけている。インド映画の歌って踊っての徹底した娯楽性と、定型化したストーリーが、ことばの壁を超える原動力になっている。皮肉なことにそれはインド映画をさげすむときの常套句である。
南アジア系移民
英国の南アジア系移民をテーマにした映画は、一九九〇年代にようやくあらわれる。それらは彼らの出身国の伝統的価値観と英国的価値観の衝突、世代間の衝突、多文化主義国家のなかでの自己表象などをテーマにしたものが多い。
初期の傑作「East is East」(1999)は、一九七〇年代初頭の北イングランドに暮らすパキスタン系一家を描いたもので、伝統的な結婚を望む父親とそれに反発する子どもたちとの葛藤をコミカルに描いた作品である。伝統的価値を主張する親世代と、それを拒絶する二世世代との対立は、南アジア系英国人にとってはすでに「笑い」として受け入れられるほど客体化されているが、もちろん衝突がなくなった訳ではない。
日本でも公開された「ベッカムに恋して(Bend It Like Beckham,2002)」はロンドン西部に住むシク教徒の女の子が親の反対を乗り越えてサッカーを続け、白人の恋人までつくってしまうストーリーだ。東アフリカ出身のインド系英国人であるG・チャーダ監督は屈託なく多文化主義を強調するが、逆にその皮相さをも露呈しているように思われる。二〇〇七年の「Brick Lane」は、バングラデシュの村から一七歳で英国に移り、二〇年間東ロンドンのブリック通りで暮らす女性が徐々に自分自身を発見していく物語である。愛がないと思っていた結婚に、より深い絆を発見し、長く想い続けた故郷の村に決別し、「ここ(英国)が私の故郷(ホーム)だ」と言えるまでの軌跡は、移民の生活をリアルに伝えることに成功している。しかし、この映画の元となったM・アリの原作が、無教養で貧しい移民という誤ったイメージを流布したとしてバングラデシュ・コミュニティーから強い反発を受けたことも事実である。
ボリウッド映画市場
一方、インド国外におけるボリウッド映画(インド映画産業の中心地ムンバイの旧称ボンベイとハリウッドを組み合わせた造語)のDVD等の売り上げがインド国内での映画興行収入を上回るようになって久しいが、英国人もこの傾向に大いに貢献している。最近のボリウッド大作はほぼ同時に英国でも公開され、興行成績で上位一〇位内につけるほどである。むしろ海外で優雅に暮らすインド人が頻繁に登場する最近のボリウッド映画(例えば「家族の四季-愛すれど遠く離れて(Kabhi Khushi Kabhie Gham,2001)」)の方が、南アジア系英国人の自意識を満足させるのかもしれない。、
そのむかし、インド洋の大海原を帆船が行きかっていた時代、奴隷にかわる労働力として、インドから数多くの契約労働者が世界各地のプランテーションへ船出していった。そのひとつが、「インド洋の貴婦人」と謳われたモーリシャスの砂糖プランテーションであった。モーリシャスの主要生産物は、今も砂糖である。
インド・モーリシャンと総称されるインド系住民は、二〇〇七年現在、人口の六八・八パーセント(約八三万五〇〇〇人)を占める。そのうち約半数は、ボージュプリーを母語とするビハール出身の労働者の子孫であり、残りは、アーンドラ・プラデーシュ、タミルナードゥ、グジャラート、マハーラーシュトラからきた移民の子孫といわれている。
ロケ地として売り込む
MBC(Mauritius Broadcasting Corporation)チャンネル2で放映されるインド映画や音楽番組、ヒンディー語(英語字幕つき)連続テレビドラマは、こうしたインド系住民に限らず国民に幅広い人気がある。モーリシャスはインド映画の海外市場として、アメリカ・カナダ、イギリスにつぎ、ドバイと並ぶ輸入国であり、インド映画の販路をセーシェルや南アフリカへ広げる窓口ともなっている。モーリシャスを舞台にした映画「Dil Jo Bhi Kahey」(2005)は、アミターブ・バッチャーン演ずるヒンドゥー教徒の労働者の息子とローマン・カトリックのフランス系大資本家の娘の恋愛と家族の葛藤を描いた物語である。
一九九一年のインドの経済開放以来、モーリシャス政府はインドとの経済関係を強化し、インド・フェアやファッション・ショー、映画祭などをとおして経済・文化交流をおこなってきた。モーリシャス映画協会はモーリシャスを映画のロケ地として使ってもらうために、観光局やモーリシャス航空とタイアップし、撮影のサポートやエキストラの手配、クルーとその家族の滞在費のディスカウントといった特典を用意して積極的に売り込んでいる。青い海と白いビーチというエキゾチックな美貌の「インド洋の貴婦人」が微笑んで、ボリウッドの旅心を誘っているというわけである。
一八九六年、当時イギリスの植民地であったインドと清朝末期の中国に、映画がはじめて持ち込まれ上映された。その後、両国の映画はそれぞれ異なる発展の軌跡をたどった。
中国では、中華人民共和国の成立後、政治的な制限を受け、一部の社会主義国家の作品をのぞき外国映画の上映が禁止されるなど、一九八〇年代の「改革開放」時代までその発展は停滞することになった。
一方、インドは一九五〇年代から映画の「黄金期」に入り、現在では、年間の制作本数や観客総数が世界でもっとも多い映画大国となっている。年間の制作本数はアメリカ・ハリウッドを上回り、ムンバイにある映画制作の中心地「ボリウッド」の名は、ハリウッドと同様、世界じゅうで知られるようになった。中国で「ボリウッド」は漢字の「宝莱塢」で表記されており、アメリカの「好莱塢」(ハリウッド)に比べると、よりロマンチックな雰囲気が漂っている。
個性豊かでわかりやすいインド映画は、巨大な隣国である中国の人びとに強いイメージを与えることになった。とくに、「改革開放」政策を実施し、外国の文化にも少しずつ門戸開放しはじめた一九八〇年代ごろの中国に、強いインパクトを与えた。現在では中年以上になっている世代の中国人なら誰しも、その影響を受け、印象が深く残っている。
わたしは、一九八〇年代中ごろまでの学生時代を中国で過ごした。大学や大学院在籍中、学内の映画館でインド映画を鑑賞したとき、周囲の観客が、そのわかりやすいストーリーとともに、豪華な民族衣装を纏った出演者たちによるミュージカルシーンに魅了されていたことをよく覚えている。
ディスコ・ブーム
当時、「大蓬車(Caravan,1971)」、「流浪者(放浪者、Awara,1951)」、「奴里(Noorie,1979)」、「両畝地(2エーカーの土地、Do Bigha Zamin,1953)」などのインド映画がたびたび上映され、人気を集めた。これらの作品は中国人にとって、インド映画の代表作になった。劇中の踊りや歌も中国の大地で急速に流行するようになった。例えば、「アバラグ、ア…アバラグ、ア…」という「流浪者」のなかの歌は、学校や街のあちらこちらで流れていた。当時、憧れの電化製品だった日本製テープレコーダをいち早く手に入れることができた数少ない大学生や、街の「万元戸(成金)」の個人経営者は、インド映画の主題曲をわざわざ大音量で流し、周囲の人びとから羨望のまなざしを集め、流行の先端を走っているという自己満足に浸ることがよくあった。
一九八五年、インド映画「迪斯科舞星(Disco Dancer,1982)」が中国で上映されるやいなや、中国にディスコ・ブームが到来した。映画の主題曲「Jimmy Adja」をはじめ、「I Am a Disco Dancer」、「Yaad Aa Raha Hai」などのディスコ曲は、もっとも人気が高く、その激しいリズムが、「改革開放」の時代に入った当時の中国の人びとの高揚した心情と共鳴したと言える。そのときから、ディスコは、あらたな流行文化のひとつの象徴として都会から伝統的な暮らしが残る農村まで急速に広がっていった。ディスコのダンスホール(「迪斯科舞庁」)は、ラッパ・ズボンとサングラスといった服装の若者でいつも溢れる場所になった。
その後の約二〇年間、アメリカや日本など「先進国」の映画が、中国で多く上映され、爆発的な人気をえるようになるとともに、中国映画の質と量も急速に向上してきた。
それに対して、インド映画はストーリーが古臭く、表現手法が単純で変化に乏しいと受け取られるようになり、人気が急速に低下していった。とはいえ、審美観の多様化が進んでいる中国では、インド映画ファンもいまだ少なくない。そのため、「雅恒影視」という中国の映像会社は二〇〇三年だけで約二〇〇本のインド映画を輸入し、DVD製品にして市場に出した。中国のテレビ局も「宝莱塢生死恋(Devdas,2002)」と「阿育王(アショカ大王、Asoka,2001)」を放映し、好評をえた。
インド映画は今もその豊かでわかりやすい個性で中国人の心に刻まれているのだ。
少々古い話である。一九八六年、中国・新疆ウイグル自治区西端の都市カシュガルを旅行中、地元の食堂へ昼食に入った。料理を注文して待つあいだ、ラジオかカセットか、食堂に流れていた音楽のフレーズがふと耳についた。英語の歌なのに妙にゆるく、そのわりにノリはよく、発音がはっきり聞き取れる。たった一度聞いただけなのに記憶に残るその歌を、一〇年後、旧ソ連・クルグズスタン(キルギス)の天山山中にある村で再び偶然耳にした。長期滞在しての調査中、ホームステイ先の一家と夜遅くにテレビを観ていたときである。ようやく何の歌かわかった。「I Am a Disco Dancer」、インド映画に流れる音楽だった。
中央アジアの山岳国・クルグズスタンで一九九四年からフィールドワークを続けているが、じつはわたしは現地の映画事情にあまり詳しくない。だがテレビ番組は、フィールドでみんなと一緒に観ているのでよく知っている。特に長期滞在した一九九五~九七年、村での娯楽といえばテレビの連続ドラマか映画番組だった。アメリカ、ロシア、香港、さまざまな国の映画を観たが、ハデな衣装に歌と踊り、シンプルといえばシンプルな勧善懲悪の筋書きで、インド映画は他の追随を許さない。夜中近く、電気を消した暗い部屋のなかで光を放つインド映画は、緑と茶が基本色の天山山中に極彩色の南国を映し出していた。
一九九五~九七年といえば、クルグズスタンは、ソ連崩壊・独立に伴う政治経済体制の転換のまっただなかにあった。ソ連時代の常識はすべてひっくり返り、これから自分たちは一体どうなるのか、方向感覚の喪失にみな深刻な不安を募らせていた。一九九八年、「クルグズスタンの言論」(一五九号)という新聞に、インド映画を「子ども時代の映画」であり「明るい色で描いたきれいな想いである」と評した記事が掲載されている。今から振り返るとすべてが混沌と混乱のなかにあると思えた時代、だからこそインド映画はあれほどクルグズ人に愛されていたのかもしれない。
一九九〇年代になってシネコン型映画館が増えると、それまでインド映画が上映されていたような映画館の数は減って、インド映画の上映の機会は極端に少なくなった。首都ジャカルタのパサール・スネン(月曜市)という下町にあったリボリは、インド映画ファンには有名な映画館であったが、一九九〇年代に入って観客が減少するようになり廃業に追い込まれている。シャールク・カーン主演の「Kuch Kuch Hota Hai」(1998)のように単発的に大ヒットして多くの観客を集める話題作が出るが、インド映画がつねに上映される映画館は今はない。
映画館ではインド映画の影が薄くなっているが、その代わりに、ほぼ毎日どこかの放送局でインド映画が放映されている。韓国ドラマや南米制作のテレノベラ(メロドラマ)と並んで、インド映画はインドネシアの民放テレビに欠かせないグローバルなソフトになっている。昼間の時間帯にインドのB級映画が放送されたり、また、ときどきプライム・タイムに大作が放送され、高い視聴率を獲得している。また、海賊版も含めビデオCD(VCD)とDVDというかたちでインド映画は流通している。一方、活字メディアでは、「ボリウッドと女性」というインド映画専門の週刊タブロイド紙が発行されているし、「ビンタン(スター)」という週刊テレビガイドにもボリウッドの人気スターのゴシップが掲載されている。インド映画が好きなインドネシア人は、けっこう多いのである。
現在では、移民三世から四世が中心となり、そのほとんどはインドの地を踏んだこともない人びとである。そんな彼らにとってのインド映画とは、祖先の地を想像する道具のひとつに他ならない。同時に映画のなかで展開される、自らが生まれ、生活を営むフィジーとは異なるさまざまな光景に、ときに、インドの良さを垣間見、ときに、フィジーの良さを再確認する道具でもある。インド系住民にとってのインド映画とは、彼らとインド、そしてフィジーを結ぶ、じつに不思議な媒体と言えるだろう。
一方、フィジー系住民のお気に入りは、やはりハリウッド映画だ。しかし、彼らの多くも、インド映画の一般的な筋書きやダンスなどには妙に詳しい。
学校の催しで、インドの映画音楽にのせた女生徒の群舞を見ることがある。ある小学校で、級友から借りたインドの民族衣装を身にまとい、ぎこちなくも懸命に踊るフィジー系生徒がいたことを覚えている。校庭中に響きわたるインド音楽にのせ、南太平洋のぬけるような青空のもと、色とりどりの衣装を身に付けたフィジー系とインド系の女生徒によって披露される群舞は、まさに「フィジーのインド映画」のワンシーンであった。
陶磁器に刻印されたまなざしの交錯―特別展「アジアとヨーロッパの肖像」から
アジアとヨーロッパの直接の接触が始まった一六世紀当時、ヨーロッパにはまだ磁器生産の技術はなく、磁器については中国から輸入する以外にすべはなかった。インド航路の開拓は、中国からの陶磁器の大規模な輸入に道を開く。景徳鎮をはじめとする中国の窯で制作された磁器は、オランダ東インド会社の重要な交易品となった。まもなく、中国の王朝が明から清へと移る動乱期に入り、中国磁器の輸入が困難になると、オランダ東インド会社は日本にその代わりの役割を求めた。おりしも、日本では、豊臣秀吉によるいわゆる文禄、慶長の役(一五九二~一五九八年)の終結とともに朝鮮半島の陶工が渡来し、ようやく磁器生産が始まったばかりであった。一六四〇年ごろには酒井田柿右衛門の手ですでに赤絵の技法も確立されていた。こうして、大量の有田の磁器が近隣の伊万里の港から積み出され、ヨーロッパや東南アジアへ輸出されていくことになる。「伊万里焼」の名は、この積み出し港の名に由来する。
一方、ヨーロッパでも、独自に磁器製作への試みがなされた。試行錯誤の末に、一七〇九年、ついにドイツのマイセンで磁器の製作技術が開発される。その技術はほどなく流出して、ヨーロッパ各地に伝わり、各所で磁器の生産が開始されていく。各国の王侯にとって、独自の磁器工場をもつことが、いわばステイタス・シンボルとなっていったのである。このうち、ブルボン家のコンデ公によって築かれたシャンティイ窯は、とくに日本の柿右衛門様式の写しの生産で知られる。一方、イギリスのチェルシー窯は、一七四五年に開窯し、一七八四年には閉窯するという短命の窯ではあったが、マイセンの模倣とともに、柿右衛門様式の写しや人形の製作で一時代を築いた。ただし、十分なカオリンに恵まれなかったイギリスでは、粘土にウシやヒツジの骨を焼いた灰を混ぜるというボーン・チャイナの技法がボウ窯で開発され、その後のイギリスにおける陶磁器の大量生産を支えることとなった。この技法を取り入れたスタッフォードシャーのジョサイア・スポードは、また、柳の木や楼閣の図柄からなる中国の山水楼閣図をもとにした、いわゆる「ウィロウ・パターン」をミントン社の創始者トーマス・ミントンから受け継ぎ、銅版転写の技法を用いて広く普及させたことでも知られる。
このように、陶磁器をめぐっては、アジアとヨーロッパのあいだで、さらにはアジアとヨーロッパのそれぞれの内部で、製品、技術、絵柄のやり取りが、互いに複雑に絡まりあいながら展開されてきた。今回の展示では、そうした絡まりあいを解きほぐして点検できるよう、東西の陶磁器や磁器人形を、アジアから見たヨーロッパ像を示すもの(AE)、アジアから見たアジア像を示すもの(AA)、ヨーロッパから見たヨーロッパ像を示すもの(EE)、ヨーロッパから見たアジア像を示すもの(EA)に整理して展観している。器壁に描かれた絵柄や、磁器人形の姿かたちのなかに、アジアとヨーロッパのあいだで取り交わされたまなざしのやり取りがうかがえるはずである。
神奈川県立近代美術館葉山館の5年間を振り返って―展覧会業務の外で
現在、近美には「学芸課」はない。二〇〇三年の葉山館整備とともに、それまでの学芸課が企画課と普及課にわかれた。展覧会の企画・実施に関して、各課に所属する学芸員の職務に差はない。ただそれに加えて、企画課は主として所蔵品の管理をおこない、普及課は主として普及・広報活動をおこなっている。葉山館整備を機に保存・修復の専門家が採用され、近美の作品収蔵環境は、見違えるように変わった。年に何度か、学芸員がそろって収蔵庫や野外彫刻の清掃をする様子は、かつては「梁山泊」とも言われた「鎌近」のイメージとはかけ離れているかもしれない。企画課には作品や写真の登録や貸し出し手続きを担当する非常勤職員もいて、そのお陰で学芸員は展覧会業務に集中できると言える。そして、葉山館整備のなかで構築された収蔵品管理システムをベースに、これら非常勤職員や、やはり葉山開館後に制度化したインターンの力も借りて、一五年ぶりに、その間の新収蔵作品四五九一点を収めた収蔵品目録を刊行することができた。
普及課の創設そのものが、今日の美術館・博物館に対する社会の要求を良くあらわしている。教育普及を専門とする職員が中心になって、ワークショップなど体験型の教育プログラムが数多く組まれるようになった。その積み重ねの結果のひとつであり、発信型の美術館を目指す手段のひとつが、「Museum Box宝箱」であろう。それには五六枚の収蔵作品カードと近美の日常を双六にしたゲームが入っていて、小学生から大人までが、近美の作品や展覧会の企画・実施に係わるよりリアルな情報を発見することができる、文字通りの「宝箱」になっている。葉山館整備とともにホームページも拡充して、電子媒体による広報活動の比重もますます増えてきたが、一方で、三〇数年ぶりに復刊された美術館たより「たいせつな風景」も、毎号「風」や「雲」といったテーマを立てたエッセイ集として、また別のコミュニケーションのあり方を探り続けている。
近美は今も、鎌倉館、鎌倉別館、葉山館の三館合わせて年間一四企画前後と、以前にも増して積極的な展覧会活動を展開している。しかし、葉山館開館後の五年間に起きた変化は、これまで述べたように展覧会事業の外でこそ顕著であるように思われる。そして、今回開催する、ASEMUS国際共同巡回展「アジアとヨーロッパの肖像」も、展覧会事業を外に開くという、こうした志向の、もうひとつの可能性を探るものにほかならない。もっとも、このような印象は立場や経験によって大きく左右されるから、これは私的な感想とお断りさせていただく。
(特別展「アジアとヨーロッパの肖像」は、二〇〇九年二月七日から三月二九日まで、神奈川県立近代美術館・葉山館で開催)
袋(標本番号H238243、高さ/45cm 幅/26cm)
このようにして作られた袋は、花婿によって使用される。花婿は、結婚儀礼の前に、親戚や近所の招待客へビンロウジを配る。ビンロウジはスパリと現地でよばれる、ヤシ科のビンロウの種子で、キンマの葉、石灰と一緒に噛む嗜好品である。このビンロウジは、結婚などあらたな人間関係や社会的な契約の成立の際に交換される。この袋は結婚儀礼のとき、花婿がそのビンロウジを入れておくものである。
結婚儀礼の最中、花婿はこの袋を介添人に預ける。袋を預けられたということは、花婿にとってもっとも心を許せる人ということになる。
インド西部には現在でも、このような女性たちの手仕事が継承されている。この袋は、昨年収集されたインド西部の刺繍布三六〇点のうちの一点である。今秋から来春まで開催される企画展「インド刺繍布のきらめきーバシン・コレクションに見る手仕事の世界」のなかで、約一〇〇点の刺繍布とともにお披露目される。ぜひ、この袋を間近で見て、インド西部の女性たちの手仕事の世界を感じて欲しい。
今年五月、ビルマ(現国名ミャンマー)に、大型サイクロンのナルギスが大きな被害をもたらした。長くこの国につきあってきたわたしは、現地のさまざまの知り合いのことを思うとともに、大いに驚かされた。その理由は、ビルマの人びとがこの国を大きな災害のない国といってきたように、実際にそうしたことにこれまでほとんど出合わなかったからである。初めて訪れたときの数年前、一九七五年に地震があって、パガン遺跡が被害を受けたことを思い出すぐらいである。
この国にとって災害といえば、天災よりも人災の方が深刻かもしれない。一九六〇年代初めの調査に基づく民族誌によれば、政府は地震や洪水とともに、人びとにとって五つの敵のひとつであるという。当時は軍が政権をとる前であったから、政権それぞれの性格によってではなく、人びとが政治権力に対し、伝統的にとってきた距離と態度からこうした語りが出てきたのであろう。
わたし自身も調査地で、ともすれば恣意的な権力の行使と、敬遠してそれに近づかない人びとの態度を見聞した。わたしのフィールドの村は、イラワジ川中流の氾濫原に位置しており、水が引くとともに順々に土地を耕して作物を栽培する。ところが、ある年に、退いていく水をせき止める堤が築かれ、氾濫原の一部が貯水池のようになっていた。村人によると、政府の命令でこの堤を築かされたとのことである。村人は、従来通り耕作ができなくなって困ったと言うが、他方で、あきらめに似た表情を浮かべるだけであった。しかし翌年訪れてまた驚かされた。堤があとかたもなくなり、従来のように氾濫原が広がっているのではないか。聞けば例年の雨季の洪水によって堤が流されたといい、そこにはこれまでと変わらずに平然と農作業にいそしむ人びとの姿が見られた。
人びとの絆による復興
今回のサイクロンの報に接し、ビルマにかかわってきた者の多くの戸惑いは、どのように人びとに救援を届けるかであった。その背景には、さきに述べたような政府と人びととの関係がある。実際に、現政府の救援対策に対しての不信や不満がその後しばしば報道されている。他方でビルマの一般の人びとが政府の手を借りることなく、自分たちの力で被災地への支援をおこなっていることを現地の知り合いから幾度か聞くことがあった。国連とASEAN(東南アジア諸国連合)とミャンマー政府による被災状況の報告書が公表されるにあたって、シンガポールの外相は現地の人びとの一致協力と団結を特にとりあげて述べた。
今回のサイクロンの災害については、これからの過程を十分に見極めていかねばならないのはもちろんであるが、どうも今のところ、復興をもたらすのは、人びととの疎遠な関係にある政府ではなく、伝統的な人と人との結びつきのようである。
今年一〇月九日から、民博で「インド刺繍布のきらめき」という企画展を開催することになった。展示されるのは、おもにインド西部グジャラート州のもので、B・B・バシンという人物から民博が入手したものである。バシン氏は、インドで三〇年以上も手工芸開発に携わってきた経歴をもつ。長年の仕事をとおして、たくさんのすばらしい職人や彼らの作った手工芸品と出会い、そこからコレクションが生まれた。
コレクションを始めた一九七〇年代、彼は警察官僚としてグジャラート州知事の補佐官を務めていた。旱魃後のカッチ地方の困窮状態を視察する旅の途中で、女や子どもが身につけている刺繍のあまりの美しさとその多様性に驚いた。そして、彼女たちが貧しさゆえに二束三文で刺繍を手放している現状に心を痛め、なんとかカッチの人びとが刺繍の技術によって生活する方法はないものかと、上司に直訴したそうだ。彼の情熱や能力を知る上司の尽力によって、行政官へと転身、手工芸開発に携わるポストをえた。その後、グジャラート州政府と中央政府の両方において、手工芸開発にかかわる重要なポストを歴任し、現在は自らNGOバルサナを組織している。
刺繍布の「声」を展示
初めて彼のコレクションを見たとき、ミラーワークの刺繍がきらめくたびに、ひとつひとつの布が生き生きとした表情で、何かを語りかけているような感じがした。バシン氏は箱のなかから刺繍布を次々に取りだしながら、「ほら、この鳥のかたち、様式化されたデザインを見てごらん」「このビーズ、これまで見たものに、こんなに光るものは他になかったよ」「このブラウスは、わたしの娘に職人さんがプレゼントしてくれたものだよ」などと話してくれた。最初は、ただ布がもつ魅力に圧倒されているだけのわたしだったが、彼がいつ、どのようにして、ひとつひとつの刺繍布を手に入れたのかを聞き、また、彼がこれまでに取り組んできた手工芸開発の仕事について深く知るようになるにつれて、このコレクションには刺繍布自体がもつ美や技のすばらしさ以外に、もうひとつ別の価値が隠されていることに、気がついた。
生活に困って生きてゆくために、大事な刺繍布を手ばなした女たちの切ない思い、社会が近代化し、経済が市場化していくなかで、手仕事の技が忘れられ、生きる場を失った職人たちの失望、そうした現状に対して、伝統技術をもつ人たちが生活できる社会を作ろうとした人たちの熱意が、ひとつひとつの刺繍布に込められていたのである。
刺繍布が語るこれらの「声」を、かたちにして展示するという難題に、企画展実行委員のメンバーは挑戦した。バシン氏が愛した一枚一枚の刺繍布の魅力、その美しさや技術をきちんと伝えること、そして刺繍布が収集された社会背景や伝統技術を守ろうとする人びとの思いを知ってもらうこと、このふたつの願いを今度はわたしたちが刺繍布に込めて、展示したいと思っている。
アハメド・アカールさんに初めて会ってもう五年ちかくになる。当時、ヘルシンキ市の多文化交流センター・カイサで文化事業担当の職員をしていた彼は、多文化主義と公平性を行政指針とするヘルシンキ市が施設の長に外国人を採用しないことを嘆いていたのを思い出す。今回アカールさんに会った目的は、昨年カイサの所長に着任した彼にそのいきさつを直接聞くことにあった。
チュニジア出身のアカールさんがフィンランドに来たのは一八年前、難民や労働移民が大量にヨーロッパに流入していたころである。しかし、彼の場合はそのいずれでもなく、当時留学していたパリで知り合った今の奥さんになる女性についてきたのがきっかけであった。一九八〇年代末のフィンランドはフランスなどに比べ、まだまだ町の景観に外国人の存在を感じさせるものは少なく、社会全体が文化的モノトーンによって支配されていた。人びとの刺すような視線も気になったようだ。フィンランド語はわからなかったが、あるときバスのなかで投げかけられたことばが、外国人への軽蔑のことばであったことは理解できた。そんな国に残ることになったのは自分でも不思議だが、その言語には興味がわいたという。以来彼はフィンランド語の習得に全力を尽くし、短期間で習得した。
おりしもフィンランドは外国人の急増に対処するためさまざまな法や行政上の整備をおこなっており、自治体も、彼らを住民として受け入れる具体的な施策に迫られていた。外国人のほぼ五割が居住するヘルシンキが、外国人との多文化交流をめざして一九九六年設立したのが多文化交流センター・カイサであった。母語のアラビア語にくわえ、英仏語の他、いくつかのヨーロッパのことばが話せるアカールさんは臨時職員に採用された。こうして彼はカイサ設立時からその成長に付き合うことになった。自分ほどカイサを知る人はほかにいないという所以である。
社会の構成員として
カイサの代表的な活動で彼が深くかかわってきたものは少なくない。そのひとつが、恒例となった移民の歌謡コンテストであるアワヴィジョンである。これは一五〇人ほどの参加者が春の決勝大会に至るまで勝ち抜いていくコンテストで、最終の決勝大会は一五〇〇人もの観客を集める大規模行事となっている。興業としても成功するほか、マスコミにも注目されプロ歌手も出るようになった。もうひとつは外国人のための多言語情報サービスであるインフォ・バンクである。これはフィンランドにすむ外国人にかかわるあらゆる生活情報をインターネットで一五もの言語により提供するもので、カイサが長年にわたりコンテンツやシステムを整備してきた。その公益性と汎用性のため来年度からは政府の直接資金援助による機関に格上げされる可能性もあるという。昨年アカールさんの所長への任命は公募による結果であったが、外国出身者として行政施設長へ登用された初めてのケースであった。
しかし、彼の目標はカイサでの派手なイベント活動や情報提供だけではない。むしろ外国人コミュニティーの文化活動支援を通じて社会での居場所を確保すること、社会の構成員として自他ともに認められるようにすることにあるという。そして、いまだに残る多数派の自己中心的な意識を変えること。なかでも彼がもっとも改めたいのは、外国人は社会のお荷物だ、自分たちの築いてきた繁栄を食い物にしている、という先入観、そして外国人への不信である。
ある新聞記事のタイトルに「宝くじにあたったのはわたしたちを受け入れたフィンランド」という彼のことばが引用された。これは、フィンランド人がしばしば言う陰口「フィンランドに受け入れられた外国人は宝くじにあたったようなもの」を逆手にとったものである。実際難民のなかにも高度な教育や技術をもつものがいるにもかかわらず、ほとんどは活用されず、生活援助で狭い世界に閉じこもり暮らすことを余儀なくされている。一方で、社会が居ながらにして、さまざまな文化やことばに触れ、世界と向き合えるきっかけを外国人が提供しているという現実はほとんど無視されているというのである。
一方で彼は、外国人の社会への甘えに対しても厳しい意見をもっている。社会適応の困難や偏見はあるとしても、少なくとも協調性とフィンランド語の習得への努力は義務であるという。アカールさんはカイサの所長という立場をこえ、メディアや各種集会で以上のような主張を積極的に発言してきた。
移民二世に希望を託す
とはいえアカールさんの将来への展望は暗いものではない。フィンランドは世界に誇れる多文化主義に基づく移民統合法、平等法をもち、それを政策で行使しつつある。今の子どもたちは移民も多数派もこの理念の下に当たり前のように混じり合い、多文化多言語にふれながら教育を受けている。移民の子どもはフィンランド語もほぼ完全に習得し、多数派と同じ可能性をもつと信じて育っている。将来彼らは社会のさまざまな分野に進出し影響をおよぼすことのできる人びとに育っていくことに期待できるというのである。
ところで会話のなかで、アカールさんが「いずれ、ここでも移民出身の国会議員がうまれるに違いない」といったことばが気になった。わたしには、それが自分の決意を言ったように思えてならないのである。
スラマット・ハリ・ラヤ!
ハリ・ラヤの一日を簡単に描写してみよう。ハリ・ラヤ当日、村びとは日々の仕事を休んで、朝から、牛肉や鶏肉のカレーと、ルマンとよばれる「ちまき」(竹の筒のなかにもち米、ココナッツミルク、少量の塩を入れて炊いたもの)を作る。料理の準備が一通り終わると、前日に掃除をしてきれいに片づけた客間(その日だけ客間になる部屋)に、カレーなどの料理やルマン、お菓子、そしてジュースなどの飲み物を並べて、客人が来るのを待つ。
当初のハリ・ラヤでは、会館に村びとがつどい、共食していたが、今では家々で食事を準備するようになった。子どもから老人まで、村びとは着飾って近しい親族の家を訪問し、おいしい料理をご馳走になり、その家の人たちや訪問客とおしゃべりをしてひとときを過ごす。訪問する際には、「スラマット・ハリ・ラヤ!(ハリ・ラヤ、おめでとう!)」と主人に言って握手を交わし、「さあ、どうぞ、食べてください」という主人のことばを合図に、料理を食べる。その後は、手作りクッキーなどを食べ、ジュースや甘いミルクティー、コーヒーを飲む。そうして、二、三軒ほどの家を訪問すると、普通はお腹がいっぱいになるが、子どもたちや若者たちは、いくらでも食べられるので、喜んで何軒もの家々を訪問する。こうして、午前中から何となく始まるハリ・ラヤは、相互訪問を繰り返しながら、夕方まで続く。
日が暮れると、村の若者たちが演奏する生バンドに合わせて野外ディスコが開かれる。大音量のロック調のリズムに合わせて、子どもたちや若者たち、そして酔っ払った男たちが夜通し踊り続けるのだ。そのなかには、オラン・アスリだけでなく、マレー人や華人の姿も見える。ときには、酔った男たち同士でトラブルになり、警察沙汰になることもある。村外から訪れる若い客人たちの本当の目当ては、男女の出会いにある。ハリ・ラヤを舞台に恋が芽生えることもある。
文化を模倣する
マレーシアでハリ・ラヤと言えば、普通は、イスラームの断食月明けの大祭(ハリ・ラヤ・プアサ)を意味している。ハリ・ラヤ・プアサでは、首相官邸も一般に開放され、おおぜいの人びとがお祝いに訪れる。訪問者には、料理やお菓子、飲み物などが振舞われるが、イスラームの戒律に従ってアルコールは厳禁である。こうしたハリ・ラヤ・プアサの祝祭は、首相の家ばかりでなく、マレー農村の家々でも断食月明けにおこなわれる。イスラームはいわゆる太陰暦を採用しているので、毎年、ハリ・ラヤ・プアサは、太陽暦を基準にすると、一一日ほど早く来ることになる。
オラン・アスリは、このマレー人のハリ・ラヤ・プアサを模した祝祭をおこなっていることになるのだが、マレー人のハリ・ラヤとオラン・アスリのそれとでは意味が大きく異なる。オラン・アスリの場合には、そこに宗教的な意味は付されていない。わかりやすく言えば、クリスチャンではない日本人がクリスマスを楽しむような感じである。
オラン・アスリ社会でも、イスラームへ改宗したオラン・アスリの人びとは、マレー人のハリ・ラヤに合わせて、祝祭をおこなっている。一方、キリスト教へ改宗したオラン・アスリはクリスマスに、また、華人との付き合いが深いオラン・アスリは、華人の旧正月(春節)に、それぞれ合わせている。いわゆる正月(太陽暦)にハリ・ラヤをおこなう村もある。その結果、年末から年始、一月、二月にかけて、オラン・アスリの村では、あちこちで週末毎にハリ・ラヤがおこなわれることになる。いずれも、ハリ・ラヤの方法はほぼ同じであるが、オラン・アスリの場合には、ビールなどのアルコールも給されるのが特徴であろうか。
親族がつどう日
わたしの調査村では、以上のようなオラン・アスリ社会が他文化を模倣する状況を改善し、村の独自性を主張するために、十数年前から毎年一〇月一日にハリ・ラヤをおこなうことにした。他村の人にもわかりやすいように「ハリ・ラヤ」と村の人びとはよんでいるが、正式名称は「ハリ・クスダラン」である。ハリ・クスダランには「むかしの苦しかった日々を思い起こす日」という意味が込められている。この名称には、模倣ではない新しい伝統を創造しているのだという彼らの自負が見え隠れしている。最近では、休暇が取りやすいように、一〇月の第一週の週末にハリ・クスダランを実施している。そのときには、都市で働いている若者たちも、休暇を取って、バスなどを乗り継いで、村に帰ってくる。以前は、知人や職場の人たちには休暇の理由が理解されにくかったが、十数年も続いた今では伝統行事として定着してきているようだ。夜の野外ディスコには、あちこちの村からおおぜいの人びとがやってくる。この日ばかりは、ゆっくり眠ることはできないが、村びとはみな毎年この日が来るのを楽しみにしているのだ。
わたしもハリ・クスダランや他村でのハリ・ラヤを何度か経験した。最初は食べ過ぎたり、会話もぎこちなかったが、次第に慣れて、誘われるままに次々に多くの家々を訪れることができるようになった。夜の野外ディスコでは、「上を向いて歩こう」をアカペラで歌ったこともある。残念ながら、恋は芽生えなかったが。
チャタテムシとはあまり聞きなれない名前であろうか。しかし、チャタテムシは世界に広く分布する昆虫である。この仲間には、野外の樹幹、落ち葉、岩の表面など湿度の高い場所で生活し、カビや地衣類を食べるものと、屋内で生活するものとがある。後者は、一般住宅にも生息しており、その名前の由来はチャタテムシの一種であるスカシチャタテが障子にとまって発する音が、茶せんでお茶を立てる音に似て聞こえるためであるといわれている。屋内で生活するチャタテムシの仲間は、障子紙や、書籍、貯蔵食品などを食べる。
博物館では、カツブシチャタテ、ヒラタチャタテ、ウスグロチャタテ、ソウメンチャタテ、コチャタテなどが、動植物標本資料、図書資料を食害する文化財害虫としてあげられる。なかでも図書資料の糊付け部分など、糊のついた紙を好み、そこに発生したカビも食べる。しかし、これらはいずれも〇・七から二ミリメートル程度の小さな昆虫であるため、資料への加害はそれほど大きくない。
チャタテムシは、多湿な環境を好むことから、それが確認された場所は湿度が高いことを知らせる、いわば「高湿度指標虫」となる虫である。また、チャタテムシが発生したということは、付近にエサとなるカビが生えている可能性が高いことを示している。このような環境は、当然、資料にとって好ましいものではない。ゆえに、資料がある場所を清潔に保つことや、資料を安全に維持できるように温度と湿度を管理することが博物館において重要な活動のひとつになってくる。
環境整備のための日常的な取り組み
民博では、資料が置かれている場所を清潔に保つための取り組みの一環として、チャタテムシを確認したときは、その食性に鑑み、周辺にカビが生えていないか、または、ホコリやゴミが溜まり、カビが発生しやすい環境になっていないか確認することを徹底している。そして、掃除をおこなうことで、薬剤などになるべく頼ることなくチャタテムシが生息しにくい環境を整えるように努めている。
その他にも、日常的な取り組みとして、資料を保管する場所である収蔵庫に職員が入るときは、専用のスリッパか作業靴に履き替え、外部からホコリやゴミをもち込まないようにしている(写真1)。これは、屋内に入る際に靴を脱ぐという習慣をもつ日本では、特別なことに感じられないが、清浄な環境を保つには非常に効果的である。この他、複数ある収蔵庫のうち、少なくとも一ヵ月に一収蔵庫を目標に順次掃除をおこない、全ての収蔵庫で一年に一度は掃除をすることにしている(写真2)。これと合わせて資料にカビや虫の被害がないかを目視で点検している(写真3)。
温度と湿度を管理することについては、空調機によって、資料の材質や季節に応じて設定した温度と湿度を保つとともに、自記温湿度計やデータロガー(写真4)で、資料がある場所の温度と湿度を記録し、設定した温度・湿度が守られているかを定期的に確認している。この結果は、資料管理の担当者や、資料保存担当教員、空調管理をおこなう関係者が共有し、もしも問題が起こった場合は、これらの関係者が協力して原因の解明と問題の早期解決を図るのである。
民博では、このように、資料に接する博物館職員が日常業務でおこなえる範囲の活動を積み重ね、衛生面に配慮するとともに、温度・湿度環境を整えることで、総括的に虫の発生を防ぎ、人間にも快適であり、資料にも安全な環境を実現できるように努力している。
チャタテムシ目 (学名: Psocoptera)
卵から孵化した幼虫が、さなぎの期間を経ずに成虫になる不完全変態の昆虫。この仲間は、体長1~10mmと小型で柔らかい体である。特に熱帯地方に多くの種類が分布しており、世界で約3000種類、日本では92種類が確認されている。文化財害虫となる種はコチャタテ科とコナチャタテ科に属しており、なかでも注意すべき種はコナチャタテ科に属する。コナチャタテ科のチャタテムシは体長が0.7~2mmで、翅を欠く。体の色は種類によって、褐色、暗褐色、赤褐色、汚灰色、淡黄色などさまざまである。
わたしは、この一〇年来、豊かな染織の伝統をもつインド西部グジャラート州カッチ地方で、染色を生業とする職能集団の調査をしている。わたしが、更紗産地であるダマルカー村を調査するようになったのは、二〇〇一年に起きたインド西部地震がきっかけである。村は、震源地に近かったため、家屋のほとんどが倒壊し、約二〇〇〇人の人口のうち七〇数名の死者を出すという大きな被害をうけた。わたし自身は、援助金をダマルカー村に送る手伝いをしたことから、この村の復興について調査をすることになった。
染色業者たちは、震災から一ヵ月後に染色業組合を作り、資金をとりまとめて土地を購入し、新しい村、アジュラクプール村の建設にとりかかった。そして政府やNGOと交渉し、復興開発援助をうけて、アジュラクプール村に家屋や工房などを建ててもらった。住民がダマルカー村を去ることにした理由は、染色用水の水質が変化し、染色に適さなくなったというものであった。
ダマルカー村からアジュラクプール村への移住は順調におこなわれたが、震災から五年を経たころから移住はすすまなくなった。アジュラクプール村には二一軒の工房が移転したものの、ダマルカー村には依然として五一軒の工房がとどまり稼働している。水が染色に適さないのなら、仕事が続けられないはずなのに、なぜ移転はすすまないのか、本当に水質は悪化しているのだろうか、という疑問がフィールドワークのさなかに浮かんできた。
染色にとって水は重要であるにもかかわらず、水の調査はこれまでおこなわれてこなかった。そこで、水の化学分析の専門家にお願いして現地に同行してもらい、一緒に調査をおこなうことにした。
水環境の変化
ダマルカー村では、染色した布を洗うために、井戸水を用いている。井戸水の化学成分を調べ、また井戸の所有と水利用の形態と歴史について調べた。そこでわかったことは、意外なことであった。確かに水質は変化しているが、それは地震のせいではなく、地震以前から進行している、地下水の水位低下が原因であることがわかったのである。
この村では、地下水を染色に用いるようになったのは、一九九〇年中ごろからである。それまで村には川があり、その水を染色に用いていた。カッチ地方は、年間平均降水量が三〇〇から四〇〇ミリメートルしかなく、半乾燥気候、あるいは乾燥気候に属している。雨期に地面に染み込んだ水が地中にたまり、それが地表に数キロメートルのあいだ表出していた。その川が干上がってしまい、染色に用いる水がえられなくなると、染色業者は農民から土地を買い取って、その土地に井戸を掘削するようになった。水位が低下するにつれて、人びとは井戸を深く堀り、それが水質悪化を引き起こしていると考えられる。
それだけではない。水の減少は、水の個人所有を生み出した。川の水を用いていたときには、染色用の水は共有資源であったが、各自が井戸を掘るようになると、水は個人所有の資源となった。井戸を所有するには、土地を購入し、井戸を掘削するだけでなく、揚水するためのモーターと、それを動かすためのガソリンや電気が必要である。井戸をもたない人びとは、井戸の所有者に料金を払って、水を使用している。水は、金のかかる資源になったのである。井戸の所有者は、投資してえた水を枯れるまで使い切りたいと考え、そのためにアジュラクプール村への移住がすすまないのである。
しかし明るい展望もある。アジュラクプール村では、水を組合の共有資源にして、個人で水を所有することを避けようという試みがなされている。地震は災厄であったが、復興援助金をえたおかげで、伝統染色の産地としての危機を脱することができたともいえる。
問いはフィールドから生まれる
人びとが、移住の理由を水質変化だと言ったのは、わたしに嘘をついたわけではない。なぜなら、地震直後に水質が劇的に変化した井戸があったからである。また、震災被害の調査に来ている外国人に対して、震災の被害であることを強調して、援助に結びつけたいという期待もあっただろう。しかし、地震の被災地には地震の被害があるものだという抜きがたい先入観がわたし自身にあったことが、村の移転の理由を見誤らせた最大の理由であろう。当初のフィールドノートを読み直すと、地震の前から地下水が減少しているのだ、と語ってくれた村人についてわたしはしっかりと記録していた。しかし、わたしの先入観は、その貴重な語りをデータとして取り上げなかったのである。
フィールドの人類学者は万能ではない。今回のように、先入観が調査の目を曇らせることもある。しかし、調査の最中に生じた、「なぜ移転はすすまないのか」という問いを大事にし、その問いをもとにしてあらたに調査をおこなうことによって、地震という災害を超えた、より大きな環境変化が現地に生じていることがわかった。さらには、乾燥気候のなかで、水環境の変化に対応しつつ染色を続けてきた職能集団の技術そのものについて、より考察を広げる可能性が生まれたのである。問いは常にフィールドから生まれるのである。
今号では「裏特集」として、10月から民博で開催される企画展「インド刺繍布のきらめき」に関する話題をいくつか取り上げている。独特の色使いと美しい文様もまたインド・イメージの精華のひとつだ。外出には絶好の季節、民博に足を運び、刺繍の美と技を見、またそこに込められた人びとの情念を感じていただければ幸いである。(三尾 稔)