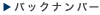月刊みんぱく 2008年3月号
2008年3月1日発行
世のなかには「総合大学」というのがある。医学部だけでできている医科大学は単科大学だ。これはすぐわかる。そして、京大や東大のように複数の学部から成るのは総合大学という。
けれど、学部がいくつあったら総合大学になるのか?そう考えたらわからなくなる。
たとえば京大には一〇学部があり、何百という学科があるが、だから総合大学か?
学部がちがうと先生も学生も互いにほとんど顔も知らないという状態で、「総合」的な教育も研究もおこなわれているとは思われない。それでも「総合」大学なのか?
こんな議論のなかでぼくは考えた。
地球環境学というのはたしかに総合的な学問であろう。そこには自然科学的な問題ばかりでなく、人文社会学的な問題がつねにからまっている。「総合」的に研究を進めねば、問題の解決には近づけない。けれど、その「総合」とはどういうことなのだ?
いろいろ議論しているうちに、ぼくはふと、じつにふざけた表現を思いついた。「総合とは五目チャーハンのようなものである」。
旨い五目チャーハンを作るには、コメとか肉とか油とか、いろいろな専門の人が必要である。
けれど、そういう専門家をひととおり集めたら、それでよいのか?
専門家たちが、それぞれ自分の作った自慢のコメや肉や油を皿に入れて並べる。それをひとつずつ食べていけば、旨い五目チャーハンができるのか?そんなことはけっしてない。
五目チャーハンを作るには、専門家たちのコメや肉や油をひとつのフライパンにほうり込み、火にかけてそれをはげしくかきまわす。そしてそれをまとめて食べる。それでこそ、「おっ、旨いチャーハンだ!」ということがわかる。総合とはこんなものだ。ぼくはそう考えたのである。
その後フランスを訪れたとき、「総合とは何だ?」という議論になった。
フランスではチャーハンのことをリ・カントネイ(riz kantonais)つまり広東ライスという。「総合とはリ・カントネイのようなものですよ」。ぼくのこのことばに、フランスの研究者たちは、皆大きくうなずいてくれた
ひだか としたか/1930年東京都生まれ。動物行動学者。京都大学名誉教授。東京大学理学部動物学科卒業。理学博士。『春の数えかた』(新潮社)で日本エッセイストクラブ賞受賞。『人間は遺伝か環境か?遺伝的プログラム論』(文藝春秋)、訳書『ソロモンの指環』(早川書房)ほか著書・訳書多数。
多民族国家中国では五五の少数民族が公認されている。総人口約一三億人の八パーセントほどに過ぎないが一億人を超える。うちチワン(壮)族は人口がもっとも多く一六一八万人を擁する(二〇〇〇年)。少数民族のうち三〇以上もの民族が広西、雲南、貴州、四川、チベット東部などの西南中国を主要居住地としている。少数民族には下位集団が存在する場合が多い。ヤオ(瑶)族の場合、言語上は三つのグループに分類されるが、広西の金秀(きんしゅう)ヤオ族自治県では文化的に差異のある五つの下位集団が共住している。民族は決して一枚岩的存在ではないのである。
少数民族の文化は多彩である。一層に家畜を飼養し二層に人が住む高床式住居、銀を好み女性の装身具に用いる習俗、漆器や竹木製の道具、蘆笙(ろしょう)や銅鼓の楽器など、どれも特徴がある。また年中行事について、多くの非漢族が漢族同様、春節(旧暦正月)を歳首とするが、タイ族は仏暦によって四月を歳首(さいしゅ)とする。イ(彝)族やペー(白)族のたいまつ祭りやチワン族の歌掛けなど独自の行事もある。少数民族のうち一二が伝統的な文字をもつが、西南中国ではイ族やタイ族の文字、ナシ(納西)族のトンパ文字に特徴が見られる
漢族と非漢族
中国の歴史は一面では漢族の勢力拡大の過程である。古代には四川や雲南などで独自の青銅器文化が発達したが、のちに漢族の勢力がおよんだ。漢族が非漢族と接触した際には図説を含む記録が漢族の側から書かれた。漢族の進出は非漢族の「漢化」現象をともなった。たとえば、チワン族の高床式住居は一見、非漢族に独自であるようだが、漢族の影響が随所に見られる。家の前門から祭壇を結ぶ中心のラインの重視、門に門神を貼り、柱に縁起のよい詩句を書いた「対聯(トイリエン)」を貼ること、鉄製の農具や鍋、カマドでの調理、イス・テーブルなど家具、建築の際に風水を見ること、柱を貫で結合した「穿闘式(せんとうしき)」構造などが挙げられる。チワン族は、春節や三月の墓参・中元節・中秋節などの年中行事の過ごし方に漢文化を受容した。しかし、他方で、歌掛けや行事食品としてモチ米製品を用いる点に独自性が見られる。なお、ペー族の木彫技術のように、漢族から受容した文化が独自に発展したり、非漢族のあいだでも地域社会での力関係にともなう影響の授受があり、漢族・非漢族の二分法だけでは語れない。そのことはトン族のことばの多義性にも垣間見られる。漢族自身にも文化変容があるし「近代化」による影響もあるが、歴史の潮流として、非漢族の文化は漢族をはじめとする外部との交流を経て形成されてきたのである。
近年、グローバル化の進展の下、観光業が発展し、文化の商品化・産業化が進み、農村が大きく変貌を遂げるなどあらたな局面を迎えている。この動きは雲南のタイ族の村など各地で生じている。あらたな文化形成の動きは現在も進行中である。少数民族の多彩な文化を知り、その現在の動向を注視することは中国文化のもつ奥深さを理解するうえで意味のあることである。
中国の歴代の王朝には、今日で言えば国内の少数民族を含めて朝貢(ちょうこう)にやってくる国々や民族地区の人びとを絵画に描くならわしがあった。世界のさまざまな国や民族の使者が中国にやってくるのは中国の文化や支配者の徳のたかさを示すものだとする考え方に基づくものだった。自分の文化や徳を誇示することを目的として描かれたこうした資料を『職貢図(しょっこうず)』とよんでいる。とりわけ、歴代王朝のなかで最大版図を獲得した清の乾隆帝が一八世紀半ばに製作を命じた『皇清職貢図』は有名である。そこには、朝鮮の官僚を描いた「朝鮮国夷官(いかん)」からはじまり、男女一対からなる三〇〇以上もの民族の図像が収められた。
この『皇清職貢図』の編纂は王朝の権威を誇示するための公的な編纂事業だったが、これに刺激を受けてか、一八世紀から一九世紀半ばにかけて、民間でも中国各地に住む民族の姿や風俗が盛んに描かれるようになった。そこでは、各民族の姿がヴィジュアルに描き出されるとともに、各民族のめずらしい習俗が文章で簡潔に紹介された。いわば絵画と説明とがセットになっていることから、しばしば『○○図説』といったタイトルがつけられた。
貴重な資料として
これらの『図説』の編纂にかかわったのは、多くの非漢族が住むことで知られる貴州や雲南といった中国の西南地域に赴任した地方官たちだった。これらの『図説』が製作されはじめたのは、一八世紀以降、西南諸地域で許されていた少数民族の首長(「土司」)による間接統治が廃止され、中央派遣官僚(「流官」)による直接統治へときりかえられる、いわゆる「改土帰流」政策が採用された時期にもあたっている。言語や文化の異なる地域に送り込まれた漢族出身の地方官は、今まで触れたことのない民族の習俗に好奇のまなざしを向け、画家たちにその姿や習俗を描写するよう命じたのだった。序文などを読むと、しばしば、決してものめずらしさから編纂したのではなく、あくまで統治に役立てるためである、などともっともらしいことが書いてある。しかし、古代日本の歌垣にも似た祭りをつうじて婚姻対象を選ぶなど、形骸化した儒教の規範に縛られることない貴州の少数民族の姿が地方官や儒教知識人たちに清新な印象を与えたことは想像に難くない。こうした異文化への強い関心によって支えられ、編纂された『民族図説』は、その大きく変容を遂げた西南中国の少数民族社会を知るうえでも貴重な資料といえる。
中国木彫の郷
世界遺産登録された雲南省麗江(れいこう)の町の魅力のひとつは、古い家並みである。高台に立つと、黒みを帯びた甍(いらか)の見事な連なりが望める。その多くの家屋はおもな住人であるナシ族ではなく、麗江の南隣りに位置する剣川(けんせん)県のぺー族の大工の手で建てられた。一九四〇年代に麗江に滞在し、『忘れられた王国』を著したグーラートは、ぺー族の大工の卓越した腕前を讃え、昆明(こんめい)やそのほか雲南の主要都市の金持ちは彼らを招いて屋敷を建造すると記している。
剣川の大工が建てる木造建築のすばらしさは、太い柱を組んで姿美しく頑丈につくられる構造もさることながら、扉や窓、梁の装飾などにほどこされた精緻(せいち)な木彫にある。花や鳥、動物などを配置した木彫がはめ込まれた扉は「格子門(グーズメン)」といい、ペー族の家ならそれがあって当たり前である。余裕のある家や寺院などの扉の幾重にも重なった透かし彫りは、息をのむできばえである。繊細な木彫を仕上げるため、一人で四〇本以上のノミを使う者もいる。彫る対象によって、鳥の眼、羽、石、枝葉、花びら、花心、さらには松葉、梅の花、蓮の花、蓮の葉など異なるノミを使いわける。大工は中国語で「木匠(ムーチアン)」というが、彼らはまさに「木の匠」とよぶにふさわしい。その木彫技術は、文化大革命を乗り越えて現代まで継承されており、一九九六年に中国政府文化部は、剣川県に「中国木彫の郷」の称号を与えた。
漢族をしのぐ水準
この木の匠の技の歴史はすべて明らかになっているわけではない。しかし漢族の仏教建築技術を受容していることは定説になっており、端緒は唐代にさかのぼると言われる。当時、大理(だいり)を中心に西南中国を支配した南詔(なんしょう)国は、四川(しせん)などに攻め入って技術者を連れ帰った。『蛮書(ばんしょ)』は南詔の支配者の築いた御殿の雄壮さを記録している。南詔末期に大理盆地に創建された崇聖寺仏塔は、唐の都、長安の大雁塔によく似ている。剣川県石鐘山石窟の石彫は仏教の隆盛と足並みをそろえ、南詔から大理時代(宋代)に刻まれた。
中国西南部の少数民族のあいだでは、このように、元来、漢族から流入した技術が独特に洗練され、地域内の漢族をしのぐ水準にまで到達したものが少なくない。それは西南部少数民族の工芸のひとつのあり方である。ある地区のある人びとに特定の技術が発達し、専門化し、他の民族にその技術を提供する。多民族が錯綜して居住する中国西南部には比較的多く見られる現象である。たとえば、戸撒(フーサー)地区のアチャン(阿昌)族は刀鍛冶(かたなかじ)に優れ、「戸撒刀(フーサーダオ)」の名は雲南中に響きわたっている。彼らは国境を越えてミャンマーなどへも出向き、人びとからありがたがられていた。剣川は比較的標高が高く、他のぺー族地域に比べて稲作が難しい地域である。その技を磨いた木の匠たちも国境地域まで足を伸ばして稼ぎ、活躍していたことが知られている。
しかし、必ずしもチャー=漢族というわけではない。なぜなら、日本人であるわたしも現地でチャーとよばれるからだ。当初はわたしが漢族と間違えられているからだろうと思っていた。しかし、人びとは日本人と承知のうえで、わたしのことを「チャー・イッペン」とよぶ。イッペンとは日本の意味。つまりわたしは「日本のチャー」なのである。あるとき村に金髪碧眼(へきがん)のフランス人女性がやってきた。驚いたことに、彼女に対してもチャーという呼称が使われた。さらに、チワン族は「チャー・ション」、ヤオ族は「チャー・ユー」、ミャオ族は「チャー・ミュー」ともよばれる。トン族にとってチャーとは異民族一般を包括しうる概念でもあるようだ。
さらに別の含意もある。人民解放軍に入隊することを「チャーになる」という。警察官もチャーとよばれる。トン族であろうがなかろうが兵士や警察官はチャーなのである。また公務員になって、お上から給料をもらって生活することを、「チャーの飯を食う」という。チャーは官憲や公権力の類を連想させることばでもあるようだ。
わたしはチャーとよばれるのは嫌いだ。幼い子どもたちにとってチャーは恐怖の対象でもあるからだ。大人たちは「チャーがおまえを袋にいれて連れ去るぞ」とか「チャーがおまえの腸(はらわた)をえぐりだすぞ」という紋切り型の表現で、しばしば幼い子どもを怖がらせている。わたしが世話になっている家の二歳の孫娘が、急にわたしに寄りつかなくなった。大人からさんざんチャーの話を聞かされたからにちがいない、とその子の祖父はわたしに解説した。
チャーということばが多様な意味やイメージを担うのは何故なのか。それが今後の検討課題だ。
水かけ祭りは、タイのソンクラーン、ラオスのピーマイと同様の起源をもつ、タイ族の新年行事である。一九八三年、タイ族の民族行事に指定された。この行事が開催される四月には、毎年多くの観光客がシーサンパンナを訪れる。しかし、今日では正式の新年行事以外の機会や場において、観光のアトラクションとしてもおこなわれている。
観光化のなかで、周遊ルートに沿ったタイ族村落ではタイ族文化をテーマとする観光開発が進んだ。その典型が瀾滄江(メコン川)沿いのムンハム地区にあるタイ族園である。一九九八年、マスツーリズムの弊害を防ぎ、タイ族の生活環境をまるごと保存しつつ、観光収益を上げる目的で設立された。五つのタイ族集落からなり、亜熱帯の植物や自然環境、タイ族の高床式住居などからなる集落景観が郷愁を誘う。経営主体は、同地区の国営農場の経営者を中核に組織された「西双版納 族園有限公司」である。
こうしたスポットを訪ねてみれば、すぐに気づくことだが、そこでは、タイ族の風俗習慣や宗教儀礼が観光商品として演出されている。最近、同公司はタイ族の水かけ祭りをまるごと体験できる「溌水節・印象」というスポットを、タイ族園と同じ周遊ルート沿いに建設した。入場券を買って公園に入ると、カラフルな民族衣装を身につけた大勢のタイ族の娘たちによる出迎えを受け、水かけ祭りを時期を問わずアトラクションとして体験できる。アトラクションとして演出された民族文化は、村民の生活を維持するうえでもはや不可欠なものとなっている。
彼らのエスニックマーカーは言語や衣服だけではない。金秀の盤ヤオの祭司に儀礼の話を聞いていたときに、他のヤオとの儀礼の違いに話がおよぶと、彼らは事細かにエスニックグループ間の儀礼の違いを説明してくれる。ヤオ族の宗教は道教の影響が強く、異なるエスニックグループのあいだでも同じような儀礼がおこなわれているが、似た儀礼でも、その儀礼次第や、参加者の規定などはエスニックグループごとにかなり違っていた。
そのときに、盤ヤオは、太上老君(たいじょうろうくん)(老子)を奉ずる梅山(ばいざん)教であり、他のヤオや漢族は茅山(ぼうざん)教や閭山(りょざん)教という道教の別派であると聞いた。ある祭司は、盤ヤオは梅山教、山子ヤオは茅山教、漢族は閭山教であると言い、もう一人の祭司は、盤ヤオは梅山教で、山子ヤオ・ ヤオ・花藍ヤオは茅山教であり、漢族は茅山教だろうと語った。
祭司たちの言は、盤ヤオが梅山教であることではおおよそ一致しており、その他の、漢族を含むエスニックグループについては諸説が交じっている。興味深いのは、道教の基盤をともにしていると認識したうえで、その宗派の違いがエスニックグループ間の差異として、明言されることである。異なるエスニックグループのところで盤ヤオの祭司が頼まれて儀礼をおこなうこともあり、相互に交流がないわけではない。言語や衣服などの違いとは異なり、漢族も含めた道教の共通の基盤のうえにさらに細かい差異を設定している。このように、金秀のヤオ族のエスニックグループ間の違いの認識は、エスニックマーカーの複雑な設定のうえに成り立っているのである。
収集に関して見れば、一九七五年以降、積極的に映像の購入に努め、ドイツ科学映画研究所の映画コレクション「エンツァイクロペディア・チネマトグラフィカ」をはじめとして、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、英国、フランスなど海外で製作されたもののほかに、国内の映像製作会社からも、多くの映像を購入した。ただしこれらのなかには、館内での研究利用に限るものが含まれている。一九七七年からの展示場一般公開に合わせて、ビデオテーク番組を充実するために、既存映像の購入、あるいは外注による映像制作が積極的に進められた。しかし、番組の劣化にともなって複製を作るには、著作権上多額の費用が発生することが明らかになってきた。さらに、外部委託制作した場合に、研究資料として記録すべき部分がとらえられていなかったり、学術的な裏付けのある情報に支えられていないなど、研究者が映像制作にどう関与するかの問題や、撮影という行為が現地に与える影響などの議論が起きた。これを受けて、一九七八年以降、民博ではできるだけ映像の自主制作を目指すようになった。
この動きには、映像民族学の研究分野を開拓するという民博設立当初からの方針も生かされている。わたしが中心となり、研究者とともに撮影クルーを派遣して自主制作する体制が整えられていった。こうして制作された映像のなかには、今や既に失われてしまった現地の儀礼や習慣などを記録した貴重なものも多く、ときにはこれらが現地文化の再生のために活用されたこともあり、民博の役割のひとつを民族誌映像が担った好例と言える。
自主制作された映像のなかには、民博自体の活動記録や、また、さまざまな理由で編集に至ることができないまま「お蔵入り」となっている映像もある。
前者には、研究公演、退官記念講演、各種シンポジウムや講演会の記録、広報事業や特別展の展示記録がある。例えば、わたしが八ミリフィルムで撮影した、民博展示場開館直前までの活動を記録した映像があり、展示場の建設現場、開館式典の様子、当時の研究部の日常や、レヴィ=ストロース氏が民博を訪問した際の模様などが記録されている。民博の活動を記録した映像アーカイブズであり、お宝映像と言えるものだが、未整理・未編集である。そのほか、著作権など権利問題が未処理のもの、伝統技術の記録映像を撮影する途中でその技術保持者が亡くなったために中断したもの、民博を訪れた海外研究者によるパフォーマンスを撮影したが許可をえていないので編集ができないものなど、研究資料としては利用できるがそのままでは公開できない映像も存在する。
これら映像は、その記録媒体の劣化などの問題をはらんでおり、あらためて整理・編集し、メディア変換をおこなうなど、保存と活用を考えねばならぬ時期に来ている。日本の各大学や研究機関においても、さまざまな活動記録映像が作られたものの、その整理や編集が不十分なまま埋もれている映像が数多くあると聞く。科学研究現場の実態や研究者の意見などを広く市民に公開し市民との対話を深めようという、科学コミュニケーションの必要性の議論が高まっており、その意味でも、研究所の活動記録から成る映像アーカイブズの整備が今後は重要になるであろう。
整理や著作権関係の処理を進めてお蔵入り映像をお宝映像に変え、広く公開していく努力が、民博を含む多くの大学・研究機関に求められているのだ。
地球ミュージアム紀行 -ソコヌスコ地方博物館/メキシコ-
わたしは現在ソコヌスコ地方の農村開発の研究をしており、タパチュラ市に足を運ぶことが多い。二〇〇七年一〇月末、調査資料の整理の合間、気分転換にソコヌスコ地方博物館に出かけてみた。
見学を終えて思ったのは、この博物館がふたつの重要な役割を果たしているということだ。第一に地元住民にソコヌスコ地方の文化遺産のすばらしさを伝える役割である。展示物の大半はタパチュラ市近郊のイサパ遺跡の出土品である。なかでも石碑と土器のコレクションが充実している。一般にイサパはマヤ文明の形成に影響を与えた地方文化として知られているが、この博物館ではそれにとどまらず、先スペイン時代の主要な都市文明としてイサパを描いている。人びとは紀元前一二五〇年から紀元後一二〇〇年まで長期間にわたってイサパに居住したという。
他にオルメカとアステカの遺物も展示されているが、それらはそれぞれイサパの前と後の文明というあつかいである。地元の小中学生の見学が多いらしく、子どもたちが手にふれて能動的に学べるように、展示方法にも工夫があった。
第二に地元住民の文化発信の拠点としての役割も見逃せない。わたしが訪問したときには、考古学資料の常設展とは別に、入り口ホールで「死者の日」の特別展が開催中だった。メキシコでは一一月一日と二日に死者の霊が帰ってくると信じられており、それらを迎えるための伝統的な祭壇が展示されていた。死を象徴する骸骨や、さまざまな供物、色紙などが美しく飾られていた。
ふと横をみると、驚いたことにFestival Obonという文字が目に入った。現地の日系クラブのメンバーがこの特別展に参加して、「お盆」を紹介していたのである。ご先祖様の霊がもどってくるという「お盆」の説明とともに、神棚や墓の模型など、日本の宗教文化が陳列されていた。さらに死の象徴なのか、はたまた現代日本のオタク系文化の紹介なのか、妖怪のフィギュア(人形)が目をひいた。そういえばここ数日、タパチュラの街ではアメリカ風のハローウィンの飾りやコスチュームがたくさん売られていた。この特別展は、流入するアメリカ文化に対する地元住民の対抗意識のあらわれといってよいだろう。
メキシコの地方都市には、ソコヌスコ地方博物館のような、小規模博物館が多数存在する。その地方ならではの歴史解釈や文化発信に出合えるため、わたしはこうした博物館は捨てがたい魅力をもっていると思う。
あやつり人形(左から、沙悟浄 標本番号H215315、三蔵法師 H215314、孫悟空 H215312、猪八戒 H215313)
あやつり人形劇(木偶戯(ムーオウシー))は広西のなかでも西部の靖西県付近のみで伝承されている。清代中ごろに外部から伝わり、遅くとも一九世紀初めまでには形成されたようである。北方から来た軍隊が当地に駐屯した際におこなわれたとか、初代の師匠がベトナムで学びもち帰ったなど諸説がある。上から糸で人形をつるす形式のあやつり人形は中国南部には少ないこともあって、また師匠から徒弟へと伝承されるため、その由来については不明な点が多い。
春節(旧暦正月)から三月までの農閑期に屋外に小屋をかけて演じられる。観覧料は県内各地の勧進元の村の農民がもち寄るほか、食事や酒もふるまわれる。演目は「水滸伝」「西遊記」「三国演義」など漢族の歴史小説、とくに戦争に題材をとったものが多い。表紙は「西遊記」である。戦闘シーンや勧善懲悪の場面はつきものだ。
上演する際にはシナリオを見ないで、即興で演じられ、またチワン語のせりふ以外にチワン族の歌を交えるなど特徴がある。演じ手は一人で数体の人形をあやつる熟練のワザが求められる。伴奏者は二~五人で、楽器には二胡・三弦やドラが使われる。人形は頭部をはずして入れ替えて使用される。衣装は専門の職人の手作りである。もっか靖西県政府が無形文化遺産として登録するよう申請している。
ソロモン諸島のビチェ村の人びとは割り算が苦手だ。足し算ならば指を使えば良い。足りなければ、ノートにたくさん線を引いて、答えらしきものをひねり出す。ただし、割り算は大変だ。指を切りわけるわけにはいかないし、葉っぱをちぎるのにも限界がある。でもビチェ村の人びとは、「公平」な分配が苦手なわけではない。
村人は焼畑、漁撈採集を生活の柱にし、収穫物をみなでわけ合うことが多い。カツオなどがたくさん獲れると浜辺に鍋が並べられる。でも単純に魚と鍋の数を計算し、均等にわけていく、なんてことはない。
この鍋のもち主の家は食いしん坊の子どもがいるからこれくらいかな、ばあさんの好きなハラワタも入れとこう、この家は漁に出る人もいないし久し振りの魚だろうから多めに入れといてあげよう、とか単なる計算では計れない要素によってわけられていく。鍋は単なる鍋ではない。そのもち主の性格や生活を語るのだ。
調理物のやりとりも活発だ。調理小屋をもっていた一九世帯に対して、二〇〇二年八月二一日から二七日までの他者への調理品などの贈与状況を調査したところ、贈与回数は計一三一回であった。一世帯平均で六・九回、調理品や収穫物の他者への贈与をおこなっていたことになる。
食事どきになると、高床の階段をトコトコと他家の子どもが皿をもって上がってくる。食事後、皿が台所に並ぶ。皿は語る。さあお返しをもっていくのだと。皿は溜まれば溜まるほど叫び声を高めていく。それは村人の、村で生活していくうえでの良心にピキピキと響き、村人同士を繋(つな)げ、また縛っていく。その響き具合は、村のまとまり具合を示すのかもしれない。
お金の「輝き」に惑わされ
ビチェ村では何度か商業伐採がおこなわれ、伐採権料がもたらされた。伐採されたのは、みなで利用してきた森林だ。だから、各家の子どもの数、収入の有無と多寡、最近の経済的な事情などを考慮しつつ「公平」な分配が試みられた。しかし、伐採権料の着服が生じ、また分配金の少なさに不満をもつ者もいた。
お金はいろんな物に交換でき、またたくさんもっていても腐ってしまうこともない。増えれば増えるほど、多ければ多いほど良く、人の心に欲望に訴えかけ続ける。村で生活していくうえでの良心の響きよりも、お金の輝きに魅せられてしまう人もいる。お金はその「輝き」で村人の良心を覆い隠し、「公平」な分配をとても難しくするのだ。
なんでも単純な割り算で均等にわけることが「公平」なのではない。おそらくそれは人を単なる物と見て、皿を鍋を単なる入れ物と見る、思考停止の無機質な状態のなかでの「公平」なのだろう。そうでない社会では、そんなわけ方は「公平」からはほど遠いものになる。
みんなが共通の生活基盤をもち、人間臭くて、面倒臭くて、「良心の縛り」のある社会での「公平」は、皿や鍋の声を聞くことでうかがい知ることができるのかもしれない。そんな声を聞きとるため、またその声を響きにくくさせる「お金」とは何か、考えながらフィールドワークを続けていきたいと思う。
一九二一年に世界で二番目の社会主義国になるまで、モンゴル国では近代的な意味での工業はなかった。社会主義の思想の下に、遊牧社会に「工業」を産業として確立すべく、首都ウランバートルに大規模な資本が投じられたのである。それ以前のウランバートルは、寺院を核とする門前町に、ユーラシア大陸の交易中継点の機能が加わった程度でしかなかった。もし、モンゴルが社会主義を経験しなかったならば、都市の建設と工業化は、これほどの規模では生じなかっただろう。
国是(こくぜ)である工業化を実現させるため、初の大規模発電所がソ連の援助で建設された。発電所は一九三四年に操業し、「中央電力コンビナート」とよばれ、一九八〇年代まで工業開発や都市生活の近代化を進める電気を生み出していた。
発電所は工業化のシンボルのひとつとして、国家的な記録媒体にその姿が多く残されている。工業成長のエネルギーを生み出す、輝かしい役割を強調するために、写真や映画に写されているのだ。一九四八年には発電所に、革命の英雄の名前「スフバートル」がつけられるなど、まさに「国家成長の熱源」としての表象を見ることができる。
物質としての存在感
わたしはこの発電所をウランバートルでおこなわれた東京大学の近代建築調査に参加して知った。第二、三、四発電所が役割を引き継ぎ、現在は廃墟のまま放置されている。公式には国有財産だが、敷地内に廃材集めの中国人が作業所を開いて占有しているために、所有状態は不安定だ。建物と土地がいつ国有財産私有化リストに入れられてもおかしくない。
この建物のもつ物質としての存在感の大きさと美しさに、わたしは圧倒されてきた。モンゴルを訪れる度に、壊されていないかを確かめている。建築家や写真家の友人がモンゴルに来れば必ず連れて行って見せ、モンゴルで事業をしている人たちにも建物を保存しつつ再生する方法がないかを相談してきた。多くの人はそのアバンギャルドな美しさに興奮し、何故こんなものがここに?と驚く。
発電所のことを調べるうちに、モスクワにとてもよく似た発電所があることがわかった。スターリン様式の代表的な建築家であるジョルトフスキーが設計した第一発電所である。ソ連の工業化政策を倣って、モンゴルでまったく同じものが作られた可能性は大きい。あるいはソ連邦各地や他の社会主義国にも同じ設計で建設されたかもしれない。この発電所は社会主義という思想によって、世界に同時に流通した物質文化があったことを示している。
この発電所をモンゴル近代化の記憶を想起する遺産として残し、再生する、という試みをモンゴルでさまざまな人たちと考えてみたい。モンゴル初の「産業遺産」の議論を始めることになるだろう。実際に保存できるめどはまだたっていないけれども、その果たした歴史的役割を考えると、この発電所こそはモンゴルにおける産業遺産の議論の「始動機」としてふさわしいのではないだろうか。
僕は大阪府に住んでいる中学校三年生の男子だ。生まれも育ちも日本だから、韓国の文化や習慣のことはあまり知る機会がない。僕の両親は生まれも育ちも韓国なので、日本文化のエッセンスが入った僕とは、ときどき衝突する。例えば、日本の子どもは親に対してことば遣いにあまり気をつけないが、韓国は儒教の影響もあってか、親に限らず目上の人には礼儀を尽くさないといけない。それで親は僕に不満らしい。
話はかわるが、親によく「大人になったらどこに住むつもりなの?」と聞かれる。大阪か東京か、という狭い話ではなく、韓国か日本か、という国際的な話である。僕は「日本に住む」といつも答えている。しかし、よくよく考えてみると、果たして日本が僕のような外国人にとって、本当に住みやすい国なのか、まだ疑問に思う部分がある。例えば、日本に長く住んでいても外国人には選挙権がない。自分が安心して政治を任せられる人を自分の意志で選ぶ事ができないことは、辛いと思う。
それでも僕にとって日本はとても住みやすいところである。しかし親にとってはあまりそうではないらしく、アメリカに住む、ということも考えているらしい。アメリカには、ときどき行くのだが、正直言ってあれ程外国人にとっても住みやすい国はないと思う。何でも自由にできそうだ。実際、僕の親戚はたくさんアメリカに住んでいるのだが、それを見ていると僕もアメリカに行って大きいことをやってみたい、と思うこともある。アメリカに限らず、僕が何も知らない場所に行って住んでみたい。日本やアメリカは医療や技術が発達しているが、貧しい国ではどうなのか、何故紛争が起きるのかなども知りたい。そんなことを僕は中学三年生なりに考えているけど、やっぱり僕には日本がいちばん住みやすい気がする。日本には友達が多いし、何より日本に住み慣れたのがその理由だ。
韓国名へのこだわり
僕は将来、日本国籍をとるつもりだが、名前は韓国名のままにするつもりだ。それは、僕の将来の夢が検事になることで、そのほかにもいろんな面で楽であろうし、一方で、自分が韓国人であるという形跡を残しておきたいのが理由だ。
学校で、友達は僕に普通に接してくれる。日本語が流暢だったためなのか、韓国人ではなく名前がめずらしい日本人に見られることがよくあった。要するに僕らは文化が同じだ。僕が韓国人であることを言っても特に友達の様子に変わりはない。
それでも、小学校のころ自分が韓国名であることが嫌だった。今から考えてみると、低学年のころ名前が変だという理由でしつこくからかわれたことがあった。小学生の低学年が他人の名前をからかうことなんてしょっちゅうあるが、僕は「日本人から見れば僕の韓国の名前が変だからからかうのだ」と解釈をしていたようだ。そのせいで今もときどき、僕の名前を紹介すると、「この人は自分と対等につきあってくれないのでは?」と思うことがある。それが災いしてか、体は大きいくせに、他人がすることを人影に隠れてずっと見ていた。小学校の卒業式や中学校の入学式は、自分にとっては嫌な行事だった。僕の名前が人前で読まれると「あいつの名前はおかしい」と他の生徒の失笑を誘うのではないか?と、びくびくしていた。
そんな性格が大きく変わったのは中学二年生の総合学習のときだった。僕の中学校は、国際教育にとても熱心で、たくさんの外国人の講師が教えに来られた。自分の名前や、日本人からすれば一見おかしく見える母国の習慣を堂々と胸を張って説明する講師の方々を見ると、僕が今まで自分の名前に抱いていた気持ちが馬鹿らしく思えてきた。おかげで何よりも中学校の卒業式を安心して迎えられそうだ
僕にとっての韓国語
韓国語は小さいころから母が熱心に教えてくれた。韓国語が僕の将来に役に立つと思ったのだろう。実際のところ、家では家族で韓国語を話すことが多い。あまり外で韓国語を喋る機会がないが、友達に韓国人であることを言うと必ずといっていいほど聞かれることがふたつある。ひとつは「韓国語を喋ってくれ」、もうひとつは「辛いものは結構食べられるのか?」である。韓国語を喋って、と頼まれたときは、とりあえず思いついたことを喋ると喜んでくれる。なかには韓国語の悪態を中心に聞いてくる友達もいる。どちらにしろ僕にとって友達が韓国の言語や文化に熱中してくれることは嬉しい。そんな友達の満足そうな顔を見ると韓国の文化を教える職についてもいいな、とも思う。韓国語と日本語が話せることは僕にとってはたいしたことではないが、他の人から見るとすごいことらしい。僕にとって韓国語は初対面の人との距離を縮めてくれる役目を担っている。
最後に僕が日本で生きてきて大事であると思ったことをまとめてみた。まず、他人と違っていてもそのなかでそれぞれの価値観を見出すことができること、そして他人と違うものをもっていても、それを自分なりに表現することである。
ナーナイは、ユーラシア大陸の北東部を西から東に貫いて流れる大河アムールの民である。アムール川は水産資源に恵まれているだけでなく、水運の大動脈でもある。この川は北東アジアの森や海の世界を中国の農耕世界やモンゴルの草原世界と結びつける働きをしてきたが、網の目のように広がる支流は、森の住民どうしを結ぶ重要な交通網であった。人びとは丸木や白樺の樹皮でできた小型のボートを使って支流奥深くに進出し、狩や漁に従事するとともに、各地の集落を訪ねて情報交換をしたりした。二〇〇五年の調査のときに本館に収集した白樺樹皮製のボートも、支流域で狩や漁に活躍した舟のひとつである。
この舟を収集したコンドン村は、行政的にはロシア連邦ハバロフスク地方ソールネチュヌィ地区に属するが、アムール川の左岸に注ぐゴリン川という支流の流域に位置する、ナーナイの村落である。ここのナーナイは言語、文化ともに独自色が強く、アムール川本流のナーナイとは少々異質である。そのために、かつて「サマギール」という独自の民族とみなされた時代もあり、現在でも自分たちを本流の人びとと区別している。
白樺樹皮舟はアムール川流域の先住民族に共通に見られる小型の舟だが、本流域の沿岸に暮らす人びとのあいだではあまり見かけない。これは支流域に暮らす人びとの舟である。軽く、細身のため、浅くて流れが速い支流でその特徴がいかせるのである。今回収集したものは長さが五メートル以上、幅は五〇センチメートル程度である。主要な材料である白樺樹皮は、幅が一メートル以上あったことから、直径が三〇センチメートルを超える大木からとられていた。近年では環境の悪化のためか、このような白樺の大木はめずらしいという。
樹皮と樅(もみ)の反発力
その製作過程は驚きの連続だった。骨組みと樹皮とを一体にして成形してしまうからである。すなわち、船の長さの分につなぎ合わせた樹皮の上に縦方向に堅い唐松の板材、横方向に柔軟な樅の板材を並べ、横方向の板を船の側舷に当たる部分で押さえた後、一気に丸めて、基本的な構造を作り上げてしまうのである。それから、舳先をホッケーのスティックのようなかたちをした棒で挟み込んで樹皮をとじ合わせる。艫(とも)も同じように成形する。白樺樹皮舟の姿は、樹皮が白い外皮を内側にして丸まろうとする力と、弾力がある樅の横板の反発力とが釣り合って保たれていたのである。
白樺は常温では堅いが、熱すると柔らかくなり、成形しやすい。そのために、細かい細工をする部分にはお湯をかけたり、火であぶったりして柔らかくする。収集された船の底には黒く焦げた部分が目立つが、それは樹皮を強く曲げようとして松明(たいまつ)であぶった跡なのである。白樺の樹皮は縦方向にはとても強く、破れにくいが、横方向には裂けやすいという欠点をもっている、製作過程でも油断するとすぐに裂けてくる。製作者たちはそれに対処する方法も知っていた。小さな裂け目や、ちょっとした穴は松脂(まつやに)を溶かしたタールのようなものでふさいだり、つなげたりする。それでも対処できないような大きな裂け目や穴があいたときには、樹皮のアップリケを作り、それを松脂ですきまができないようにはりつける。松脂は防水性が高いために、あちこちの補修に使われる。
船はできあがると底を松明であぶって清め、進水する。進水では漏水する部分を確認する。そしてその部分を補修して完成である。
操船は一本のパドルで、カヌーのように漕ぐのが基本である。しかし、川面から獲物に静かに近づくときには、両手にもった二本の棒で川底を押して進むか、やはり両手でへら状の櫂をもって音を立てないように進む。収集した舟は大型なので、もち運びは二人がかりだったが、積載量は一〇〇キログラムを超える。猟師が大型のヘラジカを積んでも沈まないようにできているのである。
この樹皮舟は補修をすれば何年も使える優れものである。しかし、舳先も艫も尖っているために、船外機をつけることができなかった。また、船体が軽いために、艫に重い船外機をつけるとバランスが崩れるのである。そのために、舟の動力化が進んだ一九六〇年代以降、急速にすたれていくことになった。
ペルー北部の小さな村。満天の星と月明かりの下に響く、シャーマンの歌声と鈴の音。深夜の儀礼で使われるメサとよばれる祭壇の脇に、たっぷりと用意されている液体の正体がサン・ペドロというサボテンである。これだけ聞くとかなり怪しいが、ペルーでは多くの儀礼に使用されるため、ポピュラーな植物であり、市場などでも簡単に手に入る。また、その歴史も古く、紀元前の遺跡の石彫にサン・ペドロの姿を見ることもできる。
儀礼のための準備はいたってシンプルで、水にサン・ペドロを入れ、煮出すだけである。重要なのは時間帯で、サン・ペドロが開花するといわれる夜一〇時には全てを終えていなければならない。面白いことに、準備のシンプルさに反して、できあがったサン・ペドロの味は、それを作るシャーマンによって個人差がある。基本的にはのどごしが悪いうえ、苦味も強く、飲むと吐き気をもよおすともいわれる。ただし、シャーマンによれば、「清め」になるので嘔吐するのはいいことらしい。文字どおり体のなかをきれいにするのである。
シャーマンの儀礼の効果は、基本的に「癒し」である。シャーマンのもとには、人間関係、恋愛、病気や商売に悩む人などが訪れる。そこで、シャーマンは儀礼を通じて、特にサン・ペドロが見せる幻覚作用の内容について参加者と会話をしながら、問題の解決を図っていくのである。
わたしが儀礼に参加させてもらったシャーマンらによると、彼らが信仰するのは山や湖、遺跡などで、儀礼の際にはそれらが力を貸してくれるという。しかし、彼らは敬虔(けいけん)なキリスト教徒でもある。よって個人差も大きいが、儀礼に使用される祭壇には、十字架やキリスト教の聖人の置物から刀、ライフル、形状や色彩の特徴的な石、遺跡から掘り出された石器など多彩なものが並ぶ。
シャーマン一家との楽しみ
これまで、親子関係にある、この地域では有名な二人のシャーマンの儀礼に参加する機会があった。わたしとこのシャーマン一家とのつきあいはかれこれ四年になるが、彼らとのつきあいは儀礼だけにはとどまらない。村では一緒に食事をしたり、酒を酌み交わしたり、馬鹿話をする仲でもある。
以前、発掘をおこなう遺跡で、調査の無事を祈って儀礼をおこなった。このとき、わたしにこれまでサン・ペドロによる幻覚や嘔吐の経験がないことをよく知る二代目のシャーマンが、にやにやしながら近づいてきて、ある液体を手渡した。特殊なサン・ペドロだというが、明らかに原液に近い。飲んでみたのはいいが、さすがにこれには耐えられず、苦しんでいるわたしの横で二代目は声をあげて楽しそうに笑っていた。
ところで、儀礼にはシャーマンと儀礼の依頼者のほかにアシスタントも参加している。彼らは、儀礼の準備から後片付けまでをシャーマンとともにし、ときにはシャーマンに代わって、参加者に儀礼手順の説明をしたりするなど、儀礼には欠かせない存在である。じつは、現在、この儀礼のアシスタントを二代目の子どもにあたる若者がおこなっている。小さなころからいつも儀礼に参加していたそうで、彼は既に儀礼を熟知している。こうやってシャーマンになっていくのかとも思ったが、事態はそう簡単ではないらしい。シャーマンになるにはきちんとした修練をつまなければいけないし、何より才能が必要らしい。
あるとき、現在アシスタントをしている彼に、今後シャーマンになる気があるのかどうか訊ねてみた。「そのときになってみないとわからないよ」と、彼はわたしに笑いながら答えた。もし、三代目のシャーマンが生まれたときは、儀礼に参加し、親子三代にわたるサン・ペドロの飲み比べでもしてみようと思う。フィールドでの楽しみが、またひとつ増えた。
サン・ペドロ・サボテン (学名:Trichocereus pachanoi)
メスカリンを含有し、個人差や服用時の精神状態、環境状況にもよるが、服用すると幾何学模様などの幻覚作用をもたらすサボテン。ペルーなどアンデス地域では、広く、シャーマンの儀礼に用いられる。名前のサン・ペドロはスペイン語でキリスト十二使徒の一人で、天国の鍵を与えられたという「聖ペテロ」を意味している。これは同様に、サン・ペドロが、その幻覚作用により、異世界への道を拓くものとされているからである。
「頭が痛いんだけど」「子どもが病気なの」「サソリに刺された」・・・。怪我をしたとき、体調の悪いとき、町の人びとはリチャードの店にやってくる。三〇歳代中ごろの彼は、いざというときに頼りになる男である。下痢や腹痛に悩まされることの多かったわたしも、いつも頼りにしていた。
ガーナ南部、人口一万人弱の小さな町にリチャードの店はある。六畳ほどの店内には、さまざまな種類の薬がところ狭しと並べられている。その多くは、パラセタモールなどの鎮痛剤かペニシリンなどの抗生物質だ。「アフリカの薬」と聞くと、薬草や呪薬を思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし、少なくともわたしの調査した二〇〇五年から現在に至るまで、ガーナの田舎町に暮らす人びとがもっとも頻繁に使用するのは、日本で暮らすわたしたちとさほど変わらない医薬品である。
リチャードは、医師や看護師、薬剤師が大学で受けるような、専門的な教育を受けていない。その代わり、「ケミカルセラー」という資格をもっている。ケミカルセラーには、鎮痛剤や抗マラリア薬など三〇種類程度の薬の販売が許可されている。ガーナの農村部には、医師や薬剤師のいる病院や薬局が近くに無いところも多い。そのため、ケミカルセラーは、農村部で暮らす人びとにとって、きわめて重要な薬の入手先となっている。彼も、そんなケミカルセラーの一人である。
町一番の成功者
リチャードの店は、町に四軒あるケミカルセラーのなかでもっとも繁盛している。実際、さほど人口の多くないこの町で、毎日一五〇人以上の客がこの店で薬剤を買っていく。この数は、町の一八歳以上の人口の六パーセント強に当たる。
リチャードは、この町でもっとも成功している人の一人と目されている。店のなかには、薬とともにテレビやパソコンが置かれている。一九九九年に電気のとおったばかりのこの町では、テレビをもっている者はさほど多くない。そのため、サッカーのガーナ代表が試合をするともなると、店は即席の観戦会場となる。集まってくるのは、彼がスポンサーの一翼を担う町のサッカーチームの選手たちだ。店の前をとおる老人が、まだ年若い彼に深々とお辞儀をすることもめずらしくない。
いったい何が、そんなにも人びとを惹きつけるのだろう。店でのやりとりをつぶさに観察してみても、さほど特別なことをしているわけではない。ちょっとした会話をしたり、注射を打つこともあるものの、多くの客は単純に薬の名前を告げて買っていく。
おそらく、お客の大半は彼の治療者としての腕前にあまり期待していない。同じ町のなかでは、信頼の厚い看護師が診断や治療をおこなっているし、近くの町の病院には医師もいる。すぐに安く薬を買えることが、店の人気の理由といえるかもしれない。町の中心部にあるバス停に隣接しているという立地の良さもあるだろう。だが、わたしには、人に安心感を与えるような彼の話し方や、散歩好きな他のケミカルセラーたちとは異なり、いつも店にいることが成功の大きな理由であるように思える。
危ない薬も
ケミカルセラーは、ガーナの医薬品流通システムが抱える矛盾の焦点となっている。医師や看護師、薬剤師の少ないガーナでは、ケミカルセラーがいなければ、農村部に薬を普及させるのは難しい。しかし、問題が無いわけではない。抗生物質や注射など売ってはいけないはずの薬も日常的に販売されているからだ。そのなかには、慢性貧血という深刻な副作用を引き起こす危ない薬も含まれているし、注射を打つときに必ずしも感染症に対するケアが充分になされているわけでもない。
ケミカルセラーと向き合うとき、民族学者もまた葛藤を抱えることになる。目の前でおこなわれる危険な行為を黙って見過ごすことはできない。とはいえ、一人のケミカルセラーの違法行為を非難したところで、状況は何ひとつ変わらない。かといって、例えば、注射のとり扱い方をアドバイスすることは、法律違反を幇助(ほうじょ)することになりかねない。今、ここで何をどうすべきなのか。正しい答えも、究極的な解決も見つけられないわたしは、常にどこか間違っている選択をし続けている。
開館30周年記念事業のご案内
編集後記
2006年の4月から編集長を務めてきましたが、次号から編集長がかわります。この雑誌は32年目に入り、今後の雑誌のあり方をめぐってさまざまな意見が出ておりますが、あらたな発展を続けていくことと思います。引き続き御愛読くださるよう御願いいたします。(池谷和信)
内容についてのお問い合わせは、国立民族学博物館広報企画室企画連携係【TEL:06-6878-8210(平日9時~17時)】まで。